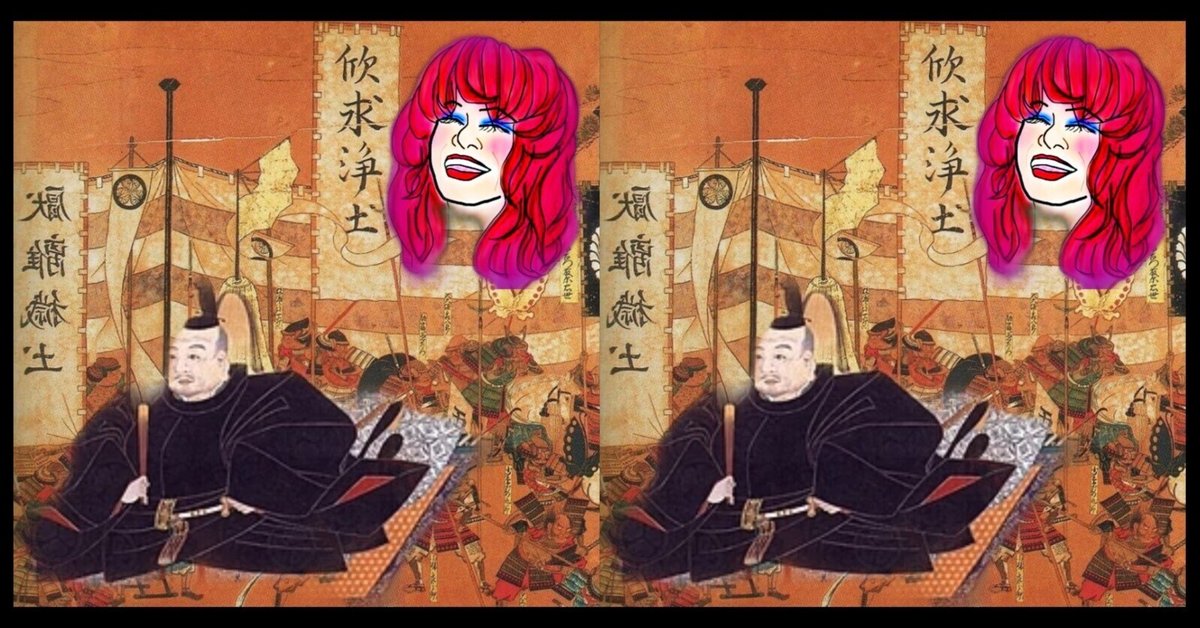
徳川家康さま☘️をたどる#86☘️一国一城令と武家諸法度
初筆 2024年 5月 17日 / 加筆修正 未
この記事は有料ですが、今とこは
実質最後まで無料で読めます🤗
有料部分の文章は
「ご購入いただきありがとうございました☺️🙇♂️」
のみですよ☺️✋
またこの記事の前半と同じ内容を音声で聞けます。
無料で聞ける: #徳川家康さまをたどる 86
⬇️
アップ次第リンクします🙇♂️
1 コンセプト
#徳川家康 さまはちょっと気の利く
フツーの人やってんやと仮定し
#家康 さまやその周囲の方々が
こんときはこー
あんときはあー
思ったんちゃうやろか、と、
いちおー書物や文献も引きつつも、
勝手に思いを巡らす
家康さまファンの思いを皆さまに届けます。
参考文献(一次資料)
#三河物語 / #大久保彦左衛門忠教 さま著
#信長公記 / #太田牛一 さま著
2 前回からのつなぎ
前回は以下を話しました❗️
三河物語の著者でもある大久保彦左衛門忠教さまは #大久保忠世 さま #大久保忠佐 さまの歳の離れた弟で、大坂夏の陣では家康さまご本陣の槍奉行であった。
家康さまはご本陣の大坂夏の陣でのご本陣の崩れ詮議で、彦左さまを「お前は旗だ❗️」と疑ったが、周りに見知った三河家臣団がいなくて、彦左さまを名指しにした。家康さまの記憶違いであり、また三河家臣団に代わり新参者が旗奉行を勤めていた。崩れはそのせい
その後、彦左さまはウソとわかっていて「家康さまの旗は倒れてない」と主張。これは家康さまの名誉を守るための忠義で、彦左さまはお腹を召すつもりで登城したらオトガメなしで、彦左さま・家康さまともに株を上げた❗️
前回はこちら❗️
⬇️
3 文化活動を通して戦乱の世が終わったことをアピールする家康さま
家康さまは、1615年・慶長20年6月〜7月にかけて
大坂夏の陣の戦後処理や幕府の権威付以外に、
在京の期間、文化活動に勤しみました。
戦乱の世を生き残ったレジェンド武将の
大御所自らが、古典や経典などの保存や点検、
講義・論議を聞くことで、時代は変わった、
もう武家同士が戦う世は終わったのだ、
平和な世の中が成立したのだ❗️ということを
世間に広く示していくのです😉🤚
例をあげてみます。
1615年・慶長20年6月1日・梵舜さまに鴨長明さまについてご質問
6月9日・五山の僧に書写させていた、平安中期の漢詩文集である #本朝文粋 (ほんちょうもんずい)2部を #金地院崇伝 さまから進上された。後日、武家伝奏経由で朝廷にも献上
6月15日・法隆寺阿弥陀院の遺物の唯識論・諸疏(しょそ)を中井清正さまが献上
6月16日・名刀・鍛治下坂(かじしもさか)など大坂城で焼けたものを美術品として鍛え直した。また同日、嘉定を行う、嘉定とは疫病を鎮める儀礼で餅を16コ食べる。
6月23日・ #伊達政宗 さまより藤原定家さま直筆の #古今和歌集 の献上を受けるが、これは政宗さまの遊び道具だろう、と受け取らなかった
6月25日・東寺の #杲宝 (ごうほう)さま(室町期学僧)の無尽蔵・句会の筆跡を見た
6月27日・ #徳川秀忠 さまや公家衆・諸大名とともに古式の舞楽・万歳楽・延喜楽などの芸能観覧
6月30日・東福寺の雲叔玄龍さま(うんしゅくげんりゅう)が献上した「左伝」「毛詩(もうし)」「詩経」「中庸」100部以上の書籍を #片山宗哲 さま・ #上田善二郎 さまに点検させた。また同日、「大蔵一覧」が献上された
このように家康さまは内外に
これからの時代は文化活動が大切で
それを自ら実践していることをマメに
アピールしたのです。
もちろんこの期間にも幕府運営について、
秀忠さまと談義したり、実務としては、
6月14日・浄土宗に対して法度を発行したり、
#織田信包 さまの遺領ををめぐり、
その長男と三男に裁定を下したりしていました。
4 一国一城令
#一国一城令 は1615年・慶長20年6月13日、
江戸幕府が制定した法令の1つで、文字通り、
諸大名に対し居城以外のすべての城の破却を
命じたものです。
もし諸大名が2国を統治している場合は、
その1国につき一城で🆗、
また一国を諸大名が分割して統治している場合は、
大名ごとに一城で🆗という内容です。
この法令の発行・実施により、
安土桃山時代に3,000近くもあった城郭が
約170まで、また城郭より規模の小さい
陣屋を含めると約300にまで減りました。
結果として家臣団や領民が城下町に
集まり住むことになり、
領国内での中央集権化がなされました。
また大名の軍事力をわかりやすく統制化することで
徳川家による全国支配も強化されました。
特に豊臣家恩顧の外様大名の多い西国で
徹底された法令でした。
法令の立案者は家康さまですが、
発令は秀忠さまで、連判として、秀忠さま付き幕臣
であり、秀忠さま将軍親政時代の重臣の
#土井利勝 さま・# 安藤重信 さま・ #酒井忠世 さま
のものが記されています。
この法令の発令あたりから秀忠さまは
実質、家康さまからほぼすべての政務を
受け継いでいるのでは❓と考えられています。
上でも述べたように、一国一城令の目的は
諸大名の軍事力を削減するためであり、
数日のうちに約400の城が壊されたと言われています。
大坂の陣の前より、家康さまおよび徳川幕府の
軍事力・経済力によって、世の中はすでに
天下静謐が実現されていましたが、
さらに、余分な城や国境の城を破却させることで
大名の財力と軍備を削減し、
力で反抗できないようにし、
法治国家において法を遵守せざるを得ないようにし、
また大名同士の私闘戦争も封じるためのものでした。
2代将軍徳川秀忠さまの時代には
大名の改易・転封が相次ぎましたが、
そのルールもこの一国一城令に照らし合わせる
ものとなっていて、この法令は家康さまテイストよりも
秀忠さまテイストのほうが強く出ています。
この法制に各大名はそれぞれに対応し、
分家統制の目的で積極的に動いた藩や、
実力があったり家老が優秀だったりで
一国に2城3城あることを幕府に認めさせた藩、
転封時に入府先に城がなく新築で困窮した藩、
諸連絡ミスで破却しなくてよい城を
破却してしまった藩、
一部の城を破却せず、要害扱いし、つまり、
防衛ポイントとし大っぴらに密かに維持した藩や
破却はせずにこっそりと保持した藩など様々でした。
いずれにせよ、大名とくに外様大名は、
御公儀すなわち徳川家・江戸幕府の目を気にしながら
藩運営をしなくてはいけなくなったのです💦
5 武家諸法度
1615年・慶長20年7月7日、
伏見城に諸大名が集められ、
家康さまの指示で #金地院崇伝 さまが起草した
#武家諸法度 が、将軍秀忠さまの名で
諸大名に申し渡されました。
以後、武家諸法度は、8代将軍 #徳川吉宗 さまの代まで
将軍が継承されるたびに都度、改訂発行され、
今回話す最初の武家諸法度は #元和令 、
たとえば3代将軍 #徳川家光 さまの名前で発行された
のは #寛永令 と呼ばれ区別されています。
元和令の目的も一国一城令に同じく諸大名統制で
ここでいう武家とは大名のことを指し、
旗本御家人や諸藩藩士(幕府からみた陪臣)などは
含まみませんでした。
ちなみに幕臣・旗本御家人については
武家諸法度に照らし合わせて作られた
#諸士法度 を遵守するように沙汰されていました。
また武家諸法度が幕臣・旗本御家人や
諸大名の家臣までを対象にすることになるのは、
5代将軍 #徳川綱吉 さま発行の #天和令 以後です。
条文の現代語訳は以下です。
武士たる者は文武弓馬の道に励むべきこと
群飲佚遊(遊興)の禁止
法度違反の者を領内に隠し置くことの禁止
反逆・殺害人であると報じられた者の領外追放
領内に他国者を交え置くことの禁止
居城の修補の際の届け出の義務化と新城構築の禁止
隣国で新儀(新しいこと)を企てる者の言上(報告)
私の婚姻の禁止
参勤作法の遵守
衣服の制の遵守
乗り輿の制の遵守
諸国諸侍は倹約すること
国主政務の器用を撰ぶべきこと(才能ある者を国主にせよ)
武家諸法度・元和令は
1611年〜1612年・慶長16・17年に家康さまが
諸大名から取り付けた誓紙3ヶ条を基本に、
金地院崇伝さま起草の10ヶ条を付け加えたものです。
大坂の陣で大坂方が浪人衆を大坂城に
入れたときの経緯とその結果を踏まえて
「よそ者を城下に入れない」や、
「反乱の元となる不穏分子の駆逐」、や
「領内に逃げた罪人を匿うことの禁止」
などもしっかり記されています。
また特に、居城補修の届出制は、
後に #福島正則 さまの改易の理由にもされました。
このように大大名さえも改易に追い込むような
使い方をされたのが武家諸法度で、
たとえば親藩大名の #松平忠直 さまが
待遇に不満を持ちわがままし放題のときに、
武家諸法度にのっとり、越前松平家の君主を
辞めさせるようなこともありました。
江戸幕府が武家諸法度のような
すべての諸大名に向けての
法令を出すことができたのは
徳川宗家が摂政や関白ではなく、武家の棟梁である征夷大将軍であること。
金地院崇伝さまや林羅山さまのように法令や過去の事例に詳しい顧問がいたこと
によることが大きいかと考えられます。
そしてこういった道筋をつけておいたのは
家康さまでした。
家康さまは、徳川家中や三河家臣団には
法令のプロがいないことを重々理解していて、
#南光坊天海 さまを思想的支柱として重用した上で、
武家のあり方を時間をかけて、また話し合いながら、
金地院崇伝さまや林羅山さまの有識者に起草させました。
6 諸大名はなぜ一国一城令や武家諸法度に従ったのか
諸大名は一国一城令が発行されると
それを遵守しました。
また武家諸法度に違反から改易・減封など処せられたら
申開きはするにせよ、最終決定に従いました。
大坂の陣において戦乱の世が終わったにせよ、
反乱・謀反を起こそうと思えば起こさなくもないのに、
江戸幕府の決定には全国の諸大名が従いました。
それはどうしてなのでしょうか❓
考えられる理由を上げておきます。
徳川家・江戸幕府の圧倒的な軍事力と経済力。家康さまは関東入府時に240万石+金山銀山の掌握に加えて、関ヶ原の戦以後、全国の役1/3の石高を徳川家親藩大名と譜代大名にて独占。さらに徐々に流通貨幣のさえも掌握したため
関ヶ原の戦直後なら戦国時代を生き抜いてきて、謀反や反乱を起こしそうな戦国気風を色濃く持った武将が大名であったが、それらはほとんど世代交代してしまい、反乱を起こすとしても、具体的な方法や気持ちの持って行き方が分からなかったり、他の大名との連携のツテのない世代が諸大名となっていた
江戸幕府も世代交代はしているが、棟梁である家康さまは、他の大名が世代交代しても、ご健在であったため
言ってしまうと、一国一城令や武家諸法度が
有効であった根本には、家康さまの長生きが
遠因となっていたのでしたー🤣😉🤚
7 次回
武家諸法度と一国一城令で
全国の大名は江戸幕府にひれ伏しました。
しかし日本国を治めるには
もう一つの大きな課題があった。
それは禁裏❗️
すなわち、御所と公家衆❗️❗️
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
