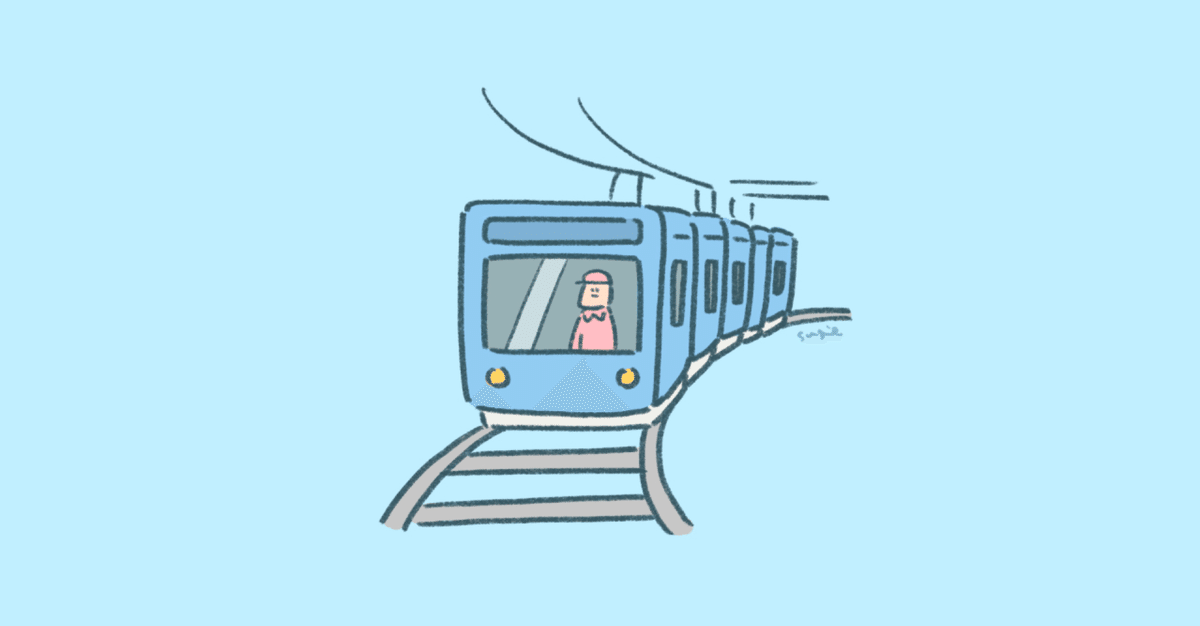
東京にやりづらさを覚えている
東京で暮らしてきて、見ず知らずの酔っ払いに絡まれたことが、一度だけある。もう十五年も前の、夏の夜のことだ。
僕は池袋駅で、池袋発の電車の座席に腰掛けていた。行儀悪くならない程度に身体をリラックスさせ、仕事の疲れを簡易的に癒しながら、出発時刻になるのを静かに待っていた。
午後十時過ぎ。ギュウギュウ詰めの満員になる時間帯ではないが、それでも着実に乗客が増えていった。八割程度の座席が埋まった頃、ひとりのオジサンが乗り込んできた。
小柄で小太り。設備工のような作業服を着ているが、黒ずみと汗じみでひどく汚れている。その上、靴はボロボロ。清潔感はどこにもない。
向かいの長椅子にひとり分だけ空きがあり、オジサンはそこに座った。窮屈だったのか、上半身を乱暴にゆすって、さらに大股を開いて、自分のスペースを広げようとした。隣に座っていた若い女性は、それを嫌がって逃げてしまった。
頂けない。
僕もそれほど礼儀正しいわけではないが、さすがにあんなことはしない。オジサンの不快な行為で、まったりタイムが汚されて、苛立ちすら覚えた。
すると急にオジサンが立ち上がって、僕の前に歩み寄ってきた。
「何ジロジロ見てんだよ」
オジサンから汗の臭いがしたが、それ以上に酒の臭いが強烈だった。僕の怒りは一気に沸騰した。
「オマエみたいなクソ野郎、誰が見るか!」
言ってしまった。たとえ相手が礼儀知らずの酔っ払いだとしても、いきなりクソ野郎などと言ってはいけない。
必然的に口喧嘩が勃発した。
僕は怒りに任せて、文章にするのをためらう位に汚い言葉で、ボロクソに罵った。対してオジサンは、酔っ払って呂律だけでなく頭もうまく回らないらしく、相当な口下手だった。その口撃は僕に何のダメージも与えなかった。
圧倒的な僕の優勢。オジサンを心地良く罵ったおかげで、冷静さを取り戻すことができた。逆にオジサンのフラストレーションが溜まる一方なのは、僕も感じ取っていた。状況はむしろ悪化していた。
「この野郎、次の駅で降りろ!」
オジサンの怒号が車内に響く。
電車は口喧嘩の間に出発していた。しかし次の駅は、僕の最寄り駅の五駅も手前だった。何の縁も用もない駅で、降りれば単に帰宅が遅くなるだけだった。
しかしこのまま車内でくだらない口喧嘩を続けていても、他の乗客の迷惑になるだけだ。僕は渋々オジサンに従うことにした。
次の駅のホームに降り立ち、湿っぽい外の熱気を感じると同時に、オジサンが僕の胸元を掴んできた。悲しいほど弱々しい力だった。やれやれ、口も腕っぷしもこの程度で、僕に突っかかってきたのか。
その気になれば、すぐにオジサンをねじ伏せられるだろう。しかし格闘術にも護身術にも通じていない僕には、力の加減がわからない。下手をすれば、オジサンを怪我させてしまいかねない。
殴りかかってくるオジサン。その拳をかわすのは簡単だったが、そこからどう対処すれば良いのかわからなかった。困っていると、間もなく僕とオジサンの喧嘩に気づいた人達が数名集まってきた。その内の、ひとりのオニーサンが仲裁に入って、オジサンを僕から引き離してくれた。ありがたい。これで終息するだろうと、ほっとした。
甘かった。
オジサンが、今度はオニーサンに絡み出したのだ。このヘタレ野郎、チ〇ポついてるなら、かかってこいよ。下品という以前に、そんなのに誰が乗るか、という位に幼稚な挑発だったが、オニーサンは簡単に逆上してしまった。オジサンの胸元を掴んで拳を振り上げる。そんな勢いで殴ったら、オジサンの顔がもげてしまう。僕は慌ててオニーサンの腕を掴んで止めて、こんなところで喧嘩はダメですよ、と宥めた。それでもオニーサンは収まらない。このクソオヤジ、ぶっ殺す、と叫んでいる。
あれ、そもそも喧嘩をしていたのは、僕だったよな。
遅れて駅員が仲裁に加勢して、ようやくオニーサンは拳を収めた。そしてブツブツ文句を言いながら、その場を後にした。やれやれ。今度こそ終息するだろうと期待を込めて予想した。
やはり甘かった。
オジサンが、今度は駅員に絡み出したのだ。快速電車ばかり増やしやがって普通電車が少ない、というくだらない言いがかりで怒鳴った。もういいから落ち着いて、と僕は面倒ながらオジサンを宥めた。
あれ、オジサンと喧嘩をしていたのは、僕だったよな。
「貴方、この人の知り合いですか」
駅員が僕に訊いてきた。
「いえ、まったく知らない人です」
「しかし帰る方向は一緒ですよね」
「まあ、そうですけど」
「じゃあ、連れて帰ってください」
どうしてそうなるのか。
「こんなワケのわからない駅員なんか放って帰ろうぜ」
オジサンが言って、馴れ馴れしく僕の肩を組んできた。ワケがわからないのはアンタの方だ、と僕は思いながらも、深く安堵していた。奇妙な過程を辿った挙句、喧嘩相手の面倒を見ることになってしまったが、何はともあれ、これでようやく帰路に戻れる。
電車に乗り直してからのオジサンは、ホーム上での荒れ具合が嘘のような穏やかな表情で、やたらと僕に感謝していた。ありがとう、アンタが止めてくれなかったら、大変なことになっていた。
酔っ払いの情緒とは、ここまで節操なく変わるものなのか、酒を嗜まない僕には理解しきれない。でも、それで良かったと思う。人と対立するのは、やはり性に合わない。たとえその人が汗臭い上に酒臭かったとしても。喧嘩より親睦、戦争より平和だ。
「アンタ、いい人だな」
親切にした覚えはまったくないが、そう言われて悪い気はしなかった。
「でも、それじゃあ、東京ではやってゆけないぞ」
そう呟いた時、オジサンの顔は妙に悲しげだった。心配しているというより、僕の未来を確信しているかのような口ぶりだった。酔っ払いのくせに、生意気にも程がある。
その言葉は、今でも僕に突き刺さったままになっている。
あの時以来、オジサンと会うことはなかった。依然として僕は東京で暮らしている。しかし、もしオジサンと再会したとしても、ほら、うまくやっているじゃないか、と言い返すことはできない。
僕は今、東京にやりづらさを覚えている。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
