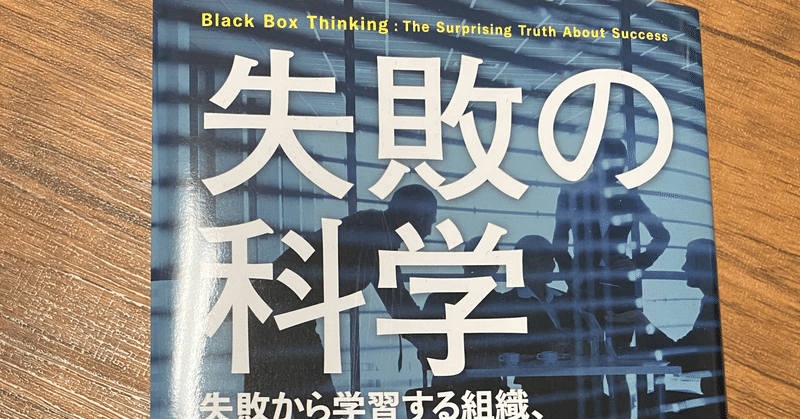
失敗を恐れる者たちへ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第一弾『21世紀を生きる者たちへ』
第二弾『複雑な時代を生きる者たちへ』
第三弾『失敗を恐れる者たちへ』 ←今回
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第一弾では、マクロ的な視点から2020年をどう捉えていけばよいかを説明した。第二弾では、ミクロ的に2020年をどのように考え過ごしていけばよいかについて説明した。
そして第三段の今回は『失敗の科学』という本を題材に、未来に何を見据えて生きてゆけばよいのかについて、現代に介在している問題点を挙げながら説明していく。
1.「人類の価値は失敗にある」
本ブログで、私が最も伝えたいことはこれに尽きる。
前々回の記事でも主張したことだが「AIは人間と敵対する脅威ではなく、人間がより良く暮らすための機会である」。これを大前提として、今回のブログを読み進めていただきたい。
著書『失敗の科学』では、人類がどのように失敗を乗り越えてきたのか、あるいは一方でなぜ同じような失敗を繰り返すのかに関して、様々な例を挙げて論理的に説明されている。
この相反する内容に関して、航空業界と医療業界が対比の例として挙げられていたので、まずはその内容を簡単に説明する。
2.失敗から学ぶか、失敗を隠蔽するか
ーーーーーーーーーーーー
航空業界ー失敗から学ぶ
医療業界ー失敗を隠蔽する
ーーーーーーーーーーーー
これは業界的な体質らしい。
IATAのデータによると、1912年のパイロット死亡数と2013年のその数値を比較すると、以下のようになる。
ーーーーーーーーーーーー
1912年ー14人に8人が死亡
2013年ー年間210人が死亡
ーーーーーーーーーーーー
一方で、英監査局のデータによると、ヒューマンエラー(人的ミス)による患者の死者数は年間3.4万人にのぼり、およそ患者の10人に1人が死亡する計算になる。
もちろん、この数字だけを見てそれぞれの業界を善し悪しに分ける気はない。医療業界にヒューマンエラーが起こり続けるのはある意味当然で、科学では未だ証明しきれない病気やウイルスが多い。
しかしながら、医療業界には「失敗を隠蔽する」文化があり、それは業界の暗黙の了解らしい。
3.なぜ人は失敗を隠蔽するのか
人が失敗を隠蔽する要因としては、大きく2つある。
ーーーーーーーーーーーー
①内因:バイアス(本の中では「認知的不協和」と書かれていることが多い)
②外因:非難というプレッシャー
ーーーーーーーーーーーー
3ー1.「解釈ではなく事実を変えてしまう」
①に関しては、宗教的な観点から説明できる。
とある実験で「教祖の予言が外れたら信徒はどう変わるのか」という実験が行われた。その結果はというと、彼らは予言が外れると、教祖に幻滅するどころかそれまで以上に教祖を信じ込んだという。
つまり「事実」と「解釈」において、解釈ではなく事実の方を捻じ曲げてしまったのだ。これが「確証バイアス」である。
3-2.「能力や権威を守りたい」
②に関しては、あなたにも身近なのではないだろうか。なぜなら会社にしても政府にしても、隠蔽工作はニュースで散々取り上げられているからだ。
彼らも信徒と同様、自分を正当化しようとする。自分にはこれを成し遂げる使命があり、そのためにこんな試練や試験をクリアしてきたんだという自負があるのだ。
彼らは現実で起きた問題を隠蔽することで、自分の過去を正当化する。
私は失敗などしていないのだ、と。
(どこかのテレビドラマにあったような…)
4.失敗を認めない=成長しない・できない
ここまで読んできたあなたは、もう気づいていると思いますが、失敗を隠蔽する人は成長しません。ちなみに、失敗の定義は以下です。
ーーーーーーーーー
失敗=理想ー現実
ーーーーーーーーー
この定義からも考察できますが「理想=現実」の中で生きている人はいないはずです。心理学者アドラーによると、人間には2つの優越コンプレックス(向上心)があるそうです。
ーーーーーーー
・優越性の追求
・理想の追求
ーーーーーーー
つまり人は、誰かよりも優れることを追求し、過去の自分よりも未来の自分のほうが優秀であろうとする生き物なのです。
しかしそう願いながらも、口だけで一向に成長しないのは、行動を起こさないもしくは失敗と向き合わないからです。
5.失敗こそ学習である
あなたにとって「学習」の定義はなんだろうか。勉強のことを思い浮かべただろうか。
では、もう一つ質問してみたい。
あなたにとって「学習能力」とはなんだろうか。
昨今耳にする機会が減ってきた気がするが、この言葉は「学習能力が高い・低い」などと使われることが多い。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学習能力の高い人は、次に同じミスを犯さない。
学習能力の低い人は、また同じミスを繰り返す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
あなたのイメージは、きっとこんな感じだったはずだ。
では、最後の質問。
人間とAI、どちらのほうが学習能力が高いだろうか。
AIは人間よりも遥かに大きなデータを蓄積・分析することができ、もはやその線では人間の勝ち目はない。
しかし、失敗から学ぶ必要がないというわけではない。むしろAIのデータにもない、他の人がやったこともないような失敗をあなた自身がすることは人類にとって多大な価値であり、そこからあなたが学ぶことはさらなる価値につながる。
6.未踏の地で失敗しよう
「人の仕事の49%は、AIによって代替可能である」
あなたはこの言葉を聞いたことがあるだろうか。
代替可能性の高い以下のような職業は、いわば本来人間がやる必要のない仕事である可能性が高い。
(画像の無断掲載禁止のため、こちらにリンクを張っておきますのでご参照ください。→https://webronza.asahi.com/photo/photo.html?photo=/S2010/upload/2016090900001_1.jpg)
では、人間が本来やるべき仕事とは何なのだろうか。
この問に関しては、前回の第二弾で「成功する方法は決まっていないが、失敗しない方法は決まっている」と冒頭で話したのと同様、やるべき仕事に決まりはない。
あえて答えるのであれば「百姓であれ!(百の仕事をする者であれ)」と答えるだろう。
先にも説明したとおり、人間の向上心や欲求は青天井である。一方で、失敗はなんとしてでも避けたいというもうひとりの自分がいることも確かだ。
ただ、2020年以降も生き続けていくあなたにはどうしても伝えておかなければならないことがある。
「周りがやったこともないことをやって、そこで試行錯誤(失敗と改善の連続)してほしい」
さいごに
私には、傲慢にも周りと一風変わった人間であるという自覚がある。周りがAを選んだらBを選ぶ。これが基本スタンスだ。いままでは、この生き方を「違い」という名の「生存戦略」だと捉えていたが、本書を読んでいる中でこんなことを思うようになった。
「仮説検証」
私は、答えのわかる問題を解くのがあまり好きではない。なぜなら、人類が本来投下すべき時間も労力も無駄にしていると感じているからだ。特に、誰かが選んだあるいは選んできた選択をしても、ある程度予測がついてしまうあるいは同じような結果になってしまう。面白くない。
だからこそ私は周りと違う選択をし、Aを選んだ結果どうなったか、Bを選んだ結果どうなったか、その両方の検証結果があることが人類にとって最も好ましいのではないかと言う潜在的な考えのもと、これまで直感的に考え選択してきたらしい。
「多様性」という言葉が望ましいだろうか。
つまり「他人と同じ失敗はしたくない。自分しかしたことがない失敗がしたい。」というのが私の欲求なのだと、現時点では推測している。
最後に一言
「失敗の希少性」こそ、21世紀を生きる人間の価値である
ーーーーーーーーーーー完ーーーーーーーーーーー
約3400字にも及ぶnoteをご購読いただき、
ありがとうございました。
せっかくなので、私のnoteを読んだ感想や疑問、批判などをコメント欄にしていきませんか?
よりよい社会を創り上げていくなかで、人々が集まり意見し合うことはとても重要です。
ただし、根拠のない批判や誹謗中傷はご遠慮ください。
弊noteの目的は「Sustainable Relationships(持続的な関係性)」をあなたや社会と築き上げていくことにあります。
コメントお待ちしております!**
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
