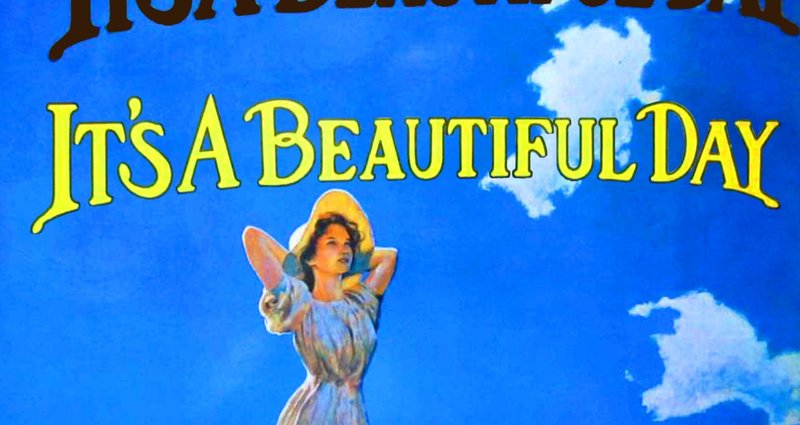2023年7月の記事一覧

社会の悪と闇に慣れていくことが、「大人になること」ではない。その悪や闇に敢然と立ち向かい、行動できることが「大人になること」なのである
よく「お前も大人になれよ!」とか、「社会に出たら、君もわかるようになるよ!」という言葉を耳にする。 確かに、まだ「子ども」と言われる頃、自分は今よりも純粋で善良な人間であった。 工事現場のおっさんに「煙草を買ってきてくれんか」と言われれば、坂道を下って走って買いに行ったものだ。そのオヤジからは、1円の駄賃ももらっていない。 「仮面ライダーカード」を集めていて、ある店で「仮面ライダースナック」を買った時、商店のオバハンが、「カードは無かよ」と言い放った時も、「それは詐欺だろ