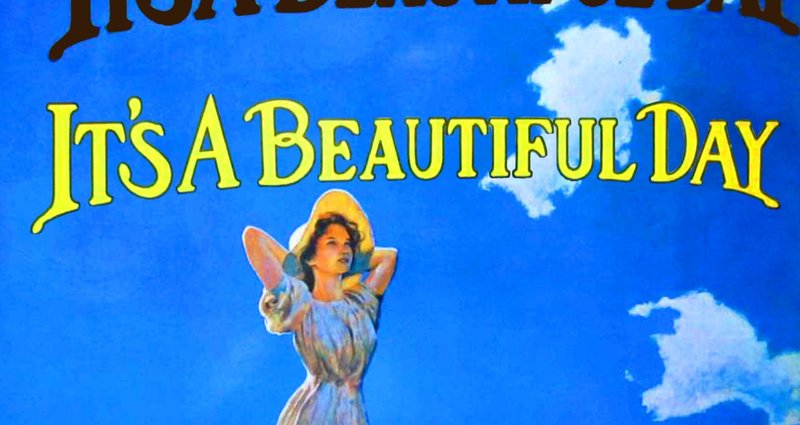2023年5月の記事一覧

「しつけに厳しい親」や「子どもに甘い親」がいるのではない。「子ども扱いして人格を尊重しない親」と「子ども扱いせず人格を尊重する親」がいるのである
金曜、NHK第一放送の「ふんわり」に、パーソナリティの黒川伊保子さんに脳科学の観点から、人間関係などを相談するコーナーがある。 この日の相談者は双子の娘を持つ父親からで、「しつけを厳しくして育てた結果、成人した今、二人がまったく自分を避けるようになってしまった。どうしたら、いいか?」といったものだった。 黒川さんは、男性に多い「問題解決型」と「共感型」で説明されようとしていたが、私はそもそも「しつけを厳しくしたから、自分を避けるようになった」と解釈している事自体が間違って

「男はつらいよ」の宣伝担当をされていた方が語った、渥美 清さんの言葉は、アンガーマネージメントとして、人生の生き方として有効である
BSテレ東で毎週土曜日に放送されている「男はつらいよ」シリーズ。 映画が始まる前に当時のエピソードを紹介するコーナーがあります。 この時は、「男はつらいよ」の宣伝担当をされていた方でした。 当時の渥美さんについて、以下のようなお話をされていました。 「普段の渥美さんは、寅さんとはまったく違う。寡黙でよく本を読んだり芝居を観たり・・・」 そして、心に残る言葉として、次のような言葉を紹介されていました。(正確ではありません) この言葉、誰にでも当てはまりますね。 人は誰