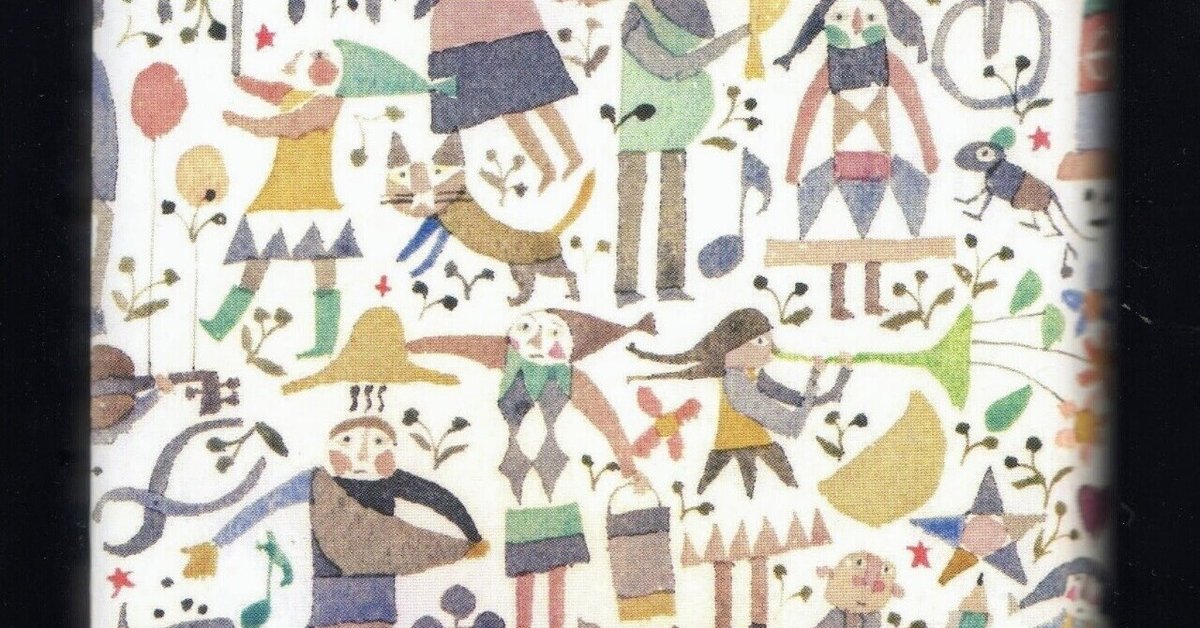
立花隆『知のソフトウェア』を読み返す

『知のソフトウェア』立花隆 著
講談社現代新書 (1984.03.20)
今回、1984年(昭和59年)の読書記録に加え、さらに加筆しました。

【情報のインプット】
pp.7〜23.
インプットの二つのタイブ p.17
① アウトプットの目的が先行していて、その目的を満たすためのインプット
② 取り敢えずインプットしている
▶ 情報の意味を読み取る能力 → 精神の集中力の関数
▶ 速読術 → ひたすら雑念を捨てて文章に集中する
参考
国立国会図書館リサーチナビ
【Note】調べ方を調べるには?
Tomoko Nakasaki
「目的先行型読書法」pp.18〜21.
本にあたる (渉猟する)
・自分が何を必要としているかを明確にする
・読むに値しないと思ったら 読むのを やめる
・初めからノートを取らない
・年鑑/統計/用語辞典などに接する
▶ 絶えざるインプットによって蓄積され形成された豊かな個性的世界こそが、よきアウトプットの土壌である。p.22
【情報のアウトプット】
pp.153〜170.
▶ インプット(情報収集/情報整理)とアウトプット(文章作成)の間はブラックボックス p.154
▶ インプット論:情報収集/情報整理
▶ アウトプット論:文章表現
▶ 無意識層は 解析されていない p.154
▶ 頭の中の発酵を待つ p.156
▶ KJ法など → 意識下の作業を物理的な作業行程に置き換えようとしたもの p.158
▶ アウトプットと無意識の効用
【無意識下の能力の涵養】
pp.163 〜 170.
▶ いかにすれば その能力を高めることが出来るか!?
【Point】
▶ 良質のインプットを出来るだけ多量に行うことである。いい文章が書けるようになりたければ、できるだけいい文章を、できるだけたくさん読むことである。それ以外に王道はない。 p.165
材料メモ・年表・チャート
pp.187〜205.
① 年表をつくる効用(時系列に整理)
② チャートを作る(見える化)
pp.187〜205.
情報のS/N比を高める努力
pp.223〜243.
▶ ガセネタを掴まないために pp.236〜243.
▶ 真実(S) 対 ガセネタ(N)
あとがき より
いろいろなトレーニングを自分に課して体得してもらう。
最後に本書の内容を一言で要約すれば「自分で自分の方法論を早く発見しなさい」と云う事である。人の方法論に惑わされてはならない。p.245
youtube「立花隆のネコビル」
立花隆と語る東大図書館
関連【調べる技術】『企画力の育て方』岩崎隆治 著
三笠書房 (1985.05.10) より p.137

書棚の背表紙

2021.06.24.
