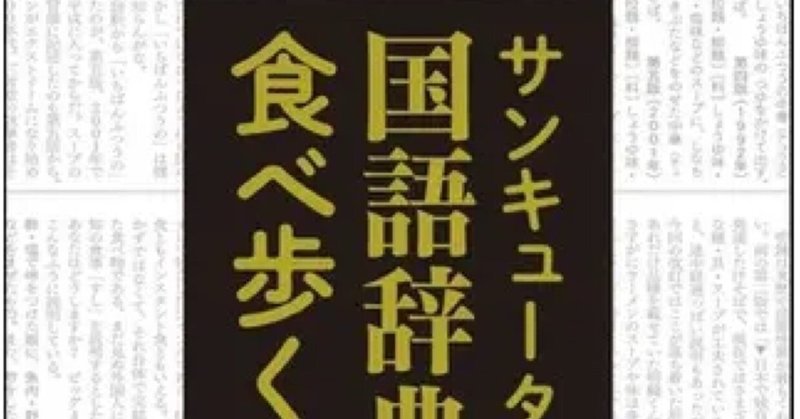
‘ちくわ‘が‘かまぼこ‘だった頃〜サンキュータツオ著「国語辞典を食べ歩く」
居酒屋のカウンターで一人飲んでいたのですが、隣に若いカップルが座りました。二人と私の間の卓上に、“季節のおすすめ“メニューが立っていて、二人はそれを吟味していました。すると、男の子が一品を指差し、「これなんて読むんだ」とつぶやき、スマホで検索しようとしていました。見ると、“冬瓜“でした。
私は思わず、「“とうがん“だよ」と教えてあげると、「“とうがん“? 食べたことないなぁ」と連れの女の子に話していました。二人は色々と注文しながらも、冬瓜はスルー。「知らなかったら、注文しなよ」と心の中で思っていた私でした。
サンキュータツオの「国語辞典を食べ歩く」を読みながら、あの二人はこの本を面白がることができるかしらと思いました。
サンキュータツオは、居島一平と漫才コンビ「米粒写経」として活動しつつ、日本語学関連の大学講師も勤めています。私は、彼の「国語辞典の遊び方」を読んで、各辞典に様々な個性があることを知りました。
彼の「国語辞典を食べ歩く」は、食べ物にまつわる言葉に焦点をあて、小型国語辞典“ビッグ4“を中心に、同じ言葉でも辞書によっていかに語釈が違うかを示しながら、編集者の工夫・特徴を記し、国語辞典がいかに面白い“読み物“なのかを説いています。
ちなみに、“ビッグ4“とは「岩波国語辞典」、「三省堂国語辞典」、「新明解国語辞典」そして「明鏡国語辞典」です。
この本を読むと、色々発見もあります。例えば、“目玉焼き“は、新明解では<鶏卵を二つ落として、並べて焼いた卵焼き(広義では、卵一つ使用のものをも指す)>です。私は普通卵1個ですが、あれは正式には目玉焼きではなく、広義で仲間に入れてやるという料理だったのです。
しかもこれは新明解のみならず、岩国も<鶏卵の白身・黄身をかきまぜず、普通は二つ並べて焼いた料理>。私は普通ではなかったのです。ただし、サンキュータツオは岩国に対して、<普通ってなんだよ、普通って>と突っ込んでいます。この本は、決して堅苦しい読み物ではなく、国語辞典を使って漫才を展開しているようなものでもあります。
“ちくわ“の項の見出しは、“そもそもは「ちくわ」が「かまぼこたった!?」“、情報満載でした。 新明解には、<すりつぶした魚肉を竹ぐしに丸く棒状に塗りつけて、焼いたり 蒸したり して作った食品。くしを抜いた切り口が竹の輪切りに似る。「焼きー」 ⇨板つき❷>とあります。
指示通り、「板つき」❷を引くと、<(←板付きかまぼこ) (竹串に刺して焼く古来のかまぼこと違って)長方形の小さな板に弓なりに魚肉を塗りつけ、蒸したものの称。略して「板」。⇨板わさ>にたどりつきます。
蕎麦屋の板わさの由来がわかると共に、もとは“ちくわ“が“かまぼこ“だったことを知ります。
さらに「かまぼこ」を調べましょう。明鏡にはその語源がこう書かれています。<古くは、円筒型にして細い竹にさして焼いた。その形が蒲がまの穂に似ていたことから> タツオさんは、<「がまの穂」、どんな?というか、「がま」って? 急いで画像検索してみてください>と書いています。
私が調べた画像はこれです。

<「がまのほ」が「蒲穂の子」「がまぼこ」となり、「かまぼこ」となったわけである。>
つまり、“ちくわ“は“かまぼこ“だったのに、板付きかまぼこが台頭し、区別するために“ちくわかまぼこ“と呼ばれるようになったのです。タツオさんは、これは「レトロニウム」というもので、<あとから出てきた概念の影響で、それと区別する必要が出てきた言葉のことだ>と教えてくれます。
「固定電話」「和室」「アナログ時計」のような言葉である。“ちくわかまぼこ“にいたっては、長すぎるので本来の意味である“かまぼこ“が省略されてしまったのです。
長くなりましたが、面白さ満載の労作。国語辞典がますます面白くなりました
ちなみに、私は電子辞書(「日本国語大辞典」「広辞苑第七版」「明鏡第二版」「新明解第七版」)、新明解第八版(紙)、「三国第七版」(iOSアプリ)で遊んでいます。ご参考として、私の「電子辞書」を巡る旅はこちらです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
