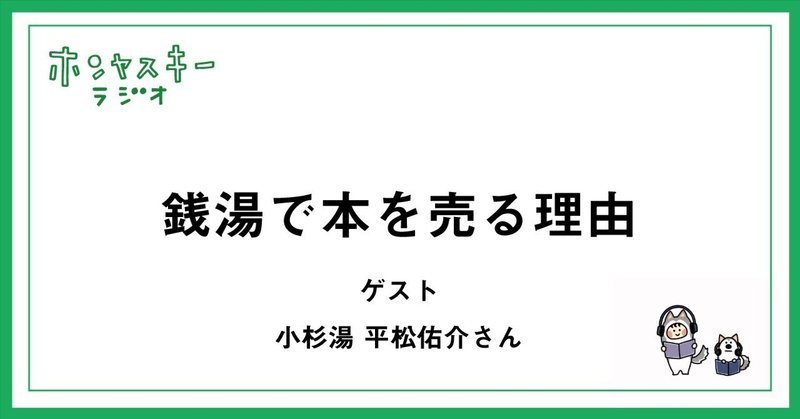
銭湯で本を売る理由
Podcast番組「ホンヤスキーラジオ」で配信されたアーカイブを再編集して記事化。今回のゲストは小杉湯の平松佑介さんです。「銭湯で本屋をはじめた経緯」「企画の発展のさせ方」や「場づくり」や「コミュニティー運営」について話を聞きました。〈2022年6月2日配信【銭湯と本屋のあいだ】より〉本配信はこちら。
<文・編集 ユースケさん>
三人の関係
まーちん:ホンヤスキーラジオのパーソナリティ。本と銭湯とそら豆が好き。
まっつん:ホンヤスキーラジオ助っ人MC。本とサウナと銭湯が好き。
平松さん:老舗銭湯「小杉湯」の三代目。銭湯を基点にした繋がりや、企業とのコラボレーションを生み出している。
まーちん:まっつんと平松佑介さんってもともと知り合いなんでしたっけ?
まっつん:そうですね。
平松さん:小杉湯で2018年かな・・・?オンラインサロンで、銭湯再興プロジェクトっていうのをやってまして、そのメンバーでまっつんが入ってくれたのが、きっかけですね。
まっつん:(あれから)4年ですか・・・。結構、経ちましたね。
まーちん:そのときから銭湯に関することで、お二人はやり取りされてるっていう感じですか?
平松さん:そうだね。その銭湯再興プロジェクトの中でも、同じメンバーの大崎の金春湯っていう銭湯を経営している角屋くんも入っていて。で、金春湯でね・・・
まっつん:うんうん、絵本のイベントとかも当時やっていて、お風呂の絵本を出版社さんにお声がけして、お風呂の中に絵本の世界を溶け込ませようみたいなことで、浴槽にいろいろ絵本の絵をかざったりとか・・・
平松さん:そのとき、まっつん、番台もやってくれてたりしたので。
まっつん:そうですね(笑)仕事帰りに小杉湯の番台してたりもしました。
銭湯で本を売る理由
まーちん:売ってみようとなったのって、何がきっかけだったんですか?
平松さん:それがいろいろあって、長野の松本の栞日という独立系の本屋さんを経営している菊地くんとの出会いがあって、栞日さんの前に建っている菊の湯という銭湯を継業する話になり、で、知り合いの藤原印刷の藤原くんから、菊地くんを紹介したいって話を言ってくれて、3人でオンラインで話したのがきっかけ。それで、そこでいろいろ話をして、独立系書店を長く経営していた菊地くんの話をきいたときに、菊地くんが銭湯を経営したらうまくいくなあってすごく思って。
まーちん:おー!
平松さん:その中で、「本屋と銭湯の共通点って、すごくいっぱいあるよねー」っていう話があり、銭湯ってシェアリングエコノミーで、番台でお金を払ってセルフサービスになるので、「人と人とのコミュニケーション」を設計するよりも「場と人とのコミュニケーション」を設計するなって思っていて、そこがやっぱり本屋さんも、書店員さんとのコミュニケーションで本を買うというよりかは、「本棚と人」とか、「書かれているポップと人」とか、そういう「場と人」とのコミュニケーションも成立しているみたいな話をしていたんだよね。
まーちん:うんうん。
平松さん:そのときに、当時の小杉湯の待合室もなんだけど、銭湯の待合室って、今、マンガ喫茶戦略みたいなのが主流で・・・。
まーちん:あ~、自分でその場で読めてってことですよね。
平松さん:でもそこで話し合ったときに、マンガ喫茶って、なんか満員電車っぽいっていうか、「自分とマンガの世界」になっちゃうんだよね。で、それがいいと思ってたんだけど、小杉湯の中でなんか一番銭湯っぽくない空間を作っていたなって。ちょっと違ったんだと思って、マンガ喫茶ではなくて本屋なんだって思って、まっつんにメンションしたんだよね。
まーちん:朝一だった気がします(笑)
まっつん:6時とか7時とか(笑)
どんな風にスタートさせたの?
まっつん:最初なので、もちろん本を売ることもそうなんですけれども、待合室の空間自体を、ちょっと流れを変えていきたいという話もされていて、当時は、まだ大きいソファーが待合室の真ん中に置かれてましたもんね。
平松さん:そうそう。
まっつん:そこの最初の一歩として、文庫本を真ん中にバッとタイルのように埋め尽くしていたんですけど。
まーちん:「湯守文庫」って名前をつけて。
平松さん:そうなんだよね。小杉湯の設計ってサウナがなくて、3つのお風呂と水風呂で交互浴っていうスタイルを推奨していて、人の動きが、ぐるぐる回るようになっているんだよね。
まーちん:お風呂の中で、ってことですよね。
平松さん:それはすごい意識してるのね。それで、待合室が、マンガ喫茶になっちゃうっていうのは、椅子とソファーが敷き詰められていたので、一回滞在すると、人が動かなくなっちゃうんだよね。それで、逆に、真ん中にブースをつくっちゃって、人が回れるようにっていうところと、両サイドに椅子を置くっていうのを、湯守文庫の取り込みから始めたんじゃないかな?
まーちん:そうですね。
平松さん:今もずっとそのパターンになっているからね。
企画の発展のさせ方
まーちん:わたし、(平松)佑介さんがすごいと思うのは、狙った動きに
なった後の発展のさせ方がうまいなと思ってて。
平松さん:あぁ、なるほどね。それはね、小杉湯でやってみて、小さく始めてみて、その風景をつくって、その風景を観察してでどうするかを決めていくっていうのが小杉湯っぽいやり方なんだよね。
まーちん:あ、なるほど!
平松さん:やっぱり日々営業してるから、大きくやっていくのがあんまり相性が良くなくて、「ちょっとソファー置いてみる」とか「ちょっと掲示を変える」みたいなのって日々やってるので、それでだんだん結構いろんな人が関わってくれるようになってきていてそうやって風景を作るっていうところから始まるので、だから作った後に育てていくんです。
まーちん:ブラッシュアップしていくんですね。
平松さん:そうだね。やっぱりすごく人が集まる要因として、「日々愛情を込めること」と「その愛情を形にし続けること」がすごく大事だと思っていて、その愛情を込め続けられた、そして、その愛情が形になった場と人との関係性なんだよね。
まーちん:うんうん。
平松さん:なので、だんだんといろんなコミュニティーが育ってきていて、全体を見た時に、待合室の本棚は、まっつんやまーちんが、愛情を込めてくれるじゃない?それでね、なんかね・・・ちょっと言語化しづらいんだけど、ある程度のラインを超えて日々愛情が込められるっていう状態が見えたら、もう任すんだよ。
まーちん:単に仕入れて売るとか、その商品を置くっていうただそれだけじゃなくて愛情を込めるっていうのがキーワードなんですね。
平松さん:そっちの方が大事だから。みんなにとって、どういう場にしてどういうふうな位置づけにしたほうがテンションが上がって愛情こめてもらえるのかなっていうのを考える。
まーちん:そっか!そうですよね!
「場作り」について聞いてみた
まーちん:ちょっと聞きたかったのが小杉湯さんって、いろいろ取り組みがあって、「小杉湯となり」だったり「あとは寝るだけ」が立ち上がったりとか、私から見てそれって「場作り」だし、そういうのをやっていく上で意識していることなど聞けると嬉しいなと思います。
平松さん:どの辺が場作りなんだろうね、それって。
まーちん:今日「小杉湯となり」にも、ちょっと顔を出させていただいたときにお話しさせてもらったんですけど、やっぱり小杉湯のことも大好きだし、小杉湯に来ていらっしゃる方のことも、とても大事に思ってるっていうのを、すごい感じるんですよね。それがみんながみんなを大事にしている、あったかい感じがして、「居場所」って言ったほうが正しいのかもしれないですけど、その辺って・・・。
平松さん:でもいろいろあるんだけど、やっぱりまず銭湯っていうのが大きい。小杉湯は、昭和8年から創業していて88年続いている。しかも同じ建物なので、建て替えをしていない。だから、さっき言ったような場に対しての愛情の積み重ねっていうのが途切れていないのね。
まーちん:うんうん。
平松さん:結構、建物を変えるって難しいなと思ってて、途切れちゃうんだよね。だから人の思いとか愛情みたいなものっていうのが、88年間積み重なっている。世代を超えて積み重ねられているっていうのが、まずすごく大きくて。で、それを登録有形文化財をとって、「50年後も100年後もここを残していきましょう」というのを共通の一番の目的にしている、というのがまず大きいと思っていて。
だから、これまでの100年とこれからの100年みたいな、時間軸がめちゃくちゃ長いの。この時間軸がすごく長いっていうのが重要だと思っていて、これだけ時間軸が長くなると、結局みんな、「最終的な目的が、この小杉湯の建物のままなんだ」「愛情を蓄積され続け、100年後も小杉湯を続けていくこと」が、みんなの共通の目的とおけると、みんな死んだ後の話になるじゃない?(笑)
まーちん:たしかに(笑)
平松さん:俺も死んだ後の話なんだよ(笑)だから、そうなるとすごいフラットになるんだよね。あくまで、その200年ぐらいの中の、俺は20年〜30年の管理人みたいなもんなんで、俺にも所有感がなくなるというか、すごく環境的になって、そこに対する関わりはフラットになるなっていうのは感じています。
それはね、やっぱり俺が創業者じゃないっていうところだと思うんだよね。しかも3代目だっていう。小杉湯は、小山さんが建てているのでそれをおじいちゃんが戦後に新潟から出てきてお金を貯めて買っているので、厳密に言うと4代続いているんですよね。
なので、そもそも平松家の創業者じゃなく、継承者であるっていうところはすごくやっぱり大きくて、それを続けていくっていうことがあるから、あんまり所有感がなくて、小杉湯という環境の中で、関わりにグラデーションがある。
だから、「小杉湯となり」のこともだけど、俺を中心に置いていなくて、あくまで「小杉湯という場・建物」を中心に置いていて、小杉湯という建物である場所との関係性で、俺とつながっていたりとかっていうところなんですけど、そこがねマジででかい。しかも、そこに日常の中でみんながお風呂に入りに来ているっていう、共通の「同じ釜の風呂」に入っている。
まーちん:たしかに!!
平松さん:なんかそういうところがあるよね、コミュニティーでいくと。なんか「同じ釜の飯を食う」とか、共通体験を日常の中に持っているっていうのが、相当でかいんだよね。
まーちん:そうですね。
平松さん:だからまずは、高円寺から半径2キロぐらいの中で、ちょっとした共通体験を持っている人たちが日常になっている人とのつながりが広がっていって、それがたまたま俺が2016年に小杉湯を継いだときに、今の「小杉湯となり」が建つ前の、風呂なしのアパートがあったんだけど壊すことになって、1年間たまたま空き家になって、もったいないなぁみたいに思ったときに、俺の友達から(銭湯ぐらしの)加藤ちゃんを紹介してもらって出会ったんだよね。
彼は、建築家であり、まちづくりの専門家なので、そういった中でエリアリノベーションみたいな観点で、ここを暫定利用でプロジェクトをやったら、面白いですよねって提案してくれた。「小杉湯となり」が生まれたのは、加藤と出会ったからなんだよね。
加藤ちゃんと出会わなければそういうところも生まれてないし、
小杉湯のとなりも生まれていないっていうのはすごく思っていて、それには、環境がすごく大切で、その環境があるからこそ、人のつながりが起きるけど、最終的に何かが起きるっていうのは人と人との縁だね。
ただ、その中心の流れを人に置いていないというのがすごい重要だなと思っていて、なので小杉湯の運営において、スタッフとして常に確認するようになっているのは、自分たちの目的は小杉湯を続けることです。日々の目標は「毎日、キレイで清潔で気持ちのいい銭湯に向き合うことだね」っていうのが、みんなで共通の目標にしているんだよね。まだまだできてないところもいっぱいあるんだけど、それがみんなの目的と目標になっている。
まーちん:うんうん。
平松さん:なので、そこだよね。続いていく建物があって、そこの環境が、とにかく本当にきれいであること、清潔であること、これがめっちゃ重要なんだよね。きれいで、そして気持ちがいい。
まーちん:その中で、人の流れとかつながりを大事に思っている人が多いから、コミュニティーになっているみたいなイメージですかね。
平松さん:そうだろうね。そこの出会いとか人との出会いで生まれていく。だから、まっつんと出会ってなければ、本屋を小杉湯でやってることはないと思うんだよね。
まっつん:小杉湯は、イベントをいろいろやっているように見えますけれども、やっぱり一貫しているのは、きれいで清潔で気持ちがいいというところで、本屋にしても、「小杉湯はなんで本を売ってるんだろう」っていうところから始まって、そこでたまたまお風呂上がりに出会った本を買って帰って家で読んで、小杉湯の気持ちのいい時間を思い出してもらえるっていう話を、始める際に平松さんもしていたので、そういうところで、根底というものがないと、というか、あるものだけが小杉湯で展開されているのかなって、僕も実際に一緒にやってみてすごく感じました。
コミュニティーの運営について
まーちん:小杉湯学生企画チームの「BUKUBUKU」のみんなが楽しそうだし、かわいい活動をしているイメージがあるんですけど、結構伸び伸びやってるイメージが強くてその辺とかは、何か意識してることあるんですか?
平松さん:確かに今までのいろんな経験が集積されていて、いわばコミュニティーの運営だと思うんだよね、8人だし。いろいろあると思うんだけど、「BUKUBUKU」みたいな形でいくと、最初から重要視したのが、「期限を決めること」あと、「小さくてもいいのでお金の流れをちゃんと作ること」っていう、2つがすごい大事っていうのは思ってたのね。
学生という観点でも、当然、卒業があるわけだから、まずちゃんとできたことがすごい重要だったなっていうのと、1期1年になって、今は2期目になっていて、2期目が今8人になっているので、何とか1年かたちになって、次に継承できたのは「期限が決まっていたこと」と「お金の流れがあったこと」っていうのはすごく大きかった。
まーちん:その2つは、始める時に今までの経験から絶対外しちゃダメっていうのがあったんですね?
平松さん:そうそうそう。あとやってみてこれも思ってたんだけど、位置づけをきちんと明確にすること。
まーちん:位置づけっていうのは?
平松さん:「BUKUBUKU」で話すと、「BUKUBUKU」がはじまったきっかけも、いっくんとの出会いで、彼がその当時、銭湯を自分でやりたいという思いを持っていたりとか、すぐ近くに住んでて、コロナの影響もあって、1年休学することにして、銭湯を自分でやるかどうか向き合いたいって。それで、タイミングもよかったので、だったら一年、小杉湯でインターンみたいな形で、やってみるのもいいかもね、ってところから、「ぜひやりたいです」ってなったのが、きっかけだったんだよね。
で、やっていったときに、俺も時間が限られてるので・・・。俺一人で、いっくんを見切れないなぁ、みたいなのもあったし、いっくんがこのまま一人でやるのが彼にとって本当にいいのかなみたいに思った時に、インターン自体をもう集めた方がいいなって。
まーちん:うんうん。
平松さん:そしたら、当時は、コロナの影響もあったので、休学したりとかみたいな学生アルバイトも多かったんだけれども、声をかけていったら8人集まったんだよね。
それで、最初はインターンシップって言ってたんですよ。「小杉湯でもインターンをやろうって」ていうふうに言ってたんだけど、そこはみんなが話し合ってくれて、結果的に「小杉湯学生企画チーム」って名前になったの。それで、自分たちで決めてくれて、小杉湯と高円寺をぶくぶく沸かすっていうので「BUKUBUKU」ってなったの。小杉湯のアルバイトスタッフである8人は、手が回っていないところとか、そういうところを自分たちが担うみたいな、あくまで「小杉湯の中の学生アルバイトがやっている企画」っていう位置づけになったんだよね。
これは重要だったの。インターンシップでやるよりも、そのコミュニティーというか、その共同体みたいなものの、定義をちゃんとスタートするのもすごい大切だなっていうのは、「BUKUBUKU」から学んだ。
まーちん:面白い!人が集まると、意見のすり合わせが大変になってくると思うんですけど、少人数に比べると、そこの意思疎通とかは、参加して
いるみんなが自発的にやっていたんですか?
平松さん:参加しているみんながやってた。
まーちん:なるほど。こっちから働きかけるというよりは、あったらやるぞみたいなスタンス?
平松さん:えーとね、毎月、活動費みたいなのを、小杉湯で出していたので、それが活動資金になっていたんだよね。
まーちん:2個めのポイントででた「お金の流れをつくる」ってことですね。
平松さん:それを、例えば福島や佐賀の唐津に行ってるんだけど、交通費や宿泊費にあてたりとか、日々のがんばったときの打ち上げにしたりとか、企画チームが物販の企画をやったときに利益を「BUKUBUKU」にシェアする仕組みとかにしたりとか。
まーちん:工夫しつつやってみて、相乗効果でよくなっていく感じ。
平松さん:もちろん、いろいろあるんだけど、やれたのはすごいよかった。
なぜ期限を決めるのは、重要なのか?
まっつん:最初から期限を決めていたのは、どんな思いからだったんですか?
平松さん:それは、銭湯再興プロジェクトをやってみても思ったんだけど、コミュニティーとして、前提続けていくのがある中でも、やっぱりゴールが必要で、1つの期限っていうのはすごい重要だと思うんだよね。
いつまでって決まっているってことが。1期・2期・3期みたいな感じでね。
小杉湯の一番の目的が、50年から100年続けるっていう話の時に、要はそれって俺の場合には2代目から3代目の継承があったわけじゃない?で、次には3代目から4代目があって4代目から5代目があるわけじゃない?それだけ長い期間続けていくっていうのは。
結局、小杉湯の場合、継承し続けていくっていうのが、大きな継承の場合、30年とかスパンじゃない?
まーちん:そうですね。
平松さん:そこもね小さくしていくっていうのが、すごい大事なんだなって思った結果、「時間を区切る」っていうふうに、俺が思ったのかな。
まっつん:なるほど。
平松さん:「BUKUBUKU」が1期から2期に継承されました。これが、一年ごとに継承されていきます。そこには、卒業生も出てくる。どんどんOB・OG的な存在も増えてくよね。どんどん積み重なっていくよね。それも継承なんだよね。この小杉湯というコミュニティーの中で、どれだけ、「小さい継承」をいっぱい増やせるかという集積が、小杉湯が50年100年続いていくことになるんだなって、すげぇ思ったんですよ。
まっつん:小さい継承・・・。
平松さん:期限を切っているのはそういう意味なんだよね。吉本の芸人さんって、「第◯期」ってすごい言うじゃない?
まーちん:う〜ん。
平松さん:期限が切られた時間の中で、共に過ごしていた同期みたいな感じじゃない?そこの何期っていうのがすごく強くなるじゃん?あれもたぶん、吉本興業は長く続いている会社だけど、そういうことな気がする。
まっつん:続けるために、区切っていく?
平松さん:そうそうそう。
まーちん:なんか、すごいな(笑)
三人:(笑い)
ホンヤスキーラジオ絶賛配信中
本屋好きがお届けする、ゆるいラジオ配信。毎回、異なる本と本屋をテーマに、様々なトークを繰り広げていきます。私たちの暮らしの近くにある「本屋さん」。それぞれのまなざしから、楽しみ方を紹介していきます。本棚の前で談笑しているようなよもやまトークをお楽しみください。
お便りはこちら。
ホンヤスキーラジオnoteを読んでくれてありがとうございます。この記事を気に入ったらスキを押していただき、SNS等で拡散していただけると嬉しいです。サポートいただけたら、今後の収録費用にあてさせていただきます!感想お待ちしております!
