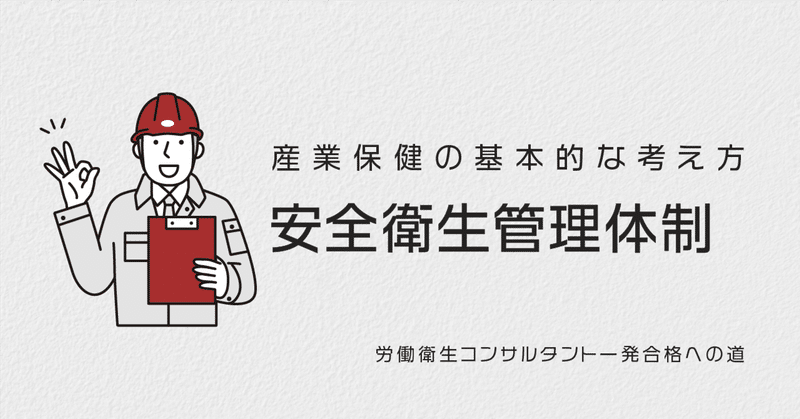
安全衛生管理体制
労働安全衛生法では、労働災害を防ぎ、事業者の自主的な安全衛生活動を確保するため、事業者は、下の図のような安全衛生管理体制を整備することが義務づけられています。 安全衛生管理体制は、事業場の従業員全員が協力して安全衛生を進めていくために必要なものです。
参考:安全衛生法施行令第2条第1号の職種の例
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001210673.pdf

参考:自動車整備業(安全衛生法施行令第2条第2号の職種)の例
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/100119-1c.pdf

紛らわしい用語の説明
「選任」は、人を選んで役職を任せること
「専任」は、任せられた役職の仕事のみを行うこと
「専属」は、その事業所のみで働くこと
「嘱託」は、専属ではなく、複数の事業場で働いてよいという契約で役職を任せること
事業者とは
法人であれば当該法人、個人企業であれば事業経営者を指し、法人である会社自体が労働安全衛生法の定める措置を講じる責任を負わされます。
総括安全衛生管理者とは
労働安全衛生法上、常時1000人以上の労働者を使用する事業場で、事業全体の責任者から選任し、事業場全体の安全衛生管理を統括したり、安全管理者、衛生管理者を指揮する者です。
衛生管理者とは
労働安全衛生法上、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場の規模に応じて、原則としてその事業場に専属のものの選任が義務づけられています。衛生管理者になるには、事業場の行に応じ、一定の資格(労働安全衛生法第12条第1項、規則第7条)が必要です。衛生管理者は、総括安全衛生管理者又は事業者を補佐する者で、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する者として位置づけられています。また、少なくとも毎週1回、作業場の巡視をしなければなりません。
安全管理者とは
労働安全衛生法上、常時50人以上の労働者を使用する安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号の職種では、事業場で選任が義務づけられています。安全管理者に選任されるには、一定の資格(労働安全衛生法第11条第1項、規則第5条)が必要です。安全管理者は、総括安全衛生管理者又は事業者を補佐する者で、総括安全衛生管理者の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する者として位置づけられています。適時、作業場の巡視をしなければなりません。
安全衛生推進者とは
労働安全衛生法上、常時10人以上50人未満の労働者を使用する政令で定める業種(安全衛生管理者を選任すべき業種と同じ)の事業場で、資格者(一定の学歴と実務経験等)からの選任が義務づけられています。安全衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者と同様の業務を担当する者として位置づけられています。
衛生推進者とは
労働安全衛生法上、常時10人以上50人未満の労働者を使用する安全管理者を選任すべき業種以外の業種の事業場で、一定の講習を受講したものからの選任が義務づけられています。衛生推進者は、衛生管理者と同様の業務を担当する者として位置づけられています。
産業医とは
労働安全衛生法上、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、資格者(医師で一定の研修修了者等)からの選任が義務づけられています。産業医は、労働者の健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、労働者の健康障害の原因の調査と再発防止のための対策の樹立等労働者の健康管理を行うこととしています。月1回作業場の巡視をしなければなりません。(条件を満たせば、2か月に1回でもよい。)
作業主任者とは
危険を伴う作業を労働者に行わせる場合、労働災害発生を防ぐためには、その作業について十分な知識と技能を持つ者に労働者の指揮をとらせるのが効果的である。その指揮をとるものとして、事業者に選任されるものを作業主任者という。作業主任者になるには、作業の種類ごとに定められた(安衛法施行令第6条)、免許の取得または技能講習の修了が必要である。
安全衛生委員会
労働安全衛生法上、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、危険防止の基本対策、健康障害防止の基本対策等を審議し労働者の意見を聴く場として安全・衛生委員会の設置が義務づけられています。
法令で決まっている安全衛生教育にはどのようなものがありますか?

①雇い入れ時教育
すべての労働者を対象に雇い入れ時
②作業内容変更時教育
すべての労働者を対象に作業内容の大規模な変更時
③特別教育
安全衛生施行規則第36条で定める危険有害業務に初めて従事するとき
④職長等教育
安全衛生施行令第19条で定める業種の職長などに初めてつく時、一定期間ごと(約5年)、大幅な変更があったとき
⑤危険有害業務従事者に対する教育
特別教育の対象となる業務、労働安全衛生施行令第20条に定められた就業制限に係る業務、これら二つに準じる業務に従事する者を対象に一定期間ごと(約5年)
⑥安全衛生業務従事者に対する能力向上教育

⑦健康教育
すべての労働者に随時
☝産業保健職に限らず人事労務の担当者など産業保健にかかわるすべての人にオススメ
☝労働衛生コンサルタント試験のバイブル
次の記事
前の記事
ホーム
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
