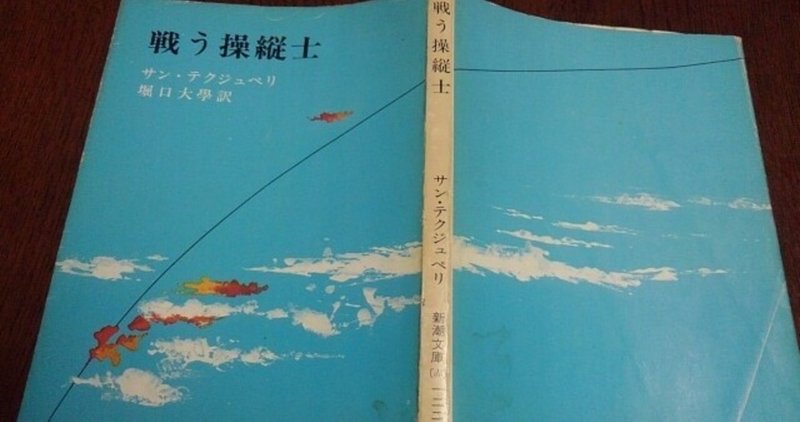
戦う操縦士の還る場所
手元に何年も前から置いているのに、読むのをためらっている本が二冊ある。
アンネ・フランクの『アンネの日記』と、サン=テグジュペリの『戦う操縦士』だ。この2冊の本の作者との出会いは、私が小学生の頃だった。
私が通っていた小学校では、おそらく長崎の原爆投下の日(8月9日)が夏休みの登校日だった。その日は、戦争を学ぶ日になっていた。
私が当時住んでいた場所は戦時中、武器を製造していたため、アメリカ軍が原爆を投下する予定地にしていたという。ところが、当日は曇りで見通しが悪かったため、原爆を投下する地点を長崎に変更したそうだ。
先生からは、この場所に落とされなかったことが幸運とかそういうことではなく、これからは戦争を起こさない様な世界にしようということと、戦時中の日本ではどういうことが起きていたかを教わった。
日本国内で起きていたおぞましい出来事の数々に私は恐れを抱いた。
どうすれば戦争が起きないかという壮大な問題に対する答えは、決して出ることがなかった。
『アンネの日記』は、小学校の同級生の女の子たちの間で人気だったが、私は読むことができなかった。
私よりも少しお姉さんのアンネが可哀想だと思い、読めなかったのだ。
そんな中、私が挿絵を気に入って読んでいた愛読書が、サン=テグジュペリの『星の王子さま』だった。
だが、小学生の私には本書でただ一つ、大いに気に入らない箇所があった。それは、自身の星に戻りたくなった王子さまが、還る手段としてヘビに噛ませて死ぬ道を選んだことだった。
『星の王子さま』は、第二次世界大戦下、アンネと同じユダヤ人であったレオン・ウェルトというサン=テグジュペリの旧くからの友人に捧げている。しかし、本書はサン=テグジュペリの妻であるコンスエロに宛てた遺書であり、戦争の愚かさと、彼が今まで経験してきた苦難と共に、温かい思い出を綴ったものだと私は考えている。
『星の王子さま』は、本書自体が暗号化されたメッセージのようなところもあり、彼の著書である『人間の土地』と、妻コンスエロの存在を知ると、その意味を少しでも理解することができるはずだ。
社会人一年目の真冬、当時私は、関東にある大きな土木工事の現場に配属されていた。そこでは大規模な地すべりが起きていて、昼夜問わず地すべりの監視が行われていた。
金曜日の夕方から土曜日の朝まで夜勤をした後、寮で一眠りした私は、箱根で短期の単身赴任をしていた父に会いに行った。
父と別れた月曜日の朝、ひとりでふらりと『星の王子さまミュージアム』に立ち寄った。
そこで、私はサン=テグジュペリの幼い日々の温かい思い出に溢れた家や、そして命を懸けた飛行の数々と、妻コンスエロの存在を知った。
不思議なことに、そのミュージアムで彼の物語が私の物語であるかのような錯覚を受けた。無論、彼の歩んで来た道とは、私の歩んで来た道はまるで違う。だけれども、私の中にも、サン=テグジュペリの中に灯っているのと同様な温かな光があるのを感じた。
宮崎駿監督も、『サン=テグジュペリ デッサン集成』の前書きで次のように述べられている。
『サン=テグジュペリを想う時、まるで自分の体験であったかのように、ありありと情景が浮かんでくる』と。
サン=テグジュペリは、新航空路を開拓していた時代にアエロポスタル社に入社し、郵便飛行路線の班に投入された。
そこで彼は、彼に精神面と技術面において厳格な指導をしたという上司のドーラや、同僚で友人でもあったメルモーズやギヨメと出会う。
命を預けても良いと思える心から本当に信頼のできる人との出会いは、紆余曲折あったとしても、心の中に光となって残り続けるのだ。
地すべり対応に追われていた当時の私にも、同様に初めて心から信頼できると感じられた上司との出会いがあった。
一生のうちに滅多に起きることではない奇跡のような出会いというものは、ある日突然、ギフトのようにやってくるものだと思う。
今年、A市で起きた中学生の女の子がいじめが原因で亡くなられた事件で、遺族により公表された写真や文書は、中学生当時の私が決して知り得ることがなかったであろう、ぎょっとするような言葉で溢れていた。
その子にとって心の拠り所となる安らぐ場所や、人は全くいなかったのではないだろうか、そして、その子が体験したものは、新たな形の武器を使った戦争ではないだろうかと思った。心の灯火も同時に吹き消す戦争もある。
簡単に言えることではないが、心の本当に安らぐ家を皆が持つ様になれば、世界は変わってゆくのではないだろうか。
『ホビット』という映画がある。
本作は、竜に奪われたドワーフの王国を取り戻す話で、これが『ロード・オブ・ザ・リング』に繋がってゆく。
黄金に目がくらみながらも最期には自身を取り戻したドワーフの王トーリンが、独り者だけれども家が大好きで欲のないホビット族であるビルボに戦いが終わった後、こう告げる。
『本が待っている。肘掛け椅子が待っている。ドングリを植えて、育つのを見よ。皆が黄金でなく、家を愛する様になれば、世界はもっと楽しいところになる』と。
ビルボとトーリンの決定的な違いは、育ってきた家庭で温かな思い出があるかないかだろう。そのビルボが持っている美味しい食卓や家での温かな出来事の記憶は吹き消そうとしてもまた蘇り、消えることは決してない。
アンネや、サン=テグジュペリに共通しているものもそれで、どんなに世界が暗闇になろうとも、温かな記憶や大事なものがあり、愛や、生きてこそやり抜きたい希望の光が灯っているのだ。
そして、その光は自分自身や他者を救う力を持つ。
アンネからは、『アンネの童話』において閉じ込められた生活の中からも光を見出そうとしたその文章から、それを痛いほど感じることができる。
一方、サン=テグジュペリの場合は、母に宛てた手紙(サン=テグジュペリ『平和か戦争か』より)等からそれを感じることができる。
『わたしにはあなたの愛情が限りなく必要です。わたしがこの地上で愛しているすべてのものが、なぜ脅かされなければならないのでしょう?戦争そのもの以上に私を怖れさせているのは、明日の世界です。破壊されたすべての村々、離散したすべての家族。死ぬのはわたしにとってどうでもいいことです。でも、精神の共同体にだけは手を触れられたくはありません。わたしたち全部が白布をかけた食卓をかこんでつどうことをわたしは願いたいのです。
(略)
渇きを癒してくれる唯一の泉、わたしはそれを子ども時代のいくつかの思い出の中に見出します。たとえば、クリスマスの夜の蠟燭の匂いに。今日、ひどく荒れ果ててしまっているのは魂です。ひとは渇きのために死にかけています。
ものを書こうと思えば書くことはできますし、時間もあります。でも、書くことはできずにいます。わたしの書物はまだ自分の中で熟していません。《飲むものを与えてやれる》ような書物が。』
サン=テグジュペリの著書『戦う操縦士』は、彼の祖国フランスがナチスドイツにより侵され、アメリカに亡命した後に出版されたものである。
本書は、ヒトラーの『わが闘争』に対抗する声明文とされ、賛否両論を巻き起こし、対ナチス戦に偵察飛行隊として彼が参戦したときの、実録として記されている。
その後に出版されることとなる、『星の王子さま』の推敲の段階におけるヘビに、ナチスドイツの文様が刻まれている絵があったのを、私はどこかで見たことがある。そして、バオバブの木は、ヨーロッパを侵略したナチスドイツの災害の表徴であると聞いたことがある。
サン=テグジュペリの妻、コンスエロは彼がものを書くよう、ずっと促し続けていたという。
戦争、特にナチスドイツへの憎しみが、表層に現れていたはずの『星の王子さま』を妻や、幼くして病気で亡くなった弟や、家族への愛で闇を覆い隠した本書は本物の愛の結晶であると思う。
そして、本書のラストシーンは、数々の飛行機事故の後遺症で自由に動けない重い身体となってしまい、戦死することを予想していた彼が、魂は必ず愛するコンスエロのもとへ還るよ、というラストメッセージのように思えてならない。
それだけではない。本書は、砂漠の中で生き、真実の泉を見つけようと彷徨い歩き続ける全ての現代人に当てはまるメッセージなのである。
宮崎駿監督は、この世界を『何もかもコスト計算がいき届き、物はあふれ、何が大切で何が大切でないのかの区別もなくなり、量の氾濫により、あらゆるものの質を変えてしまった白蟻の塚("白蟻の塚"は、サン=テグジュペリの言葉)』と例える。
それでも、宮崎駿監督はこう記す。
『白蟻の塚に、
子供達は生まれてくる。
傷つけられ、鋳型に押し込まれるために・・・・・・
破れ続ける傷口をかかえながら、それでも、ぼくらは生まれたばかりの子供達を眼の前にして、どうして祝福せずにおられようか。あらゆる可能性をその子が持って、そこにいるのに・・・・・・。世界がもはや白蟻の塚ですらなく、人類がこの星の癌細胞になって、じきにこの星を喰い尽くすとしても、白蟻は白蟻の文字で世界の美しさについて書くしかないのだ』(『サン=テグジュペリ デッサン集成』より)
私も白蟻の一人として少しでも言葉を紡げるように、そして世界を知るために、今こそアンネ・フランクの『アンネの日記』と、サン=テグジュペリの『戦う操縦士』を読まねばならない時期が到来してきたように感じた。
(了)
☆ ☆ ☆
本記事を書くにあたって、参考にしたその他の本は以下のとおりです。
いつも、私の記事をお読み頂き、ありがとうございます。頂いたサポートは、私の様々な製作活動に必要な道具の購入費に充てさせて頂きます。
