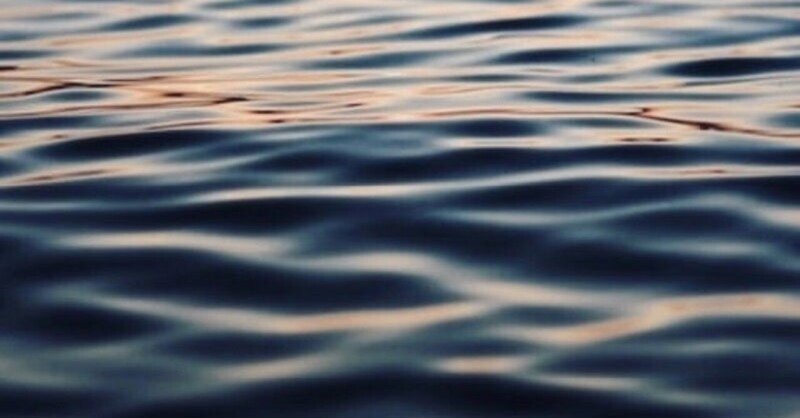
2回死にかけた話
今回は、私が20数年生きてきた中で2回死にかけたことがある、という話をしようと思う。少し長くなってしまったが、どうか最後までお付き合いいただけると嬉しい。
1.身体的に死にかけた話
1回目は小学生のとき。夏休みに父の実家に帰省した際に、海で泳いでいて溺れかけた。当時私はかなづちで、学校のプールで何度泳ぎ方を教わっても、全くと言っていいほど泳げなかった。「あぁ、私はこのまま一生泳げないんだな……」と半ば諦めていて、海で泳ぐときは浮き輪が必需品だった。
反対に、弟は小さい頃から水泳教室に通っていて、表彰もされるほど泳ぎがうまかった。弟は海でも父と一緒に遠くまで泳いで、深く潜って、岸辺で波とたわむれることしかできない私にたまに海の底の貝殻や石といったおみやげを持ってきてくれた。
かといって全く浮き輪を使わないというわけではなく、私と一緒に浮き輪で泳いで遊ぶこともあった。その日も私たちは岸からちょっと離れた岩場で、浮き輪をしながら遊んでいた。岩場は結構点々とあって、それらを行ったり来たりしながら岩場の魚や貝を観察したり、澄んだ海の世界に感動したりと忙しくしていた。しかし、ここでちょっとしたハプニングが起こるのである。
弟が海に潜るために岩場に置いた彼の浮き輪が、波にさらわれて流されていってしまったのだ。気づいた頃にはすでに5〜10mほど流されていたのだが、これは近いようで子どもの力ではなかなか届かない距離なのである(当時、風もそこそこ吹いていて追い風のようになっていた)。私たちは必死に浮き輪を追いかけるわけだが、浮き輪はどんどん遠ざかるし、その日朝からほぼ1日中海で遊んでいた私たちには、これ以上泳げるほどの体力が残っていなかった。で、私には浮き輪があって、弟には浮き輪がないこの状況で、なぜか私は岸に置いていたバナナの浮き輪の存在を思い出し、弟のために取りに行くことにしたのである。そして、手にはバナナを、腰には浮き輪をして、岩場で待つ弟の元に駆けつけるのだが、浮き輪が流されたときからずっと動揺していた私は、弟にうっかり私の浮き輪を渡してしまうのだった。受け取った弟は浮き輪で先に岸まで泳ぎはじめ、さて私も岸に戻ろう、と思って初めて気づいたことが、このバナナ、掴む取手はあるが水面だと不安定で、掴んだ状態で泳ごうとすると途端にひっくり返ってしまうのである。
かなづちの私にとってこのバナナを掴みながら泳ぐことはほぼ浮き輪なしで泳いでいるようなもので……。ていうか泳げないし。泳ぎ方分からないし。でも岸に戻らなきゃ、と思ってた矢先に急にバナナが勢いよく回転して、私の手から離れてしまったのだ。いきなり海の中で身一つになった私は、焦って手足をバタバタさせてしまったのだが、バタバタすればするほど身体が海に沈んでいって、呼吸をすることもままならず、ただ必死に弟の名前を呼んでいた。このとき、「やばい、私溺れかけてる、この手を止めたら確実に死ぬ」と思ったことを今でもはっきりと覚えている。
幸いにも弟がすぐに気づいて戻ってきてくれたため、完全に溺れずに済んだ。
しかし人間とは恐ろしいもので、私はこの日を境に急に人並みに泳げる術を獲得したのだった——。
(ちなみに補足しておくと、実際溺れたときに手足をバタバタさせることは逆効果であり、また体力を消耗してしまうことでもあるので、思い切って全身の力を抜き、背浮きして救助を待つのが正しい対処法である。)
2.精神的に死にかけた話
2回目は、新卒で入社した会社を半年で辞めたとき。精神的に病んで、希死念慮が頭から離れなかった。幸いにも実際に「自殺したい」と思ったり自殺を試みたりといったところまで追い詰められてはいなかったけれど、あのときの自分は明らかに普段の自分ではなかったし、感覚としては割と毎日、死の淵に立っていた。
それでも私の中のもう一人の自分がずっと手を繋いでくれていて、そのおかげで暗闇の中にいても足を踏み外しはしなかったのかもしれない。そのもう一人の自分とは、今まで自己肯定感が低いながらも、それでも自分を無条件に信じている自分だった。その子は普段はとても存在感が薄くて、たまに見失ってしまうこともあるけど、いざというとき誰よりも私のそばにいてくれて、私の価値を、私の存在意義を、私の生きる意味を、そっと教えてくれる。
そして、実は私を引き止めてくれた人はもう一人いる。会社を辞めたあとに働き始めたバイト先の人なのだが、私はそのバイト先に大学生時代もお世話になっていたため半ば復帰したようなものではある。ただ、やはり一度就職を理由にバイトを退職していて、もうそこで働くことはないと思っていたため、もう一度働かせてくださいとメールを送るのがとても気が引けた。当時自己肯定感が低かったこともあるが、事情を話して「半年で辞めたの?」と笑われたり「いま人は足りてるから君は必要ないよ」と言われたらどうしよう、と怖かったのだ。
しかしそれは杞憂だった。その人はすぐ返信をしてくれて、働くことを歓迎してくれた。初日に会ったときにはすごく心配してくれて、私を肯定してくれたその気遣いがすごく温かかったのを覚えている。
当時、私は退職したことで幼少の頃からの長年の夢を失い、特に生きる目的もなくただただバイトに明け暮れていた。家にいても希死念慮と前の職場でのトラウマがフラッシュバックして涙を流すことしかできなかったため、気を紛らわせるために毎日職場に通っていた。それでも、通っているうちに、日に日に自分の心が回復していくような感じがした。それは怪我した傷が少しずつ癒えていくように。いちど枯れかけた植物にまた息吹が通うように。
職場の人は皆すごく温かくて、その心に触れるたびに「私はまだ生きていていいんだな」と思えた。そしてしばらくしてその人から「笑顔が戻ってよかった」と言われて初めて、私は以前のように自然に笑えるようになっていることに気づいたのだった。
また、その人はそれだけに留まらず、私の転職支援までしてくれた。残念ながら縁がなくて不採用となってしまったけれど、「理由が理不尽だ!」なんて怒ってその会社に抗議までしてくれて、本当に頭が下がる思いである。
病んだ心から立ち直ったとき、私の中では再びこの世に生まれたような感覚があった。だから今までの自分は一回死んだも同然なのである。
きっとその人がこのnoteを読むことはないけれど、それでも、私がとても感謝していることをこの場を借りて書き残しておきたい。これはもう命の恩人と言っても過言ではないから。だから、この恩に報いるために私はどうしたらいいのかを、残っている私の命の使い方を、いつまでも模索し続けている。
ろ〜たすは、徒然なるままにエッセイを書いております。サポートいただけると泣いて喜びます。
