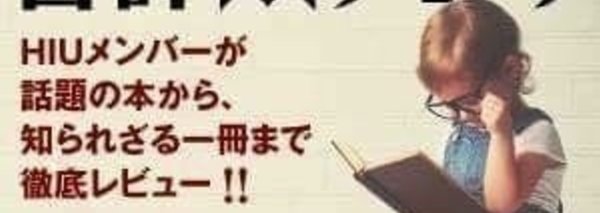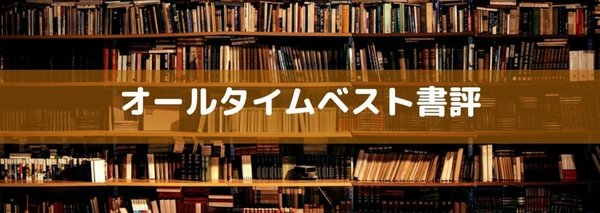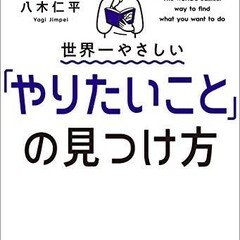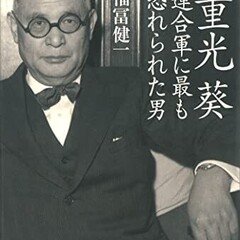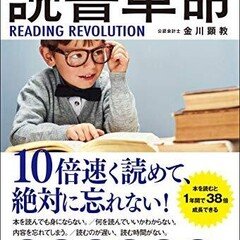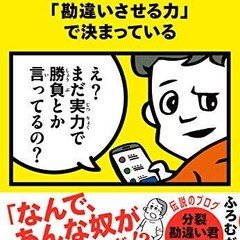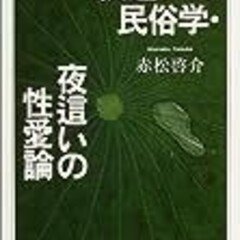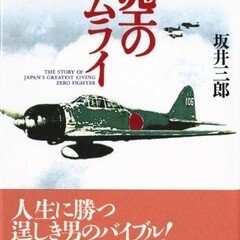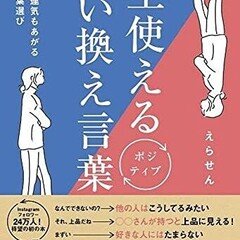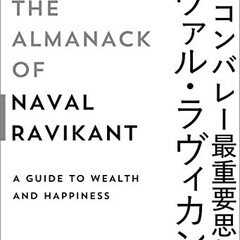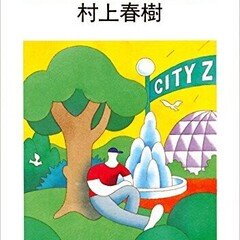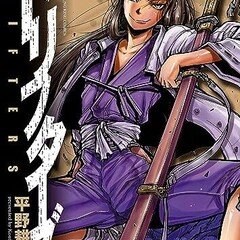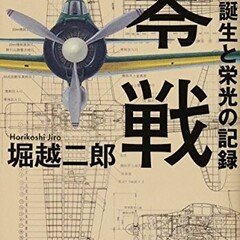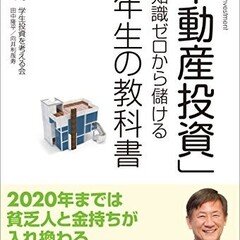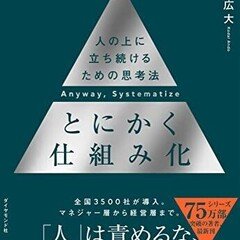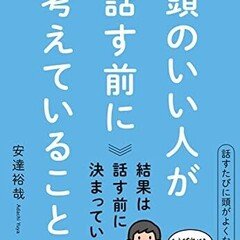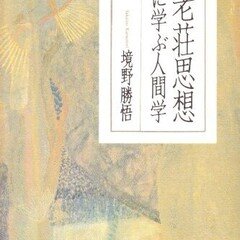最近の記事
- 固定された記事

書評_一日中TikTokを見て時間を消費している人へ__世界一やさしい_やりたいこと_の見つけ方_人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド
仕事が楽しくない。暇な時間はTikTokをずっとみている。人生を消費しているだけな気がする。そんなあなたへ、まずはこれを読め。Amazonで読み放題だし、あなたの好きなYoutubeであっちゃんが解説しているものでもいい。これを読めばやりたいことが確実にみつかる! 本書は、具体的なステップを踏みながら、読んでいくうちにやりたいことが見つかる本だ。 ほとんどの人は勘違いしている。行動しなくてもやりたいことは自分の中にある。人の役に立たなければいけないわけじゃない。やりたいことは人より得意でなくてもよい。 やりたいことを考えるにはいくつかのステップがある。まずは、価値観を考えることだ。尊敬する人は?理想と異なることは?子供がいるとすると何を伝えたい? 価値観が分かれば次は、得意なこと、好きなことだ。得意で好きなことから価値観に合うことを探していくと、本当にやりたいことがみつかる。 やりたいことをやると人生はどうかわるか。仕事がストレスでなくなるので、休暇はもっと有意義に過ごせる。やりたいことのためにさらに勉強をつみ、スキルも向上するだろう。やりたいことは人生を変える。 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド 作者:八木 仁平 KADOKAWA
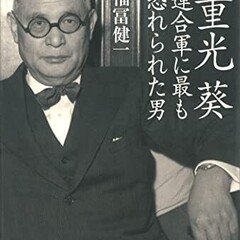
書評_歴史の舞台裏から学ぶ大東亜戦争シリーズ5__重光葵_連合軍に最も恐れられた男
終戦記念日がおわりましたが、果たして8/15が何で終戦記念日なのでしょうか。8/14にポツダム宣言を受諾し各国に通告、8/15日本が降伏宣言(玉音放送)、しかし、ソ連の侵攻が続き8/20ソ連→樺太真岡郵便局事件、そして、9/2重光葵(まもる)がミズーリ号で調印。なので、9/2が終戦記念日と思う今日この頃です。今回は大東亜戦争(第二次世界大戦)について少し学び、この調印した重光葵(まもる)と大東亜戦争とよばれる由縁、アジア諸国の礼賛についてお伝えしたいと思います。 重光葵は昭和七年、上海におり、天長節の式典に参加していました。そこで、国歌斉唱中に爆弾が投げ込まれ、片足を失います。国歌斉唱中だったので、動くと不敬なので逃げなかったのです。凄い胆力と忍耐力です。その後、重光葵(まもる)は東条英機内閣の外務大臣になります。そして、大東亜共同宣言を提唱し、大東亜会議を開催し、戦争の目的を「アジア解放」と位置づけたのです。本書にはこう書かれています。 【「首相もご承知のとおり、英米は大西洋憲章を説い小国民、小民族の保護者と宣言しておりますが、その実はバルト諸国やポーランドを画したように小国民は牲になっております。」 【しかるに日本は、小国民,少なくともアジア民族に自由を与え、自由を保護する地位に立っており、そのため主権尊重と平等対等な関係を基本にした大東亜憲もしくは太平洋憲を作るベきと考えます」】 【「アジアの解放、建設、発展が日本の戦争目的です。帝国はすでに支那において平等に取り扱う新政策に乗り出しております」重光は、大東亜戦争を英米の「大西洋憲章」に対抗し、アジアの解放をめざした「大東亜意章」を提言したのである。】 当時は西洋の植民地として東南アジアは支配されていました。そこで、その国の解放を目的としたのです。でも、大東亜戦争として知っている人は少ないのではないでしょうか。その理由を本書から引用します。 【現在、学校の教科書は、大東亜戦争をGHQが強制した太平洋戦争という呼称に変え、アジアの解放ではなく侵略戦争と教えているが、実は、日本の戦った戦争は、太平洋戦争ではなく大東亜戦争であり、アジアの解放という理念を掲げ戦ったのである。】 もともとは大東亜戦争が日本の呼称でしたが、GHQの戦略で太平洋戦争に変わったのです。その後、戦争が終わり、アジア諸国はどのように言っているのでしょうか。 【バー・モウは「ビルマの夜明け」において、「日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢缺した国はない」「日本が無数の植民地の人々の解放に果たした役割は、いかなることをもってしても抹消できない」「東京で開かれた大東亜会議、この偉大な会議は、十二年後、アジア・アフリカ諸国のバンドン会議で再現された精神であった」と述べている。 このように日本の大東亜戦争や大東亜会議がアジアの解放に大きな役割を果たしたと、多くの人が評価している。インドのラダ・クリシュナン大統領は、「インドが今日独立しえたのは日本のおかげであり、それはベトナムであれ、カンボジアであれ、インドネシアであれ、旧植民地であったアジア諸国は、日本人の払った大きな犠牲によって独立できたのである」と総括している。 日本は、アジアの解放を達成したのである。大東亜戦争緒戦の日本軍の快進撃は、長いあいだ植民地国として諦めていたアジア諸国を目覚めさせた。 日本軍勝利のニュースはシャルル・ド・ゴールをして、「欧州によるアジア支配の終焉」といわしめた。「欧州によるアジア支配の終焉」を日本軍が実現したのである。】 日本は提唱しただけでなく、敗戦はしたもののアジア解放の目的を達成したことが、アジア諸国の言葉からわかります。戦後も、重光葵(まもる)はGHQ占領下でマッカーサーやダレスなどと交渉して、日本が出来るだけ有利になるように交渉を進めていきます。 願くは 御国の末の 栄行き 吾名さげすむ 人の多きを ミズーリ号での調印の日、重光葵(まもる)が詠んだ歌です。その時、「将来、重光の名を多くの人が蔑(さげす)むほどに、日本国が栄えることを願う」という意味らしいです。誰が重光翁を蔑むことがあるのでしょうか。重光翁をはじめとする戦時中の方々の御蔭で敗戦国ながらも経済発展をし、我々の生活があるのだと感じずにはいられません。日本がアジア諸国の解放をしたことなどを学べる一冊です。 重光葵 連合軍に最も恐れられた男 作者:福冨健一 発売日:2011年8月5日 講談社
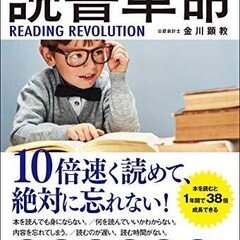
書評_今度こそ_真の読書家になろうではないか___本の読み方_で人生が思い通りになる_読書革命
ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、孫正義・・・世界に名だたる名経営者・投資家であり成功者たちには「ものすごい読書家」という共通点がある。 「じゃあ、自分も本を読みまくれば…」と思うかもしれないが、もちろん、そんな単純なものでもない。 本を読んでも身にならない、何を読んでいいのかわからない、読んだのに内容を忘れてしまう、読むのが遅い、読む時間がない・・・など、本が好きで読書家になりたいのに、このような悩みをもっている方、著者の「単なる速読術」とは違う「10倍速く読めて絶対に忘れない超効率的な読書術」の世界を、のぞいてみてはどうだろうか。 本の読み方には人それぞれ、持論や癖があり、どのような提案にも賛否両論があるとは思うが、「本の内容すべてを読む必要はない。」という著者の教えに、私は「最終的、合意」した。 最初は、素直な受け入れ態勢で読んでいたつもりの私にも、「自己流の読み方理論」が根付いていたようで、「いや、それは…」「でも私は…」という反論が幾度となく起こった。 しかし、『自分に必要な部分だけ読んで、それをしっかりものにする方が「覚えてない」より、ずっと良い』という著者の意見に、ズバッと射貫かれた。 全くもってその通り、異議なし! また、2:8の法則も面白かった。 「全社員のうち2割が全体の8割の売り上げを上げている」などのように、「全体の2割の貢献が、全体の8割を占めている」という法則である。 だから、「本も自分にとって大切な2割が理解できていたら、その本の8割を理解できているといえる」のだと・・・なるほど、説得力ありだ。 本書の著者は、公認会計士で「YouTube図書館」のオーナーとして、動画にて本のアウトプットをしているので、ご存じの方も多いかもしれない。 私は今回、この本を読んだことで、買ったままの山積みの本、読んだけど頭に入ってなくて「また読むかも」と取ってある本など『放置本、一掃大作戦~我が「知識と行動」に変えるなり~』の開始に至った。 非常に有り難い。期待通りだ。 本書全体の「自分の気になった2割」からの一部を述べたが、この本は「思考の軸を鍛える読書」「本の選び方」「効果的なアウトプット方法」「読書を習慣化する方法」など、読書尽くしの一冊だ。 加えて、「予測読み(さらに分け読み、つなげ読み、調べ読み)」「断捨離読み」「記者読み」「要約読み」など、具体的かつマニアック?な手法も書かれてあるので「何なのだ、それは?」と興味をひくものがあったなら…本書を手に取ってみることで、あなたの読書生活にも革命を起こせるかもしれない。 「本の読み方」で人生が思い通りになる 読書革命 作者:金川顕教 総合法令出版
- 固定された記事
マガジン
記事
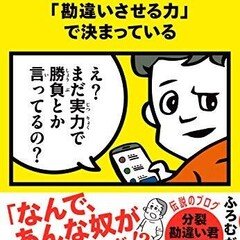
書評_容姿_資格_学歴_肩書き_実績_錯覚資産は重要__人生は_運よりも実力よりも_勘違いさせる力_で決まっている
YouTubeを見るとき、動画はどうやって選ぶだろうか? サムネイルとタイトルをまず見て選ぶだろう。内容よりも再生数の初速はタイトルとサムネイルできまる。人生も勘違いさせることが重要だ。 本書はタイトルの通り『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』という内容だ。読み始める前は「勘違いさせる力を身に付けても実力がなかったらダメだろう」と、思っていたが読み進めていくうちに理解した。錯覚資産を持つことは確かに重要だ。 錯覚資産とは容姿・資格・学歴・肩書き・実績などのことだ。見た目が良い、難関資格を持っている、学歴が高いなど、相手に仕事ができそうと錯覚させることができる資産のことだ。 錯覚資産があるとなぜ良いのか? 例えば上司が部下の誰に重要なプロジェクトを任せるかを考えるとする。その時あまり情報がない場合この錯覚資産をもとに仕事を任せる人を決める。つまり、錯覚資産を多く持っていると重要な仕事が回ってくるというわけだ。ここからが重要なのだが、重要な仕事が回ってきた結果、周りより実力がつき結果として実力がつくことになる。 本書ではこのように、錯覚資産を多く持つことで、結果的に自身の実力が大きくなることを説いている。その他にも人生をうまく生き抜く方法が書いている。スキルが高いのに認められないと思っている人は読んでみると良いだろう。 人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている 作者:ふろむだ ダイヤモンド社
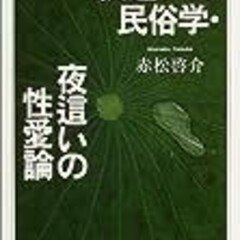
書評_ちょっと昔の本当の話夜這いで始まる恋がある__夜這いの民俗学_夜這いの性愛論
民俗学の父といえば、柳田國男ですが、性とやくざと天皇は扱いませんでした。この本ではその穴の一つ、既に滅んでしまった日本の性、夜這いを著者赤松啓介が行商を通して日本各地を歩き、それぞれの村で夜這い仲間として迎え入れられた自らの体験を通して語ってくれています。 「え、昔の人はお見合いで結婚したんでしょ?」 「日本の女の人は、昔は処女で結婚したんでしょ?」 これ、作られた怪しげな伝統です。お見合い結婚なんて、長い長い日本の歴史の中では実に近代的なシステムです。昭和以後の都会では一部そうだったのかもしれないけど、農村や漁村では夜這いが普通、夫婦の形も非常に緩いものでした。浮気なんて当たり前、嫁が隣の家の息子に抱かれて嫉妬するなんてことはみっともない。集落中みんな穴兄弟、さお姉妹。これが常識でした。 昔の農業は機械化されていない為、とにかく人手が必要でした。では田んぼを大きく持っている地主はどうやって村の若者を集めたのか。農作業が終わった後は地主が酒と飯をふるまい、給仕を自らの妻や娘や女中、後家さんにさせて、自分はとっとと寝てしまいました。酒と飯をふるまわれた若者たちは、今度はその家の女とねんごろになる。あそこの家の娘はかわいいぞ、とかあそこの女中さんと仲良くなりたい、なんて家は多くの若者が集まり、農作業も早く終わったのです。 村の娘は初潮を迎えると、離れの部屋で寝ました。村の若者が夜通って来られるようにする為です。また、村の男の子は、村の年寄の寄り合いで「そろそろあいつら筆おろしだな」なんて話になると、夜、神社や寺に行かされて、そこでは年寄連中が自らの家から出した嫁や女中連中に相手をさせました。5対5ぐらいで向かい合いくじ引きなんかで相手を決めると、あとは手練れのおねえさんに導かれて、初体験を迎えるのが当たり前だったようです。 その際に照れ隠しの為、お互いに掛け合った歌、柿木問答が始まります。 「あんたのとこに柿の木あるの?」 「はい、あります」 「私が上がって、ちぎってよろしいか?」 「はいどうぞ、ちぎって下さい」そっと抱き寄せる 「そんならちぎらしてもらいます」スルッと胸に手を忍ばせる こんな秘め事が、夜ごと村々では行われていました。 子供が出来てしまったらどうするの?この場合の解決策も実に大らか。娘に子供が生まれた場合は両親の子供。妻が浮気してできた子供は夫婦の子供。古典落語の小話にもあります。「わしが抱いてるこの子、お前そっくりやなぁ」 夜這い、今後これを塗り替える新しいフィールドワーク研究は出てくる事はないでしょう。夜這いはもう滅んでしまった、大らかな日本の古き良き性愛文化なんだから。あなたは昔の日本のフリーセックスで大らかな世界と、堅苦しい自由恋愛、結婚したら倫理という束縛をきつく受ける今の日本、どっちが好きですか? 是非この本を読んで考えてみて下さい。 夜這いの民俗学・夜這いの性愛論 作者: 赤松啓介 出版社/メーカー: 筑摩書房 発売日: 2004/06/10
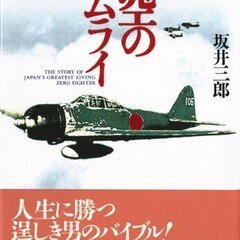
書評_歴史の舞台裏から学ぶ大東亜戦争シリーズ2_実在のエースパイロット__大空のサムライ_上__死闘の果てに悔いなし
「つくづく、人間の運命ほどわからぬものはない」、飛行機乗りで大東亜戦争(第二次世界大戦)を戦い、生き抜いた著者の坂井三郎氏の言葉が印象的でした。アジア解放をかかげた大東亜戦争中、他国と渡り会う戦力となったのが世界最強の戦闘機「零戦」であり、そのエースパイロットの一人が坂井三郎氏です。彼は200回以上の空中戦を戦い、64機の敵機を撃墜して、世界的なエースとなりました。この本では、坂井氏が日本の栄光を信じて、散っていった多くの戦友たちとともに、青春時代に大空で戦い闘った迫真の記録として描かれています。「生きる」「命をかける」とはどのようなことか、見ていきたいと思います。 本書を開くと目次の後に、日本やオーストラリアなどを含めた太平洋諸島の地図があり、その戦闘領域の広さがわかります。この地図を元に本書を読み進めると、索敵しながらの移動距離と時間などからパイロットの凄さが伺えます。次に、昭和13年10月5日の初陣から昭和20年8月17日の東京湾迎撃まで、坂井三郎氏の出撃記録があり、その数に圧倒されます。しかも、載っている記録以外にも出撃があるのです。 当時、飛行機乗りは平時でさえ、命の危険性がありましたが、増して戦争とのなると、その危険性は数十倍とみられていました。本書の冒頭で坂井氏がガダルカナル島で敵の八機編隊に突っ込み、大きな負傷を負い、意識朦朧としていく姿が書かれています。そして、生還。しかし、戦争の中で多くの日本の平和のために多くの戦友を失っていくことが書かれております。それを乗り越える精神、この頃はまだ明治維新の気迫があったように思えます。 二十歳前後の若者が命を捧げて守ってくれた日本。今の環境は彼らの賜物だと感ぜざるを得ません。今の自分が生きている有難さを実感せざるを得ない一冊です。 (本書は上下巻からなっており、本評は下巻も若干含まれているのでご容赦下さい) 大空のサムライ 作者:坂井三郎 発売日:2001年4月19日 潮書房光人新社
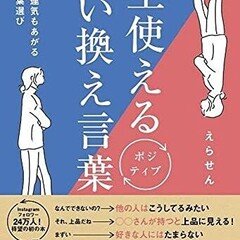
書評_この本一冊で最高のWell-beingを実現__一生使えるポジティブ言い換え言葉_-_好感度も運気もあがる魔法の言葉選び
「コップに半分しか水が入っていないのか、それともコップに半分も水が入っているか」。同じ事象でも考え方によって感じ方や次のアクションが変わるのは通説だが、本著はそういう面であらゆることをポジティブに変換することで自分も相手も幸せになるツール。 幸せの感じ方は人から与えられるものではなく自分で定義するもの。特に人は他社と比較することで甲乙をつけてしまい不幸を感じやすいという。本著は相手と比較したとしても感じ方・考え方で自分自身が幸せを感じることが出来ることを説いている。 ポジティブワードを使っていれば自分だけが幸せを感じるだけでなく、聞いている相手も幸せになるという良いことだらけ。 本著を通じて自分自身が多くのネガティブワードを使っていたことに気付かされた。という面では、他社からの信任を得たい人や求心力を高めたい人には是非お勧め。 一番ウケたのは著者の紹介で、「断捨離を始めて最終的には家も捨てました」という紹介文章。 一生使えるポジティブ言い換え言葉 - 好感度も運気もあがる魔法の言葉選び - 作者:えらせん ワニブックス
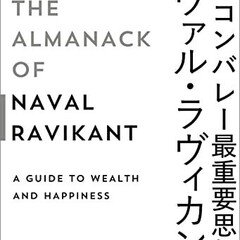
書評_現代の哲学者から学ぶ__シリコンバレー最重要思想家_ナヴァル_ラヴィカント
この本は、彼のツイート、ポッドキャスト、インタビューからの洞察を集めて編纂したもので、富、幸福、教育、起業、技術、哲学など、さまざまなトピックについての彼の見解を提供しています。 まず特徴的な点は、320ページあるにも関わらず、どのページからでも読むことができるということです。読者は自分のペースで、自分の関心に基づいて本を読むことができます。それはまた、読者が特定のトピックや思考について深く掘り下げるのを容易にします。 また、著者は読書の重要性を強く認識しています。彼は、読書が知識を深め、新しい視点を提供し、自己啓発に役立つという考えを強く支持しています。さらに彼はソーシャルメディアと適切な距離を保つことを推奨しています。 そしてナヴァルのおすすめ図書が巻末に載っているという点でも読者にとって大きな価値があります。彼の推奨する本は、彼の思考や哲学に影響を与えたものであり、それらを読むことで、彼の視点をさらに深く理解することができます。 "シリコンバレー最重要思想家 ナヴァル・ラヴィカント"は、ただの本以上のものになりえます。それはガイドブックであり、知識の宝庫であり、そして新たな読書の旅への道しるべでもあります。この本を手に取ることで、あなた自身の知識と理解が深まることを願っています。 シリコンバレー最重要思想家ナヴァル・ラヴィカント 作者:エリック・ジョーゲンソン
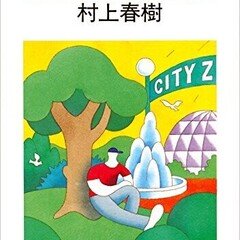
書評_8ページで感じる村上春樹の世界__スパゲティーの年に
春になると読みたくなる村上春樹の超短編小説である。出会い、別れ。遭逢、邂逅、別離、喪失という時の流れの中にある何も変わらない日常。その日常に人間の本質に迫る小説である。さぁ、村上ワールドへようこそ! この著書はスパゲティーを茹で続ける「僕」の話である。ただスパゲティーを茹で続ける変化のない生活に、突然女性から電話がかかってくるという話である。 僕は決して退屈な人生を送っているわけではない。スパゲティーを茹でるというルーティンをこなしているだけなのだ。その日課をこなしている中に起こった他人からの接触を拒否するのである。結果そこに在るのは静かな孤独だ。 女性は艶かしい口調で僕に話しかけてくるが、僕は関わることがめんどくさいと感じ拒否する。女性と関わることで変わる日常があったかもしれない。だが、僕は変わらないことを選択したのだ。僕は決して不幸でも嘆いているわけでも憂いているわけでもない。僕は僕の人生を選んだのだ。 人間は孤独であることをこれでもかと言うほど見せつけてくる小説である。たった8ページでその孤独について表現する村上春樹の真骨頂である。誰でもある「僕」。誰と居てもどこに居ても何をしても、結局は人間は孤独な生き物であると痛いほど痛感する。一人で産まれ、一人で死んでいく。ただその間の生が美しい。 カンガルー日和 (講談社文庫) 作者:村上春樹 講談社
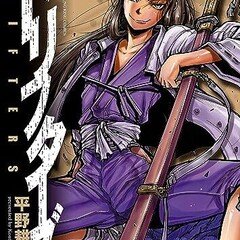
書評_5年ぶりの新刊_まずは1巻から読み返した方がよいだろう__ドリフターズ_7_
6巻が出たのが2018年、5年ぶりに新刊が出た!小学校1年生も6年生になっている!まずは1巻から読み返した方がいいだろう。そう、織田信長とハンニバルが組んで土方歳三と戦ったりしちゃう漫画の続編だ! 5年ぶりなので、まずは内容をおさらいしよう。本作は歴史上の人物が出まくる戦国時代を描いたような漫画だ。 登場人物たちは何故だか異世界に転生している。その異世界とはエルフやオーク、竜や巨人などがいる世界だ。 歴史に名を残した人がそんな時代で大活躍していく。天才は時代が変わっても状況がかわつてもやはり天才だ。ワクワクが止まらない漫画だ! ドリフターズ(7) (ヤングキングコミックス) 作者:平野耕太 少年画報社
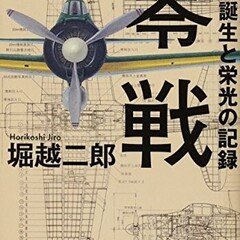
書評_歴史の舞台裏から学ぶ大東亜戦争シリーズ4_世界最強__零戦_その誕生と栄光の記録
アジア解放が目的である大東亜戦争(第二次世界大戦)に向けて、他国と対等以上に競り合える力が必要でした。このため、日本国の実力を向上させる必要がありました。そして、その実力の象徴する「零戦(ゼロせん)」と呼ばれた世界最強の戦闘機が登場しました。この本は、零戦の設計を手掛けた堀越二郎氏がアイデアから完成までの過程を記録しています。当時はCADのコンピューターソフトがなく、設計図や資料などを全て手書きで書いており、その努力や忍耐力がよくわかります。また、設計主任を任命された堀越氏は重圧をどのように乗り越え人間的に成長し、技術者としてどういった心構えがあったのか、紹介したいと思います。仕事で成長したい人、技術者には必見です。 「零戦」の正式名称は「零式艦上戦闘機」と言い、海軍の制式戦闘機が皇紀二六○○年に正式採用となりました。「零」の由来はその末尾のゼロになります。(皇紀二六○○年は昭和十五年です。今は皇紀を使う人が少ないですが、神社で御朱印を頂くときに書かれることがあります。ちなみに今年の令和五年は皇紀二六八三年です) 零戦は国の行く末をかえた国家プロジェクトとも言えたのではないでしょうか。その零戦の設計主任に堀越氏が任命されたとき、どのような思いだったのか。本書を引用すると 【私には、設計主任という責任は、非常に重荷に感じられた。だが、責任の重さに、いつまでも押しつぶされているわけにはいかない。未熟な私を、新艦戦の設計主任に命じた会社の意図はどこにあるのか。 それほど経験はないが、かえってそれゆえに、マンネリズムを打ち破れるのではないかと期待したからではないだろうか。もっと大きく考えれば、日本の航空工業が、いつまでも世界の後塵を拝していてよいものか。私は気をとりなおして、まっこうからこの仕事にぶつかっていった】 零戦の設計者というだけで、凄い人とレッテル貼りをしていましたが、「責任の重さに押しつぶされているわけにはいかない」と書かれており、最初は重圧に負けていたと推測できます。ただ、それを打ち破り、日本の航空工業を考えて気持ちを切り替え、自分自身を奮い立たせ、全力を尽くして零戦に取り組んだことが伺われます。 その後、堀越氏はこのように書いています。 【困難を避けて通らなかったことは、のちのことを考えると正しい決断だった。 それは、会社の上司のおおらかな態度や、おつきあい願った海軍の人びとの支援のたまものだったと思う。七試の設計をやってみて、私は日本でだれよりも早く、これからの単発機のあるべき姿をつかむことができた。 また部下の能力を発揮させるコツを得たというか、人間的成長といえるものがあったような気もする】 困難を受け入れる勇気、そして、堀越氏をサポートしてくれる人がいたからこそ困難を乗り越えられたのでしょう。また、その経験の中で育成能力を身に付けた話が印象的でした。最後に技術者としての心がけを紹介したいと思います。 【われわれ技術に生きる者は、根拠のない憶測や軽い気持ちの批判に一喜一憂すべきではない】 【長期的な進歩の波こそ見誤ってはならぬと、われとわが心をいましめつつ、目のまえの仕事に精魂を打ちこんだ】 【アイデアとタイミングがよくなければ戦果は上がらない。アイデアとタイミングは、その製品の性質をよく理解し、環境や競争相手の状況をおしはかり、よい判断と実行力がともなって生まれるものである。アイデアというものは、その時代の専門知識や傾向を越えた、新しい着想でなくてはならない。そして、その実施は人より早くなければならない】 【戦果をうるには、時代に即応するのでなく、時代より先に知識を磨くことと、知識に裏づけられた勇気が必要である】 【後進国が先進国と肩を並べるには、それだけの覚悟が必要なのだ】 技術を確立するためには根拠を重視し、批判に感情を傾けない姿勢や長期的な視点で目の前の仕事に邁進する姿勢は現代でもいえる事ですね。自分も見習わなければなりません。また、アイデアだけでなくタイミングも重要で、早く良い決断をして実行に移す重要がよくわかりました。特許がまさにそうですね。そして、研鑽、勇気、覚悟という言葉に惹かれました。人間である以上、この3つが人間的成長に不可欠だと感じました。 零戦を通して、人や仕事に対する向き合い方、人間的成長についても学べる一冊です。 零戦 その誕生と栄光の記録 (角川文庫) 作者:堀越 二郎 発売日:2012年12月25日 角川書店(角川グループパブリッシング)
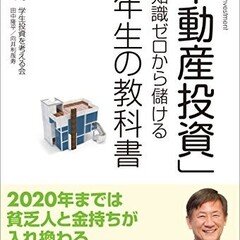
書評_成功者の考え方が学べる___不動産投資_知識ゼロから儲ける1年生の教科書
著者は、元外資系保険会社の支社長を勤めあげたFP資格を有する投資家。 転勤の多い管理職として働くかたわら、早い段階から不動産投資と株式投資に取り組むことで巨万の富を築いた。 この本は、手堅い物件選定、融資付け、管理業務など不動産投資に関する一連のプロセスが分かりやすく書かれている。 普通の不動産投資本はこれで終わるのだが、本書の特筆すべき点は、収益性を高めるために必要なコミュニケーション術や株式投資と比較した視点が付け加えられていることである。 当然ながら、よい物件情報を運んで来てくるのは不動産業者である。 よい情報を受け取っても、銀行の担当者が融資判断を素早くだしてくれなければ物件は他の人に買われてしまう。 また、物件を購入できても、地場の不動産業者と上手に付き合うことができなければ空室を埋めることは難しい。 つまり、投資を成功させるのに、コミュニケーション術は切っても切り離せないテクニックなのである。 著者は、長年、モノではなく信用を売る保険業界で働いてきた。 つまり、他人から信用される行動をとり続けてきたからこそ素晴らしい人格が形成されたのだと思う。特にこの部分は見習いたい。 本書は2016年に発行された書籍であるが、時代に左右されない投資で成功するのに役立つノウハウを学ぶことができる。 初心者、上級者にかかわらず、投資に取り組む方は、是非一読して欲しい。 「不動産投資」知識ゼロから儲ける1年生の教科書 作者:河田康則 発売日:2016年5月11日 ぱる出版
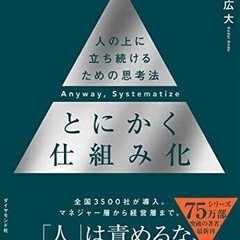
書評_仕組み化を制するものはビジネスを制する__とにかく仕組み化_人の上に立ち続けるための思考法
大ヒットシリーズ「リーダーの仮面」「数値化の鬼」に続く待望の続編。 1作目で著者のファンとなり、続く2作目、そして今作と期待を大きく上回る内容ばかり。 私自身経営者という立場だが、3作通じて共感と驚愕の連続であった。 何よりすでに自身の仕事において、本シリーズで学んだ内容を意識および実践などしている。 著者はマネジメントのプロ、株式会社識学代表の安藤広大氏。 会社名でもある「識学」とは、組織の継続的な成長を実現するためのマネジメント理論。 創業8年で約3500社に識学メソッドが導入されている。 「あなたがいないと困る」この言葉は麻薬だ。 冒頭この一文から始まるわけだが、ここで多くの人がハッとするのではないか。 組織の中で替えの利かない人ほど上に立つ、そう思っていた人は少なくないはず。 かくいう私もその一人である。 では逆になぜ歯車として機能する人こそ上に立てるのか。 そしてタイトルでもある「仕組み化」がなぜ重要なのか。 そういった内容が実例を交えて詳細に解説されている。 私は普段Kindleで読書しているが、この作品含めたシリーズ3作においては、ハイライト(マーキング)のオンパレード。 よくあるビジネス書とは異なり、私からすると参考書と呼んでも過言ではない。 経営者だけでなく、チームのマネージャー、またこれから上を目指している人など、多くのビジネスマン必読の書籍である。 とにかく仕組み化――人の上に立ち続けるための思考法 作者:安藤 広大 ダイヤモンド社
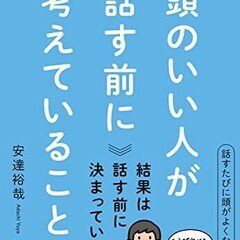
書評_自分のコミュ力が高いと勘違いしていたことを痛感__頭のいい人が話す前に考えていること
人から理解され信頼を獲得する話し方が惜しみなく説明されている。人は相手を信頼するときは、傾聴されるだけでなく、共感を得ることでもなく、適切なアドバイスを受けることでもなく、「相手が真剣に自分のことを考えてくれている」ことで信頼できる人か、頭の良い人かを判断をしている。 最近、論破王などロジカルシンキングで相手をねじ伏せるプレーが横行しているが、論破には何もメリットはなく、課題に対して一緒に考えることが一番重要であり、本質的にコミュニケーションにつながる。 特に面白かったのは、話し方系の本が沢山あるが、重要なのはどう話すかではなく何を話すかであり、小手先の話し方の技術を身に着けても人の心を響かせることは難しい。つまり、話す前にどれだけ「考え尽くすか」にかかっている。 HIUでは多く人が初めて会うという経験をしているがそこで短時間にどう仲間づくりのための信頼を獲得するかのメソッドが分かりやすく説明されているので、特にHIUの皆さんにはオススメではないかと感じた。 頭のいい人が話す前に考えていること 作者:安達 裕哉 ダイヤモンド社
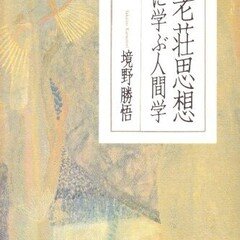
書評_戦略_智慧_役立つ日常生活編7_60歳発心で102まで長生き__老荘思想に学ぶ人間学
老荘思想(ろうそう しそう)は、古代中国の哲学における二つの主要な思想流派の一つで、老子(ろうし)と荘子(そうし)の二人の名前から名付けられました。私的な解釈ですが「肩肘張らず自然と調和して生きようや」というような感じと思います。「気にすることで体の調子を悪くする」、「呼吸を長くして、気が長くなる」など色々と生活に役立つことが書かれています。本書で一番興味深かったのが、60歳にして自分の人生を振り返り発心(ほっしん)して、それまでとは違う道をみつけた「趙州(ちょうしゅう)」です。彼は発心したおかげで102歳まで生きました。その教えについてみていきたいと思います。 自分自身の価値観を理解し、それを大切にすることは、人生において非常に重要です。しかし、時には古い価値観や思考パターンが自己成長の障害となることもあります。だからこそ、「価値観を捨てることが大事」と言えるでしょう。自己成長や幸福を追求するためには、自分自身を制限するような古い信念や無用な心配を手放し、新しい価値観や前向きな考え方を取り入れることが重要です。本書ではこのように書かれています。 【断念することによってすべてがかわり、目の前に新しい世界が開けてくることにもなるのです。】 既存の価値観は居心地の良さ、安心感を与えてくれるコンフォートゾーンから抜け出すのを妨げます。でも、思い切って価値観をすてると新しい世界感が広がるのです。それを実践したのが趙州(ちょうしゅう)です。趙州は60歳まで官吏(かんり)、いわゆる役人をやっていました。そして、ふと思ったのです 「これは俺の人生ではないのかもしれない。もう一つ、別の本当の生き方があるかもしれない」 発心(ほっしん)です。彼は80歳までいろいろなところにいって学び、そして、102歳まで長生きしました。学ぶことや行動することは若さを保つ秘訣なのですね。(※発心:思い立ってある物事を始めること) 自分自身の中にある素晴らしい可能性を信じ、古い思考パターンや自己制約を捨て去る勇気を持つことで、より自由で充実した人生を築くことができるでしょう。自分の心と向き合い、自己変革を遂げることで、より良い未来へと進むことができると思った一冊です。 老荘思想に学ぶ人間学 (致知選書) 作者:境野 勝悟 発売日:1993年5月1日 致知出版社