
【短編】マイ・ファースト・ペパーミント
「ブリザードだって」
娘のさゆりは肩を少しすぼめて、かじかんだ手に自分の息を吹きつけながら言った。
白州高原にスキーをしに来たのはいいが、あまりの寒さに耐えきれず、一旦休憩を取ることに決めた。さゆりはまだ外にいたかったようだが、大人は我慢が嫌いだ。
20年以上愛用しているグローブの防寒機能は低下しており、もはや「素手では無い」程度で、手は凍え切っていた。
分厚いはずのスキーブーツも経年劣化のせいか、じわじわと寒さに浸食され、足の感覚が少し無くなっている。
ロッジに入ると中は暖房で暖まっていたが、急に血流の良くなった手足が痒くなった。しかし、靴は脱げないのでもどかしい。
「本当にすごいね。リフト乗り場も見えなくなった。」
さゆりは吹雪で全く見えなくなった外を見て楽しんでいる。
「みて、ネックウォーマーも凍ってるよ。」
鹿児島で生まれ育った11歳のさゆりにとって凍えるほどの寒さは初めてだ。
「ちゃんと乾かさないと後から辛くなるぞ。」
「うん。」
さゆりはネックウォーマーとグローブを両手で抱えながら走っていった。
さゆりのスキーウェアはなかったので親戚に頼んでお下がりを貰ったがサイズが少し大きいみたいだ。丈が長くてポンチョを着ているように見える。久々に見たさゆりの子供らしさだった。
普段、さゆりはすごく大人びた子だ。仕事でなかなか家にいない私の代わりに家のことをしてくれている。恥ずかしい話、私は家事が苦手だ。
2年前、彼女の母親は私に愛想を尽かして出て行ってしまった。さゆりは母親の元に行くのだろうと思っていたが、予想に反してさゆりは私と暮らすと言った。きっと、父親の不甲斐なさを心配してのことだったのだろう。
それからさゆりは自分が子供であることを忘れたように振る舞うようになってしまった。私がそうさせてしまったのだ。
そんなさゆりを久々に旅行に連れてきた。私は東北の出身だが、元妻が鹿児島出身だったのでそこに家を借りた。離婚した時、引っ越すことも考えたが、さゆりにこれ以上の苦労をかけたくなかったのでそのままとどまることに決めた。
スキーは久しぶりだ。結婚してからは一度も行っていない。家にあったスキー用具も埃をかぶって眠っていた。
私は雪が大好きだ。雪国に住んでいると雪は迷惑な存在だが、私は子供の頃から大好きだった。朝の登校前に雪かきをすることも、道の側に積み上げられた雪に飛び込むことも、窓枠に積もった雪を手を滑らせて回収し、家の中で溶かして怒られたこともあった。とにかく、雪は全てを凍らせて、美しく光らせた。
さゆりも私の血を引いているようだ。旅行に行く前は少し消極的だったが、車の窓から雪が見えた途端、目を光らせてはしゃいでいた。それを見た時に普段どれだけさゆりが我慢してるのかが伝わってきた。
そんなことを考えてると、さゆりが戻ってきて私の隣にちょこんと座った。
「さゆり、何か食べようか。」
「えっ、いいの」
「もちろん、お腹空いてるだろ。」
「うん!」
私たちはカウンターの前に立ち、その上に並べられた無数の写真を見ながら二人で頭を悩ませた。
「さゆりは何を食べるか決めた?」
「うん、カレーうどんにする。あっ、でも服が白いから汁がはねたら大変だね。変えようかな。」
「そんなこと気にしなくていい。もしも汚れちゃったら服を返す前にお父さんが洗濯しておくから。」
「ホントに?」
「ほんとだよ。だから好きなものを食べな。」
「じゃあカレーうどんにする。お父さんは何を食べるの?」
「うーん、お父さん塩サバ定食にしようかな。」
それぞれ食券を買ってカウンターで手渡し、準備が出来たら知らせてくれるブザーのようなものをもらい、席に戻った。
「お父さんは子供の時からスキーやってたの?」
「そうだよ。お父さん地元じゃ一番だったんだから。」
「そうなの!すごーい!」
「さゆがいるから辞めちゃったの?」
このさゆりの一言を私は間髪入れずに否定した。
「それは違うよ、さゆり。九州には雪が降ってないからだよ。」
「でもお父さんがスキーやっていたなんて知らなかった。」
「ほら、鹿児島ってきれいな海がたくさんあるだろ。鹿児島に住み始めてから山より海の方が好きになったんだ。さゆりも海は沢山行ったことあるだろ。」
「うん。海は好き。だけど、さゆね、真っ白の山が大好き。寒いけど、寒いのも好き。」
私は黙ってさゆりの頭を撫でた。するとブザーが鳴ったので食事を取りに行き、二人とも夢中で食べた。寒さは予想以上に体力を奪う。さゆりはやはりカレーが飛び散るのを気にしてゆっくり食べていたが、結局少しだけ汁がついてしまい少しだけしょんぼりしていた。そんな様子を見て私はまた黙って頭を撫でた。
二人とも食べ終え、食器を片付けるついでに私はトイレに行った。トイレから出てくるとさゆりがアイスの自動販売機の前にいるのが見えた。
「さゆりアイス食べたいのか?」
さゆりは少しなにかに悩んでいるようだったが、ゆっくりうなずいた。
「何味が食べたいの?」
「えっと、この青色のやつ。」
さゆりが指さしたのはペパーミント味だった。さゆりがミント味が好きなんて知らなかった。
「さゆり、この味食べたことあるの?」
「ううん、ないけど、おいしそうだから。」
「じゃあ試してみようか。食べれなかったらお父さん食べるから。」
「うん!」
さゆりは嬉しそうに笑った。そして続けて
「いつもね、暑い時にアイスを食べたことはあるけど、寒い時はないの。」
といった。確かにスキー場にいるとアイスが食べたくなることがある。
「なんか、さゆりと話してるとアイス食べたくなっちゃったからお父さんもアイス食べようかな。もしもさゆりがアイスを残したらお父さんが二本とも食べちゃお。」
そう言うとさゆりはけらけらと笑った。
アイスを買っていると、さゆりが一瞬だけ外に出て良いかと聞いてきた。なぜかを聞くと「アイス食べる前に寒さチャージしてくる」とのことだった。私は笑って送り出した。さゆりにとってこれが「親孝行」ならぬ「子孝行」になっていればいいなと思った。
帰ってきたさゆりは雪だらけになっていたが、そのまま席につきアイスを食べ始めた。
「歯磨き粉みたいな味する」
予想通りの反応だった。初めてのペパーミントは歯磨き粉の味。皆が通る道だ。結局私が買っておいたイチゴ味のアイスをさゆりはペロッと食べた。
「寒い時にアイス食べるといつもよりおいしく感じるね!」
そういったさゆりの顔は11歳そのものだった。
帰り道の車の中で名残惜しそうに外を眺めているさゆりは徐々にいつもの大人なさゆりに戻ろうとしていた。
「さゆりにペパーミントは早かったな」
私がそう笑うと、さゆりは不満そうにほっぺを膨らませた。
「楽しかった?」
「うん。また来たい。」
雪は全てを凍らせ、美しく見せる。子供は子供のままに、いつまでもペパーミントを苦手であってほしい。
私は穏やかに降る雪にそう願った。
縦書き版

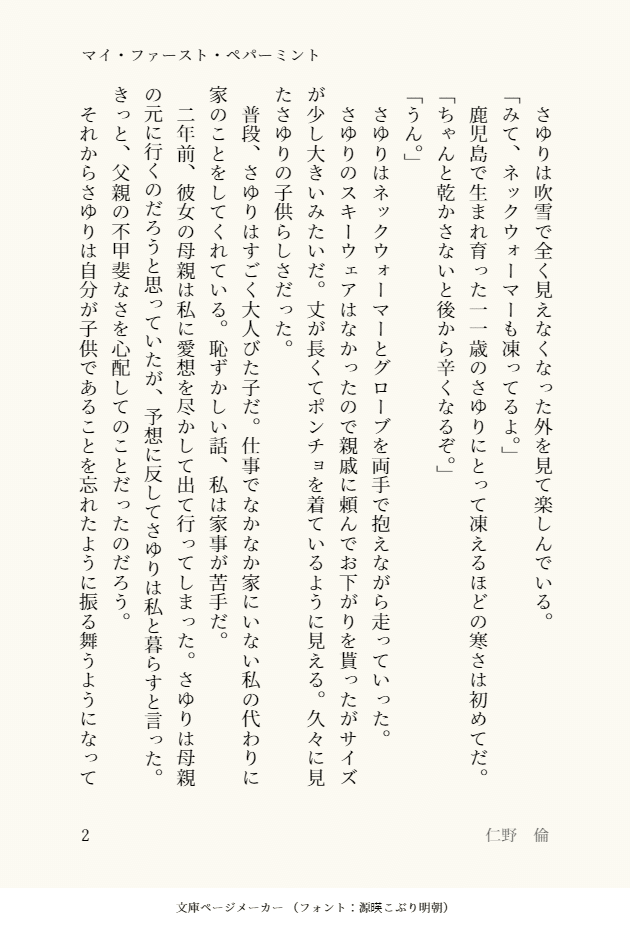






この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
