
【インペリウム】国別デッキ解説 カルタゴ
このマガジンでは、ボードゲーム「帝国の時代:インペリウム・クラシック」(以下インペリウム)に出てくるデッキを国ごとに、歴史的観点で解説していきます。
ゲーム上のシステムや攻略についての解説は一切ありません。ご了承ください。
また、インペリウムをプレイする(orした)方が読んで楽しんでもらえるような構成にしています。そのため、インペリウム内の用語を多少含むことをご容赦ください。用語がわからなくても読み進められるようにはしているつもりです。
インペリウム記事Part2です。
今回はカルタゴについて説明していきます。
カルタゴを知っている人の大半は世界史履修者ではないのでしょうか……?高校世界史でもローマに倒されたくらいしか出てこないので、詳しく知っている人はかなり少ないと思います。かく言う私も今回の記事執筆にあたって初めて詳しく調べます。頑張ります。
カルタゴざっくり解説
まずカルタゴとは何なのか?国の名前です。
この国の首都も同じくカルタゴという名前です。現在のチュニジアにあたります。
紀元前9世紀~紀元前2世紀までと、約700年間活動していた国です。長いですね。
領土も広範囲にわたります。各地を点々と支配していたので領土自体が広いわけではありませんが、かなり多様な地域に進出しています。

なぜこのように広い地域を点々を支配していたのでしょう?それは、彼らが商業で活躍していたからです。もう少し詳しく説明します。
カルタゴはフェニキア人という民族による国家です。
フェニキア人は地中海東岸、今のシリアやレバノンあたりで活躍していた民族です。
彼らが国家を形成しはじめたのは紀元前15世紀頃。日本では遮光器土偶で有名な亀ヶ岡遺跡、つまり縄文時代終盤あたりです。

フェニキア人は世界史上では重要な民族です。それはなぜかというと、海上貿易を盛んに行っていたからです。先ほどのカルタゴの領土を見ても分かるとおり、西はイベリア半島(今のスペインやポルトガル)から東はレバノンあたりまで、かなり広い範囲を貿易圏としていました。要するに、地中海沿岸の広い地域は彼らの貿易圏だったのです。

これだけ広い範囲を貿易するわけですから、当然多様な地域の商品がフェニキア人を介して出入りします。その中で誰にでもなじみのものがあります。
それがフェニキア文字です。「いや知らんわ」というツッコミが聞こえそうですがちょっと待ってください。このフェニキア文字、アルファベットの祖先なのです。正確には、アルファベットの祖先のギリシア文字の祖先です。
フェニキア人が活躍していた時期と古代ギリシア文明(都市国家アテネなど)の時期はかぶります。上記の地図でも、ギリシアに近いクレタ島がフェニキア人の航路に入っています。つまり、フェニキア人とギリシア人は交流があったということです。
フェニキア文字に母音をいくつか足して、ギリシア人はギリシア文字を作りました。このギリシア文字の最初の文字、αとβから「アルファベット」と呼ばれるようになったのです。
さてこのフェニキア人がつくったカルタゴですが、強大なライバルが立ちはだかります。それがローマです。後で詳しく説明しますが、戦争で敗北したカルタゴは、そのままローマに征服されて滅亡の一途を辿ります。ただ、彼らの都市自体はカエサルによって再建され、大都市として繁栄しました。
このように、史実ではローマに負けてしまうカルタゴですが、このインペリウムでは戦略次第でローマも圧倒する大帝国に育てることができます!ぜひプレイしてみてください!
カード解説
ここからカード1枚1枚の解説に入っていきます。ただ、全部説明すると煩雑になるので、固有名詞(人名や出来事、地名など)のカードとその国の説明に欠かせない用語の説明とさせていただきます。
順番はカード左下の番号の若い順です。
象

カルタゴデッキのカードにはやたら象のイラストが出てきます。これはちゃんと史実に基づいています。
それはローマとの戦争、ポエニ戦争における象の活躍です。
軍事用に象が使われるケースはしばしばありました。有名な例はアレクサンドロス大王。彼はペルシアやインドと戦う際に象を運用しました。これが地中海世界で戦争における象の運用の始まりだとされています。
カルタゴでは、ローマとの戦争で37頭の象を連れてアルプス越えをしたと言われています。そのときのカルタゴ側の将軍が、この後紹介するハンニバルです。
ローマからしたら、地形的に海から攻めてくると思っていたカルタゴがまさかの高嶺アルプスを越えて攻めてきたのですから、驚きです。
結果としてカルタゴはローマに敗北しますが、それでもこのアルプス越えは現在でも語り継がれています。

ハンニバル

先ほども出てきた、ローマとの戦争(ポエニ戦争)で活躍した将軍です。フルネームはハンニバル=バルカ、と言います。
「ハンニバル」は「慈悲深きバアル神(嵐と慈雨の神)」、「バルカ」は「雷光」という意味だそうです。かっこいい。
ハンニバルが軍の指揮をとったのは26歳の時でした。
その3年後には先述の象を率いたアルプス越えを行いました。アルプス越えについては、先ほど詳細を述べたので割愛します。
ちなみに、このアルプス越えは後世にも語り継がれたと書きましたが、その証拠が有名な絵画に隠されています。それが下の絵画です。

ダヴィド作「サン=ベルナール峠を越えるボナパルト」、つまりナポレオンの絵です。この絵の左下の岩には、3人の名前が書かれています。それぞれ、「BONAPARTE(ボナパルト)」「KAROLVUS MAGNVS IMP(カール大帝)」「HANNIBAL(ハンニバル)」と書かれています。これは、アルプスを越えた英雄たちの中にナポレオン自身も並んでいるという意志の表れです。ハンニバルが約2000年後の英雄にも評されていることが分かります。
ハンニバルはアルプス越え以降の戦いでも活躍を見せました。ポエニ戦争の中でも有名なカンナエの戦いでは、ローマ側の指導者を次々倒し、ローマを追い込みました。
しかし、ローマも反撃を行います。その先頭に立ったのがハンニバルの好敵手とも称されるスキピオ(大スキピオ)です。敵ながらお互いに能力を認め合っておりハンニバルは休戦交渉を持ちかけましたが、スキピオは拒否、戦いが始まりました。この戦いをザマの戦いと言います。
結果、ハンニバル軍は大敗し、スキピオにより戦争が終わりました(正確には、もう一度ローマとカルタゴは戦争をします)。スキピオはハンニバルを処することなく戦争を終わらせるという寛大な処置をとりました。しかし、これがローマ人たちの反感を買うことになってしまいます。
ハンニバルは敗れた後、母国の経済立て直しを行いました。しかし、業績を上げたために妬まれ、反ハンニバル派の動きが活発になってしまいます。結果、ハンニバルは亡命し、最終的に自害しました。
ちなみに、今でもローマではハンニバルは恐ろしいものという扱いのようです。子どもが悪さをしていると、「ハンニバルが来るぞ!」と言うそうです。日本のなまはげみたいな扱いですね。
イベリア

今のイベリア半島と同じです。スペインやポルトガルがある半島のことです。

最初の方で出したカルタゴの勢力図の通り、カルタゴはイベリア半島の地中海側地域も勢力下に置いていました。
特に栄えた街がカルタゴ=ノヴァ(現カルタヘナ)です。
カルタゴ=ノヴァはローマ帝国側からの呼び方、つまりラテン語です。和訳すると「新しいカルタゴ」という意味です。
紀元前227年頃にこの都市がフェニキア人によって建てられたと言います。
ローマ帝国に占領された後も、イベリア半島の重要な都市として発展しました。
しかし、7世紀にゲルマン人大移動でやってきた西ゴート人により滅ぼされ、衰退の一途を辿ることになります。この都市の復活はイスラーム教徒による支配を待つことになります。
ベルベル人

北アフリカの広い地域に古くから住んでいる人々です。総人口は不明ですが、現在でも北アフリカだけでなくヨーロッパやカナダのケベック州などで多くのベルベル人の方々が暮らしています。
有名どころで言うと、フランスの元サッカー選手のジダンがベルベル人です。彼の両親は、当時フランス領だったアルジェリアからパリに移住してきたベルベル人です。
意外にも、女優の沢尻エリカもベルベル人の血を引いています。お母さんがアルジェリア系フランス育ちのベルベル人です。ジダンの両親とルーツは同じですね。
世界史上でベルベル人が出てくるのは、イスラーム王朝を立てたところです。11世紀にムラービト朝を、12世紀にムワッヒド朝がそれぞれ立てられました。どちらもエジプトより西の北アフリカを中心とした国家で、支配者がベルベル人になります。
ちなみに、ベルベル人の由来はギリシア語の「バルバロイ」から来ています。意味は「よく分からない言葉をしゃべる人たち」です。つまり、ギリシア人が他の民族を指した蔑称が由来なのです。
それが理由なのか、ベルベル人本人たちは自分たちのことをアマーズィーグと呼ぶそうです。イマジゲンと呼ばれることもあります。
カルタゴの女王、ディードー

カルタゴを建国したと言われている伝説上の女王です。
現在のレバノン、つまりフェニキア人の元々の中心地だった地の出身です。彼女はその地で兄と共同で国を治めるように父から命じられましたが、兄は権力と財産の独占を狙ってディードーの命を狙いました。
そこでディードーは亡命し、現在のチュニジアに辿り着きました。このチュニジアこそがカルタゴの中心となるのです。
チュニジアに辿り着いた彼女は、その地の王に土地の分与を願いました。すると、王は牝牛一頭の皮が覆えるだけの土地なら譲ろうと言いました。そこでディードーは、牝牛の皮を細かく切り刻み、土地を取り囲みました。これが後のカルタゴになりました……という伝説らしいです。Wikipediaで調べました。
彼女は歌劇や美術などのモチーフにもなっています。有名どころだと、ダンテの『神曲』やシェイクスピアの様々な作品に出てきます。
また、かつてカルタゴが栄えたチュニジアでは、紙幣の顔になっています。
バレアレス諸島
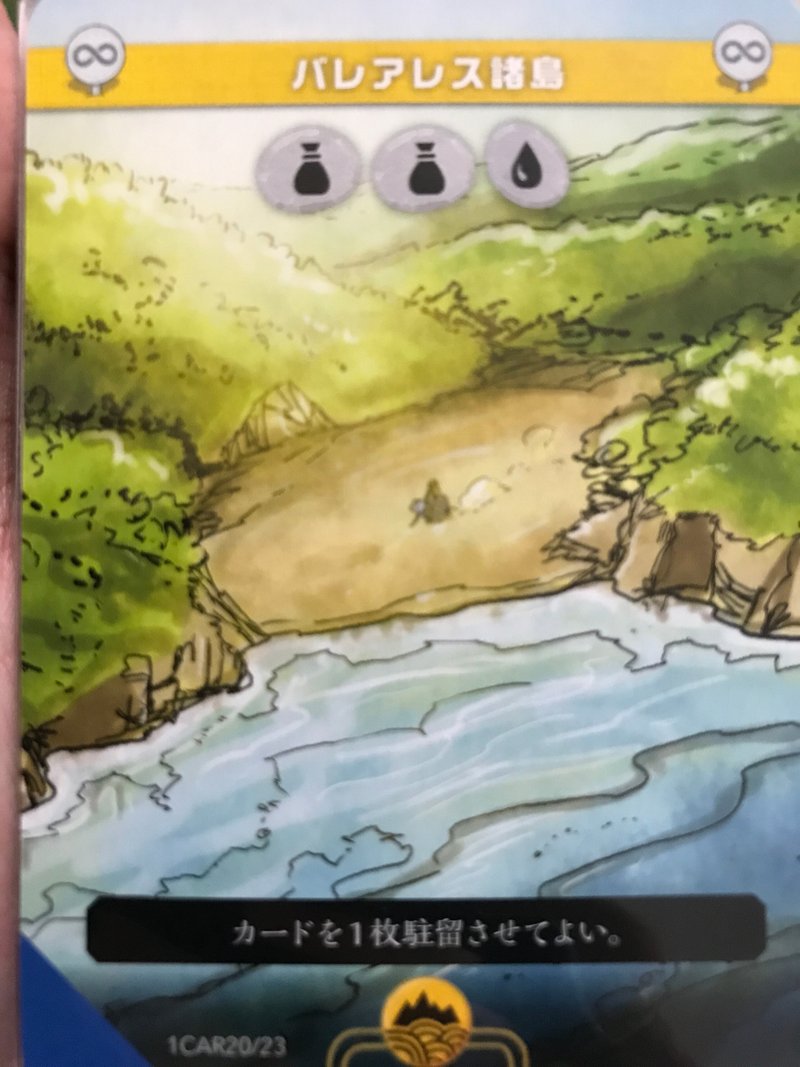
現在のスペインの一部です。
場所は以下の通りです。

その中でも一番の大きい島であるマヨルカ島は、現在人気の観光地となっています。
初めてバレアレス諸島にフェニキア人がやってきたのは、紀元前8世紀頃です。この後、ローマ帝国の支配を受けるまでカルタゴによる貿易で賑わっていました。特にイビサ島のエイビッサは、地中海各地でつくられた製品を輸入する貿易センターのような役割を担っていました。
その後もローマ帝国やゲルマン人、アラブ人、スペイン人などが支配しました。ローマ帝国に支配された時に、ワイン製造技術が持ち込まれたそうです。今でもマヨルカワインが売られています。
カルタゴが地中海貿易の要所としたように、近代でもイギリスやフランスがこの地を狙いました。幾度かの戦争でイギリスやフランスの領土になりましたが、ナポレオンの時代にスペイン領に復帰しました。
モーリタニア
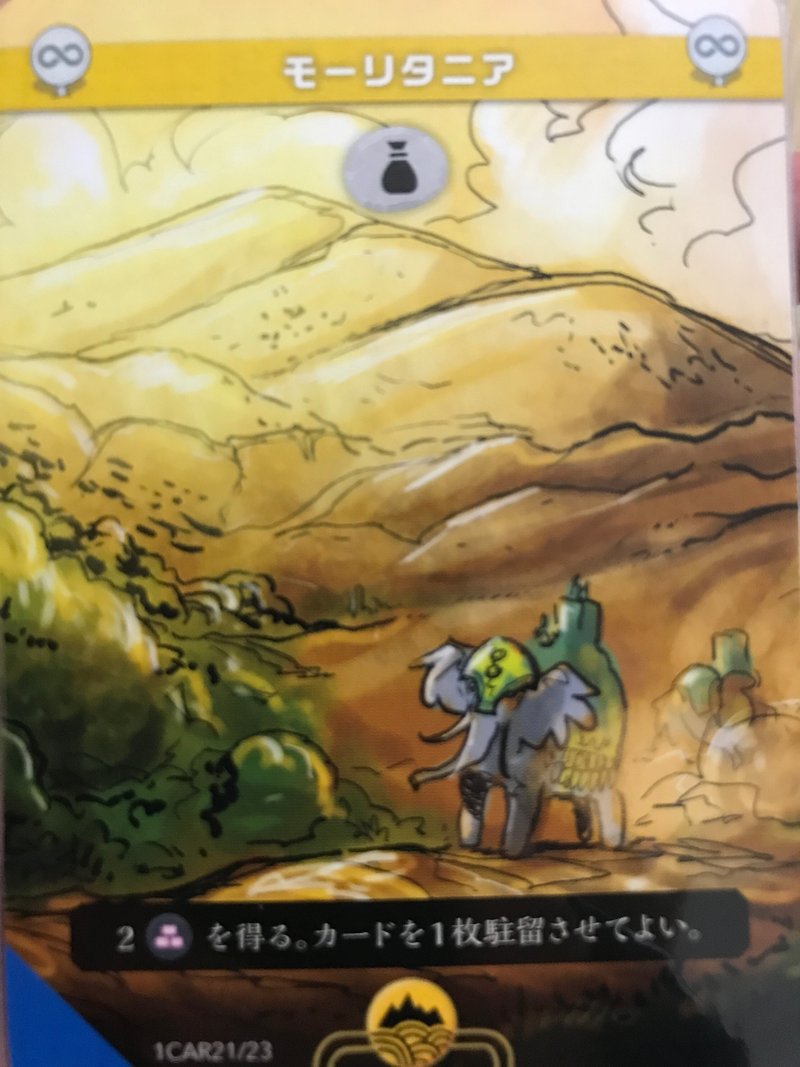
現在モーリタニアという国家がありますが、そことは関係ないようです。
実際、現在のモーリタニアの領土とカルタゴの領土でかぶる地域はありません。
現在のアルジェリアやモロッコあたりが該当します。
調べても詳しく分かりませんでした……。
元々はベルベル人の国家が存在していました。カルタゴはこの国全体を支配したのではなく、海に面したところを自分の支配地域にしたのでは無いかと思います。これくらいしか分かりませんでした……。
おわりに
カルタゴはローマの陰に隠れてしまいがちな国ですが、古代の地中海貿易を担った重要な国家です。民族的にも多種多様で、現在の多くの国の歴史を形作っています。
私も知らないことばかりで、今回調べる中でかなり勉強になりました。
インペリウムに感謝です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
