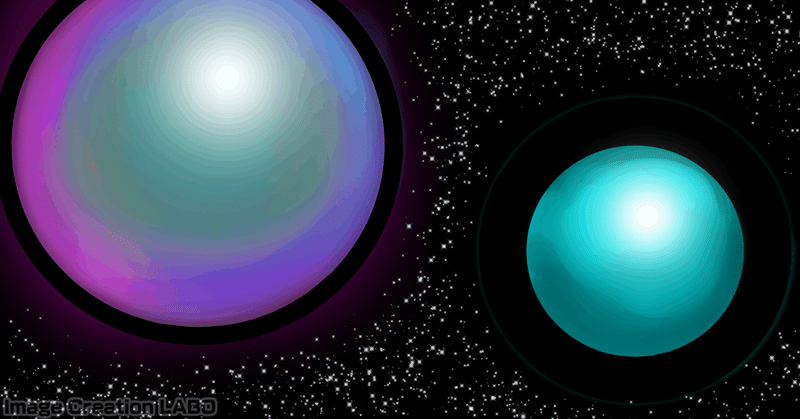
NASAの予算は妥当なのか
1960年代というと60年以上も前のことになる。わたしは愛知県豊田市にある実家でよくテレビを見ていた。その頃の番組は10年後に大阪万博をひかえ、夢を語るような番組がいくつもあった。わたしはテレビの中でも特に「宇宙家族ロビンソン」という白黒ドラマが好きだった。
この邦題はオリジナルではLost in Spaceという。ロビンソン一家がロケットで宇宙をさまよう様子を描いた物語。いまでこそ古いけどフライデーというロボットが人間と対話をする。一家に連れ添ったドクター・スミスがいろいろと悪いことをしでかす。このドクターの悪だくみとこすい性格が騒動を起こしロビンソン家族に迷惑をかける。そこがなんともくやしいというか。なにをやっているんだという思いを持ちながら見ていた。まさに宇宙旅行ドラマにはまっていた。
あるオンラインイベントでNASA(アメリカ航空宇宙局)について話題にしてみた。これまでNASAはアポロ計画やジェームズ・ウェブ・テレスコープといったあっと驚くような偉業を達成してきた。しかし反面予算は年々膨れ上がっている。2022年度の予算は実に$19bn(190億ドル)という。これを現在の為替レート133円で円換算すると約2.5兆円に達する。年間にこれだけの予算を計上している。
途方もない数字でこれを日あたりに換算してみる。1年365日で割ってみると一日当たり約68億円を予算として持っていた。普通に考えれば国家予算は次年度に持ち越すことはない。一日68億円を科学者の研究費用に使ったということになろう。その研究には火星や月に移住するような計画や地球外生命体がいるかどうかといったことまで証明する。
はたしてこんなことにこれだけの予算をかける必要があるのだろうか。これをイベントに参加した人たちに質問してみた。
ある人はこういってきた。この2.5兆円というものはだれが払っているのか。その原資はなんなのかというもの。もっともな質問であろう。おそらくNASAの予算の内訳は税金、国の発行する債券(借金)、そしていくばくかの寄付金であろう。寄付は割合としては少なくほとんどが税金と借金でまかなわれている。民間企業ではないので何かを売って儲けるということはしない。
意見は賛否に分かれた。賛成派はこういう。宇宙は地球から離れた場所でありその研究分野は広大である。地球物理学は従来の物理学だけでなく物質、通信、気象、進化といったあらゆる科学を含めたもの。それらの研究の発展には欠かせないものだ。一概に妥当な金額とはいえないが費やすだけの価値はある。地球物理学をはじめ科学全体の発展には欠かせないもの。その裾野の広さから研究は人類の発展のためになるという意見があった。これはもっともな意見であろう。
地球では実験できないことを宇宙では試すことができる。いくつも仮説を立ててその中から実証できるアプローチ(研究手法)を編み出すことができるという。たとえば無重力状態で人はどのような活動ができるのか。これも正しい。地球上でできることが宇宙に飛び出したとたんにできなくなる。しかしそういった制約があるためにいろいろな技術の発展を生み出すこともある。月の上にある物質の測量といったこともこの離れた地球上からテレスコープを使って実験できる。なにかしらの仮説を立てて手法を確立することで秤を使わず測量をすることができる。
衛星を使った通信により5Gができた。それによりドローンをいくつも飛ばして操作ができる。東京オリンピックの開会式で使われたドローンの様子はこの技術を使ったものだ。あんなことができるとはだれも予想しなかっただろう。
しかし反対意見もあった。やはり一日に68億円をかける必要はないだろう。もっと他の事、特に地球上で起きているより深刻な問題を解決することにお金を使った方がいいのではないか。温暖化、環境破壊、貧困、食料、健康。これも正しい。宇宙に異星人がいるかどうかということを探求するよりは地球上でいままさに起きているこれらのことに予算を向けた方がいいのではないか。
気象衛星からの写真の精度を高めて気候変動の実態調査をする。地球温暖化のメカニズムを宇宙から測量することで気象の変化をより早く地球上に伝えるということはできないか。人工衛星による通信により5Gが実現したことにより通信速度は格段に上がった。地上の鉄塔を伝わるよりも衛星を介した方が反対側にいるひとたちと早くそしてより映像のきれいなものを伝えることができる。日本とアメリカは地球の反対側にお互いが位置している。
衛星によって時差をあたかもないようにできることも可能であろう。成層圏から宇宙に向かうのでなく地球に向かってなにかしらの研究をした方がいいのではないか。少なくとも異星人を探すよりはお金をかける価値があるであろう。
1960年代に放送をされたテレビ番組のことをよく思い出す。宇宙家族ロビンソンというのはあの当時からすればありえないこと。あの人と会話するロボットは特に印象に残っている。ロボットは機械であるため故障はすれども疲労することはない。電気があるかぎり。そしてあのかたちをしたロボットはいくつも改良されいまでは人工知能のかたちに近いものもあらわれている。それがスターウォーズに登場したR2-D2といったドロイドでもある。
そして1970年に万博会場で月の石を見たことを覚えている。あのときのテーマは「人類の平和と調和」だった。でもはたして人類は平和になったか。調和を保てているかというのは怪しい。むしろ科学の発展どころか逆噴射してしまいかえって人類を不幸にしているのではないかと疑う。人類は戦争の恐怖へと向かっている。
そんな中で科学の発展のためにNASAが一日68億を使っていることを話題にしてみた。予算を立てて使うことは決して無駄ではないだろう。ただその妥当性が問われている。宇宙より緊急の課題が地球上にあるのではないか。
はたしてこれを読んだ大学生の読者の方々はどう考えるであろうか。
