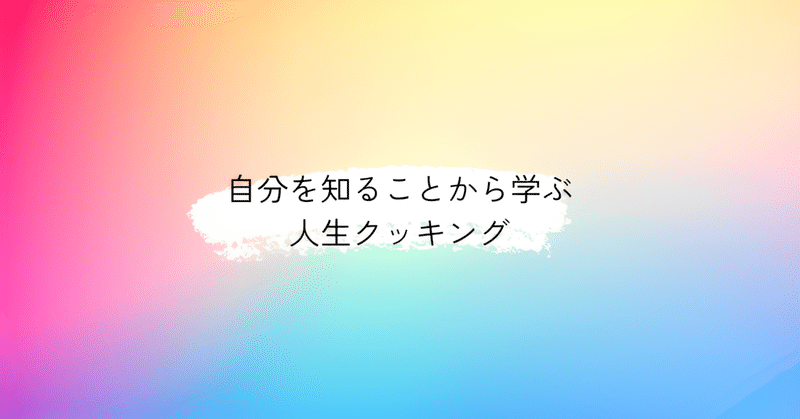
【人生クッキング #009】接続される学習時代
こんにちは、ひろげとんです。
今日のトピックは「学習と教育」についてです。
ぜひ見ていただけると大変励みになります。
では、長くなりましたがさっそく本題に入らせていただきます。
(前回の記事は文末に載せています。)
1. コネクテッドラーニング

皆さんは学生時代にどのような教育を受けた、もしくは受けているでしょうか?
紙媒体を基本とした教科書ベースの教育、スピーチやディベートなどのアクティブラーニング、メディテイションラーニングなど様々な教育を受けてきたと思います。
近年は総務省が中心となりCYBERやSecHack365などのセキュリティに特化したe-Larningなどを実施しており、小学校教育からプログラミングをさせるなどのIT人材の強化が話題となっています。実はこの学習、ある名前があります。
そう、「コネクテッドラーニング」と言うのです。
コネクテッドラーニングの説明の前に上記した総務省の教育について以下に解説します。
【CYBYR】
NICT(情報通信研究機構)のNCTC(ナショナルサイバートレーニングセンター)において、2017年度から行政機関等の実際のネットワーク環境を模倣した大規模仮想LANの環境を構築の上、国政機関等、地方公共団体及び重要インフラ事業者等の情報システム担当者などを対象とした体験型の実践的サイバー防衛演習を実施。
※全都道府県で年間100回、計3000名規模、2020年度までに延べ11413名が受講。
2021年度から地理的・時間的要因などによりCYBERが受講できない者への対応としてオンラインコースA、2020年東京大会に向けた実践的サイバー演習「サイバーコロッセオ」の実施結果を踏まえたコースCをそれぞれ提供開始。
【SecHack365】
上記と同様に2017年度から、25歳以下の若手のICT人材を対象に新たなセキュリティ対処技術を生み出しうる最先端のセキュリティ人材(セキュリティイノベーター)を育成するイベントを実施
※これまでに合計171面が修了。
次にコネクテッドラーニングの解説に移ります。
【コネクテッドラーニング】
もともと2005年にDigital Media and learning Initiativeという「デジタルメディアがどのようにして若年層の世代のコミュニケーションや学習、遊興に影響するか」をリサーチするマッカーサー基金による約50億円の研究から始動した。
「興味関心の萌芽」「関係性の中での相互学習」「実際に学習したことに対して社会で実践を試す機会」を指しており、この3つが重なり合うベン図の真ん中を彼らはコネクテッドラーニングと定義している。つまり「学習機会は学校に制約されるものではなく、様々な生活の場所、例えば学校や家、コミュニティに学びの機会があり、それを繋げて学習していく」と言う考え方もと、上記した3つの要素の重なる部分をできるだけ大きくし、学習の場を拡張していくことを目指している。
初期メンバーは南カリフォルニア大学のヘンリー・ジェンキンズ教授、ノースウエスタン大学学習科学のニコール・ピンカード准教授、カリフォルニア大学アーバイン校情報学部のミズコ・イトウ教授らである。
2. 学習環境の変化による学校の崩壊

僕はこの教育を受けたことはありませんが、現在の小学生から全員にタブレットが1台配られたりと、IT教育の推進が活発に行われています。
これがいわゆる次世代教育の一環であり、デジタルメディアというテクノロジーを駆使した教育システムです。
では、これが主流になると何が起こるのか。
それは「学校という環境の崩壊」です。
例を挙げてみましょう。僕も利用していますが、「edX(エデックス)」などがいい例です。この解説に入る前に、そもそも最近の潮流である「MOOCs(ムークス)」について解説した方が分借りやすいのでその順番で解説します。
【MOOCs】
Massive Open Online Coursesの略称で、インターネットを通じて無料で世界各国の有名大学の授業を受けることができる新たな学習環境のこと。近年インターネットの普及とともに新たな大規模プラットフォームとして注目されているサービスのこと。効果・メリットは…
① 費用面の負担が減ること
② 教育の地域格差の解決が見込まれること
③ 「誰でも学べる」生涯学習に貢献すること
の3点が挙げられる。
次に、「edX」を解説します。
【edX】
2012年秋に、MIT(マサチューセッツ工科大学)」とハーバード大学が共同で約6000万ドルを出資して設立されたMOOCsのこと。
世界のトップと呼ばれる大学がオンライン学習講座を提供している教育プラットフォームのこと。
これは非営利組織として設立され、プラットフォームのソースコードがオープンソースとして公開している。2019年9月現在、約120の大学・企業と提携し約2800を超えるコースが提供されており、2000万人以上の学習者がいる。また、これは個人向け講座のほか、企業向けのeラーニングコース「edX For Business」の提供を行っている。例として、ビジネス分野を中心にAmazonやマイクロソフトといった企業の専門家の講座などがある。
以上のように現在学費のようなものを掛けずにほぼ無料で、さらに場所の選択の必要性も消去されたことにより「学校」という存在自体の必要性が無くなりつつあります。デジタルメディアの発達によりフリースクールなども話題となっています。
ここからが重要なのですが、では果たして先ほど述べた「学校の崩壊」、これは正確性の高い事象なのかという点です。
僕は違うと考えていまして、学校は残ると考えています。というのも学校と言う施設はコミュニティの場として、そしてリアルに対面が基本システムであるという役割に比重を占めているからです。
確かに勉強・学習をしに行くだけならもうデジタルに自信を接続して場所を選ばずに学習できる環境は整備されているのでそちらを選ぶ方が効率もよく時間のリソースも割かなくて済みます。お金もほどんと掛かりません。でもリアルで対面でコミュニケーションを取ることで学習できることもあるのではないか、と僕は考えています。そのために学校は必須なのです。
最近話題になっているNFTと呼ばれる界隈もまさにプログラミングやITを勉強するにはもってこいの内容です。それは全てデジタルに接続されたコミュニティ内で学習できます。でもどうでしょう。人間同士の関りが減って、断絶された世界で学習できることなどたかが知れていると思いませんか?
人間はコミュニケーションを取って育ってきた動物です。それもかなり高い知能を駆使してです。デジタルの発達によってコネクテッドラーニングやMOOCsなど新たな学習方法が提唱されている中、再度見つめ直す必要があるのではと僕は敢えて警鐘を鳴らしたいです。デジタルに脳を接続することに違和感はないですが、洗脳されて高知能である人間の脳を自ら退廃させる行為だけは避けていかなければ、本当の意味での学習はできないのではと感じています。
3. まとめ
皆さん、どうでしたでしょうか?
「学習や教育にはデジタルとリアルの両軸を考え続けなければならない」、とても大切な考え方ですね!
何か意見などあればコメントいただけると大変嬉しいです!
では次回のNoteもお楽しみいただければと思います!
今後とも応援よろしくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
