
Nurse With Wound list再考② 憑在論(Anarchy)の視点より
Nurse With Wound リスト(以下・NWWリスト)の膨大なラインナップは今日でも振り返るに値する内容であるが、新奇な音楽、つけくわえればDJ的な「使える音楽」という視点からの再評価は2010年代のアナログ再発ブームによってそれなりに進められたと思える。リスト作成者たるスティーヴン・ステイプルトンとジョン・フォサーギルが「1970年ごろから79年前半にかけて」集めていた音楽から選出されたそれらの多くは互いに通底する要素があり、リストの作り手たる二人は直接的にそれを理解していなくとも、直感的に感じ取っていた。今日ステイプルトンは、この音楽たちが新奇で異形、フリーでプログレッシヴなのは、音楽のための音楽ではなく、革命のための音楽だったからだと結論づけている。ダダ、シュルレアリスム、フルクサス、ウィーン・アクショニズムの優れた芸術はみな、政治的な発露であり、一見一聴して「それが」表面化していないことがかえって独特の美的価値を生んでいる。
『MUSIC + GHOST』で音楽ジャーナリズムにおける憑在論について調べた際にはNWWも取り上げたのだが、NWWリストに載ったバンドの政治性についてはさほど言及しなかった。しかし、68年5月でピークを迎えた反骨の精神が遠きにあるという感覚をもってすれば、憑在論というレンズでNWWリストを眺めてみることに意義があると思える。
雑に訳せば憑在論(Hauntology)とは、過去に失敗した試み(ソ連崩壊に伴って叫ばれたコミュニズム)、かつて抱かれていた未来(第二次世界大戦後の英国政府がとった福祉国家的ヴィジョン)への志向が、表面化することはなくとも潜在的に生き続けては離れないという価値観である。音楽ジャーナリズムにおいてはマーク・フィッシャーら「英国育ち」の書き手が、自分たちが過去に経験してきた「英国産」ポピュラー文化の回帰を特定のアーティストから見出したことをきっかけに、一つのコンテキストにまで成長した。そこにはBBCが制作していたリベラル色の強い教育番組に象徴される文化的背景としての公共があった60年代末と、パンク的クラブ・カルチャーともいえるジャングル(洗練されすぎた「ドラムンベース」ではない)が隆盛した90年代末へのノスタルジーがある。
NWWと憑在論が結びつけられる機会は少ない。いまだに一面的なオカルト・神秘主義のイメージがあるせいかもしれないが、こと「ノスタルジー」という重要な概念が絡んでくる憑在論において、NWWの世界観とそれを形成した音楽たちは、いずれも再考に値する。そこには80年代以降のアメリカナイズされたヨーロッパから消え去ったもろもろの記憶がカクテル状に澱んでおり、(主張として表面化こそしていなかったが)ポピュラーカルチャーから政治的運動まで浸透していた変革と融和のアイデアの残滓が、しかし絶えることなく残り続けている。スティーブン・プリンスによるフィールドワークにして、英国ポピュラー文化における憑在論の例を一つ一つ取り上げた研究書『A Year In The Country』でも紹介されている復刻レーベル「Finders Keepers」が、NWWリスト掲載バンドのコンピレーションを企画したことは、NWWに憑在論の色があることを証明している。
失われた未来とは60年代後半の英国だけに留まらず、西ヨーロッパ諸国が夢想していたものでもあった。NWWリストは、かの時代の索引とみなすこともできるだろう。
リストが持つ音楽的傾向の一つは、英語圏以外のフリージャズやプログレッシヴ・ロックが多いことである。それらの多くはFuturaやOhrなど、60年代後半という変革の時期を迎えていた西ヨーロッパ各都市内から生まれた自主レコードであった。そこには創造的な源泉としてのアナーキーがあり、デモの現場たる街頭に祝祭を見出すセルジュ・カタローノ(Komintern)から、連帯を拒んで独善を貫くロルフ・ウルリッヒ・カイザー(Ohrレーベル)までの幅をもつ。パンクに触発されて自分たちのレコードを作ったNWWが、これらアナーキーな運動体としての音楽をリスト化したことは、パンクが表向きに否定していた76年以前と現代を繋ぐ橋を架けるというポストパンクの偉業に数えられてしかるべきである。
CAN
西川長夫『パリ五月革命 私論』で綴られる学生たちによるオデオン座占拠のくだりでは、著者が現地で目にしたデモ隊の標語が列挙されている。これらはルネ・バックマン『5月のバリケード―スチューデント・パワーの105日』(早川書房 1969)に記されていて、西川は本書から引用することで当時の様子を描写する。「革命は委員会のためにあるのではない、あなたのためにある」、「何から何まで、ダダ」、そして「ビタミンCが不足」である。72年のシングル「Vitamin C」でダモ鈴木が歌うラインが68年5月由来だと断定することはできないが、CANも60年代の音楽的変革が生んだ集合の一つであることは変わりない。Kominternのようなバンドとの差異は、創造的な意味で革命を果たすことで、現実のそれを果たすというものである。集団生活の現場であったケルンの館を解放区と見立て、そこから外の世界と繋がるという孤高な実験は、ホルガー・シューカイらが師事していたシュトックハウゼンの精神性が垣間見える。
The Plastic People of the Universe
「I Am The Warlus」への好意を公言するホルガー・シューカイは特例だが、NWWリスト・バンド(そしてNWW自身)の多くにとってのサイケデリックとは、The BeatlesではなくSoft MachineやPink Floydであり、ロックンロールとはフランク・ザッパやThe Velvet Undergroundのことを指した。チェコスロバキア共産党政権下のプラハに、ソ連を盟主とするワルシャワ条約機構が軍事介入した1968年8月にミラン・フラヴサたちが結成したThe Plastic People of the Universe(PPU)も、その例に漏れない。
PPUの反権威な態度と影響力はすさまじく、1970年の時点で政府から公式に演奏禁止の令をくだされ、禁を破ったメンバー数名が投獄されるほどであった。また、バンドの歌詞の多くは同じく政府からマークされていた詩人にして哲学者エゴン・ボンディによるものであった。ボンディの詩は当時のチェコのアンダーグラウンドにおいて重要なテキストであり、当時のチェコ・シュルレアリスム運動と国家社会主義批判を接続していたと思われる。PPUの音楽は彼のテキストを拡散するという大きな役割も果たしていた。代表作となるファースト・アルバム『Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned』は『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』をもじったもので、サイケデリックへの回答として、真っ黒な陰に潜む60年代チェコ・シュルレアリスムが浮上した歴史的瞬間といえる。
Henry Cow
68年5月に結成されたHenry Cowは、音楽性から政治性はもちろんのこと、Do It Youselfの精神面でもNWWに影響を与えている。Virginから契約を切られたバンドは、Universe ZeroやEtron Fou Leloublanらに声をかけ、78年3月に反商業的音楽運動「Rock In Opposition」を展開する。それに伴い、思想と音楽の両立としての前衛を貫くため、Recommended Recordsが設立された。FuturaやOhrのようなレーベルがロンドンに出来ただけでなく、当時Guru Guruから脱退したばかりであったウリ・トレプテの世話をする過程でレーベルの人物(クリス・カトラーやジェフ・リー)らと対面できたこともステイプルトンにとっては大きな刺激となった。
Rock In Opposition第一回のフライヤーはステイプルトンの名前が世に出た最初の仕事とされており、おまけに牛を有したバンド名(もう一つのきっかけが南ロンドンのMilk From Cheltenham)が、レーベル名「United Dairies」のアイデアを閃かせたというのだから、NWWがユーロ・プログレッシヴ・ロック左派の継承者といっても過言ではないだろう。
Komintern
Red Noise(ボリス・ヴィアンの息子、パトリックも在籍したフリー・ロック・グループ)に参加していたセルジュ・カタラーノとフランシス・レモニエールらが結成したグループ。後のAtollであるリシャール・オベールや、ジルバート・アルマンも参加するハブ的存在となる。『Ugly Things』誌によると、ヴィアンとセルジュ・フランシス組が分かれたのは、表現による革命に言語を持ち出すか否かを巡った議論の末であるという。なお、純粋に音楽だけを求めたパトリックは、76年にEGGからソロアルバムを発表する。
Red Noiseが瓦解したのち、East Of Edenのサポートを頼まれていたセルジュとフランシスは、遅れたヒッピー・ムーヴメントの盛りを迎えていたイビサ島帰りのオリヴィエ・スドザリックらとセッションしたことをきっかけにKominternを結成する。同郷のバンド・Mahjun(NWWリストに名前あり)に触発されたセルジュは、トロツキズムにヒッピー経由のエコロジー理論と、ロック・ミュージックに付随するサイケデリックを投げ込んだ。こうしてKominternはThe Incredible String Bandのように郊外へ居座ることを選ばず(ここに英国~スコットランドとフランスのカウンターカルチャーの特色が出ている)、都市を拠点にカウンターを図る運動体となった。この精神性はMahjunやFille Qui Mousseらとともに掲げたスローガン「F.L.I.P. (Force for Liberation and Intervention in Pop)」に集約されている。
1971年のアルバム『Le Bal Du Rat Mort』は全体的にマーチ調で華やかである。彼らにとってポップとは、劇場や封鎖された大学を繋ぐ街頭の道に活気を与える音楽であった。リリースの大元はなんと英国のHarverstで、反資本主義的メッセージを掲げた音楽が資本側から放たれる(『Ugly Things』が書くには、実際に企業から検閲を受け、アルバムの発売が少し遅れたという)スリリングな関係があった。
ジャケットはメキシコの画家にして共産主義支持者であったディエゴ・リベラの壁画『Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central』から切り取られたものになっている。パレードの中心を闊歩する貴族たちに紛れて、先住民であるカトリーナが己の身を隠すために貴族に扮して歩いている様が有名だが、Kominternがこれを利用したのは、街頭を歩く庶民たちと、対向する貴族たちとの立場をひっくり返したアイロニカルな意図があるように思える。
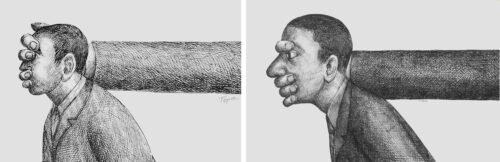
60年代フランスから生まれたフリー(音楽上の制約と人間の精神的な意味、両方で)志向の音楽は、ジャーマン・ロックと並んでNWWの不定形な芸術性を形作っている。ドイツとフランスの両方をまたぐのがウォルフガング・ダウナーやFuturaのリリース各位といった一部のユーロ・ジャズと呼ばれた音楽かもしれない(余談だが、ダウナーが制作した西欧ジャズ・ミュージシャンリストは、NWWリストのモデルである)。
これらのレコードは当時の前衛演劇とかかわりが深く、Théâtre du Chêne Noirや、日本では太陽劇団と訳されるLe Théâtre du Soleilは、アナーキーという視点からNWWリストを覗いた時に視界へと入ってくるだろう。アリアーヌ・ムヌーシュキンが立ち上げた太陽劇団の集団体制・共同作業の様式は、80年代末にアイルランド西部へ移住したステイプルトンとその家族・隣人たちの農耕生活と接続できる。個人を貫徹することが世界に対する反抗となる、その磁場として創作があって、生活がある。
太陽劇団が68年に上演した『夏の夜の夢』や『魔法使いの木、ジェロームと亀』といった劇では、スタンリー・ラスリィと、その父親であるジャック・ラスリィが音楽を担当していた。ジャックはパートナーのイヴォンヌとともにフランソワ・バシェの音響彫刻(Structures For Sound)を発展させた人物であり、もう一人の息子テディは後にMagma(当然というべきか、NWWリストに名前あり)のメンバーになる。
ジャック・ラスリィの主な音楽仕事は、テレビ番組、それも公共局が放映していた教育系プログラム用のものだった。その一つに、60年代後半から英国グラナダTVで制作さていた『Picture Box』のテーマソングがある。この名前、ひいては番組全体に満ちている静かだが奇妙な空気は、憑在論の領域に早くから座していたGhost Box Recordsの原風景になっている。
ラスリィが奇妙な電子音によって描写していた光景の一つには「宇宙」がある。それは60年代の精神を語る上で避けられない「未来」という概念の可能性そのものであった。次の更新は、この視点からNWWリストを眺めてみる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
