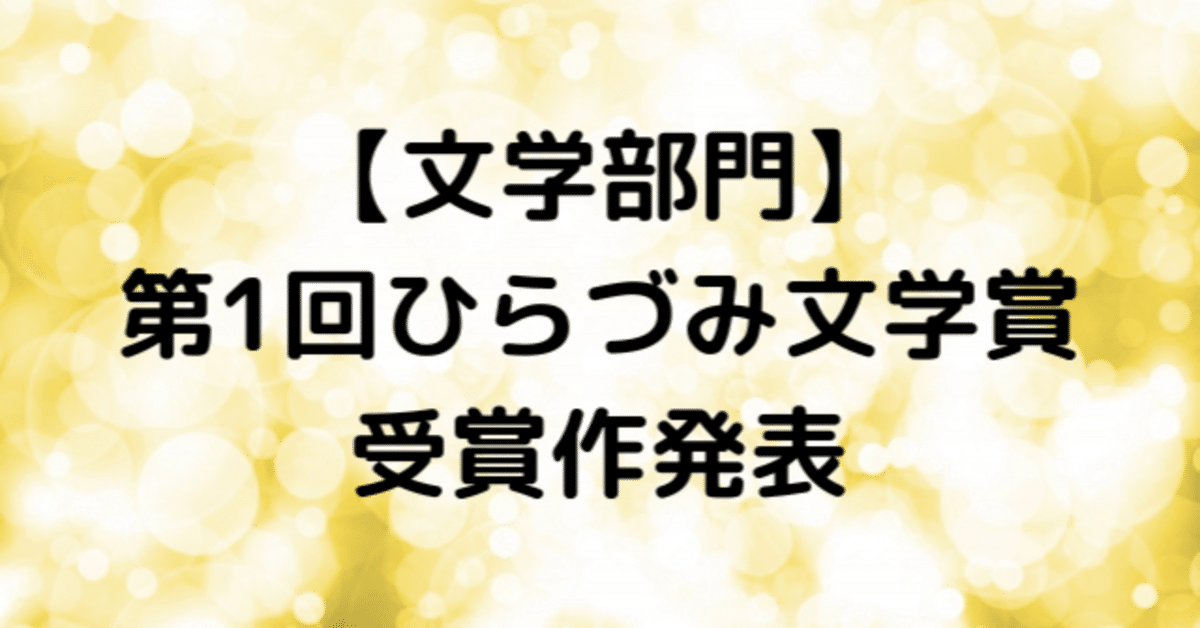
【受賞作発表】第1回ひらづみ文学賞/文学部門
※当初、「大賞」1本、「優秀賞」3本を選出させていただく予定でしたが、審査の結果「佳作」を設けさせていただく運びとなりました
【大賞】該当作なし
【優秀賞】二十七歳の告白(五十嵐文章)
私はその日、二十七年間の決して短くも長くもない人生で初めて、「青田買い」と言う言葉を知りました。
青田買い。後で辞書を引くと、私が認識していた意味とはまったく異なる意味だと解説されていたので、きっと彼が示した用法の方が、やはり正しいのでしょう。私のほうが間違っていた。今となっては、容易に負けを認めることができます。いや、認めざるを得ない。対して、私が用いた用語はそれと似て非なるもの、その時私は確かに、「青田刈り」と言っていました。スマートフォンに内蔵された電子辞書には、まるで誇らしげにでかでかと「誤用」と書かれています。インターネットで調べれば、なんでも「青田刈り」とは戦時中の軍事戦略のひとつで、敵が食糧不足に陥るように敵地のまだ青い田畑の稲を刈り取ってしまう、という、なんとも陰湿な攻撃のことだそうですね。そんなことも知らずに私、とても恥ずかしい。
高校時代には模擬試験で文系科目都内三位だったんです、私。しかしそんな些末なことを未だに誇りとしている時点でたかが知れているのでしょうね。有名私大文系卒業の自称インテリ女のくせに、偉そうに難しい言葉を垂れ流して。女だてらを絵に描いたようなグレーの細身のセットアップのジャケットの袖を、手持ち無沙汰に捲ることしかできません。
目の前で上目遣いにこちらを見つめる少年は、私にひとこと、日本語間違ってますよ、と言い放ったきり、意志の強そうな瞳を大きく見開いて扉の前から微動だにしませんでした。私は、それを良いことに、改めて彼のかんばせをまじまじと眺め回しました。
ラムネのように白くなめらかな頬は、それでいて指先で軽く押しただけで内側から果汁が滲み出しそうな程に瑞々しく、細かな筆で書き込んだかのように密度の濃い睫毛に縁取られた大きな目からは、葡萄の実のような黒目が零れ落ちそうです。そのまなじりは勘が強そうにきゅっと釣り上がり、対して真っ白な広いおでこの下に乗っかっている眉毛は困ったような八の字を描いています。何か言いたげに薄く開かれたピンク色の唇は、上下緩やかに曲線を描き、口角がきゅっと上がっているものの、決して快活そうな印象を与える役割を持ってはいません。少なくとも、私にとってはまるで雄猫を誘う発情期の雌猫の口元を見ているような、おおよそ雌猫に誘惑されるような優雅な生活などしていないのに、そんな荒唐無稽な比喩を用いたくなってしまう程には、彼の濡れた唇から色気のようなものを感じ、内心動揺していました。
なにも唇に限ったものではなく、肌の白さを際立たせるかのような健全そのものの黒髪や、オーバーサイズの真っ赤なパーカーの襟から覗く、白樺の小枝のような首筋、そして細身の体格に反して肉付きのいい、ダメージジーンズに包まれた太ももなどからも、どうしようもなく感情を揺さぶられてしまいました。無意味にストライプシャツの袖のカフスを直したり、ポケットに両手を突っ込んでみたり、私は狼狽を表に出さぬよう、必死に平静を取り繕うことしかできません。
成人式を迎えて早七年、もうすぐで八年になります。立派な大人として、そんな感情をまだ十代の半ばほどに見える少年に向けてはいけない。私は必死に大人としてのロールを演じようと彼に対峙していましたが、その心のうちにあったのは〝脅威〟のひとことでした。
このとき、私は目上の大人に可愛がられるのに必死でした。そろそろ武器となる若さも底をついてきた頃。若さなんて九ミリの弾丸よりも消耗の激しい、今どきリサイクルすら利かない非効率な武器です。しかしそんな一丁拳銃にいつまでも縋り付き、部署の話の判る元バンドマンの上司に甘えられるだけ甘えようと、甘え下手の私は必死の毎日を過ごしていました。まだ甘えさせてほしい。可愛がられる方でいたい。そんな日々の中で突然、取材対象であるはずの目の前の少年に対して自分自身が抱いてしまったいささか邪な感情は、私にとっては脅威でしかなかったのです。
彼は潤んだ唇を更に少しだけ舐めて、控えめな声量で言葉を重ねました。上唇と下唇の間を、唾液の糸が一瞬繋がりました。 「青田刈りだと、まだ実も成らない稲になっちゃう。僕にだって青い実ぐらいは成ります」 その小洒落たセンテンスから、やっぱり言語センスは良い子なんだわ、と、改めてその才覚を確信しました。この子の作った曲を、もっと聴きたい。聴かせてほしい。やっと音楽誌編集者らしい欲求が胸の奥で沸々と湧いてきて、彼に知られないよう私は密かに胸を撫でおろしました。
そんな情けない大人の思惑など知ったこっちゃいない、と言った素振りで堂々と相対する彼でしたが、次の瞬間には緊張した面持ちを急に弛緩させ、ちょっと俯いて悲しそうな笑顔を浮かべました。下がった眉毛が更に緩い曲線を描き、庇護欲をそそるか弱さが立ち込めます。 「こういうこと、いちいち突っ込んじゃうからいけないんですよね、僕。円滑な対話のためにはそんなこと気にしないほうが良いに決まってます」
歳の割にはやたら年寄りくさい言い回しを使う子だと思いました。やっぱり私の第一印象は間違っていなかった。彼は根っからのインテリなのでしょう。「円滑な対話」なんてオブジェクト、当時の私からは果たして飛び出したでしょうか。敗北のような気持ちを噛み締めながら彼の様子を注視していると、お腹が痛いのか、少し身体を屈めて両手をパーカーの大きなポケットの中に突っ込みました。気がつけば長い前髪の合間から覗く額には薄っすらと汗が滲んでいます。柔らかそうな下唇がげっ歯目のそれのような前歯に押し潰され、熟れすぎた果実のような色にうっ血していました。お腹をさすりながら、彼は気が抜けたように更に破顔します。前歯から開放された唇は紫色に変色し、白い肌が幾分か青みを帯びています。思わず顔を覗き込む私を見つめ返し、少年は心配は要らない、と言わんばかりに小さく首を振りました。 強がった様子で大丈夫です、とだけ小さく囁いた彼に、私はソファを勧めました。雑居ビルの小さな一室に十セットのデスクを詰め込んだしがない編プロの応接コーナーのソファがどのようなシロモノなのかはご想像にお任せしますが、擦り切れた革のカバーは決して座り心地快適とは言えません。しかし立っているよりは幾分かましだろうと考えての苦肉の配慮だったのですが、彼は一貫して首を縦に振りませんでした。まるで、自分のアイデンティティを無断で値踏みした上に頭金も支払わずに質草を突き返した非情な大人を、人の好さそうな笑顔の裏で蔑み、拒否するような頑なな態度でした。 「いいです、大丈夫。日常会話も満足にできないようなこどもにかかわり合いにならないほうがいいですよ。僕みたいな悪い子は、」 頑なな表情で頑なに言いかけた彼でしたが、突然両手で口元を覆い、床に膝を突いてしまいました。今回ばかりは下心も何処かへ吹き飛ばされた私はその針金細工のような肩を掴んで立たせ、吐き気を急激に堪えた為か朦朧と焦点の定まらない目をしている彼を担いでエレベータで階下まで降ろし、おもてに着けていた車に乗せて自宅まで運んだのです。
彼は私が勤める編集プロダクションのある、都内の小さな街のライブハウスを中心にアイドル活動をしていました。その街は都内でも随一の「芸術の街」と言われる場所で、小さな劇場や老舗のライブハウスなどが沢山ある街でした。映画などにもよく出演している有名なバイプレイヤーの役者さんが自宅兼アトリエを設けていたり、小さな雑貨屋や古着屋なども多く点在し、中学時代からロックバンドと学生演劇に傾倒していたいわゆるサブカル系の私にとっては天国のような街でした。音楽ライターを目指し、学生時代からウェブメディアへの寄稿や有名な音楽誌への投稿を繰り返していた私は、当然のように当時から愛読していた音楽雑誌社の新卒採用に応募し、そして当然のように悉く不採用の通知を受け取りました。残ったのは書店でも棚の端にあるか無いかぐらいのレベルのタウン誌の出版社や、今どき女子高生も跨いで通りそうなピンクのヘッダーが眩しい、最近エビデンスの不誠実さから記事大量削除・閉鎖を余儀なくされた女子力キュレーションメディアのパクリサイトを運営する小さな編プロぐらいのものでした。しょせんは私大文系卒程度の私には選ぶ余地も無く、現在はその女子力パクリサイトで音楽関連の記事を作成・編集しています。幸いにも我が社は社員十五人の少数精鋭な為、誠実さだけがウリです。何処かのキュレーションメディアのように「肩こりの原因はあなたの肩に乗っかっている地縛霊かも?!」なんて眉唾どころか反吐が出るようなエビデンスを振りかざすリスキーなことはしませんが、しょせんは女子力キュレーションメディアです。音楽関連の記事と言っても私が好むようなキャッチーでありながら先鋭的、程良く俗っぽさを持ちつつもポリシーがあり、しかし女の子好きしそうなカリスマ性のあるミュージシャンのディスクレビューなどを書かせてくれるようなことはあまり無く、メンバー全員の顔が同じ原型師が作った美少年フィギュアのように見えるK-POPアイドルや、あざとい歌声で平坦なラブソングを歌うお可愛らしいギター女子なんかの音源ばかりを聴かされるある意味地獄のような日々を過ごしているのが現状でした。しかし、そんな世間一般のニーズにしか(・付ける)照準を合わせていない我が社にも時々物好きが現れることがあります。地域で活動しているミュージシャンが、とにかく自分達の名前を広めてほしいと音源やライブのチケットを持参して訪ねてくるのです。ロックに耳が慣れている、と言う理由だけでそのようなミュージシャンの取材を一手に任されている私は、編集長が普段音楽なんてヒットチャートの上位曲しか聴かないようなタイプの女性であるのを良いことに、直属の元バンドマン上司にだけ相談をしながらほぼ自分の好みだけを判断材料に、毎日送られてくる音源やユーチューブなどにアップされている映像の中からめぼしい取材対象を探し出すのですが、いくら好きなジャンルの音楽とは言えそこはプロとは言い難いインディーズミュージシャンです、当たりばかりとは言えません。せめて熱意には応えようと直々に顔を出してくれた子達だけは必ず記事を書くようにしていますが、稀にどう足掻いても褒めようがないある意味神がかった音楽家と出会ってしまう場合もある程なので、正直やりがいのある仕事とは一概には言えないのが実情でした。
しかし、彼が持参した音源は、そんなアマチュアミュージシャンの中でも群を抜いて異彩を放っており、私の鋼鉄でできた――ザラのポピュラーミュージックでは大正琴程度の音色も鳴らないと自負している――頑なな琴線をこれでもかと揺さぶっていったのです。
怒涛のように押し寄せるコーラスときつくディストーションのかかったギター、敢えてボリュームが絞られたワンフレーズ目のシャウト。三拍子の静謐なドラムンベースとの対比が悪夢のように鮮やかなメロディラインを奏でるシンセサイザーは、オルゴールを早回し逆再生したような音をしていて、私は軽く吐き気を覚えました。勿論、褒めているのです。キャッチーでクリア、踊れて歌詞には子守唄程度の意味すら持たせないアイドルソングや、カップル動画のBGM程度しか意味をなさないシンガーソングライターの曲ばかりがもてはやされる、数字が全ての昨今の業界で、こんな変態じみた音楽を作っている勇者がまだ存在していた。気持ち悪いばかりじゃない、あくまでも歌メロは流れるように美しく、覚えやすいのが更にニクいところです。そして何より、彼自身の歌声が素晴らしかった。大学生や専門生なんかならばわからなくはない。敢えて王道から逸れ、それでいて多くの人の耳をこっちへ向けられるような人材なんて、経験則上一生懸命探せばいくらでも見つかります。ボーカルの歌唱力だって中学生ぐらいからバンド活動なんかをしていればいくらでも鍛えられるでしょう。よく通るハイトーンを敢えてぐっと抑え、低めのキーから始まる変則的なメロ部分を経て、カタルシスを起こすようなサビに差しかかる時の爆発力。喉の奥から嗚咽を堪えて嘆きを絞り出すような歌い出しに、吐息をたっぷりと含んで潤んだようなブレス。何よりロングトーンを伸ばす時の、ヴィブラートとはまた違う、細かな震えのようなものに全身が粟立ちました。まるで老婆のように掠れ、か弱く震えた歌声。しかしハイキーのウィスパーは外国の少女のように可愛らしく、一体この歌手は何百年生きてきたのかと、私は迷宮の中で迷子になるような思いでした。まさか、今デスクのPCで音源を聴いている私の目の前で心配そうに膝を揃え、パーカーの裾を両手で掴んで直立不動でこちらを覗き込んでいる、声変わりもしたばかりの少年のものだとは、きっと誰も思わないでしょう。 壁際に配置された指定席でPCに音源の入ったUSBを挿し、ヘッドホンをした私は、隣で苦しそうに肩を竦めている彼を見上げました。停止ボタンをクリックし、幾つなの、とヘッドホンを外しながら聞くと、彼は十三歳です、と応えました。十三歳、じゃあまだ中学生じゃない、ちゃんと学校には行ってるの、と私は返します。まるで世話好きの親戚のおばさんのような言葉に、彼は非常に母性本能をくすぐる笑顔を浮かべ、ヘヘ、と力なく笑いました。 「どっかの配信者さんみたいに両親に無理強いされてるとかじゃないですから、安心してください。寧ろ僕は自分がアイドルできることに感謝してるんです」 音楽しか僕には無いから、と彼は弱々しく言いました。音楽でしか、僕は世間と繋がれないから。
「だから、年齢とか関係ない、純粋な気持ちで聴いてほしいんです。僕がまだ中学生だとか、そんなことは関係ありません。公平に判断してください」
彼は真っ直ぐな瞳で私を見つめ返していました。今にも零れ落ちそうな程に大きく見開かれた目は、時折控えめにぱちくりと瞬きをし、その度に長い睫毛が切れそうな電球に照らされた薄暗い部屋には濃すぎる程の影を頬に落とします。私は矢も盾もたまらず彼の顔から目を逸らしました。殺風景で秩序的なキーボードに目線を這わせます。私はじんわりとした恐怖を感じていました。下腹部が俄に熱くなってきます。下唇を噛んで、思案するふりをしながら心を落ち着けようと試みました。あんな歌声で、あんな曲を、哲学的で且つ寓話的な……賛美歌のように達観した音と言葉に溢れたあんな曲を、あんなに綺麗な、夢のような少年が、目を見開き涙を浮かべ、柔らかそうな唇を唾液で塗らし、胸を掻きむしり、時にあどけなさすら残るかんばせに恍惚の色を滲ませながら歌ったのかと思うと、気が狂いそうでした。公平な耳で判断するなんて、私にはまだ無理だ。私はなんとか大人らしさを保とうと、敢えて高慢な態度を取ることにしました。
こういう才能のある若い子は、総じて己の能力や美意識や容貌に強い自信と執着心を持っていると相場が決まっています。天狗の鼻が伸び切ってピノキオになってしまっては遅いのです。私みたいな意地の悪い大人に早々に出会って、一度折られておかないと。サウンドは良いわ、歌も上手なのね。本当に歌が好きなんだってことは伝わってきたわ。先ずは相手を油断させる為に、好ましい所を素直に褒めました。強張った表情を浮かべていた白い顔が一気に緩み、仄かに頬の赤みが増します。私はこのまま胸のうちの感動を全て彼に吐露し、その嬉しそうな笑顔を見たい、あわよくばこのままこの胸に掻き抱いて連れ去ってしまいたいぐらいの衝動に駆られましたが、好きなものにはとことん甘くなってしまう――以前大好きなミュージシャンのひとりがカストリ週刊誌にすっぱ抜かれてプライベートでひどい目に遭った時にも、CDが売れなくなってしまうのではないかと無意味な心配を重ねてレコード屋で同じアルバムを三枚も購入するなどと言う奇行を繰り広げた程の甘さ――持ち前の幼稚性を、このときばかりは大人の意地が上回りました。花が咲いたように口元を綻ばせる彼の息の根を止めるように、厳しい言葉を投げつけます。でも歌詞がちょっと難しいんじゃないかしら。あなたぐらいの年齢のアイドルだったらファン層は十代の学生さんとかじゃない? 私は大人だから良かったけれど、あんまり難しい哲学的な言葉を使うと大多数のニーズには応えられないんじゃないかしら。あなたもプロを目指しているなら、どれだけ相手に的確に伝えたい言葉を伝えるかを最優先に考えたほうが好ましいことぐらいはわかるわよね? 私にはまるで頭の良さをひけらかしているように見えるわ。清少納言じゃないんだから、まず漢字を減らしたほうが良いと思うの。信念があるのは良いことだけれど、相手に合わせて折れることだとか媚びることもこの世界じゃ大切なの。泣いたって解決しないのよ、信じたくないだろうけれどそれが真実ってやつ。あなたは男の子だから知らないかもしれないけれど、あなたぐらい若くて綺麗なアイドルなら、もしも女の子だったら枕ぐらい普通にしてるのよ。あなた、男の子だからって調子に乗ってるんじゃないかしら? あなたみたいな小生意気な子、ちゃんとした大人は青田刈りもしないわよ。
普段PCモニタの前で大量の明朝体と睨み合っている私には殆ど無用の長物だった声帯が、久々の出番に浮かれかえってちょっと長く喋り過ぎてしまいました。途中までは大人びすぎた感性と爛熟した言語中枢を使いこなしている幼い脅威への素直なリアクションでしたが、後半に進むにつれ、私の内部では全く違う類の脳内麻薬のようなものが飛沫を上げ、溢れかえり始めていました。私が厳しい言葉を重ねる度に、少年は俯いた首の角度を大きくし、淡く染まる唇をきつく噛み締めます。緩い丘を形成する下まぶたには、涙が果汁のようにじわりと滲み、理詰めで罵倒する程に竹の根のように繊細な下睫毛を滑り、その先の辺りで留まってふるふると震えます。まるで熟れる前のまだ酸っぱい果実の、その芸術的な程に鮮やかな色と小さいながらに滴り落ちる程の甘味を隠し持った身体を、指先で捻り潰すようなサディスティックな快感を深く覚えてしまった私の口は、なかなか静かになってくれませんでした。赤い色の薄い布に包まれた、海洋生物の標本のような骨格をした肩が微かに震える度、私の支配欲はどうしようもないぐらいに満たされました。赤ずきんに出てくる狼はもしかしたら、おばあさんになりすまして赤ずきんを食べる瞬間、こんな気分だったのかななどと世迷い言を考えていると、少年は必死にきゅっと引き結ばれていた唇の、仄かに上がった口角の端からありがとうございました、と涙声の謝辞を絞り出して扉のほうへと去ってゆこうとしたのです。私は急に口惜しくなり、浅ましくもその羽根でも生えていそうな肩甲骨を追いかけました。あくまで冷静に、まあわざわざ会社に顔まで出してくれたんだからそこまで送るわよ、と言うような顔をして彼を追いかけると、所々凹んだブリキの扉を前に、彼は突然くるりと振り向いて私を真っ直ぐ見上げました。おそらく百五十センチを超えたばかりの小柄な背を一生懸命に引き伸ばし、顎を上げて立った姿はまるで鶴か何かのようで、私は少々怯んでしまいました。凛とした趣すら漂うその表情には、さっきまでのか弱さはありません。睫毛で風を起こすようにゆっくりとまばたくと、彼は言ったのです。
「僕のファン層は七割が二十代のお姉さんです。僕は最大限そのニーズに応えるようなソングライティングを試みているつもりです。あと、」
その日本語、使い方間違ってますよ。
車の助手席に乗せた彼の息遣いが気になって、私は運転に集中できませんでした。未だかつてない程にアクセルを踏む足が震えるドライブは二十分程続き、信号の度に横目で同乗者の様子を確認し続けました。束ねた白糸のようにしどけなく投げ出された手首と首筋が、真っ赤なパーカーとその上に被せてやったデニム地の丈の長いブルゾンの端からちらりと姿を覗かせて、窓から差し込む月と街の光を反射しているようです。今自分の身に一体何が起こっているのか理解できない私には、彼のそんな姿が、非日常が化学反応を起こした結晶のように見えました。 自宅に着くと、一先ず彼を自分のベッドに寝かせました。ブルゾンを畳んで枕元に置き、とりあえず目が覚めた時に水分だけは摂れるようペットボトルを台所のシンク下の物入れから持ってきてサイドテーブルに置きます。日頃からあまり強くない胃腸を労って常温のミネラルウォーターのペットボトルを大量に用意していた自分を、生まれて初めて褒めてあげたくなりました。暗がりの部屋で、淡い紫のチェック模様をした布団に寝かされた彼の身体は、すっかり弛緩していました。見知らぬ女の部屋に連れ込まれたなんてことには勿論気づいた風もなく、飴細工のようにぐったりとそこに横たわっています。指先で摘んで軽く持ち上げても筋肉が緩みきって、まるで力の入らない腕。私は小さな野良猫を抱き上げた時の感覚を思い出していました。
小さい頃、実家の近くのゴミ集積場に棲み着いていた可愛い野良猫の親子。末っ子の黒猫が私によく懐いていて、手から猫缶や鶏ささみを食べてくれました。小さな身体を抱き上げると、内臓がずるりと下がる手応えがありました。健気な程に細く小さな手脚は温くやわらかくて、まるで薄い外皮に生命の塊が詰まっているようなその感触が、私は大好きでした。ベッドの端に頬杖を突いて、少年の様子を眺めていました。カーテンを開けっ放しにしている窓から差し込む僅かな光を反射して光る首筋の汗が、邪な私の目を釘付けにしました。唾液の滲んだ唇はゼリーでコーティングされた洋菓子のようにただただ蠱惑的で、その隙間から漏れるふいごのような吐息すら悩ましく思える程でした。生命が、休むこと無くそのシステムを駆動させている音です。まるでボイラから煙が吐き出されるように規則的かつ有機的に溢れる二酸化炭素は、二十七歳の恋人すらいない――作る気すらない――女がひとりで住まう殺風景な部屋に、あっという間に充満したようでした。壁中に敷き詰められた音楽評論や現代文学の文庫本、大量のCDが収まった棚ぐらいしか自慢できるようなものも無い小さな部屋に、青臭く甘い香りが立ち込めたような錯覚を覚えます。
できたばかりのオシロイバナのつぼみがそのまま雨に打たれて腐っていった時のような、土の上から漂う芳香を想起させるその香り――実際に彼の吐いた呼気から漂っていたのかどうか、私の錯覚だったのかは今となっては確認する術もありません――は、私の延髄を通って理性を司る中枢を無視し、後頭部から喉奥を通り、背筋を優しく撫でて下腹部まで到達しました。その一瞬の迸りが爪先から逃げ出すより早く、私は矢も盾もたまらず着たきり雀のジャケットを脱ぎ捨てて彼の太ももに跨り、自らのシャツのボタンをひとつ、外しました。まだ背骨のひだを尖った爪先でそっと撫でられたような感覚が残っています。唾液が口から迸って布団に染みを広げました。弾けんばかりに生命が詰まった弾力を両手のひらに感じながら、彼の白い顔を覗き込みます。
私の浅ましい息が無垢の唇にかかるその直前、閉じられていた彼の目が、ぱちりと開きました。
「優しいおばあさんに会いに来たら、狼さんに食べられそうになった、って気分」
ガラス玉のような光沢を放つ瞳が平坦な声音を発しました。
一瞬、部屋中の時間が止まったかのような錯覚を覚えました。甘くなった空気が寒天のように重たく硬直し、指先を少し動かすとその断面にヒビが入るような気すらしました。口の端を唾液で湿らせた女が膝の上に乗っているのです、私が彼だったら腰を抜かし、横っ面を叩いてその場から逃げ出していることでしょう。しかし、彼はそう言ったきり動揺するでもなく、ハチドリの羽根のような睫毛を一ミリたりとも震わせることもなく、愛玩人形のようにただただそこに横たわっていました。私のほうが腰を抜かして座り込んだままでいると、失笑するように口角をふいに上げて言葉を続けます。 「びっくりさせてごめんなさい、いいよ続けて、大きな声出したりしないから」
見開かれた目に表情が一切無いのがひたすら恐ろしかった。まるで深い空洞が広がっているように見えました。闇が詰まったような眼窩から逃れたくて、私は前のめりになっていた上体を元に戻します。今私の目の前にいるのは何か人間ではない、得体の知れない生き物なのではないかと思う程に、幼気さを帯びた「歳相応の大人びた少年」の雰囲気は、気がつけば彼の肉体からすっかり消え去っていました。脅威、と言う言葉が再び脳裡を過ります。さっき聴かされた、あの圧倒的な歌声が脳細胞の奥から鼓膜へ滲み出してきました。せめて大人らしく振る舞おう――最早今の私には、「大人らしく振る舞う」以外の自我を保つ為の術は残されていなかったのです。無論、自然と言葉に棘が現れます。分泌液が増加しているにも関わらずからからに乾いた口を、垂れかけた唾液を飲み込むことで潤し、精一杯大人らしい声で言いました。あなた、随分とすけべなのね。まだ中学一年生でしょう? 大人が相手にするとでも思ってるの? 我ながら悲しくなる程弱々しく、捻れて掠れた声でした。案の定静かな威圧感を相手に与える効果など、今の私の言葉には全く無かったようです。彼はやたら艶然とした様子で笑みを深くすると、濡れた唇を光らせて囁くように言います。「思ってるよ、だって僕、綺麗だから」
綺麗な男の子なんてあなたぐらいの年齢にもなればそこらに掃いて捨てる程いるわよ、と言い放ってやっても良かったのです。今どき雰囲気イケメンと言った便利な言葉もある時代、他人の好意を喚起する異性のチャームなんて多岐に渡ります。実際彼レベルの美形であればこの辺りのライブハウスを必死に探し回ればあとふたりは見つかるでしょう。ですが、私は言葉を失ったまま彼の甘ったるそうな唇の下に鎮座する小さなほくろを見つめていました。
常に何かに苛立ち、口を開けばパート先のスーパーで遭遇した迷惑な客や同僚への愚痴ばかりで承認欲求の塊だったママと、そんな妻のつまらない所帯じみた話になんか耳を貸す気も起きぬと言わんばかりに常にむっつりと口をつぐみ、ろくろく働きもしないで毎日飲んだくれていたパパのお陰で少女漫画にすら恋の夢を抱けないこどもに育っていた私は、両親を大学卒業と共に事故で一斉に亡くすという一大イベントの後も異性に対してはめっぽう淡白でした。幼少期より少しずつトラウマを刷り込むこと程、こどもの人格を歪ませるのに効果的な手法はありません。顔が良いだけの男になんて性的欲求どころか、単純な好意すら虫酸が走ると思っていた私がこんなにも駆り立てられたのは、間違いなく彼が「綺麗だから」なんて貧相な理由ではありませんでした。しかしきっと彼は、自分が全身から発する絶世唯一のコケットリーのようなものをよく自覚しているのでしょう。私の奇妙で身勝手なリアクションを淡い微笑みで容易く包み込み、静かにそこに横たわり続けています。いっそ貫禄すら感じるその佇まいにすっかり驚いた私は、つい頓狂な声を上げてしまいました。
あなた、したことあるの。彼は間髪入れずにすぐさま、無いよ、と応えます。 「でも、いつかはしなくちゃいけないんでしょう? どうせなら、早いとこ済ませたほうが良いのかなあって。普通じゃないって、とってもつらいことだから」
普通のことなら、しておいたほうが良いのかなあって。彼はうわごとのように囁いて力無く笑います。嫌なことならしたくないけど、きもちいいことはすきだから、早くしちゃいたい。えへへ。 私はやや呆れて、そのお陰で平静さを取り戻しました。私もまだまだゆとり世代と言い表される年齢ではありますが、今どきの若い子の貞操観念はいささかファンキーが過ぎる。私が中学一年生の頃などはファーストキスすらまだという子がクラスの七割以上でした。そんなゴミ箱に捨てるみたいな言い方ひどいじゃない、と私は彼を叱りました。お母さんから貰った大事な身体なのよ。しかし彼は怠そうに溜息を吐き、私の言葉が終わらないうちに唇を尖らせて言葉を返します。
「じゃあお姉さん、責任とってくれるの? 僕をこんなにして、責任とるつもりだったの」
僕のお母さんに、責任とるつもりだったの。
私だって、曲がりなりにも女性です。いつかまかり間違って誰かに何らかの責任をとってもらうような可能性はゼロではないかもしれないとは思っていましたが、まさか自分が「責任とってよ」などと言われるような立場になるなんて、一ミリたりとも思ってはいませんでした。返す言葉を見つけ出せないでいる私に、彼は枕営業に持ち込まれたティーンアイドルのような表情で眉を片方だけ持ち上げ、笑っちゃうよね、と吐き捨てるように言いました。伏せられた睫毛が翳りを増して、青い月の光をより色濃く投影します。
「お姉さんはさ、寂しいから、今寂しいから、僕に食いつきたいだけなんでしょう?」
そんな言い方、と私は素直に嘆息しました。食いつきたいなんて、そんなけだもののように言わないでほしい。私は決して恵まれた生まれではないし、ちょっと人よりあたまがいいつもりではいるけれど、それ以上の誇りなど身体の何処を叩いても出てこないし、彼のような伸びしろに満ちた才能も、街ですれ違う百人のうち少なくとも九十人は振り返らせるような美貌も持っていないし、人並みの女性らしさとも無縁でお肌をボロボロにしながら毎日ブラックすれすれのデスクワークを深夜まで余儀なくされている寂しい独身女だけれど、それ程まだ飢えているわけではないはずです。ましてや歳上の素敵な紳士とかならまだしも、相手は歳下の、しかも中学生だなんて。下手をすれば犯罪にだってなりかねない。ひどい。なんて可愛くない子なのだろう。
私の中での彼への印象が摂氏零度を超えてマイナス地点へと向かえば向かう程、――認めたくはありませんが、その反面で、彼から漂う後ろ暗い色香が、増していっているのを感じていました。 舌っ足らずのまだあどけない声が、お姉さんはけだものだよ、と平然と言い放ちます。私に反論の余地も与えず、彼は徐ろに右手の指先でパーカーの裾を摘んで捲り上げます。ローライズなジーンズと赤い布の隙間から、えぐれたウエストと滑らかな白いお腹が見えました。開いている方の手でジーンズのボタンを外すと、ちらりと見える紫色の下着の中に、よくしなりそうな細長い指をそっと滑りこませ、まさぐるように動かし始めます。ぎょっとした私ははからずもその様をまじまじと見つめてしまい、すっかりそこから見動きが取れなくなってしまいました。
ニヒルな色を浮かべていた少年の表情が、まるでチョコレートが溶け出すように、少しずつとろけていきます。ほころんでいた口元がだらしなく開かれ、マタタビを焚かれた子猫のような口角から、唾液が一筋滴っていきます。微かに肩を竦め、小首を傾げているのがシナを作っているようで、憎たらしさが更に増したようでした。ガラス玉だった大きな目からは淫靡な大粒の涙が溢れ、真っ白だった頬が紅を差したように、じんわりと赤く染まります。まるでこちらの欲情を煽っているかのような喘ぎ声が唇の隙間からか細く漏れ、下着の隙間から見える申し訳程度の腰骨が、痙攣するようにがくがくと震えています。心なしか、部屋に立ち込めた青く甘ったるい匂いが増したような気がしました。頭の奥の、脳味噌ではない何処かがじんじんと痺れています。身体の芯が熱く滾り、下半身が崩れ落ちそうでした。
彼の言う通り、私はやはりけだものなのでしょうか。
次の瞬間、ありきたりなメタファーではありますが、私の中の何かが砕けた音が聞こえたような気がしました。私は、目の前の獲物の柔らかな肢体に、一心不乱にむしゃぶりついていたのです。
私の爪はかぎ針のようにただひたすら鋭く尖り、手をついた場所に生えている雑草すらも一瞬で粉々になる程でした。赤ずきんの魅惑的な後ろ姿に導かれて迷い込んだ森の奥で、私はその柔らかな純潔の肌に爪を立てます。
私は、人間だったのでしょうか。
その瞬間の私の頭の中からはつい先程までの実感と生活感を伴った、そこに存在しなければならないはずの記憶がすっぽり抜け落ちていたようでした。今となっては不思議で仕方ありませんが、その時の私にはそのことを不思議がるいとますら無く、何故かそれはそのような「事実」なのだと受け入れ、ただただ目の前の獲物を、欲求の赴くままに捕食することしか考えていなかったのです。
彼の――赤ずきんなのだから普通は女の子なのではないかとも思いますが、その時の私は毛むくじゃらの獣でしたのでそんな高度な思考には辿り着けませんでした――、赤い洋服の裾から覗く白い腹からは、真っ赤な内臓が覗いていました。
いいえ、違います。
あれは、そう、果実だった。
赤い野苺のような実が、夥しい数の野苺の実が、彼の華奢な腰の皮膚を突き破って溢れ出しています。それも実のひとつひとつが獣の私の掌程度もある大きな実で、指先で摘むと、まるで血のような真っ赤な果汁を甘い芳香と共に垂れ流します。
薄い胸に爪を立てると皮膚が切れて血が滲む訳でもなく、手応えも無くその表面が凹んでじわりと果汁が溢れます。鬱蒼と繁った森の中は、気がつけば彼が放つ甘ったるく熟れた果実の匂いで埋め尽くされてしまいました。私は、彼のその腹の中に顔を埋めて意地汚く果汁を啜ります。食べても食べても腹が減り、口が渇き、反面で胃の底からせり上がるような吐き気を覚えてもいました。鋭い犬歯が赤い実に突き刺さるたび、弾けるように口の中に甘酸っぱい味が広がり、私の気持ちはとても満たされます。ぐちゅぐちゅといやらしい音を立てながら草の上に横たわる彼の肉体を貪り食う私は、鼻をつく夜露の草いきれの匂いにすら発情して尻尾を振りました。舌に絡みつくような赤い果汁の質感は、唾液と混ざり合って喉奥を流れ、口の端から溢れ出し、彼の白い太ももを経血のように汚します。地べたについた膝が泥に塗れるのも厭わず、私は舌を遣い、歯を遣い、指を遣って彼の青い肢体に実った果実を犯しました。
彼は持ち上げた服の裾を両手でぎゅっと握り、首を仰け反らせ、息を切らしています。時折思い出したようにか細い声で苦しげに喘ぐと、小刻みに痙攣して脚をバタバタと動かします。こんなになってしまっているのに腰を振る元気があるというのも不思議なものですが、彼の白い顔は快楽に上気しているようでした。
彼が、掠れた声でうわごとのように、たくさんお食べ、と囁きます。両手を草の上につき、上体を少しだけ起こして熱い吐息を漏らします。腹から実がひとつ転がり落ちて膝の上に落ちました。私は何故かちょっぴり冷静になってしまい、なんだか子持ちししゃもみたいだなあなどと思いながらその様を固唾を呑んで見ています。 彼は、溢れんばかりの果汁を垂れ流しながら身を乗り出して私の毛むくじゃらの顔を覗き込み、とびきり甘い声でおねえさん、と言いました。
おねえさん、
おしえて?
「人間が獣じゃないなんて保障は、何処にあるの?」
荒い吐息混じりの舌っ足らずな口調とは相反するその理性的な物言いに、獣の私はたいそう驚いて口を噤みました。愛液のようにだらしない唾液が口の端から滴り落ちます。赤い頭巾の下から覗く彼の白い顎が、喘ぎ疲れたのかひくひくと歯の根が合わないように震えていました。腹の果実と同じ色をした唇が物欲しそうに微かに緩み、しかしそこから迸る言葉はまるで、すれ違う者すべてに問答をけしかける挑発的な哲学者のようなものでした。
「もう要らないはずの鼻毛だって脇毛だって生えてるし、ほかの命を食べないと生きていけないんだもの、人間だって獣と一緒だよ。おねえさん、食物連鎖って知ってる? 知ってるよね、小学校で習うもの。強い生き物が弱い生き物を食べるの」
生きる為だけに生きている獣と、文明を築いた人間を同じ論上に上げてはいけない。日本語を発する器官があるのかすら怪しい私はそう思ったが、反論の余地など残されてはいない。
「人間は文明を生み出した高等生物だなんて言う、頭の良いひともいるだろうけどさ、ご飯を食べないと生きていけないし、セックスしないと増殖できない時点で、ただのちょっと賢い哺乳類でしかないじゃない。支配しているようでいて、強い生き物には弱い生き物がいないと、生きていけないんだよ。確実に人間だってその一部なんだよなあ」
確かに、人間が文明を築いたのは他の動物のように「ただ生きている」だけではつまらないから、生まれてから死ぬまでの大いなる暇つぶしのようなものなのだと、何かで読んだ気がします。文字も数字も政治もすべて、結局は私達人間が勝手に生み出した「余計なもの」であり、野生生物のように生きていれば不必要なものなのかもしれない。
しかし、豊満な毛皮に覆われた私の胸に、ふと疑問が湧きました。そんなスペースオペラレベルの暇つぶしをしたいだなんて、やっぱり人間は他の獣とは違うのではないか?
そうだ、人間には、ただ生きているだけの毎日をつまらなく思う「心」がある。 私はカサカサに乾いて上顎とくっついてしまいそうな舌を無理矢理動かし、その天啓のような反論を彼に投げかけようと試みます。
しかし、そうだ、私は人間ではない――私は身体中を毛の鎧で覆われた獣でした。調理器具を持ち歩かずとも捕食対象をその場で手ごめにできる代わりに、言語を発する為の中枢を失っています。鳴きそこねたイボガエルのような声で「ここ、ろ」と言うと、彼は嘆息するように失笑します。
「心なんて他の生き物に無いって言える? おねえさんは人間の子供を育てる狼の逸話を知らないの? 心ひとつで生きていける高等生物なんてこの世にはまだいないよ」
彼は、心底おかしそうに小首を傾げて笑います。まともな言語を発する前に論破された私は、荒い息を肩でしながらただ彼を見つめていることしかできません。彼は身体を少し起こし、膝立ちで私ににじり寄り、リビングのラグのような私の膝の上に乗っかって全体重をかけます。すっかり身動きを封じられた私は、赤い液体に汚れた彼の下半身を、涎を垂らしながら見つめていました。そんな私の顔を小さな白い両手がそっと包みます。顎をくいっと上げられ、目を合わせられました。頭巾の影から、潤んだ大きな瞳が上目遣いに私を見つめ、そして優しく囁きました。
「だから、良いんだよ。これが普通なの。ねえおねえさん、普通じゃないって、とってもつらいことでしょう?」
三大欲求が直列繋ぎな獣の私には、その誘惑は非常に酷なものでした。
次に私が気がついた時に見た光景は、真っ赤に染まった草の上に打ち捨てられた、赤い洋服でした。私は、木の股に背中を預け、何もかんがえられない脳味噌で暗い森の中に埋もれていました。鼻腔にこびりつく彼の匂いが更に血流を促し、身体の芯が痺れたように疼きます。四肢の末端が弛緩しきって鉛のように重く、腕を上げるだけで心臓が軋みました。
何故かそのとき、私は、幼い頃に見てしまった両親の情事の風景を思い出していました。
まだ三歳の少女には衝撃的すぎて詳細までは既に忘れてしまっていますが、母が父の上に覆い被さり、背中をひくつかせているのが、父の寝室の襖の隙間から見えたのだけは、鮮烈に覚えています。男の悪い部分を凝縮したような父と、女の悪い部分を凝縮したような母。その様はまるでカマキリの夫婦のようだなあ、と、高校生ぐらいの頃に考えたこともありました。私が男女の事情や性的な事柄に対して極端に淡白になったのは、その頃からかもしれません。いっそのこと、木の股から生まれたとでも言ってほしかった。
腑抜けのようにそんな回想に身を委ねていると、突然、急激な腹痛に襲われました。ひどい下痢を起こした時のような内臓を捻り潰される痛みに次いで、今度は未知の激痛が私を襲います。腹の皮を引き裂かれるような痛みです。毛皮を剥がれる動物はこのような痛みを感じているのか、寧ろ毛皮用の狼のほうがひと思いに殺されてからの所業なのだからまだましではないか、などと思いながら、蹲って草の上を転がっていると、まるで麻酔でも打たれたかのように激しかった痛みが一瞬にして消え、その代わりに全身から力が抜けました。金持ちの家の絨毯のようにその場に伸びてしまった私の上には、一面の殺風景な夜空が広がっています。
一等星すら輝いて見えず、まるで宇宙に空いた穴のようにぽっかりと黒い。もしかしてこれは空などではなく、私達獣が捕らえられた、檻の天井なんじゃないかしら。夜を迎えるたびに黒い布がかけられて、人工的に夜空が作られるのじゃないかしら。右端に浮かぶ申し訳程度のお月様は、黒い布に空けられた小さな穴だ。あんなに小さな空気穴から、私達は酸素を得ているのだ。
気が遠くなりそうな無感覚に、人肌のぬるま湯の中に浸されているような気分になっていると、狼の腹が突然、裂けたのです。
勿論、まったく予兆も何もありません。感覚を失った私の腹がミシミシと音を立て、まるでポケットティッシュの袋のように、そこに予め切り込みでも入っていたかのように、ふたつに裂けました。瞬きすら忘れた私はただ、目の前で繰り広げられるシュルレアリスムな地獄絵図を眺めていました。
ゴムのように伸びた私の腹の皮膚の中から、何か、ヒト型のものが出て来ます。それは針金細工のように細く曲線的で、全身から赤い液体を滴らせながら、プールから上がってくるかのように私の胸に足を乗せ、一旦直立し、膝をついて四つん這いになりました。
着せ替え人形程のサイズでありながらヒトの形をし、自力で動くそれは――
彼と、同じ顔をしていました。
竹の根のように細く白い髪はやや透き通り、微かに発光して薄闇を照らしています。その髪の隙間から覗く、困ったような下がり気味の眉も、潤んだ大きな瞳も、誘惑的にめくれた柔らかそうな唇も、私には、見覚えがありました。見覚えなんてものじゃありません。私は、腹の底から這い上がってくる恐怖に頭を抱えました。しかし私には今腹が無いので、この恐怖が一体何処から湧いて何処へ向かうのかわからず、パニックを起こして声を上げてしまいました。
吠える獣の私の上に乗った小さな彼は、青白い肌をしています。さきほどのような卑猥な血色は一切消え、まるで中国の陶器のような頬で、狼の遠吠えをおかしそうに笑います。指で少し触れただけで折れてしまいそうな――否、折れる、と言うよりは手応え無く貫通してしまいそうな彼の肩からは、微かに向こうの景色が透けて見え、ソーダ味のゼリーのように無機質な柔らかさが感じ取れました。その肌の表面を、ラズベリージュースのような液体が、薄っすらと覆っています。
ふいに、彼がお尻を上げて伸びをしました。
生まれたての子猫のようなその仕草に目を奪われていると、その滑らかな背中から、翼が、 たわわに羽毛を湛えた翼が、一翼、生えたのです。
若鳥の雛のように赤い液体に湿らされた片方だけの翼は、その小さな羽毛一本一本を震わせ、意志を持っているかのように蠕動していました。
触れなば壊れてしまいそうな造形作品のような彼の背中で、それだけは、まったくの有機的な生き物のように動いていたのです。
サモトラケのニケのような姿になった彼は、上体を上げて私の胸の上に膝を抱えて座り、とびきり可愛らしくにっこりと笑います。
「驚いた? 僕もおねえさんの真似をしただけだよ。僕のこの身体も、何かを食べないと生きていけないから。お腹がすいちゃったの」
何かを言っている、と思いました。正常な思考回路を失った獣には、言葉が理解できません。胸が詰まり、呼吸が止まりそうになります。私の胸にのしかかる彼はまるでクラゲのように重さを感じないのですが、何故か息ができなくなったのです。口を半開きにして無理矢理に酸素を取り込もうとしたら、唾液が吹き出しました。だらしなく大量の涎を垂らす私を彼は派手に笑い飛ばし、天使のような笑顔を満面に浮かべます。鈴の鳴るような声が、耳鳴りのように私の鼓膜を圧迫しました。
「みにくいね、おねえさん。こんな僕を見てもほら、涎が止まらないよ?」
身を乗り出した彼の淡い桃色の唇が、イモムシのように蠕動し、私の耳元でとびきり甘い声が聞こえます。今や役割を持っていない脳味噌が、溶け出して耳から出てきてしまいそうな、甘い甘い声。
「僕、おねえさんのそういうすけべなところ、すき。愛おしいと思う。本当だよ、みにくくて、人間的で、食べちゃいたいぐらいに、可愛い」
彼が私に見えるように、口を開けて見せてくれます。小さな口腔の中には細い針のような歯が夥しく生え、規則正しく並んでいました。真っ赤な舌が見えます。その赤は、さきほどまで彼の腹の中に蔓延っていたあの赤とは、まったく違うものでした。 夢のように美しい青の中、その赤はまるで地獄のように赤く、そこだけが、生物であるかのようでした。
気がついた時、私は病院のベッドに眠らされていました。
お医者様には働きすぎ、過労と診断され、突然死寸前だったと脅かされ、一週間の入院を言い渡されました。連日の深夜に渡る残業が功を奏したのでしょうか、私は合法的に連休を手にすることに成功したのです。
しかし、気味が悪くなる程に白い部屋の中、隣のベッドを使っている男性の、毎日見舞いに来る若妻とのラブラブな会話を聞かされ続けるのは逆に気が滅入ってしまいます。私は、その一週間を、魔法にかかったように朧気になった記憶を掘り起こすように、ヘッドフォンで彼の歌を聴きながら過ごしました。
今でも、私の記憶の中には先程綴ったような、悪夢とも淫夢ともつかない記憶しか残っていません。確かにあの時私は狼で、今でも夜中になると、時折自分が何者であるのか、本当に人間であるのかというアイデンティティクライシスのような感覚に見舞われ、洗面所の鏡を震えながら覗くといった日々を過ごしているのです。万年思春期の私が幼い頃から恐れ続けている、獣のような「女」の姿。私はそうなりたくないと頑なに思いながら、あの曲を自ら聴いては、喜んであの日の記憶を喚び起こしていました。
霧雨のようなコーラス、きつくディストーションのかかったギター、三拍子のドラムンベースと悪夢のように明るいシンセサイザー。
そして、どこまでも高潔で、途方も無く蠱惑的な、彼の歌声。
私は、彼に、もう一度会いたい。
私は、あの日確かに、彼に食べられたのだと思いました。
入院生活も最後の一日になったころ、病院の中庭を散歩していると、私は見覚えのある後ろ姿を見つけました。都心の一等地に構える共済病院の小さな中庭には、入院患者とその家族しか入れないはずでした。私は、規則正しく並んだ煉瓦の花壇に咲く、大輪の赤い芍薬に紛れるように佇む細い背中をひと目見た瞬間、思わず一心不乱に追いかけていました。
芍薬の花壇を回り、その先の飛び石の置かれた土の道を、その背中はどんどんと歩いていきます。私は彼に気づかれるかもしれない、と一瞬思ったものの、はやる身体を抑えることができずに歩みを進めました。
私は、彼のようになりたいと思っていたのかもしれません。
いつだって、「当たり前」に逆らうことで自己を保ってきました。流行りモノのアイドルは聴かず、ライブハウスにも音楽フェスにもひとりで向かい、まだマイナーなミュージシャンを自分の嗅覚で発見することに史上の喜びを感じ、澁澤龍彦と丸尾末広とゴーリーを愛して下北沢で就職しました。誰もが結婚したら幸せになれると、半ば盲目的に保証もなく信じ込むロマンチックラブイデオロギーが当たり前の社会で、私は早々にそのような「当たり前」を、捨てたはずでした。産んで育てるだけの獣になんて、延々と増殖を繰り返すだけのプラナリアのような群衆と一緒になんて、生きるためだけに食べるハイエナ野郎になんて、なりたくもない、と。
ですが、私も、結局のところ、彼ら彼女らと同じ、獣でしかないのでしょう。
木の鬱蒼と茂る植え込みに、彼は膝をつきました。あの日と同じデニムのブルゾンと赤いパーカーの下に着た膝丈のガウチョパンツの裾から、汚れた膝小僧が見えます。私はとりあえず近くの低木樹の陰に身を隠しました。鼻をつく青臭さに、あの夜の記憶がまたフラッシュバックして、気がおかしくなりそうになります。
私は身勝手な大人です。あんなに小さくか弱げな幼い子を犯しておいて、記憶が無いのを良いことにのうのうと入院患者ぶっています。その上、あの子にまた会いたいだなんて、厚顔無恥にも程がある。
パーカーのお腹に包んだ何かを取り出し、土の上に横たえる彼の生まれたての子鹿のような背中を見ていたら、何故だか涙が滲みました。
何故あの時、私は完全に彼に食べられてしまえなかったのだろう。彼の若い肉体の一部と成り代われたら、どんなに楽になれるだろう。肉体の重さに耐えきれない私は、そんな世迷言を繰り返します。
霞んだ視界の向こうで少年は、土に穴を掘っています。
傍らに置かれている物体は、小さな青い雛鳥の、死骸でした。
私は恐怖に竦みました。雛料理に使われた卵の中身のようなそれを、彼は両手を汚して掘った穴の中に、赤ん坊でも寝かせるようにそっと仕舞います。そして、土をかける前に、口の中に含んでいた白い飴玉らしきものを、死骸の上にひとつ、落としました。
指先で濃いピンクの唇の隙間からうやうやしく飴玉を取り出し、唾液の糸を引かせたまま穴の中にぽとりと落とす仕草は、何かの淫猥な儀式のようで、背中が粟立ちました。
彼は、雛鳥の死骸の上に丁寧に土を被せると、膨らんだブルゾンのポケットから三五〇ミリリットルのペットボトルを取り出しました。透き通った液体に少しだけ唇をつけ、残りをすべて鳥を埋めた場所にかけました。からの容器の蓋を丁寧に閉めた彼は、人形のように無表情だった顔を、満足げに緩めます。
すると、彼が埋めた雛の墓から、定点カメラの早回し映像のように、芽が生え、茎が伸び、そして、大きな大きな赤い芍薬の花が、咲きました。
根から鮮血を吸い込んだような、赤い花。
花が咲くのを見届けた少年は、その、歳相応の幼気さの滲む顔に、心臓がしびれる程無邪気なくしゃくしゃの笑みを浮かべ、こちらを振り返りました。
【優秀賞】風の墓守(四条葵)
私は墓守だ。七年前からずっと、私は霊廟に住んでいる。太陽が昇って朝が来て、なにもない一日が終わり、夜が来る。ただそれだけの毎日を、私はこの静かな墓地で暮らしている。
私が暮らしているのは、海の見える田舎町。大事件など滅多に起きず、起伏の無い日々が続いていく。そんな街の一隅に、私の家はある。
私は死は一つではないことを知った。心臓が停まり、呼吸が止み、血液が冷却したら、それは間違いなく生者の最期だろう。だが肉体的な終焉のみが死なのではない。精神もまた、その死を持っている。判断力を失い、朦朧とした意識の混濁の果てに、魂が失明したら、それもまた死である。私が看取ったのは、そんな精神の最期なのだ。
幼年時代とは、誰しも幸福なものだ。私は幼少期には幸せな生活を送っていた。だが幼稚園を卒業し、父の仕事の関係で生まれ故郷から程近いこの街にやって来た時から、私の地獄が始まった。
小学校一年生の時、私は学校で朝顔の種を植えた。青いアクリル製の植木鉢に、黒土を入れ、種を播き、水をかけた。夏になったら花が咲きますからね。そんな担任の女教師の言葉を信じ、鉢を学級花壇の隅に並べた。翌日登校してくると、並んだ鉢の中で、一つだけが地面に叩き落され、土が無残に散乱していた。そこには自分の名札があった。誰かが故意に鉢を破損したのだ。今にして思えば、それが全ての始まりだったのだ。
クラスに一人、格闘技好きの児童がいて、私は毎朝登校すると、その子にいつも無理矢理格闘技の技をかけられた。毎朝毎朝、教室の後ろの空いた場所で、殴られたり蹴られたり、責め苦が続いた。最も恐ろしかったのは、両足を掴まれて振り回された時だった。自分の体が遠心力で浮き上がった瞬間の恐怖を今でも忘れない。
私は祖父母に育てられた。まだ幼稚園を終えたばかりで、抵抗することも知らない私は、学校でこんな目に遭っていると祖母に訴えた。だが昭和一桁生まれの祖母が今時の虐めの悲惨さを知る由はなかった。「やめろー」って言ってやればいいの。それが答えだった。
やがて私は、自分が実際に虐められている現場を祖父母に見せれば、助けてくれるかもしれないと考えた。そしてある秋の運動会の日、いつものように暴行を受けていた私は、保護者席で運動会を観戦している祖父母の前に行き、殴られたり蹴られたりしている自分の姿を見せた。
ほら、虐められているよ、助けて。
その日の夜、祖母は言った。
「あんたどうしてやられたらやり返さないの。言ったでしょ、やめろーって言えって。そう言えばいいのよ。なんて情けない子かしらねえ。みっともないからよして頂戴」
私はその時悟った。誰も助けてくれないのだということを。
銀行員だった父は滅多に家におらず、朝、私が目覚める前に家を出て、深夜、寝入った後に帰宅した。親子の会話らしい会話は殆ど無かった。母親は母親で、夜といえば民放の番組ばかりを見ている人で、やはりやりとりは皆無だった。学校で虐めに遭っているということを相談する身内の人間がいなかったのだ。
暴力と孤独と悲哀の小学校を終えると、私は学区内の公立中学に通った。だがここでも、私は今までよりも一層酷い虐めを受けた。
クラスの生徒は誰しも私を不可触民として扱った。口をきく者はいなかった。男子も女子も、自分が大切にしている鉢植えにたかる害虫を見る目で私を見た。目が合うと、必ず嫌悪に満ちた目つきで視線をそらした。クラスに安永という担任がいて、昼に一人で弁当を食べるのは禁止だと言った。一人で食事するのだって、そいつの人生じゃないか。一人で生きていくことを選んだ立派な自己責任だ。そう思ったのだが、誰も一緒に食事をしてくれなかった私は、お願いしますと頭を下げて、あるグループの端に机を並べて食事をさせてもらっていた。
三年生の時、男子だけの二クラス合同の技術の時間に、私は常々虐めていたリーダー格の生徒に因縁をつけられ、土下座して謝れと言われた。その場にいた教師はそれを見ていたが、黙殺された。私は膝をつき、土下座をした。その時の屈辱、悔しさ、敗北感、そして見つめた床の上の木屑の匂いを、私は終生忘れないだろう。
そんな具合であったから、私の中学校での学業成績はふるわなかった。三年生の時、担任の教師が私に紹介した進学先は、県で最低の底辺高だった。
私は納得がいかなかった。散々私を面白おかしく虐めた連中は名門進学校へ行くのに、私は底辺高。だが力の無い私の何が通るでもなく、私の進路は決まった。だが私はその時、何かの本で高校再受験というものを知った。東京の御茶ノ水に再受験専門の学校があって、そこへ行けば高校を選びなおせるというのだ。私は両親に切に願った。どうか再受験させてほしい。その学校へ行かせて欲しい。
だが母をはじめ、両親の対応は冷たかった。私は横浜の山手学院か森村学園に行きたかった。そこを再受験するのだといくら言っても、聞く耳を持たなかった。
高校は小田原にあった。下り電車に乗って着いた先の、それも裏口を出て、ひたすら山を登った。途中、観光客相手に地元の名産品や弁当を売る一画があって、そこを通り抜ける時には色々な弁当の匂いが混ざり合った得も言われぬ悪臭がした。学校は山の中にあった。周辺には何もなかった。落ちこぼれの隔離施設。そんな言い方が一番だった。
私は負けなかった。来年絶対に高校を再受験する。そう思うことが、この絶望を受け入れる唯一の支えだった。私は地元の書店で高校受験の参考書と問題集を買い、家で自習を始めた。一年はあっという間に過ぎ、私は両親に約束通り再受験をさせてくれと言った。御茶ノ水の再受験学校へ行って、手続きをして欲しい。
母はいかにも形だけというふうに私を連れてその学校へ行った。すると面接官の島田という男が出てきて、私たちを迎えた。
島田は特別な事情があっての再受験でなければ難しいこと、私の学力では志望校合格は難しいこと、そして再受験の事実が露見したら今在籍している高校に虐められるぞ、と言い、結局私の請願をつっぱねた。母も特にそれに異を唱えなかった。
その夜、悔しさを抱えたまま二階の自室にいると、電話が鳴った。呼び出し音の止まった電話を前に、数秒躊躇した後、私は受話器をとった。
母と祖母の声だった。
「もしもし、あたし」
「ああ、どうだった、今日の東京の学校?」
「あんた、はっきり言われたわよ、無理だからよしなさいって」
「あはは、そうなの」
「そうよ、言われたわよ、あんたじゃ無理だって」
「あはは、そう」
「そうよ、もうこれで再受験なんてこと言わせないわよ」
「あはは。まあこれで、小田原の高校に、通うでしょ」
「そうよ、ほんとにバカみたい」
私は受話器を置いた。母と祖母の真意を知った。初めから再受験を許可する気など無かったのだと分かった。私はこの日以来、この二人を完全に憎悪した。
それから私は東京大学という存在を知った。ここは日本で一番難しく、およそあらゆる世界の頂点にいる者は、ことごとくここの出身であるという。絶望と屈辱の渦の中で、私は東京大学合格を心に誓った。東大に受かって、今まで私を非人間扱いした連中を見返してやる。それが私の人生の新しい、そして太陽の如く力強い目標になった。どんなにつらい時も、東大合格という目標を思えば耐えられた。
六年が過ぎ去った。その間に私は高校を卒業し、地元の予備校に通い、ひたすら受験勉強をしていた。しかし、中学、高校と落ちこぼれた私に、数学を克服することは至難だった。また全体に基礎力不足だった。結局私は東大はおろか、早慶も叶わず、学習院大学の法学部に合格した。初めて踏んだ東京の土。大都会の校舎。何から何まで私の憧れだった。だが、周囲に比べ四年も浪人しているという事実は、私の大学生活開始に最大の障害となった。私は間もなく学校で居場所を失い、次第に授業に出なくなった。友達も恋人も出来ず、私はやがて一人となった。
ある花冷えの四月、新宿御苑に行った。丁度桜の花時で、苑内はあちこちで花見に興じる人々で一杯だった。私は無関係なのだ。あらゆる仲間と友情から、無関係なのだ。私は異邦人だった。そして間もなく、私の大学生活は終わった。
私は大学を中退したのだ。そしてまた、高校時代に嫌いな学校に無理矢理通い続けた精神的ストレスが原因で、統合失調症を発症していたとその時わかった。私は当時、学生相談室に通い、就学上の悩みを色々打ち明けていたが、私の状況では障害年金を申請し、受給したほうがいいと言われた。母もその相談の場に同席していた。相談が終わった後、丁度昼時だったので、私と母は学生食堂に入った。一面にガラス窓で、テラス席で楽しそうに談笑する幾つもの学生の輪を見ながら、母はスパゲティナポリタンを、私はフライ定食を食べた。半分も食べないうちに、母はフォークを置き、帰ると言い出した。そして昼下がりの食堂を一瞥するや、「情けない」と言って泣き出した。母は高校時代にはクラスの中心的な生徒だった。同性、異性問わず沢山の友人恋人がおり、その息子としては、あまりにも情けない青春だったのだろう。
私はその時から、家で親子喧嘩をするようになった。そもそもが行きたくない高校に無理矢理通わせたのが原因なのである。中学校だって私立に行かせてくれていれば虐めなど受けなかったはずだ。学力崩壊になったのも、対人関係構築が出来なくなったのも、全てその教育方針の間違いが原因なのだ。私はことあるごとに、両親にこう言って訴えた。高校だってサポート校や通信制に行かせてくれてれば、精神病になることもなかった。なぜ私立中学受験をさせてくれなかったのか。来る日も来る日も、私と両親は争った。やがて母は鎌倉の実家に帰ることになった。これ以上私と生活を共にすることは出来ないと父が判断したのだった。
だが私は東大を諦めなかった。大学を辞めた以上は、また東大を受験すると言って、再受験の勉強を始めた。駿台や代ゼミの東大コースにも通った。だが半年と経たないうちに、どちらも挫折した。数学が出来なかったのだ。やがて英国地歴は出来るようになったが、数学理科は壊滅的に出来ないという状態になった。受験生活最後の年、十一月に受けた駿台の北大入試実戦模試では、B判定にあと五点足りないC判定を獲った。それが私の最後の受験勉強らしい勉強だった。私はそれ以来家に引きこもり、外界との接触を絶った。
私の家は霊廟だ。私という精神の死者が暮らす墓地なのだ。私はそこで一日を暮らし、静かに生きる。そうして私は四十四歳になった。
じゃあ行ってくるからな。そんな父の声が、襖の向こうから聞こえてくる。私はそれに曖昧に返事をして、枕もとの時計を見る。十時少し前だ。私は布団の中で大きく伸びをし、醒め行く眠りの後味を喉の奥に感じた。私が寝ているのは一階の和室。朝起きると、布団一式を畳んで押し入れにしまうのが日課になっている。顔を洗い、着替えると、バタートーストを食べ、牛乳を飲む。時は四月。すっかり瑞々しさを増した陽光がレースのカーテン越しに入ってくる。今日も何もない一日が始まるのだ。
父は朝のうちから、一日をずっと鎌倉の母の実家で過ごすのが習慣になっている。夜の七時頃に帰宅するまで、この家は私一人のものだ。
いつの頃からか、風俗店に興味を持つようになった。スマホで地元の場所と風俗店というキーワードを入れると、周辺の店が何件か表示される。
私は女子高生という存在に憧れていた。高校生の時からずっと、彼女達は遠い彼方にいた。電車に乗って、隣に女子高生が来ると、無意識にその短いスカートから伸びる長い脚に目がいった。そのしっとりした髪が、透明な肌が、澄んだ瞳が、私の股間をいたたまれなくさせた。私は出来ることならその脚に手を伸ばし、掌でその白い皮膚を撫で、スカートの中にある女性器を舐めて、胸を揉み、唇を重ねたかった。だが私にとって彼女たちはすぐ隣にいる、しかし絶望的に遠い存在だった。駅で女子高生を見るたびに、私の性器は勃起した。若く、瑞々しく、溌剌として、明るい。私にとってそれは、すぐ隣にいる、しかしどこまでも堅いガラスで隔てられたものだった。
二十九歳の時、私は自分が童貞のまま三十歳を迎えるという現実に絶望した。私には女との接点が無かった。そのままずるずると三十代を終え、四十代が始まって一年目の冬、私は平塚にある風俗店に行った。
初めての経験であったので、スマホで店のホームページをまず確認した。そこには店の紹介と、在籍している女の子の写真が載っていた。その店のコスチュームは高校の制服のようなブレザーで、髪を茶色に染め、きわどい短さのスカートを履いた少女たちがいた。と、一人の女性に目がいった。肩までの長い髪で、目には曇りガラスがかけられていたが、スカートから伸びる脚は美しく、華奢な体つきをしていた。
私は店に電話をした。すぐに店員が出た。年の頃は三十代といった感じの男性だった。
「あの、なにが出来るんですか?」
私の声は明らかに上ずっていた。
「電話で言えることじゃないんで」
そのすぐ後に電話を切った。やはり一度行ってみよう。そう決心しても、股間の疼きが収まらなかった私は、その女の子の写真でオナニーをした。その柔らかそうな太ももを、胸を撫で、首筋にキスする妄想で、あっけなく射精した。いつもティッシュばかりを相手にしている私の性行為に虚しさを覚え、実際に女の子で自慰行為が出来るその店に行ってみよう。そう決意した。
一月の、寒い日だった。私は東海道線に乗り、平塚で降りた。駅の改札口から店に電話をして、道案内を請うた。その通りに寂れた商店街を抜け、場末の数件の居酒屋とパチンコ店がある一画に、その店はあった。誰も見ていないことを確認して、二階へと続く狭い、急な階段を昇った。
二人の店員がいた。一人にスマホであたりをつけておいた女性の名を告げた。奥に通された。部屋に入る前に消毒用のスプレーを口にかけられた。私の両手を見て、爪を切ってあることを確認した。
部屋は二十畳程の広さで、室内は暗かった。視界の限り、長椅子が並べられていて、他の客達が行為に耽っている。なぜか八十年代のポップスがかかっていて、随分前に聴いた日本人歌手の歌を聴いていた。私はマフラーを外して、着ていたコートと一緒にその場にあったフックに掛けた。
間もなく女の子が現れた。こんにちは、と言って私の隣に座った。暗くて顔はよく見えなかったが、それでも整った目鼻立ちをしていた。私が今まで見てきた美人達の顔立ちを要約したような雰囲気だった。やはりきわどい短さのスカートを履いている。柄はピンクのチェック模様だ。
「今まで来たことある?」
そう訊かれて、こういう所に来るのは初めてです、と答えた。
「そうなんだ」
しばし後、めいさんは私のズボンに手をかけ、脱がせようとした。私は慌てて腰に手を当て、ちょっとそれは、と止めた。
「まだいいの?」
「はい」
それからめいさんは隣に座り、私にもたれかかって身を寄せてきた。女の子の体温を感じて、同時に化粧と髪の匂いを嗅いだ。ポップスの歌詞がやけにはっきりと聞こえる。時間終了と何番様ご案内お願いしますというアナウンスがガヤガヤと聞こえた。
「キスする?」
いきなりそう言われたが、私ははいと答えた。
「一応初キスなんで」
「そうなんだ」
めいさんは私の正面の膝の上にまたがって、性器の周りに両手を這わせてきた。太ももがスカートから覗く。私はそれに触りたかった。
「脚、触っていいですか?」
「いいよ」
意外にもあっさりした返事だったので、感情が停止していた機械となっていた私は両手の掌でその太ももを触った。暖かかった。そして滑々していた。生まれて初めて女の太ももに触った。
めいさんが唇を寄せてきた。私は無意識にそれを受け止めた。唇と唇が触れ合った。酸味の無い蜜柑の果実のような味がした。感覚だけが輪郭を伝えてきた。私とめいさんの唇は確かに触れ合ったのだ。めいさんはそのまま舌を伸ばしてきた。私も舌を伸ばした。互いの舌が絡み合って、生まれて初めての接吻を経験した。
陶酔の中にいると、めいさんが私のベルトを解き、ズボンを下した。パンツも外した。勃起していた私の性器を、めいさんがしゃぶった。亀頭に得も言われぬ疼きを覚えた。めいさんが性器をしごき始めた。下半身の感覚が麻痺した。
私の手は一切を求めた。掌の赴くままに、胸を弄り、太ももを撫で、めいさんの髪を触った。私達は暗闇の中で抱き合った。両手がめいさんを求めていた。勃起したまま、めいさんの太ももが亀頭に触れた。シックスナインでお願いします。私がリクエストすると、めいさんはいいよと言って私の上に乗った。目の前にめいさんの女性器があった。私の心臓の鼓動は最高に達した。同時に亀頭に暖かい愛撫を感じた。めいさんの口だった。性器にイソギンチャクが吸いついているかのような不思議な感覚だった。私は舌を出して、めいさんの女性器を舐めた。味はしなかった。不思議な暖かさだけが、舌に触れた。高校時代から、あれほど憧れた女の子の股間が目の前にあった。下半身の快楽と、舌の至福を同時に感じた。私は射精に向けて両足に力を入れた。まだ時間は三十分ほど残っているだろう。その間に済まさなければこの悦楽にきちんと終止符を打つことが出来ない。私は射精を試みた。めいさんは先程よりも速く性器をしごいている。亀頭に感じる口の熱気はとても粘り気のあるもので、私の性器を段々と包んでいった。指先まで充満した性欲で、太ももと尻を触った。快楽が全身を満たした。両足の指の先まで力を入れて、ペニスに全筋肉の力を注いだ。ああ、いく、そう呟いた瞬間だった。私は射精した。この二十数年の間、私の中に溜まっていたリビドーの全てが、熱い奔流となって尿道を通り、めいさんの指の中に迸った。私はその瞬間、感情が漂白された人間のように、全身の筋肉を失った動物のように、脱力した。虚無感だけが残った。つい先程まであれほど私を駆り立てていた獰悪な収奪欲も、女への憧れも、胸や太ももや唇への執着も、一切が冷却されて私の肉体を解き放った。こうして私の性交は終わった。
その後、私達は服を着た。再び元の姿になって、ほんの十分ぐらいの間、私達は話をした。
めいさんはなにも訊かなかった。ただ私の住んでいる街や、好みの女の子のタイプを除いては。私はそれらになにとなく答えた。全て正直だった。体から入る女の関係とはこんなにも自然に行くものなのかと思った。
時間が来た。めいさんは私をもう一度抱きしめて、一緒に出口まで行った。別れ際に私にキスをしてくれた。
私は全身の血液が浄化されたような感覚を味わっていた。つい昨日まで不潔な妄想で女の子を見ていた自分は何だったのだろう。もっと早く来ればよかった。いろいろな思いが脳裏をよぎった。午後の街は相変わらず寂れていた。冬の冷たい風が、コートを濡らす。
帰りのバスの発車を待つ間、私は駅前の「平和都市宣言」と書かれた時計台の柱を見るともなしに眺めた。数人の女子高生が、彼方の横断歩道を渡ったり、街路を歩いている。もう私は彼女達には囚われないでいいのだ。もう私は触りたい物に触り、舐めたい物を舐め、放出したい物を出したのだから。
不思議な解放感と、安息と、精神の平和とを感じた。
バスが発車した。今日この日の事はずっと忘れないだろう。ふと、めいさんの顔が浮かんだ。あの美しい両脚と太ももとが、眼の奥で不思議に溶け合った。
その日私は不思議な精神の高揚感を覚えた。めいさんと交わした会話や、その時のめいさんの表情や、言葉を何度も反芻した。あの暗い部屋でめいさんと語り合ったとりとめもないことが、ランプのように私の心に灯った。それはひたすら暗闇しか知らなかった私の生涯を照らし、今まで知らなかった喜びを与えた。めいさんの華奢な手足や、膨らんだ胸や、美しい顔立ちや、あの優しい声、そして何よりも、母や祖母という老人しかいなかった私の人生で初めて経験した若い人。それは紛れもなく愛の喜びだった。めいさんにしてみれば、所詮私は一人の客で、その場限りの関係だったろう。だが私にとっては違った。めいさんは私が一生で出会った初めての愛しい人で、愛を捧げる対象だった。私は出来ることならめいさんと、客としてではなく、恋人として出会いたかった。これは私の人生の不運だろう。もっと早くめいさんと、高校なり大学なりで、同じ世界の人間として生きていたかった。
夢見心地の一日が終わり、夜になった。居間で寝転んでいると、車の音がした。起き上がって台所の勝手口を見ると、車のテールランプがガラスを照らしている。父が帰って来たのだ。私は父と紅茶を飲んだ。こうして帰ってくると、私は父と茶を飲むのが日課になっている。私はその席で、今日のことはもちろん一言も話さなかった。こういう時の父との話題といったら決まっている。小学校の時、私を私立中学に進学させることは考えなかったのか。小学校時代、私が虐められている時に、父親として何故なにもしなかったのか。それをひたすら父に問うのだ。婿養子だった父は、祖父母の顔ばかり見て私のほうは見ていなかったこと、この家の空気では、とても私立中学受験などという雰囲気ではなかったことを話し、いつも私を不快にさせた。いつも同じ話題で、いつも同じように私は激怒した。高校時代、私を無理矢理底辺高に通わせ、挙句の果てにストレスで統合失調症に追い込んだことに話が及ぶと、父は静かに悪かったと謝った。だがその程度のことで私は赦せなかった。
人道的にどうなんだ? 人一人を発狂にまで追い込むという行為は、人として許されるのか? もう私は結婚出来ない。職にもついておらず、収入が無い私は、恋人を作って結婚し、家庭を持つという男なら誰でも手にする幸せが得られないのだ。あなたは自分の息子から何もかもを剥奪した。普通の人生も、友人も恋人も、結婚も、何もかも。それで人の親と言えるのか。
重い沈黙が座を領した。年老いた父は無口になった。こうしていつもの夜が過ぎていく。
それでも私はその日は幸せだった。自分の部屋に下がって音楽を聴く時も、大好きなバッハやワーグナーやヴェルディの曲の中で、自分の精神が少女の手によってくるまれた繭の中で、蝶に羽化する想いだった。
その翌日から私は、再びスマホで近隣の風俗店情報を調べた。そして私はデリバリーヘルスという存在を知った。電話で女の子が自宅まで来てくれるという。丁度持ち合わせがあった私は、父がいない昼間の間に女性を一人呼ぼうと決意した。そして私は風俗店「ラブ・レボリューション」の存在を知った。
二
ラブ・レボリューションは平塚を拠点に湘南地区に展開しているデリヘルで、在籍している女性達は二十人程だった。女の子の紹介写真を見ると体をくねらせて椅子やソファに腰かけている少女達の悩ましい肢体が載っていた。店名を平塚キャンパスと名乗っているこの店は、十八歳から二十三歳くらいまでの娘が中心らしかった。私が大学に通っている時分には絶対に手の出なかった存在だ。
いつものように父は朝の九時半頃家を出て、一人の私は、ラブ・レボリューションのスケジュールコーナーを見ていた。すると、白のブラウスに濃紺のタイトミニスカートを履いた少女が眼に入った。猫脚のクリーム色の張地のソファに座り、右脚を折って両手で抱えている。髪はポニーテールで、黒に近い茶色だ。両手の指は柔らかそうで、これで自分の性器をしごいたらと考えるだけで股間が勃起してきた。
料金システムを調べた。九十分一万九千円で、交通費が千円、指名料が二千円だった。他にオプションでコスプレというのがあって、ナースやセーラー服の恰好でプレイすることも出来るらしかった。ざっと二万五千円程。なんとか手持ちの現金で賄える金額だった。
そのまま「お店に電話」というのをタップして、電話をかけた。若い女性の店員が出た。
「あの、みなさん、お願いしたいんですけど」
「はい、今空いてます」
それを聞いて血圧が急上昇していくのを感じる気がした。
「九十分コースでお願いします」
「はい。オプションは?」
「コスプレをお願いします」
「どれがいいですか?」
私は迷わずセーラー服と答えた。私の女子高生好きは未だに続いていたのだ。
「三十分程で行きます」
通話を終えた後、時計を見た。午後一時三十分だった。彼女が来るのは午後二時頃、それまでに準備を終えておかなければならない。
部屋はいつも寝ている和室をあてることにした。私は箒で軽く室内を掃除し、布団を敷いた。枕もとにティッシュの箱を置いた。私はもう一度スマホを取り出し、ラブ・レボリューションのホームページでみなさんの写真を見た。ミニスカートから伸びる細く長い脚、柔らかそうな指、胸の膨らみ、そして香りのよさそうな首元。何よりも、ポニーテールの髪型が好みだった。準備を終えた私は、布団の横で膝を抱えてじっとしていた。あの写真の子が来てくれて、体に触れて、キスが出来て、性器をしごいてくれる、そう考えただけで股間が不穏になった。
この辺り一帯は閑静で、昼間でも近所の物音はあまりしない。私は時折玄関の前に面した床の間横の小窓を開けて、まだ来ないかと外を覗った。こうして待っているといくつかの考え事をする。他にも彼女を呼ぶ男はいるのだろう。みなさんはその度にキスをして、太ももや胸を触らせ、性器に指を挿入されるのだろう。いろいろな男達の共有の娘。そう考えると、純粋に自分の魅力で勝ち得た愛ではなく、金で買った愛なのだという思いが胸の中に充満した。それはホルマリンのように心を満たし、心臓を麻痺させる。性欲だけで娘を好いている自分がたまらなく空しく思える。
微かなエンジン音と、車のドアを開ける音がした。急いで小窓を覗いた。ロングスカートを履いて、大き目のバッグを抱えた女性が、黄色いフォルクスワーゲンから降りてきた。みなさんだ。私はそのまま玄関に近づき、チャイムを押すみなさんを見た。私は部屋を出た。
玄関の引き戸を開けると、みなさんがいた。二重の涼しい目元に、高く小さな鼻、薄桃色の唇を緩ませて微笑んでいる。
「よろしくお願いします」
みなさんはそう言って玄関を上がった。白い靴下が可愛らしかった。
自室にみなさんを入れた。香水のふくよかな香りがした。みなさんは窓際に荷物を置くと、服を脱ぎ始めた。まずシャワーを浴びるらしい。私も服を脱いだ。お互い全裸になって、廊下を挟んで向かいにある浴室に入った。私は蛇口を捻り、水がお湯になったのを確認してから、みなさんに渡した。ブラジャーを取ったみなさんの胸が間近に見えた。みなさんは手にした洗剤を指で押して、液状石鹸を出し、私の性器を洗い始めた。ヌルヌルの手が性器に触れた。亀頭にみなさんの指を感じた。途端に勃起した。
「もうこんなに勃ってるの?」
みなさんは瑞々しい笑顔だった。
入浴を終え、私達は脱衣所で体を拭いた。勃起した性器を見られるのに特に恥ずかしさは感じなかった。みなさんも女性器を晒していたからだ。
部屋に戻ると、みなさんは全裸の上にセーラー服を着始めた。この服を選んだのには理由があった。高校生の時、毎朝バスで一緒になる名前も知らない少女に初恋をしたことがある。その彼女が着ていたのがセーラー服だったのだ。
それから私はみなさんの太ももや、胸を弄った。女性器を見て、「舐めていい?」と訊いた。いいよ、という返事だったので、女性器を舐めた。「指、入れていい?」と言ってうんと言ってもらえたので、中指を入れた。みなさんの中は暖かかった。私はみなさんの上に乗り、「キスしていい?」と訊いた。許可されたので、唇を重ねた。両手でみなさんの顔を掴んで、キスをした。清らかな前歯の感触の後に、みなさんの柔らかい舌を感じた。私達は股と股をつけ合った。この上ない快楽が、全身を震わせた。体中の血液が湯だつ思いだった。私はみなさんを抱きしめた。
それから三十分程、私はみなさんの体を貪った。みなさんの脚を、胸を、唇を、味わい尽くした。ポニーテールのみなさんは全てを受け入れてくれた。シックスナインの体位で、私は射精した。みなさんがティッシュを引き抜いて、飛び出した精液を拭った。いっぱい出たね。そう言ってみなさんは笑った。
その後、みなさんはシャワーを浴びたいと言った。一緒に浴びる? そう訊かれたが、すでに性欲が失せていた私は自分はいいと答えた。みなさんがシャワーを浴びている間、布団を片付けた。まだ五十分程時間があった。シャワーを終えたみなさんが体を拭きながら入って来て、服を着た。麦茶飲みます? 私が言うと、うん、ありがとうと言った。私はキッチンで二人分の麦茶を注いで部屋に運んだ。みなさんはグラスを受け取ると、私の隣に座った。女の子とこの距離で話をしたことはほとんど無い。みなさんはまた服を着ていた。もう私はみなさんの全裸を知っているのだ。そう思うと、不思議な親愛の情が湧いてきた。ポニーテールは麦茶を飲みながら私と世間話をした。
仕事はなにしてるの? そう訊かれて、作家志望だと答えた。文学賞に出す小説を書いているんだ。そう言って、床の間に積んである手書きの原稿を見せた。字、超綺麗じゃない? そう言ってみなさんは私の原稿を二三枚読んだ。
みなさんは美しかった。改めて見ると、二重の切れ長な眼や、艶のある瑞々しい髪や、散々私が触った滑々の白い頬は本当に若い人特有のものだった。私は出来ることならこんな恋人が欲しかった。やはり私はめいさんと初めて会った時と同じ思いを抱いた。即ち、もっと早く、みなさんと同じ世界の人間として、友人や恋人として出会いたかった、という感情である。
「大学どこ?」
私が何気なく訊くと、大学は行っていないと言った。
「高校出たきり、そのまま」
どこの美容院で髪を切っているのとか、趣味は何とか、休みの日はどうしているのとか、そんなとりとめもないことを話して、ふと大学の話になった時、みなさんはお兄さんは今の生活どう? と訊かれた。
「まあ、それなりだけど」
「夢はなんだった?」
「大学教授」
「そうなんだ。でも今のままじゃ無理だよね」
「うん。なんとか抜け出したいと思うんだけど」
みなさんは麦茶を一口飲むと、「私も抜け出したい、今の生活……」と漏らした。その時のみなさんは六畳間を通り越して、遥か遠くを見る目つきをしていた。私も夢を語る時は、こういう遠い眼をしているのだろうか。
「大学行きたい?」
みなさんは答えなかった。ただ横を向いたまま、麦茶を飲んでいた。午後の静けさが二人を領した。
「あたし、夢があったんだ」
みなさんは視線を変えずに続けた。私は麦茶を一口飲んだ。この子はまだ十八歳だ。夢を持つことを過去形にする年齢ではないだろう。
「夢? どんな?」
「女子大に行きたい」
私はみなさんの視線の先を見つめた。床の間に飾られた檜扇を見るともなしに見ていた。
「女子大? そこでどうするの?」
「フランス文学を勉強したい」
「フランス文学? 誰を? 時代は?」
「アンドレ・ジッド」
思わぬところで私はかつて学生時代に読んだ小説の名前に巡り合った。
「狭き門?」
「そう」
みなさんの美しい顔立ちを眺めながらこんなことを語らうのは不思議だった。私はそもそも女の子と会話をするという経験がかつてないのだから。
「御茶ノ水女子大?」
「そんな難しいところじゃない」
「じゃ、東京女子大?」
「それも違う」
みなさんはまた一口麦茶を飲んだ。
「日本女子大」
「へえ……」
不意に、学生時代の思い出が甦った。みなさんはまだ若いし、美人だ。きっと素敵な学生生活が送れるだろう。私は学習院にいる頃、ある本を閲覧しに協定を結んでいる日本女子大のキャンパスに行ったことがある。木々の梢が穏やかで、校舎は美しく、静かな構内だった。
「結婚したい?」
私が不意に話題を変えたので、みなさんはふと私を見た。二重の大きな眼で、その眼差しは優しげだった。
「したい」
「彼氏は?」
「いない」
「そうなんだ」
午後の部屋は静かだった。閉め切ってある雪見障子からは、部屋に面した竹の植わっている坪庭が見える。ここには誰も入ってこない。
「ね、大学ってどんなとこ?」
みなさんが静かに訊いた。
「自分は、ほとんどキャンパスライフって、経験してないから」
それは嘘ではなかった。周囲から浮いていて、合コンやクラスの女の子とランチを食べることも出来なかった私の大学生活は、地味の一言だったのだ。
「ゼミとか、あるんでしょ?」
そう言われて、私は退学寸前に在籍していた仏文科のゼミの話をした。二十世紀フランス文学のゼミで、プルーストの原典を輪読する。参加していたのは私を含めて五人程だった。
「楽しかった?」
「イケメンだったら、楽しかったと思う」
学習院の、いや、日本の私大のキャンパスは、顔が全てと言っていい。女の子は美人で可愛い子が、男子は二枚目でかっこいい子が主役になれる。あとはゴミ屑として顔の無い群衆に埋もれるだけ。それが日本の私立大学だ。
「神様に愛された子」
「え!?」
みなさんが驚いた風だったので、私は言葉を付け足した。
「太陽の光が当たる子、そんな子が、楽しい大学生活を送れるよ」
みなさんの顔から表情が消えた。さっきまでの笑顔はやはり営業用のスマイルだったのだと思った。本当に心に刺さることを言うと、そういう飾りは漂白される。そして精神の骨格が露わになった表情になる。眼は虚ろで、口元は微笑みが溶け去り、明るさが消える。みなさんの本当の表情を垣間見る想いだった。
「みなさんが女子大生だったら、どんなだろうなあ……」
私は少し悪戯をしたくなった。可愛くて、明るいオーラの出ているこんな子が大学に行っていない。そんな現実が、私にはなにか一種の皮肉のように思われたのだ。
「合コンとかしたい?」
みなさんは麦茶を一口飲むと、途端に瞬きの回数が多くなった眼で、中空を見た。そこには間違いなくキャンパスに立った自分を見ているのだろう。
「したい」
「どこと? 早稲田? 慶応?」
みなさんは一瞬言葉に詰まって、それでも喉の奥にこみ上げてくる言葉の奔流を隠せない様子だった。
「そこまで頭良くなくてもいい」
「どうして? みなさんなら大丈夫だよ」
私はみなさんの第一印象から受けた率直な感想を込めて言った。
「慶応でも早稲田でも一橋でも、みなさんならどことでも合コン出来るよ」
そうかなあ、どうかなあ、みなさんはそう言ってグラスの中の麦茶を揺すりながらしばし声を上ずらせていたが、はっきりとした目つきになって、私のほうを見た。
「あたし、なに話せばいいのかわかんない」
「そんなこと関係ないって」
私は麦茶を一口飲んだ。
「女の子は可愛ければ、それで十分なんだよ。みなさんはそれをもう満たしているから、あとは周りがついて来るだけだって」
そうかなあ、と相変わらずみなさんは半信半疑な様子だったが、それでもなにかみなさんの心の希望の鉱脈に私の言葉が届いたのだろう。そんな風に思った。
私達は麦茶をすっかり飲み干した。まだ時間は二十分程あった。私は一回席を立って、キッチンから麦茶の入ったボトルを持ってきて、二人のグラスに注いだ。
今日この日、私はすっかりみなさんのことが好きになった。その愛嬌のある仕草や、受け答えの可愛さ、天性のものと思わせる明るさ、そしてなによりもこんな私と屈託なく話してくれた性格の良さに、私はすっかり魅せられてしまった。
私は思った。みなさんのような人こそ、大学へ行くべきだ。それも名門校へ。そして楽しい学校生活を送って勉強し、素敵な想い出を沢山作る。恋人も作る。そして青春する。みなさんのような人こそ、そういう人生を生きるべきだ。
私はある決意をして、みなさんにこう訊いた。
「みなさん、この仕事のこと、親にはなんて言ってあるの?」
「なにも言ってない」
おおかた予想していた答えだった。私は続けた。
「みなさん、自由になるお金は? 貯金はある?」
みなさんは少し改まった風をして、「五百万ぐらい」と答えた。
もう迷う余地は無かった。私はグラスを手にこちらを見ているみなさんの視線に挑むように、真正面からこう言った。
「みなさん、大学行かない?」
「え……?」
一瞬、みなさんの目元が凍った。みなさんは中空を見たまま絶句した。私はかつての自分の受験生活の過酷さを思い出しながら続けた。
「行かない? 日本女子大学」
「……」
みなさんは一瞬私の言葉の意味がよく飲み込めない風だった。二重の眼を私のほうに向け、口を半ば開いて言の葉に窮している、そんな顔をしていた。先程まで私に性的快楽を与えていたその唇が、微かに震えているように思われた。
「行こうよ、日本女子大」
みなさんは下を向いた。そのまま畳を静かに見つめた後、顔を上げた。
「あたし、頭悪いから」
「勉強すればいいよ」
とうの昔に忘れ去ったはずの受験勉強への意欲が沸き起こってくるのを感じた。年老いた私にこれ程の意志があるのだ。若いみなさんには十分やる気があるだろう。その気になれば、偏差値の十五や二十は簡単に上げられる。
「お兄さん、昔家庭教師やってたとか?」
「そうじゃないけど……」
私は改めてみなさんの風貌を見た。色白で、眼が大きくて、鼻が高くて、髪はしっとりしていて、こんな子が女子大にいたら、きっと幸せになれる。私とは大違いだ。
「受験勉強なら、少し詳しいし、人より長くやっていたんだ。大丈夫、勉強ならゼロから教えるから」
みなさんは信じられないという風に、私の顔を覗っている。その目には、女の勘というのだろうか、私のみなさんへの下心があるのかと疑う雰囲気もあった。しかし、その様子はすぐに変わった。
「お客さんとは付き合えないから……」
「付き合うんじゃない」
私は力を込めて、彫り刻むように言った。
「勉強を教えるんだ。みなさんが日本女子大に合格出来るように」
静寂があった。午後のひとときが歯車のように進んでいる。
「あ……」
ふと、みなさんはスマホを取り出した。
「今、出ます」
気が付くと、時間がきていた。思いもかけず長く話し込んでしまったようだ。
「もう、行かないと」
「あ、待って」
私は咄嗟に、ライティングビューローの上にあった便箋の残りの一枚に、自分のメールアドレスと、スマホの番号、名前と現住所を記して、みなさんに渡した。
「私は有馬、有馬浩一。その気になったらいつでも、メールでも電話でもいいから連絡して」
そうして二つ折りにした便箋を手渡した。
みなさんはしばらくそれを見ていたが、すうっと手を伸ばすと右手で受け取った。それをどう扱っていいかわからない風だった。目元に明らかな困惑の表情を見せながら、その便箋と私の顔を交互に眺めた。やがて、それじゃ、と言ってみなさんは帰っていった。
それから私は何か途轍もなく大きなことをしてしまったのではないかという思いと、これで良かったのだという思いを同時に感じた。私一人がこんなことをしたからといってみなさんの何が変わるでもないのかもしれない。でも少なくともみなさんの幸せに関与することは出来る。帰り際、私にさようならを言った時のみなさんのあの可愛い笑顔や、今日の私との話し方、話したこと等、いろいろなことを思い出しては、みなさんのたった一日の記憶を大切に心にしまっておいた。
夜になり、父が帰って来た。いつものように紅茶を淹れて二人で飲んだ。その席で、私は今日のことはもちろん一言も話さなかった。父はいつものように鎌倉の実家での母の様子や、施設に入所している祖母のことなどを語った。私はそれにあいまいに答えながら、今日のみなさんのことを考えていた。果たしてみなさんは何らかの動きを起こしてくるだろうか。メールだろうか、電話だろうか。
その翌日のことだった。朝、いつものように執筆していると、メールの着信を知らせる音が鳴った。急いでスマホを見ると、みなさんからのメールだった。私はすっかり嬉しくなってすぐに中身を開けた。
有馬さんへ。みなです。昨日はありがとうございました。大学のこと、まだ決めたわけじゃないんですけど、お話聞いてくれますか?
私は小学生の時に、初めて描いた絵を担任の先生に褒められた時のような感覚を覚えた。もちろん、いいよ。私はすぐに返信した。
みなさんへ。私はみなさんがどこに住んでいるか知らないけど、家に来るのに抵抗があったら、外で会いましょう。辻堂駅前のデニーズ、知ってますか?
そう送信した後、十分程で返事が来た。
有馬さんへ。みなです。わかります。何時頃がいいですか?
何時でも。私はそう返信した。すると午後の三時頃にと返信があった。私は時計を見た。午前十一時半だった。それまでにいろいろと準備をした。と言っても、メモ帳代わりのノート一冊と、筆記用具を用意しただけだったが、それでもいよいよこれから一大事が始まるのだど考えると、得も言われぬ高揚を感じた。
これは人助けだ。私がみなさんを救うんだ。そう考えて、あとは私の家庭教師としてのスキルだけが問題なような気がした。これからみなさんに勉強を教えるんだ。大丈夫、私大だから三教科だけでいい。英・国・地歴。それさえ出来れば受かるんだから。
私はスマホと、筆記用具と、それらを入れた鞄を持つと、呼んでおいたタクシーに乗り、辻堂駅へ向かった。
三
辻堂駅は、東京から一時間程、湘南地方のごく普通の駅舎だ。北口にはここ十年程前に出来た大きなショッピングモールがあり、近隣の藤沢駅からも、毎日大勢の人がやって来る。そんな辻堂駅の西口は、今や姿を消しつつある商店街がかろうじて残る程度の所。私とみなさんが待ち合わせたのは、そんな西口のデニーズだった。駅のバスロータリーから数十秒歩き、エスカレーターを昇って二階。
私は午後三時十分程前に到着すると、出迎えた店員に二名です、待ち合わせですと告げて、通りを見下ろす窓際の席に座った。眼下の人群れを眺めながら、時折駅にやってくる下り電車を見やり、みなさんはあれに乗っているんだろうかと思ったりする。
三時になった。すると入り口のほうから、見覚えのある姿が現れた。みなさんだ。
「ああ……」
私はごく手短に挨拶を澄ませると、なにか飲みます? と訊いて、はいと言われたので、ミルクティーを二人分注文した。
「よく来てくれました」
私は生まれて始めてデートをする中学生のように緊張していた。女の子と二人でファミレスに来るのは本当に初めてなのだ。
「ありがとうございます」
明るいピンクのブラウスに、春らしいブラウンのマーメイドスカートで現れたみなさんは、間もなく運ばれてきたミルクティーをおいしそうに一口飲んだ。
いわゆる「リア充」はこんな経験をしょっちゅうしているのだろうな。私が大学生の時も、私の知らない所で、こういうことが頻繁にあったに違いない。そんなことを考えていると、私は本題を思い出し、こう切り出した。
「昨日のこと、決心つきました?」
するとみなさんは、ブーケのような笑顔を少しだけ真面目に結びなおして、私のほうを見た。
「私が日本女子大なんて、本当に行けるんですか?」
私は自分の長い経験を活かして、今の日本の大学受験の実情を説明した。
今から一年あるのだから、時間は十分にあること、英語は必要なら中学レベルからやり直せばいいこと、国語は古文、漢文を得意分野にすればきちんと戦えること、地歴はとにかく覚えてしまえばいいということ、それらを、時に比喩を交えて、時に具体的に参考書名を挙げて、詳述した。
みなさんは次第に真面目な顔つきになってそれを聴いていた。途中、ミルクティーのおかわりを注文した。話し終えた時には、午後四時十分前になっていた。
「よくわかりました」
みなさんはさっきまでの余所行きのスマイルをやめて、真剣な眼差しで私を見た。
「で、学習計画なんだけど……」
私は用意していたノートを取り出してテーブルに広げ、筆記用具を取り出して説明を始めた。
「まず、今は五月の中旬だから、とりあえず模試を受けて下さい」
私はノートの一ページ目に、駿台全国模試と書いて見せた。
「駿台全国模試?」
みなさんはいまいちピンとこない様子で、それを受けてどうするんですか? とミルクティーを一口飲んだ。
「今の時点で、どれだけ出来るか知りたいんです。英語と国語と、そうだ、地歴は地理と世界史と日本史と、どれを取りますか?」
「私は日本史が好きだったんで」
みなさんは私が書いた駿台全国模試の文字を見つめた。
「じゃあ、日本史で決まり」
私は更に、ノートに英・国・日本史と書いた。
日本女子大の偏差値や受験科目は、事前にスマホで調べておいた。英国地歴の三教科で、偏差値は文学部で五十七、五だった。
「この場合、三教科もれなく六十くらいにしておけば合格出来ます」
「三教科を六十……」
私はミルクティーを一口飲んだ。
「日本女子大って、マーチレベルだから」
「マーチってなんですか? 」
みなさんはまたミルクティーを一口飲んだ。
「明治・青学・立教・中央・法政のこと。頭文字を一つずつとって、マーチ。関東の準一流大学のことです」
「準一流? じゃ、一流はどこなんですか?」
「一流は早稲田・慶応ですよ」
私はその時、前日にスマホで調べておいた日本女子大の概要で、大事なことを話すべきだったのを思い出した。
「ああ、そうだ、みなさん」
みなさんは中空を見ていた視線を私に向けた。
「日本女子大って、仏文科無いんですよ」
「え……」
調べておいて良かった。みなさんは本気で知らなかったようだ。
「英文科なら、ありますけど」
みなさんはそれを聞くと、テーブルの上のティーカップと水の入ったグラスを見るともなしに見て、しばし、言葉に詰まっていた。
「さっき、一流大学って早稲田と慶応っていいましたよね?」
「はい」
「早稲田には仏文科あるんですか?」
「あります」
私はウェイトレスにお水のおかわりをお願いすると、水を注いでもらった。
「でも早稲田は……」
私はスマホで旺文社の大学受験サイトを調べながら続けた。
「文学部の偏差値が六十七・五。これは日本の私大で一番難しいです。すくなくとも文学部では」
みなさんは無言でミルクティーを飲み干すと、私の手元を見ていた。
「有馬さん、でしたよね?」
「はい」
みなさんの顔が急に深刻になった。そこには初めて会った時のあの軽い明るさは無かった。
「私、早稲田行けると思います?」
「え!?」
私は水の入ったグラスを置くと、みなさんの顔を見た。その眼はいつになく真剣だった。この仕事を始めた際に覚悟を決めた、その時もこんな顔をしていたのだろうか。
「出来ないことはないと思いますけど」
「駿台全国模試でしたっけ?」
「はい」
「それをまず受けるんでしたよね?」
「そうです」
「それから偏差値伸ばせばいいんですよね?」
「出来ますか? みなさん?」
私達は言葉に窮した。マーチレベルまでなら自分が受かったことのある大学だからなんとかなるが、その上の早稲田となると、私も受かったことはない。
「この駿台全国模試は……」
私はスマホで調べながら説明した。
「今年は実施基準日が五月二十九日の日曜日。時間は三教科なら国語が十一時十五分からです。英・国が百分で、日本史が六十分。ところで」
私は水を一口飲んだ。
「みなさんは今まで模試って受けたことあります?」
「無いです」
高校は特に進学校ではなく、周囲に大学進学をする人があまりいなかったのだという。
「早稲田に志望変更ですか?」
みなさんは俯いて、飲み干したティーカップをしばらく眺めていたが、やがて意を決したように私のほうを見た。
「私、早稲田の仏文科行きます」
「では……」
私は早稲田の入試の概要を説明した。早稲田なら東大受験生時代に併願校として何度も検討したことがあったし、入試制度もよく知っている。毎年二月の半ば頃が試験日で、科目は英・国・日本史。私はやはりスマホで早稲田の入試を調べながら続けた。
「英語を特に伸ばさないとだめですね」
「英語、ですか」
「そう、英語。で、次が国語。優先順位は漢文、古文、現代文の順。日本史は合格ラインさえ超えればいいんで、教科書中心にちょっと難しめの問題集と過去問に多く当たって、基本ラインを押さえておけば。ただ、早稲田クラスって、私も受かったことないんですよ」
私はとりあえず、みなさんの英語の偏差値を訊いた。
「高二の時で、五十二ぐらいでした」
「するとあと十五は上げないとだめですね」
私はノートに、ペンで書いた。
「ビジュアル英文解釈っていうのがあるんですけど、これやって下さい。いろんな英文が載ってる問題集なんで、その和訳を作ればいいです。あとは駿台の英文法頻出問題演習のⅠ・Ⅱ、これと、あ、単語集はZ会の速読英単語でいいです」
「はあ……」
みなさんはおとなしく私の言うことを聞いた。そもそも受験勉強自体をあまりしたことがないのだろう。一通り各科目の問題集を挙げた後、私は出来ればそれを向こう三か月ぐらい、つまり夏休み前ぐらいに終わらせてほしいと告げた。
「これ、全部ですか?」
「そうです」
さすがに生涯初の受験勉強としてはきつすぎるか。そう思ったが、模試も迫っているし、なにより志望校は早稲田だ。手加減するわけにはいかない。
「早稲田、行きたいんでしょう?」
みなさんは頷いた。その眼には、明らかに覚悟を決めた人特有の光の鋭さと、顔つきには強固な意志を感じさせる輪郭の太さがあった。
結局その日は、勉強の打ち合わせと、スマホでの模試の申し込みをして、デニーズを後にした。午後五時過ぎだった。帰り際、一緒に北口のショッピングモールにある有隣堂に立ち寄り、一緒に参考書や問題集を選んで買った。速読英単語、英文法頻出問題演習Ⅰ・Ⅱ、ビジュアル英文解釈Ⅰ・Ⅱ、英英辞典、基本英文七百選等を購入し、三科目分の代金は二万円を超えた。まだ模試までは二週間以上あったが、とりあえず単語集だけでもやってみて、そう言って改札口で別れた。模試は駿台藤沢校を会場にした。
模試の前日、みなさんからメールが来た。いよいよ明日です。出来るでしょうか。そうあったので、私は自分の受験生時代を思い出し、とりあえず今の実力を測るのが目的だから、結果は気にしなくてもいいと返信した。
そして模試当日、またメールがあった。今から受験です。頑張ります、とあった。私は春の模試は気楽に受けていい、と返信した。
それからしばらくした六月の下旬、みなさんからメールがあった。模試の結果を見せたいので会って下さい、そう書かれていたので、私はまた辻堂駅前のデニーズを指定し、午後三時に会おうと送った。
その日、また窓際の席に座って待っていると、前と同じようにみなさんが現れた。軽く挨拶して、席に着く。暑いでしょう? アイスティーにします? 頷いたので、私はホットティーを、みなさんにはアイスティーを注文した。
「結果、どうでした」
みなさんはパソコンに届いたメールの成績表をプリントして持ってきた。早速偏差値を見てみると、英語五十一、国語五十五、日本史四十八で、早稲田大学文学部はD判定だった。
更に個別に得点状況を見ると、英語は長文読解が、国語は古文と漢文が、日本史は室町、平安時代の出来が良かった。
「みなさん、よくわかりました」
私は成績表をテーブルに置くと、運ばれてきたホットティーに砂糖を入れた。
「この駿台全国模試は日本で一番ハイレベルな模試だから、今回のみなさんの成績、というか偏差値は、普通だと英語五十八、国語六十、日本史五十一ぐらいです。国語が良いのか救いです。国語って、一番伸ばすの難しいですから。だから夏の間英語を頑張って、国語は……」
私は成績表の国語の欄の、単元別の得点状況を確認した。古文、漢文は共に七割程取れている。
「古文と漢文を引き続き頑張って、現代文は私大型の問題集を夏の間に一冊、しっかり仕上げれば、秋以降に伸びます。日本史は特に問題は無いです。ひたすら覚えるだけですから」
「そうなんですか」
みなさんはそれを聞くと、安堵したように目じりを下げ、アイスティーのストローを咥えた。
「ねえ、有馬さん」
「なに?」
私はホットティーを一口飲もうと、カップを口につけ、すすった。
「一緒に早稲田見学に行きません?」
私は不意に口に入れた紅茶を派手に噴き出してしまった。隣にいた会社員らしき若い男性客が驚いてこちらを見た。
「そ、そんなことしたら、『店外デート』になっちゃうでしょう?」
私はナプキンで口元を拭きながら、咳き込んだ。思わずみなさんは笑った。
「そんなんじゃないですよ。私まだ早稲田大学って行ったことなくて、一度本物のキャンパスを見てみたいんです」
「そ、それならいいですけど……」
じゃあ、いつにする? と訊いて、土曜日以外ならいつでも、と答えた。
「じゃあ、今度の木曜日、いいですか?」
私は承諾した。そしてこう付け加えた。
「春のD判定は、おおいに希望があります。ほんとに夏の過ごし方次第ですよ」
その木曜日、私とみなさんは二人で上りの東海道線に乗った。辻堂駅の改札口で待ち合わせて、出かけたのだ。そういえば、私はみなさんがどこの人なのかまだ知らない。
「家は藤沢の鵠沼にあるんですよ」
初夏の電車内はすでにクーラーがよく効いていて、ボックス席に座った私達はとりとめもないことを話し合った。私はその時、クリスマスはどう過ごすのか、と訊いた。
「彼氏とデートとか?」
「デートなんかしません」
みなさんは車窓の景色を見ながら答えた。
「女友達と二人で映画を観に行きます」
「そうなんだ」
私は意外だった。こんな可愛い子だから、彼氏の一人や二人いてもおかしくないと思ったのだ。
品川で山手線に乗り換え、渋谷方面を目指した。高田馬場に着くと、ここが早稲田の最寄り駅ですよ、と告げた。
発射音の鉄腕アトムの歌を聴きながら、人の多い階段を降り、改札を出た。丁度早大構内行のバスが停車していたので、私達はそれに乗った。
「有馬さんは早稲田大学、見に行ったことあるんですか?」
そう訊かれて、まだ学習院の学生だった頃、何度か訪れたと言った。
バスが発車して、十五分程街中を走ると、終点の早大構内に乗り入れた。
バスの窓からは、大隈講堂が見えた。実際にキャンパスに降り立ってみると、その堂々たる甍は言葉を失わせるものがあった。高い時計塔、入り口のアーチ、その上の飾り窓。東大安田講堂、慶応大学図書館と並ぶ、近代の名建築だった。みなさんは言葉もなく見上げている。
「講演会や、入学式で使うみたいだけどね」
私達は構内に入っていった。程なくして、大隈重信の銅像が見えた。高い位置にあり、行き来している早大生を見守るかのように佇んでいる。
「この人が創立者なんですよね」
「そうだよ」
みなさんは瞬きすら忘れたように、眼前の光景を見つめている。大隈公の像の左右には、風格のある校舎が並び、キャンパス内は名状しがたい活気に満ちていた。次々と繰り広げられる早稲田の風景に、私達は言葉もなく圧倒されていた。
「みなさんも早大生になれたら、ここの一員になれるんだよ」
みなさんは喜びとも憧れともつかない陽気な顔で、湯島聖堂に参拝する受験生のような厳粛さで構内を見ていた。
「やっぱり雰囲気あっていいなあ……」
私達はひとしきりキャンパス内を歩いた。どの校舎がどの学部かまではわからなかったが、それでも入学したらこんな所で学べるのだと思うと、胸を高鳴らせるには十分だった。
「ねえ、学食でお昼食べません?」
「学食ねえ、どこにあるんだろう」
私も同意して、私達は学食を探した。やっとの思いで大隈ガーデンハウスを見つけると、三階で提供されているという大隈定食を食べた。鯖の塩焼きと、から揚げ二つと、ご飯にお味噌汁、惣菜一品がついて五百円という価格だった。私は学習院にいた時も、学食を女の子と食べたことなど無かった。その私がこんな形で女性と食事が出来るとは、なんというめぐり合わせだろう。
食後、私達は大隈庭園を訪れた。芝生が一面に敷かれ、遠くに木立の見える庭は、都心とは思えない学生達の楽園らしかった。
「ねえ、みなさん、あなたも合格したら、ここで彼氏とデートしたり、友達と寛いだり出来るんだから」
みなさんは微笑んだ。私達は手をつなぐことこそなかったが、それでも私は幸せだった。
その時だった。
私は何者かに右腕を掴まれた。驚いて振り返ると、警察官が二人、私を見ていた。
「あの、すいません、ちょっといいですか……」
一人は若い巡査風で、一人は年季の入ったベテランの警官らしかった。私は仰天して、「なにか?」と訊いた。
「ちょっとね、職務質問したいんですけど……」
私はみなさんと顔を見合わせた。それでも、やましいことは何もなかったので、私は驚きつつも、はい、どうぞと答えた。
「お荷物拝見していいですか?」
「はい……」
私は背負っていた鞄を見せた。警察官は二人でその中を検分し始めた。といっても、ノートに筆記用具以外、なにも入っていない。しいて言えば、私のメディカルポーチを見つけて中を見て、病院の診察券やら、通院医療費公費負担制度の台帳やら、障害者手帳やらを見つけた時には、「患者さん?」と訊いてきた。私はそうだと答えた。そばで見ていたみなさんはそれを初めて見る。
「お仕事は?」
「無職です」
さらに警官は「両手を挙げて」と言った。私が言うとおりにすると、脇の下から足元まで探って、身体検査をした。ナイフを持っていると思われたのだろう。
「はい、いいです。ご協力ありがとうございました」
警察官は揃って背中を見せて立ち去って行った。警視庁の文字が見える。
職務質問をされたせいで、私の素性はすっかりみなさんにわかってしまった。
「有馬さん、病気なんですか?」
私はそうだと答えた。
「もう十五年以上ずっと。今は地元の病院に通院してる」
「発作とか、起きるんですか?」
「いや、ほとんどそれはない」
「今日も、ひょっとして随分無理してここまで来たとか?」
それは嘘ではなかった。私の普段の行動半径はせいぜい十数キロだ。今日はみなさんのために特別に頑張った。
「まあ、そうなんだけど……」
それから私達は二人で帰路についた。バスで高田馬場駅まで戻り、再び山手線に乗って、品川駅に行った。帰りの電車の車中、みなさんはスマホで撮影した早稲田大学の写真を見ている様子だった。
私は密かに驚いていた。いつも通りの一日で、いつも通りの服装で、それでも私は警官に呼び止められるようなことになったのだ。私は余程、不審者と思われる風体をしていたに違いない。
「学習院で彼女が出来なかったのも、もっともかもしれないな」
私は向かいのみなさんの顔を見ながら、そんな風に考えた。
四
夏が終わった。七月、八月の間は週に一回、西口のデニーズで待ち合わせて、私は夏の間の勉強の進み具合と、各科目の疑問点について、みなさんと話し合った。みなさんはなんとか八月の上旬にビジュアル英文解釈のⅡまでを終え、文法知識や単語・熟語の語彙も増えた。国語は私の勧めた通り、河合塾の古文と漢文の基礎から標準の問題集を終え、日本史は三回目の教科書通読と、Z会の問題集を終えつつあった。
「九月には、いよいよ第二回目の駿台全国模試があるから」
私はいつも通りミルクティーを飲みながら、秋の模試受験計画を話した。みなさんは神妙な顔でそれを聞いている。
そんなことが何回かあり、いよいよ模試の前日となった、十月のある日、いつものようにデニーズで話していると、みなさんのスマホが鳴った。みなさんが出ると、どうやら親しい人からの電話らしい。
「え……、今? ちょっと用事があって……、うん……、うん……、じゃあ、バイバイ」
私はティーカップを置くと、テーブルの上のノートから目を上げて、みなさんを見た。五か月経って、もうノートは半分程が、メモや、スケジュールや、参考書・問題集リストで埋まっていた。
「誰? 彼氏?」
「彼氏なんかいないから」
みなさんはアイスティーを一口飲んだ。
その時だった。店の入り口から、一人の、年の頃は二十歳前後とおぼしき青年が、私達の座っている席へと歩み寄って来た。いらっしゃいませ、何名様ですか、そう訊いた店員を無視した。高い鼻に掘りの深い顔立ち、よく日に焼けている。
「あんた、いつも由香ちゃんに何の用?」
「はあ!?」
その時、私はみなさんの本名が由香さんであると初めて知った。
「ちょっと、繁人、なんでここに……」
みなさんは慌てて私を睨みつけている繁人と呼ばれた青年を制した。
「おかしいと思っていたんだ。あんた由香ちゃんのなんなんだよ?」
「やめて、繁人。この人は、勉強教わってるだけ」
みなさんは声を震わせて必死に言明している。この青年はみなさんの、いや、由香さんの彼氏なのか。
「あの、何を勘違いしているのかわかりませんけど、私は有馬といって、みなさんとは、いえ、由香さんとはたまたま街で知り合ってですね、で、みなさん、いや、由香さんが大学に行きたいと言うから、こうして相談に……」
「もう由香ちゃんに近寄るな!」
繁人と呼ばれた青年は左右の席の客が振り向くような声で言った。
「繁人、だからあたし達はそんな関係じゃ……」
「行くぞ! 由香ちゃん」
みなさんは、いや、由香さんはうろたえながら私と繁人の顔を交互に見て、やがて荷物を手にすると目を伏せてその繁人という青年について行き、店を出た。
その夜、由香さんからメールがあった。
今日はすみません。あの繁人君とは高校以来の付き合いで、私の元彼です。
メールにはそうあった。高校卒業後は東京の大学に通い、来年二年生になるという。
やはりこうなるのだな。私は思った。あれだけ可愛い子だ。恋人の一人や二人いたっておかしくない。私はもうデニーズでは会えないのか? とメールした。
ごめんなさい、当分会えません。そう返事があった。
そして十月。第二回目の模試の当日の夕方、メールがあった。
家に帰って自己採点してみますけど、手ごたえありました。多分B判定とれると思います。メールにそうあった。
やがて十月下旬のある日、どうしたわけか、またデニーズで会いましょうとメールがあった。
昼から雨が降り出した、暗い日だった。私はいつもの席に座り、眼下の通りを歩く人の傘を見るともなしに見ていた。みなさん、いや、由香さんが現れた。
「今日はホットティーにします?」
はい、という返事だったので、私は二人分のミルクティーを注文した。
「で、模試は?」
私がそう訊くと、由香さんはプリントした成績表を広げた。偏差値は英語六十五、国語六十三、日本史六十七で、早稲田大学はB判定だった。
「これはいい。あとは本番まで勉強量を増やして、続ければ早稲田行けますよ」
私は嬉しくなって、運ばれてきたミルクティーに砂糖を入れた。
由香さんは湯気を立てるティーカップをしばし見つめていた。やがて、意を決したように切り出した。
「繁人とは、その、そういう関係があって……」
私は驚かなかった。大方、予想していた展開だ。
「構いませんよ。私、別に由香さんとそういう風になりたくてこの受験指導してる訳じゃないし……」
重い沈黙が座を領した。覚悟していたことだった。しかし、だからとはいえ、こうもあっけなく真実が露呈するとは思わなかった。
あの繁人という青年は、今日ここで私と由香さんが会っていることを知っているのだろうか。
「あの……」
「はい……」
由香さんはミルクティーを一口飲んで、私のほうを見た。
「あの、繁人さん……」
「野村繁人ですね」
「野村さんというのね……」
私は意を決した。こういうことは、早めに訊いておいたほうがいい。
「野村さんは私のことをなんと……」
「はい?」
「ですから、私のようなですね、こんな精神障害者が由香さんにまとわりついていることを、なんと言っていますか?」
「せ、精神障害者だなんて……」
由香さんはティーカップを置いた。
「繁人とは、もう関係ないですし……」
「でも、あの日のやりとりだと……」
私はあの野村という男のみなさんへの態度が強く印象に残っていた。由香さんとは強い絆で結ばれているのが傍目にもよくわかった。自分のような「異分子」が入り込む余地など無いではないか。そこまで考えて、私はふと齟齬を感じた。待てよ、自分はそもそも由香さんに何を求めているのだ。由香さんにはただ勉強を教えているだけ。いわば生徒と教師だ。それ以上でもそれ以下でもない。
「その、ね、野村さんが私のことを『変な虫がついた』みたいに思っているとしたら……」
「そんなことはありません」
由香さんは次第に湯気を失っていくティーカップを前に、いつになく毅然とした態度で言った。
「繁人とはほんとに、もう何もないんです。有馬さんが気にすることではないですよ」
それを聞いて、私は心のどこかで野村繁人への敗北感を感じながら、そこまで言うならと、由香さんに向き直った。
「それならいいんです。では勉強を続けましょう」
そう言いつつも、私はやはり決して心地よいとは言えない感情が湧いてくるのを感じた。あの野村繁人は自分などよりもはるかにイケメンだし、背も高い。誰がどう見ても、由香さんとはお似合いだ。私は所詮、由香さんとは途轍もない距離のある人間なのだ。そんな風に考えていた。
「いよいよ秋です。夏の成果を確認したら、実戦力養成をしないといけません。これからは過去問と、問題集を解きまくって、どんどん場慣れを作っていきましょう」
「はい」
由香さんは相変わらず勉強になると真面目だった。その日、私達は再び一緒に北口の有隣堂へ行き、秋冬にこなすのにふさわしい問題集を数冊買った。
「もうしばらくすると……」
私は書店の参考書コーナーを見渡しながら言った。
「願書が販売されます。早稲田の願書を買っておいて下さい。ああそうだ、調査書が必要になります。高校に連絡して、年内には揃えておいたほうがいいですね。由香さん、早稲田以外はどこか受けます? 滑り止めとか……」
「滑り止めは受けません」
由香さんは直ちに答えた。
「早稲田一本、ですか?」
「そうです」
それを聞いて、改めて自分が由香さんに大学受験を勧めたのは間違いではなかったと思った。何よりも若さと情熱がある。こういう人にこそ、早稲田はふさわしい。
帰り際、改札口まで由香さんを送りに行った。
「野村さんとは」
私は突然思い出して、言った。
「別に付き合ってもいいですよ。前にも言いましたけど、私別に由香さんとそういう関係になりたくて、この進路勧めたわけじゃないですから」
「そんな……」
由香さんは言葉も無く改札で私を見た。すでに人が溢れ始めた夕方の改札口で、私達は川の中に立つように、人群れの流れを感じていた。
「ていく、いっと、いーじー!」
人混みの中でその言葉が聞こえたかどうか、由香さんは私をしばし見ていた。
「どういう意味ですか? 」
私は声を張り上げた。由香さんは咄嗟に上目遣いになると、こう答えた。
「気楽にやれよ! です」
「はい、合格!」
そのまま私達は別れた。私は由香さんに手を振った。由香さんも私に手を振り返した。
これでいいのだ。私達は所詮違う世界の人間だ。今更何を気にしている。野村繁人だって、本当はああいうイケメンが、由香さんにはふさわしいのだ。私はそう考えていた。そうして私は、その年のクリスマスを迎えた。
その日、父はいつものように朝から家を空けていた。一人の私はなにとはなしに家の中にいた。一階の居間で執筆していると、スマホにメールが届いた。由香さんだ。
こんにちは。今日空いてます? そうあったので、今日はずっと家にいると送った。
家、お邪魔していいですか? そう訊かれたので、由香さんさえよければどうぞ、と返した。昼頃、近所の蕎麦屋に鴨南蛮そばを注文し、食べ終えて食器を洗い、玄関に置いていると、スマホが鳴った。
「もしもし、由香です。今近くまで来てるんですけど……」
私は今そこから何が見えるかと訊いて、内科医院と調剤薬局が見えますと言われた。
「ああ、じゃあ、その信号を渡って、お豆腐屋さんが見えるでしょ。そこの前を通って、二叉路を左に歩いて、T字路を左、と教えた。五分程で玄関のチャイムが鳴った。引き戸を開けると、由香さんがいた。
手短に挨拶を済ませると、丁度午後の一時半ごろだったので、紅茶でも淹れましょうと言ってケトルでお湯を沸かし始めた。由香さんがこの家に来るのは、初めてデリヘルの客として呼んで以来、二度目だ。
「寒かったでしょう?」
私は冷蔵庫にあったスコーンを電子レンジにかけ、ココット皿にストロベリージャムとクロテッドクリームを盛りつけた。
それから私達は二人で紅茶を飲んだ。
「今日はどうしたの? 何か用?」
「クリスマス、どうしてるかなと思って」
そういえば、以前クリスマスは女友達と映画を観て過ごすのだと聞いたのを思い出した。
「映画は? 友達いないの?」
「急にバイトが入っちゃって」
一緒にスコーンを食べた。由香さんはスコーンを食べるのは初めてだと言った。二つに割って、クリームとジャムをつけて食べるのだと教えた。
「おいしいですね」
「ベノアのスコーンだから、味いいでしょ?」
その後、紅茶を飲みながら、繁人という元彼とはどうかと訊いた。
「繁人とは、その……」
由香さんが言葉に詰まったので、言いたくないなら無理にとはいわないと伝えた。
「話したくないこともあるでしょう」
由香さんはふと笑みを浮かべると、そうそうと言って鞄から書類を取り出した。
「一緒に願書、書いてもらおうと思って」
それは早稲田の願書だった。書店かどこかで買ってきたのだろう。了承した旨を言うと、早速ティーカップを横に置き、書類を並べた。
「記入例に従って書いていけばいいよ」
初めてのことで、きっと緊張しているのだろう。由香さんがボールペンで一通り書いた後、私はそれをチェックした。
「うん、大丈夫。検定料はなんとかなった?」
「はい」
由香さんは貯金から料金を引き出して払うつもりらしかった。学部は文学部一択だと言った。
こういう時は、いい息抜きだ。なにか世間話でもと思い、最近の生活はどうかと訊こうとした時、玄関のチャイムが鳴った。
「ちょっと待ってて」
私は居間を出ると、玄関の引き戸を開けた。
「あのさー、向かいの水島だけど……」
水島さんだ。長いこと鉄道会社に勤めていて、運転士をしていたという。今は退職して、車を洗ったり、庭の芝生を刈ったりしているのをよく見かける。
「何か?」
やや突き出た腹をして、禿げた頭をしたその水島さんは、細いがよく眼力の効く目で私を睨みつけた。
「あのさー、もうこういうのやめてくんない?」
「はい?」
私は訳がわからなかった。一体私が何をしたというのだろう。
「私が何か?……」
私が戸惑っていると、水島さんはタバコの匂いのする口で、続けた。
「昼日中から女連れ込んでさあ、何やってんのかわからないわけないじゃん」
一体この人は何を言っているのだろう。私はますますわからなくなった。
「見て、知ってんだよ。この前も女来たでしょ?」
この春に、由香さんを呼んだ時のことを言っているのだ。
「立派な風俗擾乱だよ、あんたのしてること」
「あのー、私は……」
水島さんは玄関の女物の靴を目ざとく見つけると、射るような視線を向けた。
「風紀が乱れるだろう」
「わ、私はなにもやましいことは……」
誤解されているようだ。確かに初めはそういう目的で呼んだ女性だが、今はそんなことはしていない。
水島さんは相変わらず厳しい視線で私を見ている。私は言葉に窮していた。
「有馬さん、どうかしたの?」
ふと、居間のほうから由香さんがドアを開けた。水島さんがまじまじと彼女を見た。
「あんた、この男に呼ばれたんだろう?」
「違います」
由香さんの思わぬ返答に、私は由香さんと水島さんの顔を交互に見た。
「じゃあ、あんたらどういう関係なんだよ?」
水島さんはさも胡散臭そうに私達に視線を向けている。
「彼氏と彼女です」
「え!?」
私は思わず驚いて、由香さんの言葉を聞いた。由香さんの口から最も予想しなかった言葉が出てきたことで、私は一体そんなことを言ってしまっていいものかと戸惑った。
「クリスマスを二人で過ごしてるんです。何か問題でも?」
水島さんは苦々しい眼で私達を見ていたが、やがて「わかったよ」と言い捨てて玄関から消えた。私はドアを閉めた。
「ありがとう、由香さん」
由香さんはなんでもないという風にフフッと笑うと、居間に戻っていった。
「由香さん、早稲田に入ったらサークルとか入りたい?」
私は居間のテーブルに座りながら、何気なく水を向けた。
「ダンスサークルとか入りたい」
「ダンス?」
いかにも今時の若い人らしい。私は微笑ましくなって、そんな未来になった由香さんのことが眩しくて、いいなあ、と言った。
「バイトとかは?」
「カフェで働きたい」
女子大生の典型だな。私はそんな風に思って、こんな子に給仕されたらさぞ幸せだろうと由香さんを見た。ポニーテールは紅茶を飲みながら微笑んでいる。
「ねえ、由香さん」
私はふと真面目になった。由香さんはティーカップを置いた。
「この入試、正直、由香さんがここまでやってくれるとは思わなかったんだ」
「急にどうしたの?」
私は由香さんの可愛らしい眼を見ていた。
「私も受験生の時は随分勉強したんだけど、あのね、私本当は東大行きたくて、それで勉強してたんだけど、でも結局無理で、早慶も引っかからなくて、それで仕方なく別の大学に行ったんだ」
「そうなんだ」
由香さんは紅茶を一口飲んだ。由香さんは相変わらず美しかった。傍で見ていると、こちらまで幸せになる思いだった。こんな子が本当に彼女だったら、それこそ最高だろう。
「だからね、由香さん、由香さんには私の分まで幸せになって欲しいんだ」
なにやら意味深なことを言ってしまったと自分で思う。由香さんは少しだけ真剣に私のほうを見た。
「私、もうこんな年だから、今更大学に戻ってキャンパスライフを、なんて無理でしょう? だからその代わりに、由香さんには思いっきり大学生活を謳歌して欲しいな」
「どうしたの、急に改まって」
私は何も言わず由香さんの眼を見て、そのキラキラした瞳に嬉しくなった。
「年が明けたら、間もなく本番だよ」
私は少しだけ真面目になった。
「もう各科目ともほぼ完成しているから、あとは過去問を繰り返し解いて……」
由香さんが真剣になるのがわかった。
「大丈夫。由香さんなら出来るから」
私達はしばし二人で見つめ合った。お互いの瞳を見て、私はここまで澄んだ眼をしているかと思った。
「あ、そうだ」
私はふと隣の和室へ行くと、ライティングビューローの引き出しから小さな紙袋を取り出した。
「これ……」
由香さんはなに? と言って開けていい? と訊いた。いいよと私は答えた。
「御守り?」
それは鶴岡八幡宮で買ってきた合格御守りだった。由香さんのために、わざわざ鎌倉まで行って買ってきていたのだ。丁度今日が渡すいいタイミングになった。
「ありがとう」
由香さんは嬉しそうに御守りを手にしていた。一途にそれを見つめる眼がまた可愛い。
「本番、頑張って」
私は静かに由香さんの顔を見た。やんわりした顔立ちにも、意志の強さを感じるものがあった。
「あたし、絶対合格する……」
由香さんなら出来るよ。私がそう言うと、由香さんは今まで本当にありがとうと述べた。
「これくらい、なんでもないよ」私はそう答えた。
五
二月十七日、早稲田大学文学部の入試当日、由香さんからメールがあった。
「あたし、絶対合格します。頑張ります」
私は平常心で、と返した。大丈夫、今までの蓄積を全て出し切れば十分合格可能だから、と。
一科目目が始まる頃、私はこの春からの一年を思い返していた。春の出会い、それから始まった受験勉強、最初の模試、夏の勉強、秋の模試、そして冬の追い込み。
全てが、まるで声の無い映画でも見るように心の中で繰り広げられていった。
ビジュアル英文解釈、頑張ってくれよ、英文法頻出問題演習、役に立ってくれ、速読英単語、頼りにしてる、詳説日本史ノート、おかげで知識が身に着いた、得点奪取古文、漢文、なんとか戦えるようになった、現代文のトレーニング、いまこそこれで鍛えた力で合格ラインを超えるんだ。
十時からの英語の試験が終わった十一時半ごろ、由香さんからメールがあった。
結構ボロボロかも知れません。正直自信ないです。でも一応お昼食べます。
私は、恐らく今年度は難化したかもしれないから、とにかく次の試験に向けて気持ちを切り替えて、と返信した。
大丈夫、由香さんなら出来るから。そう返しながら、なんとか六割は超えてくれと願っていた。
一時になって、午後の試験が始まった。国語だ。私は予め、国語は漢文、古文、現代文の順で解くのだと教えてあったから、最初の漢文で躓かなければいいなと思っていた。
二時半過ぎ、再びメールがあった。
国語、いけました。手ごたえありました。
私はすぐに返信した。
油断しないように。最後の日本史、頑張って。
最後の科目の時間、三時半になった。この一時間で全てが終わる。
五時頃、その日最後のメールがあった。
日本史、なんかバラバラでした。取れてる気しません。でもやるだけやりました。
私はお疲れ様、とだけ返信した。これでいいのだ。由香さんはやるだけやった。あとは結果を待つだけだ。
それから九日後の発表まで、由香さんから連絡は無かった。私は自分からメールするのも変だし、なにか不自然な気がして、あえて何も言わなかった。きっと疲れが出たのだろう。発表に向けて、今のうちに休んでおいたほうがいい。そう思って、そっとしておいた。
そして二月二十六日、由香さんからメールがあった。
「由香です。やりました。合格です」
やった。合格だ。私は今までの私と由香さんの努力が報われたと知って、一人、部屋で合格の報を噛みしめていた。
これで由香さんは早大生になれた。楽しい青春が待っている。キラキラのキャンパスで、新しい仲間たちと出会い、新しい生活を始め、新しい人生を生きる。由香さんの喜ばしい出発だ。
「おめでとう! 由香さん。やりましたね」
そう返しながら、私は気がつくと泣いていた。由香さんの合格が、我がことのように嬉しかったのだ。自分のボロボロの青春が、由香さんの夢によって生きなおされる、そんな思いがした。
その翌日、いつものように、辻堂駅西口のデニーズで私達は待ち合わせた。三時になって、由香さんが現れると、私は二人分のロイヤルミルクティーを注文した。
「おめでとう、由香さん」
由香さんは恥ずかしそうに俯くと、それでもこの一年とは全くと言っていいほど違う顔を私に向けた。
「ありがとうございます」
それから私達は何を語り合ったろう。将来の夢、バイトのこと、サークルのこと、新しい学校での授業のこと、新しく出来る友達のこと……。
「ジッド、出来ますね」
「はい……」
「好きな作家なんでしょう?」
「そうです」
「入学の準備、しっかりね」
「はい」
私はロイヤルミルクティーを飲んだ。ファミレスの紅茶が、まるで銀座の風月堂のアフタヌーンティーのように美味しかった。
「あの……」
由香さんが何か言いかけたので、私は「はい」と答えた。
「繁人、なんですけど……」
「ええ……」
「やり直そうと思って……」
「そ、そうですか……」
覚悟はしていた。いつかこういう時が来るのだと思ってはいた。
「うまくいくといいですね」
由香さんはふと私を見た。微かな喜びが、その笑顔に宿っていた。
「あの……」
「はい」
由香さんはロイヤルミルクティーを一口飲んだ。
「今まで、本当にありがとうございました」
「いえ……」
私は謙遜して、思わず眼を伏せた。
「繁人のこと、その、気にしないで下さいね」
「え!?」
私は意外だった。野村繁人のことを気にかけているというそぶりを、私が見せたのだろうか。
「いえいえ、由香さんの大事な彼氏ですから」
私はなんとか言葉を探して、取り繕った。
「また一緒にデートとか、出来るといいですね」
「はい……」
私は早大生になった由香さんが、野村繁人と楽し気にデートしている光景を思い浮かべた。それはまぎれもなく健全な青春の風景だった。そしてそれは私とは縁の無いものだった。生涯、縁の無いものだった。
「若くても、美しくなければなんにもならないし、美しくても、若くなければなんにもならない」
「え!?」
由香さんは会話を踏み外したというように、私の顔を見た。
「フランスの偉い人の言葉です」
私はロイヤルミルクティーを飲んだ。
「美と若さは、併せ持ってこそ意義がある……」
隣の席に、三人の女子高生が座った。銘々楽しそうに会話を交わし、メニューを選んでいる。私はそんな様子を見るともなしに見た。
「若いって、いいですね」
由香さんは、ふと私を見た。
「ねえ、由香さん、私はもう青春とか、若い人の愉しみとか、そういうものとは縁の無い人間になりました。それでも、いえ、だからこそ、由香さんに覚えておいて欲しいことがあります」
「はい……」
私はティーカップをソーサーに置くと、続けた。
「青春って、選ばれた人にしかないんです」
「選ばれた人……」
由香さんはその大きな眼をして、手にしたティーカップを見つめた。
「そう。選ばれた人。野村繁人さんや、由香さんみたいな、イケメンで、可愛い人、そんな人だけが、青春を楽しめるんです」
由香さんはいつになく真面目な顔になった。
「仲間を作ったり、友達を増やしたり、恋愛したり、勉強を頑張ったり、バイトしたり、いろいろあると思うんですけど、そういうのって、誰もが出来るわけじゃないんですよ」
「……」
私は隣の女子高生を見やりつつ、続けた。
「若くて、美しい人だけが出来ること……。それが青春なんです」
「でも、有馬さんは……」
そう言われて、私は由香さんのほうを向いた。真っ直ぐな眼が、私を見ていた。
「私にその青春への、プラチナチケットをくれました」
私は不意に愉快になった。私は確かに由香さんの人生を変えられたのだ。
「まあ、だってそれは……」
私は水を一口飲んだ。
「私が持ってても、なんにもなりませんから」
そう言って、私は笑った。由香さんは笑わなかった。ただ真面目な顔で、私を見ていた。
「ねえ、由香さん」
「はい」
由香さんはロイヤルミルクティーを一口飲むと、じっと聞いていた。
「由香さんもいつかは結婚して、子供を作りますよね?」
由香さんはそれは遠い将来のことと言うように、遠い眼をした。
「お子さんには、きちんとした教育を与えてやって下さい」
「きちんとした、教育……」
その言葉を反芻しながら、由香さんは噛みしめていた。
「そう。例えば中学校だったら、私立の、穏やかで、家庭的な校風の学校。そんなところで、大切なお子さんを育てて欲しいな……」
私はふと、自身の少年時代を思い返していた。虐め、暴力、荒廃、孤独……。そんなものを味わうのは、自分が最後でいい。
「由香さんも」
私は続けた。
「大事な息子や娘が出来たら、やはり大事に育てて欲しい。だってそれは、子供への誠意だから。親としての、子供への誠意だから。親の誠意の賜物、それが教育です」
「親の誠意の賜物……」
「あははー! ちょーイケてる! ねえ、今度あたしに見せて!」
不意に、隣の女子高生が声を上げた。なにかスマホで写真でも見せ合っているようだ。
「ねえ、有馬さん」
「何か?」
由香さんはテーブルの上のティーカップとコップをさっと見ると、こう切り出した。
「有馬さんは彼女とか、いたことあるでしょ?」
思わず声を出して笑ってしまった。
「私は彼女なんて、いたことないですよ」
由香さんは信じられないという顔をして私を見た。私は水を一口飲んだ。
「なんでそんなこと訊くんですか?」
「いや、その……、有馬さんもやっぱり、女の子のこととか、好きになったりするのかなって……」
「それは……、ね……」
もはや仕方のないことだ。そんなこと、もうどうにもならない。
「愛の無い青春」
由香さんが、えっと声を上げた。
「そういう青春を生きる人間もいるんですよ」
私は隣の女子高生達を、相変わらず横目で見ていた。楽しそうにスマホを見せ合っている。
スマホが鳴った。ごめんなさいといって由香さんが出た。
「あ、繁人? うん……、うん……、わかった。じゃあね」
由香さんはスマホをバッグにしまった。
「繁人さん、ですね?」
「はい」
「やり直せそうですか?」
「だといいなと思います」
「幸せになってくださいね」
「え!?」
やや重すぎる言葉だったのか、由香さんは驚いて私を見た。
「素敵な彼氏だ」
それを聞いて、少しばつの悪そうな笑みを浮かべると、由香さんは改めて私を見た。
「早稲田、楽しんで下さい」
私はそれきり、何も言わなかった。午後のデニーズでのひと時が過ぎゆく。由香さんは繁人からの電話のあったスマホを、愛おしそうに眺めていた。
六
また、春がやってきた。
風は薫り、空は高く、桜は今年も花開いた。
由香さんからのメールは、四月の初めは数日おきに来たが、やがて、向こうからは来なくなった。
デリヘルを呼ぶことは、無くなった。たまに冷やかしでスマホで地元のデリヘルのホームページを見たりする。でも今の私はデリヘルで使うお金があるなら、CDを買おうと思うようになっていた。
父は相変わらず、朝に家を出て、夜まで母の実家で過ごすという生活だ。
四月の終わりに、その年の一月に応募していた新人賞の一次選考通過発表があった。私はなんとか一次は通っていた。学習院時代に縁のあった哲学教授にそれを伝えると、彼は喜んでくれた。
まだほんの入り口だけれど、一次選考に通ったことで、私は少しだけ自分に自信が持てた。そして純文学の賞にも応募してみようと思い、新たな作品を執筆する毎日だ。
内科、精神科と、相変わらず私は病院に通っている。その通院の合間に、移動のタクシーの窓から楽しそうに街を歩く若い学生達が見えたりする。そんな時は、輝いている彼らがうらやましいと思う。本当に、そう思う。
由香さんと繁人とは、やり直せたのだろうか。だったらいいなあと思う。
家で執筆の合間に、スマホで色々な曲を聴いた。その中に、死んだ後の自分は風になって、大空を吹きわたっている、という主旨の歌詞の歌があった。
いい歌だ、と思った。
私も、そう、風になりたい。
ああ、神よ、願わくば、私を風にしたまえ。風になって、千里を駆け、由香さんのいる所で、見守っていたい。光になって、鳥になって、星になって、由香さんを見守っていたい。たとえ今は他の男のものになっていようとも。
私はそれでもいい。ただ、透明で、無垢で、新しい風になって、私は愛する人を、見守っていたい。
【優秀賞】蒼白の天使(西村修子)
今朝、ねえさんの顔は緑色だ。海草だか蓬だかをパックにして顔中に貼りつけて眠ったのだ。きれいに洗い流したはずなのに、皮膚に緑色が沁み込んでいる。
僕はスタッフだけど、たまにお呼びがかかると舞台にも上がっている。だから芸名が必要かな、と首を捻っていると、
「デデにしなさいよ、あたし好きなの、デデって名前が」
過去にデデなどというヒモでもいたのかと勘繰ったのだが、スカーレットねえさんは単にダダイズムという言葉が好きなので、ちょっと可愛くデデなのだそうだ。
裏口から芳ばしい匂いが侵入してくる。作造爺さんが七輪を起こして好物のホルモンを焼いているのだ。爺さんは地面に胡坐をかいて焼酎の小瓶を開け、ラッパ飲みをするのだが、瓶の中身はなかなか減らない。爺さんは口の中でセーブして少量ずつを飲み下すように操作しているのだ。
「秋の彼岸以外は、モツ焼きじゃな、わしの人生」
脂の滴るホルモン焼きを割箸でつまみ、大きく開いた口に放り込む時の爺さんの表情ときたら、喜ばしいというか、幸せ者というか、実にいい味を出している。爺さんは春の彼岸はともあれ、秋には精進料理で一日過ごすと言い、「彼岸」とはあの世のことで、人間だれしも一度は彼岸に行く、但し二度と帰って来ることはできないなどと僕をつかまえて講釈を垂れた。
アルバイト要員はいつも二人と決まっているようで、エイくんは客引き、ビイくんは劇場の雑用係を担当している。エイもビイも本来学生だったり、失業中だったりで、生活の合間を繋ぐバイト感覚の連中だった。だからエイやビイは頻繁に人員交代していた。
唯一のスターはスカーレットねえさんなのだが、出演者自体がスカーレットねえさんしかいないのだ。
「華麗なるスカーレット嬢、見なきゃ損です、お客さま、どうぞ」
まだ陽の高いうちにエイくんが声を張り上げる。
劇場内の照明がフェイドアウトしていく。僕は照明と音響の係も担当しているのだ。
最初だけスカーレットねえさんに手ほどきしてもらったが、今は何の問題もなく仕事を進めることができるようになった。筋がいいとねえさんからも褒められたのだ。劇場にはオーナーらしき男がいるはずなのだが、僕は顔を見たことがない。常時仕事に専念しているのは、看板スターのスカーレットねえさんと下足番の作造爺さん、それに僕の三人だけだ。あとはアルバイト要員がちょろちょろしているぐらいだ。
ステージに看板スターのスカーレットねえさんのシルエットが浮かび上がる。漣のようにゆったりとした腰の動きだ。中央に陣取っているピンクの椅子に、ねえさんはそろりと座り込む。観客席には妙な静寂と熱気のような体温が充満しているのだ。僕はねえさんの下半身に焦点を当てて、カラフルに照明を操作する。椅子の回りに目をやると、大小さまざまなバナナの実が散乱しているのだ。スカーレットねえさんは、思わせぶりに一本ずつ拾い上げ、バナナに頬ずりをする。かなりの時間をかけて、ようやく一番大きいバナナを手にするのだった。煽情的なねえさんの演技力もさることながら、僕はむしろお客の方に関心がある。観客は嬉々とした表情の中年男や、三白眼で口をあんぐり開けている生っちろい痩せぎすの男、勝手にズボンのベルトを緩め始める若造や、罰あたりな寺の住職などが、スカーレットねえさんの間近までにじり寄って来るのだ。一応はロープを張ってスターのねえさんの身を守ってはいるが、なぜか観客のお行儀は良くて、ねえさんに手を触れることはないのだった。
スカーレットねえさんのひとり芝居で、クライマックスの刺激的なシーンが展開されている。客席は呼吸を止めたみたいに静まり返っている。
僕はスカーレットねえさんの一部だったバナナが、半分になって床にポトリと落ちるのを見つめていた。ねえさんは客席に向かってにこやかにお辞儀をし、いつものように両手を広げてスターとしての挨拶をするのだ。それから、やんやの拍手が会場を埋め尽くすのを、僕は照明係であることを忘れて眺めていた。幕が下りれば、熱演したスカーレットねえさんの落としたバナナを拾い上げに行かなければならない。舞台をきれいに雑巾がけして本日の仕事は終了するのだ。
きょうのスカーレットねえさんはやたらテンションが高くて、大小さまざまのバナナがあちらこちらに散在していた。粘着力のあるバナナがステージの上にくっついて、雑巾がけに時間がかかる。僕はひとり何役もこなしているので、大忙しなのだ。
「ビイくん、ステージ手伝ってよ」
「あのう」
エイくんが代わりに返事をする。
「ビイくんはさっき辞めるからと、帰って行きました」
「そうなの、じゃエイくんでもいいから手伝ってくれない」
「困ります、僕は単なる客引きということで雇われているので」
どうせエイも長く勤める気なんかないのだ。こんどやって来るエイとビイにはステージの後片付け業務を付与する必要がある。
僕は茶色に変色していくバナナをスピードを上げて拭き取った。
楽屋に戻ると、スカーレットねえさんは派手なバスタオルを体に巻きつける。それからファンから差し入れの豚の角煮を親指と人差し指でつまんで口に放り込み、化け猫みたいに指についた脂を舐めた。
「愛は永遠ね」
スカーレットねえさんがソバージュの髪を揺らして笑った。ひと息ついた時のねえさんの口癖だ。歯に付着した赤い口紅が虫喰い歯に見える。唇は豚の脂身で鈍く光っているのだ。僕はだんだん体が麻痺して、頭が痺れてくる。愛なんて説明できるものじゃない。ねえさんはもう戻れないのだろうか。そうではない。僕が戻れないのだ。そしていつも虚しい。
僕は少し前まで、この劇場から歩いて三十分足らずの工場で契約工員をしていた。そしてこの劇場の観客のひとりだった。スカーレットねえさんはステージで熱演した後、いつも客席の僕に向かって微笑し、
「明日もおいで」
と声をかけてくれた。劇場を出る時、男たちは、スカーレットが俺だけを見つめていた、と口々にいうけれど、ねえさんは間違いなく僕だけを見ていた。僕はねえさんのステージについついのめり込んで劇場に転職をしてしまったけれど、工員がつまらなかったわけではない。契約工員として僕は毎日出勤し、真面目に業務に就いた。
「やあ、カオス」
マナブはいつも僕に笑顔で挨拶する。僕の名前はケイスケなのに、なぜかカオスと呼んで、訂正する事もない。お前の存在はまさしくカオスの産物だよ、とマナブは訝しそうな僕の面前ではっきりと言い放った。僕はマナブが工員たちに、あいつは少しここが足りないから、と話している後ろ姿を見たことがある。あいつというのは僕の事だとわかっていたが僕は普通の一般的な十七歳だと思っている。僕は男だから、ひとりになると普通に性器をいじくっている。一般的なことだ。それを作業場の十分休憩にマナブに見られた。
「いやあ、見られちゃったか」
僕はしたり顔だったのだが、やっぱりな、とマナブは呟いた。
「おまえ、やっぱ遅れてるんだよな、どっか。そんなとこ弄い回すのは幼児の特性なんだぜ」
僕はズレてるわけでもなく、遅れているわけでもない。「どっか」というのは脳みそを指しているらしいが、幼児が性器をいじくってばかりいるものだろうか。
「おとなの男は実際に女とやりまくるのさ」
僕は中学を卒業して就職のために施設を出た。僕は学校の成績はあまり良くはなかったけれど、無事に工場に就職できた。そのことを誇りに思っているのだ。マナブは僕と同時に入って来たのに、端から作業場の副班長をしている。だけど、この工場の副班長なんて班長の中年工員がよほどのことがあって休みをとらないかぎり用のないポジションなのだ。威張れたものじゃない。
訳もわからない電子部品を、僕はピッピ、ピッピと機械にかける。一日中その繰り返しだ。自分が一体何の仕事をしているのか、さっぱりわからなかったので、副班長のマナブに尋ねてみた。
「わかる必要ないんだ、おまえはピッピやってれば、給料になるんだ、ありがたいことじゃないか」
「でも」
「そりゃ説明してもいいのだが、あまり高度な話はおまえさんの身の毒になると思うよ、変なことで疲れない方がいいぞ」
マナブは踵を返して、振り向きもせずに足早に離れて行ったが、自分にもわかっていないのではないのか。わかっていないから簡単な説明もできないのだ。マナブ自身が高度な説明を受けたなんて到底思えない。
工場から歩いて二十分ぐらいの所にいい雰囲気の図書館があることを知った。僕は学校にいた時から、絵を描いたり読書することが割と好きだった。だからマナブなんかにばかにされないように、色んな本を読んで自分を磨こうと思ったのだ。
日曜ごとに足を運んで、気が向くままにパラパラと本を捲ったり、窓から外の景色を眺めたりして過ごした。
その日、図書館で僕はいい匂いのする女の人に出会った。女の人は大型で重そうな本を抱えてすわり、笑みを浮かべてゆっくりと表紙を開いた。彼女はページを捲るたびに、うん、うんと頷いたり、ちょっと眉を寄せて考えるような仕種をする。僕はそろーりと近寄って、彼女の後ろから覗き込む。ずいぶん立派な絵の本だ。こんなものがあるとは知らなかった。この図書館のどこに置いてあるのだろう。僕が目を見張っていると、
「ん?」
と不審そうに彼女が振り向いたのだ。
「ルノアールよ、好き?」
女の人は小声でそういった。僕は返事のしようがなくて、いい匂いのする彼女の目を見つめた。
「絵の本はどこにあるの?」
僕の問いかけに彼女は立ち上がって、大きな画集のコーナーを指さしてくれた。僕は適当に選んだ画集を持って、女の人の隣に座り、いい匂いをかぎながら本を開いた。
「すごい」
彼女が目を見開いて僕の手許を見つめる。僕は表紙の青い色がとても綺麗なので、何も考えずに画集を選んだのだ。
「フェルメールね、センスいいわ」
センスなのかどうなのか一向にわからなかったが、僕は時間のある限り、図書館に足を運ぶことにした。だって、ここに来たら、この女の人と会えるかもしれないのだ。
仕事の終了時間が待ち遠しい。のんびりできるからじゃない。図書館に出かけて、あのいい匂いのおねえさんに会いたいのだ。学校は絵の描き方を教えてくれたけれど、あのおねえさんはいろいろな画家を知っているみたいだ。僕の網膜には、いい匂いのおねえさんの微笑しか残っていない。仕事が終わったら、彼女のところへ一直線だ。
持ち場を手早く片づけ、図書館へと駆け足をして、一刻も早く彼女に会うのだ。館内に飛び込んで、僕はこじんまりとした図書館をぐるりと見回した。ルノアールやいろいろな画家たちの絵が載っている大きな本のある場所にも足を運んだ。
いない。
鼻から大きく息を吸い込む。だけどあの女の人のいい匂いはどこにも漂っていないのだ。
そうか、きょうは平日なのだ。彼女はまだ仕事中だ。まてよ、この前会った時も平日だったと思うが、いや、そうじゃない、日曜日だ。休みの日だった。僕は暫しの間、彼女を探して、息を整えてから椅子に座り込んだ。
(ねえさんは来ないこともあるんだ、そうさ、来ないこともあるんだ)
僕は唱えながらその日を過ごした。
一週間が終わる土曜日のことだった。僕はいつものように図書館の椅子に座り込んでいた。やたら顔が大きくて手の小さい浮世絵という本を睨みつけて、僕は背筋を伸ばして固まっていた。ねえさんは来ない、いや来る、来るわけない、来るに決まっている、と唱え、念じ、ふてくされていたのだ。浮世絵の本を閉じた時だ。
「久しぶりかな」
背中に彼女の声だった。一回会っただけなのに、僕のこと覚えていたなんて。それにしても匂いがしない。
「おねえさん、香水は?」
僕がねえさんを見つめているので、彼女はクックと笑った。
「香水好きなわけ?」
「おねえさんの匂いだから」
あ、そうだ、とねえさんは呟き、
「夕方から仕事なの」
と僕を見据える。
「あまり時間がないから、一緒に来る?」
わけもわからないまま、僕はねえさんの後を追った。
二人で歩いて路地裏に入っていくと、簡素な建物の裏口にたどりつく。
「こっちがあたしの出入り口なの」
僕らは手をつないで中へと歩いたのだ。
僕が劇場に通い始めてから三日目のことだった。工場の休憩時間にマナブが声をかけてきた。
「おい、ケイスケ」
本当の名前で呼ぶなんてマナブの奴、どうかしている。
「おまえ、最近おかしなところに出入りしているんだってな」
「ああ?」
僕は反射的に余裕の表情をつくったと思う。マナブなんてまだガキみたいなものだ。内心、僕のことが羨ましくてしようがないのだ。
「おまえがどう勘違いしているか知らないが、どんなものでも女は魔物だぞ、油断させといて男の生き血を吸おうとしているんだぞ、洗脳されちゃだめだ、洗脳、わかるか、おまえ、女は吸血鬼だ、吸血鬼なんだからな、いいか、おまえなんてひとたまりもないんだ、女は吸血鬼だ」
マナブは洗脳だ、吸血鬼だと繰り返し、僕の貴重な休み時間を無意味に費やして去って行った。おかしなところだなんて、スカーレットねえさんに対して侮辱も甚だしいではないか。魔物だ、吸血鬼だなどとマナブの思い込みと決めつけには、いつもながら呆れ果ててしまう。
工場との契約が切れて、僕は難なく劇場へ転職することができた。
世の中の人はよく夢を見るらしいが、僕は滅多に夢を見ない。
それは夢を見ても忘れているのさ、俺なんかはよく覚えているけどな、とマナブが僕をちらりと見て呟いたことがあった。
そんな僕が、楽屋でうたた寝している時、妙な夢を見たのだった。
―あそこだよ、坊や
乾いた声が聞こえたのだ。
「坊やじゃない」
夢の中では、僕は女と寝てきた直後だったのだ。僕は間違いなくおとなの男だ。それでも乾いた声は、僕の心の声に答えてくるのだった。
―女としたって? それはただの男の話さ、私は人間の精神を言っているのだよ
僕には無関係な話に思えた。ただ「あそこだよ、坊や」という意味ありげな言葉が、作造爺さんの言っていた「彼岸」に結びついて、空恐ろしく思えた。
マナブが僕のことをどう思おうと、今の僕は歴とした劇場の常勤として雇用されている。この劇場の従業員として、なくてはならない人材なのだ。
「きらびやかな世界へ、どうぞ」
客引きの笑い顔はけっして卑猥ではなく、夏の青空と同じで底抜けに明るいのだ。
その日、スカーレットねえさんの楽屋に珍しく客人が訪れた。
「いい小屋じゃない」
ねえさんよりかなり年上の女はあたりを見回した。
「あのさ」
と女は一呼吸おいて、ねえさんを見据えた。
「昔あんたが付き合ってた子さ、今頃になってアンデスに探検に行っちゃったのよ」
女はスカーレットねえさんが差し出した番茶に口をつける。
「それでどうなったと思う?」
女の目が面白そうに光った。
「あの子ね、アンデスの山を歩いていて鷲に襲われたんですって。ひ弱な男がアンデスの探検隊に入るとはねえ。でもあたし、テレビで見たことがあるのよ。羊が崖っぷちを歩いていると鷲が勢いよく飛び降りてきて崖から下へ蹴落とすのよ。ああいう鳥は弱いものをよく見抜くらしいわねえ」
僕の目に翼を大きく広げた鷲の姿が空を覆った。スカーレットねえさんが女を凝視している。
「彼は無事かって? だから言ったでしょ、死んだわよ、もちろん。崖の羊と同じよ、崖下でバラバラになった死体を咥えて、子どもの待っている巣との間を何度も往復して鷲の餌になったのよ」
バチンと音がしたと思うや、女が頬を押さえてスカーレットねえさんを睨みつけた。
「なにすんだよう、あんたのためを思って知らせに来てやってるのに、それが先輩のあたしに対する態度かよ、あたしゃ、あの子の葬式をしてやろうと思ってるんだ、遺体はないけど、あんたに少しでも情というものがあるなら、香典ぐらい奮発してもらわなきゃね、あたしはあんたが消えてからというもの、仕事のないあの子の食いぶちを必死で稼いで世話していたんだ、感謝ぐらいしてもらっても罰は当たらないだろうがよ」
やっぱり魂胆は金か。僕はもう女の顔を見なかった。
スカーレットねえさんが引き出しから小さく畳んだ紙幣を二枚出して広げた。
「あんたとは、話すだけ無駄よ」
ねえさんが喋ったのはそれだけだった。女は十代の女の子が持つような派手な花模様のビニール製の袋に札を突っ込んでから、ふてくされた様子で戸口に立ち、振り返った。
「あんた、あの後、子ども産んだろ、孤児院にでも入ってるのかよ」
捨て台詞を吐くと女は返事も聞かずに後ろ手で扉を閉めた。
スカーレットねえさんは少し紅潮した頬で立ち上がり、水道の水を勢いよくコップに取って、喉を鳴らし一気にあおった。
「デデ、今の女さ、猥褻な八ミリに時々出演して小銭を稼いでいるのよ、知り合いと言うほどでもないのよ、でもお金に困っているのなら哀れだもの、施しただけのことよ」
その後、ねえさんが喋ったことは、どこかで聞いたような、僕にも関係のあるような、だけど、あまり理解できない話だった。
スカーレットねえさんは、基地のある街で仕事をしていたという。基地のことなら僕だって知っている。基地、外国人、そして戦争、だ。
ねえさんは街のレストランでウェイトレスをしていたと言った。
「レストランに基地の将校が来たことがあってねえ、あたし、パーティーに誘われちゃったんだ、将校の新任パーティーによ、どこからかあたしの噂を聞いて来たのでしょうね、あそこのレストランにいい女がいるって」
ねえさんは満更でもなさそうに息継ぎをする。
「デデ、想像できる? あたしベルベットのドレスを新調して出かけたのよ、盛大なパーティー会場で、あたしは男たちに笑顔で言い寄られ、女たちの羨望と嫉妬の眼差しに晒されたわけなのよ、あの頃からあたしはダンスが得意だったのよ、将校と踊ったぐらいだもの、彼、耳元であとでお話しましょう、とか言ってたけど、あたし、トイレに行くふりして逃げ出したわ、ほんとよ」
僕には、ねえさんの「ほんとよ」の声音が、「ほんとは将校と二人でどっぷり楽しんだのよ」と言いたげに聞こえたのだ。
「ま、何にしても、あたしは同情心が強いものだから、みんながまるで十年来の知己みたいな顔をして、たかろうとするのよ、もう本当に絶句するしかしょうがないわよねえ、絶句、わかるデデ、ものも言えない状態なのよ、猥褻女優じゃあるまいし、あたしのは伝統芸能なんだからね、あたしの舞台は芸術なの、あたしの取り巻きはみんな舞踊以上のものを求めているんだから」
舞踊以上のものって、スカーレットねえさんがいつもやってる、あれのことだろうか。あれは舞踊以上のものってわけか。ともあれ、僕はこの時「絶句」という言葉を覚えた。
「いい? 猥褻女優とあたしの違いはね」
ねえさんが唇を舐めて湿らせている。
「猥褻女優に要求されるのは男の性欲を満たすことだけよ、男の本能に身を任せるだけ、
言いなりの女に男たちは大喜びする、それだけのことよ、猥褻八ミリはいつもそうよ、何の芸もなくたって寝転がって為されるがまま、男の煩悩に応じているだけなのよ、教養も技も何も必要ない世界を誰も芸術だなんて評価しないわ、だけどあたしには特別の才と芸があるの、あたしが追求しているのは常人には真似のできない才能の世界なのよ、わかるかしら、デデ」
だけどスカーレットねえさんは隠し撮りされたステージの技を、八ミリのスタッフに編集されたことを知らないでいる。誰が隠し撮りしたかなんて、楽屋裏ではだれひとり口にしない。僕は実際に見たわけじゃないけれど、経営困難になると、この劇場のオーナーが八ミリのスタッフに連絡を取るのだ。
「猥褻女優とアーティストのあたしを一緒くたにするなってんだ」
まだ息巻いている。スカーレットねえさんは延々と話しては唾を拭い、なんとか僕を説得しようとする。多分これが洗脳というものなのだろう。
「でもなぜ、そんなにこだわるの」
「あん?」
「なんだか、ねえさん、言い訳しているみたいで」
僕はスカーレットねえさんの気持ちを計りかねたので、素朴な疑問を口にしただけだった。でもねえさんの両手が僕の方に伸びてくる。僕はまた何か気に入らないことを喋ったのだと悟り、心の準備をしていた。緩慢に近づいてきたスカーレットねえさんの両手が僕の両方の頬を水平に引っ張っていく。
「デデ、あんたの皮はほんとによく伸びるわねえ」
翌日は久しぶりの劇場の休日だった。スカーレットねえさんが珍しく音楽を聴いている。舞台用の煽情的なメロディかと思ったのだが、仕事と無関係の幼児の泣き声に似た歌声だった。スカーレットねえさんは何か想い出に浸っているのだ。ねえさんは両手を広げて指の間からこぼれおちる感情を眺めている。戸外の景色までが流れ出て色を失うような悲観的な音楽だった。僕はふと、ねえさんの肢体に母性を感じていた。
デデ、あんた本当にいい子ね、と酒に酔って僕の頭に手をおいたのは昨日の事だ。
今日だってスカーレットねえさんは酒をしたたか飲んだらしく、顔全体が紅く火照っているのだ。
「姐御をそっとしとけよな」
作造爺さんが僕を部屋に連れ込んだ。爺さんは下駄箱のすぐ傍らに仕切りをして、自分の部屋にしているのだ。
「姐御は産み落とした赤ん坊が涎混じりにデェデ、デェデと言いながら手足を動かす様を眺めて、抱きしめては可愛がっていたのだがな」
そうか、デェデか。僕の芸名はダダイズムではなく、赤ん坊の思い出だったのだ。
「ここだけの話じゃが、姐御は子どもを育てることができんでのう、施設に預けたまではよかったが、事故か何かで死んでしもうて、それからというもの姐御は荒れに荒れて、訳も分からず借金が嵩んでのう、ええように食いものにされて男の分まで背負わされたんじゃよ、そのうち悪い奴らの力づくでおかしな八ミリに転がり落ちてしもうたんじゃ」
作造爺さんはこの劇場のことなら隅から隅まで知っていると言った。
まさかスカーレットねえさんと一緒に暮らしていたわけでもないだろう、などと考えめぐらせていると、爺さんが不意に僕を見つめた。
「言っとくが、子どもの父親は俺じゃねえぜ」
だれもそんなことは思ってもいないのに。作造爺さんだって、どこをどう流れてきたのか、どこまで本当の話なのか分かりはしない。爺さんは棚から下ろした安酒を振舞ってくれたのだが、僕はどうもアルコールに馴染めない体質らしい。飲んで五分も経たない内に喉元に酒があがってきて止まらず、トイレに駆け込む始末だった。
「今でこそ、姐御だ、看板スターだと持て囃されているが、あれがここに舞い戻って来てから暫くは、何から何までこのわしが世話して、スターの階段を昇らせてやったのさ」
まるで作造爺さんがスカーレットねえさんを育てたように聞こえるが、爺さんは単なる下足番兼雑用係にすぎないではないか。ねえさんは子どもをなくしてから借金もして、男に騙されもして、暴力も振るわれて猥褻女優も体験した。そういうことだ。それから日常的に性器を乱暴に使ったものだから、今の仕事に転職したのだと爺さんは言う。だけど僕はそこのところがよくわからない。乱暴に使うと、ここの舞台に転職するようになるのか。
「そりゃおまえ、フィストだぜ、フィスト。英語のわからんおまえさんに説明したってどうなるものでもないけどよ、女を腑抜けにするにゃ恥を恥とも思わないように躾けなきゃなんねえんだ、猥褻女優ってのは足を踏み入れたら一巻の終わりだな、業界の奴らは、ばたばたとエゲツナイことを強要して、早めに女を諦めの境地に追いやるものさね、それでもすぐに飽きられちまって、牛でも馬でも豚でも、もちっとは可愛がってもらえるもんだろうに、次から次へときっつい役をあてがわれて、女はもう何をされても抵抗できないモノになっちまうのさ、シャバに出たって無駄、脱け出たってもう誰にも相手にされないと達観するわけだわな、じゃが、ああも粗末に扱われたんじゃなあ、猥褻女優で生きていくしか道はない、同じ境遇の女たちとなら何とかやっていける、つまりこうなったからには現状に適応しようという心理にでも陥るのだろうなあ、そこが業界さんの付け目なのさ、しっかし開き直った女はめっちゃ強いぜえ、明るく元気になんでもこなす、別に下卑るわけじゃないさ、何ひとつ拒否しないで、何でもやっちまう、それでもって、あれやらこれやら使いこんでると、そりゃあもう、ガバガバだわな、けど、ここならその方が都合がいい、なんせ技術の世界だからな、股ってのは狭いよりは広々としていた方がいい演出ができるってものさ」
ますます以て僕は混乱してくる。いつだったか工場に勤めていた頃、マナブにカオスの話を聞かされたことがあった。僕はすぐに混沌として混乱してくるからカオスの世界の住人なのだそうだ。今の僕の気分は本当にカオスだ。作造爺さんは、なんせガバガバだからな、女をバタバタ、ガバガバにして、がっぽり儲けるんだ、バタバタガバガバ、ガバガババタバタ、と節をつけてしつこく唄うものだから、すぐ近くにスカーレットねえさんが突っ立っていることにも気付かないのだった。ねえさんはしばらく無表情でいたけれど、背中を向けて部屋を出てから三十秒もしないうちに戻って来ると、手にした便所のスリッパで高速マシーンもどきの早打ちで作造爺さんの頭を叩き続けた。
夕方になると、ひとりでホルモン焼きを楽しんでいる作造爺さんが、さっき裏で焼いたばかりの丸腸だ、と僕を部屋に誘った。
「ほら、食べやすいようにひと口大に切ってあるだろ、それを食べなきゃ男が立たない」
いつも爺さんは七輪で焼きながら食べているのだが、と思いながら僕は切断されて皿にのった丸腸をしばらく見つめていた。ステージの床に転がったバナナを思い出していたのだ。爺さんが上目づかいで僕を見ている。
「ここんとこ、女物の下着が盗難に遭っているんだがな」
爺さんは俯いたままだ。そうか、丁重にホルモンのもてなしをしてくれるのでおかしいと思ったら、作造爺さんは僕のことを下着ドロと疑っているのか。それで僕に自白しろと促しているのか。要するにスカーレットねえさんの下着をかっぱらっていく奴がいるわけだ。
「警察に届けたの」
僕は当然の正論で尋ねた。
「いや、それがな、あれは姐御の物じゃないんだ」
爺さんが丸腸をひと切れ口に放り込む。やっぱり、モツは焼きながらに限るな、と呟いている。
「なあ、デデくんよう、女の気持をよく理解するためにおまえさんはどんなことをしているかね」
僕はスカーレットねえさんの助手の立場でもあるのだ。いや、助手そのものだ。僕の毎日の仕事が、ねえさんを通して女を理解することに繋がっているではないか。
「わしゃのう、隣町の店で、今時の女が着けているようなパンチィをしこたま買い込んだのさ、それを気が向いた時に穿いてみると、なんだか気持が女になったみたいでのう」
僕は身を仰け反らせた。何と叫んだか、覚えていないぐらいだ。
「じゃが、この前から愛着のある下着が、みすみす盗られていくんじゃ、デデくん、もしも怪しい奴が物干し場に現れたら、わしに知らせてくれよのう、一緒に悪い奴を捕まえようじゃないか」
僕は返事をしなかった。爺さんにそんな趣味があることよりも、作造爺さんの股に密着した女物の下着が可哀そうで、ものも言えなかったのだ。それに、爺さんが犯人を悪い奴呼ばわりするなんて片腹痛い。これを「絶句」と言わずして何と言うのだろう。
「さあ、食えよ、おまえさんみたいににやけてたんじゃ、オカマの掘られ役しか回って来ないぞ」
丸腸が僕の腹の中で小人のスカーレットねえさんになった。複数の彼女ははしゃいだり、くつろいだり、優雅に踊ったり。それでも僕は戻れない。自分の心が人間以外の何かになった気がして、人間の僕に戻れないのだ。
「わしゃ、昔、女と暮らしたことはあるが、結婚なんてものはしたこともない、身軽なものさ、おまえさんはその内、自分に見合った女と一緒になるだろうが、少しは世の中を知っておいた方がいいぜ、きょうは特別におまえさんだけに披露するけどな、高かったんだぞ、この本」
爺さんが背中のあたりに隠していたらしい艶々した派手な本を引っ張り出した。
「ここには外人も来るからよ、日本じゃ手に入らないから、ちょいと都合してもらったんだ、うん、高いけどな、じゃけんど、さすが舶来だ、高いだけのことはある」
本を開くと外国人の男と女の写真ばかりが載っている。外人はいつもこんなことばかりしているのだろうか。世界中となると、随分いろんな考えの人間が生きているのだな、僕はこの世を見回しても、納得できないことだらけだ。
「デデくん、ショックかい」
爺さんが僕の顔を覗き込む。
「女の人はそんなにいい気分なのかな」
「なわけないってよう、昆虫だって繁殖以外の性交を喜ぶメスなんかいやしないんだ、テレビなんかによく出てくるだろ、大自然の中の動物、魚類、虫類、どれもオスに追いかけ回されて、逃げ回るメスの図ばっかりだぜ、メスは繁殖のためだけに、自分が気に入ったオスを選ぶのさ、オスの快楽のために餌食にされるのは人間だけだろうな、うん、男のわしが言うのもなんだが、いい気分なのは男だけなんだ、だから男の勝手を正当化するために女の快楽神話を捏造するわけなのだよ、うん」
僕はやっぱり納得できない。爺さんの自信たっぷりな解説を鵜呑みにしてもいいものだろうか。何がどう疑問なのかと訊かれれば、僕はわからない処さえもわからないと答えるしかないのだ。
「猥褻女優は自分からとびこんで、大喜びで出演しているみたいだろ、男の言いなりに、男が喜ぶような台詞を口にしないとあの世界では生きていけないのさ、そうやって堕ちるところまで堕ちたと女に自覚させるのさ、脅したり、強制したり、若い女なんて造作もないものなんだぞう」
作造爺さんが象の貯金箱を振り動かしている。
「最初はみんな世の中から謀られるのだがな、男の甘言、ちょいと借りた金、モデルさんへの勧誘が実は地獄への入り口だったなんてのは、世間の誰もが知ってることなんだぞう、そんなものなんだぞう」
爺さんが貯金箱の象をうんうんと頷かせている。象の腹で一円玉の軽い音がした。
今夜のスカーレットねえさんは極彩色の羽毛にくるまれている。
「どう、デデ、いい衣装でしょう、あたし極楽鳥になりきるわよ、後ろの方を引き摺るようにしたいの、ちょっと手伝ってちょうだいな」
この舞台の一週間前から、僕はねえさんと一緒にピンポン玉に金色の途料を塗っていた。僕は仕事だから言われるなりにかなりの量のピンポン玉を金色に変えていった。きれいに乾いた玉は手触りもつるつるのすべすべで、頬ずりしても気持ちがいいのだ。
僕はねえさんと二人きりで仕事ができたことに充分満足していた。二人の間に作造爺さんなどが入ってきたら僕の気分はぶち壊しになるところだ。
極楽鳥の舞台では、黒子として僕の出番もあるのだ。重要な役割りだとねえさんに言われている。スカーレットねえさんが身に着けている極楽鳥の尾羽を丹念に整えたのはこの僕だ。艶やかな衣装に包まれたスカーレットねえさんが舞台の袖から中央へと吸い込まれていく。極楽鳥の胸の羽が大きく膨らんで、ねえさんの顔が随分と小さく見える。伝統芸能を見届けようと、いつもより以上に観客席は熱気に包まれている。
スカーレットねえさんは優雅に、時に激しく踊りまくり、音楽が神妙なメロディに変わった途端、派手な翼を広げて緩慢な動作で坐り込むのだった。突然、観客席が水を打ったように静まり返る。咳払いも、笑い声も、僅かな話し声さえも消え失せるのだ。僕はバックミュージックのボリュームを殆ど聞こえないほどに低くしてから出番を待った。スカーレットねえさんが舞台中央に坐った時は、観客が真剣になる時で、その時点からねえさんは例の舞踊以上の伝統芸能を披露するわけだった。
黒子の身なりをした僕は、言いつけられた通りに、袋いっぱいに詰め込んだピンポン玉をスカーレットねえさんの周囲にばら撒く。僕の姿は誰の印象にも残らない。観客たちは誰もみな、立ち上がったり這ったりして、スカーレットねえさんの伝統芸能を見届けようと舞台のかぶりつきに集まっているのだから、僕のことが目に入っている者はひとりもいないのだった。僕が黒子の役をするので、この日の照明は自動点滅するようにセットしてある。観客はライトに近づいてくるが、スカーレットねえさんの動きを見逃すまいとしてみんな目が血走っているのだ。
黒子の僕はスカーレットねえさんが極楽鳥の扮装をして金色の卵を数え切れないほど産み落とすシーンを、驚きと感動で涙を流しながら眺めていた。その時、やっぱり、ねえさんは超、超人なのだと納得したのだった。
スカーレットねえさんは楽屋でステージの準備もすれば、寝泊まりもしている。ベニヤ張りだけど、ちょっとしたマンションみたいな綺麗な部屋だ。壁には不思議な絵が掛かっている。女の人の背中に大きな青い翼が生えているのだ。一度ねえさんに絵のことを尋ねたことがあった。
「どこが不思議なのよ、デデ、これは普通に普通の絵なのよ」
スカーレットねえさんは自慢そうだった。
「作者不詳なのだけど、確実なのはルネッサンス以降の画家ということね、もしかしたらレオナルド・ダ・ヴィンチの作かもしれないわよ、世界の新発見だわ、タイトル知らないでしょ、『蒼白の天使』っていうの」
「ソーハク?」
「ほらさ、こんなふうに青っぽい色が全体を覆っているでしょ、蒼白の天使、まっさおなエンジェルってことよ、ブルーな心理状態を表現しているのでしょうね、もうひとつ、『喜びの天使』って赤系統の絵があるのよ、これはまだ発見されてないんだけど、いずれあたしが手に入れてみせるわ」
「そう」
僕は水彩絵の具を使って描かれた蒼い絵がやたらと派手で豪華な額縁に嵌め込まれてあるのが不思議に思えただけだ。それに顔色が青くて病気の天使にも見えるのだが、スカーレットねえさんの話にはやっぱり説得力がある。ルネッサンスだの、『蒼白の天使』だの、『喜びの天使』は赤系統だの、未発見の絵の題名まで知っているのだ。僕だってダヴィンチの名前ぐらいは聞いたことがあるが、彼女の博学には及びもつかない。
「ダヴィンチだってえ? どんな食い物だ、そりゃあ」
作造爺さんが素っ頓狂な声をあげた。爺さんだってダヴィンチぐらい知っているだろうに、わざと話をはぐらかそうとする。
「だって、スカーレットねえさんが」
「ああ、姐御は絵が好きだからな、昔からノートに描いたり、チラシの裏に描いたり、いらなくなったカレンダーに描いたりさ、あの壁の絵だって厚めのカレンダーの裏側を利用して描いたのさ」
後で気づいたのだが、僕らの会話はねえさんに筒抜けだったのだ。
昼間、楽屋に入るとスカーレットねえさんが夢中になって手を動かしていた。後ろ姿が何かに打ち込んでいて、人を寄せ付けない。この背中はねえさんのプライドなのだ。邪魔をしないように後戻りして、暫くしてから再び楽屋に入った時、スカーレットねえさんは、小さな流し台で絵の具のパレットを洗っている最中だった。この光景は僕にも覚えがある。小学校の時にお母さんの顔を描きましょうという授業があったのだ。その時すでに僕には母親がいなかったのだけれど、そんなことは問題にせずに画用紙に自分で考えた女の人の顔を描いた。あまりうまく描けなかったのだが、先生に褒められて、僕は意気揚々とパレットを洗って後片付けをしたのだった。スカーレットねえさんも誰かの顔を描いた後片付けなのかもしれない。
パレットを洗い終えると、スカーレットねえさんは爪の間に詰まった青い絵の具を洗い流している。楽屋の簡素な手洗い場が青く染まっているのだ。
「作さん、ちょっと」
スカーレットねえさんの声がする。作造爺さんが下顎を突き出してやってくる。
「そこの絵だけど、ちょっと下ろしてみて」
「へえ」
自分でやれよ、の目つきでねえさんを流し見ている。
「時々、絵の裏側を確認しないとね、シミが付いてたら困るから」
スカーレットねえさんが大仰な仕草でゆっくりと額縁を回転させた。裏側は真っ白で塵ひとつ付着していない。真っ白できれいで分厚い画用紙だった。
「なんだ、いい画用紙じゃないか、作造さん、カレンダーとか何とか言ってたけど」
僕は思わず片手で口を押さえる。
「なに? デデ、カレンダーってなんのことかしら」
スカーレットねえさんが背筋を伸ばして、作造爺さんの方に顔を向けた。
「いや、なに、以前そこにあっしがカレンダーをかけようとしたものだから」
「あら、そうだったかしら」
「あっと、さあて、今夜も大忙しだ、姐御のステージが大入り満員になるからな」
作造爺さんがそそくさと楽屋を出て行った。スカーレットねえさんのショーには多国籍の外人さんたちも、観覧席に現れる。下足番の作造爺さんも万国共通の英語を使ったりして接客もするわけだ。小さな舞台だけど畳張りの客席とあまり段差がなく、近い目線なので親近感があってよいと僕は思う。
「ねえさん、どうして画家にならなかったの」
「この指を見て」
ねえさんが右手の中指を宙に浮かせた。
「時々うごかなくなるのよ、思うようにならないの」
でも指が動かなければ違う指に、手がだめなら足で、それもだめなら口に絵筆を咥えても描く人は描くのじゃないのか。それに伝統芸能を披露する時のスカーレットねえさんの指先は自由自在に滑らかで、思うように動き回っているではないか。
「ねえさん、ひとつ質問してもいい?」
スカーレットねえさんは真顔で小さく頷いた。
「あのさ、ダダイズムってなに」
ああ、そのことか、というふうにスカーレットねえさんは微笑した。
「デデの名前は、実はダダイズムじゃなくてね」
僕は緊張してしまう。
「ルノワールが愛した最後のモデルの呼び名なのよ」
スカーレットねえさんはショーの支度があるからと、立ち去って行った。
つまりだ、僕はねえさんに愛された最後の男なのだ。ダダイズムのことは分からずじまいだが、そんなことはどうだっていい。
いつも前向きなスカーレットねえさんが、その夜は俯きかげんだった。理由はわかっている。いつだったか、真っ赤な薔薇の花束を抱えて舞台に駆け寄りスカーレットねえさんを驚嘆させた、やけに紳士ぶった中年男の宇津木のことだ。宇津木は花束でねえさんの心をつかみ取ったとでも思っているのか、自信に満ちた態度で予告もなくねえさんの楽屋に上がり込んで来るようになった。
僕はねえさんの楽屋に置いてある衣装ケースやら、ピンクのチェストが並べてある裏側の隙間で寝起きしている。僕は寝たふりをして気配を殺していたが、楽屋に入り込んできた宇津木は、さんざんスカーレットねえさんに泣き声を上げさせて、自分は含み笑いばかり洩らしていた。床の振動が僕の身体にも直接伝わってくる。僕はますます小さく丸まってしまう。二人が静かになった時、ねえさんの呟く声が聞こえた。
「いずれ私のお乳も垂れてしまうのね」
え、と声を出しかけて僕は目を見開く。ストレートな言葉が、ねえさんの乳房の重みを感じさせたのだった。それに宇津木と別れたくないねえさんの気持ちも伝わってきたのだ。
「あなたのお乳は垂れないよ。私が見守るかぎりはね」
なんて気障なせりふだ。ねえさんに岡惚れしたからと言っても、この男はあまりに年甲斐もない感覚に陥っている。それでも二人の仲はしばらくの間続いていた。
宇津木が現れるとスカーレットねえさんの体から熱いものが溢れ出し、あたりの波長を乱していく。ねえさんのプライドを以てしても欲情を抑えきれずに熱を放っているのだ。
とそこまで考えて、そう思いこみたいのは僕自身にほかならないことに気づいた。プライドがあってもなくても、欲情を抑え込む必要などありはしないのだ。
ねえさんは昨夜のことが尾を引いて、まだ体の奥がけだるいと僕の前で平気で言ったりする。それに宇津木という名の厚かましい中年男はいつも堂々と楽屋に入り込み、時にはねえさんの横に坐っている僕の存在を無視して、スカーレットねえさんを見つめながら右手を軽く開き、匂いをかぐ仕草をするのだった。宇津木は少し意地悪な上目づかいでねえさんの反応を楽しんでいるのだ。きのうのスカーレットねえさんは、抱きしめようとする宇津木の腕を振りほどきながら、そのくせ身体ごと男に纏わりついて離れなかった。柔らかく温かく、もぎとりたくなるようなねえさんの匂いが宇津木の指に沁みついているのだ。まだ鮮やかな情事の記憶を思い出し、ねえさんがどんな表情で恥じらいを見せるか、それとも少し怒った顔を見せるか、宇津木は面白がっているのだ。僕は狡猾な中年男の宇津木を憎み、ねえさんに何もしてあげられない僕自身を呪った。
スカーレットねえさんの下瞼から頬にかけて薄紅色に染まっている。宇津木は離れようとするねえさんの肩を強く引きよせ、捩った首筋に何度も舌を這わせた。
「おもちゃね」
「いや愛だよ」
「おもちゃよ」
「いや愛だ」
「おも・・・」
繰り返すたびに、ねえさんの身体から熱い体温が溢れ出る。
二人の前で為す術もなく存在感のない僕は、冷たい路上にうずくまる捨てられた子猫だった。
僕の部屋は狭苦しいが、ベニヤ張りの壁には小さな窓もあるのだ。僕は眠りに就く前には必ず夜の空に声をかけた。
「おやすみ」
とか、
「おつかれ」
とか、月が出ていてもいなくても、星が見えても見えなくても、夜空を見上げて挨拶をした。仕事が早めに終わった日は、僕はありあわせの物で空腹を満たした後、誰が何と言おうとさっさと寝床に就くことにしている。窓の外は薄暗く、見上げると半円形のお月さまが、蒼白い光を地に落としている。僕のいる部屋の片隅にも、和らかな光が差し込んでくるのだった。
「半月さん、おやすみ」
僕が声をかけると、後ろから声が返って来た。
「今夜は上弦の月っていうのよ」
スカーレットねえさんは体を斜めにして僕の寝場所に侵入してきた。
「ああ、ねえさんか、お月さまの声かと思った」
僕は少し驚いてしまう。ねえさんは良く物事を知っているので、たぶん僕の生涯の師ということになるのだろう。
「デデ、抱きしめてもいい?」
ねえさんが僕の寝床にするりと潜り込んできたが、僕はもう少し上弦の月を愛でたい気分だったのだ。でも香水とは違うやさしい体臭が僕を包み込んでくる。スカーレットねえさんは赤ん坊をあやすみたいに僕の背中に掌を添えた。ねえさんが泣いているような気がしたのだが、知らぬ間に僕は眠りに落ちてしまった。
「お客さま、どうぞ! 終電車までお楽しみください」
エイ氏が、がなり立てている。今度のエイ氏は恰幅の良い中年男だった。人員削減されたサラリーマンだと自己紹介していたが、どう見ても使い込みがばれて、会社を馘になったみたいな風貌だった。
その日、僕はねえさんから言付かった郵便物をポストに投函に出かけた。封書を手にしてから妙なことに気づいた。その封筒からは、僕がムラムラ発情した時と同じにおいがするのだ。鼻に押し当ててみるとやっぱり精子のにおいだった。
「ねえさん、あの封筒、臭かった」
僕は帰ってから即座にスカーレットねえさんに報告をした。ねえさんは神妙な表情で付け睫毛をつけている最中だったが、なんら動揺することなく言った。
「糊を切らしていたから、昨日の男の精子で代用したのよ」
そう言えば、ねえさんは昨夜、縁切りレターとか言いながら手紙を書いていたが、精液で封をしていたのか。昨日の男とは、おそらく厚顔無恥の中年男、宇津木にちがいない。というか僕はそうあってほしいと願っているのだ。
ねえさんが楽屋に男を連れ込むのは、それ以前もそれ以後も珍しいことではなかった。
作造爺さんは、
「姐御の唯一の娯楽なんだろう」
と涼しい顔をしている。
伝統芸能の時間が近づくと、ねえさんは潤んでいた目を擦って勢いよく立ち上がり、素早く舞台衣装に着替えた。スカーレットねえさんはステージのプロなのだ。
「デデ、森の木って好き?」
僕は返事もせずにねえさんの顔を見上げた。スカーレットねえさんは、頭のてっぺんから足の先まで、緑色の葉っぱだか苔だかの衣装を身に纏っている。僕に覚え込ませようとして何度も復唱させたエルンストの絵そっくりの扮装なのだ。
「好きだよ」
「それならいいの」
その日のステージに僕は森の樹木として出演した。僕の周りは張り子の木々だが、僕はスカーレットねえさんの動きに合わせて、左右に揺れ、前後に撓った。ねえさんは激しい嵐にも負けない森の女王になりきって踊り、さらに舞踊以上の演技に移るのだった。
客席に見覚えのある男が坐り込んでいる。男はタイミングよくステージの間近に走り寄って来た。奥歯が見えるほど大きく口を開けて目を見張り、興奮しているのだ。こんな面があったのかと、僕はマナブの変貌ぶりを眺めていた。
伝統芸能が終了しても、マナブはまだ居残っていた。
「ハマるよなあ」
マナブは森の木の扮装をした僕の全身を眺め回し、上から下まで何度も視線を往復させた。マナブはこの日が初めてではなく、極楽鳥の舞台からスカーレットねえさんのファンというより、信者になったのだと言う。マナブ、あの時いたのか。
「マナブ、かぶりつきまで来てたかなあ」
「初めてだったので、行儀よく席に着いていたよ、ただ俺はすこぶる感動したんだ、あの踊り子、きっと世の中に出てくるぞ」
踊り子だって? 気安く呼ぶんじゃない。世間に出てこなくてもスカーレットねえさんは人間としての価値が高いのだ。だからねえさんはいつもプライドを維持していられるのだ。
「ああ興奮したので手が湿ったなあ、ハンカチハンカチ」
唐突にマナブが、ズボンのポケットから赤いハンカチを取り出した。
「おっとっと、いけねえ、まちがえた」
マナブはポケットの奥から色とりどりの布を引っ張り出す。
「ケイスケ、これなんだかわかるか、カラフルだろう、これがナオミの、こっちがリエのだな、それからこの花柄がチエコ、これ全部女のパンティ、俺は断ったんだが、女たちが貰ってくれとうるさく追い縋るからしかたなくな、このちっこいヤツまで、ぜぇんぶパンティだ、何度か穿いたパンティだよ、ま、意味ないけどな」
赤いハンカチと思ったのは、サナエの過激なパンツなのだという。
「それがハンカチ代わりじゃ不便だろうな」
僕はマナブに貸してやろうと思い、ポケットから黄色のタオルハンカチを出した。
「なんだよ、おまえ、もう手は乾いたよ、おまえ相変わらずつまらん奴だな」
目の前を羽虫が飛び回るものだから、マナブは羽虫を追い払いながらカラフルな下着をそそくさとポケットにしまい込んだ。
仕事が終了してから、どうした風の吹き回しかスカーレットねえさんが皆のために飲み物を買ってきてくれた。劇場には売店がなく、僕たちは近くの駅で買い物をすることが多かった。
「あたし、缶より瓶の方が好きなのよ」
ねえさんが買い物袋からコーラの瓶を取り出す。
「こりゃありがてえ」
作造爺さんが膝をぴしゃりと打って立ち上がった。
「いいわよ、あたしが配ってあげる」
スカーレットねえさんがコーラの瓶を男衆に手渡す。なんだ、冷えてないじゃないか、と作造爺さんが独りごちる。贅沢言うなよ、爺さんの分まで買ってきてくれたんだぞ、僕は爺さんを横目で睨んでやった。伝統芸能のアーティスト、スターのスカーレットねえさんの厚意を何だと思っているのかな。それにしても、ねえさんが僕たちの為に駅で飲み物を買ってきてくれるなんて今までないことだった。有難いというよりも、僕には何だか不自然に思えるぐらいだった。
「冷えたコーラは一本しかなかったのよ」
ねえさんがオレンジジュースの瓶に口をつけた。それからねえさんは、ちょっと、と言って部屋を出た。お、僕のは冷たい。ほくそ笑んでいるとマナブが僕を見ながらコーラをラッパ飲みした。
「スカーレット嬢はやっぱり俺に惚れてんだ。よく冷えてるよ、このコーラ」
「うそつけ」
僕は本気で叫んでいた。マナブの瓶は汗をかいていないのだ。汗をかいているのはスカーレットねえさんのジュースと僕のコーラだけだ。
「なんだよ」
マナブが不服そうに言い、一気にコーラを飲みきった。
ドアが開き、スカーレットねえさんが戻って来ると同時に、冷えた外気が流れ込んで僕たちを冷静にさせた。きっと、ねえさんは僕への愛をコーラで表現したかったに違いない。
ドアの外では、夜の空が果てしなく広がっているのだ。
翌日、作造爺さんが僕の前にやって来て、口をもぐもぐさせながら外を指さした。
「ほれ、前に言っただろ、昨日もだよ、トイレの窓から物干し竿のピンクのパンチィが不自然に揺れているのが見えるんだよ、わしが視線を移そうとした時、黒い影がするりと現れてよう、影は薄く透けたピンクのパンチィをいとおしそうにもみしだき、竿から取り上げると頬ずりをするんだ、(そっそれは・・・)わしゃ声を出しかけて、ぐっとこらえた、下着ドロの奴はピンクのパンチィを姐御のものだと思い込んでるんだな、クンクン匂いなんか嗅ぎやがってからに、ちょいとわしが悪戯心で三日間履いたままだったのさ、いや、もちろん洗ってはいるがよ、女の気持を推し量るにゃ女の下着を身につけるのが一番じゃからのう、わしゃ、おい、と声をかけてサンダルを突っかけて追いかけたんじゃが、そいつはえらく素早くてのう」
僕は直観した。そいつがマナブだってことか。夜干しで、まだ生乾きの洗濯物が物干し竿にしっかりと絡みついているのだ。爺さんだって下着ドロを追いかけたかどうか眉唾ものだ。マナブの奴、とんだピエロだ。サナエの赤いパンツも、ナオミやリエのパンティもマナブの妄想の産物なのだ。うちの物干し竿から失敬したに決まっている。僕は急激に笑いがこみ上げ、どうしようにもセーブできなくなってしまった。作造爺さんは床に転がって爆笑している僕を口をすぼめて眺めているのだ。僕は爺さんの口が肛門にそっくりだと思い、余計におかしくなって笑い続けた。
作造爺さんもマナブも、見栄っ張りで、こそこそしていてカッコ悪い男だ。考えるに僕だけが仕事に真剣に取り組むプロの心意気を持っている。僕は何があってもステージだけは成功させようと一生懸命なのだ。いつだってそうだ。この日のスカーレットねえさんの舞台衣装は日本調だった。これがジャポニスムというものなのだろう。少し前にねえさんが見せてくれた本の中に、ものすごく綺麗な日本の着物を着た金髪の外人女の絵があった。日本趣味なのよ、ジャポニスムなのよ、ルノワールなのよ、とねえさんが嬉々として教えてくれた。僕は照明を自動に切り替えて、観客席の後ろの方からねえさんの演技を眺めていた。真紅の打ち掛け姿のスカーレットねえさんが日本舞踊を舞っている。扇子が大きくて、ピタリと静止した時のねえさんの姿ときたら、以前見せてもらった外人女の絵姿そのものだった。スカーレットねえさんの為に誂えたような豪華な日本の着物。ところが舞踊の最中に、ねえさんの背後に真っ黒な影が見え始めたのだ。ねえさんの影だと僕は思い込んでいたのだが、その影はねえさんとは別に蠢いているのだった。真っ赤な着物のスカーレットねえさんと訳のわからない真っ黒な影。黒い布で全身を覆っているのだが、黒子の役を僕以外の者にやらせるわけがない。今夜も客席のかぶりつきにマナブが陣取っている。だから黒い影は当然マナブではない。
突然、影が布を取り払い、スカーレットねえさんの周りで踊りだし、観客席はすっかり盛り上がってしまった。なぜなら黒い影は黒い布を剝がしても、やっぱり黒い男だったからだ。劇場始まって以来の黒人さんの登場だった。彼は黒人さんにしてはひどく華奢な体格で、野性味のない男だった。それにしても僕の知らない男が、僕の知らない間にスカーレットねえさんのバックで踊るなんて。何だか不愉快だ。ジャポニスムのねえさんは暫くの間黒人さんを相手に淑やかな舞を舞っていたのだが、二人の男女がくっついたり離れたりする舞台演技の途中で、彼が狂ったような大声で喚き始めた。何かを叫んでいるのだが、どうも日本語の堪能な外国人らしく、何しやがるんだ、と僕には聞こえるのだ。後になって知ったのだが、ステージの黒人男は本物の黒人ではなくて、その辺の兄ちゃんに頼んで身体中真っ黒に仕立てた日本人なのだった。
スカーレットねえさんはレイプされかけたと大声をあげ、男は殺人未遂だと騒ぎたてた。殺人未遂と男は言うが、スカーレットねえさんは刃物なんか持っていないではないか。
「こんな重たい着物を引き摺ってるからって」
スカーレットねえさんは、ステージの中央で仁王立ちだ。
「動きにくいのをいいことにして」
スカーレットねえさんと大騒ぎしている黒い男が揉み合っている。スカーレットねえさんの一大事なので僕は慌てて舞台に跳び上がり、ねえさんを抱きかかえて楽屋に運んだ。観客席の男たちは、なんだよ、やめるのなら金を返せ、などとしょうもないことを叫んでいる。
「この女、力任せに俺のを引きちぎろうとしやがって」
なんだ、それぐらいのこと。殺人未遂は大袈裟だ。舞台の幕を下ろしてから、僕は下足番兼雑用係の作造爺さんをつかまえた。
「作造さん、なんであんな日本人使うんだよ、僕は何も聞いてないよ。いっそ本物の黒人さんの方がマナーはいいだろうに」
マナーがいいかどうかはともあれ、僕に知らせもせずに素人の男を使うなんて。常にスカーレットねえさんの味方である僕としては憤慨せずにはいられない。
「そりゃ、筋肉隆々の黒人だと、わしら突き飛ばされて、太刀打ちできないだろうよ、それにあの兄ちゃんを連れてきたのはわしじゃないぜ」
作造爺さんが僕の手を振り払った。
「この劇場の偉いさんが、どっかから引っぱってきたんだ」
爺さんはそそくさと部屋に戻ったきり出てこなかった。下駄箱の隣にある爺さんの狭い部屋から安酒の匂いが漂ってくる。
散々な一日だったので、僕は早々に寝床に就いた。壁代わりの衣装ケースにスカーレットねえさんの舞台衣装が詰め込まれている。
(眠れないなあ)
僕は何度も寝返りを打つ。擦り切れた毛布にくるまって、いつだったかねえさんに習った眠りの呪文を唱えた。こんなに羊が一匹、こんなに羊が二匹、う~ん、羊が四匹・・・
窓の外では静かに雨が降り始め、僕は呪文をやめてしまう。
二日続きの雨は強さを増して、とても外に出られないほどだった。それなのに、スカーレットねえさんは雨の中を出かけたらしく、劇場内のどこにも居ないのだ。僕は心配で群青色の合羽を身につけてねえさんを探しに出た。傘は持たなかったので、激しい雨が体にくい込むほどだった。弱々しい傘の骨など、こんな豪雨に打たれたらひとたまりもないだろう。僕は小走りで駅に向かいながら、少し前にスカーレットねえさんが僕に冷たいコーラを買ってきてくれたことを思い出していた。ねえさんはきっとこのあたりにいる。僕は小走りの速度を上げた。
駅の裏通りまで来て、僕はずぶぬれの男女がぴったりと抱き合っているシーンを目撃してしまった。早朝の駅裏は人気もなく、二人は恋愛映画の再現をしているのかと思えるぐらいドラマティックな雰囲気だった。男は青いワイシャツで、女は白いワンピース姿だった。しばらくして女が離れようとすると、男は女の背中を引っ掻いて留めようとする。どちらも頭から全身水浸しなのだ。このあたりから僕は妙な感覚に陥っていた。女は力任せに身を引き、後ろに尻もちをつく。男が跪いて下腹を押さえている。突如として男の腹から鮮やかな血が吹き出るところを僕は見た。しかしそれは降り続ける雨に吸い取られ、鮮紅色の血は灰色のぬかるみに混じり込んで色褪せていった。振り向いた女は雨に目を細めて僕の姿を捉えていた。
激しい雨に濡れたスカーレットねえさんのワンピースは透明だ。下着も付けていないので固い乳首の形がくっきりと浮き上がっていた。なんだかプールから上がってきたばかりみたいだと僕は思って眺めていたのだ。
もう何か月経っただろう。僕はスカーレットねえさんと、まさしく顔と顔を突き合わせて話をしている。と言っても、ねえさんが一方的に喋っているだけなのだが。僕はすこぶる姿勢よく座って、ねえさんと接近しているのに、なんだかとてもまどろっこしい。
「えらい画家の先生から依頼されてモデルをしたこともあるのよ」
宙を見つめるスカーレットねえさんは幸せそうだ。
「楽にしていいのですよ、つらければ多少動いてもかまわないのですって、先生が」
ねえさんが微笑みながら言った。
「あたしは少し緊張していたので、首筋が汗ばんでいるのを悟られたのだと思っていたの、絵のモデルというものはけっして身動きしてはいけないものだと思っていたから、一点を見つめて瞳の開き加減も変化のないよう、瞬きさえ遠慮していたのよ、動いてもいい、
と言われて気分がくつろいだことをよく覚えているわ」
スカーレットねえさんは心底、舞台女優なのだ。詩人で、頭脳明晰で、感受性が強くて、僕はねえさんと一緒にいて生き甲斐のようなものを見つけたと思っている。
「あたしはモデルのために新調した白いワンピースを着ていたのだけれど、今考えると花嫁の気持ちでいたのかもしれないわねえ」
僕はスカーレットねえさんの打ち明け話を一度に聴き終えたわけではない。何回にも分けて、顔を突き合わせて、真正面から、目と目を合わせて、じっくりと聴いていたのだ。
「一日のモデルが終わった時、外はもう夕暮れになっていたの、目を閉じて体の力を抜いていたら、あたしに触れてきた感覚があったのよ、目を開けると、先生が窓を開けて、あたしの肩に手をおいていたの、外気と風を含んだ柔らかな感触だった、あたしにとっては大それた刺激だったけれど、嫌悪感がまったくなかった、そう、僅かばかりもなかったの、若い男に接するのならばときめき方も違っていたかもしれないけれど、包み込むような先生のやさしさが、自然にこちらの気持ちがほぐれてくるのを待っているようで少しもいやではなかったのよ、だからあたしは先生を愛していると心から納得できたの、それなのにあたしは拒絶しようとしている、心は先生を受け入れたいのに、湿った砂があたしの踝を擽るみたいで、体が拒絶している、しばらくしてから先生が耳元で囁きかけたの、・・・嘆かないでくれ、君は私の最後の女性だ……あたしは努めて声を押し殺そうとしたけれど、だめだった、なぜだと思うデデ、そうねえ、デデ、あなたにならわかるかもしれないわねえ、これは知恵とか知識とかではなく感受性の問題なのよ、先生の肉付きのよい腰のあたりが、あまりにも意外に思えたのよ、枯れたはずの先生の肉体が、狡猾な動きにつながっていくことへのあたしの拒絶反応だった、あたしは先生のことを心底愛していたの、それなのに私は……」
僕は口を挟むこともできず、ただ頷くだけだった。
「あたしは先生の為に苦しんだのに、先生はこう言ったのよ。予想通りの性だ、滑らかで、絹のような音色でと。男と女に予想通りの性などあるものですか、あたし号泣したの、恋という厄介な感情は、なぜ平穏な日常をかき乱し、なぜ水のように足許を濡らして過ぎ去って行くのかしら。ふと見ると窓から射し込む夕陽があたしの身体を染めて、あたしの白い服が夕焼けで血塗られていたのよ。」
スカーレットねえさんの心が乱れている。ねえさんが刺した青いワイシャツの男は、この偉い画家の先生だったのだろうか。
「あたしを取り巻くすべてのものが息を潜めていたの。知らんふりをして黙っていてくれればいいのに、先生は初めからあたしの身体に予想を立てている、そのうえ悪いこともしていないあたしを、先生好みの理想の女に仕立てようと考えているみたいだった。そんなおかしな話はないでしょう、あたしの身体を自由にする大義名分みたいにね、あたしにもプライドというものがあるわ」
そうだとも、スカーレットねえさん。ねえさんはプライドを第一に優先する。その先生と言う奴は、ずうずうしくって、利己主義で、ねえさんに近づくこと自体がもってのほかの男だ。
「ねえさん、彼岸て言葉、知っているよね」
作造爺さんのことを思い出して、ねえさんの目を見つめた。爺さんは今もモツを焼いているのだろうか。秋の彼岸も近いのだ。
「悟りを開けば彼岸に行けるって言うわよね、だけどあたしにとっての彼岸は、真っ赤な彼岸花のことだけね、一斉に咲き揃った彼岸花は時期が過ぎると、目立たなくなっていつのまにか消えているの、彼岸花を手折ると母親が死ぬって言い伝えがあるじゃないの、子どもの頃、あたしは母親が死ぬという恐ろしさから、彼岸花を手折ることなく暮らしてきた。母の死を迎え、初めて解禁した花束は深紅の彼岸花だった、でもその時、間違いなく母親は死んだのだ、あたしは確実に孤独だと感じたのよ」
スカーレットねえさんの頬が心なしか青ざめて見えたが、すぐにそれは蛍光灯の乏しい灯りのせいだと気づいた。
「ずっと以前、住んでいたところに大きな沼があってね、よくスケッチに行ったものよ」
「沼」
と僕は反芻したが、スカーレットねえさんの瞳は時代を遡っているのだ。
「あの頃、あたしは一緒に暮らしていた男に逃げられて、なんとか縒りを戻したいって、そればかり考えてた」
ねえさんは、さもおかしそうにフフと笑うのだ。
「現実から逃げ出したくってねえ、山道をひたすら登り続けたの、すると突然、水草の繁った溜池が現れるのよ、本当にびっくりするほど唐突にね、水田の灌漑用水に利用されているのだけど、魚や蛇や亀やさまざまな生物が棲みついていたわ、溜池の周囲には固い雑草が群生して松や山桃の木が自生していた」
宙を泳いでいたスカーレットねえさんの目線が僕に注がれた。ねえさんの目の中に、久しぶりに僕の心が映った。
「あたし的には、古い沼なのよね」
雑草の生い茂った細い山道を登って、突然現れた太古の沼なのだ。僕は駅裏で見つけたスカーレットねえさんを思い出していた。僕たちにコーラを買ってきてくれた時も、ねえさんは男と逢っていたのだ。あんなことさえなければ、雨さえ降らなければ、僕たちはもっと自由だった。だけど反面、今だからこそ僕はねえさんを独り占めしていられるのだ。
「見つめると、沼があたしに囁きかけてくるの、外国の恐ろしいメロディーみたいにね、自生した椿の花が風に揺れて、ぽとりと花を水面に落とすと、花は淀みに浮かんで揺れうごくの、あたしはしばらくの間、人を不安に陥れる沼を見下ろしていたわ」
「なんだか、こわいよ」
僕は不穏な沼を覗き込んでいる気分だ。沼は数えきれない魂を吸収し、咀嚼してもなお飽き足らず、貪欲に唸り続ける。緑色のヒシの葉が水面を覆い、水底には大鮒や真鯉がそろりと尾びれを振って出番を待っているのだ。ねえさんは沼から次々と生まれ出る生命の循環と引き換えに、沼に何を捧げようとしたのか。
「あたしは沼に身投げなんかしないわよ、デデ」
ねえさんが僕を見てほほえんだ。まったく、ねえさんという人は千里眼だ。いつも僕の心を読みとってしまう。
「あたしは静かに緑の水を眺めていたの、沼に突き刺さった倒木が、まるで大きな棘に見えたわ、一羽の鳥が沼に棲息する生き物を物色して、大きく翼を広げて影を落とすと、くもった水面が緩やかに蠢いてね、得体の知れない振動音が聞こえてくるの、沼の活動が始まるのよ」
ねえさんが、ふう、と息を吐く。
「でもそこで摩訶不思議なことが起きたのよ」
僕の存在がカオスならば、スカーレットねえさんは摩訶不思議な存在そのものだ。
「大きく息を吸い込んだ時、急に笑い声が聞こえたのよ、あたし、目を疑ったわ、霞のせいではなく、目の前を数人の老若男女が音もなく動き回っていたの、あたしは反射的に木の陰に身を隠したわ、少ししてから様子を窺い、そろりと這い出てみたのだけれど、だれもあたしを見咎める者はいなかった、あたしは腰をかがめて、蕨の側に自生している春蘭を掘り起こそうとしたの、逃げて行った男が野生の蘭が好きだと言っていたから、なんとかこの春蘭でもう一度気を惹きたかったのよ、土ごとスーパーの袋に詰め込んで、あたしは額の汗を拭った、その時、背中で声がしたのよ」
―お嬢さん、どうじゃね、蕨は採らんのかね
「振り向くと孫の手を引いた爺さんが片手に蕨の束を握っているじゃないの」
―灰でアクを抜くんじゃがね
「お嬢さんと呼ばれて悪い気はしなかったけど、しつこく話しかけてほしくないのよ、爺さんは近くの寺の住職だと知っていたけど、あたしのショーを見に来る常連でもあるのよ、そう、デデがあたしの前に現れるずっと前からのね」
その住職なら、僕が工員だった時から劇場に通って来ていた。僕の隣に坐ったこともあるのだ。
―僧侶などと言う、人間の生き死にを目の当たりにしていると、人の世の無常を感じて重い気持ちになるけれど、ねえさんのように生きている証を披露してくれる人がいることはわしの死生観によい変化を齎してくれるように思うのじゃよ
「などと尤もらしいことを、神妙な顔つきで言うじゃないの、あたしはステージとは違う服装だったのに、住職はあたしだとわかっていたのよ」
―わしは、人の心を癒してくれるねえさんに敬意を表している、だから、老い先短い年寄りのために入場料を半額以下にしてくれないだろうか
「何が、だからなのか、このスケベ爺は自分だけは特別とでも考えているのかしら、あたしは花は好きだけど蕨は食べないの、て言ってやったわ、あたしが春蘭の袋を持ち上げてからにっこり笑った時、沼に亀が音を立てて転がり落ちたの、見ると、住職の喉仏が上下に動いて、傍らでおとなしくしていた孫の姿が見えないじゃない、沼の淵で叫び声が聞こえ、ようやく爺さんは自分の孫がよその男児に突き飛ばされたことに気づいたのよ」
―ねえさん、たすけておくれ
「孫を沼に落とされた住職の声だったわ、水草に絡まれて、小さな男の子の手足は自由がきかないし、住職はあたしの顔を見上げて懇願するの、住職の孫はよその子と亀を取り合っていたのよ、亀が勝手に転がり落ちたものだから孫まで沼に落とされたってことよね」
―ねえさん、おねがいだ
「ねえさん、ねえさん、て何よ、さっきまでお嬢さんじゃなかったかしら、寺の住職だけど、女を見れば涎を垂らして発情するほど衒気の余った爺さんなのよ、自分が跳びこめばいいじゃないのよ、孫の一大事にわが身を捨てることもできないとは、なんという生臭坊主なのかしら、爺さんは水面を見つめて動こうともしないのよ」
―ねえさん、たのむ、早くしてくれ
「時間を潰す間に子どもは濁った水を呑みながら、沼の深みへと沈んでいくじゃないの、あたしは仕事でもないのに、裸の太腿をこの助平な爺さんに見られたくはなかったのだけど、しかたなくフレアーの長たらしいスカートの裾を捲くってみたの、その頃のあたしは子どもなど大嫌いの部類に入るぐらいで、よその小生意気なガキが溺れようがくたばろうが与り知らないことなのよ、爺があたしを頼りにしているのがまったく気に入らなかったのよ、あたしはふと思い出したの、知り合いの女がハワイ帰りの小金持ちの爺さんを垂らしこんで、ちょっとした財産を手に入れた武勇伝のことよ、老後の世話を餌にすればたいていの年寄りは女の職種など問題にしないと、めでたく小金持ちになった女はグレードを上げたタバコをくわえて笑っていたわ、この爺さんの孫を沼から引っ張り上げて命の恩人にでもなっておいたら、よほどいいことでも起きるのだろうかと考えたけど、せいぜい寺に招待されて、あたしの嫌いな精進料理を振舞われるのが関の山よ、それどころか仏さまを笠に着て何を考えているやらわかったものではないわ」
―ねえさん
「住職の甲高い声であたしはわれに返ったの、ガスが吹き出しているような沼の水をたっぷり飲んで、子どもが横向きになり、体半分を澱んだ水に喰われていた、もがきもせず虚ろな目を半開きにしているのよ、あたしは下着が尻にくい込んで気になってしようがないのだけれど、それでも男児に手を伸ばしてトレーナーの裾をつかまえようとしたの」
―ねえさん、たのむ、とびこんでくれ
「インチキ住職の声が澄んだ空気に響き渡ったわ」
―ねえさんは弁天様じゃ
「自分が飛び込めばよいものを、住職はあたしばかりをけしかけて、あたしはずり落ちるようにして沼の際から踏み込んでいったの、予想どおり泥に絡み取られて動きがとりにくいのよ、数知れない蛇に巻きつかれたかと仰天してしまったけど、黒く変色した水藻の群れだったわね、ようやくつかんだ男児の足首をハンマー投げのように振り回し、勢いつけて放り投げたら、叢に落ちたハンマーの記録をとりに行く爺さんの足取りは軽やかでねえ、あたしは粘土状の泥にまみれた素足を拭う元気もなくなって、地面に腰を下ろしていたのよ、あたしの人生など澱んだ水ほどの価値もないと、この爺は内心笑っているにちがいないのよ、だけど爺が突如奇声をあげてね、爺のしゃがれ声は沼の水面に凍りついてしまったわ」
―坊、坊やあ、起きておくれえなあ
「爺さんはなんども同じ言葉を繰り返し、ピクリともしない孫の体を抱きかかえているのよ、爺さんの嘆きをよそに蕨採りの人達はあたりを徘徊しているの、自分たちの関心事以外は視界の片隅にも入っていないみたいに、あたしは意味をなさなかったあたし自身の行動にうんざりし、それ以上に爺さんのいいなりになってしまった情けない自分に腹が立っていたのよ、それなのに、すぐそばで屈託のない笑い声が聞こえてくるのよ」
―こりゃ、やわらかいよう
「よく伸びた蕨を手に中年の主婦が笑みをこぼしていたわ」
―たくさん採って塩漬けにしとけば何年も保存できるものね
「いい気なものだとあたしは舌打ちしたわ、人命救助に失敗し、着ているものはびしょ濡れで、せっかく採集した春蘭は横倒しになって葉っぱが折れているじゃないの、あたりを見回してあたしは奇妙なことに気がついたの、蕨採りの彼らは本当の人間なのだろうかって、最初よりもずっと人数が増えているのよ、どこから現れたものか見当もつかない、あたしが見ているのはあたし自身が作り出した幻なのではなかろうかって、とすると溺れた孫をかかえて泣き叫んでいる爺さんはやはり虚構の産物なのだろうかって、それともあたしと同じく現実の世界から迷い込んできた人達だったのかしら」
そうではない。僕は確信していた。スカーレットねえさんこそが彼岸の人なのだ。
ねえさんが、ふう、と息を吐く。
悟るのは坊さんに限ったことじゃない。脳みそで悟るものでもない。ねえさんは煩悩を知り尽くして、人生に体当たりしている内に、彼岸に身を置けるほどの悟り人になったのだ。
「この前デデが言ってたでしょ、彼岸のことよ、もしかしたらあの沼は彼岸と繋がっていたのかもしれないわねえ」
いつもながら、感心するぐらい事務的な女性刑務官が僕を誘導する。
面会の席で真正面から顔を合わせたスカーレットねえさんの指に、赤い絵の具が付着している。赤系統の絵の具で、絵を描いているのだ、きっと。
「もうすぐよ、ここを出るころには『喜びの天使』が手に入るから」
ねえさんの頬が紅潮している。その時、僕は閃いたのだ。
「ねえさん!」
「何よ、デデ、びっくりするじゃないのよ」
ねえさんが大きな目を、もっと大きく見開いている。無理もない。僕の声に女性刑務官も驚いた様子だったのだ。
「僕らの劇場には看板ってものがないよね」
「そうだったかしら」
「そうさ、プラカードには、スカーレット嬢、大熱演とかの呼び込みのセリフはあるけど、劇場の建物に看板揚げて、キューピッドの絵なんかを描いたらいいんじゃないかな、と思って」
ねえさんの頬が見る間に桜色に染まった。
「新しい劇場になるのね」
「うん、それで看板には『喜びの天使』って文字を入れるんだ」
「いいわ、イケてるわ、すごいわ、デデ」
僕たちは興奮して、しばらくの間、笑い声を押し殺しながらはしゃいでいたのだ。
「ねえさん、絵の具を差し入れようか?」
「あん?」
スカーレットねえさんが僕を見つめた。ねえさんは手を伸ばして僕の頬を引っ張りたがっているのだ。だから僕は反射的に二人の間を遮っている透明の壁に頬をくっつけた。
「デデちゃん、待っててくれる」
「もちろんだよ、待ってるよ」
スカーレットねえさんの目尻に小鳥の足跡がひとつ増えた。ねえさんの背中には青い翼が生えているのだ。僕は本気だけれど、スカーレットねえさんはここから出たら、そのままどこかへ舞い飛んでいくのではなかろうか。青い翼を大きく広げて。でも僕は待ってると答える。たぶんそれが愛なのではないかと思えるからだ。
【佳作】鈍色の蛍(よしのかい)
「─ なにやで。こんなん、ごっつ高うついたんちゃうん?」満更でもない風に浮かべた久方振りの笑みを見てやっと安堵した。
きちんと柄を染め出した生地が背筋の伸びた肢体に良く馴染んで見える。
「─おおきに。ええなあ─せやけどうち、変われへんわがままやん。もういい加減、うんざりちゃうん─?」言いながら水鳥の淡い色合いの染付けを見回しまた笑窪を見せると、美沙は形の良いピンクの唇をこちらに突き出し口づける真似をした。
『─AB型やで。とにかく、ややこしい性格なんよ─』折に触れ機嫌を損ねては、宥めに根負けした体でそんな風にちょっと鼻に掛かる甘え声で胸に頬を擦り寄せて来たりする。
小顔で黒目勝ちな瞳、小悪魔的な風貌が評判で嘗て経営していたスナックは繁盛していたが体調を崩し閉店を余儀なくされた。
伊蔵は店の常連で、来店の度深夜二時のラストまでいて帰りの食事に伴う繰り返しの内に男女の関係になった。
『─なんか歌舞伎役者みたいな名前やね。かっこええわ。その細面にも似合うて─うちな、馬面が好みやねんか─』何度目かの食事の後、どちらが誘うでもなく足を向けたホテルのベッドで美沙が笑みを浮かべそう言い、その時初めて左の頬に笑窪を見つけた。
「─ええ生地やろ。柄も気に入ってくれたか?」伊蔵がそう言うと美沙は戯けた風に翻る様に振り向き、満面の笑みを向け大きく頷いた。
時折見せるちょっと大仰な仕草が少女の様で可愛らしい。
艶っぽい容姿に隠れたそんなところも気に入っていた。
「─辛ないか。ちょい歩かせてしもうたさかい─」そう問うと額に滲んだ汗を左の手の甲で拭い、
「─今日は体調もええの。いけるで─」笑みを崩さずにそう応えた。
美沙が突然の発熱に伏せたのは半年程前のことだった。
「─なんや─身体が怠う、て─起きられへん─えらい腰が、きつい─」箪笥が二竿とドレッサーがあるだけの狭いアパートの六畳間の畳敷きの寝間で深夜、布団から腕だけ伸ばし途切れ途切れに喘ぐ様に言いながら並べた横の布団にいる伊蔵の短髪に触れて来た。
頭の地肌に触れた指先が異様に冷たく、寝入りばなのぼんやりした視界の端にもその腕が震えているのが分かった。
緊急搬送された病院で腎盂腎炎と診断された。
過労に因る免疫力低下が要因だろうと医師に言われた。
「─ほれ。言うたやろ。無理し過ぎなんやで─」そう言うと美沙は点滴のチューブを左手の人差し指でゆっくりなぞりながら、ぼんやりした眼差しを向け薄く笑った。
「─それでな。何やら入院加療が必要らしい。色々検査もある─店も休まなな。何より身体が第一やさかいな─」伊蔵が言うと美沙は俄かに顔を曇らせ、
「─なあ、─あんたは居なくなれへんよな─」独り言の様にそう口籠もるように呟いた。
一週間の入院で済んだが、安静を厳重に忠告された。
「─何や。テレビもつまらんなあ─携帯も飽きたわ。早よ、店開けたいなあ─」いかにも退屈を持て余した風に畳の床に尻を着け両脚を長く伸ばし、身体を左右に捻るストレッチをしながらこちらを見て不満げに唇を尖らせる様子が可笑しくて思わず声を立て笑うと、
「─あんたはええなあ。いつも浮世離れしてる風で─悩みごとなんてないやろ」美沙はのんびりした口調でそう応えると俄かに声を落とし、
「そう言うたらな、─」と言葉を続けた。
「─しばらくしてへんさかい─しゃあないかも分からへんけど─」そう言い暫くの間を置き、右手の親指と人差し指に摘んだ長い赤茶けた毛髪から不意に目線を逸らせ伊蔵の目をじっと見据えると、
「─コートにな。うちの買うたったコートに付いとってん。外側にどこぞの飲み屋の匂いと、安もんの化粧と─女の匂い。ほんでこれは内側にな─」耳許に真顔を近づけ囁く様にそう呟いた。
「─し、知らんで、わしは─全く、身に覚えなぞ─あらへん─」つい訥々とそう応えると、美沙は今度はさも可笑しそうに左手を宙にひらひら浮かせ声を立て笑い、
「ほんまに嘘つくんが下手くそやわ。わしの癖は分からへんわよね─小鼻をひくつかせてんねん─」そう言うと不意に真顔になり同時に左の掌を高みから振り下ろして来た。
つい呑みに出たのが失敗だった。
昔から酒が入ると気が大きくなりまた浮気癖も顔を覗かせる。
『─なあ。もう借家住まいは嫌なんよ。ぼちぼち持ち家が欲しいわ─』そんな美沙の願いを叶えるべく同棲から間もなく二人で貯蓄を始め呑み歩きも控えていたのだが、今朝方入った雇用先からの連絡が気持ちを落ち着かなくさせていた。
東日本の震災後、実入りが良いと紹介を受けた原発構内の仕事が元請けの会社の社員の大きなミスにより下請けまでを含む謹慎措置になったのだと言う。
裏社会から足を洗い以来職方の仕事を探し勤めては、いつか手に職を付けなければと考えながら漠然と転々として来た。
収入の多い原発の仕事が無くなることは大いに痛手だ。
道を踏み外したとは云え漢として渡世を謳って来た自分が、細々と店を商って来た美沙に例え束の間としても生活の今後を頼る様な恥を晒すことは憚れる。
まだ西成にでも行けば日雇いでも仕事に就けるのだろうか。
もやもやとそんなことに思案を巡らせてる内に、
「─ちょい、おかん見てくるさかい─」と外出の為の嘘が口をついて出た。
伊蔵の母親は二駅離れた肥後橋の借家に住んでいるが交通事故で右脚を不自由にしていて、帰省すると度々様子を見に行く様にしている。
伊蔵が福島に行き留守の間は美沙が面倒を足繁く見に行く。
美沙は伊蔵の母を「肥後のおかん」と呼び二人は本物の親子同然に親しくしていた。
母親のことは随時気掛かりだが、その日は先ずこれからの身の振り方を一人になり考えたかった。
直ぐにカウンターの奥に指定席のある嘗ての行きつけを思い出した。
だが馴染みのその赤提灯は既に暖簾を下ろしていて、店を探し歩きながら飲み屋街の外れにあるスナックに行き当たった。
ドアを開けると薄暗い店内の煙草にきな臭さが入り混じった独特の匂いが美沙の店を思い出させた。
「─おはようさん。お初やわね」のんびりした口調で店のママが出迎えた。
「まだいけるんか─」そう問うとママは徐に腰を屈めビールの小瓶をカウンターの下から取り出し、目の前に置かれた百円ライターで器用に蓋を開けた。
「一本はサービスやで─」言いながらグラスに注ぎ笑みを向けて来た。
「─何や、ベビーフェイスやな。可愛らしいで─」丸椅子に腰掛け直すと、垂れ気味で黒目勝ちの円らな瞳に向き合い、
「─ならわしも挨拶代わりや。ボトルを入れてもらおか」そう言うと乾いた喉にビールを流し込んだ。
乾き物を花柄の皿に盛り合わせながら店内に流れる有線の演歌に合わせ低く口ずさむグロスの艶っぽい紅の唇を見つめていると、俄かに欲情が頭を擡げあげ掛けているのに気づいた。
カウンターを照らすオレンジ色の薄暗い照明が淡いピンクのサテンのドレスの下の肉づきを余計豊満に魅せている。
「─一人で、やっとるんか」問うたその声が半ば上擦っている様に思え、伊蔵は咳払いすると不自然に店内を見回した。
左腕の重みで目覚めた。
赤茶け艶のない髪が顎に触れ、化粧の香は憶えがある。
飲み始めてから閉店まで客は自分だけで、隣に座ったママの身の上話を聞かされながら確かに肩を抱き寄せたのだ。
深い寝息を立てている唇を見つめながらふと美沙の顔を思い浮かべ、何とも言えぬ切ない気持ちが迫り上げて来た。
ふと気づき携帯を見るとメッセージの着信があり、確認すると彼女からだった。
『─おかん、変わりないんか』短いその文言に目を瞑る思いで、
「─阿呆やなあ─堪忍やで─」口の中でそう呟くとそっと身動ぎし、委ねるように凭れている腕の温もりから静かに離れた。
「─おかん、元気やったん?」まだ酒の抜け切らぬ重い頭を項垂れるように昼近くに帰宅するとそう声を掛けられた。
「─あ、─ああ。─みぃによろしゅう言うとったで─」少しの躊躇いの後そう応えると、美沙は狭い台所で何かを刻みながら、
「─そうか。元気ならよかった。─ほんで泊まるなら泊まるで、連絡くらいしてや─」と背を向けたまま短く言い、また小気味良くまな板に包丁の音を響かせた。
過去にも移り気の向くまま女を抱いて来たが、美沙と暮らす様になってから他の女に気を外らせることは無かった。
無為に背を見つめ言葉を探していると、
「─そうや。お醤油が切れそうなんやわ。あんた悪いけど買うてくれへん。あ、臍乃屋はんやで─」その言葉に救われるように立ち上がり、
「うん」とだけ返事をすると伊蔵はまたコートを羽織り外へ出た。
近くの乾物屋を雑多な物の調達の馴染みにしている。
年配の夫婦が旧くから営んでいて大手のスーパーに圧された商いを案じ、なるべく他所では買わないようにしていた。
「─こつこつ商うとる店が先やないか。安売りは情けやないで」自身の商売を鑑みてか、美沙は唇を尖らせては口癖のようにそう言っていた。
頭上で大きな羽音がし、見上げると直ぐ近くの電線に大柄なハシブト烏が止まりこちらを見下ろしている。
道行く人々の移動を監視する様に太い嘴ごとを動かしている。
目線が合った時不意に高い一鳴きを上げ、羽を何度かばたつかせ今度は注視をぴたりと自分に止めた。
「─しゃあないやろ。してしもたことはもう─」暫く烏を睨むように見上げた後目線を戻しそう口の中で呟くと、伊蔵は猫背を更に丸めるように長い足をとぼとぼと乾物屋に向けた。
「─かんにんや」叩かれた右の頬を三本指の先で摩りながら頭を深く垂れ詫びると暫くの間の後、美沙は今度は声高に笑い始めた。
「─ふうん。ほんまに謝ってるな。─しゃあない。許したるわ」その言葉に半ば安堵して顔を上げ、
「二度とせえへん─」そう詫びを重ねると、
「当たり前やで。うちも二度目はあらへん」きっぱりした口調で言い切り、
「─せやけどな、あんたの謝り方は好きやで。逃げも隠れもせえへん。いつも何か、そんな覚悟じみた感じがしてな。」そう付け加えまたさも愉快そうに声を立て笑った。
伊蔵には幾つかの前科がある。
皆傷害の案件だが逮捕される度、非は自らに無いのだと主張して来た。
「─売られてん」警官に詰られると決まってそう返して来た。
実際自分から先んじて手を出すことはしない。
若い頃から長身で一見優男の風貌に目をつけられては喧嘩を売られ降りかかる火の粉を払う繰り返しの果てに、風聞から裏社会の組織にも誘われ実際に組み込まれたりもしたが生来は諍いを好まぬ小心者も自覚している。
四人家族で職人気質そのまま厳格な父と年嵩の離れた兄は記憶にある限り折り合いが良くなく、事あるごとに諍いを起こしそれは朝晩を問わず食卓を囲む時に頻繁だった。
泣きながら必死に取りなそうとする母と飛び交う怒号─。食卓はいつも張り詰めていて団欒の雰囲気は乏しかった。
美沙と初めて夜を共にした朝、碗から立ち上る味噌汁の美味そうな湯気を見つめながら、
「─わしな。中学ん時いじめられっ子でな。ちいと背が高いだけで先輩やらにしばかれたり蹴られたりな。─それが嫌で─学校もよう行かへんようになった─」そう呟くように言った。
「─そうなんや」茶をゆっくり啜りそう応えながら、浮かべるその笑みが堪らなく和やかに見えた。
欠片でも自身の身上を自ら他人に吐露したのは初めてのことだった。
「─うん」そう応え、笑みを返し軽く頷くと、長い間自分の中に閉じ込めていた蒼茫とした何かがやっと癒える様だった。
「何時から舞うんやろな。蛍─」わざと灯りを落とした部屋からの窓外を仕切りに気にしながら美沙が問うて来た。
蛍たちは沢周りの低地から杉の樹の高い木立の天辺にまで圧倒的と云う表現が相応しいくらい見事な乱舞を見せるのだと言う。
「─陽も落ちたさかいな。もう舞うてるやろう」そう応えると美沙は帯留め紐を一度解き、器用にリボンに結び直した。
想像してた以上の光景だった。
時折小枝や葉に止まり放つ幻想的な光がやがて舞い上がり、夜空の星々との重なり合いが思わず息を呑ませる。
身動ぎもせずその情景に圧倒されながら繋いだ美沙の掌が汗ばんで来るのを感じた。
「─綺麗、─すごいなあ─」深い吐息と共に吐き出す周囲の観光客たちの感嘆を聞きながら伊蔵は、
「─鬼火、─」と呟いた。
「ほんまにすごかったなあ─!初めてやわあ、あんなん─ まるで人慣れしとるみたいに近づいても来んねや。ちいと驚いたわ─」興奮冷めやらぬ様子で美沙は笑うと、備え付けの冷蔵庫からビールを取り出し栓を抜いた。
「─どないかしたんか。ずうっと黙って」注ぎ口を注視しながら美沙が言い少しの間の後、
「─鬼火、─思い出したんや─」注がれる琥珀色の液体に立つ泡を見つめながら伊蔵が口を開いた。
「─鬼火─?」美沙が返すと、
「─わしがまだ、成人する前な─」と話を続けた。
伊蔵は父親が五十を過ぎた時の子どもで長男とは一回り以上年嵩が離れていた。
父親は建具の職人をしていて気難しく仕事柄の気質もあってか一徹そのものであった。
「─とうとう終いまで、わしのことは認めてくれへんかったなあ─」先年二三回忌の法要があり久方ぶりに会話した際も苦笑を混じえそう話していたが、成績や生活態度、様々を事細かに揶揄されることを嫌い、高校卒業を機に逃げる様に海運学校に進学した兄とは反りが合わなかった。
「─そんなんあれへんねん。ほんまはあんたに期待しとったし、行く行くを頼りたかったんやさかい─」母はそう言って穏やかに窘めたが、
「─いや。事あるごとに、あかん。ものにならへん言われてきてんで─」兄は眉間に皺を寄せその言葉を払う様に掌を自分の目の前に泳がせながらそう返した。
伊蔵が幼少の頃の記憶には親子の激しい言い争いが断片的だが多々残されている。
あまり要領の良くない兄は父の顔色を窺うなど意識しなかったのだろう、些細なことで怒らせては諍いの元に自ら火を起こしていたのだと母が後年笑っていた。
「─何でん望む物は買うたっとったんやで、あん子には。そら厳しうもしたけどな。─あの人もどんくさいさかい、そんなんでしか愛情を示されへんかってん。」法事が済み寺からの帰路タクシーの中でそう言い、
「─あんじょう伝わらんなあ。─心はあんじょう─悲しいなあ。家族やさかいな、余計─」そう付け加え目線を俯けていた。
夏真っ盛りの八月の初旬だった。
油蝉の鳴き声に日暮らしの甲高い鳴き声が混じり始めた頃、庭の駐車場に入る父の軽トラの音が聞こえた。
「─あら、今日はちょい早いんかいな─」台所にいた母が振り向き、伊蔵も青紫に腫らした目を上げた。
当時伊蔵は中卒の後進学せず父親の伝で型枠大工の職に就いたのだが、間もなく先輩の職方とトラブルを起こしてしまい謹慎を言い渡されていた。
理由もなくいきなり因縁をつけ最初に頭を小突いて来た相手の非を主張し、先方の親方もそれは承知していたのだが折り合いの難しさからとりあえず伊蔵を休ませることにしたのだった。
鬱屈し塞いだ気持ちは直ぐに荒んだ行動に代わり夜の街に出歩いては喧嘩を繰り返す様になり、顔や身体の傷は絶えなかった。
「─どないしたんやろ─中々来えへんわね。資材の下ろしが大変なんかいな─あんたちょい行って、手伝うたってや」忙し気に夕餉の支度をしながら母が言った。
近くに止まっているのだろう。
カナカナカナ─と響きの良い鳴き声を聞きながら納谷に手を加えた駐車場に行くと、軽トラの荷台に突っ伏す形で父がいた。
瞬時に異状を察知した。
恐る恐る近づき腰の辺りに触れたが微動だにしない。
「─おと、ん─」掛ける声が上擦り震えた。
徐に覗き込んだ白髪の短髪の下に半眼の日焼けた赤銅色の顔があった。
息をしていないことが分かった。
少しだけ開いた口元から白濁した泡と涎が垂れている。
喧しい蝉の鳴き声が周囲の音と共に一斉に意識から遠去かり生唾を呑み込む音だけが耳の奥で聞こえた。同時に胸の鼓動がどくどくどく、と急速に迫り上がると伊蔵はその場に膝からへたり込んだ。
脳出血が死因だった。
通夜、葬儀が済み焼場に到着しても涙が止まらなかった。
『─自分に非はあらへんのやろ。なら、それでええやないか』前の晩、最後に交わした会話だった。
不登校の時も職方との諍いの時もそう言ってくれた。
いつも口元を真一文字に結び厳格だったが、父が好きだった。
半ば茫然と骸が焼き尽くされ骨になるのを待ちながら兄の様子をぼんやり見ていた。
打ちひしがれ憔悴している母に代わり、忙し気に動き回っている。
だが通夜の晩も葬儀の時も涙を流してはいなかった。
弔問客と何やら会話しながら浮かべた兄の笑みを見た時、また涙が溢れ出て来た。
居た堪れなくなり涙を左の手の甲でぎゅっと拭いながら外に出ると、降り頻る雨に抗う様に長い煙突から真っ直ぐに煙が上がっていた。
煙の黒色が徐々に白に変わるのをぼんやり眺め、立ち籠める匂いが父の匂いなのだと思うと思わず嗚咽が漏れた。
歪んだ顔を上げもう一度煙突を見上げた時、立ち上る白色の煙の後を追う様に丁度人の顔ほどの大きさの橙色の火の玉がふわっと舞い上がった。
「─鬼火、や─」まるでその呟きに呼応し小躍りするみたいに左右にゆらゆら振れながら天に昇るその火の塊が、湧き上がる涙と目に入り込む雨の雫で幾重にも滲んで見えた。
「─なんかな。あん時のこと思い出してな─」苦笑混じりにそう言うと、
「─そうか。ええおとんやったんやね。─間違いのう、あんたも似とるんやろな。─ええ人やさかい─」美沙はそう言い笑みを浮かべた後、残りのビールを音を立て美味そうに飲み干した。
「─明日の晩、また楽しみやなあ。」まだ興奮しているのか美沙は天井から吊るしてある蛍光灯のナツメ球の微かなオレンジの灯りに華奢な両の手を翳し、あたかも蛍の動きをなぞる様に利き手の左の人差し指を愉しげに宙に描いて見せている。
「─そないに喜んでくれてよかった。─旅行なんぞ連れて行ってやれへんかったさかいな。」欠伸混じりにそう応えると美沙は少し笑い身を起こし、
「─ほんまに嬉しいで。おおきに」と言い頬に口づけて来た。
退院後数ヶ月が過ぎたが折に触れ怠さから日常でも身体を横たえることが多くなり、店も開けられず鬱屈を露わにする様になった美沙を何とか元気づけようと旅行でもと思案していた時、偶然携帯のSNSで新潟の観光案内から蛍の記事を見つけた。
以前に郷里の話をしていた際、蛍を見た子どもの頃のことを懐かしそうに話していたことを思い出し計画した。
「─窓開けて寝たんが、いかんかったんかなあ─」額に手を当てながら怠そうに美沙が言った。
クロークで体温計を借り計ると微熱がある。
「─無理せん方がええな。─何やったら、予定繰り上げて早めに帰るか─」そう言うと、
「嫌やで。今晩も見るんや、蛍。こんなん大したことあらへん─」そう応え笑って首を振った。
入院以降、美沙は体調を崩すことが多くなっていた。
『─風邪やなんか殆ど引かんかったんやで。こないだでつい、身体に休み癖がついてしもたんや。怠け癖やな─』本人はそう自嘲するが不安だった。
春先からあまり食欲も見せず、心なし身体も痩せて来ているように感じる。
時折下腹の痛みもある様で市販の鎮痛剤で紛らわせていた。
「─なあ。帰ったらいっぺん、検査に行ってみいへんか─」そう言うと美沙はまた笑いその言葉を払う様に左の手をひらひらして見せた。
退院時の定期通院の勧告も聞かずにいた。
『─大丈夫や。お医者は好かんねや』そう嘯いて一度も受診していない。
「─何や、心配症やなあ。あんな、うちの身体やさかいうちが一番知ってんねんて」そう言いながらまた丁寧に畳んだ浴衣の生地を愛でるように頬を寄せた。
「─せや。そないに浴衣気に入ったなら、着物もええやろ。今度買うたるで─」その様子を見てそう言うと、美沙は顔を輝かせ嬉し気に片笑窪を見せ幾度も大きく頷いた。
昼過ぎに熱は少し上がったが、宿に頼み用意してもらった素麺を啜り薬を飲み休むと楽になった様子で夕刻には起き出した。
「─うまいなあ、このイカ。糸かぼちゃ言う、このお酢のもんも─」そう言い旺盛な食欲を見せると、珍しく膳を平らげた。
「─なんでもな、梅雨時はスルメイカが旬らしいで─ほんまに甘いなあ─せやけど、お前がようさん食べると安心するわ─」そう言い安堵した風に溜め息を吐き徳利に指を伸ばすと美沙は、
「─あかん、もうあかんで。また灯りのない夜道を歩くんや。手え引いてくれるんが千鳥足やなんて頼りんならんわ─」そう窘め綺麗な眉間に小さな皺を寄せ笑った。
漆黒の闇に煌めく華が咲いている。
杉の葉に止まる沢山の明滅がまるで呼吸している様だった。
『生暖かい気温と、月明かりの無い好条件が幾晩も続くのは珍しいんですよ』と宿の仲居が言っていた。
息をする度湿った深い新緑の匂いがする。
寝みあぐねているのか、遠くでカケスの低く掠れたひと鳴きが聞こえた。
温泉街のすぐ近く、多宝山と云う山麓から汲む清水の名が「冬妻蛍」の由来だと云う。
幻想的な光の舞いを感嘆する観光客たちの騒めきに混じり沢を流れる水の音も確かに聞こえる気がする。
思わず耳を欹てた時、ついと一筋の光が近づき浴衣の右の袖に付いた。
「─ほうれ、捕まえた─」美沙がそっと袖を上げ、嬉しげに指を寄せ左の掌に乗せ渡すと、蛍は少しの間明滅させた後不意にその光を消した。
「─ 何やの。─動かなへんくなったら、一向に綺麗ちゃう。ただの虫や─」俄かに萎えた声でそう言い、闇の中暫くの間じっと自分の掌を上げ目を凝らしていた。
「─ ずうっとな─ずうっと─続くもんなんて─あらへんねやな─儚いもんやなあ─」その声が俄かに潤んでいた。
「─美沙」伊蔵が思わず声を掛けると同時に、
「─帰るわ─」美沙はそう言い掌の上の小さな亡骸を払い落とすと、くるりと背を向けた。
「─どないかしたんか─」突然の振る舞いを解せず追いながら問うたが、振り向かず応えもしなかった。
その晩、美沙は高い熱を出した。
「なあ。あんたは─いなくならへんよな─」いつか聞いた問いだった。
「─何や、何を言うてんねん」額に当てたタオルを冷やし交換してやりながらそう応え笑うと、
「─みんなな。みんな、うちの前から─おれへんようになってまうねん─」そう言い潤ませた眼差しを向けて来た。
翌朝には熱も微熱までに下がり帰路につけたが、長い道すがらも美沙は表情を曇らせたままだった。
「─墓参り、行かなな─」列車の窓外に流れる景色を見つめながらそう呟くと伊蔵に目線を移し、
「─もう何年も行ってへんさかい─」と言った。
翠雨が鋪道一面に跳ねている。
傘に落ちるはっきりした雨音の規則性が耳に心地よく聞こえた。
背の高い針葉樹に二羽の小鳥が戯れ合うように餌を探し忙しなく枝を上下している。
時折動きを休め餌を啄むと、そのまま嘴を別の一羽の口元に運んでいる。
「─メジロや─夫婦仲ええさかいな─」伊蔵が枝を見上げ笑った。
やがて上を通る太い電線から雨を集めた大粒の雫が小枝に落ちると驚いた一羽が細くひと鳴きし羽搏き、もう一羽も追随し互いに纏わる様に雨空に飛び去って行った。
「─まだ、しんどいんとちゃうんか。何も帰りに寄らんでも─」整備された園内の敷地を歩きながら伊蔵が言うと、
「─夢見てな─昨夜。熱のせいか寝苦しうてなんや、何遍もおかんが出て来てな─あんたの話のせいもあるんかな─」目線を俯け、濡れそぼる足元を見遣りながら薄く笑いそう応えた。
貝塚にある市営の公園墓地は天候の加減で大阪湾、淡路島まで眺望することが出来る。
「─今日は雨降りやさかい、景色も残念やわ─」そう言うと立ち止まり雨の景観を見回し目線をまた相合い傘の柄の先の伊蔵に戻し、
「─ようある話やけどな。うち、おとんのほんまの子やあらへんねん─」と雨音に紛らす様に言った。
花の名をつけた区画毎の墓があり、美沙の母は「紫陽花」の区画に眠っている。
丁度雨降りに鮮やかな佇まいを見せ、今日は薄紅の紫陽花が雫を滴らせながら林立していた。
「─おかんの好きな花やねん。まだ一緒におる時、おとんが墓買うてくれた─寿陵(じゅりょう)やら言うてな、生前にお墓買うのんはええんや─。好きな花毎年咲けば、それだけでお供えや。眠ってても淋しうないやろ─そない言うてな─。」伊蔵の翳す傘の下で線香の束に火をつけ、煙を手で追い立てる様に払い線香立てに供え、
「─ほんまはな、何よりいつも、─おかんを、─うちらを優先してくれてはった─」掌をじっと合わせそう呟いた。
「─知っとるやろ。飛田新地─」
墓参りを済ませ、一息吐きに寄ったカフェで冷えたコーヒーにミルクをたっぷり注ぎながら言葉を選ぶ様に話し始めた。
「─提灯、やな─」そう応えると美沙は薄く笑い、
「─あそこで見初められた娼妓の娘やねん、うち─ほんまのおとんは、─どこの誰か─知らん─」と言った。
大阪の花街は芸妓本位の遊郭と娼妓本位の遊郭との共存の割合が高く、後発の花街である飛田では娼妓本位の傾向にあった。
昭和三十二年に売春防止法が施行され娼妓の存在も危ぶまれたが、この法律では売春を『金銭等の対償を受ける目的で不特定の相手と性交すること』と定義づけている。つまり売春そのものや売春の相手になることは禁止しているがその行為そのものや売春の相手になること自体に対する罰則は設けられていない。
しかしそれに伴う勧誘や斡旋行為は罰則の対象になるため飛田遊郭を含め現存の風俗店の多くでは建前上は性交行為が禁じられており、万が一何かあったとしても客とコンパニオン間の自由恋愛によるものとして店側は一切関与も関知もしていないと言う立場を貫き通している。
自由恋愛を謳う以上、本気の恋愛に発展することも当然の成り行きであり、やがてその成就を愛人関係として、また法律上では成立しないが家族の括りとして密やかに囲い繋がる選択肢等、男女の顛末の在り方が様々であることは今も昔も変わらない。
伊蔵にも鮮明に憶えがある。
飛田新地と聞いて直ぐに「勢津」と云う名とその面影が浮かんだ。
飛田遊郭は各通りごとに在籍している女性の年代が異なる。
勢津は三十路手前で童顔だが日本的で妖艶な風貌をしていた。
「─うちはな、セックスが好きやねん」臆面もなくそう言い放ち切長の一重を細め笑っていた。
「─あんたの汗、ええ匂いがする─」行為に及び腰を激しくうねらせながらそう言っていた。
「─何や、汗に匂いの違いやなんかあるんか」息を荒げそう返すと、
「─あるで。あんたの汗はな、見た目とおんなじ─色男や─」快楽に耽切る様に切長の目を閉じ、長い黒髪を振り乱しながらそう言っていた。
見た目より明け透けな物言いと偽りのない感じが気に入り通った何度目かのある日、勢津の左腕に細かな刺し痕を見つけた。
明らかに注射痕だった。
「─いつからやねん─」腕を掴み上げ率直にそう訊くと、
「あははは─バレてもうた。もう一年以上前からや」勢津は悪びれる様子もなく笑い赤い舌を出し、
「ヤル前にな、打つのがいっちゃんええねんで。あんたも試してみぃへんか─」そう言い声高に笑った。
伊蔵は無言でその肩を引き寄せ顔を上向きにすると頬を強く叩いた。
勢津は驚いた様に伊蔵を見つめていたが少しの間の後、薄い唇を歪めまた笑い、
「─捨てたんや。何もかんも─うちを縛りつけとったもん、みぃんな捨てた。自由やねん、うちはもう自由やねん。─何や、今度はあんたが縛りつけるんか─なら、もうええ。─二度と来んどいてや。自分かてヤクザもんやないか─」途中俄かに真顔になると半ば吐き出す様にそう言い、背を向け階段を降りて行った。
気乗りのしないまま組み込まれた裏社会で薬物の悍ましさと依存症の顛末を嫌と云うほど見聞きしていた。
勢津の白く柔らかな腕には無数の注射痕があった。惚れた腫れたではなく、つい先刻の彼女の意味深な言葉も含め何とかしてやりたいと思っていた。
だがその僅か数日後、再び訪ねた時勢津は既に店に居なかった。
「─何や、いきなり辞めてもうてな。行き先もよう言わんと。電話一本やで、呆れるわ。ええ歳して義理もへったくれもないんかなあ」店の女将はそう言うと不機嫌に眉を顰めていた。
暇を見ては界隈の店を当たり、伝手を頼りに行き先を探してみたのだが見当がつかなかった。
だが数ヶ月が過ぎたある日、小さなシノギの終えたミナミの繁華街で勢津を認めた。
明らかに自分と同業と思しきいかつい男と腕を組み、愉しげに笑っている彼女の頬は不自然にこけていてそれが何に因るものなのかは容易に想像出来た。
『─みぃんな、捨てたんや─』不意に思い返したその言葉に彼女の笑顔を照らし合わせ、伊蔵は以降を気に掛けることを辞めた。
「─おかんな、Aやねん。でな、おとんがO─あり得へんやろ。うちのAB─」笑みを崩さずそう言い、氷に阻まれ混ざり切らず、焦げ茶より黒に澱むミルクの白を時折ストローの先で戯れるように突きながら水滴の汗をかいているグラスを見つめ、
「─中学ん時、保健の授業で知ってな─丁度そん時─おとんが病気で手術せなならんようなって、血液型わかってん─あり得へんことやけど苗字まで、違うとることもな─初めて知った─」と続けた。
「─うん」伊蔵が咄嗟に返答に窮しそう頷くと、
「─けどな、ええおとんやった。あんたんとこと同じ─優しうて、頼りんなってな─」そう言い手元を止めふと目線を俯けた後、
「─血の繋がりなんて、どうでもええことやった─」と小さく呟いた。その耳に、
『─他人やろ!親気取りはやめといてんかッ─!』そう自らの怒声が蘇ると口元から俄かに笑みを消した。
愚にもつかぬ母への無言の反抗を窘められ、つい口をついた言葉だった。
「─なあ、おとんは何で─たまにしか家におれへんの」問うたその声が上擦り掠れた。
気づいた血縁についてどう切り出したものかと思案した挙句、いつもの二人切りの夕餉の時に努めて冷静を意識しそう訊いてみた。
「─出張が多いさかいな。仕方あらへんのや─」いつもと同じ返答に一瞬躊躇ったが、
「─ほんまの─親やないからか─」思い切ってそうぶつけてみた。
母は目線を上げぼんやり娘を見つめ、暫くの間の後、
「─何を─阿呆なこと言うとんのや─」声を上擦らせ、やっとそう応えた。
指先が震え持っていた箸を落とし、いつもは優しい眼差しが怯えたように揺れていた。
美沙は不意に泣きたくなりその後の言葉を呑み込むと、
「─かんにん」とだけ言い席を立った。
その晩、遅い時間に出生からの経緯の全てを聞かされた。
母は泣いていた。
知るべきでは、問うべきでは無かったと悔いながら、しかし花街で自らを売り生業を立てていた母から産まれた自身をさえ穢らわしいと思った。
「─何や、きたならしいな─!うちなんか─生まれてこな、よかった─」思わずそんな言葉が口をついて出ていた。
それから暫く母を無視する日々が続きそんな折、家を訪れた父が見兼ねその振る舞いを窘めたのだった。
心臓の施術を間近に控え、明らかに体調を崩していた父を罵倒した。
意味不明の感情の行き場が分からなかった。
『─かんにん。か、─かんにんな─どないしても、児が欲しかったんや─』嗚咽に途切れ途切れのその声が、優しかった母の面影を思い浮かべる度に胸の奥を深く抉る。
「─幸せになりたかった─ただ、それだけやったのに─」深い贖罪を訴える様に見上げた目線を伊蔵に向けた。
「─きっといろんな理由で、あそこにいなならん人たちがおる─しんどい事情かて、ようさんあるんや─」伊蔵はそう言うと優しい眼差しを返し、
「─生きな、ならんからな─」と言葉を加えた。
その晩、美沙は酒を過ごし珍しく酔った。
トタン屋根に落ちる雨音の跳ねる間隔が強く短くなり、風向きなのだろう、離れた場所にある踏み切りの遠い警告音が疎らに紛れ込んで聞こえて来る。
「─うちな。男好きのする顔やろ。おかんに似てるねん。─」酔眼を揺らし伊蔵の左腕を枕に凭れ鼻に掛かる甘え声で美沙が呟いた。
「─男好きって何やねん。可愛らしい顔しとるで、自分は─」笑ってそう応えると、
「─やっぱりな、蛙の子は蛙やな。おかんをあんなけ詰っといて、おんなじやわなあ─水商売やなんて─」怪しい呂律でそう言い自嘲する様に笑った。
「何言うてるねんな。立派に商うとったやないか」宥める様にそう言うと今度は不意に瞳を潤ませ、
「─やっぱり、あんたはええ人やなあ─」そう言い胸に縋りつき声を上げ泣き出した。泣きながら、
「─なんもなくてええ。─なんもいらへん─ただ幸せがええ─なあ、お母ちゃん。なあ、─お父ちゃん─」幾度も幾度も伊蔵の胸の中で声を篭らせそう繰り返し、やがて眠りについた。
翌朝、目覚めると布団の中に美沙は居なかった。
とつんとつん、と薄い鉄板を弾く音が聞こえ雨はまだ降り続いている様だった。
「─みぃ」半身を起こしそう呼ぶとやがて水洗の音がしトイレのドアを閉じる気配が聞こえたが、一向に足音がしない。
「─みぃ。何しとるんや─」暫くの間を置きそう言い立ち上がり見に行くと、
「─何や、─変やねん─」そう言い、ドアの前に立ち尽くす美沙がいた。
「─何が変やねん─」そう問い返すと少しの間の後、
「─生理でもないのに、血が出る─こないだからやねん─それに、ずうっと下腹がごっつ痛うてな─」蒼白にそう応えた。
「─通常は女性ホルモンの作用によって引き起こされるのですがね。経血がお腹の中に逆流することで発症することもあります─」エコー写真の一枚一枚を確認しながら淡々と続ける医師のその言葉をぼんやり聞いていた。
『子宮内膜症』─
母と同じ子宮の病気だ。
「─初潮が早かったり妊娠回数が少ない、つまり月経の回数が多いだけ発症リスクが高まります─それで、今後の治療についてですが─」
「─まさか手術、─でっか─」医師の言葉に被せ伊蔵が口を挟むと、
「─更に詳しい検査の結果次第ですね。内膜症が大きかったり、他に良くない病変部があれば切除しなければなりません─」俄かに銀縁の眼鏡の上の眉間に皺を寄せ、初めてこちらに目線を向け医師がそう応えた。
外に出ると雨は上がっていたが灰色の雲で空は覆われたままだった。
「─鬱陶しいなあ、ほんまに─。せやから梅雨は好かへんのや─何やの、あの医者かて─東京弁やらも気に入らんわ」深い曇天を見上げ無表情に美沙が言った。
まだ濡れた敷石をセキレイが餌を探し時折立ち止まり啄み、長い尾を左右に振りながら歩を進めている。
やがてチチッ、と短い鳴き声が聞こえ、番いであろう一羽が舞い降りて来るとつかず離れずの位置を保ちながら同じ動作を繰り返している。
「─もうじきに夏んなる。わしは好かんけど、みぃの好きな季節やないか─」伊蔵が言うと美沙は鳥たちの動きを見つめながら小さく頷き少しの間の後、
「─遺伝、なんかなあ。─おかんと、同じ─子宮の病気─や、なんて─」吐息に紛らすようにそう呟いた。
「─玄米食がええんやて。食物繊維やな─後な、ブロッコリーや大豆や。─よしゃ、わしが工夫したるわ─」気持ちを取り成すように伊蔵が声を張った。
「─なんも普通でええて。おおきにな─」少し腫れぼったい瞼を擦り苦笑すると、狭い畳敷きの部屋の隅の釣鐘型のケージの中でカナリヤが小さく囀った。
「─やよなあ。ぽんちゃん」そう声を掛けるとカナリヤは小さな丸い頭を上げ、今度は応える様に長い歌聲を返した。
診断を受けた帰り、通りすがりのペットショップの店頭で美しい囀りに思わず二人共に足を止め買い入れた。
ローラーカナリヤは他種の黄や紅の単色に比べ混色の地味目だが特化して鳴き声が美しい。
名付けた時美沙は、嘗ての飼い犬や縁の下に勝手に住みついた野良猫にも同じ名をつけたのだと笑った。
「─ほれ、綺麗な聲やろ。眼も優しうて別嬪さんやで─」そう言いケージの隙間に人差し指を入れると、カナリヤは驚いたのか羽を激しく羽撃かせ上段の止まり木に飛び移った。
「─人にあまり懐かんのやて。店員が言うてたやろ」そう言って伊蔵が笑うと、
「─ええのや。女の子やさかい尻軽やないのんがな。なあ賢いなあ、ぽんちゃん─」そう言い唇を尖らせカナリヤと向き合いトゥルルル、トゥルル、と鳴き真似をして見せた。
「─なあ、せやけど今回は長いんやなあ、休み。まだ仕事戻らんでええんか─」そう問われ、少し考えたが伊蔵は偽りのない現状を話した。
「─身入りがええからな。また戻れたらええんやけどな」そう言うと、
「─ええやんか。ちいとゆっくりしたらええ。かなりしんどい仕事なんやろ─」そう言い、
「─心配せんかて、当面暮らすくらいの貯えはあるさかい」と付け加えまた笑みを浮かべた。
「─不安、やねん─ほんまは─独りが─。良くないことばかり考えてまうねん─」枕を並べた寝床で真っ直ぐに天井を見上げ美沙がぽつりと呟いた。
「─うん」間を置いて伊蔵がそう応えると美沙はそっと右手の細い指を節くれだったごつい指に絡めて来た。
湿っぽい風に煽られ、高く伸びた常緑樹の繁った葉が近くの街灯の明かりに影を造り半分開けた網戸の向こう側で微かな音を触れ合い揺れている。
「─福島におった時な─よう飲みに行った─作業がはねた後な。作業員も地元のがようさんおって、─一人と仲良うなってな─」伊蔵は美沙の指を優しく握り返し、記憶を辿る様に訥々と話し始めた。
防護服着用の作業は当初かなり心身を疲弊させたが、目の当たりの作業に没頭すると次第に息苦しさや熱さにも慣れるようになった。
「─何でも慣れるもんだべ。な。人はそだもんだよ。慣れでしまうんだ」伊蔵よりも一回り近く歳上の葛西がそう言い、人の好さげな笑顔を向けビールの大瓶を傾けて来た。
「─かいだ汗の分は、たっぷり補給しねぇどな」部類のビール好きを自称するだけあり、乾き切った喉に水を流し込む様にグラスに並々注いだ泡立つ琥珀色の液体を一気に呷ってはまた注ぐ。
正体不明になる頃には客は皆帰り、その晩も葛西と伊蔵だけが残っていた。
「─まぁたそらほど飲んで、明日さすけねえの?毎晩毎晩だべ─」カウンター越しに店の女将が半ば心配そうに口を挟むが、
「─さすけねえよ。明日は休みだがんな。それにおらにはもう、酒しかねぇんだからよ─」葛西はそう言い呑めるだけ呑むと、
「─そだこどよりもよ。そろそろ一緒んなるべ。お互い独りだべ。しがも好いどるもん同士なんだがらよッ」そうヘラヘラ言うと、一箇所だけある狭い奥座敷にふらつきながら歩き仰向けに倒れ込み、直ぐに鼾をかき始めた。
「─辛えんだよ。復興なんてまだまだ及びもしねぇ─。この人も家族みな、家ごど波さ呑まれだがらね─ひとり息子さいでね。─小学校入学前だったんだ─買ったばかりの、空色のランドセル。毎晩抱きしめで寝でるんだ、この人─」鮮度の良さげな馬刺しを角皿に盛りつけながら女将が呟いた。
やがてカウンターから出て来、皿を伊蔵に差し出すと無遠慮に大きな鼾をかいている葛西の靴を脱がしてやりながら、
「─帰りたぐねえんだよ─仮設住宅さ─ 酔って寝れでしまえば苛みも軽くて済む─原発の仕事さキツいだろ─。せめで目一杯の仕事しでねえと自分が許せないんだね─独り、残されて─生きでる自分が─。酷いもんだったがらね。震災は─本当に。おらあ今だに真っ当に波さ見られねぇ。─いんや、海のせいでねぇ、散々暮らしさ支えでくれだに─罰当たりだよな─」そう言い大きな溜息を吐くとテーブルから丸椅子を引き出し太い尻を乗せ、ぽつりぽつり話し始めた。
「─おらの三月十一日は、亭主の仕事先が豊間でな─。逃げる時電話してくれだけど、携帯も 中々繋がんなくでやっど繋がっだんは夜の七時過ぎだ─酷がっだあ─。原発のせいで、犬猫やお年寄り残して町から人も食料も消えた─地獄だわ─あちこちで人の遺体─動物達も─泥団子みだいんなっでな、腐っでた─何年、何十年だっても記憶は消えねえよ─消せるわげねぇ─」女将はそこまで話すと前掛けから煙草を取り出しゆっくり火をつけ葛西を振り返り、
「─ほら。まだ泣いでる─。おらもだけどね、じっと目ぇ閉じるど自然さ泣いでるんだ。─きっと、気持ぢの奥深ぐさ涙が沁みづいでるんだね─」そう言い深く煙を吐き出した。
「─避難所にさ。お年寄りだけでも百五十人居たのさ。だのに、届いたお握りが二十個だよ─そんで沢山のお葬式─近所の婆ちゃん、包む金も無くなっだから、もうお悔やみにも出らんねえって泣いでた。─その婆ちゃんも、翌日風呂場で倒れでだ─独り残されでさ、誰にも見らんないような場所で、─首ぐぐった方もいだっけ─」女将はそこで言葉を切ると眉間に皺を寄せ、店の入り口近くに置いてあるラジオから流れる八代亜紀の演歌に鼻唄を合わせた。
「─いい歌だよね─舟唄。─死んだ亭主が好ぎだったっげ─」そう言い薄く笑い、
「─なんでね。色々ありすぎだから、分かっだよ。─命はね。凄いって、─終いはないし、一生懸命向き合えば向き合うだげ、生ぎるための鏡んなるって─。前に寺のお坊さんに言われでね。─そん時は何のこどだが分からねかっだけど、ずうっとどん底まで堕ちだらやっと言葉の意味が見えで来だんだ─」
そう続け不意に俯いた。
見ると葛西にもある深い笑い皺に薄っすら滲むものが揺れていた。
「─だめだなぁ。いづまでも吹っ切れねぇ。─やっぱり涙が沁みづいでる─」女将は伊蔵の視線に気づくと無理矢理笑みを造り、もう一度顔を伏せる様にして立ち上がると店の暖簾を下ろしに建て付けのあまり良くない引き戸を音を立て開けた。
「─思い出したわ。子どもん時─阪神淡路─神戸に住んどった、─うちを可愛がってくれたおばちゃん─早うに旦那さん死んでもうて、やっぱ子がおれへんでな。─マンション潰れて、─飼うとった犬抱いたまんま─瓦礫ん中で─」その時窓硝子が強い南風を受け不意に大きな音を立てて揺れ、美沙は姿勢を変え伊蔵の手を弄り直した。
「─色々ある─。生きとるんや、当たり前に。災害や厄災─色々、な。─試されとるかな─。生き残りや。せっかくの生き残りの分なけきっと、これからを試されとるんじゃな─そう言うてその人は笑うとった。わしもそない思う。─病気かておなじや─大丈夫や─」伊蔵は体を横にして美沙を頭から右腕の全部で包み込むように抱きしめると、
「─傍におるで。─みぃのええようにな─」穏やかにそう言い、そっと頬を撫でつけた。
「─なあ、また─行かなあかんとこがあるねん─」美沙はそう言うと、記憶を辿るように父親のことを話し始めた。
「─何や、─えらい旧くからの建物みたいやなあ─」五階建ての所々老朽化した外観を見廻しながら伊蔵が言った。
大阪の丁度中央の辺りにあるこの建物が美沙の父親の入居している老人施設だった。
心臓のバイパス手術を終え暫く経った頃、不貞の関係が本宅に露呈してしまい二人は別れざるを得なくなった。
当然だが、その際母自身も修羅場の矢面に晒されることになり様々に揶揄されたことが原因で心身のバランスを崩してしまい心を病み、また折悪く時期を同じくして子宮筋腫が発覚した。
母は病を父には伝えること無く最期まで独り闘病を貫いた。
美沙は高校進学も諦め、働けなくなった母の代わりに糊口を凌ぐためパートにバイトを掛け持ちするが入院、手術の費用の捻出にはとても覚束なかった。
公的な援助があることを知り申請し受理された時には筋腫は大きくなり詳細な検査の結果、子宮肉腫と判りその進行と転移は早く、入院加療中に敢えなく他界した。
その年の六月に四十を迎えたばかりだった。
美沙は父を恨んだ。
弔いは実に淋しいものだった。
公的な補助を受けているものの規定で、通夜及び告別式は省略され
「直葬」の形態、詰まり火葬と納骨のみが取り行われた。
祭壇は設けられず、近隣で親しくしてくれた数名と美沙、そしてどの様な経緯で知ったのか父も参列したが、美沙は一切口を利かなかった。
母が檀徒になっていたお寺のご住職が懇意で駆けつけてくれ棺に向かい読経してくれた。
朝から降り出した雨が焼き場の整えられた敷石を叩いていた。
「─お天道さんも、泣いてくれよる─」雨空を見上げ、そう言った父の言葉が忌々しく聞こえ泣き腫らした眼からまた涙が溢れ出た。
その後、定期的に現金書き留めが送られて来たが紙幣だけ抜き取ると、同封されていた手紙は一度も読むことなく破り捨てた。
数年経ったある日、また届いた書き留めを見て差し出しの住所が変わっているのに気づいた。
住所の記載には老人施設の名称が別記されていた。
その後も何度か書き留めは届いたがやがてぷつりと途絶えた。
敢えて途絶えた事情を類推することはしなかったが、控えて置いた住所を頼りに訪れた。
『介護付き老人施設─』の銘板のある広い門を入ると直ぐに綺麗に整備された花壇があり丹精に育てているのだろう、紅やピンクの薔薇が整然と咲き乱れていた。
風が強くばらばらと音を立てて背の高い楠木が枝を揺らす度、陽の色の花芯に円錐形の白を纏う可憐な花びらが小刻みに踊っている。
ヒヨドリが盛んに高い鳴き声を上げては餌を探して啄んでいた。
「─ほんまに、立派な建物やなあ─」美沙がそう言った時、丁度車椅子の男性を補助しながら職員らしき中年の女性が右手から近づいて来た。
職員は二人を見て会釈をした後、
「─あの、ご面会でっしゃろか」と愛想のよい笑みを浮かべ訊いて来た。
「─はい。─福本、慶治に─」美沙がそう応えると、
「ご関係は、ご親戚でっか─」そう訊かれ一瞬躊躇い、少しの間の後、
「─娘、です─」と応えた。
「では取り次ぎしますよってに、中に入って待っとってくださいね」職員はそう言いドアを開け広い玄関口に二人を招き入れた。
程なく男性職員が現れると、奥ばった部屋に案内された。
あまり座り心地の良くないソファに掛け待っていると、やがてノックの音がして先刻の職員に伴われやはり車椅子に乗った老人が入って来た。
職員が席を外した後、老人は深々と頭を下げ、目線だけ上げ半ば訝しげに美沙を見つめていたが程なく相好を崩し、「─お久しぶり、─」酷く掠れた声でそう言った。
遠い記憶にある面影に重なるまで多少時間は掛かったが、確かに父だった。
細めた優しい眼差しと、目尻にある笑い皺が紛れもなく父だった。
薄くなった頭髪と浅黒く皺深い顔が否が応でも老いを感じさせ、車椅子に収まる身体が余りにも華奢に見え、咄嗟に言葉が出て来なかった。
「─お久しう─、元気─やったんか─」やっと発した声が思わず上擦り、震えた。不意に感情が衝き上げ、
「─堪忍な、─おとん、─」次いでそう言った途端、涙がこぼれ出た。涙は長い時間美沙の中で堰き止めていた感情を伴い、止めどなく溢れ出た。
「─な、何をや─何を詫びる─」父もしわくちゃに顔を歪めそう返すと、車椅子から前のめりに腕を伸ばし懸命に美沙の手に触れて来た。
「─ええ人、やったな」夕刻の電車の中で吊り革に掴まり揺られながら伊蔵が笑みを浮かべた。
美沙は小さく頷くと、
「─冷たい、─手ぇやった─」そう小さく呟き、じっと車窓の外を見つめた。
『老人施設─』の概要は漠然と知っていたが「要介護」の現実を初めて目の当たりにした。
父は一度も車椅子から立ち上がることはなかった。
「─おかんの弔い以来やった─」そう言った時、『─すまへんかったな─。銭が底ついてもうてな、─送ることも出来へんくなった─』そう言い深々と頭を下げたつい先刻の父の姿が重なった。
浮気が露呈し、夫婦間が上手く立ち行く筈もなく間もなく離婚し家屋敷を含め財産の殆どを慰謝料として贖った後、何年かの借家住まいを経たまだ六十半ば、施設に入居したのだと言うことだった。
「─福本さん、よかったね。娘さんが来てくれはって」暫くして様子を見に来た職員がそう声を掛けると父は子どもみたいな笑みを見上げ、何度も大きく頷いていた。
『─最近、ちょい物忘れも激しなってきましてな。─もしかして医師の診断が必要かも分かりまへん─』職員は帰り際そうも言っていた。
「─娘を、よろしう言われたで」伊蔵はそう言うと俄かに頬を緩め照れ臭そうに美沙を見た後、小鼻の横を右手の人差し指の爪で掻いた。
予約していた受診時間が来ても中々呼び出しが無く、後から来た患者たちが先に診察室に入って行く。気づくとソファに掛けているのは自分たち二人切りになっていた。
「─一番終いに回されとる─やっぱりようないんや、な─」落胆を隠せぬ様子で美沙がそう呟いた時、漸く番号が呼ばれた。
「─将来的にご出産の希望はおありですか」過日診察した医師から担当が代わったと言い胸の名札を見せ挨拶された後、女医が穏やかな口調でそう訊いて来た。
美沙は一瞬返答に窮した様子で伊蔵を見たが直ぐに医師に向き合い、「─じき、─高齢出産やから─」と応えた。
「─そうですか。」医師は短くそう応えふと曖昧に笑みを浮かべると、
「─実は、病変部が小さくありません。─今後の治療についてですが─子宮とその周辺、卵巣に加え卵管を摘出の必要があります─」そう続けた。
不意に意識の半分が飛んだ気がした。
見せられた白黒の反転した写真画像がぼんやり目の当たりに迫り、「─子宮、摘出手術─」おうむ返しにそう口にしたつもりだったが声にならなかった。
女医がカレンダーを見、何やら指差している。
口元が動き明らかに何かを示唆しているのだが言葉が意識下に入らず意味が飲み込めずにいた。
「─早い内がええ、─な」伊蔵のその声に初めてはっとすると、突如目の前が潤み涙がこぼれ掛けた。
出前の中華料理が膳一杯に並べられている。
自分では思うように身体も動かせず、料理出来ない伊蔵の母、喜代の精一杯の持て成しなのだろう。
乏しい年金のやり繰りから捻出されたであろう代金が申し訳無かった。「─久しぶりやなあ。二人揃うてなんて、─なんやまた正月みたいやなあ」嬉しさを隠せぬ様子で浮かべる笑みを見ながら、いつだったか買い物途中、すれ違う幼児をふと止めた車椅子の中から何とも言えぬ眼差しで見送っていたことを思い返した。
『─なあ、おってな。ずうっと─出来ればあの子と、うちのために─』伊蔵の留守の折、様子を見舞いに来る度そう言っていた。
「─せや。とっときの酒もあんねん。秀吉さんも飲んだ云う銘酒やで─」そう言い椅子から立ち上がり掛けた喜代を制し、
「ええよ、おかん。お仏壇のお供えやろ。うちがお下げする─」そう言うと喜代は切れ長の目を細め、
「おおきにな。あんたにおかん言われんの、ほんまに嬉しいわあ。うちな、ほんまは女の子が欲しかってん」そう言って伊蔵をちらと見て小さく舌を出し笑った。
六畳の仏間にはいつも香の匂いが満ちている。
借家は平家で六畳と八畳の二間と台所、風呂場があるが几帳面な喜代はどこも綺麗にしている。
交通事故で右の膝蓋骨を骨折してしまい未だに神経障害に苦しめられているにも関わらず、掃除は小まめに欠かさない。
『─汚れは、あかんねや』そう言い足を引き摺りながら、気づけば雑巾を持ち歩いている。
お仏壇も隅々まで磨かれていて、濃い香が漂うのは経を唱え、まだ間もないからなのだろう。
黒檀と思われる仏壇は割と大きめで、観音開きの扉の中左手に『天野酒』と書かれた酒がお供えしてあり、その横にキンツバと団子が重ねて置いてある。過日蛍を観に行った時の土産だ。
ふと右にある戒名の刻まれた位牌を見、過日の伊蔵の父親の話を思い出し両の掌をじっと合わせた。
「─おかん、土産早う食べんといたんでまうで─」酒瓶を差し出しながら笑うと、
「─土産なんぞもろうたん、久しぶりでな。何や、勿体のうて─」そう応え喜代も笑った。
「─心配せんかて、だいじょうぶや。見てみぃ、この足。ほれ、何とか動きよるやろ。運がええんや。普通なら死んどる事故やがな─あんたかて、だいじょうぶや。縁あって、もう娘同然や。運はな、感染る。間違いのう、ええ運が感染っとる─」好物の海老チリを美味そうに頬張り、ご機嫌に酒を美沙のコップに注いでやりながら喜代が笑った。
「─ええんか。酒なんぞ呑んで─」苦笑して伊蔵が言うと、
「─何言うてんねん。今、元気なんやさかい、好きに飲んだり食べたりがええんや」そう返し美沙も笑った。
久方ぶりに楽しい晩餐だった。
喜代も珍しく酒を呑み愉しげだった。
どこか遠くから消防車のサイレンが聞こえて来る。
大火事なのかサイレンは間もなく複数に重なり、パトカーのサイレンも混じり込んで来た。
「─何や、ごっつ大事やな─」美沙が言うと、「─風のある晩やからな。災難やなあ─」気の毒そうに伊蔵が応えた。
まだ夜半は少し涼しく、湿り気はあるが心地良い風が網戸越しに入り込んで来る。
「─寒ないか。窓閉めよか」伊蔵が言うと、美沙はゆっくり首を振り、
「─嬉しそうやったな、おかん。─逆に、ええ見舞いしてもろたわ。何や、おかんと話しとると元気もらうわ」そう小さく声を弾ませた。
線香の匂う部屋の客用の布団に枕を並べてぼんやり天井を見上げていると、蛍の宿を思い出す。
「なあ。また行きたいなあ、蛍見に─またあの綺麗な浴衣着て─」そう言うと、
「─何や。嫌いんなったんとちゃうんか、蛍」伊蔵がそう応え笑った。
隣の小さな鼾を聞きながら何となくまんじりともせずトイレに立つと、既に喜代が起きテーブルに付き茶を啜っていた。
「─まだ、陽も昇っておらへんよ」微笑を浮かべ美沙が言うと、
「─じきにな、新聞配達のバイクが通る─」喜代はそう応え、
「─暮らしの音はな、幸せやねん」と付け加え笑った。
程なくバイクのエンジン音が聞こえると、
「─さあ、一日の始まりや」そう言い美沙をじっと見つめ暫くの間の後、
「大丈夫、大丈夫やで─」穏やかな眼差しを向けそう言った。
不意に泣き出したい衝動に駆られ思わず顔を俯けると、喜代は椅子から立ち上がりちょこちょこ近づき、低い背を懸命に伸ばし節くれだった両の掌で美沙の顔をふわっと包み込んだ。
駅前の賑やかな雑踏から離れ、アパートが近づくに連れ何やら周辺の異変に気づいた。
遠目にも人影が慌ただしく動いているのが分かる。
「─火事、やないか─」遠くの赤い回転灯を見つけ指差し、美沙が言った。
火元は「臍乃屋」だった。
出火原因は定かでは無いが、主人の煙草ではないかと近隣の住民が遠巻きに噂していた。
幸いにも夫婦共逃げ遅れる事なく、風のある夜半にも拘らず類焼が無かったのが救いだったが店舗兼二階建て家屋の殆どが焼け落ちてしまっていた。
「─何や、けったいな屋号やな。ヘソの屋やなんて─」以前にそう言ってからかうと、
「何言うてんねや。人かてヘソが一番大切なんやで、身体のど真ん中で全部の要やんか。ウチはな、その要のもんを商うとんのや─」主人は前歯の欠けた口を大きく開いてそう豪快に笑い返していた。
消防署員、警官たちが忙しく立ち回り野次馬の揶揄する視線に晒され、現場の端っこに夫妻はただ顔色無く立ち尽くしていた。
まだ燻った匂いのする焼け焦げた柱や消化剤で爛れた床に調味料や酒瓶、半分以上溶け殆ど原型のない海苔の入ったパッケージが散乱していた。
「─昨夜、─やったんや─寝しなの─」伊蔵が半ば呆然と呟いた。
「─歳取ってはったけど、お洒落やったな。二人共─」素麺を啜る箸を止め美沙が呟いた。
毎週月曜の定休日には決まって夫婦で外食に出掛け、主人はスーツに必ず蝶ネクタイの出立ち、女将は事ある度に自分への褒美に買い込むのだと自慢していたワンピースを纏い、少し濃い目の化粧を施していた。
時には派手目のグロスを唇に重ねたまに出会すと、「─困ったもんやで。別嬪が余計目立ってまう─」臆面も無くそう言う主人の言葉に頬を染めたりもする。
「─荷が降りるねん。やっと嫁ぎよる。やっと、夫婦二人になれる─」二番目の娘さんが三十路半ばで漸く縁談が決まり嫁ぐ前、主人は和かにそう言っていたが、その後買い物に訪うと挙式が済んだ直後から寝込んでしまったのだと言う。
「─ えげつない泣いてな。式の始まりから終いまで。挙句に、やっぱ自分なんかに娘はやれへんって。へべれけに酔うて新郎に、やれ甲斐性なしやの、ケチ腐れやの悪態ついて、ついでにお相手のご両親にまで絡んでな─」女将はアルバムになった挙式の写真を見せながら、
「─ほれ、ベソかいて見えるやろ」そう言って中央の新婦の横で口元をへの字にしている自分の亭主を指差すと大きな声を立て笑い、
「─ ほんまに淋しがりでな。ちょいでもうちが見えな、おっきな声でまさみ、まさみぃ言うて名ぁ呼びながら家中探したりするんやさかい」と付け加え、大きな溜息を吐いていた。
「─服も、焼けてしもたんやろな─。写真とかも、何もかんも─」眉間に小さく皺を寄せ美沙が言った。
何処かで仔猫の鳴き声が聞こえている。
焼け跡のものなのか、風向きの加減でまだ焦げ臭い匂いが網戸越しに入り込んで来る。
「─寝つけへんのか─」気配を察したのか伊蔵がそう声を掛けて来た。
「─どこに身を寄せてはんのかな。何や気になってな─」美沙がそう応えると、
「─わしも何や寝つけへん。コーヒーでも飲むか、駅前のコンビニでも行ってくるわ─」伊蔵が言い、美沙も伴い外に出た。
玄関のドアを閉めると直ぐに視線に気づき、振り返るとそれは猫の目で縦長の光が二つ、じっと二人を認めていた。
「─何や、あんたがおかんか?仔ぉ産んだんか─。えらいなあ─」目線を屈め美沙が和かに言うと暫くの間こちらを見据えるようにしていたが、やがて闇に光を消した。
夜気に孕むきな臭さはやはり現実で、東向きにある臍乃屋の焼け跡から漂って来る様だった。
自然に駅とは真逆のそちらに足が向いた。
街灯の明かりに劣化し所々捲り上がったアスファルトの剥がれが鈍く照らされている。
深夜の通りに人影は無くサンダルを履いた二人分の足音だけがジャリジャリと聞こえていた。
程なく空の右手の月明かりを背に先細りした焼け柱が見え、記憶にある店の引き戸の手前の位置まで来た時、
「─誰か、おる─」ふと足を止め伊蔵が闇に目を凝らした。
焼け跡に居たのは臍乃屋の主人だった。
焼け爛れ紫黒く変色し原型の捩れたレジスターを見下ろしこちらに背を向けた格好でぽつねん、と立ちじっと動かずにいる。
言葉もなく見つめていると気配に気づいたのか不意に振り向き、こちらに向き合うと妙に姿勢を正し、短髪の白髪を深々と下げて来た。
「─言葉が─出て来いへんかった─」闇の中、ぽっかり目を開け伊蔵が言った。
数日後、家賃を振り込みに銀行に行くと低い背を見つけた。馴染みのあるカーキ色のキャップを被った出たちは大家だった。ふと振り返り伊蔵に気づくと短い歩幅で近づいて来、直ぐに臍乃屋の火災を話して来た。聞くと、やはり出火原因は主人の煙草だと云うことだった。
「─ほんまにえらい迷惑やわ。離れとる筈のウチにまで消化液やら飛んで来よってな。庭の盆栽やらみなだめにしよった─ま、何や結構な額の火災保険に加入しはってた言うからな。きちんと弁済はしてもらうけどな─ 何や他でもな、干しといた布団が使われへんくなったやら言うてるんやて。あの雨降りにな─皆んな、迷惑かけといて焼け太りは許せへんねやろな」大家はそう言い元から偏屈そうに曲がっている左の口元を更に歪め笑うと、
「─あんたとこも、近いんや。ちいとでも被害はなかったんか。何ぞあれば、遠慮のう請求した方がええで─」汗ばみ脂ぎった顔を俄かに近づけそう耳打ちした。
あの晩の主人の佇まいが頭から離れずにいる。
威勢良く戯言を言い胸を張っていた面影は無く酷く老いて見え、その様が亡き父の記憶に一瞬重なった。
「─帰ったで」玄関のドアを開けそう言うと、
「─遅かったな。混んでたんか」
美沙の言葉に、
「─うん。─週明けやさかいな」伊蔵はそれだけ応えると、小さく吐息をつき腰を下ろした。
ついていたテレビから聞こえる賑やかな笑い声に目線を上げると、落語を演っていた。
演目に「こがねもち」と書かれている。
噺の概要は、切り詰めて小金を溜め込んだ長屋住まいの坊さんが患い寝込む。そこへ隣に住む男が見舞いに訪れる。坊さんは金を遣うことを嫌い医者にも掛からず、薬も飲んでいないと言う。
何か食いたいものはと訊くと、あんころ餅が食いたいと言うので買って来てやるのだが、人が見ていると食えないと言い男を帰らせる。男は自分の部屋に戻り壁穴からそっと様子を窺うのだが、坊さんは餅の中から餡を出し、自分の胴巻きから小金を取り出し餅に詰め込みそれを飲み込んでいた。
しかし餅が胸につかえ苦しがり始め、慌てて助けようとしたが死んでしまう。男は弔いを受け取り仕切るが焼いた死体の腹を包丁で裂き、金を懐にして立ち去ってしまう。
この金を元手に、男は餅屋を出し大層繁盛したと云う─。
「─ やり切られへんな。何や、この噺─みな、この金兵衛言う輩と同じや─」終いまで聞き舌打ちをしてそう呟くと、
「─何やどないしたん。何怒ってんねん」噺家の滑稽な演じ回しを笑っていた美沙が怪訝に問うた。
押しいただく姿勢のまま、白封筒を手に主人は身動ぎせずにいた。
項垂れたその肩が震えていた。
「─何や、何勘違いしてはんねや。やるんとちゃう、きちんと表書き見てや─」伊蔵がそう言うと主人は初めて封筒を見つめた。
『正油代』─表書きに右肩上がりのぞんざいな筆文字でそう書かれてある。
「─乾物代の先払いや。貸し売りやのうて、貸し買い、やな─」そう言って笑うと主人は顔を上げずに暫くの間の後、
「─何や、─下手くそな─字やなあ─しかも、醤油が間違うとる─」と言った。
「─自分、─小学校は─出とんか─」やっと笑い掛けたその声が不意に潤み、震えた。
「やかましわ─おう、何や。臍乃屋やろ。また商うてや。要のもんをな、─約束やで、約束したで─」そう言い背を向け歩き出すと少しの前を置いて、
「─おおきに、─ほんまに─おおきに─」丁度降り出した雨音に紛れ、微かな咽び泣きが追って来た。
「─あ。せや。わしは凍み豆腐が好きなんや。それも仕入れといてや─」伊蔵は声を張りそう言い、振り返らず右の拳を高く上げると大粒の雨を避ける振りをして足を早めた。
「─またおったで、臍乃屋─」伊蔵がそう言うと、
「─そうか。─何や気持ちは分かるけどな、何してはんねやろな─毎晩毎晩─」美沙が呟くと、
「─きっとな、商うてはんのや」そう応えた。
「─商い、─」美沙がまた問い返すと、伊蔵は笑って、
「─せや。店始めた時から、今まで─。記憶やら何やら色んなもん皆んな売り払うてな、また出直すための支度や─」そう応えた。
「─せやな。あの人らなら大丈夫や、きっとなんぼでも出直せる─あら、なんやあんた、目ぇが赤いで」美沙も笑みを浮かべそう言い、マニキュアを塗る手を止め目を向けると、
「─なんもあらへん。汚れた雨が目に入ったんやろ─」伊蔵はそう応え左の手の甲で目元に滲んだものをぐい、と拭った。
近隣に工場があるのだろうか、
バタバタバタバタと、換気のために開け放った窓から何かの機械音が聞こえる。
朦朧とした意識の中、術後の耐え難い痛みが迫り上げ細切れに目覚めていた気がする。
施術が済んだ直後に覚醒を促され、抜かれた喉の管の痕がひりひり痛む。
短い時間を置いて看護師さんの声かけが耳に入るのだが何を処置されているのか理解出来ずにいた。
夢を見ていた。
亡母の夢だった。
それが術中なのか、つい今し方なのか分からない。
草原に佇んでいると、黒塗りの大きな車がやって来てドアが開いた。後部座席に座っているどこか見覚えのある女性が和かに助手席に座るよう身振りで促す。
助手席を開けると、運転席でハンドルを握っているのは母だった。免許等持っていない筈だったが、別段気に掛けることはなかった。
「─久しぶりやね、元気か」母は笑いながら話しかけて来た。
「─元気やあらへん。病気してな」不可思議にも母が亡くなっている意識はなかった。
母はそれには応えずに、
「えらい別嬪さんになったなあ。うちに瓜二つや─」そう言い満面に笑みを浮かべると、そのまま車を走らせた。
ミラーを見ると後部席には先刻の女性を含め三人いるのだが、どの顔も見覚えのある気がする。
母は昔話をしながら愉しげにハンドルを握っている。
前横の車窓に流れる景色も記憶にある気がした。
「─なあ、おかん─何でおかんは、わざわざ不倫を選んだん─?─おとんに家族がおること、知っとったんやろ」長い間自分の中で燻っていた疑問をぶつけてみた。
夢の中だからなのだろう、躊躇いはなかった。
「─うん、知っとった。けどな、時には恋のが勝ることがあるんや。寄り添いだけで─切のうなる、─それが恋や。うちはもう長いこと、あん人に恋しとる。あん人も同じや─けどな、おとんは家族を蔑ろにしたんやないで。恋をしとるだけや。血の繋がりがな、邪魔することもあるねん─家族やからこそ、寄り添い切れん。恋やないとあかん、満たされん。─そないなもんもあんねや─」母はそう応え暫くすると車を止め、
「─さ、着いた─降りるで。─終点や─」穏やかにそう言い、指を伸ばし美沙の髪を優しく撫でつけて来た。
件の女性にドアを開けられ、降り立った場所は目の前に太く背の高い樹があり道が二手に分かれている山道への入り口の様な場所だった。
「─あんたはここまでや。ええか、左手に行くんやで。」母は運転席から声を張りそう言うと笑みを浮かべ、こちらを見おどけた仕草で手を振って見せた。
「─何でや?まだ一緒に行くわ─うちも、行きたい─おかんといたい─」不意に泣きそうになりそう言うと、
「─まだまだや。お前はまだまだな、─支度が整わん─ほな、また、な─」母はそう応え、
「─せや、終いになるけどな。─あんたに兄妹、残してやれへんかった─それだけは、堪忍や─」両の掌をこちらに向け合わせそう付け加えると車を発進させた。
半ば茫然と遠去かる車体の後ろを見送った後、ふと足元に空色の華が揺れているのを見つけた。
「─あやめ、や─」美沙の好きな華だった。
腰を屈めその花びらに触れた途端、揺すられた様に身体がびくん、と大きく震え目覚めた。
両の頬が濡れていて、泣いていたのに気づいた。
今し方の夢を思い返し、思わず「おかん、─」そう呟くと締めつけられるように切なさが胸いっぱいに押し寄せ、美沙は咽ぶ様に声を押し殺し泣いた。
『─そろそろ、ええよ』やっと流動食が出た三日目の朝方、そうLINEを入れると面会時間の二時きっかりに伊蔵が訪れた。
前回の腎盂腎炎と違い、女性としての大切な臓器を失くした未知の精神状態も想像がつかず、また医療器具に様々を管理されているやも知れぬ術後の姿は見せたくなかった。
「─傷みは、どないや─」眉間に皺を寄せ、伊蔵がそう言うと、
「─痛いに決まっとるやろ。死にそうやわ」美沙はわざとらしく眉間に皺を寄せそう応えた。
「─腹腔鏡とは云え、六時間超える大手術やったさかいなあ─ほんまにお疲れさん─」伊蔵はそう言うと、腰の辺りまで掛けてある薄い布団の上に置いた点滴をしてない方の手を握り自分の方に引き寄せ、
「─無事で、よかった─ほんまに─」と染み染み呟いた。
明らかに疲れ切った顔をして目が赤く血走っている。
「─どないしたん。心配して、泣いてたんか」美沙がそう悪態を吐くと伊蔵は、
「阿呆。─誰が泣くかいな─。何や、寝つけへんかっただけや─」と言って苦笑した。
「─あんな、うち─女やのうなってしもた─」術後から抱いていた虚無を初めて口にした。
「─堪忍な、─子ぉ─産めへんようになって─」そう声にした途端、泣き出したい気持ちが押し寄せて来た。
「─堪忍、な─」もう一度そう言うと、自然に涙が溢れ出た。伊蔵は握りしめた指先に力を込めると、ゆっくり首を横に振り左手の指で美沙の髪を幾度も撫でつけた。
「─優しそうやね、旦那さん」伊蔵が帰った後、検温に来た看護師が言った。
中途半端な関係を自嘲する様に曖昧に笑みを返すと、
「─めっちゃ泣いてはったんやで、旦那さん。手術終わって、ストレッチャー乗って移動しはる笹生(さそう)さんの姿見て。ずうっと後追って来て声出さんと、涙ぼろぼろ零しはってな─何や、羨ましかったわぁ」そう言って笑った。
病室は四人部屋で入院患者は美沙を含め三人だった。
一人は恰幅の良い年配で子宮筋腫の施術だったと聞かされた。
「─筋腫が思うとったより大きくてなあ─あんたもまだ若いのに、えらいことやったなあ─」そう言って人懐こい笑顔を見せたが、後一人の婦人はベッド越しに仕切られたカーテンを開けることは殆ど無かった。
一度だけ、カテーテルがやっと抜けた日。トイレに立った時初めて見かけ軽い会釈を交わしたが、筋腫施術の女性と変わぬ年恰好に見え酷く痩せていた。
「─打ち止めや─。もう、みぃんな出尽くした─」朝から蒸し暑く遠くに蝉の鳴き声を聞きながら鬱ら鬱らしていた意識に、男性の嗄れ声が聞こえて来た。
隣のベッドの愛想の良い女性は白石と名乗り、眼にも疾患がある様で院内にある眼科に診察に出ていた。
声は窓際にあるもう一人の婦人のベッドのカーテン越しから聞こえる。
「─正樹もな、何やら出来た言うて年始めに手術して胃の半分取ってもうた─。茜は、去年暮れに子宮頸癌─わしあ、工場潰した─。ほんでお前の筋腫や─。もう、みんな出尽くした。─しんどいことは、みぃんな打ち止め、これが終いや─」そう言って掠れた笑い声を忍ばせた。
「─せやなあ。そんなら、ええなあ─」婦人も少し笑みを孕ませそう応えると、
「─せやで。どこぞの芸人はんも言うとったやないか。今、生きとるだけで丸儲け、や。後はもう、ええことしか来いへん。─幸せの出直し、や」夫と思しき男性はそう言い、今度は抑えた野太い笑い声を殺風景な病室に響かせた。
翌日の午前中、婦人は家族に伴われ退院した。
「─世話んなりました。先に失礼します」婦人は丁寧に頭を下げそう言い、同室の二人にわざわざ買って来させた箱入りのメロンを見舞いだと置いて行った。
「─ まあ、ご丁寧に。こんな高価なものをおおきに」丸い身体をベッドからやっと降ろし、白石が挨拶し美沙も同様に頭を下げると、
「─ 次は病気やなしにお互い様元気で、どうぞご縁があるように─。」婦人はそう言い初めて笑顔を見せた。
美沙はその時、婦人にも後ろで笑みを浮かべている旦那さんにも目尻に笑い皺があるのに気づいた。
「─あんたのおかんにもあるなあ─。きついこと、ようさんあった筈やのに─」その日の午後、見舞いに来た伊蔵と病室の隣にある談話室で缶の緑茶を啜りながら美沙が言った。
「─笑い皺はな。きっと散々きつい目ぇ見て来たさかいや─きつい、しんどい─そないな気持ちから自分救うため笑うしかのうて、その度きっと、皺んなった─福島の葛西はんにも、おばちゃんにもあった─」伊蔵がそう応えると、
「─そない言うたら、おかんにもあったわ─」美沙はそう言い、過日の夢を伊蔵に話した。
「─護って、くれてはるんや─有難いこっちゃ─」伊蔵はそう言うと、感慨深げに大きく息を吐き目を潤ませた。
その翌日退院の日が決まり、カーテン越しに声を掛け報告すると、
「─あらあ、おめでとうさん。よかったねえ」と明るい声が返って来た。
「─そう言うたら、白石はんもそろそろ退院ちゃいますの─?」美沙がそう問うと、暫くの間の後、
「─うちな、─他にも何や、─あるらしいわ─」俄かに声を落としそう返答があった。声の調子からそれ以上を訊くことは躊躇われ、美沙は天井を見上げるとじっと目を閉じた。
「─あ、せや。車買うことにしたで─」タクシーの中で伊蔵が言った。
「─セコ(中古)やけどな、昔の知り合いが安う譲ってくれる言うさかい。色々不便やからな、車くらいないとな」そう付け加え笑った。
「─車、かあ─」そう言い、ふとハンドルを握る伊蔵の横にいる様子をイメージするとそれだけで病に疲弊し鬱屈していた気持ちが少し癒えるようだった。
入院は僅か八日だったが長い時間闘病して来ている様な気がする。
病名を報され治療法を説明され以降、何をしていても気持ちの底に病が纏わりついていた。一応の覚悟は決まっていたつもりだったが、しかし女としての掛け替えのない機能を失う事実と経験のないその先行きに溜飲を下げられる筈も無かった。
施術が近づくとふと真夜中に目覚めては不安に囚われ、悶々と寝返りを打つ日々が続き項垂れた気持ちも更に萎えて来た。
入院を控えた前の週、伊蔵が用事で出掛け、独り居た堪れず喜代の家に出向いた。
蒸し暑い夕刻で冷えたビールを数本と馴染みの店でたこ焼きを買って行った。
「─お帰り」そう言い満面の笑みで迎え入れてくれた。
「─もうちょいやな─だいじょうぶや、しんどいやろうけどな直ぐに過ぎる─」丁度お仏壇の前で椅子に掛けていた喜代は蝋燭の灯を消すと、こちらに顔だけ覗かせそう言うと手招きした。
招かれるまま横に正座し手を合わせると、
「─ 娘を、─護っとくんなはれ─よろしゅうに─」喜代は深々と頭を下げた後美沙を見つめ、
「─もう、だいじょうぶや。神さんは絶対やさかいな。お任せしたら後はな、待っとればええ─。気持ちん中で、じぃっと掌ぇ合わせてな。ほしたら何でも、一番ええようにしてくれはる─」目を細め穏やかにそう言った。
「─あんな、おかん─。やっぱり─罰、─なんかな─」ビールの缶のプルトップを左手の指先で弄びながら、美沙が目線を俯けたまま呟いた。
「─うちな、─昔、─児ぉ─堕したことがあんねん─」初めて誰かに打ち明けることだった。
まだ二十代初めの頃、ガソリンスタンドに勤めていた時、同年代の店員と仲良くなり、関係を持った。
相手は真面目な男で懐妊を知るときちんとした形を取りたい、と結婚を申し出て来た。だが親が興信所を使い美沙の身辺を調べ、既に亡くなっていた妾の立場にあった美沙の母親の過去や身寄りのない現状を知り猛反対した。
男は駆け落ちも覚悟の上だからと
強引に所帯を持とうとしたのだが、そんな折り児が育ち切らずに胎の中で息絶えてしまった。
堕胎施術を受け、深い傷心のまま二人もそれ以上を向き合い切ることが出来ず別れたのだった。
「─そうか─。えらい辛いやったなあ─けど、あんたのせいやないやないか─」喜代が労るようにそう言うと、
「─違うねん─。うちな、─」美沙はそう応じ掛け、俄かに眉間に皺を寄せ暫くの間言葉を探るようにした後、
「─うちな、妊娠わかった時─育てられへん─無理や─まだ、いらん─。そない思ってしもたんや─。せやから、─お胎ん中で─」そこまで言うと不意に声を詰まらせ、
「─うちが、─殺した─」と肩を震わせた。喜代は部屋の隅に見つけた蟻を指先でそっと摘み、台所の窓を開け外に出してやりながら、
「─神さんはな、罰なんぞ当てへんよ─」笑みを浮かべてそう言い、ひょこひょこまた仏間に足を向けるともう一度美沙を手招いた。
喜代は椅子から手を伸ばし線香立てから一本を抜くと燭台に灯した蝋燭から火を移し香炉に供えた。
「─この一本が、今日の感謝の分─」そう言い掌を合わせ、
「─線香立ての線香が少のうなったら、また足してな─この線香全部の分なけ掌を合わせたら、もっと護られる。ずうっと、幸せでおられる─いつもそない思いながらご先祖を供養するねん─」緩やかに揺れながら天井に昇る紫煙を追うように目線をなぞりそう付け加え、美沙に向き合うと、
「─ 悟りやなんかちゃうねんで。─ただな、また明日も生きていたいだけや。好きなもん食うて、あんじょうな」そう言って声を立て笑った。
「─人はな、きっとそんなんでええんや─。失敗やら後悔やら、ようさんやらかしながらな。やから神さんはな、相手にせんよ。ハナっからよう知ってはるさかい、人の浅はか、愚かをな─せやさかい、見守ってくれはるだけや。罰なんぞ当てたりせえへん─罰はな、返ってくるもんや。許し難い何かをしでかしてな─。心んどっかで赤い舌出した時、罰は返ってくる。─だいじょうぶ。あんたは、だあれも傷つけてへん─一番傷ついたんは、自分やないか─児はな、ただ縁(ゆかり)がなかっただけや。あんたのせいなんかやない─」
喜代はそう言い蝋燭の火を消し立ち上がると、正座し項垂れた美沙の頭を優しく撫でつけた。
退院すると直ぐ、タクシーを使ってまで見舞いに駆けつけてくれた。
「─ただ今」美沙がそう言うと、
「─お帰り─。待っとったよ─」喜代は声を詰まらせそう応え、眉間に皺を寄せ眼を潤ませていた。
婦人科の受診は特に時間が掛かる。
土日明けの月曜は予約時間が朝一であるにも関わらず、診察室の前は混雑していた。
伊蔵は仕事の関係で都合がつかず、美沙独りで病院に来ていた。
室内機が天井から大きな音を立ててはいるのだが、見た目にも旧い機能は余計蒸し暑さを感じさせた。
血液検査を含め幾つかの事前検査があるため早めに来なくてはならず、早朝から慌ただしく支度をしたためまだ眠い。
建物中央のライトコートから入る強い陽射しが遠慮なく夏の盛りを思わせ好きな季節の筈が、今年は疎ましく感じるようだった。
診察室は大きな柱を境にして奥が婦人科、手前が産科に分けられている。
婦人科の診察室の突き当たりがトイレになっていて、時折通る妊婦の姿を視界の端にぼんやり見ながら、
「─あの人らとうちと、─何が違うんやろ─」思わずそんな言葉を呟いていた。
異状なしの診断に安堵し、一連の受け付けが済み精算機に診察券を挿入した時、不意に肩を叩かれた。
振り向くと病室で一緒だった白石が笑みを浮かべていた。
突っかけを履き、あの日と同じ部屋着の出たちをしている。
「─みぃちゃん、お久しぶりやねぇ、その後はどないやの─」白石は変わらぬ高い通る声でそう言うと、細い目を更に細めた。
時間があるなら、と二階にある談話室に誘われお茶を飲むことになった。
談話室には先にひと組がいて、一番奥の大きなテーブルで話し込んでいた。
「─白石はんこそ、だいじょうぶなん?まだ入院しはってたやなんて─」少し窶れた感じの顔色を案じそう言うと、
「─違うねん。あんたが退院するちょい前から腰がえらい痛うて、検査したら十二指腸潰瘍やら言われてな─胃カメラ飲まされたり、ちいと余分に入院しとってな─」白石はそこまで話すと天然水のキャップを捻り、美味そうに二口くらいを喉を鳴らし流し込み、
「─ほんでな、そん時は三日くらい投薬して様子見てから退院したんやけど、十日くらい前にまた痛みが酷うなってな。出戻ったんやわ─」そう付け加え笑った。
「─明日、やっと退院なんやわ。けど、最終日にみぃちゃんに会えてよかったわあ─せや、LINE教えてくれへん?また時々、お話ししたいわ─」白石がそう言い、ちょっと躊躇したが携帯を出した。
「─あらあ、綺麗やねえ─」待ち受けにしている画像を見て白石が声を上げた。
「うん。蛍─。観に行った蛍は巧く撮れへんかって、拾い画やけどね─」美沙が言うと、
「─ええなあ。うちも行きたいわあ─蛍やなんて、そない言うたら子どもの時以来見てへんなあ─」携帯の画面を見つめ羨ましそうに白石が呟いた。
「─子どもん頃思い出すわあ─金網の虫籠と団扇持ってほ、ほ、ほたる来い─やら歌うて蛍追ったなあ─団扇煽いで蛍落としてな。─草むらに落ちた蛍は片手でつまんだりせんでな、こないして両手をお椀型に膨らませて潰さんようにそうっと籠に入れた─蛍を潰してもうて手ぇ洗わんと目の病気になる。おかんから、そない教えらとったなあ─」白石は昔を懐かしむようにそう言い、更に目を細めた。
談話室は各テーブルが離れて設置されているが、ジュース類の販売機以外は何もなくちょっとした物音や話し声も空間に反響しよく聞こえてしまう。
先にいたひと組は、白髪の男とまだ中年少し手前くらいの女、その子どもと思しき高校生くらいの女の子だった。
「─なあ。せっかくじゃ。お前らもせっかく死を間近に見つめとる。ならもっともっと─生を─生きることを見つめんとあかんで─」年配の男性が俄かに声を落としそう言うと、
「─はあ?なあに言うてんねや。取ってしもて、あんじょうしとればだいじょうぶや。たかが、胃のポリープやないか。内視鏡やで」女が清楚な風貌に似合わぬぞんざいな物言いでそう応え笑った。
「─医者の言うことなんぞ信用出けるか─。血ぃまで吐いたんやぞ─せやけどな、まだまだ生きるでぇ。わしはな、お前のその唇が好きなんや。形のええ、柔らこい唇がな。どこぞのもんに盗られてたまるか。」男が女の言葉など意に介さぬように風に外聞もなくそう言い放つと、
「─お、おとん、やめてやって─!他にも人がおんねやで─ごっつ恥ずいわ─」声を潜ませ女の子が口を尖らせ、こちらの方にちらと目線を送って来た。
「─何が恥ずいねん。わしはな、生きるでぇ。どんなけ恥晒しでもええ。おめおめと、生きる。─わしがいのうなったら─きっとな、─きっとお前らが─淋しいからの─」男が俄かに声を落としてそう言うと、
「─何や何や、えらい大仰やなあ─今にも、死んでまうんか?」女はそう言
い、今度は高い声を立て無遠慮に笑った。
「な、─何や、─何が笑うねん─しゃあないやんか─。─初めてなんやぞ─手術やら─」男が不意に項垂れ半ば声を潤ませると、今度は母親そっくりの声を立て女の子が笑い声を響かせた。
「─ええなあ、みぃちゃんも、あの人らも─」白石が沁みじみそう呟いた。
美沙が目線を戻すと、
「─うちは、独りやから。心配も─見舞いにも、だあれも来いへん─」そう付け加え淋しげな笑みを見せた。
まだ残暑の容赦のない陽射しがアスファルトを照らしつけ、先を歩く人たちの足元に逃げ水を造り出している。
舗道を踏み付ける度、柔らかな感触が足の裏から伝わり地面から焦げたような匂いを感じるのは気のせいなのだろう。
体調が思わしくなく、数日振りに外出した。
「─いけるんか?ごっつぅしんどそうやけど─」伊蔵が心配そうに声を掛ける。
「─だいじょうぶや。買い物したら直ぐに帰るさかい─」美沙はそう言うと小さく息を吐き、額の汗を左手の甲で拭った。
術後から酷く疲れやすくなり、大してある訳でもない家事も休み休みでないとこなせないようになっていた。
『─大切な臓器を摘出しましたからね。体質によってそれぞれの症状が出ることがありますから─』先日担当医からはそう言われたが日常的にそれが続くことがかなりのストレスになり、伊蔵の有難い気遣いやサポートにさえ苛立ちをぶつけるようにもなって来ている。
「─わしが買うたるさかい、ちいと良さげなもんにしようや─」靴屋の店先で、伊蔵が言った。
八月終わりの父の誕生日に靴を贈りたかった。
姿勢よくスーツを着こなし、いつも磨かれた靴を履いていたお洒落な父が、くたびれたワイシャツ一枚の姿で狭い車椅子の中で小さく背を丸めていた。
足元の靴は外側が傷だらけで色も酷く褪せていた。
「─茶が好きやねん。サイズは、25半や─」美沙が言った。
サイズを咄嗟に言えたことが自分でも意外だった。
遠い昔、玄関口に揃えてある父の靴に自分の靴を並べ見比べた時、インソールに記された数字の記憶だ。
「─これは、どないや」伊蔵が手を伸ばし差し出した新品の靴を見、
「─ええなあ─おとんの好きそうなデザインや─」そう応えながら車椅子のステップに乗せられたズボンの下の、か細くなっていた足を思い返していた。
「─歩けんのかも知れんなあ─もう、─」美沙がそう呟くと、
「─ええやないか。そんなら、おとんの足元はずうっとピカピカのまんまや」伊蔵がそう言って笑った。
確かに誰かに呼ばれた気がする。
微睡から目覚め声のした方向をぼんやり向くと、狭いベランダの塗装の剥げ落ちた柵に四十雀が止まっていた。
美沙を認めた様に正面から見据えてくるとツツピーツツピー、と甲高く囀り、それに即座に呼応しカナリアが美しいハーモニーを奏でた。
「─夏鳥や言うてたなあ、元気なもんや─みぃと同じに暑いのんが好きなんやな─」布団の中で欠伸をしながら伊蔵が笑った。
「─何かな、今年は夏がしんどいわ─」籠を覗き込みながら美沙が苦笑した。
「─今年は行けへんかったなあ─吹田」伊蔵が言うと、
「向日葵はまだ盛りや思うけどな、吹田はもう仕舞いやな─」そう応えながらドレッサーに向かった。
大阪の万博記念公園には聳える太陽の塔のに従ずる様に広大に広がる多くの品種の向日葵を観ることが出来る。
「陽の使い」とされる向日葵が太陽をコンセプトにしたモニュメントに向かい咲く様が印象的で毎年夏には訪れていた。
「─あんたは嫌いやんか。何しろ夏に弱いさかいなあ。去年も会場でぐったりしとったな─」美沙が笑うと、
「─何言うてんねん。福島ではな、全身防護服来てされてそれこそ滝のような汗垂らして仕事しよったんやで」伊蔵がそう言い口を尖らせた。
「─あ、そない言うたら確か隣町の外れに畑あったなあ。向日葵の」美沙が思い出しそう言い、
「─せやったな、行ってみるか」そう応え伊蔵が腰を重そうに上げた時、玄関の呼び鈴が鳴った。
出ると宅配業者が息を切らし大きな箱を二つ足元に置いた。
『あかつき』は福島の桃で箱を開けた瞬間から実に芳醇な甘い匂いを放った。
差出人は葛西だった。一箱目の中に便箋が入っていて見ると、
『元気しとるか。おごってもらった酒代のお返しじゃ─』収まりの良くない殴り書きのような文字でそう書かれていた。
宿舎を出る前の晩の高くない酒代に義理を覚えていたことが可笑しくて笑みを浮かべると同時に、
「─まだ、会えるよな?─な、─ダチだもんな─な、─」へべれけの呂律で何度もそう繰り返していた葛西の淋し気な顔を思い出した。
その晩、深夜に白石からLINEが入った。
病院で連絡先を交換して以来、頻繁にメッセージのやり取りや時には電話もするようになっていた。
通話は白石が中々切ろうとせず、時には二時間近くになることもあった。
「あんな、─淋しいねん。もうちょい話してや」そんな風に素直に気持ちを吐露し寄り掛かる彼女に親近感を持った。
隣町に住んでいることも知り、今度食事に行こうとも話していたが普段は不躾に深夜にメッセージを送るようなことはしない。
開いて見ると長い間音信不通だった姉から急に連絡が来て、一緒に住むことになった、との一報だった。
短い文脈から彼女の嬉しさが伝わって来る様だった。
複雑な家庭環境で育ち、中学を出て直ぐに勤め出し暫くの間親戚をたらい回しにされ辛酸を舐めて来たのだと云う身上が自身とも重なりを感じていた。
「─何や、嬉しそうやな」布団の横から美沙の表情を覗き込む様にして伊蔵が言った。
「─病院で同室やった人からや。色々話しとる内、仲良うなってな。よかったわあ─あ。せや、あんた確かこないだ送られてきよった桃な。まだ残っとるやろ─」美沙が言うと、
「おう、売るほどあるでぇ」剽軽抑揚で伊蔵が応えた。
『─よかったなあ。近いうち、手土産持って遊びに行くよってに』そうメッセージを送ると直ぐに既読が付き、
『ほんまに!嬉しい!待っとるで』即座にそう返信が来た。仕舞いにたくさん付けられたハートマークを見て思わず声を立て笑うと、部屋の隅で被せた布地カバーの下でカナリアが同調した風に短く囀った。
翌朝、まだ早い時間にまた小さく繰り返し囀りが聞こえるので起き出して様子を見て見ると、籠の中に細かな羽があちこちに散乱していた。
「─あら、どないしてん。ぽんちゃん─」そう声を掛け人差し指を
隙間から入れると激しく羽をばたつかせた。
「─何や、えらい機嫌ようないなあ」そう言いながら餌箱の餌を取り替えた。
「─食欲もないんか─またこないに残して─」そう言い、もう一度様子を窺うと幾分元気がないようにも見える。
この数日、食餌の量が明らかに減っていて、囀りもあまり聴かないような気がしている。
「─あかんで、元気ようしてくれへんと─」そう言うとカナリアは無表情な眼差しを嘴ごとこちらに向け、不意に何かを吐き出した。
「─これは、─そのう炎かなあ─本来、インコとかに多いんやけどね─」消毒液の匂いと特有の動物臭の混在する狭い診察室で医師が似合わないロイド眼鏡越しにこちらに目を向けた。
「─鳥って、食べたもんが胃に到達する前「そのう」言う食道が袋状になったとこに食べ物蓄えるんやけどね。─何ぞの原因で消化管の流れが悪うなってしもたり、免疫力が落ちたりすると細菌がそのうん中で異常な繁殖したりするねん。─何ぞ、人間の食べもんあげたりせえへんかった?」前をはだけた白衣の胸の辺りに右手を突っ込み、ぼりぼり掻きながら医師がぞんざいな物言いで訊いて来た。
美沙が即座に首を横に振ると、
「─ま、一応マクロラブダス症言う厄介な病気やったらあかんから検査しときまひょ─」そう言われ、翌日の再診を予約した。
『マクロラブダス─』帰りのタクシーの中でそう検索し、不安になった。
カビ菌により発症し重篤な場合死に至ることもあるのだと云う。
「─ぽん─?あかんで─いなくならんでや─、あかんで─」籠を覗き込みそう声を掛けずにはいられなかった。
籠からプラに囲われた観察用のケースに藁を敷き移し、処方された薬を定期的にスポイトで与えた。更にサーモスタットを購入し温度管理をするとカナリアはやっと囀るようになった。
検査結果でカビ菌の感染ではないことに安堵したが、昼夜となく様子を窺い気持ちの休まる時がないこの数日から、大仰かも知れぬが生命との寄り添いを学んだ気がした。
子どもの頃学習した『五分の魂』と云う言葉と、過日自分の掌の上で息絶えた蛍を思い返し、
『─ただの虫や─』そう言い小さな骸を払い落としたあの時を反芻した。
「─天(そら)の使い、やねんで─なあ、ぽん─」カナリアにもう一度そう声を掛けると何故かついと涙が零れ落ちた。
翌朝、朝餉の片付けを終え白石の家に出掛ける支度をしている時に電話が入った。
父のいる施設の職員からだった。
「─えらい喜んでましてな。手紙、預かってますねん─けど、それから間も無く─福本はん、ちいと様子が─」職員は何やらそう言い淀んだ。
『─靴をおおきに。新品の靴、何年振りやろう。ほんまにおおきに。今度来てくれはる時は、真雪も一緒に』
真雪─。母の名だった。
「─この手紙は、いつ、─のものです─」暫くの間を置いて美沙がそう訊ねると、
「─ついひと月程前です─送られてきた来た靴履いて、嬉しそうにしておって、─そん時はまだ様子もそないにおかしなかったんです─。言われた通りに私が代筆しましてん─」職員はそう言い、もう一枚の紙を応接室のテーブルに滑らせて来た。
『診断書』─アルツハイマー認知症─。最近になり同じ話を繰り返す傾向が見受けられる様になり、この半年程は特に記憶の時系列に矛盾が目立つ─。
「─特別養護施設へ移ることになる思います─」職員が淡々と告げた。
目の前で持って来た水菓子を車椅子の中で美味そうに頬張る父は、確かに先日とは様子が違って見えた。
美沙を見ても和かに笑みを浮かべるだけで挨拶もなかった。
「─あの、─改善つまり、治療は出来まへんのでしょうか─」伊蔵がそう訊くと少しの間の後、
「─さあ、─私どもでは何とも─」そう応え、プラスチックのスプーンを忙しげに動かしている父を見つめた。
外に出るとまだ草いきれが鼻をついて来た。『─私どもでは、何とも─』その言葉の真意を探り取ろうとしていた。
ふと足を止め振り返り無機質な建物を見上げると目につく老朽化が、この前よりもみすぼらしく見えた。
「─よう似合うてはったな、─靴─」帰りの電車の中、伊蔵がそう言った切り二人とも口を開かなかった。
各駅で列車のドアが開き、乗降車する雑踏が聞こえる度泣き出したい気持ちが迫り上がって来た。
混み合う人々に紛れ、背の高い伊蔵がその表情を隠す様に顔の前に立ってくれているのが救いだった。
列車の揺れに任せる振りをして、そっとその胸に顔を凭れ美沙はほんの少し泣いた。
伊蔵の腕が小刻みに震えたその肩を優しく抱き寄せていた。
照りつける酷い残暑の陽射しのせいではなく眩暈に足元が震えていた。
袋に下げた桃が転げ落ち、音を立てず足元でひしゃげた。
袋を落とした訳ではなく、重みに耐え切れず袋が破けた。
「─あ、─」腰を落とし拾い掛けると詰め込んだ桃が次々こぼれた。手を伸ばし、だがその前に上を見上げた。
女性の言葉の意味が分からなかった。
「─ニ週間になります─」白石に目元のよく似た女性はそう言うと、自分も腰を落とし転げ出た桃を拾い出した。
熟し食べ頃の芳醇な匂いが残暑の熱を孕んだコンクリート造りの玄関前の床の上で更に匂い立ち、蝉の鳴き声が不意に耳に喧すしく響くと完全に平衡を失い、その場に蹲った。
「─ようさん貰うてもうて、─丁度旬やし、─食べてもらお思て─」その姿勢のまま目線を上げずにそう言うと少しの間の後、
「─おおきに、─妹も、─喜ぶ思います─」女性はそう応えると深く頭を下げた。
混乱していた。
平穏に話しかければ何事のない言葉が返るものだと思った。
「─心筋梗塞、でした─」期待外れの追い打ちに動けずにいた。
額から、首筋に滲んでいた汗が一瞬で引いた。暫くの間の後、
「─いやや、─」そう言って見上げた視界が逃げ水の向こう側を見るみたいにゆらゆら揺れていた。
「─いやや、─いややで─」もう一度そう言うと、白石の姉は不意に顔を歪め腕を伸ばし震える手で美沙の顔を抱きしめて来た。
二駅離れた場所から歩いて帰って来た。
照りつける陽射しも流れ落ちる汗もどうでもよかった。
列車で帰れば車内に独り平然と揺られている自信がなかった。
途中、土地住宅街に入り腰を下ろした小さな公園のベンチで遊んでいる親子連れを見ていた。
暑さに熱せられたステンレスの滑り台を愉しげに悲鳴を上げながら滑り落ちる女の子の下で待ち構えた父親が水鉄砲で水を掛けている。
思わず浮かべた笑みを不意に流れ出た涙が消した。
『─児が、─欲しかった─』そう言っていた白石の声がまた耳に蘇ると伏せた眼から涙がぽたぽた足元の砂を濡らした。
どのくらい時間が掛かったのだろう、アパートの玄関を開けた時には陽が傾き始めていて足は泥の様に重く疲れ切っていた。
「─おかえり。遅かったな─え?どないしたんや。真っ赤っ赤やで─。」出迎えた伊蔵が直ぐに美沙の異状に気づき、麦茶に氷を入れ持って来た。
畳に腰をペタンと下ろし冷えた麦茶を飲むと幾分気持ちも落ち着き一息大きく吐いた時、俄かに窓の外が暗くなり疎らな雨音が聞こえて来た。
「─せや、始まりよったで、臍乃屋─いよいよ建て直しや─」一連の話を聞いた後、美沙の気持ちを取り成す様に伊蔵が言った。
「─ほうか─、よかった─」そう応えると火災に遭う前、元気だった夫妻の和かな顔が思い浮かび少しだけ気持ちが癒えるようだった。
「─やり直しやな、また最初から─」伊蔵が言いながらコップに麦茶のお代わりを注いだ。
「─やり直し、─せやな─。何でも、やり直し─出来たらええなあ─」美沙はそう言うと、伊蔵の腕を引き寄せその胸に凭れ掛かった。
「─いつかな、─一緒に行きたいなぁ言うてな─蛍観に─」そう言うとふくよかな白石の面影がまた浮かび、泣き腫らした眼から涙が零れた。
「─ あかん─なんぼでも、涙が─出る─」伊蔵の腕の中でしゃくり上げながら白石の笑顔が締め付ける様に胸に際限なく去来する。
「─けどな、仕舞いに姉さんに逢えたんや─せめてええことが、締めくくりになった─」伊蔵がそう宥めると、
「─死んでもうたら何もならへん─続かなあかんねや、ええことは続かな、─何を、─」わかったようなことを、─そう見当違いの詰りかけた言葉がまた泣き声に代わった。
夕から降り出した雨が激しさを増し、折からの強い風を孕みバラバラと硝子窓を叩いている。
雷鳴が遠くで聞こえていた。
「─児がな─欲しかった─。そない─言うてはった─同じやね。─うちと同じや、─縁(ゆか)りがなかったんやね─そう、肥後のおかんに教わった言葉で慰めたった─」窓外に時折光る稲光をぼんやり見つめそう呟くと、俄かに得体の知れない憤りが湧き上がって来た。
「─なあ、縁って─何やねん─一体、─誰が、─ある人とない人、─誰が決めて、─振り分けるんや─」そう言い口元を歪めた。暫くの間の後、
「─境涯、─かのう─」伊蔵がそう応えると、
「─ほんなら、みんな境涯、やな─おとんが、認知んなったんも─白石はんが、幸せのやり直し出来へんかったんも─臍の屋はんの災難も、─どこぞで今、独りぽっちの人も、─貧乏も、─病気やら何やらも─みぃんな、境涯や─」美沙はそう言い、
「─何もない人かて、ようさんおるやないか─。たった今、何不自由なく笑うてる人らかて─何や、─不公平やないか─」そう付け加え形の良い唇を噛み締めた。
俄かに雨音が止み、同時に激しい光が点滅し闇の窓外に走ると少しの間を置き重い地響きが小刻みな振動を伴い長く轟いた。
「─境涯、─おかんもな、同じこと言うてたわ─おとんと別れた後、病気んなって─銭がのうて─きちんと治療も、入院も出来へんかって─。うち、泣いてばかりおった─何の役に立たんのが悔しいて、─情けのうて─ほしたらな、泣かんでええよって─みんな、うちのもんやさかい、─病気も─貧乏も、─みんな、おかんのもんやさかいな─って─けどな、あんたがおる─おってくれる─。おおきに、─おおきに─それもみな、おかんの境涯や─。自分のもんやさかい─大切にせなな、─そない言うてた─」美沙はそこで言葉を切ると大きく息を吐き、
「─これからや。─あんたにはな、これからようさん、ええことが─ある─緊急搬送された病院で、そう言うて─笑顔遺して、死んでった─」震える声でやっとそう言い、顔を歪めた。
「─忘れたることや」喜代の言葉に目を上げた。
「─忘れ去る、のんちゃうで。記憶に大切に残したれば、それでええのや。いつまでも泣いて面影に縋り寄ったらな、そん人もあんたが心残りで、よう産まれ変われへんやないか─」喜代は優しい眼差しを細め、
「─生き抜いた─。うちのおとん、─あんたのおかんも同じや。─白石はんはな、─生き抜いたんや─あんたのおとんも、これからを生き抜く─」やり切れない想いを抱えあぐね、悄然と訪いを入れた喜代の家で彼女はそう言葉を続けていた。
雨降りが続き稲光が部屋の硝子越しに見える厚く垂れ込めた鈍色の雲間から、万別に形を変え断続的に蒼白い光を落としている。
時折凹凸に隠れ光る様があの日、杉の葉の裏で光を明滅させていた蛍の様に見えた。
「─何や、─蛍みたいやな─」美沙が呟くと同時に、今度は長い光が鈍い雷鳴を響かせた。
「──あん時の蛍にも─児がおったんかなあ─産まれた草に帰して、─弔うてあげたらよかった─」そう言うと、
「─せやな。─次はきっと、そないしてあげたらええ」伊蔵が穏やかにそう応えた。
雲が流れて来ているのだろう、稲光は雷鳴との間隔を狭めながら明滅を繰り返している。
「─ええなあ─。綺麗や─天(そら)には、─どないな色も似合う─」思い出してはまだ潤む目元を左手の指先で拭いそう言うと、伊蔵が寝返りを打つように美沙に身体ごと向き合い、
「─前にな、─児ぉ産めへんようになった─女やのうなった─そない言うとったやろ─違うで─。それは違うとる─おかんの口癖やないけどな、─わしはな、運がええんや。─道踏み外してしもた時から、自分の家族やなんて─生涯、持てへん思うてた。─あのな、─子がおらんでもええ。家族がおれば、─わしらはもう、家族や─誰のためやない。─わしのために─そばにおってくれ─。ほしたらな、わしも─わしは、みぃの傍で─生き抜く─」訥々と言葉を選びながらそう言った。
「─何や、ごっつ─大仰な─」プロポーズやな、─そう返し笑おうとしたが、声にならなかった。
それ以上を言葉にしたら大きな声を上げ泣いてしまいそうだった。
美沙は顔だけ向きを伊蔵の反対側に向けると口元をぎゅっ、と結び衝き上げて来る感情を危うく抑えた─。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
