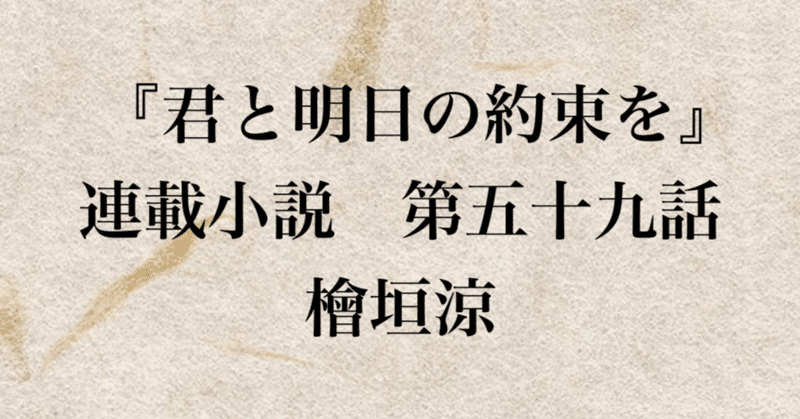
『君と明日の約束を』 連載小説 第五十九話 檜垣涼
檜垣涼(ひがきりょう)と申します。
小説家を目指して小説を書いている京都の大学生。
よろしくお願いします💐
毎日一話分ずつ、長編恋愛小説の連載を投稿しています。
一つ前のお話はこちらから読めます↓
気持ちが混乱したまま時間を過ごしていた。
彼女に会わせる顔がないと思うのは、自分の都合のいいように解釈しているだけなのかもしれない。でも、彼女と会う資格がないことは明らかだった。
というか、そんなことどうでもよかった。彼女と顔をあわせる勇気が、その時の僕にはなかった。
彼女は、退院しているのだろう。そんなこと考えたくないのに、頭の中をコントロールできなかった。
*
しんと静まりかえった廊下。何十回と訪れているはずのその場所が、父親を取り囲むどす黒い空間にしか見えなかった。
悪の巣窟。本で読んだ悪者が住んでいる場所。齢十歳、世界に対して偏見を持っていなかった少年が、病院を恐怖とか、悪いイメージと結びつけたのは、その日が初めてだった。
病院だからじゃない、むしろそれまでの病院のイメージは、父親に会える楽しい場所だと思っていた。だから、ただただ心臓に直接突き刺されるような胸の苦しさを感じたときは吐き気がした。もう何十回と訪れているはずなのに、僕はいつもと違う異様な雰囲気を感じていた。
さっきまでは家にいて、寝る時間になって布団を被り、目をつぶっていた。夢と現実の間でふわついた気持ちになっていると、お母さんの大きな声に起こされた。抱きかかえられた僕は、すぐさま上着を着せられ車に乗せられた。
目的の場所は、聞かなくてもなんとなく分かっていた。
普段ならシートベルトが締まっているか確認するお母さんが、今日は何も言うことなく車を発進させた。焦った顔をしているお母さんに迷惑をかけたくないという思いから、僕は自分でしっかりベルトを締める。
しばらくして、予想通りお父さんの泊まっている病院に到着した。
お母さんに手を引かれ早足で病院の廊下を歩く。夜遅くに病院に来るのは初めてだから、夜の病院がこんなに暗いとは知らなかった。非常灯の明かりと、それが床に反射した光がぼんやり浮かんでいる。
なんだか怖くなって、僕はつないだお母さんの手をぎゅっと握る。
するとお母さんは一瞬僕の方を振り向き、「大丈夫よ」と震えた声で囁く。初めて聞く泣きそうなお母さんの声で、僕の胸の中は余計不安に包まれた。
ーー第六十話につづく
【2019年】恋愛小説、青春小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
