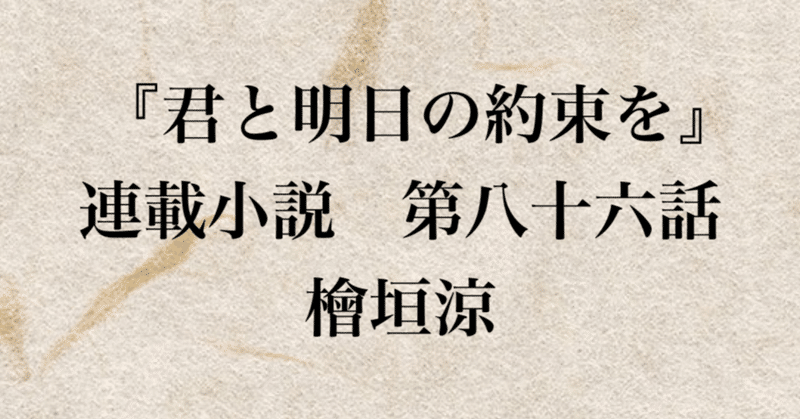
『君と明日の約束を』 連載小説 第八十六話 檜垣涼
檜垣涼(ひがきりょう)と申します。
小説家になりたい京都の大学生。
よろしくお願いします🌸
一話分ずつ、長編恋愛小説の連載を投稿しています。
そろそろ終盤に差し掛かってきています!
一つ前のお話はこちらから読めます↓
印刷された彼女の小説を持っている彼女の思考には、当たり前だけどその可能性は浮かんでいない。
「書いて欲しい」
「……は?」
思わず飛び出た呟きといった感じだった。
「この小説、ここまで君が書いたんだ」
彼女に誤解を与えないように、正確に伝える。
彼女は手の中にある原稿の束をしばらくじっと眺めて、それから机に戻しゆっくりと顔を上げた。
「……私が?」
「そう」
冗談に思われないよう、目を合わせる。
彼女が何か思い出すように視線を上げた途端、低く呻き声を上げる。もしかして、無理矢理記憶を思い出そうとしたから?
「大丈夫?」
彼女は、顔を歪めて頭を押さえている。どうしていいかわからず、彼女の隣で何度かその言葉を繰り返す。
「無理して思い出さなくていいから」
彼女が脂汗をかいて、苦しそうに唸る。誰か呼んだ方がいいだろうか。
咄嗟にナースコールしようかとボタンを取った右手を掴まれる。
「大丈夫」
予想以上に強い力で握られ、慌ててボタンから手を離す。
彼女は荒い息を落ち着けて、徐々に痛みが治まってきたのか表情も穏やかになる。一度深呼吸した後、口元に手をもっていき、真剣になにかを考え出した。
僕は黙って彼女の様子を見守る。窓から吹き込む涼しい風に彼女の髪が揺れる。
「そっか――そうか」
口元に手を当てたまま呟く。
「うん、私がこれを書いたのは理解した」
驚いた。彼女が納得するにはもっとかかると思っていた。
「え、信じられるの?」
「だって、私、何かしら忘れてるんでしょ。本読んでた時、ずっと頭重い感覚あったけど、今のでわかった。何も思い出せないけど、ミツ君が言うんだし、忘れているということくらいは信じられる」
彼女はまたあの、小説家になると言い切った時と同じ涼しい顔でそう口にする。
「で、続きを書いて欲しい、なんだよね?」
「うん」
「記憶失う前の私が何か言ってたの?」
「いや、僕が」
変わらない。そのための準備もするつもりだ。
「手伝うって約束したんだ。だから、お願いします」
ーー第八十七話につづく
【2019】恋愛小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
