
【書評】リーンマネジメントの教科書
【一言まとめ】
リーン マネジメントとは、メンバーが小さな実験を繰り返し、不確実性が高い中でも、リスクを軽減させながら新規事業をうまく立ち上げ、その新規事業を取り込むことでビジネスプロセス全体を変革していくマネジメントスタイル。スモールグッドビジネスをどんどん立ち上げることを使命とする著者による、新規事業立ち上げに奮闘する大企業マネージャーたちへの指南書(※すべてのスモールグッドビジネスを立ち上げんとする起業家たちの参考にもなります)
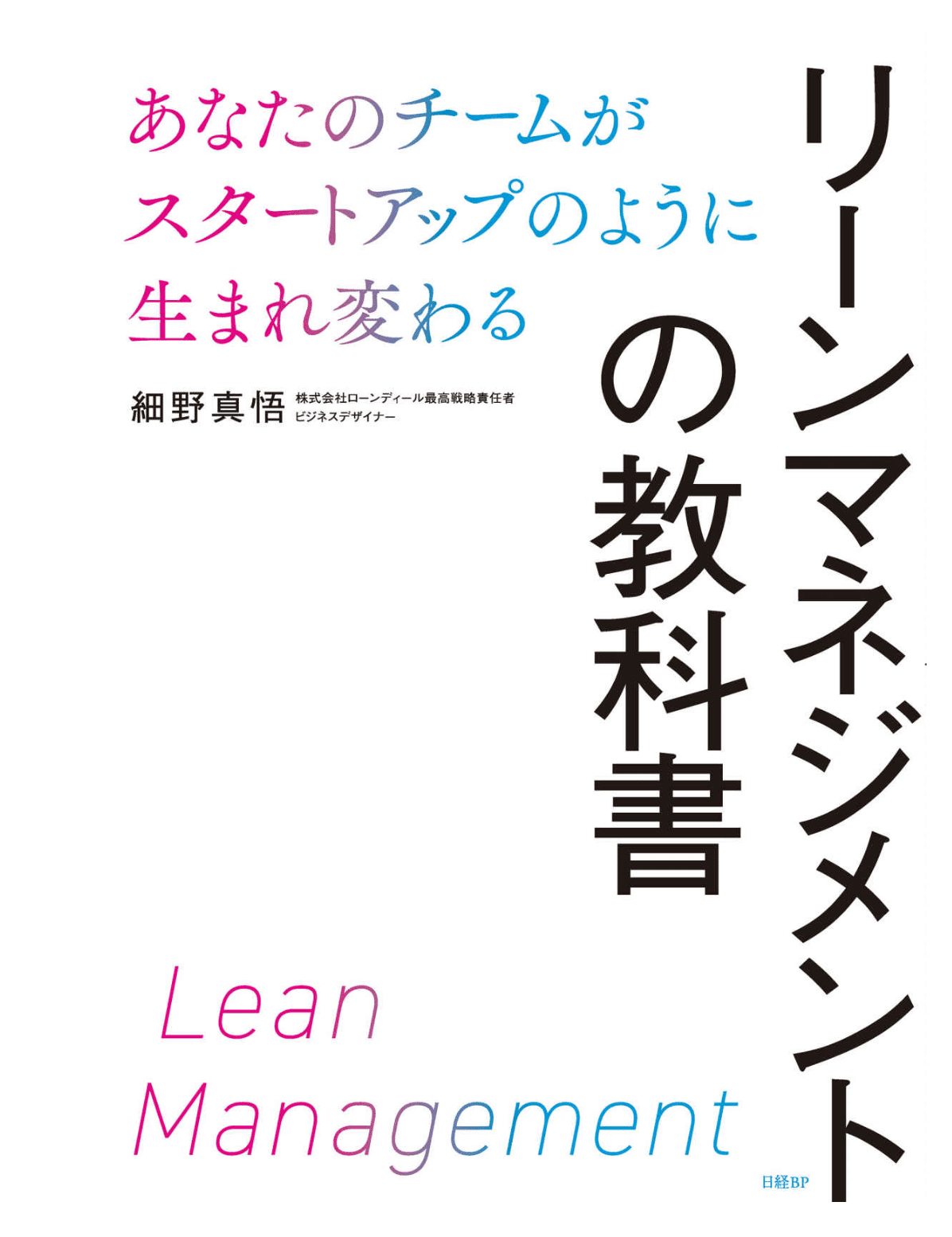
【要約】
・リーンスタートアップの考え方で最も大切なが顧客開発(発掘)。プロダクト開発の前に、まずはそのプロダクトが課題を解決することに対して、想定価格を支払ってくれる顧客を見つけること
・一神教マネージメントとは正解に最も近い場所にいるのが経営者だと崇め、唯一の正解に向かって全社一丸となって向かっていけば良いって言う日本の大企業によく有るマネジメントスタイル(不確実性の高い新規事業などのマネジメントには適さない)
・「実験」とはやるかやらないかの2択を迫られる状況に置いて小さな実験をすることによって意思決定を先送りすること。客が何を求めているのか探るため、まずは仮説を立て、それを確認するために、最小限のコストと時間で小さな実験をする(予算もかなり使ったし、もう止められない!!地獄のピタゴラスイッチを作動させない)
【良い実験を行うための5つのコツ】
・コツ1「顧客は本当は何を求めているのか」という仮説を検証するために、Yのうち、少なくともX%はZすると定量的に記述
・コツ2 「最低でもこれくらい顧客が動かないと撤退する」と言う撤退ラインを決める
・コツ3 顧客アンケート調査は無意識に嘘をついている可能性があるもの。欲しいと言う言葉を真に受けず顧客が身銭を切るアクションをとってくれるかどうかで判定
・コツ4 仮説をXYZで検証する場合は、母集団が変わらないより検証可能なサイズの小さなサンプル(できる限りN数小さくて良いように母集団選択)で行うか(サンプルズームイン)、または、購入までの顧客の反応をステップを刻んで確認していく(ステップズームイン)と言う方法を使う
・コツ5 半年から1年かけて100万円から1000万円の予算で行うプロトタイピングではなく、数時間から1週間、10万円以下の予算でできるプレトタイピングで実験を行う
【リーンスタートアップ 実践のために教えるべき定石と道具】
・<定石1> 将来の不確実性が高い状況下で意思決定を遅延させるためにリアルオプション戦略をとる。実験でほぼ成否をわかるようにできれば、うまくいかなかった場合の損失を減らし期待利益を最大化できる
・但し、その案件がうまくいくかどうかが高い確率でわかる実験を考えるには、AIにはできないクリエイティブな発想が必要。
・<定石2> 一つの工程のバッチサイズを極小化し、ワンピースフローで各工程を連続して実施できるようにし、実験を一人で回せるようにする。壮大な実験は無駄の塊になる可能性(YouTube 一個流し 封筒)
・<定石3> 不確実性が高いからこそ、担当者が案件を1度に複数案件回せるようにポートフォリオマネージメントの考え方で実験できるようにする(1つ失敗して困るようでは担当者はフルスイングで挑戦しない)
・<道具1> バリデーションシートを活用しリスキャストアサンプション(やる意味がそもそもあるのか?確認できる課題)を最速で実験検証する
・バリデーションシートは、1) 成し遂げたい事は何で、2) 成功を何で測定し、3) どのくらい伸びないと撤退すると言う撤退ラインを決め、4) 初期アイデア仮説を明確にし、5a)検証したい仮説、5b)検証方法(実験)、5c)進捗と結果 、について整理する
・<道具2> プロセス評価とは、 「評価されるために動く」マインドセットのメンバーに失敗に対する心理的安全性を与える評価指標を提供すること
・実験を奨励する文化を作り出す評価指標
・四つの項目を基本3段階で評価(+, /(フラット),ー)。
1)実験結果の明瞭度(次のアクションが明確にならない場合マイナス)
2) 自律度(関与とサポート度)
3) 実験の難易度(マイナスはつけない)
4) コストと納期(予算オーバーはマイナス)
【付箋と抜粋】
・リーンスタートアップの考え方で最も大切なが顧客開発(発掘)。プロダクト開発の前に、まずはそのプロダクトが課題を解決することに対して、想定価格を支払ってくれる顧客を見つけること
・一神教マネージメントとは正解に最も近い場所にいるのが経営者だと崇め、唯一の正解に向かって全社一丸となって向かっていけば良いって言う日本の大企業によく有るマネジメントスタイル(不確実性の高い新規事業などのマネジメントには適さない)
・普遍性の高いニーズに対して大量生産や、改善の手法で対応するときは、一神教のマネージメントが有効
・不確実性が高い今の時代に新しいことを始める場合、新たなビジネスプロセス全体がどのような形になればうまくワークするかなんて、最初の時点では誰もわからない
・リーンマネージメントの全体像は、リアルオプション、スモールバッチとワンピースフロー、ポートフォリオの3つのセオリーと、バリデーションシート、プロセス評価の2つのツールで構成される
・大企業では、何かイノベーションを起こそうとする場合、今までやっていた仕事を否定して、新しいことに着手しようとする人がいますが、それは絶対にやってはいけません
(大企業などでの新規事業の進め方への提案)
・誰が考えついたのかはどうでも良く、顧客にとって本当に必要なものは何なのかをマネージャーとメンバーが必死になって同じ方向を向いて考え抜くことが大切
・未知なことに取り組むときに、マネージャーがすべき事は大きな仕事を当てるぞ!と派手なことをやろうとするのでなく、すでにある予算の中からギリギリ使える少ない予算を確保し、まずは短期的にわかりやすく成果が出る施策の実験に振り分けていく
・変革を段階的に進めているやり方もある。大きな1つのコンセプトのもとに人が変化についてこれるスピードで小さな変化を断続的に進めていく
・プロダクトリリースは、特定のキーワードを打ち出していく戦略をとる。そうすることで今後も続くんだなと言う期待感を持ってもらい、企画側の覚悟を会社全体に知ってもらうことができる。
リーンマネジメントの概要(実験フェーズ+実装フェーズ)
(実験フェーズ)
・実験フェーズは伸びシロ探し、課題仮説、打ち手仮説、実験の4つ
・〈伸びシロ〉ビジネスが大きく成長するための「伸びしろ」はどこにあるのかと言う考え方をベースに、「構造的な問題」について仮説を立て、それを証明する事実を探していきます。手元にデータがなくても大胆に仮説を立てていく
・〈課題仮説〉まだ表面化していない大きな問題を探すには、実際に自分で体験してみて、顧客の声にならない声に気づくことが近道
・〈課題仮説〉伸びしろが見つかったら、次にヒアリングを実施、データと観察力の両刀使い、定量データと定性データのどちらも駆使しながら課題仮説を、立てていきます
・〈打ち手仮説〉1つ目は自社で過去にタブーとされていた打ち手が本当に今でもタブーなのかを確かめること
・大企業では、自社が1番大事にしている、不可侵の領域があり、「それ以外で」何ができるかを必死に考えていくと言う暗黙のルールある
・〈打ち手仮説〉2つ目は、課題に対して打ち手を一対1で考えず、一網打尽にする仮説を立てる
・〈打ち手仮説〉筋の良い打ち手を考える上で必要なのが、自分たちの業界以外でうまくいった課題と打ち手との組み合わせを頭に入れていく事です。ポイントは組み合わせのストックが大切で、常日頃から他業界を含めて突き抜けた事例を貪欲にインプットし続けることでしか身に付けることができません
・〈実験〉先に課題を解決できることを証明するため小さく実験
・〈実験〉リスクがあるのではないかと議論している暇があるなら、リスクを小さくして実験する。実際大した問題はなかったとさっさと証明する方が賢い
(特に大企業の新規事業で大切)
・〈実験〉実験で大事なのはメンバー一人ひとりに複数の案件を回してもらうこと。1つしか案件を持っていないと心理的安全性が担保されず正直に実験結果を振り返ってくれない可能性がある。うまくいかないと分かっただけでも事業にとってはプラス
・〈実験〉実験をする上で欠かせないのは現場の協力者。実験に協力してくれる現場の人を見つけることがとても重要
(実装フェーズ)
・〈実装フェーズ〉一神教マネージメントでは本当に必要かどうかわからない機能まで全部要件定義に盛り込んで起案する一方で、リーンマネージメントでは実験で証明できた部分だけどうやって今の業務フローの中に組み込むかを起案する
・〈実装フェーズ〉PowerPoint禁止、べき論禁止、全体の戦略ストーリーに合わせて、起案企画側は支援するだけ、現場発のアイディアで展開
(実験とは?)
・実験とはやるかやらないかの2択を迫られる状況に置いて小さな実験をすることによって意思決定を先送りすること。客が何を求めているのか探るため、まずは仮説を立て、それを確認するために、最小限のコストと時間で小さな実験をする(地獄のピタゴラスイッチを走らせない)
・実験してうまくいかなければ即撤退
・良い実験を行うための5つのコツ
・コツ1「顧客は本当は何を求めているのか」という仮説を検証するために、Yのうち、少なくともX%はZすると定量的に記述
・コツ2 「最低でもこれくらい顧客が動かないと撤退する」と言う撤退ラインを決める
・コツ3 顧客アンケート調査は無意識に嘘をついている可能性があるもの。欲しいと言う言葉を真に受けず顧客が身銭を切るアクションをとってくれるかどうかで判定
・コツ4 仮説をXYZで検証する場合は、母集団が変わらないより検証可能なサイズの小さなサンプル(できる限りN数小さくて良いように母集団選択)で行うか(サンプルズームイン)、または、購入までの顧客の反応をステップを刻んで確認していく(ステップズームイン)と言う方法を使う
・コツ5 半年から1年かけて100万円から1000万円の予算で行うプロトタイピングではなく、数時間から1週間、10万円以下の予算でできるプレトタイピングで実験を行う
(リーンスタートアップ 実践のために教えるべき定石と道具)
・<定石1> 将来の不確実性が高い状況下で意思決定を遅延させるためにリアルオプション戦略をとる。実験でほぼ成否をわかるようにできれば、うまくいかなかった場合の損失を減らし期待利益を最大化できる
・但し、その案件がうまくいくかどうかが高い確率でわかる実験を考えるには、AIにはできないクリエイティブな発想が必要。
・<定石2> 一つの工程のバッチサイズを極小化し、ワンピースフローで各工程を連続して実施できるようにし、実験を一人で回せるようにする。壮大な実験は無駄の塊になる可能性(YouTube 一個流し 封筒)
・<定石3> 不確実性が高いからこそ、担当者が案件を1度に複数案件回せるようにポートフォリオマネージメントの考え方で実験できるようにする(1つ失敗して困るようでは担当者はフルスイングで挑戦しない)
・<道具1> バリデーションシートを活用しリスキャストアサンプション(やる意味がそもそもあるのか?確認できる課題)を最速で実験検証する
・バリデーションシートは、1) 成し遂げたい事は何で、2) 成功を何で測定し、3) どのくらい伸びないと撤退すると言う撤退ラインを決め、4) 初期アイデア仮説を明確にし、5a)検証したい仮説、5b)検証方法(実験)、5c)進捗と結果 、について整理する
・<道具2> プロセス評価とは、 「評価されるために動く」マインドセットのメンバーに失敗に対する心理的安全性を与える評価指標を提供すること
・失敗に対する心理的安全性を与えるためには、評価される前提条件はうまくいくことだと思っている考え方を変える、明確な成果⇒明確な失敗⇒曖昧な成果の順で評価、同時に三つの案件を持たせる
・特に大企業のにいる人のようにいい学校に入るためにテストで高得点を取り続けてきた人にとっては成果というのは良い結果を出すことだと脳に刷り込まれているこの人たちにどんどん失敗しろと口で言ったところで実際にやってもらえることはほとんどない
・実験を奨励する文化を作り出す評価指標は四つの項目で評価(+, /(フラット),ー)。
1)実験結果の明瞭度(次のアクションが明確にならない場合マイナス)
2) 自律度(関与とサポート度)
3) 実験の難易度(マイナスはつけない)
4) コストと納期(予算オーバーはマイナス)
脱平凡発想の二つの要件とは?
・一つは目の付け所が良い(多くの人は気づいていない、インサイトがある)という「着眼点」。もう一つは、多くの人が思いつかずまたは実行できないような解決方法を思いつくという「ソリューションがすごい」
・着眼点における脱平凡とは、「世の中のほとんどの人は X を信じているが真実は X の逆である」という真実を探し出すこと。インサイトのある着眼力を身につけるには、自分オリジナルの仮説を立て続け、鍛錬を積むしかない
・ソリューションの脱平凡はバイアスブレイクを使って三つのステップで考え出す
・ まずはみんなが同意するアイデアの良さのエッセンスを二つ抽出(パラメーターは10個以上検討の上でキーとなる2つを抽出)、次にそれとは異なる、場合によっては対立軸となる良さを書き出す(美味しい⇒まずいではなく、おいしい⇒量が多い)この異なる(別軸の)良さを出すには、「偏愛(自分の好み)」「(アイデアの)組み木」「(業界の)タブー」
・筋の良い「別の良さ」がだせないのは、1)圧倒的なインプットの不足、2)ビジネス構造の理解不足、3)自分の好き嫌いの理解不足、4)アウトプットの練習不足
リーンマネジメントを実践形式で体験できるFUKUSEN
実際に、新規事業やスモールグッドビジネスを立ち上げてみたい!という方は、著者が運営されているFUKUSENへの参加を検討されると良いと思います。個人的にはかなりイチオシで、外資コンサルでのOJT、世界最先端と言われるミネルバ大学のリベラルアーツ(一般教養)と私が体験したきた学びと比べても、無料登録で見れてしまうコンテンツだけでも秀逸で相当価値があると思います。

サポートを検討いただきありがとうございます。サポートいただけるとより質の高い創作活動への意欲が高まります。ご支援はモチベーションに変えてアウトプットの質をさらに高めていきたいと考えています
