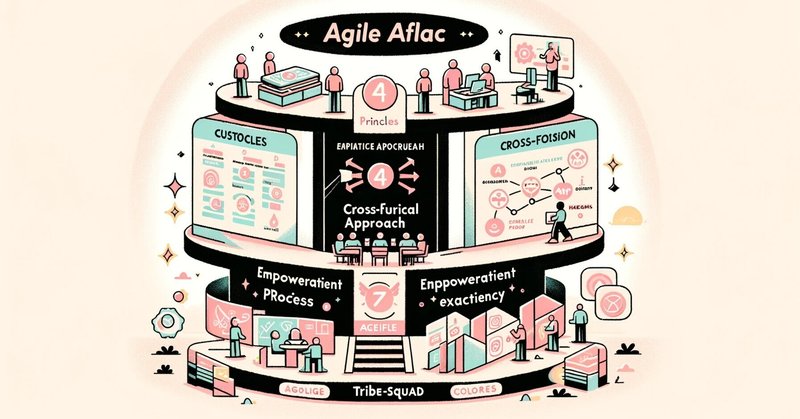
ヒエラルキーからアジャイルへーアフラックのDX成功事例
Aoba-BBTの番組、DXライブ08は「ヒエラルキー組織」でした。ビジネスブレイクスルー大学大学院の今枝昌宏教授とアフラック生命保険株式会社のアジャイル推進室長である吉田政史氏が、日本企業におけるDXの課題と、アフラックが実践するアジャイル型の組織モデルについて議論しました。以下アフラックのホームページにもにも詳細に記載されています。
日本企業におけるDXの課題
階層型組織の弊害
従来の日本の大企業に多く見られる階層型組織は、意思決定のスピードが遅く、新しいビジネスモデルへの変更や適応が難しいという課題を抱えています。これは、DXのように迅速な変化が求められる時代に大きな足かせとなります。なぜなら、階層型組織では、意思決定がトップダウンで行われることが多く、現場の声が反映されにくいからです。また、部門間の縦割り意識が強く、連携が取りにくいという問題もあります。VUCA時代の到来
VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった言葉で、現代のビジネス環境を特徴づけるものです。VUCAの時代においては、将来の予測が困難であり、迅速かつ柔軟な対応が求められますが、従来の階層型組織では対応が難しい場合があります。例えば、市場の変化に迅速に対応するためには、現場の状況を把握し、柔軟に意思決定を行う必要がありますが、階層型組織では、情報伝達が遅く、意思決定に時間がかかることがあります。顧客ニーズの多様化
顧客ニーズが多様化・複雑化する現代においては、部門ごとに最適化された業務運営では、顧客全体のニーズを捉えきれない可能性があります。部門間の連携や情報共有が不足し、全体最適な視点での意思決定が困難になることがあります。例えば、ある商品に対する顧客からのフィードバックが、商品開発部門だけでなく、マーケティング部門や営業部門にも共有されなければ、顧客満足度を向上させるための効果的な施策を打つことができません。
アフラックのアジャイル型組織モデル「Agile@Aflac」
アフラックは、これらの課題を解決するために、アジャイル型の組織モデル「Agile@Aflac」を導入しました。
3階層モデル
Agile@Aflacは、原則、手法、組織の3階層で構成されています。アジャイルの5原則(顧客価値にフォーカス、実証的アプローチ、機能横断的、エンパワーメント、反復的プロセス)を基礎とし、具体的なアジャイル手法(スクラムなど)を活用し、組織全体をアジャイルに適応させています。3階層モデルの各階層は、以下のように定義されています。1階(原則): アジャイルの5原則を理解し、日々の業務に組み込むことを目指します。
2階(手法): スクラムなどのアジャイル手法を活用し、透明性と効率性を高め、コミュニケーションを促進します。
3階(組織): トライブ・スクワッドモデルを導入し、柔軟性と機動性を高めます。
トライブ・スクワッドモデル
機能横断的なチーム「スクワッド」を複数集めた「トライブ」という組織を形成し、迅速な意思決定と価値創出を実現しています。スクワッドは、それぞれの専門性を持つメンバーで構成され、特定の顧客価値に焦点を当てて活動します。これにより、部門間の連携が強化され、顧客中心のサービス提供が可能になります。アジャイルコーチ
アジャイルコーチは、チームに伴走し、アジャイルの原則に基づいた働き方をサポートします。チームが自律的に活動できるよう支援し、問題解決や改善を促します。コーチは、アジャイルの専門知識や経験を持つ人材が担当し、チームメンバーの育成にも貢献します。
Agile@Aflac導入の背景
アフラックでは、組織のサイロ化、意思決定の遅さ、部門最適の業務運営などが課題として顕在化していました。また、外部環境においても、顧客ニーズの多様化や競争環境の激化が進み、これらの課題に対処しなければ、企業としての成長が困難になるとの危機感が募っていました。そこで、経営陣は、SpotifyやINGなど、海外企業におけるアジャイルの活用事例を参考に、アジャイル型の業務運営モデルを導入することを決定しました。
経営陣のコミットメント
アジャイルの有用性を実感
経営陣は、海外視察やLEGOを用いたワークショップを通じて、アジャイルの有用性を実感しました。特に、LEGOを用いたワークショップでは、顧客のニーズを満たす街づくりをチームで行うことで、アジャイルの原則である顧客中心、チームワーク、継続的改善などを体験的に学ぶことができました。この体験を通じて、経営陣はアジャイルに対する理解を深め、その導入に積極的にコミットしました。アジャイル推進室の新設
アジャイル推進室を新設し、経営陣と連携してアジャイル推進の目的と原則を明確化しました。アジャイル推進室は、アジャイルの専門家を集めた組織であり、アジャイルの導入・定着を支援する役割を担っています。この組織の新設により、全社的な取り組みとしてアジャイルを推進する体制が整いました。社内浸透
全役職員を対象にエンゲージメントプランを策定し、アジャイルの理解促進を図りました。全社会議や動画、研修などを活用し、アジャイルの考え方や手法を浸透させました。これにより、社員のアジャイルに対する理解度を高め、アジャイル型の働き方への抵抗感を減らすことができました。
アフラックにおける成果
Agile@Aflacの導入により、アフラックは様々な成果を上げることができました。
顧客満足度向上
保険契約の保全手続きにおけるNPS(ネットプロモータースコア)が18ポイント向上し、業界1位を獲得しました。これは、顧客の声を聞きながら、機能横断的なチームで改善に取り組んだ結果です。商品開発期間短縮
医療保険の新商品開発期間が従来の約半分に短縮されました。これは、部門間の連携を強化し、初期段階から多角的な視点で検討を進めた結果です。顧客体験向上
マイページのUI/UX改善やアフラックメールのペーパーレス化により、顧客体験が向上しました。お客様の声を直接聞き、それを元に改善策を検討・実施することで、顧客満足度を高めることができました。営業変革
AIを活用した保険募集人のトレーニングシステムを導入し、生産性が向上しました。これは、ビジネス部門とIT部門が連携し、募集人のニーズに応えるシステムを開発した結果です。社会貢献
キャンサーエコシステムの構築が評価され、消費者庁長官表彰を受賞しました。これは、がん患者とその家族の課題解決に向けて、様々な関係者と連携し、顧客中心の取り組みを進めた結果です。従業員エンゲージメント向上
組織横断的なチームでの活動により、社員の学習機会や成長機会が増加し、88%の社員が働きがいを感じています。
アフラックは、アジャイル型の働き方を組織文化として根付かせ、機動的な業務執行を実現することで、社会と共有できる新たな価値を創造することを目指しています。この取り組みは、大企業におけるDX推進の成功事例として、他の日本企業にとっても参考になるものと言えるでしょう。特に、経営陣のコミットメント、全社的な浸透活動、継続的な改善などが成功の要因として挙げられます。
人事視点から考えること
アフラックがアジャイルを導入するにあたり、人事の視点から考慮すべきポイントを考えてみたいと思います。アジャイル導入は、組織全体の業務効率や柔軟性を向上させる重要な取り組みであり、人事部門はこの変革を成功させるための重要な役割を果たします。
1. エンパワーメントと権限委譲
従来のヒエラルキー型組織の問題点
従来のヒエラルキー型組織では、意思決定が上層部に集中し、現場の意見が反映されにくく、意思決定に時間がかかるという問題がありました。この結果、現場の社員は受動的になり、創造性やイノベーションが抑制される傾向がありました。アジャイル導入後は、トライブリードやプロダクトオーナーに権限が委譲され、現場の迅速な意思決定が可能となります。
権限委譲の重要性
権限委譲により、各チームが自律的に業務を進めることができるようになります。これにより、現場の社員は自分たちの判断で行動できる自由度が増し、責任感が醸成されます。これは、社員のモチベーションや創造性を高めるために非常に重要です。現場での迅速な意思決定が可能となることで、顧客対応や市場の変化に迅速に対応できるようになります。
具体的な施策
人事部門は、権限委譲をスムーズに進めるために、各リーダーに対してリーダーシップ研修などを実施し、権限を持つことの重要性と責任を理解させることが必要です。また、各チームが自律的に業務を進めるための支援ツールやリソースを提供し、必要な場合にはアドバイスやサポートを行います。
2. 人材育成とキャリアパスの多様化
従来のキャリアパスの問題点
従来のキャリアパスは固定的であり、社員の成長やスキル開発が限定的でした。これにより、社員のキャリア成長が停滞し、モチベーションの低下が懸念されました。
多様なキャリアパスの必要性
アジャイル環境では、従来の固定的なキャリアパスではなく、多様なキャリアパスが存在します。社員はトライブやスクワッド内での異動やプロジェクトを通じて多様なスキルを習得し、キャリアを柔軟に発展させることができます。これにより、社員のスキルセットが広がり、組織全体の競争力が向上します。
具体的な施策
人事部門としては、多様なキャリアパスをサポートするための研修プログラムやキャリアカウンセリングを提供する必要があります。また、社員が自身のキャリアを積極的に開発できるように、自己啓発のためのリソースや学習機会を提供します。これには、オンラインコース、セミナー、ワークショップなどが含まれます。さらに、定期的にキャリア開発のためのフィードバックセッションを実施し、社員の成長をサポートします。
3. チームベースの評価システム
従来の評価システムの問題点
従来の評価システムは個人のパフォーマンスに焦点を当てており、チーム全体の協力やコラボレーションの重要性が十分に評価されていませんでした。この結果、個人主義が強まり、チーム全体のパフォーマンス向上が阻害されることがありました。
チームベースの評価の重要性
アジャイル導入後は、個人のパフォーマンス評価からチームベースの評価システムへとシフトする必要があります。トライブやスクワッドの成果が重視されるため、チーム全体の協力やコミュニケーションが評価されるべきです。これにより、チームメンバー間の信頼と協力が促進され、組織全体のパフォーマンスが向上します。
具体的な施策
人事としても、新しい評価システムを検討し、導入する役割を担います。この評価システムでは、チームの成果や協力、イノベーションへの貢献が評価されるようにします。また、評価基準を透明にし、定期的にフィードバックを提供することで、社員が評価の基準を理解し、自身のパフォーマンスを向上させるための具体的な行動を取れるようにします。さらに、評価結果を基に、報酬やインセンティブを設定し、社員のモチベーションを高める施策を導入します。
4. 継続的な学習と改善
継続的な学習の重要性
アジャイル環境では、継続的な学習と改善が重要な文化となります。社員は定期的にフィードバックを受け取り、自己改善に努めることが求められます。これにより、常に最新のスキルや知識を習得し、業務に反映させることができます。
具体的な施策
人事部門は、継続的な学習を支援するために、社内研修プログラムやオンライン学習プラットフォームを整備します。また、フィードバックの仕組みを構築し、定期的な評価とフィードバックセッションを実施します。これにより、社員は自身の強みと改善点を把握し、具体的な改善策を講じることができます。さらに、学習と改善を促進するためのインセンティブ制度を導入し、学習意欲を高めます。
5. コミュニケーションと透明性の確保
コミュニケーションの重要性
アジャイル導入に伴い、組織内のコミュニケーションと透明性が重要となります。トライブやスクワッド内でのオープンなコミュニケーションが奨励され、情報共有が迅速に行われることが求められます。
具体的な施策
人事部門は、このようなコミュニケーション文化を促進するためのワークショップやトレーニングを提供する必要があります。また、組織全体の目標や戦略が明確に共有されるよう、透明性を確保する取り組みを行います。これには、定期的な全社ミーティングや経営層からの情報発信が含まれます。さらに、社員が自由に意見を述べることができる環境を整えるためのオープンドアポリシーや意見箱の設置なども検討します。
6. アジャイルコーチの役割
アジャイルコーチの重要性
アジャイルコーチは、チームがアジャイル原則を実践し、効果的に機能するためのサポートを提供します。アジャイルコーチは、チームのパフォーマンス向上や問題解決を支援し、チームの成長を促進します。
具体的な施策
人事部門は、アジャイルコーチの育成と配置を担当し、彼らがチームを効果的にサポートできるようにする必要があります。アジャイルコーチは、チーム内のコミュニケーションを促進し、心理的安全性を確保する役割を担います。また、アジャイルコーチのトレーニングプログラムを提供し、彼らのスキルと知識を継続的に向上させます。さらに、アジャイルコーチの役割と責任を明確にし、チームメンバーとの信頼関係を築くためのサポートを行います。
総まとめ
アフラックのアジャイル導入は、組織全体の効率性と柔軟性を高める重要な取り組みですが、人事部門の役割も非常に重要です。エンパワーメントの推進、人材育成の強化、チームベースの評価システムの導入、継続的な学習の支援、コミュニケーションの促進、そしてアジャイルコーチのサポートを通じて、アジャイル文化を根付かせることが求められます。
これにより、社員のモチベーションとパフォーマンスが向上し、組織全体の競争力が強化されます。人事部門は、この変革をリードする重要な役割を果たし、組織の持続的な成長を支えるために、全社員のエンゲージメントと成長を促進する必要があるでしょう。
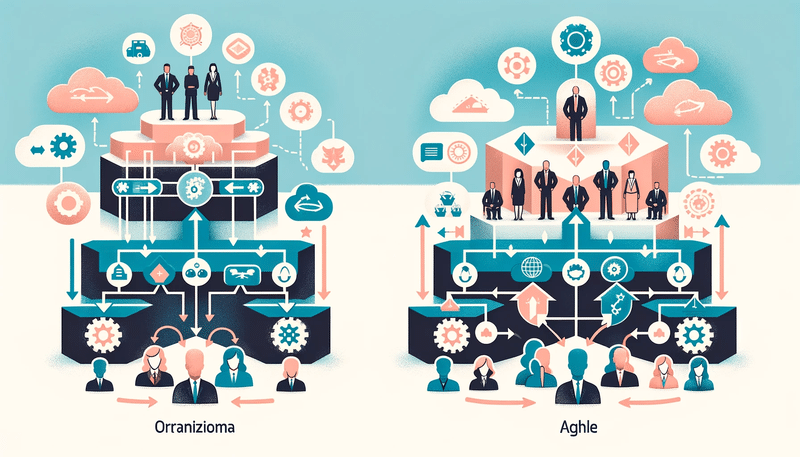
アフラックのアジャイルモデル「Agile@Aflac」の三層構造を示しています。
左側には、「原則」層が描かれ、顧客価値にフォーカス、実証的アプローチ、機能横断的、エンパワーメント、反復的プロセスの5つのアジャイル原則が示されています。
中央には、「手法」層が描かれ、スクラムなどの具体的なアジャイル手法が透明性と効率性を高めるために活用されている様子が示されています。
右側には、「組織」層が描かれ、トライブ・スクワッドモデルが示されています。これは、機能横断的なチームが連携し、協力的に活動している様子が表現されています。
柔らかなパステルカラーで描かれており、親しみやすいビジュアルスタイルになっています。このイラストは、Agile@Aflacモデルの各層の特徴とその働きを視覚的に理解するのに役立ちます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
