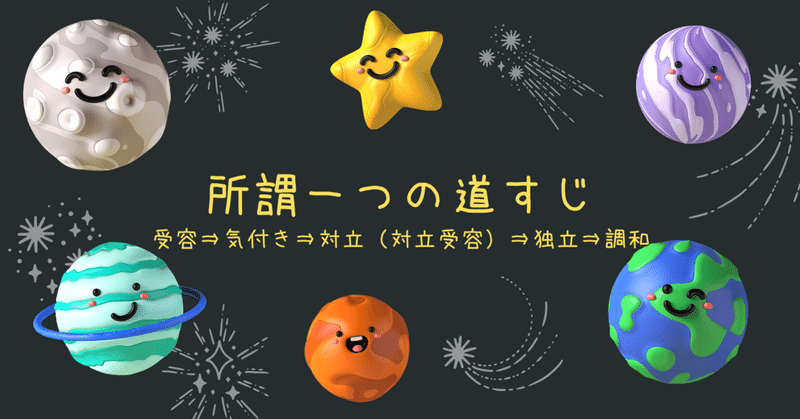
所謂一つの道すじ
最近良く思う事がまた言語化されてきました。
受容⇒気付き⇒対立(対立受容)⇒独立⇒調和
正解なんてないけれど、だいたいこういう流れを辿っていっているんではないかという自論。もちろんこれら一つ一つの段階にも正解はない。
けれど、勝手気まま無責任に書き散らしていきます。異論は認めない(嘘)。
わたしの周りにも、世間でやたらと騒動になっている風邪みたいなアレを中心に、世の中が嘘で塗り固められていると感じている人が増えてきました。
わたしはもともと懐疑精神旺盛というか、メジャーな意見、情報に触れた時にだいたい「何かしっくりこないし、多分逆なんだろうな・・・」と思ったり、反射的にそれで得をする存在は何だろう?とか考えてしまうので、基本的にはこっそりと反論、というか心の中でグレていることが多かったです。
心の中でグレる、というのは目立って反発するようなことはせず、いい子を演じながら「ケッ」と思ってる、みたいな。
わかりやすく反発するのがどうもくだらなく思えたり、とはいえ若い時は負のオーラを漂わせて、たまに思いっきり対立することもあったのですが。
最近の騒動、それに対立する意見や情報、Q何とかに関連するような話を見たり聞いたりしていて、特に強い言葉を使う人々から時折感じる気持ち悪さというか違和感から
「ああ、これは対立の重いエネルギー・・・」
と、そういったものに楽しさ、嬉しさを感じないので、そこからどうありたいのか、どうあるほうが良いのか考えていたら、一連の流れがイメージされてきました。
以下、その流れの段階一つ一つの概要。
受容
まず与えられ、受け入れる。わかりやすい例が教育。
まっさらなところに権威的な存在からの教えを受けて、それを信じます。
陥りやすいのが
「〇〇(先生とか自分が信じる人)が言っていたから」
というのが、自分の行動原理になっていて思考停止している状態。
おせっかい、に触れると心がキューッとするというか、もの凄い違和感に襲われるんですけれど、おせっかいが出来る状態というのは、一定のものを盲目的に信じている状態、と勝手に思っています。
まあ、状況にもよる、とか色々あるとは思いますが、普通の対人関係において、社会的にそういう役割についてしまった訳でもなく、頼まれもしないのにわざわざ他人に対して指導をする、というのは相当自分の信条に自信があるのではないでしょうか。
そして、全てのことにおいて正解はない、ということは明白なので、少しでもそういうことを自分自身で思考したことがあれば、結果的に迷いなく選択したことであっても「自分にとっての正解」でしかなく、「万人にとっての紛れもない真実」であろうはずがない、ということに気付くはずです。
小さい子供と触れ合う事が多い生活をしていますが、
「あっ、(マスクから)鼻出してる!」(子供にありがちな”事象を指摘しているだけ”ではなく明らかに”出すな”という意志表示)
と人を指さす子を見たりすると、鼻が出ているか出ていないかの違い、そもそもマスクの効果があらゆる方面から様々な解釈があることを総合した上で、あなたは「鼻を出してはいけない」という選択をしたのか?その上で他人にも自分と同じ考えになりなさい、と説いているのか?と問いたくなってしまいますが、まず子供は色んなことを受容していく環境に置かれます。
(いや一生・・・?)
そして子供の頃に受容したもの、というのは根深く残る傾向があります。
気付き
すでに前項で若干触れている要素ですが、
受容した上で、感覚的でも論理的でも
「ん?」
といった違和感、時には「嫌だな」という拒絶。そこに気付く事。
何故、自分が受容していたのか
受容すると自分や周りがどうなるのか
受容するメリットは何か
受容させたい人が存在するが、それは何故か
そこからより違和感がなく、自分にフィットするものを探します。
また、もちろん違和感が全くなく受容したものがフィットする、ということもあります。
対立(対立受容)
自分にフィットするものがだいたい定まってきた時、ここでまた陥りやすいのが、対立です。
時に自分にフィットするものと受容させられようとしていたものの乖離が大きいと、そこに憤りを感じる事が多いのです。何故なのでしょう・・・
そして、仲間を作って相反するものを攻撃したり、勝ち負けに固執するようなスタンスになっていたり、ひどいと戦うことが目的になっていたり・・・
スピリチュアル的にもよく言われることですが、対立すると、その相手をフォーカスすることになるので、それが自分にとってより大きな存在になってきます(体験済み)。
勝つのが困難なことも多いし、そもそも勝ったあとってどうなるんでしょうか。わたしは勝った人達にフィットしない人がいつか現れて、対立するような気がします。
というか結局、これもおせっかいの一種なんだと思います。
ただ、対立の中に一種の快感が生まれることがあります(体験済み)。
単純に意見や事象についての考察を表現するだけではなくて、、、
相手に対して、周到な正論で滑稽さを指摘して陥れたり、わざわざ嘲笑したり、強い言葉を使ったり、そういった行為を仲間と共感しながら行う事。ネット等では、もの凄く手の込んだ、高いスキルで作り上げられていて、確かに面白く出来ている対立のエネルギーの固まりを目にすることがあります。
あれ、楽しいんですよね。攻撃が楽しいんです。わかります。そして癖になる。中毒性がある。
そういう時の気持ちを思い返すと、涙を流しながら喜んでいたというか、ホント中毒って言葉がしっくりくるんですけれど、今では一言に「悲しかった」と感じます。何で人間アレを楽しめるようになっているんでしょうか?
わたしの中ではある種答えっぽいのが出ているのですが(元来そういうエネルギーを好む種類の生物の遺伝子が人間には・・)、それは置いといて、そういうのは悲しいなと思います。
そして、カッコ内の対立受容。これは「気付き」から対立と対立受容の二股に分かれているイメージです。
冒頭でのわたしが心の中でグレていた、というのもこれに近い状態です。
色々な違和感や憤りを感じつつも、意識的か無意識的かそれらを丸ごと飲み込んで
「しょうがない」
「どうせ考えても無駄」
「我慢しよう」
といった、諦めや拗ねを抱えて、愚痴のような簡単で軽いものでしか表に出さずに過ごしている状態。
パッと見、程度の差こそあれど、この状態の人が一番多いと思います。
これは、気付かずに心身に負担をかけていることになります。対立して攻撃しているのもストレスだと思うのですが、飲み込んで抱えて無理して、それを継続して、その結果に希望も持てなければそりゃあ身体にも負担をかけてしまう。心と身体は繋がっています。
これも悲しい。
まーここまできてなんですけど、この一つ一つの段階は綺麗に分かれているのではなくて、境目は曖昧で、この部分はこっちだけど他はあっち、みたいなマーブル状な感じです。人間なので当然。
独立
対立ではない、対立受容でもない、ではその先は何か。
独立、としたのは、盲目的な受容も対立もしない。ただ自分のあるべきを理解して在ること。難しいです、難しい。
最近人と喋っていて出てきた言葉は、時に「すれ違う(無視ではない)」。
なんというか、自分はこう、というのがはっきりしていて、それを純粋に楽しみながら在ることが出来ていたら、他をちゃんと見た上で気にならなくなってくると思うのです。
巷でよく言われている「風の時代」。検索すると出てくるキーワードが
個人主義・自分軸
変化・自由・柔軟
心を大事にする
流動的・・・
とか沢山ありますが、ちょうどそんなイメージでした。こういうの流行っているのでしょう。
相変わらず物理的な、具体的にどうするのか、が見えてきませんが、そもそもそういうことなのだと思えてきました。三次元の感覚が少しずつ希薄になってくるというか。
ちょっとだけ具体的なやつとして、これからはフリーランスが熱い、的な表現も巷では溢れていますが、まぁ確かに結果的にそういう面もあります。
組織に属すると受容しなければならないことが多いですし、となると対立(対立受容)が発生しやすくなります。ホントは自分次第でそれはどうにでもなるのですが、やはり難しいので、なるべく難しくないようにするにはフリーランス、というやり方は効果があるような気がします。
ここらで、わたしの好きな「純粋なエネルギー」というのも発し易くなってきます。あるべきでいながらそれぞれが楽しんでいれば、そういうエネルギーになってきますよね。
個人主義というキーワードを出してしまいましたが、別に一人っきりでやるという意味ではないです。
本来、世の中はもっともっと多種多様で、あらゆるところでお互いが想像もつかないことをやったりし始めるはず、という昔からのわたしの感覚。
悲しいことも全然少ないんじゃないかなぁ。
これまでのところは、わたし自身実感として体験したものも多いですが、この先は「こうなんだろうなぁ」と思ったり、人の話を聞いたり読んだりしてフィットしてはいるものの、まだ捉えきれていない、と感じているものです。実は。だからもっと言葉がめちゃくちゃになったり、受け売りみたいになってきます。
調和
さらに境目なんてもうあるのかないのかなのですが、独立の項で言っているようなことが色んなところで起きてくると、それだけではないような状態になってくると思えて仕方がないのです。
独立、個、なんですがそれ故に調和していくんです。
一つ一つの固まりが個人であろうと集団であろうと、お互いが干渉せず、在り方を認め合っているような状態、1万年以上大きな争いのなかった縄文の文化がそうであった、といった説もありますが、そんなイメージ。
個、という言葉を使いながら、個を強めていくのではなく、自他の境目がなくなっていくというか・・・物理的にではなく精神的に・・・
まぁ、案の定うまく言葉に出来ないので、独立の先には何かあるかもです、って感じにして締めます。
締め
また時間が経って、思うところが出てくるのかな、と思います。修正したくなるのかな。異論は認めます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
