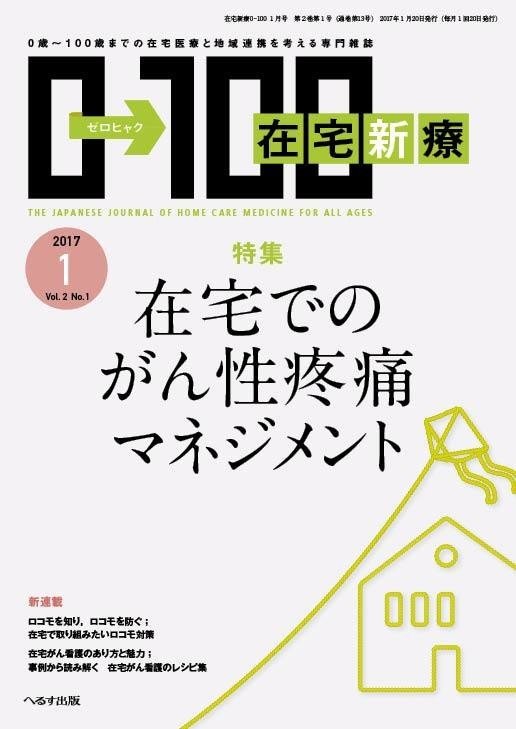【第5回】白衣を着たらスーパーマン、でも脱いだら何もできない。そんな天使じゃ地域へは飛び立てない!
個別性の宝庫である在宅医療の世界には、患者の個性と同じように、ケアする側も多彩で無数の悩みをかかえています。悩みにも個別性があり、一方で普遍性・共通性もあるようです。多くの先輩たちは、そうした悩みにどのように向き合い、目の前の壁をどのように越えてきたのでしょうか。また、自分と同世代の人たちは、今どんな悩みに直面しているのでしょうか。多くの患者と、もっと多くの医療従事者とつながってこられた秋山正子さんをホストに、よりよいケアを見つめ直すカフェとして誌上展開してきた本連載、noteにて再オープンです(連載期間:2017年1月~2018年12月)
【ホスト】秋山 正子
株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長、暮らしの保健室室長、認定NPO 法人maggie’s tokyo 共同代表
【ゲスト】間渕 由紀子(まぶち ゆきこ)
株式会社たまこうき 訪問看護宮沢の太陽/ふらっと相談くらしの保健室たま
―――――――――――――――――――――――
対談前の思い・テーマ
① 急性期の看護は面白かったから、ずっと現場にいたかった…
病気をみたり、人をみたり、急性期の看護は実に興味深く面白かった。だから、地域連携の責任者をやるように言われたときは、「私の看護師人生をどうしてくれるの!」と抵抗もしました。現場で看護をしていたかったので、現場を離れたくはなかったですね。
②地域って、在宅って、面白いです
急性期の看護からは離れましたが、地域連携の仕事もやってみると面白く、打ち込みました。ただ、振り返ってみると、病院にいたころに地域のことが今ほど見えていただろうか、と思います。地域に根差さないと見えてこないつながりや複雑さが地域にはあって、それもとても面白いと感じています。
東京都西部地区で、病院と地域をつなぎ続けてきた
秋山 「国立市在宅療養何でも相談窓口」相談室長の間渕さん、室長として何年になりましたか。
間渕 3年目です。相談件数も増えてきて、相談室が地域に浸透してきている印象です。
秋山 前職の「国家公務員共済組合連合会立川病院」(以下、立川病院)の地域医療連携センターの業務経験が、しっかり生きているようですね。病院長が代わったときに、病院自体も地域へ向けて門戸を開いた感じですか?
間渕 それまでも医療連携室はありましたが、東海大学の病院で院長もされた篠原幸人先生が病院長として来て、「地域からの依頼は困っての依頼なのだから何でも受けなさい」「小さいことでも受けなさい」と、地域をみるように一気に大きく変わったんです。その後、私も連携センターに異動になりました。
立川病院って、いわゆる殿様商売的な雰囲気があったと思うんです。外では「仏の相互(立川相互病院)、鬼の共済(立川病院)」って言われていたくらいで。でも、病診連携を主体的に国が動かしはじめたころで、篠原院長は、「患者に来てもらってこその病院だ」と、はっきりと方針を示し、「こんな殿様商売を民間はしていない」「医師が頂点のピラミッドじゃなくて、皆がフラットにならなければ」と訓示されました。
連携室で、私はかなり自由に働かせてもらっていて、そこで与えられていたキーワードは、「地域とつながる」と「救急を受ける」。救急隊から来る救急ではなく、地域の医師や施設などからの救急を受ける「窓口の仕事をしてほしい」と言われて、看護職として担当になりました。地域の医師からの電話を一元的にほとんど私が受けていて、地域とそこからつながりはじめました。
秋山 病院内だけでの連携と、地域全体との連携を考えるのとでは、かなり勝手が違ったのではないですか?院内で「チーム医療」というと医師とつながり、ケースワーカーとつながり、栄養士とつながり…みたいに、専門職同士がキューッとまとまっているけれど、地域はそのように整ってはいない。
間渕 たしかに。
秋山 方針さえ決まれば院内の連携はそれほど説明なしでもつながっていけると思いますが、外とつながる際には、相手は見えていないし、相手の考えもわからない。まず、色眼鏡なしで話をしてみて、「あれ?」と思ったら、「あの人、どういう人?」って、情報収集するでしょ(笑)。どんな考えで仕事をしている人かというのを見たり、何人かから聞いたりして、「ああ、そういうふうに地域で働いているのか」とわかったうえで、話をしていく。
「なるほど。だからこういう反応なのか。私がいつもつながっている人とは違うけど、頑張っている人だな」と判断して、多少のズレはあっても、患者・家族にプラスになりそうな人とはつながろうとアプローチしていく。
間渕 脈があるな、という人はね。
秋山 この人を入れると、新しい連携が築けてうまくいきそうだったら、多少違うところがあっても、何とか地域に出てきてもらおうとしますね。それにはこちらがツンケンしてたら、絶対にそれはできないわけじゃない。そのツンケンが、病院のなかだけだと、けっこうあるでしょう?
間渕 ありますね、力んじゃってね。でも、私たちもそうだったもの。病院にいるときって、白衣を着たら、もうスーパーマンになった気分なのよね(笑)。
秋山 目の前の患者のために何でもする!ってね(笑)。
間渕 それで、脱いだ途端に普通の人以下になってね(笑)。何もできない人になってしまう。病院で働いていたときって、それくらいテンションを上げて頑張ってたんだと思うんですね。キャップの位置を直したり、白衣が汚れてないかとか、すごく気をつかって、いい意味のナイチンゲール精神みたいなものを胸に病棟に行き、私は別に天使じゃないけれども、ペテン師かもしれないけれども、頑張ろうって(笑)、やってきたじゃない?でも、地域ってそれじゃ通用しないから。
ずっと現場にいたかったけれど…
秋山 「鬼の共済」と言われつつ、地域とつながる面白さも感じたんじゃないですか?
間渕 最初はかなり抵抗もしましたけどね。ずっと外科系の病棟にいて、手をかければかけるほど元気になるみたいなところにやりがいを感じていたので、「私の看護師としてのキャリアをどうしてくれるんだ!」って。でもなぜか、外来を統括する外来診療室師長というポジションになって、「医師のことも管理しなさい」と管理者に言われたんです(笑)。
秋山 最初は外来への異動だったんですか。
間渕 そう。それでその外来で、衝撃を受けたの。内科の外来ってすさまじく忙しいのに、看護スタッフ皆が医師のほうを見ていて、患者のことをぜんぜん見ていない。カウンターがあるのにカウンターに誰もいない。だから、異動してから1カ月しないうちにミーティングを開き、私が「外来に来ている人たちに関心を寄せましょう」「待っている人たちの具合の悪さを拾い上げられるような看護師であってほしい」と言ったら、パートの看護師を含めて総スカンで。
秋山 そこは臆せず指摘したんですね。
間渕 「外来のことを何も知らないくせに、偉そうなことを言いますね」みたいに皆から言われたけれど、「外来のことを知らないから言えることがある。皆が、患者を見ずに医師のほうだけを見て、カルテ整理だけをしている看護師であってはならないと思うので、まずそれをやめましょう。カルテ整理は私でもできるから私がやります」と、しばらくは外来に張り付いてカルテ整理をし、ほかの看護師にはカウンターに立ってもらったの。そのほかにもさまざまな提案をし、体制を考えてだんだん慣れてきて、1年ほど経ったとき、「地域連携センターを建てるから、そこのセンター長に出ろ」と言われたんです。「私は看護職なのに…」とまた抵抗して。翼の折れたエンジェルじゃないけど(笑)、「なんで私がそんなところに行かなきゃいけないの?」って、すごく抵抗したの。
秋山 現場から離れたくない。
間渕 そうそう。でも「地域に向けて立ち上げて、うまくやれるのはあいつしかいない」って院長が言ってるなら、と。ただ当時は、どこも医師がセンター長だったから、私自身も、「医師がやればいいのに」と思っていました。「なぜ看護師が長なのか」と抵抗を示す医師やケースワーカーもいたけれど、看護師を置くは・・・しりでもあったんですね。だから、翼の折れたエンジェルが、違う翼を得て、エンジェルではなかったけど、それからペテン師人生が始まったんです(笑)。
秋山 外来で総反発を食らって、普通だったらそこでシュンとなるところを、1年かけて変えて、次につながっていくというのは、粘り強いですね。
間渕 面白かったわよ。
秋山 面白いっていうところがすごいよね。
センター長という立場を、逆に医師じゃなく看護が担うことで、外からはやわらかい印象をもたれる面もあったと思います。
間渕 それに加えて、センター長が医師の病院でも、その医師が直接電話を取るわけではなくて、事務員が取って、医師につなぐのがほとんど。私は窓口でありセンター長だったから、連絡を直接受けて「こういう状況だから、何分くらいで受け入れてください」ということを院内に情報伝達できたので、当初の反発はあったにしても、医師はだんだんそれに慣れてくれました。その代わりギブアンドテイクで、その医師が困ったときには何かで助けてあげるようにして、皆、お互いに仕事としては敵対せず助け合えるようになったの。
敵対してる場合じゃなくて、私は、病院に受けてもらうのが仕事なんだから、地域から“お客様”を受けて、渡さなきゃいけない。
秋山 地域に渡すけど「受けません」ではダメだもんね。
間渕 まず受けなければならない。そうすると、私が院内の医師に伝えたときに、要求される情報がすごく多くて、「データは?」とかいろいろ聞かれる。地域にはデータがない場合、採血も何もしてないような場合もあるんだけど、そんなときにデータ以外の情報を得ようといろいろと聞くと、地域の医師は別として、地域の介護老人保健施設などの看護師からくる電話での内容は、言っていることがよくわからない。「○○のための受診・入院です」ということが伝わってこなくて、「どういうこと?」ってよく聞き返していたんです。
だから「鬼の共済」と言われるのは、私たち連携センターも同じだったと思う。地域から見たら、「頼むと何か厳しいことを言われるけど、ちゃんと話せばやってくれる」場所。そういう関係はできていたんだと思うのだけれど、今、私が地域に出たら、皆がそれを言うわけ。「怖かったんですよね」って(笑)。私、あんなにやさしかったのに。
秋山 逆に言うと、地域の窓口である連携センターのほとんどに看護師がおらず、置かれていたのがソーシャルワーカーや事務の人だから、地域の看護師はあまり状況的なことを聞かれる場面がなかったんでしょうね。だから聞かれても答えられないというのを、初めて経験した。でも、それって地域の人たちの訓練になったんじゃないかしら。
ところで受け手側の視点としては、病院のベッドコントロールをする立場の人とも連携していないと、どこが空き病棟かがわからないですよね。
間渕 連携センターにパソコンがあって、そこで情報は見ることができたので、相談はしやすかったの。外科の病棟勤務時代から、医事課と協力して一緒にベッドを運んだりと、皆が動いてベッドコントロールをしていた。けっこう、どこでも自由放題していたかもしれない(笑)。
秋山 ベッドコントロールも、目の前の患者のニーズに応えることというか、患者目線を貫く一つの形なんだけれど、多くは、そこだけを小さく見がちです。一方で、全体を俯瞰して見ることができないと、地域連携は難しい面があるのですが、それを病棟時代に俯瞰してみられる人というのは、少ないと思う。それをもう、身につけていたのね。
自分の病棟だったら簡単にできるけど、連携センターになると、ほかの病棟の師長に対して相談するわけでしょ? それは、師長たちとのあいだで、どうだったんですか。
間渕 いろいろありましたよ(笑)。「今日は、手術でいっぱいでダメです」と言われて、「でも、今そこに手術が必要な人が来てるわけだから、どうにかならないの」って。きっと裏ではブーブー言ってたんでしょうけど、ちゃんと皆、協力してくれた。「あの人が言うからしょうがないかな」って、だんだんと私のやり方や病院の方針だからと慣れていったんだと思います。
秋山 そのときに、「自分が楽をしよう」とか、「自分がよく思われよう」とかいう私利私欲でなくて、間渕さんの場合は、常に患者目線という筋が一本通っているのだと思います。それで患者が入って来られて、よい看護ができて、ほかの人も早く帰ることができて、という経験を病棟側もすることで、「言われたことを受けても、決して後がこじれない」と実感できる。その経験をしていかないと、つなぐ人も信用はされないですね。
在宅経験ゼロでも、地域を支え、暮らしを支える
秋山 間渕さんは、在宅の経験はまったくないんだけれど、地域との連携や暮らす人としての患者を深くみることができている。外来の経験によるものでしょうか。
間渕 それもあると思うのと、後は入職したときの師長の影響じゃないかな。入職したばかりでいろいろなことを知らない私たちに、「あなたたち新人は何もできないんだから、尿器や便器をうまく使える人になりなさい」「患者さんが恥ずかしくないように運ぶ術すべを知りなさい」って、いつ運べばいいか、どういう洗い方がよいか、温めておく心遣いとかを師長から教わったの。
秋山 そんなこと、学校で教えないですよね。
間渕 食事を残したときには、「おいしくなかったのか、好きじゃないのか、食欲がないのか、そこまで聞いて一人前よ」、みたいなことを最初に言われた。こうるさい師長さんだった(笑)。うるさかったけれど、食べて排泄するというのは、普通のことだから、当然ですよね。
看護師も、三つ子の魂百までというのと一緒で、新人から5年くらいの間に出会った人がよい人だとよい基礎の吸収につながるのかな、と振り返ってみて思います。
あとは、病棟時代にボランティアで在宅に出ていたことと、認知症の母の介護経験は今の仕事につながっているかな。
秋山 在宅にボランティアで?
間渕 そう、訪問看護をしたかったんだけど、その当時はまだ訪問看護はなくて。
秋山 病棟にいたときに、そう思ったんですか?
間渕 脳神経外科病棟にいたときに。家に帰したいというのと、入院期間の短縮が急に始まったこともあって、脳神経外科というのは、そのころまでどうしても遷延して長く在院する人たちがいて、その人たちを家に帰さなければならなかった。
主任のころに出会った遷延性の意識障害の女性が、動けないで、体位変換は必要だけれども、車椅子には乗せられるような状態で、「病院にいたら食べさせられないけど、お家なら食べられるから帰りましょうか」と提案したの。そうしたらその人の夫が「追い出すのか」と怒っちゃって、「お前のことを一生恨んでやる」と、すごい剣幕だったんです。
娘が2人近所に住んでいて、「帰れると思うよ」と話はしていて、でも夫が「うん」と言わなければ連れて帰れないということだったので、たまたま私が通勤の途中で寄りやすい家だったので、引き換えにボランティアで週に1回か2回行くからといって、結局その人を家に帰して14年間みました。
秋山 エーッ!
間渕 30代後半のころ。あとは、脳腫瘍の人を自宅で看取るのを支えることもできました。
秋山 脳神経疾患は、どうしても普通の生活がしづらくなるのに、ましてや退院後、ボランティアで行くというのは、すごい(笑)。
間渕 退院させちゃったから(笑)。
秋山 それから14年生き抜いたということで、最初、その患者の夫がすごく怒っていたけど、どうだったの?
間渕 病院では、アイスクリームしか食べられなかったのが、ちょっと調子がいいときにはプリンを食べさせてあげられたり、意識状態がクリアなとき、ちょっといいかなというときには、「目、開いてるね」と車椅子に乗せて、夫と一緒に散歩に行ったりして。そうしたら、「おめぇが来るのを待ってんだ」みたいなおじいちゃんになっていきました(笑)。
秋山 だんだんね。
間渕 それはもう楽しかった。そのころは、まだ介護保険がない時代で、大工さんが板を持ってきて車椅子のスロープにしてくれたりして。その夫ももう亡くなったけど、今でもその家族とはお付き合いしてます。だから私は、本当に訪問看護師になりたかったの。
秋山 おお!
間渕 ほかにも、病棟から外泊のときに付いて行ったり、ボランティアで付いて行ったりとかして。けっこう周りから言われたけど、1人じゃなくて、何人か巻き込んで、「楽しいから行かない?」みたいに(笑)。
秋山 へぇー。
間渕 帰りにパンもらってきたりして(笑)。「パンもらっちゃったよ。皆で食べない?」「お金じゃないからいいんじゃない?」って。
地域に帰る患者も家族も、わからないことがいっぱいあったし、今もあると思うんです。本当に私、自分の母親の介護のときにわからなかったもの。どこに相談に行けばいいのか、どんなサービスがあるのか。ベッドも車椅子も買っちゃった。そのころは、もう介護保険はあったんだけど、それこそ、介護保険の使い方も知らないから。「これは、買わなくてよかったんですよ」と言われて「そうなの? どこに相談に行けばよかったの?」って。
でも、母の経験を通して、私がこれだけわからないんだから、病院の人も、地域の人もわからないだろうと……。だから、いっぱいパンフレットを作ったりする活動もしてきました。
間渕 病院・病棟とは全然違う在宅の世界。 かつて教わった看護の本質を見つめ直せる現場ですね
地域は、病棟とはまるで別の世界
間渕 でも、在宅は面白いね。奥が深くて。知らないことが山ほどあって。外来も在宅も、病棟とはまるで別世界なのね。
秋山 それは何?患者が生活者に変わるから?
間渕 全然わからないからかしらね。病棟から外来に行ったときには、うつ病になりそうだった。3カ月くらいは、しんどかった。
秋山 こちらがやれる範囲が見えないんだよね。
間渕 見えない。ないというより見えない。
秋山 在宅も外来も、患者は実は自立してるわけじゃない?生活者であり、自立している人に対して、どう支援をするかというのは、実は難しい。
間渕 難しい。それこそ脳神経外科の患者が、外来に行った途端に病人じゃないんだよね。病人じゃなくて社会人だからいろいろな人がいて、怒る人もいるし、結局、外来の看護師が怒られたら師長の私が出て行かなければならないじゃない?「この人、なんで怒ってるのかな?」と。
でもまあ、患者のほうを向かずに下を向いてカルテ整理をしていたら、そういうことになるよね。
秋山 患者を見てないというか、「見るとかかわらなければならない」というのもあるかもしれないですね。そんなふうに、病院で話を聞いてもらえていない状態の人が、maggie’stokyoへ来る。
間渕 病院という場では本音は言わない。本当に言わないね。
今思えば、病院にいたときも、もっと外に出ればよかったな。病院にいるときに、地域のことがちゃんと見えていたかな、って思います。見えているつもりだったけど、地域に出てみて、根差してみて初めてわかる細やかさ・複雑さが、地域にはある。
今はその人の生活がわからないと、どういう人かがわからないと思って、必ず訪問するようにしているの。がんの人でも、相談に来たときに、「おうちに訪問していいですか」と言って家に行くんだけど、ゴミがあれば、袋に入れながらしゃべって(笑)。台所はきれいかな、トイレは大丈夫かなとか、お鍋がいっぱいあって焦げてるから、この人認知症あるな、ってわかる。すごく面白い。
秋山 家の中へ入って、気になることがあったら見たり聞いたりできますよね。
間渕 そうそう。でも病院も少しずつだけど、変わってきている。「病院の人は生活が見えてない」って言われがちだけれど、でも「地域包括ケア病棟」っていう名前がいい意味でついたから、「家に帰しますよ!」って最初に言ってくれたり、「地域ケアを一緒にしなければならない」と、病棟の人たちの感覚が少し変わったと思う。もっと変わる必要はあるんだけど。
先日も、自宅で看取りができた家族が挨拶に来てくれて、「あなたにもっと早く会えていれば、3月の段階で帰れましたね」って。「3月から半年以上ずっと『うちに連れて帰りたい』って何回言ったかしれないけれど、病院で看護師さんにそう言っても『帰れるはずがない』と言われるだけでした」って。
秋山 そうした病院にある思い込みを突破するにはどうしたらよいでしょうね。
間渕 「この状況で帰れるわけがないでしょ」みたいなことを、言っちゃうんだよね。
看護の「看」は「手で見る」こと
秋山 一つは、入院させないことよね(笑)。だから、入院させないための医療や、ケアのマネジメントが必要なんだけれど。
最近思うのは、「何もしない」医療、自然に支える医療、何もしないで自然に、枯れるように亡くなっていくというのを、病院は知らないんだということですね。
間渕 それから、若くてまだ病気と闘える人と、高齢で闘えなくなった人がごちゃ混ぜになってることとか。新しい薬も出てきて、若年のがんの人たちには、まだ希望がある。若い人たちにはトライしてほしいと思うじゃない?「1日でも長生きすれば新しい治療法が出てくるから」って、がんの人たちに相談されると私はそう言うのよ。それで皆、頑張れるじゃない?
でも、高齢者はそうじゃないよね。1日頑張っても若くはならないもの。そのことを誰かが言わないとダメ。身体が萎えていくこと、筋肉が萎えていくこと。私が在宅の相談室でみていると、高齢者も若い人もごちゃ混ぜになっているから、逆に若い人のことを早く諦めたりすることもあって、そこをうまくコントロールできる人はいないのかな?と思います。
秋山 「何もしない」という積極的な選択は覚悟がいるけれど、ケアがキュアになる時期というのがあるんですね。吸引ばかりじゃなくて、口の中をきれいにして、体位を換えながら背中をさする。ちょっと横向きになることで、息が穏やかになる。そうやって少し胸を開いてあげたりすると、手によるケアはキュアを超える。そういう時期がある。それは、本当に何もしていないのではなくて、ケアという道具でちゃんと支えてるわけです。
それを選択するには勇気・覚悟がいるから、看取る側も覚悟がいり、そこを支える私たちがいる。ケアは、上手に教えると家族も参加できます。ケアにかかわることで家族はすごい満足感も得られるし、患者は息がスーッと楽になるから、「楽そうだよね」と見守っていられる。そうして周りで皆で話をしているうちに、「あれ?息をしてないな」という看取り方ができたりしますね。
間渕 やっぱり、そうやってきちんと言い換えてあげることが大事だと思う。それも治療の一つだよと言ってあげれば、治療しないことはひどいこと、終末期に何もしてあげないことはひどいこと、なんて思わず、「何もできなかった」と感じないで済む。
かつて私たちが習った「看護の看は手で見るんだよ」みたいに、手に目があるみたいに習ったんだけど、それを伝えていかなきゃいけないのかしら。若い人たちにも、家族にも伝えられれば、誰でもケアは、看護はできるんだものね。
秋山 最近よくいわれるユマニチュードじゃないけど、本人の目線に合わせて「帰りたいですか?」と、私たちは言ってきたよね?
間渕 言う、言う。
秋山 「触りながら話しましょう」って、当たり前よね(笑)。
間渕 「目を見て話しましょう」ね。本当に、当たり前のことができなくなってるのかも。
動けない人を端坐位にするときも、昔は上半身を左右前後に揺らして、「危なくないかな?」と動かしてみたと思うけれど、訪問看護師と仕事をすると、今はそんなこともしないの。一方で、医療的なことはすごく好き。でも、入浴介助はしても食事介助はしない。「食事は生活だからヘルパーに」って。
秋山 いやいや(笑)。例えば、自分の手で食べられる人の食事、誤嚥性肺炎の危険がある人の食事は、再入院の予防をする必要があるから、意図的に食事の場面を選んで訪問します。食事のセットをしながら少しの間、横について、看護的な見方で観察します。生活行為で分けるのではなく、個別のニーズをアセスメントして、予測してかかわるから意味があるのだと思いますね。
間渕 すぐれた実践のできる看護師は、医療的ケアだけに収まらないかかわり方をするから、もっとちゃんと包括的に生活全体をみられるんだけど、そうじゃない看護師もいる。
秋山 褥瘡の処置っていうと、そこだけ。
間渕 そう、そこだけしかできない。
秋山 栄養もみようよ、清潔もみようよ、って。
間渕 その人がどんな生活をしているかを、ちゃんとみようよ、と言いたい。そのうえに医療的な知識や技術が重なって、初めて看護になるんじゃないかって、私はこれまで言ってきたんだけど、今はそうじゃないんだよね。
秋山 治療はしなくてもケアはできるわけだから、そのケアの方法をきちんと提示してかかわれるように、私たちがかかわっていく。
間渕 そこをそうやって言葉にできて言える人が少ないんだと思う。「こうすることで、患者さんは楽になりますよ」と言ってあげられない。それを、秋山さんみたいに伝えることができる人は、まだまだ少ないと思うんだよね。
秋山 もっともっと、取り組みたいと思います(笑)。(了)
§ § §
対談をおえて
間渕 同郷の出身で頑張っている憧れの秋山さんとたくさんお話しできてうれしかったです。高齢者になって「何もしない」医療や、自然に枯れるように亡くなっていくことを急性期病院では知られていないこと、ケアがキュアになること、看護の看は「手で看る」と習ったこと、など看護について秋山さんとお互いに確認し合ったり、若い看護師時代に戻ったように熱く語り合い、時間を忘れるくらいでした。今後、地域の多職種と顔が見える連携をさらに構築して、国立市での「療養に関する何でも相談」について多職種と力を合わせて柔軟に対応していきたいと考えています。
秋山 同郷であることがわかってから、どこか共通項があると感じはじめていました。「目の前にいる患者さんのために何でもする」と、いつも全力疾走する姿が思い浮かぶ話に思わず聞きほれつつ、勤務する場が違っても、新しい場でさらにパワーアップして地域を耕していく姿に、在宅現場の看護師が学ぶことがたくさんあると思いました。病院と地域をつなぐ役割を具体的に果たす仕組みづくりも学びたいものです。
―――――――――――――――――――――――
【ゲストプロフィール】
国家公務員共済組合連合会立川病院に入職後、各科をローテーションで経験。とくに急性期の看護にやりがいと面白さを実感しながら勤務していたが、同院内に地域医療連携センターが開設されると同時にセンター長に任命される。看護の実践とは異なる部分に戸惑いながらも、病院の中から地域を見つめる働き方を面白く感じる。地域の診療所や施設からの急患を受け、病院から地域への退院を支え、クレームやセカンドオピニオンの対応もしながら10年間勤務。2014年からは病院の外で、地域と医療、住民と医療をつなぎ寄り添う相談室の窓口に常勤、国立市民の暮らしを支える。2006年10月から、居住地である昭島市の「暮らしの保健室多摩」で相談対応をしていたが、閉鎖に伴い、2008年7月から「(株)たまこうき 訪問看護宮沢の太陽」で責任者をしつつ「ふらっと相談くらしの保健室たま」で住民や専門職の健康相談を対応している。
【ホストプロフィール】
2016年10月maggie’s tokyoをオープン、センター長就任。事例検討に重きをおいた、暮らしの保健室での月1回の勉強会も継続、2020年ついに100回を超えた。2019年第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受章。
※本記事は、
『在宅新療0-100(ゼロヒャク)』 2017年1月号
「特集:在宅でのがん性疼痛マネジメント」
内の連載記事を再掲したものです。
『在宅新療0-100』は、0歳~100歳までの在宅医療と地域連携を考える専門雑誌として、2016年に創刊しました。誌名のとおり、0歳の子どもから100歳を超える高齢者、障害や疾病をもち困難をかかえるすべての方への在宅医療を考えることのできる雑誌であることを基本方針に据えた雑誌です。すべての方のさまざまな生活の場に応じて、日々の暮らしを支える医療、看護、ケア、さらに地域包括ケアシステムと多職種連携までを考える小誌は、2016年から2019年まで刊行され、現在は休刊中です。