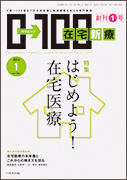【番外編/第13回】「地域包括ケア時代のコミュニケーションって何だ!? これからの医療人材を考える」
個別性の宝庫である在宅医療の世界には、患者の個性と同じように、ケアする側も多彩で無数の悩みをかかえています。悩みにも個別性があり、一方で普遍性・共通性もあるようです。多くの先輩たちは、そうした悩みにどのように向き合い、目の前の壁をどのように越えてきたのでしょうか。また、自分と同世代の人たちは、今どんな悩みに直面しているのでしょうか。多くの患者と、もっと多くの医療従事者とつながってこられた秋山正子さんをホストに、よりよいケアを見つめ直すカフェとして誌上展開してきた本連載、noteにて再オープンです(連載期間:2017年1月~2018年12月)
今回は番外編として創刊時の特別対談を模様替えして再掲します。
【ホスト】秋山 正子
株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長、暮らしの保健室室長、認定NPO法人 maggie’s tokyo 共同代表
【ゲスト】孫 大輔 (そん だいすけ)
対談当時:東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター
現:鳥取大学医学部地域医療学講座、日野病院組合日野病院総合診療科、日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医
―――――――――――――――――――――――
「みんながくる場所」=「みんくるカフェ」。東京大学で医学教育を担いながら、家庭医としての実践とともに、市民-医療者コミュニケーションの促進とよりよい関係構築のためのワークショップ「みんくるカフェ」の主宰もされている孫大輔先生と、長年訪問看護と地域づくりの実践者として活躍され、看護教育にも携わられている秋山正子氏に、これからの地域づくりに求められるコミュニケーションについて論じていただきます。
地域医療・家庭医療に飛び込んで出会ったもの
秋山 私が孫先生と出会ったのは、先生が聖路加国際大学で大学院生をされていたころでした。臨床医もされながら、家庭医をめざそうと思われ、大学病院を飛び出した。見えているものがそれまでの医療とは少し違っていましたか。
孫 全然違いますね。卒後8年目まで腎臓内科医で、ネズミを使って腎臓の研究をしていて、そのときにやっている医療と、自分がもともとやりたかった医療にギャップが出てきてしまったんです。
そのころ家庭医療のことを聞いたりして、自分の理想のような「こんな医療があったんだ!」という発見があって、エイッ!と飛び込んだのが9年目です。
秋山 訪問診療などで出会う患者たちというのは、病院のなかで出会う患者とは違った様相で、その人の素の状態、本音の部分がそのまま出ていませんか。
孫 より生活に近い患者というイメージです。家庭医になってからの患者との接し方では、よりその人の暮らし、生活の背景がみえます。生活に密接にからんだ病気をたくさん扱いますので、そういう意味では、暮らしに入っていく感じですね。一方で、生活習慣とか、その人の暮らし方をしっかり変えていく、そこにこちらも入っていかないと治らない・治りにくい病気でもあるので、ある意味、重症度とか複雑さは低いんだけれども、難しさは非常に高い。
専門医として働いていたときには、薬物療法のようなものに頼りますが、在宅や家庭医療では薬に頼らない治し方をしなければならない。そういうところにすごくシフトした印象がありました。そのなかで、「みんくるカフェ」の活動のように、病院や医療機関の外でどういうふうにアプローチするかというのを考えてきました。
どう鍛える? 医療者のコミュニケーション力
秋山 それまでは、大学病院のなかで、ある意味権威の象徴である白衣を着たお医者さんとして、しかも非常に専門性の高い治療をされていて、一段高いところからのコミュニケーションをしていた。在宅を始めるに際しては、かなり違ったコミュニケーションのスタイルを求められるわけですが、そのトレーニングは医学部ではほとんどされていない(笑)。
孫 病院のなかでも昔に比べると医師のスタンスとか、役割はどんどん変わってきていると思います。ただ、在宅医療とか地域の医療の先生たちは、いろいろなところにスッと入りこんでいくようなスタンスで、俗っぽい言い方ですけれども、決して上から目線ではない姿勢が、自然と身についている。そういうコミュニケーションの取り方から、立ち居振る舞いみたいなものをみて「全然違うなぁ」というのを、こっちの業界に来て、すごく思いました(笑)。
◆患者の体験を知覚する“力”
秋山 医療者のなかで考えているのではなく、患者から学ぶというのは、医学でも一般的にはいわれますが、もっと違った「患者のもっている力をどう引き出すか」みたいな側面についてはどうですか。
孫 そこはすごく深い問題で、患者のもっている「知」というものがあります。専門的なexpert knowledge に対して、lay expertise(素人の知)と表現している人がいます。それは、例えば患者が自分の闘病経験をとおして、自分たちでつくり出す知であって、それは患者によってしか患者に伝えることができないのだということ。
いわゆる素人の知というのは、まだ学問的にそれほど探究されていません。「みんくるカフェ」も、市民のほうは専門家から学べるとして、専門家のほうは市民・患者から何を学んでいるかというのはなかなか深い問題で、よくわからない。その一つは、もしかしたら患者にしかない知のようなものかもしれないし、単純に患者から意見を言ってもらうことで反省して、内省が深まるという学びもあるのですが、それ以上のものがあるのかなと私は考えています。
秋山 患者自身の病気=「病者としての体験」というのは、患者にしかわからないと思うんですよね。その人がそれを体験したなかで語る言葉には、時々とても驚くような表現があります。医療者には、病気というものを内的に体験している患者を、まるごとフラットに感じ取る力が要るのではないかと…。
在宅では、病院の中でものすごくサマライズされた単語だけが並ぶ症状の表現ではない、何か不思議な表現を聞くことがあって、それが逆に新鮮に思えることがあるのですが、それは私が感じているだけでしょうか。そういう体験はありますか。
孫 在宅での患者が発する言葉や表情は、入院しているときとは全然違います。患者がいる空間を含めてのその人の存在で、患者が家から切り離されている入院の場というのは、非日常でしかないわけです。非日常空間(病院)におかれている患者が医療者に伝えてくる言葉と家での言葉というのは、相当違う。
それを医療者、特に医者が、どこまで知覚できるかは非常に怪しくて、まず医学教育で習わないということもあるし、加えて患者は一般的に、医者の前では行儀よく振る舞いますよね。
訪問診療といえども、医師の訪問の場合は時間も非常に短いです。訪問看護は30分・1時間かけますけれど、医師は初診の患者でせいぜい20~30分、通常の訪問診療では5~10分くらいで回っていきます。この環境では、患者はすごくお行儀よく振る舞っていると、非常に感じます。
秋山 医師が見ている“顔”と、訪問看護師が見ている“顔”とは、確かに違うかなとは思います。ただ、そこでの対話の力というのは、時間が長い、短いではなくて、診療にすごく影響があると思っています。
◆医学教育と医学生の変化の兆し?
孫 医学教育の教員になって3年です。教育的視点で医学とか医療をみるときに、患者に対する共感といったものを、学生たちに本当に教えることができるのか、という問いを常に考えていて、医学生の共感能力が、教育によってどのように変化するかという研究を今やっています。共感の定義としてはsympathy =同情とはちょっと違います。sympathyは感情移入に近くて、共感というのはむしろ認知的な能力なので、教育によって成長させることができると考えている人たちも多いのです。
でも、秋山さんのお話のような、患者の本当の苦労とかsuffering(苦悩、つらさ)というのは、現場に行ったり、患者から直接聞いたりするなかで自分の想像力を使うという経験で成長するもので、学生にそれをわかってもらうのは、なかなか遠い道のりです。
ただ、その段階として、学生のときに身につける共感能力と、現場に出て長い経験のなかで培われる能力というのがある。今は、「健康と病いの語りディペックス・ジャパン(https://www.dipex-j.org/)」という患者のナラティブの動画サイトを使ったり、2週間の長期医療実習の最後に、患者ではないのですが市民と、「みんくるカフェ」のようなワールドカフェで対話してもらうという東京大学の医学教育で初の試みを取り入れているところです。
秋山 市民と学生とのディスカッションはどんな雰囲気でしょうか。
孫 けっこう“言う”市民もいて、僕はそういう経験も必要だなと思っています。東大生の場合は、基本的にそうやって真っ向から反論されるという経験が、学生でもほとんどないと思うので。ミソクソにとまでは言いませんけど、学生の発表の後に、ワーッとこきおろすおっちゃんもいて(笑)。
秋山 そこでいろいろ議論があった後で、学生たちの反応はどうですか。
孫 東大生という特殊な集団なので、両極端なんです。実習が「ものすごくよかった」「ほかの職種について学ぶことはほとんどないので、医療に対するイメージがガラッと変わった」と言う学生もいれば、「意味ない!」「こんな遠いところまで来させられて、流れ作業のような外来を見せられて、意味がわからない」みたいな意見もあって、真っ二つです。
東大の場合はそれまで地域医療の実習はまったくなく、2年前から地域医療実習が始まったので革命的だと思います。最初は1学年100人中50人だけの実施でしたが、今年から全員必修になり、東大としても地域医療を重視して、全学生に学んでもらおうという姿勢を示しています。
秋山 かなり革命的ですね。本郷を飛び出し柏という地域・町にある医療の拠点で学ぶことは、地域につながっているということをあらためて教える場になると思います。医学生は将来の志望として、地域というチャンネルはあまりもっていないですか。

医療者の共感する力は、どう養えるだろうか
秋山「医療者には、患者という存在をまるごとフラットに
感じ取る力が要るんじゃないかな」
孫「臨床現場で培われる共感能力の前段階にある、学生の時点での
共感能力をどう伸ばせるか、取り組んでいます」
孫 地域をみる総合診療医とか家庭医という概念が新しいので、全国的にも最近、学生の志望の一つとして急に出てきたという感じです。学生は、医療・医者というとほとんど病院医療をイメージしているので、訪問診療みたいなところを経験するチャンスが非常に少ない。「そういう医療が、これから必要なんだよ」ということも、わかっていってもらう必要がありますね。
地方の大学の話を聞くと、総合診療医を志望する学生がものすごく増えているそうで、診療科の希望をとると、総合診療科が最も多い大学もあると聞いています。一方で東大は、100人中2~3人です(笑)。
ただ、2~3人でも、本気でめざしてくれる人が出てきたので、それはすごくうれしくて。僕も、この2~3年いろいろと開拓してきたんですよ。まず、東大プライマリ・ケア研究会という学生向けの勉強会を毎月やって、そのうちにそういうことに興味のある学生を集めた東大総合診療勉強会「よろずや」というのが1年くらい前にできて、今は学生が自主的に進めています。
秋山 何か変化の兆しが…。
孫 そうですね。ほぼゼロだったところから、2~3人になったので(笑)。
「顔の見える関係」「フラットなコミュニケーション」って何だろう?
秋山 私が「暮らしの保健室」(対談会場)をつくった最初の1、2年目には、ボランティア的に何人もの病院の先生たちが話をしに来てくれたんです。専門医が、緩和ケアの話などをしてくれたりしたんですよ、白衣を脱いで、まったく不特定の人に。
ここは話し手と聞き手の距離が近いので、「どんな質問が飛んでくるかわからないところで話すのは、意外に緊張するなぁ」と言われてました。
孫 講演会のほうが楽ですよね。質問も、わりと直(ちょく)で来ないので。
秋山 逆をいえば、ここに座る市民側というか聴衆側はフラットな関係にだんだんと慣れていっているものだから、容赦なく「ここでその質問をするの?」みたいな話も率直にするんですよ。
孫 医療者が話をするときに、自分の医療機関で話をするのか、そうではない場所なのかでどう違うのかということですよね。例えば「暮らしの保健室」に医者が1人いると、集中攻撃じゃないけど「せっかくの機会だから、自分の健康相談をしよう」みたいな感じにもなりやすくて、それは容易に病院のなかのコミュニケーションに近づいてしまう。一方で、医者もいるんだけど、その人に集中砲火を浴びせるのではなくて、その人も皆と一緒に考えていくような対話をする「みんくるカフェ」的な場もあり、そこで得られるものもありますよね。
◆対話を本気で望む医療者が増えている
秋山 「みんくるカフェ」のファシリテーター養成講座を卒業した人たちが、各地で「みんくるカフェ」を始めている。市民と医療者とのスムーズなコミュニケーションができていく地域がみられるというのは、なかなかすてきです。
孫 僕なんかより、よっぽど上手なファシリテーターが多数いるんです。もともとちょっとやっていた人が、「みんくるカフェ」の養成講座に来て、よりパワーアップして自分の地域でやっています。
病院の中だけでは限界があるし、時間も限られている。こういうことをやりたいという医療者が増えているのは、単純にいいことだなと思いますね。
秋山 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML(コムル)を始めた辻本好子さんが、患者学ということを述べています。患者側も要求を通すということではなくて、こういう聞き方をしたら医療者側の感情を逆なですることになると気づき、そういう言葉は使わないで、ちゃんと自分の思うこと・質問したいことをきちんと伝える。そういうマナーとか、ルールというのを、患者学として学ぶべきだとしていて、お互いに歩み寄るためのコミュニケーションの技術というか、それがスキルアップしていかなければいけないかなと思います。
ちょうど、医師と患者の間に立つ医療コーディネーターなどの言葉が出てきていますが、看護はその間に立つことがけっこうあって、調整をしたり、そういう能力を発揮しながらチーム員それぞれがうまく機能するように努力をするわけです。そういう力を、こちらも上げていかなければならない。
孫 COML の山口育子さんの講演で、患者側の言い方と医療者側の言い方との溝がどうしても埋まらないことがあって、「その溝はもしかしたら永遠に埋まらないものかもしれない」と言われた。それを聞いたときに愕然としたんですけれど、逆に、医療者側も患者側の視点をわかったと思い込みすぎてしまうと、それはそれで傲慢というか、わかったつもりになっているだけかもしれない。
ですから、医療を続ければ続けるほど、患者の視点や気持ちを、本当にわかっていなかったなぁと思うことがあります。そういうものなんだな、そこに向かって歩み続けるプロセスなんだなと。
秋山 溝が埋まっていないことを、きちんと自覚したうえでコミュニケーションしていく。「溝はある。けれども理解はしたい」という、その思いを伝えていくことで、溝は厳然としてあるんだけれども、近づけるのかなと思います。
◆臨床現場でのコミュニケーションを成熟させよう
秋山 今いわれているチーム医療、特に地域包括ケアという、これから向かっていく方向においては、他職種とも協働していかなければならない。
トップダウンは、実は下の者は楽です。ある意味、責任は負わずに、言われたことだけやっていればいい。ただ、トップがとてもすばらしい人だったらいいですが、そうとはかぎらないわけで、ではどうしたらいいか。やはりフラットなコミュニケーションができる状態であることが大切です。
孫 多職種連携の話が、最近すごく盛り上がっていますけれども、それは、いろいろなところでの関係性がフラットになってきていることと関係があると思います。昔は、医療者―患者関係も、医師―他職種の関係も、ヒエラルキーの関係にあって、それに甘んじていたわけですが、多職種連携の本質をみていくと、現在もまだかなりの部分でヒエラルキーの問題があって、それが大きなバリアになっています。
秋山 ヒエラルキーのトップに立つ医師が、「自分がトップの位置にいる」とあまり自覚しない状態で、トップにいながらフラットなつもりでいると、とんでもないことが起きるんじゃないかと…。
孫 裸の王様みたいですが、そういうことは容易に起こり得ます。自分を相対的にみるのは、皆、なかなか苦手ですから。対話を重ねて自分を相対的にみたり、ある事象を多角的な視点でみることが、今すごく求められています。
◆医学・看護教育でのコミュニケーションを考える
孫 現場の問題点をみると、単純に他職種の専門性とか、職能を理解していないことが、じつは多いです。例えば、医者が作業療法士とは何をする人かが、あまりよくわかっていないとか。各職種の力量をわかっていないために、全然連携が取れていないことが起こります。
他職種理解のためにきちんと勉強することが学部でもあまりないですし、患者のケースを中心にして、複数職種のチームで最適化して仕事をしていく訓練も、ほとんどないです。最近になってやっと、チーム医療とか、多職種連携の教育が入ってきましたが、非常に大切なのに、ほとんど学部で習っていないことの一つですね。
秋山 意外に医学部のある地方の大学で試みをしているところがあったりしますね。
孫 昭和大学はその一つです。1年生の医学部、看護学部、リハビリなどの学部と、3~4学部を富士吉田市に集めて、1年間全寮制で過ごさせるんですよね。1つの部屋に3職種くらいがルームメートになって、強制的に1年間をそこで過ごすというのをやっていますね。もう卒業した学年がいて、そのおかげで他の職種とのコミュニケーションに壁がないというか、抵抗がないと学生から聞きました。
秋山 看護は、いちおう基礎教育で各職種の中身を習うので、医学部の学生よりは他職種を理解しやすいのではないかと思います。
一方で、看護教育に対する危機感を抱いてもいます。医師が臓器別に専門分化したのを追いかけて、それと似たようなことをしているグループもある。もちろんそれも、一つの道でもあるので否定はしませんが、よりジェネラルなというか、看護こそ総合性を求めていかないといけないんじゃないかなと思っています。
地域包括ケア時代の共通言語って何だ?
◆白衣を脱いで一歩をどう踏み出すか
秋山 これからは間口の広いことが考えられる人、「生活の場」すべてにいる看護の対象者に対応できる人材が大切になってきます。
そのときに、医師・看護師の関係だけではなくて、多職種、しかも地域のなかに生活する本当に多くの人とコミュニケーションがとれなければならない。患者とのコミュニケーションという意味だけではなくて、ほかの言語を使う人たちとも、どうコミュニケートしていくかは、大きな課題です。そういう意味でも、幅広くアンテナが張れる人が育っていくことが大事だなと思っています。
孫 秋山さんが、朝のラジオ体操が終わった後に、隠れ脱水の話をしたり、まさにコミュニティに溶け込んだ形で教育や対話をされている。そういう取り組みができれば、どうコミュニケーションをとるかという話を超えると思うんです。共通言語というよりは、入っていく姿勢みたいなものかなと。
社会に本当に有効なはたらきかけとは何かと考える若い人たちも増えてきているので、単に「コミュニケーションのとり方を学ばないとダメだよ」と言うより、もっと飛び越えて「こういうことをどんどんやっていくと、従来の枠組みにとらわれない社会貢献ができるんだよ」というような。そういう形でコミュニティに飛び込んでもらうというのも、ありかなと思うんです。
秋山 いろいろなはたらきかけをする際、旧来型・日本型のコミュニケーションではなく、「私はこう思っている」「これまでこうやってきた」「これについてこう提案したい」と表出することが必要で、同時に世代などを超えていくことも大切です。白衣を脱いで町に出たら、いろいろな人がいる。そこに勇気をもって一歩踏み出していく。病院のなかって、じつをいうとすごく守られている環境なんですよ。守られていて、かつ自分たちを守るべく身構えている。その鎧を脱いで、自分をある意味解き放って前に出るには、何らかの後押しをする人や教育のしくみといった一工夫は必要だと思っています。それは新しい医療の側面、特に看護の側面かもしれない。
白衣という鎧と同じで、「白い巨塔」もやはり厳然とあるんですよ。巨塔のなかにいて見えるものと、見えにくくなっているものがあるから、そこから出て行くことも必要なんじゃないかと思うんです。
孫 病気になったら「白い巨塔」的なところへ行くというあり方から、そういう医療の拠点が地域に小さい形で出て行くというイメージへ、地域のなかに点在している病院の手前のサービスや、それこそ専門職の人たちがこの暮らしの保健室みたいな形でいてくれて話ができる。そういうほうが絶対にいいですよね。
秋山 それこそが、包括ケアですよね。
孫 社会の医療化に反対する人たちもいますね、すべてが医療の視点でとらえられていってしまう…というような。
秋山 もっと手前で医療的な面でのアセスメントをきちんとできるようにしていけば、それ以上の医療化は防いでいけると思うんですよね。そこをスルーしてきてしまったんじゃないかなという気がします。逆に私は、超高齢社会のなかで、「超高齢者が病院に行くとロクなことがないよ」(笑)と伝えたい。
本当に必要なときは病院を利用させてもらうけれども、今までのように、全部病院にお願いしたらすべてがうまくいっていた時代とは違うことを、一般の人も知る必要がある。行ったら楽だということではないので、地域包括ケアのしくみのなかで、在宅療養を経験して、成功体験がきちんと蓄積されないとならない。単に家に帰して、そこに何もつなげなかった結果、結局は困り果てて、また病院へ戻るということを繰り返していて、それでは在宅は定着しないと思います。
きちんとつないで、たとえ一人暮らしでも在宅で安心して過ごせる状況をつくったうえであれば、病院に行くことをそれほど選ばないと思います。20年近くこの新宿区の牛込・四谷地区でかかわってきましたが、この地域で要支援・要介護状態になった人は、今のサービスをそのまま希望する人がほかの地区よりも高い割合です。それはやはり、在宅経験をした人が多い地域だからだと。積み重ねてやってきたことの結果が、多少なりとも出ているかなとは感じていて、それにはちょっと希望をもっています。
◆超高齢社会の明るい未来
孫 最近、あまりにも超高齢社会が暗くとらえられすぎているので、「ぜんぜん、そんなことはないよ」と、特に若い人たちに発信していきたいと思っています。元気な高齢者が増えて、高齢者が産みだす価値が高まる社会であれば、ものすごく明るい社会じゃないですか。
そういうふうにとらえていかないと、高齢者が2人に1人で、過疎化が進んで、人口減少で自治体が消滅して、若い人に負担が……という、ものすごく暗いイメージになっているので、ちょっとそれは違うんじゃないかなと思っているんです。
秋山 先日、ここ(暮らしの保健室)の上の階の一人暮らしの人の家に新聞が溜まっていたことがありました。この人が独居でちょっと心配なことは、皆がそれとなく感じていて、新聞が重なって入っていたから「大丈夫かしら」と思って、近所の高齢の男性が、お菓子屋のおばさんに何か聞いているか尋ね、おばさんは、そこまでは知らないので、暮らしの保健室に聞きに来たんです。暮らしの保健室は、先週の水曜日には様子をみているんだけど、それ以上はわからない。
そこで少し動いてみると、本人は娘さんの家で元気だということがわかったんです。最初は「部屋で倒れていたらどうしよう」とか、心配が膨らむんだけど、無事であることを皆で共有できた。その後、「周囲が心配するから新聞は預かっておきましょうか」という話になって周りの人たちの心配を減らす。人のつながりがそうやってできていく様を、つい先日経験したのです。
それで、その次の日にラジオ体操があったんですが、その心配したおじさんが寄ってきて、「昨日は、どうも大ごとになっちゃって…」と言われた。でも、その人が言ってくれたから、そこまでわかったわけで、大切なきっかけなんですね。人間関係が続いていくんです。
孫 ラジオ体操も、交流の場になっているんですね。東大の近くに谷根千という下町があるんですが、そこは銭湯が高齢者の交流の場になっていて、大切な恒常的ソーシャルキャピタルではないかという仮説があるんですが(笑)、いまその銭湯が、かなり税金をもっていかれるので相続できなくてつぶれる状況が増えていて、それを地元の人が非常に心配に思っているらしいのです。
それで、銭湯を支える活動にリンクさせて、高齢者の健康を支える地域活動みたいなものができないかなというので、少し取り組みを始めようとしているところです。
秋山 ナショナルトラスト風に買い上げればいいんですよね。
孫 本当に公的な銭湯にしたら…(笑)。
秋山 井戸端がなくなり、縁台で将棋もなくなり、床屋でのコミュニケーションもない。そしたら銭湯は貴重なコミュニケーションの場ですよね。そこで何かやる若者グループがいそうな気がするんだけど。
孫 ちょっと組織しましょうかね(笑)。 (了)
―――――――――――――――――――――――

【ゲストプロフィール】
対談当時:東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター
現:鳥取大学医学部地域医療学講座、日野病院組合日野病院総合診療科、日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医

【ホストプロフィール】
2016年10月 maggie’s tokyo をオープン、センター長就任。事例検討に重きをおいた、暮らしの保健室での月1回の勉強会も継続、2020年ついに100回を超えた。2019年第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受章。
―――――――――――――――――――――――
※本記事は、『在宅新療0-100(ゼロヒャク)』2016年1月号(創刊号)「特集:はじめよう! 在宅医療」内の、「創刊記念対談:地域包括ケア時代のコミュニケーションって何だ!?;これからの医療人材を考える」を再掲したものです。
『在宅新療0-100』は、0歳~100歳までの在宅医療と地域連携を考える専門雑誌として、2016年に創刊しました。誌名のとおり、0歳の子どもから100歳を超える高齢者、障害や疾病をもち困難をかかえるすべての方への在宅医療を考えることのできる雑誌であることを基本方針に据えた雑誌です。すべての方のさまざまな生活の場に応じて、日々の暮らしを支える医療、看護、ケア、さらに地域包括ケアシステムと多職種連携までを考える小誌は、2016年から2019年まで刊行され、現在は休刊中です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?