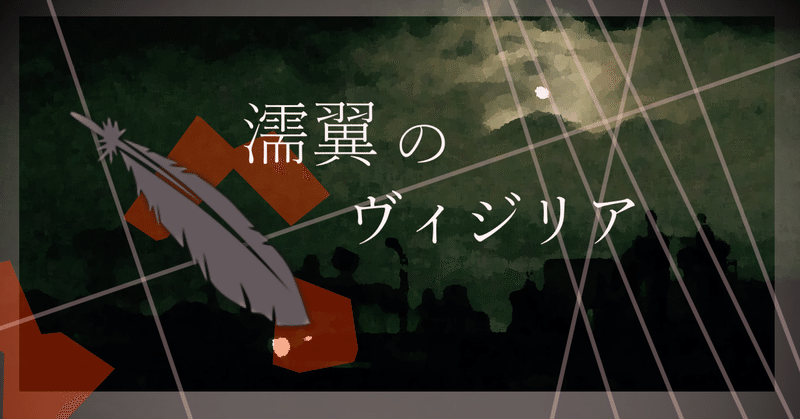
【小説】濡翼のヴィジリア【第一話】
あらすじ
世はヒトと獣が分かたれたばかりの20世紀初頭、長く列強諸国の脅威に脅かされ、今しも二重帝国によって呑み込まれつつある東欧。法院の審問官ウィルドは相棒のレナータと共に妖精をターゲットとした連続殺人事件を追っている。
劇場での大量虐殺をきっかけにエスカレートした犯行は、やがて国を巻き込んだテロ事件へと発展していく。秘密結社、妖精狩りの過去、切り離された民族――渦巻く陰謀の果てに現れた黒幕と、ウィルドたちが出した答えとは。これは誰もが当事者になってしまう時代が始まる直前の、とある惨劇の記録である。
『焼けた鉄と、河原の石のような濡れた匂い』と法院では教えている。
生き物の壊れ方はどれも似たり寄ったりだ。
血と糞尿のおぞましい臭気に、ほのかに交じる濡れた肉の香。
廊下には床にはまだ羽が残っていた。大振りの風切り羽――力任せにむしられたせいで根に血が付いたままだった。
「焼いた刃でひと刺し。いつものパターンです」
突き当りを調べていたレナータがカンテラを振って言う。
空気取りが開かれ、ふうふうと彼女が息を送ると、灯りが少しだけ強くなった。廊下いっぱいに散乱した青い羽がシルエットとなって浮かび上がる。
「検視課から死体が上がったのかね」
「いえ、向こうの壁に穴が。燐も濃いので、あそこが殺害現場ですね」
壁の穴はウィルドの腹の高さにあった。化粧板を外して調べてみると、壁材の方は傷だけで焦げてなかった。刺して、焼ける前にすぐ抜いている。
「得物はサーブルだ。刀身の反りは二六ミリメートル」
「よく折れませんでしたね」
「床面と水平に構えてる。デュエリストだな……腰を低く構えて”フレッシュ”! ぶすりと心臓ごとひと突きしてすぐ切っ先を逃がしている」
ロビーを調べると、暖炉に細いものを突き刺した跡があった。レナータがかがんで触れ、「ここの灰、鉄で汚れてます」とつぶやく。
「この場所で刃を焼いたか。刺す前かい」
「ええ。でも、毎回こんな面倒なことを?」
「血で汚したくないんだろう。熱で縮んだ肉からスッと刃を抜くほどの技量があるわけだ」
「潔癖症なんですかね」
「さあてね……」
ひとつ、部屋を開けた。
むっと生臭い熱気があふれてレナータがえずく。ウィルドは構わず立ち入って、莚を敷いた床に膝をついた。使ったにしては乱れていない。置いてある桶も中身は空っぽだった。
「現場はここだったね?」
「たぶん。店主によると、被害者が入るのはいつもここだったと」
「桶が使われていない」
レナータがジャケットの袖で口を覆いながら入ってくる。嫌悪感を隠す気はないらしい。
「さッすが我が同胞。最期のときまで高潔だった……!」
「それ、本音かな」
「ンなわけないでしょうが。寿命の前におっ死ぬ間抜けなんざ全員残らず役立たずのゴミクズです」
「ブレないねえ。感心だ」
ウィルドは笑って、シャツのポケットからメモ帳を取り出した。レナータがカンテラを寄せてくれたので、その灯りを頼りに報告をまとめる。
「ああ、これでいい。大丈夫だ……」
この桶のこと、警察はたぶん記録していないだろう。
帯剣しながら娼館通いできるやつを相手にする度胸は、彼らには無い。
この国でフェアにやりたい判事は、まず法院に行く。金もヒトもまるで足りていないが、あそこだったら札束を切らなくてもマトモな資料をもらえる。
トコトコと階段を降りるレナータの透ける赤い羽を見ながら、ウィルドはこのあいだの五四〇歳の誕生日を思い出した。仙鳥というものは言われるほど長命ではないのだが、気が付けば同僚はみんな曾孫世代になってしまった。
ふむ、と尖った爪でホルスターの銃把をこちこちと叩く。
「どうにも鳥というのは鼻が利かなくていけないな」
「夜目と同じくらいですか?」
「ああ。だからカンテラをしっかり持ちたまえよ、きみ」
寝る直前に裁判所の遣いが来て、呼び出された。眠くて仕方がない。
幸い、この気難しい新人は助手として充分に働いてくれるから、早く帰ることはできそうだった。
死体が上がると、いつもウィルドが呼び出される。
たしかに死骸なら飽きるほど見てきた。自らの手でヒトの死骸を作ったこともある。まだ新鮮なものを口にして、血肉としたこともある。ほんの少し前までヒトも獣も同じだったから、当たり前のことだった。
ヒトは――ほとんどの獣と同様、骨と肉と血で出来ている。その組織の大部分は水と炭に由来し、残ったものを析出するとわずかな食塩や鉄といったものが現れる。
ここには燐のにおいが溢れているらしい。
燐は、いわば筋肉を動かす燃料だ。
カウンターには未開封のワインが残っていた。ぴっ、とそいつの口を切ってウィルドは飲み下す。腐ったものには特に燐が多い。腐らせて作るワインとて例外ではない。
「すみません、それ証拠品です」
「うむ。今は私の腹で調査中だ。そして分析によれば、この酒は事件と関係ない」
「このアル中カラスが……」
「なんか言ったかね?」
レナータは憤慨したようにカウンターに座って、グラスを滑らせてきた。ウィルドが残りを注いで戻すと、彼女は小鳥みたいにちまちまと飲んで顔をしかめた。
「まっずッ! これで売り物なんですか」
「個人醸造の密造酒なんてそんなものさね。パンの酵母を使い回してるから、ちっとばかし芳醇に腐ったブドウ汁といったところだな」
「それに金を払うやつがいるんですか。理解できない……」
そっと盗み見たカウンターのメニュー表は、すべてラテン表記で書かれていた。カウンターの後ろには聖人のイコンが飾ってある。正教徒の店なのだろう。
「これで四件目。どんどん犯行のスパンが短くなってます」
レナータが舌打ちしてグラスを押しだす。
「人間なんて昔みたいにきっちり管理されるべきなんですよ。あいつらって、要するに毛のないサルでしょ。野生動物なんです。誰かが芸を仕込まないとどんどん野蛮になって仕方がない」
荒っぽく眼帯が外されて、海賊傷の付いたまぶたが曝け出された。
曰く、まだ電気のない時代に妖精狩りに遭って片目を潰されたらしい。今でも根に持っていて、休みの日には市役所の前で怪しげな看板を振っていると聞く。
「……私は人間、嫌いじゃないがねえ」
「意味わかんない。だって連中って全身がハゲなんですよ?」
「ハゲだってこれからの季節は涼しくて悪かないぜ?」
ウィルドは横目で店内を眺めた。
ダウンタウンの闇酒場。二階には休憩所があり、一階もステージのある派手な造りをしていた。雇われの女給は八人だと言っていた。どいつも不法移民だ。
「また妖精か」
きっと見つかっていないだけで、被害者はもっと多いだろう。
「ええ。人間だけ襲ってくれればいいものを」
「今のところ全員、外からの移民だ。犯人のルールははっきりしている」
「行動力のある馬鹿って厄介ですよね。移民が嫌なら黙って引きこもってりゃいいのに」
「そうしなかったから我々が動いているわけだよ、レナータ審問官」
ウィルドは爪を伸ばして、レナータが首にかけたメダリオンをはじいた。
酒場の外に出てみると、今晩は明るい月が出ていた。
暇そうにしていた御者にチップを放り投げてタクシーに乗る。ウィルドが手提げカバンから蒸留酒のスキットルを取り出してグビグビと飲んでいると、向かいにレナータが座ってきた。
彼女もいつものようにパイプにハーブを詰めると、ぽっとマッチで火を点けた。軽く三度ほど吹かしたところでスケジュール帳を開いて、鼻から薄荷色の煙を吐き出す。カンテラは座席に置かずに、大事に膝で挟んでいた。
「まだ資料課は仕事があるのかね」
「いえ。貴官こそ、このまま法院に?」
「この時間じゃ帰ったところで誰もおらんだろうよ」
連絡窓をちょっと開けて、通りの名前を御者に告げる。蹄鉄の音を聞きながら、ウィルドは流れゆく景色を見つめた。
二重帝国からの資本が入って以来、この国も工業化が進む一方だ。
ウィーンから伸びてきた鉄道は、首都を縫うように走る路面電車と、働き口を求める移民の流入をもたらした。公共交通機関のせいでタクシーはずいぶん減ってしまったらしい。
「家に二年のボルドーがある。当たり年じゃないが、付き合ってくれないか」
「いいんですか?」
「ああ、早めに空けてしまいたい」
タイルの割れた地面。区画整理された狭い道――新市街の建物はすべて同じ形をしている。どいつも外国の工場から運んできた安いレンガを組み上げた、人の入った石棺だ。住んでいるのも労働者ばかりだから、昼にはゴーストタウンに様変わりする。
繁華街をひとつ外れるだけで、こうした現代のスラム街が広がる。
かつては紫色に輝く町、と言われたこともある景色だ。
「『紫に澱んだ町』の間違いだろうさ……」
ヒトの時代はいつも澱みを運び、街を吹き溜まりに変える。
今や、鉄と石炭の風はヨーロッパ中に吹き荒れている。
レナータが不思議そうに見上げてきて、ポンと口から煙のリングを吐き出した。
「まったく、昔は良かったと思わないか」
「自己実現に失敗してるやつのセリフですよ、それ」
彼女はまたつまらなそうにスケジュール帳に目を落とした。
思わず笑みが漏れた。これだから自分はこの娘が好きなのだな、と思う。
06/12/2023 小道具の描写に誤りがあり、修正
#創作大賞2023 #ファンタジー小説部門
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
