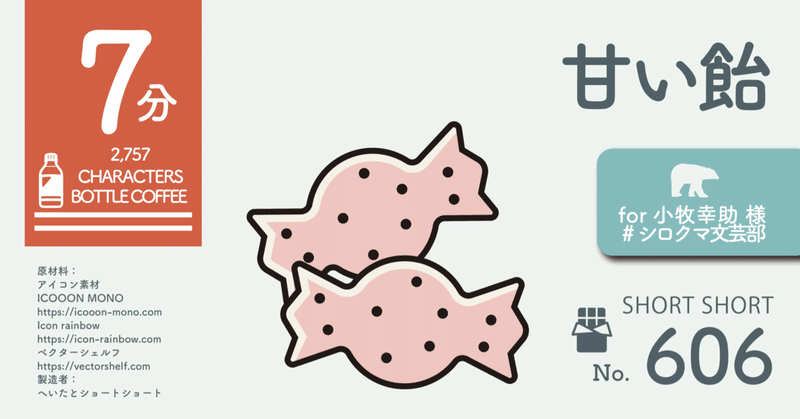
掌編小説 甘い飴(#シロクマ文芸部)
舞うイチゴ。甘い匂いのする包み紙。
最近父さんと母さんがよく怒鳴り合いの喧嘩をしている、と思ったら私のことだった。自分の部屋に戻るふりをしてリビングに聞き耳を立てたのだ。
「そのチラシ、嫌味か」
父さんがイラついた声が聞こえた。ガタガタ、と物音がして母さんが
「捨てようと思って置いといたの」
と少し怯えた声で言った。
「ローンは組まんからな」
吐き捨てるみたいに父さんが言った。少し間があって大きな声を出した。
「悪かったな。稼ぎが悪くて」
「そんなこと言ってないでしょ」
「目が、言ってんだよ」
「私立行くとは限らないし」
「聡子だぞ?」
私か。
と出そうになった声を飲み込んだ。音を立てないように自室に戻った。
床に転がっていたピンクのウサギのぬいぐるみを拾い上げて、ベッドに寝っ転がってぎゅうぎゅう抱きしめながら
「私か」
今度は声に出して言った。
ここの一ヶ月くらいの慣例の、小学生みたいにむくれた父さんと、岩のように押し黙っている母さんに挟まれて食べる朝食の気分は最低だった。私かよ。私のせいで喧嘩してるんだこの二人。多分、学費だ。最悪だ。私があほの子のせいで家庭が崩壊しかかってるだなんて。恥ずかしかった。もっと早く気がつくべきだった。
「行ってくる」
父さんが席を立った。母さんは答えない。
「おかわり」
空になった茶碗を母さんに差し出した。母さんが怪訝そうな目で私を見た。
「何にも聞いてないよ?」
慌てて言った。冷や汗が出た。母さんが複雑そうな顔をした。
「3杯目よ」
ほんの少しだけご飯をよそって返してくれた。
「あんまり、心配しなくていいから」
父さんの食器を片付けながら母さんが言った。私ってどうしてこんなに阿呆なんだろう。
「そんなの、さっちゃんが本気出したら、ちょちょいのちょいだよ!」
昼休み。幼馴染のモッチーが自分の爪を眺めながら言った。イチゴミルクの甘いにおいがする。
「またその飴舐めてるの?」
『人の気も知らないで』と言いそうになるのを我慢する。ふふふふん。とモッチーが得意そうに笑って、右の人差し指で自分の癖っ毛をくるくる巻いた。
「だって好きなんだもん」
髪の毛をほどくとポケットから平たい缶を取り出した。缶のフタいっぱいに油性マジックで落書きがしてあった。
「一個食べる?」
モッチーが缶のふたを開ける。中に白地にイチゴ模様の包み紙のキャンディーがぎゅうぎゅうに詰まっていた。
「いや、いいよ」
開けた蓋を閉めさせながら、また『気楽でいいよな』と言いそうになるのを我慢した。モッチーの子供っぽさがたまにすごく嫌になる。もう高校2年なのに能天気すぎ。小学生じゃないんだから。
「本気出すかあ」
残念そうな顔をするモッチーから目を逸らしながら伸びをした。
「ちょちょいのちょいだよ!」
モッチーが合いの手を打った。
コーヒーだ。アイスコーヒー。
勉強するのだ。夜中まで。
残念なことだが(非常に残念なことだが)、自分の頭の悪さを私はよく知っていた。でも仕方がない。家内安全のためだ。成績を上げることにした。やるしかない。
夕食後、いつもはすぐに動画を見て寝ちゃうところを、ちゃんと宿題をやってから寝ることにした。いつも浜田さんのをモッチーと書き写していたけど、自力でやるのだ。寝てしまわないためにカフェインは是非とも必要だった。エナジードリンクを買うお小遣いはなかったけど、父さんが朝飲むインスタントコーヒーはあったから。粉を水で溶かせばいくらでもできた。インスタントコーヒーの減りが早くなるのに父さんはすぐに気づいたけれど、勉強するのに起きてたいから飲んでると正直に言ったら、それ以上は咎められなかった。
「中間テスト、どうだったー?」
甘ったるい息のモッチーが私に尋ねる。黙って成績表を見せてやる。
「『ちょちょいのちょい』じゃーん」
モッチーが感嘆の声を上げた。褒め上手だ。昔から。確かに前回より少し良くなったけど、ようやく赤点がなくなったぐらいのことだ。
「あったまいー」
赤点の方が多いモッチーがひじで私を突いてる。
「でも、無理しちゃダメだからね」
モッチーが私の目の下を指差した。
「クマができてる」
「友達」「自分」「足を引っ張る」
帰るなりスマホで寝転びながら検索をした。自分のステージにあった友人を持ちなさい、みたいな記事を何本か読んだ。時計を見て青くなる。随分時間をくっていた。本当だ。と思った。こんなことで頭を悩ませるなんて馬鹿げていた。台所に行って、いつもより濃いめのアイスコーヒーを作った。遅れた分、今日はたくさん起きていなくちゃいけない。氷をたくさん入れた。気合いが入るような気がした。
勉強机に置いて、ノートを開いて、一問解くたび一口飲んだ。初めの頃こそ苦かったけど、もう何にも感じなかった。苦いとか甘いとかどうでもよかった。
深夜だった。2時くらい。流石に頭がぼんやりしていた。
効かないなあ、とまたコーヒーを一口飲んで、差し込むような痛みが胃に走った。
お腹を抑える。冷や汗が出た。うずくまって、それでも足りなくて床に滑り落ちた。
「おかあさん」
小さくうめいた。涙が出た。このまま死んでしまうのかもしれないと思った。
「おかあさん」
出るだけの声を振り絞る。物音がした。誰かが走ってくる。
私は救急車で運ばれた。
「冷たいものの飲み過ぎだって」
ベッドで寝ている私に母さんが言った。ため息をついた。運ばれて、手術も何にもなかった。診察があって検査があっただけ。家に帰されて、わけがわかんないまま寝てしまった。もうお昼だった。
「あと、寝不足」
ぺたん、と私のおでこを叩いた。
「『心配しなくていい』って言ったでしょ」
「さっちゃーん。おすおす!」
ドアを開けて大きな声で誰かが部屋に入り込んできた。モッチーだった。
「あと、友達来てる」
母さんが言った。笑いをこらえていた。思わず起き上がった。
「モッチー、学校は?」
「熱出た。ことにした」
モッチーは当然のように言って、下げていた買い物袋を私の膝の上に置いた。
「お見舞い」
のぞくと、中にいつもの飴玉が大袋でいっぱい入っている。
「自分の好物か!」
呆れて大声が出た。
「そうだよ」
ふふふ。とモッチーが笑った。いらない、と言おうとすると、モッチーが私の頭をぐしゃぐしゃなでた。
「頑張ったねーえ?」
涙が落ちた。自分でもびっくりした。ぼたん。一粒落ちて、止まらなくなった。
「え? うそうそ? なになに?」
モッチーがおろおろする。「なんでもないよ」と言おうとしても声が出なかった。
「ありがと」
ぐちゃぐちゃになりながらやっと小さな声で言って、ビニール袋を捌いて、中の袋から飴を一個掴んだ。中も見ないで包み紙を開いて一粒口に放り込んだ。
「甘い」
イチゴミルクの飴はすごく甘かった。舌の上で転がす。イチゴが舞った。甘い。本当に久しぶりに思った。甘ったるい。モッチーみたい。
ショートショート No.606
小牧幸助さんの「#シロクマ文芸部」に参加しています。
今週のお題は「『舞うイチゴ』から始めまる小説・詩歌を書く」です。
