
スピノザ『エチカ』試論
はじめに
本稿では,バルーフ・デ・スピノザ(Baruch de Spinoza, 1632–1677)の主著『エチカ』(Ethica, 1677)の読解を試みる.
『エチカ』というタイトルを畠中尚志(1899–1989)は「倫理学」と訳している.「倫理学」といえば一般的には道徳哲学(moral philosopy)が観念されるのではないだろうか.だが,はたしてスピノザの「エチカ」は「倫理学」で良いのだろうか.「倫理学」と訳したからといって,本書では道徳や規範についてほとんど書かれていないように見える.もしかするとスピノザはその透徹なまなざしで事象を捉え記述したことによって,「倫理学」の意味そのものを刷新してしまったのかもしれない.だとするならば,スピノザの「エチカ」はいかなる意味で「倫理学」なのだろうか.この点について江川隆男(1958–)は次のように述べている.
『エチカ』に結晶化されたスピノザの哲学は,アリストテレス以来の〈形而上学(メタ・フィジック)〉などではけっしてない.人は,スピノザの哲学に「形而上学」の思考を想定すべきではない.それは,むしろまったくの反–形而上学としての〈自然学(フィジック)〉ではないのか.そして,それは,同様に〈道徳学(モラル)〉などではけっしてない.というのも,それは,むしろ反–道徳主義としての〈倫理学(エチカ)〉だからである.こうした意味での〈自然学〉と〈倫理学〉との完全な融合が,まさに『エチカ』の思考の根本をなしている.言い換えると,スピノザは,哲学を形而上学と道徳主義から解放したのである.
伝統的形而上学としての哲学,道徳哲学としての倫理学,そのどちらの路線もスピノザは退けたものとして『エチカ』を提示したというのである.これはスピノザ『エチカ』の哲学史上の位置付けについての非常に魅力的な解釈である.少なくともスピノザの『エチカ』が,従来の意味での「倫理学」とは異なっていることがわかる.
幾何学的秩序による論証
スピノザが亡くなったのと同年に『ベネディクトゥス・デ・スピノザ遺稿集』(B. D. S. OPERA POSTHUMA, 1677)が出版された(「ベネディクトゥス Benedictus」はスピノザのラテン語名である).この『スピノザ遺稿集』に収められて『エチカ』は初めて公刊された.


エチカ
幾何学的秩序に従って論証され,
そして
五部に分たれ,
その内容以下の通り,
第一部 神について.
第二部 精神の本性および起源について.
第三部 感情の起源および本性について.
第四部 人間の隷属,あるいは感情の力について.
第五部 知性の能力,あるいは人間の自由について.
「幾何学的秩序に従って論証された」とあるが,この「幾何学的秩序」とは一体何であろうか.
すでに本文を読んだことのある読者ならご承知と思うが,「定義」から始まって「公理」そして「定理」とその「証明」へと進んでいく叙述様式のことをスピノザは「幾何学的秩序に従って論証された」とする.このような叙述様式は哲学書あるいは思想書においては非常にユニークであり,同じことだがこの点がスピノザをスピノザたらしめているといっても過言ではない.
スピノザ以前のユークリッド幾何学の哲学者への影響——ホッブズの場合
ちなみに,トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes, 1588–1678)は欧州を旅して,最新の科学に触れ,ユークリッド幾何学に影響を受けたおかげで,晩年あの三部作を書き残したと言われている.
ウィリアムの突然の死によってキャヴェンディッシュ家を一時離れることになったホッブズは,近隣の貴族クリフトン卿に請われてその子息の「グランド・ツアー」に同行し,一六二九年から三〇年にかけてフランスとスイスを廻る.「幾何学との恋に落ちた」というJ・オーブリーによる『名士列伝』の言葉であまりにも有名な,エウクレイデスの『原論』との出会いは,この二度目の大陸旅行のおり,ジュネーヴに滞在中のことであったと言われている.
さる紳士の邸宅の図書室で,開いて置かれてあったその書物にたまたま目を留めると,その個所は第一巻の定理四七,すなわち有名な「ピュタゴラスの定理」の証明であった.ホッブズは定理を読み,当初それが真理かどうかを人間が知ることは不可能であると思ったという.ところが,証明を読み,さらには先立つ諸定理から最初の諸原理(定義)にまで遡ってみたとき,彼はその真理性をついに確信せざるをえなかった.明確な定義から出発して,真理(定理)を演繹的に論証していく幾何学の方法は,ホッブズがそれまで慣れ親しんできた,多彩なレトリックを駆使して読み手(あるいは聴き手)を説得していく「人文主義」の手法とは,まったく異質なものであった.
もちろん幾何学やエウクレイデスやピュタゴラスの定理について,彼がこのときまで何も知らなかった,とは考えにくい.ただ,幾何学的方法の真の意義に初めて気づいた,ということは十分ありうるだろう.大学で学んだスコラ哲学にも,最初にイタリア訪問で出会った人文主義にもなかった,議論の余地のない確実な「学知」(scientia; science)を獲得する「方法」の実例が,そこには示されていたのである.
とはいえ,ホッブズもスピノザもユークリッド幾何学に影響を受けながらも,両者の叙述の仕方は大きく異なっている.
スピノザと幾何学的秩序
そもそもスピノザはユークリッド幾何学とどのようにして出会ったのだろうか.この点については残念ながら,スピノザのいわゆる「破門」以後の資料が乏しいとされ,伝記的資料を読んでいても判然としない.が,どうやらスピノザが幾何学的秩序に関心を持ち始めたのは『神・人間そして人間の幸福に関する短論文』(生前未刊行)を書いた頃のようである.
スピノザが『短論文』を印刷しなかった理由の一つは,おそらく,彼がその表現形式に不満であったという点にある.彼はこのころすでに,定義・公理・定理をもとに命題を証明する(そして証明された命題は定理に追加される)という幾何学的秩序に関心をもち始めていた.彼は四つの命題を幾何学的に証明し,それを『短論文』の付録とする.幾何学的秩序を実地に試してみたのである.これ以後スピノザは,『短論文』を内容的に練り上げるとともに,新たな中身を幾何学的秩序のもとで表現するという作業に着手する.彼は,まとまった原稿ができるたびに,それをアムステルダムの「スピノザ・サークル」に送り始める.まさしくこの原稿が,後年の『エティカ』の最初期の草稿にほかならない.
その後スピノザは「スピノザ・サークル」の友人たちの期待に応え,デカルト哲学を幾何学的に再構成した『デカルトの哲学原理』を1663年に出版している.
ではスピノザは何故,その叙述様式に幾何学的秩序を採用したのだろうか.やはりデカルト哲学の影響だったのだろうか.この点については正確なことは言えないが,少なくともスピノザがその叙述様式に幾何学的秩序を採用したことによって,本来の幾何学的秩序の形式とスピノザの『エチカ』における叙述様式との間に相違があることが明らかにされてきた.
たしかに,スピノザが幾何学的秩序を採った主要な理由は,『省察』付録「第二答弁」においてデカルトが言うように,それが説得法——「同意を奪取する」方法——として有効であるという点にあったのであろう.しかしながら,われわれが『エティカ』を読解するためには,「実体」「属性」「様態」「神」といった基本用語をスピノザが線形的かつ構文論的にいかに並べ替えて諸命題を紡ぎ出しているかを考察しても実際問題として不毛なのである.そのような数学的潔癖さを求めるなら,われわれは数学者・論理学者としてのライプニッツが『エティカ』について再三記したのと同じ批判を繰り返さねばならないであろう.「『エティカ』において彼〔スピノザ〕は、かならずしもつねに,みずからの諸命題を十分に説明しているわけではない.私はこの点に判然と気づいている.論証の厳密さから逸脱したために,彼はときとして誤謬推理を犯しているのである」.また「たしかにスピノザは論証についてたいして熟達しているわけではない」.
松田克進(1963–)によれば,「公理体系で書かれているかぎりは,後続する諸命題が先行する諸命題から積み上げ式に,かつ,構文論的(形式論理的)に導出されねばならない」(松田2007:414)が,「『エティカ』における実際の「論証」はそのような線形的かつ構文論的な秩序では書かれていない」(松田2007:414)という.したがって,スピノザは,『エチカ』の外観とは異なって,幾何学的秩序にはそれほど厳密には習熟していなかったものとみなされている.工藤喜作(1930–2010)は,幾何学的秩序についてのスピノザとユークリッドの相違点について次のように述べている.
エチカに於いて示された幾何学的方法とは,論証の綜合的な方法であって,ユークリッドをそのモデルにしたものであった.しかしそれはすでに指摘した如く外面的なものに止まり,その内面にいたらなかった.彼はユークリッドからその哲学を説明するため多くの例を借用したとは云え,その方法の基礎たる定義に於いて,またその根源の認識たる直観知に於いてユークリッドとは異なるものがあった.彼に於いて精神に真に関係する幾何学的秩序は,imaginatioを援用してでなく,精神それ自身から生ずる純粋な知的な秩序である.斯かるものは最早ユークリッドには見当らない.直観知や定義に於けるデカルトの影響を考慮するならば,デカルトがその「方法序説」第二部に於いて示した方法の四つの規則,或いはレグラエに於いて詳細に論じた広義の幾何学的方法が,スピノザの幾何学的な方法でもあったことは疑い得ないところである.
スピノザの幾何学的方法による論証が実際にどのようなものであるのかについては,これから本文とともに次第に検討していきたいと思う.
幾何学の発展——ユークリッド幾何学から非ユークリッド幾何学へ
そもそも「幾何学」とは何だろうか.これはもともと古代ギリシャ語の"γεωμετρία",すなわち「土地 γη, geo-」を「測量すること μετρεω, metron」の謂である.
ユークリッド幾何学と呼ばれるものは,アレクサンドリアのエウクレイデス(Εὐκλείδης)の編纂したいわゆる『原論 Στοιχεῖα』に収められている.点や線,直線などの「定義」から出発し,「公準(要請)」,「公理(共通概念)」へと進む.
このユークリッド幾何学はすでに数多くの批判にさらされてきた.平行線公準が成立しないことから非ユークリッド幾何学が生まれた.ユークリッド幾何学はいわば「平面上の幾何学」だが,非ユークリッド幾何学はいわば「曲面上の幾何学」である.いまスピノザの『エチカ』を読むということは,こうした幾何学の発展も無視できないものと考える.はたして,スピノザのいう「幾何学的秩序」とは,いかなる意味で「幾何学的」だというのだろうか.というのも,ユークリッド幾何学の先に非ユークリッド幾何学が成立したように,ユークリッド=平面「幾何学的秩序に従って論証された」スピノザの『エチカ』の先には,もしかすると非ユークリッド=曲面「幾何学的秩序に従って論証された」非スピノザ的エチカもまた成立するかもしれないからである.
定義
まずは第一部「神について」の「諸定義 DEFINITIONES」からみていこう.


定義
一 自己原因によって私が知解するのは,その本質が存在を含むもの,すなわち,その本性が存在するとしか考えられえないもの,である.
二 同じ本性の他のものによって限定されうるものは自己の類において有限である,と言われる.例えば,或る物体は,我々が常により大なる他の物体を考えるがゆえに,有限である,と言われる.同様に,或る思想は他の思想によって限定される.これに対して,物体が思想によって限定されたり思想が物体によって限定されたりすることはない.
三 実体によって私が知解するのは,それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの,言いかえればその概念を形成するのに他のものの概念を必要としないもの,である.
四 属性によって私が知解するのは,知性が実体についてその本質を構成していると知覚するもの,である.
五 様態によって私が知解するのは,実体の変状,すなわち他のもののうちに在りかつ他のものによって考えられるもの,である.
六 〈神〉によって私が知解するのは,絶対に無限なる実有,換言すれば,おのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体,である.
(…中略…)
七 自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって行動に規定されるものは自由である,と言われる.これに対して,ある一定の様式において存在し・作用するように他から規定されるものは,必然的である,あるいはむしろ強制される,と言われる.
八 永遠性によって私が知解するのは,存在が永遠なるものの定義のみから必然的に出てくると考えられる限りで,存在それ自身,である.
第一部には八個の「定義」が登場する.他の各部門を見ても「定義」は八個以上は出て来ない.スピノザは「定義」の数を必要最小限にするべく,何度も何度も思考を研ぎ澄ましたはずである.
「定義」における「幾何学的秩序」
定義一から定義五までは,基礎概念について述べられている.これによって,はじめて定義六で「神」の概念が示されている.
定義が登場する順番,その「幾何学的秩序」はいかにして考慮されているのだろうか.もし定義が逆の順序で展開されていたら,一体どうなっていたであろうか.
定義
八 永遠性(aeternitatem←定義六)とは,存在(existentiam→定義一)が永遠なるものの定義のみから必然的に(necessario→定義七)出てくると考えられる限り,存在そのもののことと解する.
七 自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって(a se sola→定義三)行動に決定されるものは自由であると言われる.これに反してある一定の様式において存在し・作用するように他から(ab alio→定義二)決定されるものは必然的(Necessaria←定義八)である,あるいはむしろ強制されると言われる.
六 神とは,絶対に無限なる(infinitum←→定義二)実有,言いかえればおのおのが永遠(aeternam→定義八)・無限の本質を表現する無限に多くの属性(attributis→定義四)から成っている実体(substantiam→定義三),と解する.
五 様態とは,実体の変状,すなわち他のもののうちに在りかつ他のものによって考えられるもの(→定義二),と解する.
四 属性(attributum←定義六)とは,知性が実体(→定義三)についてその本質を構成していると知覚するもの,と解する.
三 実体(substantiam←定義六)とは,それ自身のうちに在りかつそれ自身によって(per se←定義七)考えられるもの,言いかえればその概念を形成するのに他のものの概念を必要としないもの,と解する.
二 同じ本性の他のものによって(alia←定義七)限定されうるものは自己の類において有限(finita←→定義六)であると言われる.例えばある物体は,我々が常により大なる他の物体を考えるがゆえに,有限であると言われる.同様にある思想は他の思想によって限定される.これに反して物体が思想によって限定されたり思想が物体によって限定されたりすることはない.
一 自己原因とは,その本質が存在(existentiam←定義八)を含むもの,あるいはその本性が存在するとしか考えられえないもの,と解する.
これらの定義は「神 Deus」について語るためのものである.「神」の「無限性 infinitum」は,定義二で述べられた「有限性 finitum」の裏返しとして暗示されている.「神」の「永遠性 aeternitas」は「存在 existentia」と同義であることから,「自己原因」によって「神」を説明しようとしていることが読み取れる.
とはいえスピノザはすべての語彙を定義しているわけではない.「本質 essentia」「本性 natura」「存在 existentia」「知性 intellectus」などの概念は,ここでは自明なものとして用いられている.しかし我々にとって『エチカ』を理解する際の躓きの石となりうるのは,こうしてスピノザによって自明なものとして用いられている概念によってではないだろうか.
知解可能なものとしての「神」
スピノザがこのように「神」を思考された実体として知解可能なものとして言い表したことによって,通常観念されてきた「神」とどれほど異なる概念が示されたことになるのだろうか.スピノザが宗教的に不遜たる所以は,従来観念されてきた人間にとっては知解不可能であるはずの「神」を,人間にとって知解可能なものとして記述してしまったところにあるのではなかろうか.
定義一:抹消された主体,「私」という主語
定義の中でも真っ先に掲げられているのが「自己原因」である*1.

一 自己原因とは,その本質が存在を含むもの,あるいはその本性が存在するとしか考えられえないもの,と解する.
この畠中訳の「自己原因とは,〜〜と解する」という訳文だけを見せられて「この文の主語は何か?」と問われて答えられる人は,はたしてどれだけいるだろうか.
"intelligo"という動詞は一人称単数である.したがって,「自己原因〔という言葉〕によって私が理解する intelligo のは,以下のことがら id である」というように翻訳できる.
確かにラテン語の原文には英語の"I"やドイツ語の"Ich"のような「私」という単語が表記されていないのだが,ラテン語では主語は動詞の人称変化によって明確に表記されているのであって,主語の不在を示しているのではない.しかしながら,日本語に翻訳されるやいなや「解する」という動詞だけでは主語の人称変化を表現できない.つまりここで主体=主語の欠落が生じてしまうことになる.「自己原因」をかように理解する主体=主語である「私」は,もちろん著者であるスピノザに他ならない.畠中訳がこれを省略したことによって,「私」という主体=主語が,スピノザ『エチカ』を読解する上で無視され,骨抜きにされてきたということはないだろうか.
他の邦訳ではどのように訳されているかと気になって,さしあたり工藤・斉藤訳(中公クラシックス)をチェックしてみたところ,訳文は次のようになっていた.
一 自己原因とは,その本質が存在をふくむもの,いいかえれば,その本性が存在するとしか考えられないもののことである.
ここでは主語は「自己原因」であり,もはやそれを理解する「私」の主語どころではない.「理解する intelligo」ということさえもが,どこかに消えてしまった.これは一体どういうことであろうか.
上野修(1951–)の論考においては,「私」という主語はその存在自体が抹消されている.
だれもが知るように,『エチカ』の言説の際立った特徴はその非人称性にある.じっさい論証という形をとる『エチカ』の言説は諸々の定義,公理,先行する諸定理から自らを導き出していくわけで,まるでひとりでに展開するように見える.「論証がそれ自身に語りかけているのだ」とさえ人は言いたくなるだろう.だが正確にいって,論証の中でいったい誰が語っているのだろうか.こう言ってよければ,論証しつつある論証主体とは何者なのか.著者スピノザ?いやそうは言えない.われわれはユークリッド幾何学の論証を辿るさい,ユークリッドその人の再生された声を聞き取っているわけではあるまい.それと同様,われわれはスピノザの声を聞き取っているわけではない.たしかにそれはスピノザという名の人物によって書かれたテクストかもしれないが,著者自身がそう望んだように,論証の真理は著者のいかなる伝記的要素にも左右されてはならないのである.それゆえ,『エチカ』の中で語っている論証の主体は誰でもありはしない.いやむしろ,それは何か人称的実質を欠いた,名もなき主体のようなものなのだ.これが『エチカ』の根源的な非人称性である.
(…中略…)
ひるがえって『エチカ』を見れば,その幾何学的秩序に欠けているのは,まさにこの一人称の「語る〈わたし〉」にほかならない.このことは,著者スピノザがもっぱら間欠的に,論証の糸の外部に位置する備考という形でしか一人称で介入しないという事実からも明白である.『エチカ』の言説は「わたし」といって語るどころか,いったい誰がその主体であるのか言明されないまま諸定理が述べられてゆく.
ここまで上野が長々と一人称の主体の欠如を語っているのを見ると,上野がラテン語原文でスピノザ『エチカ』を読解していないのではないかという疑いを禁じ得ない.上野が云々する『エチカ』の非人称性は事実ではなく,繰り返すが冒頭1行目の定義一からすでに一人称の「私」が登場するのである.
こうしてみると,翻訳書で『エチカ』を理解するのは心許ない気がしてくる.二次文献ではあるが,最近出版されたもので最もユニークによく練られた訳文は, 秋保亘(1985–)による以下の訳文である.
「自己原因ということによって私は,その本質が実在を含むもの(id cujus essentia involvit existentiam),あるいはその本性が実在すると〔して概念する〕以外には概念されえないもの(id cujus natura non potest concipi, nisi existens)と知解する」[E1Def1]
ここで秋保は主語である「私」を訳出するとともに,"intelligo"が「知性」と関わる動詞であることを示すべく「知解する」と訳し,"concipi"も「概念」と関わる動詞として訳出している.こうした点はラテン語原文で読む読者の間ではすでに周知のことがらであったが,出版物においてはどういうわけかなかなかお目にかかれない訳出なのである.
もっとも「私」という主体=主語の復権を云々したからといって,『エチカ』の読解が大きく変わるのかどうか,私にはまだ分からない.しかし,語り手としての一人称単数の「私」の視点(つまりヘーゲルの"für uns"ような一人称複数の「我々」の視点ではない!)を明確にすることは,『エチカ』読解のためのひとつの試みとしては面白いのではなかろうか.
「自己原因」の解釈と「神の存在証明」
その「自己原因」を,いわば我々つまり読者が理解するためには,「あるいは sive」で並置された二つの事柄でもって総合的に理解しなければならないであろう.「その本質が存在を含むもの」と「その本性が存在するとしか考えられえないもの」の両方に共通するのは「存在」である.
あらゆる存在者に先行してアプリオリに絶対的に存在するもの,他のものを自己の存在理由としないもののことを,スピノザは「自己原因」と呼んでいるのではないだろうか.
いわゆる「神の存在証明」として有名であるが,こうした考え方はアリストテレスの「第一原因」に似ている.アリストテレスは「第一原因こそが神だ」と述べた.しかし,スピノザは「自己原因が神だ」とは述べていない.スピノザがそういう直截的な言い方をしていないのは何故であろうか.
定義二:「類」と有限性・限定性
定義二では「類」の概念が述べられる.
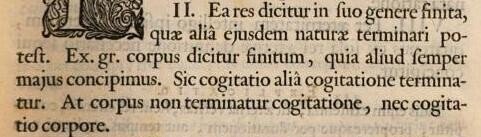
二 同じ本性の他のものによって限定されうるものは,自己の類において有限であると言われる.例えばある物体は,我々が常により大なる他の物体を考えるがゆえに,有限であると言われる.同様にある思想は他の思想によって限定される.これに対して,物体が思想によって限定されたり,思想が物体によって限定されたりすることはない.
「自己の類」とはおそらく「同じ本性」(この場合、同じ範疇(カテゴリー)のものと呼んでも良いかもしれない)を持つ同士の群(グループ)のことであろう.
「物体」と「思想」とは「同じ本性」を有していない.つまり両者は同じ範疇(カテゴリー)のものではない.だから,「物体が思想によって限定されたり思想が物体によって限定されたりする」というのは,いわばカテゴリーミステイクをおかしているから成立しないことになる.
英語で言うところの"compare apples to oranges"や"apples to apples"等の慣用句も似たようなことを表現していると言えるかもしれない.もしかすると比較とは本来的に「有限化作用」の謂なのだろうか.
定義三:自己充足せる「実体」
定義三では,「実体」の概念について述べられている.

三 実体とは,それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの,すなわちその概念を形成するのに他のものの概念を必要としないもの,と私は解する.
スピノザによれば「実体」とは,いかなる他者をも自分自身の構成要素として必要としない概念のことである.本来性,固有性とでもいうべきものだろうか.
定義四:「属性」と構成物

四 属性によって私が知解するのは,知性が実体について実体の本質を成していると知覚するものである.
「属性」をこのように「知解する intelligo 」のは,一人称単数の「私」である.一方で,「実体についてその本質を構成していると知覚する percipit」のは,「知性 intellectus」であるとされる.この「知性 intellectus」は,一体どういう位置付けなのだろうか.これは,「知解する」私の内なる「知性」なのか,それとも「知解する」私の外部に位置する第三者的な存在なのだろうか.
定義三より,「実体」とは自己内存在であって,他者の存在を必要としない概念である.「実体」の「本質を構成している」ものは,やはり「実体」にほかならない.というのも,「実体」の本質が何か別のものによって構成されるなら,それはもはや「実体」ではないからである.とすれば,結局「属性」とは「実体」にほかならない.
スピノザは「実体」の構成要素を「属性」と呼びたいようだが,これは表現するのがなかなか難しい概念だ.「属性」は「実体」の外部から,つまり「知性」の側からみなされたあり方だと言える.
定義五:「様態」と他なるあり方
定義五では「様態」について述べられる.

五 様態とは,実体の変状,すなわち他のもののうちに在りかつ他のものによって考えられるもの,と私は解する.
要するに「様態」とは「実体」が他なるあり方へと変化したものの謂いであり,これを「実体の変状」とスピノザは呼んでいる.このような発想は,流出する一者の概念にありそうであるし,また後のいわゆるドイツ古典哲学にも影響を及ぼしているような気がする.
定義六:神と無限性
定義六では「神」について述べられている.


六 神とは,絶対に無限なる実有,言いかえればおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体,と私は解する.
説明 私は,絶対的に無限な,と言うのであって,自己の類において無限な,と言うのではない.なぜなら,単に自己の類においてのみ無限なものについては,我々は無限に多くの属性を否定することができるが,これに反して,絶対的に無限なものの本質には,本質を表現し・なんの否定も含まないあらゆるものが属するからである.
スピノザの「神」を理解する鍵は,「無限(性)」の把握にかかっている.
「自己の類において無限な」あり方と「絶対に無限な」あり方の違いはなんであろうか.「自己の類」については定義二で述べられていた.「同じ本性の他のものによって限定されうるものは自己の類において有限であると言われる」(定義二).「絶対に無限な」あり方は「自己の類」を超越している.
「永遠」と「無限」が並べられている点については後で触れることにする.
定義七:自律と他律
定義七は,いわゆる「自律」について述べたものと解釈できる.

七 自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって行動に規定されるものは,自由であると言われる.これに対して,ある一定の様式において存在し・作用するように他から規定されるものは〈必然的〉である,あるいはむしろ強制されると言われる.
ここでは「自由 libera」と「必然的 Necessiaria」という二つのあり方が示されている.すなわち自分で自分を規定する自律的なあり方が「自由」なあり方と呼ばれ,他者によって自分が規定される他律的なあり方が「必然的」なあり方と呼ばれている.
自由と必然性をステレオタイプな対立概念と見なす場合,「自由」なあり方が「自己の本性の必然性」と一致していることに疑問を抱くかもしれない.しかしそういう通俗的観念は,すでにホッブズにおいて退けられているのでここで繰り返す必要はないであろう.
定義八:永遠=存在
定義八でスピノザは「永遠(性)」という時間的概念を「存在」という非時間的概念に還元している.

八 永遠性とは,存在が永遠なるものの定義のみから必然的に出てくると考えられる限り,存在そのもののことと私は解する.
説明 なぜなら,このような存在は,ものの本質と同様に永遠の真理と考えられ,そしてそのゆえに持続や時間によっては説明されえないからである,たとえその持続を始めも終わりもないものと考えようとも.
スピノザ自身も,「永遠(性)」という概念が通常,時間的概念であることは認識している.しかし,「永遠」とはあるものがずっと在るということ(始点と終点があろうとなかろうと)であり,それはもはや「存在そのもの」のことであろう,というのである.
これは『なるほど一本取られた』という感じだが,「永遠(性)」とは——通常は時間的な意味においてだが——「無限(性)」のことであろう.実際,スピノザは定義六において「永遠」と「無限」を並べている——「神とは,絶対に無限なる実有,言いかえればおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体,と解する」(定義六),と.
公理
続いてスピノザは「公理 AXIOMA」について述べている.
「公理」とは何であろうか.「公理」は先の「定義」と何が違うのであろうか.「定義」は八つから成り立っていたが,「公理」は七つから成り立っている.
公理一:存在様式の区別
公理一では,存在様式の区別について述べられている.

一 すべて在るものは,それ自身のうちに在るか,或いは他のもののうちに在るか,である.
存在様式の区別は二つだけである.すなわち,それが「自己」つまり内部にあるか,「他者」すなわち外部にあるか.
「すべて在るもの」とは「神」のことである.それが「自己」(内部)にあろうが「他者」(外部)にあろうが,「神」の存在様式の違いにすぎない.「他者」にある場合には「実体の変状」と解される(定義五).
公理二:概念規定
公理二は概念規定について述べられている.

二 他のものによって考えられえないものは,それ自身によって考えられなければならない.
この公理二は,「実体」についての定義三を裏返したようなものである.「他のものによって考えられえないもの」とは「神」のことである.
公理三:因果
公理三では,「原因と結果」つまり因果について述べられている.

三 与えられた特定の原因から必然的に結果が生ずる.これに対して,何らの特定の原因が与えられなければ,結果の生ずることは不可能である.
ここでは「原因」と「結果」についてごく普通の原理原則が述べられているだけのように見える.が,このことを前提としなければスピノザが『エチカ』を書くことなど不可能であっただろう.というのも「原因」と「結果」の論理必然的な帰結によって,『エチカ』の幾何学的秩序による論証は成立しているからである.
公理四:因果と認識
前の公理三と同じく因果に関わるものだが,公理四では因果における「認識」の働きの側面が取り上げられている.

四 結果の認識は,原因の認識に依存しかつこれを含む.
公理三で見たように,原因に基づいて結果が生じるのであるから,結果を認識するためには,その原因を認識することが必要である.
公理五:共通の認識と概念
公理五では,共通の認識と概念について述べられている.

五 相互に共通点を持たないものはまた相互に他から認識されることができない.あるいは一方の概念は他方の概念を含まない.
たがいに共通点を持つということは,同じ類に属するものと考えられる.これに対して「たがいに共通点を持たない」場合,両者はたがいに異なる類に属するものと考えられる.異なる類に属するものどうしはたがいに共通点を持っていないので,たがいを認識するための指標を自分の中に持っていないので認識できないし,概念できない.

この公理を逆に言うと,互いに共通点を持っている場合には,互いに認識可能であり,一方の概念が他方の概念を含むことになろう.このことを図に表すと以下のようになる.

ところで「たがいに共通点を持たないもの」が,たがいに共通点を持つようになることはできるだろうか.そうすれば両者は相互に認識可能となるはずだが.そのためには,上の図のように両者が重なり合うところまで,つまり共通点をもつところまで近づく必要があろう.
とはいえ,ここで一つの疑問が湧く.普通に考えると,認識能力とは感覚器官の有無に左右されるはずである.仮に相互に共通点を持つものがあったとして,それらが一切の感覚器官を持たないとする場合,それらは互いに認識しあうことができるのだろうか.
公理六:真の観念
公理六では「真の観念」について述べられている.

六 真の観念はその対象〔観念されたもの〕と一致しなければならない.
この一文で悩ましいのは,"objectum"の訳語に当てられることの多い「対象」という語で"ideato"を表現している点である.
『知性改善論』第33節にも「真の観念 idea vera 」について言及した箇所がある.

(三三)真の観念〔Idea vera〕(実際我々は真の観念を有するから)はその対象〔suo ideato〕と異なる或るものである.なぜなら円と円の観念とは別のものであるから.というのは,円の観念は円のように円周と中心を有する或るものではないからである.同様にまた,身体の観念〔idea corporis〕は身体そのもの〔ipsum corpus〕ではない.そして観念がその対象〔suo ideato〕と異なった或るものであるからには,それ自体,理解され得る或るものであろう.換言すれば,観念はその形相的本質〔essentia formalis〕という方面から見れば,他の想念的本質〔essentia objectiva〕の対象〔objectum〕たり得るのである.そして更にこの別な想念的本質はまた,それ自体で見れば,実在的な且つ理解され得る或るものであろう.このようにして無限に進む.
この訳文の中で「対象」と訳されているのは"ideato"と"objectum"の二つであることがわかる.スピノザは先ず「真の観念はそれが観念されたもの ideato とは異なるもの」だと述べている.そこで例として挙げられているのが,〈円の観念〉と〈円〉との関係、および〈身体の観念〉と〈身体〉との関係である.〈円〉は「円周と中心を持つ」具体的な存在であるが,これに対して〈円の観念〉はそのような具体性を持たない抽象物であるとされている.この場合,具体的に「円と中心を持つ」〈円〉は,〈円の観念〉の「観念されたもの ideato」であると考えられる.では〈円の観念〉とは何であろうか.それは今まさにこの議論をしている最中に円を具体的に描かずに我々が観念しているところのものである.「観念がそれの観念されたもの suo ideato と異なった或るものであるからには,それ自体、理解され得る或るものであろう」.わざわざ図に表現しなくとも,「我々は」(円の)「真の観念を持っている」からこそ議論が可能なのである.
ここで振り返って,スピノザが公理六「真の観念はその対象〔観念されたもの〕と一致しなければならぬ」と述べるのはどういう意味であろうか.例えば,円の真の観念は三角形や四角形と一致しないが,円とは一致する.逆に,円の真の観念が三角形や四角形と一致してしまっては困るし,そうであってはならない.なぜなら観念と異なる対象との一致は,概念の混乱状態を生じさせるからである.
(だが,極小の三角形を無限に敷き詰めていくと円になるという議論もある.つまり無限に敷き詰められた三角形は円と一致する.この点についての考察は別の機会に譲りたい.)
公理七:〈非 - 存在〉概念
公理七は〈非 - 存在〉概念について述べられる.

七 存在しないと考えられうるものの本質は,存在を含まない.
「存在」とはスピノザ的に言えば「神」のことである.「存在しないと考えられうるもの」とは,「神」ではないもののことを指している.「神」ではないものの本質には,当然「存在」は含まれない.というのも,スピノザにおいて「存在」とは「神」にほかならないからである.
だが,そもそも「存在しないと考えられうるもの」は「考えられうる」のだろうか.あるいは,我々は「存在しないもの」について考えることができるのだろうか.「存在しないもの」について考えることができるのであれば,その場合「存在しないもの」,〈非 - 存在〉というものが存在することになりはしないのだろうか.同じようなことについてハイデガーは考えていなかっただろうか.
定理
以上の「定義」と「公理」を踏まえた上で,「定理 PROPOSITIO」が述べられる.第一部の「定理」は全部で三十六つ出てくる.
定理一:アプリオリな「実体」

定理一
実体は本性上,実体の変状に先立つ.
証明
定義三および五から明白である.
スピノザは,定理一の内容証明は定義三と定義五を参照すれば明らかだとと述べている.証明の文字数を最小限にとどめようとすればこういう書き方になる.念のため定義三と定義五を確認しておこう.
〔定義〕
三 実体とは,それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの,すなわちその概念を形成するのに他のものの概念を必要としないもの,と私は解する.
五 様態とは,実体の変状,すなわち他のもののうちに在りかつ他のものによって考えられるもの,と私は解する.
公理一に書いてあるように,存在様式には,それ自身のうちにあるあり方と他者のうちにあるあり方の二つがあるが,ちょうど前者が定義三にある「実体」のあり方に対応し,後者は「実体の変状」のあり方に対応する.「実体の変状」とはいわば「実体」の派生形態,あるいは変化形態である.だが,実体が他のもののうちにあること(つまり定義五「実体の変状」)は,勝義の「実体」の本性(定義三)には含まれていない.
反対に「実体は本性上その変状に先立つ」のではないと考えてみたらどうだろうか.つまり実体の変状が実体に先立つとした場合,実体は実体の変状(つまり「他のもの」のうちにあるあり方)によって成り立つことになってしまい,そうすると実体は「それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの」(定義三)という実体の本性と矛盾してしまうことになる.
よって「実体は本性上その変状に先立つ」と考えられることになる.
定理二:異なった属性を有する二つの実体
定理二では「異なった属性を有する二つの実体」について述べられている.

定理二
異なった属性を有する二つの実体は,相互に共通点を有しない.
証明
これもまた定義三から明白である.なぜなら,おのおのの実体はそれ自身のうちに存在しなければならず,かつそれ自身によって考えられなければならぬから,すなわち,或る実体の概念は他の実体の概念を含まないから,である.
スピノザは「定義三から明白」だとしているが,この定理を理解するには定義三だけでなく,「属性」について述べられた定義四や,「共通点」について述べられた公理五も必要だろう.
〔定義〕
三 実体とは,それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの,すなわち,その概念を形成するのに他のものの概念を必要としないもの,と私は解する.
四 属性とは,知性が実体についてその本質を構成していると知覚するもの,と私は解する.
〔公理〕
五 相互に共通点を持たないものはまた相互に他方から認識されることができない.すなわち一方の概念は他方の概念を含まない.
以上のことを踏まえて定理二を図式化すると次のように表せるだろう.

「異なった属性を有する二つの実体は相互に共通点を有しない」(定理二)場合に「たがいに共通点を持たないものはまたたがいに他から認識されることができない」(公理五)のであるから,「異なった属性を有する二つの実体」は「またたがいに他から認識されることができない」ことになる.
二つの実体を知覚する知性
しかし「異なる属性を有する二つの実体」の両者を認識しなければ定理二を述べることもできない.つまり何者かがメタ的な視点に立って「異なった属性を有する二つの実体」について述べているのである.定理二を述べることができるのは,知性の知覚のはたらきによるものである.

「知性」が二つの実体を区別することができるのは,二つの実体が異なる属性を有していることを知覚するからである.
定理三:「物」と「実体」
定理三では共通点と因果の関係について述べられている.
定理三
相互に共通点を有しない物は,その一が他の原因たることができない.
証明
もしそれらの物が相互に共通点を有しないなら,それはまた(公理五により)相互に他から認識されることができない,したがって(公理四により)その一が他の原因たることができない.Q.E.D.
ここで述べられている「相互に共通点を有しない物 res 」とは,一見すると定理二で述べられている「異なった属性を有する二つの実体」のことかと思うかもしれない.だが,これまで「実体」が「物」だとは一言も述べられていない.したがって,この「物」を「実体」と解釈してもよいのかどうか, 注意が必要である.
この証明で参照されている公理四と公理五を見てみよう.
〔公理〕
四 結果の認識は,原因の認識に依存し,かつこれを含む.
五 互いに共通点を持たないものは,また互いに他から認識されることができない.すなわち一方の概念は他方の概念を含まない.
公理では「物 res」はまだ登場していない.公理では「実体」にも「物」にも適応可能な,より抽象度の高い記述がなされていたのである.
Q.E.D.
Q.E.D.とは"Quod erat demonstrandum"の略である.これは訳注にも書いてあるように「これが証明されるべきことであった」という意味である.定理三の「証明」からQ.E.D.が付けられているのだが,以前の定理の証明にQ.E.D.が付いていなかったのは何故だろうか.以前の定理の証明にQ.E.D.をただ付け忘れていただけでないとすれば,そこには実質的な違いがあるはずである.
定理四:物を区別するもの
先に定理三を考察した際に「物」を「実体」と同一視してもよいかという問題提起をしたが,この定理四においてようやく「物」と「実体」とが結び付けられて論じられている.


定理四
異なる二つあるいは多数の物は実体の属性の相違によってか,さもなくば実体の変状の相違によってたがいに区別される.
証明
存在するすべてのものは,それ自身のうちに在るか,他のもののうちに在るかである(公理一により).すなわち(定義三および五により)知性の外には,実体およびその変状のほか何ものも存在しない.ゆえに知性の外には,実体,あるいは同じことだが(定義四により)実体の属性,および実体の変状のほかは,多くの物を相互に区別しうる何ものも存在しない.Q.E.D.
定理四で述べられていることは,二つ以上ある場合の「物」つまり複数の多様な「物」はいかにして本質的に区別されるのか,ということである.本質的に,というのは,「実体」に従って,ということである.なぜなら互いに異なる属性や異なる変状を有している二つの実体は本質的に区別されるからである(定理二による).
「物」が,それが内属しているところの実体の属性よって区別されるにせよ実体の変状によって区別されるにせよ,ここで重要なことは,「物」が区別される仕方は,「物」それ自体を観察することによってなされるのではない,という点である.「物」それ自体を観察して区別する仕方は近代科学の発想であるが,ここでは「物」よりも「実体」の方が先行している点で非常に観念論的である.
「物」が区別される仕方は,例えばそれが「実体A」に帰属する性質(実体Aの属性や変状)を有しているのであれば,それは「実体A」群に区別されるし,あるいはそれが「実体B」に帰属する性質を有しているのであれば,それは「実体B」群に区別されるというようにである.
知性の外部は存在するか
定理四の「証明」では「知性の外には extra intellectum」という新しい表現がみられる.「知性 intellectus 」は定義四において初めて登場した(ただし定義一から登場する「〔私が〕知解する intelligo」を除けばの話だが).
ここでスピノザは,定義に従って「実体」もその他なる在り方である「変状」も,それらを「知性」が知覚する限りにおいてしか存在しない,あるいは知性の外部には何も存在しない,と述べている.
しかし,このことは我々の思考を知性の外側へと,知性の外部へと向かわせる.知性の外部とは知性の限界を越えたところのことであるが,スピノザのいう通り知性の外部は存在しないということになねば,結局,存在というものは,知性の内部においてつくりあげられた構築物だということになりかねないのではないだろうか.
「物」と「実体」の関係
念のため,スピノザが定理四で言及している公理一および定義三・四・五を引いておく.
〔公理〕
一 すべて在るものはそれ自身のうちに在るか,それとも他のもののうちに在るかである.
〔定義〕
三 実体とは,それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの,すなわちその概念を形成するのに他のものの概念を必要としないもの,と私は解する.
四 属性とは,知性が実体についてその本質を構成していると知覚するもの,と私は解する.
五 様態とは,実体の変状,すなわち他のもののうちに在りかつ他のものによって考えられるもの,と私は解する.
スピノザが参照するこれらの公理や定義においてはいずれも,「物」と「実体」の関係が述べられていない.「物」と「実体」の関係が述べられていない以上,定理四の「証明」は,定理四の内容を十分に証明していない,あるいは論証が不十分である,と私は思う.
定理四を見る限り,スピノザは,「物 res」が存在する以上,そもそも存在するものはすべて「実体」であるから,「物」と「実体」は同一のものだと考えているように思われる.
定理五:自然と実体
『エチカ』第一部定理五では「自然」と「実体」との関係について述べられている.

定理五
諸事物の自然のうちには,同一の本性または同一の属性を有する二つの実体あるいはそれ以上多くの実体は存在し得ない.
証明
もし数多くの異なる実体が存在するならば,(前定理により)それら異なった実体は属性の相違によってか,さもなくば変状の相違によって区別されなければならないであろう.もしそれらの実体がただ単に属性の相違によってのみ区別されるならば,そのことからしてすでに同一の属性を有する実体は一つしか存在しないことが容認される.一方で,もし変状の相違によって区別されるなら,(定理一により)実体は本性上その変状に先立つのだから,変状を考慮せずに実体をそれ自体として考察するならば,すなわち(定義三及び六により)実体を真に考察するならば,それは他のものと異なるものとは考えられない.すなわち(前定理により)同一の属性を有する実体がより多く存在することはできず,たった一つだけ存在できるのである.Q.E.D.
上の"In rerum natura"という箇所が,畠中訳では「自然のうちには」と訳出されている."rerum"は第五格変化名詞 rēs, reī f. (こと,物)の複数・属格であり,文字通りには「物どもの…」という意味である.したがって,"In rerum natura" は「諸事物〔万物〕の自然のうちには」と訳すことができる.畠中は "rerum natura" をただ単に「自然」と訳出しても同義だと判断したのだろう.
「諸事物〔万物〕の自然」は,ニュアンスとしては「森羅万象」(この世のあらゆる物事)のようなイメージに近いかもしれない.この「森羅万象」のイメージを, 後の部門で登場する有名な「神即自然」と掛け合わせると,それはもはや〈神゠羅万象(しんらばんしょう)〉だと言えるかもしれない.
以前の定理では複数の実体が存在する場合について考察を進めてきたが,ここでは神羅万象に内在する「実体」は一つのみであり,すべて「同一本性」「同一属性」を有していることが述べられている.もし他の実体が存在するとすれば, 「事物の自然」の外側にあると考えられる.だが「事物の自然」の外側を思考することは可能であろうか.
「定義三および公理六」?
『エチカ』第一部定理五の「証明」の"per Defin. 3. & 6."(定義三および六により)という箇所が,各邦訳では「定義三および公理六により」と訳出されている(畠中訳,工藤・斎藤訳).これは一体どういうことだろうか.
原因は,現在流通しているラテン語版『エチカ』ではこの箇所が"per definitionem 3 et axioma 6"とされていることに起因する.しかしながら,1677年ラテン語版の原文には,「公理」に該当する文字が見当たらない.
筆者はいつからこの箇所に"axioma"が付加されたのかをGoogleブックスを利用して調べてみた.すると1891年の英訳『エチカ』にまでは「公理」の文字を確認できなかったが,1895年のオランダ語訳『エチカ』において初めて"axioma"が付加されていることがわかった.
オランダ語訳『エチカ』(1677年)
まず最初のオランダ語訳『エチカ』(オランダ語訳『遺稿集』,1677年)は,ラテン語版『エチカ』と同年に出版されている.この最初のオランダ語訳『エチカ』は,ラテン語版『エチカ』の最終稿以前の草稿を底本としているので,両者には数多くの相違があるとされる.しかしこの最初のオランダ語訳にもラテン語版と同様,第一部定理五の「証明」には「公理」の文字が見当たらなかった.

フランス語訳『エチカ』(1842年)
次にフランス語訳『エチカ』(Émile Saisset訳『スピノザ 著作集』第二巻,1842年)にもやはり「公理」の文字は見当たらなかった.

英語訳『エチカ』(1891年)
英語訳『エチカ』(Elwes訳,改訂版,1891年)にも「公理」の文字は確認できなかった.

オランダ語訳『エチカ』(1895年)
オランダ語訳『エチカ』(H. Gorter訳,1895年)においてようやく"ax."(公理)の文字が確認された.

畠中尚志は邦訳『エチカ』に付した自身の解説の中で,ラテン語版『遺稿集』とオランダ語訳『遺稿集』における『エチカ』の相違について次のように述べている.
オランダ語訳遺稿集における『エチカ』は,ラテン語遺稿集の『エチカ』すなわち原版『エチカ』とは独立して,スピノザ自身の原稿からーーしかも原盤『エチカ』よりやや古い別な原稿から訳されたものであると考証されるから,その利用は『エチカ』の本文批判(テキスト・クリティーク)に欠くべからざるものである.もっと詳しく言えば,スピノザの死の以前『エチカ』の一原稿から友人によってオランダ語に訳されつつあったものがオランダ語訳遺稿集の『エチカ』として現われ,そのオランダ語訳の基となったラテン語原稿にスピノザが生前自ら手を入れて決定的にしたものが遺稿集の『エチカ』すなわち原版『エチカ』として現われているのである.原版『エチカ』とオランダ語訳『エチカ』との相違個所は,ゲプハルトによれば,一五六個所以上に及ぶという.このうち原版『エチカ』のみにあってオランダ語訳『エチカ』にない個所は,スピノザが生前最後の原稿においてそう付加あるいは改作したのであってむろんそれが決定的形態とされるべきであり,オランダ語訳『エチカ』はその点何の権威も主張することができない.オランダ語訳『エチカ』の利用の意義は,原版『エチカ』との些少の相違——それは原稿の誤記や出版の際の誤植や編集者の粗漏から原版『エチカ』のほうが正しくない場合もありうる——を通してしばしば原版『エチカ』の不備な箇所を是正し,またかなり多くの疑わしい個所について決定的形態を確立するのに役立つことである.さらに従来不完全な形で伝わっていると考えられた個所,あるいは研究者たちによって単なる推定に基づき訂正の提案がなされている個所は,もしその個所が原版『エチカ』と同じようにオランダ語訳『エチカ』にもそうあったとしたら,少なくともスピノザ自身は二度原稿にそう書いたのだから,我々はそれを決定的形態として保持しなければならぬことになる.
1677年に出版されたラテン語版『エチカ』と同年に出版された最初のオランダ語訳『エチカ』の両方において,第一部定理五「証明」のうちに「公理」の文言はなかった.それゆえ「公理」の文字が付加された現在流通しているテクストは少なくとも1677年の最初の版に基づいて修正されるべきではないだろうか.
定理六:他者によって産出されざる実体

定理六
或る実体は他の実体から産出されることができない.
証明
諸事物の自然のうちには同一の属性を有する二つの実体は存在しえない(前定理により).すなわち,(定理二により)相互に共通点を有する二つの実体は存在しえない.したがって(定理三により)或る実体は他の実体の原因であることができない.あるいは或る実体は他の実体から産出されることができない.Q.E.D.
系
この帰結として,実体は他の物から産出されることができないことになる.なぜなら,公理一および定義三と五から明白なように,諸事物の自然のうちには,実体とその変状とのほか何ものも存在しない.ところが実体は実体から産出されることができない(前定理により).ゆえに実体は絶対に他のものから産出されることができない.Q.E.D.
別の証明
このことはまた反対の場合が不条理であるということからいっそう容易に証明される.すなわち,もし実体が他の物から産出されうるとしたら,実体の認識はその原因の認識に依存しなければならなくなり(公理四により),したがって(定義三により)それは実体ではなくなるからである.
ここではなぜ「或る実体は他の実体から産出されることができない」のかが論証されている.
上の「或る実体」と「他の実体」とは互いに同一本性・同一属性を有する実体であろうか.それとも異なる本性と異なる属性とを有する実体であろうか.それぞれの場合について考えてみよう.
まず,もし「或る実体」と「他の実体」とが同一本性・同一属性を有するものと解釈すると,そのような在り方はそもそも定理五によって同一本性・同一属性を有する複数の実体はあり得ないのだから,成立し得ないことになる.
次に,もし「或る実体」と「他の実体」とが異なる本性・異なる属性を有するものと解釈すると,定理二によりそのような諸実体は互いに共通点を有せず,そしてまた定理三により共通点を有しないもの同士では一方が他方の原因となることができないのであるから,こちらもまた成立しないことになる.
定理六の「系」においては,定理六の内容がより一般的な命題として立てられている.
定理六の「別の証明」では,いわば背理法(reductio ad absurdum)によって定理六が論証されている.つまり「ある実体は他の実体から産出されることができない」という命題を偽と仮定して「ある実体が他の実体から産出されることができる」という命題から出発し,それが実体の定義と矛盾することによって定理六の正しさを示している.
定理七:実体と存在
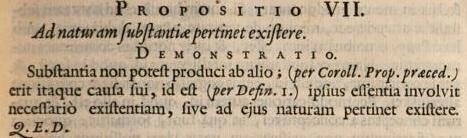
定理七
実体の本性には存在することが属する.
証明
実体は他のものから産出されることができない(前定理の系により).ゆえにそれは自己原因である.すなわち(定義一により)その本質は必然的に存在を含む.あるいはその本性には存在することが属する.Q.E.D.
定理七では,「実体」と「存在」との関係が初めて説明されている.
先に見た定理六の「系」において,「実体は他のものから産出されることができない」という命題が導出された.ここまでは前回の確認なので問題なかろう.
論証する上で問題なのは「実体は他のものによって産出されることができない」という命題を「自己原因」として理解できるかどうかである.
〔定義〕
一 自己原因とは,その存在が本質を含むもの,あるいはその本性が存在するとしか考えられえないもの,と私は解する.
定理六の「系」における「実体は他のものによって産出されることができない」という命題には,定義三における「実体」の定義が繰り返されているに過ぎないのではないだろうか.
〔定義〕
三 実体とは,それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの,すなわち,その概念を形成するのに他のものの概念を必要としないもの,と解する.
スピノザは,定理七の「証明」を,定理六の「系」から証明しようとしている.だが,実際には,定義三を定義一と同義のものとして説明すれば,定理七は証明できてしまうのではないだろうか.定理七の「証明」においてわざわざ定理六の「系」を迂回しなければならなかった論理必然性は一体どこにあるのだろうか.
定理八:実体の無限性

定理八
すべての実体は必然的に無限である.
証明
同一の属性を有する実体は一つしか存在せず(定理五により),そしてその実体の本性には存在することが属する(定理七により).ゆえに実体は本性上有限なものとして存在するか無限なものとして存在するかである.しかし有限なものとして存在することはできない.なぜなら,有限なものとして存在すればそれは同じ本性を有する他の実体によって限定されなければならず(定義二により),そしてこの実体もまた必然的に存在しなければならぬのであり(定理七により),したがって同一の属性を有する二つの実体が存在することになるが,これは不条理だからである(定理五により).ゆえに実体は無限なものとして存在する.Q.E.D.
定理八では「すべての実体は必然的に無限である」と述べられているが,これまでは「本性上」などと述べられてきたのに,ここで「必然的に」とは一体どういう違いがあるのだろうか.
結論から言えば,この「必然的に」とは,前の定理から論理必然的に帰結することを意味していると考えられる.
スピノザは,定理八の「証明」の最初で,定理五と定理七を引いている.これによって議論の後半で定理五の拘束力が強くなっている. スピノザによれば,実体の在り方には「有限」と「無限」の二つの在り方がある.スピノザによる定義では,「有限」とは他者による規定を受けている在り方を指す.証明の方法としては,実体の在り方が有限であるとは考えられないので,逆に実体は無限だという命題を引き出している.実体の「無限性」が「有限性」の否定を通じて示されている.
ここで一度スピノザによる「有限性」と「無限性」の定義を確認しておこう.まず「有限性」については定義二で次のように述べられている.
〔定義〕
二 同じ本性の他のものによって限定されうるものは,自己の類において有限であると言われる.例えばある物体は,我々が常により大なる他の物体を考えるがゆえに,有限であると言われる.同様にある思想は他の思想によって限定される.これに対して,物体が思想によって限定されたり,思想が物体によって限定されたりすることはない.
より大きなものを想像できる場合に,その在り方は「有限」であるといえる.
これに対してスピノザは「無限性」の在り方を〈絶対的に無限なもの〉と〈自己の類においてのみ無限なもの〉とに区別していた.
〔定義〕
六 神とは,絶対に無限なる実有,言いかえればおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体,と私は解する.説明 私は「自己の類において無限な」とは言わないで,「絶対に無限な」と言う.なぜなら,単に自己の類においてのみ無限なものについては,我々は無限に多くの属性を否定することができる(言いかえれば我々はそのものの本性に属さない無限に多くの属性を考えることができる)が,これに反して,絶対に無限なものの本質には,本質を表現し・なんの否定も含まないあらゆるものが属するからである.
定理八に関して言えば,「同一の属性を有する実体」が問題となる限りでは,そこでは〈自己の類においてのみ無限なもの〉だけが取り上げられているように思われる.
備考一:部分的否定と絶対的肯定
スピノザはここで次のような「備考」を加えている.

備考一
有限であるということは実はある本性の存在の部分的否定であり,無限であるということはその絶対的肯定であるから,この点から見れば,単に定理七だけからして,すべての実体は無限でなければならないことが出てくる.
「有限であるということは実はある本性の存在の部分的否定であり,無限であるということはその絶対的肯定である」とは一体どういうことであろうか.
定義二によれば「同じ本性の他のものによって限定されうるものは,自己の類において有限であると言われる」のであって,同一本性の他者によるこの限定作用こそ「部分的否定」に他ならない.
これに対して定義六によれば「絶対に無限なものの本質には,本質を表現し・なんの否定も含まないあらゆるものが属する」のであり,これこそは「絶対的肯定」である.
備考二:〈実体〉=〈神〉を自然物や人間の本性と類比的に捉えてはならない

備考二
事物について混乱した判断をくだし・事物をその第一原因から認識する習慣のないすべての人々にとって,定理七の証明を理解することは疑いもなく困難であろう.なぜなら彼らは実体の様態的変状と実体自身とを区別せず,また事物がいかにして生ずるかを知らないからである.
どうして定理八を理解するのが難しいのか.それは,定理八の命題が推論によって理解されうるような論理的帰結として示されているからである.換言すれば,その論理を追うことができるものだけが理解できるような命題だからである.

この結果として彼らは,自然の事物に始原があるのを見て,実体にも始原があると思うようになっているのである.いったいに,事物の真の原因を知らない者は,すべてのものを混同し,またなんら知性の反撥を受けることなしに平気で樹木が人間のように話すことを想像し,また人間が石や種子からできていたり,任意の形相が他の任意の形相に変化したりすることを表象するものである.
ここで退けられているのは,〈実体〉を〈自然の事物〉に擬えて理解しようとする類比的な捉え方である.〈自然の事物〉は種子から発生し成長していく.その際に『卵か先か鶏が先か』という問題は生じるが,このような〈自然の事物〉と同様の流れを通じて〈実体〉は生成するのではない.


同様にまた,神的本性を人間的本性と混同する者は,人間的感情を容易に神に附与する.特に感情がいかにして精神の中に生ずるかを知らない間はそうである.
「人間的感情」について詳しくは本書「第三部 感情の起源および本性について」に譲らざるを得ないが,要するに『人間との類比によって〈神〉を捉えてはならない』というのがスピノザの首尾一貫した主張である.
(つづく)
注
*1: スピノザの「自己原因」とデカルトのそれとの比較については,中野2003をみよ.
文献
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
