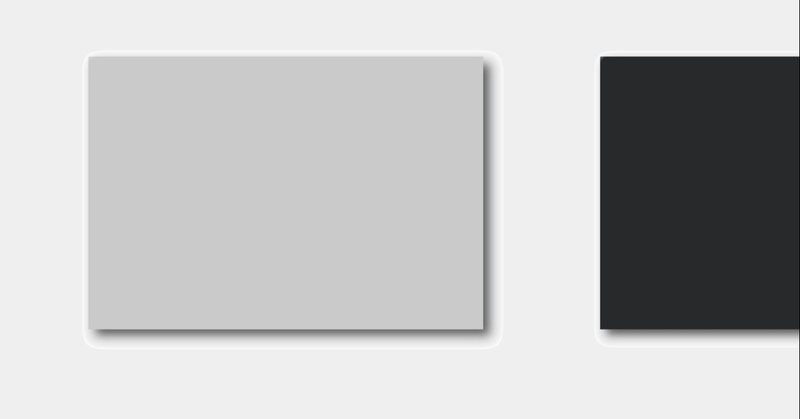
日本国憲法ー「概念」の二重錯誤
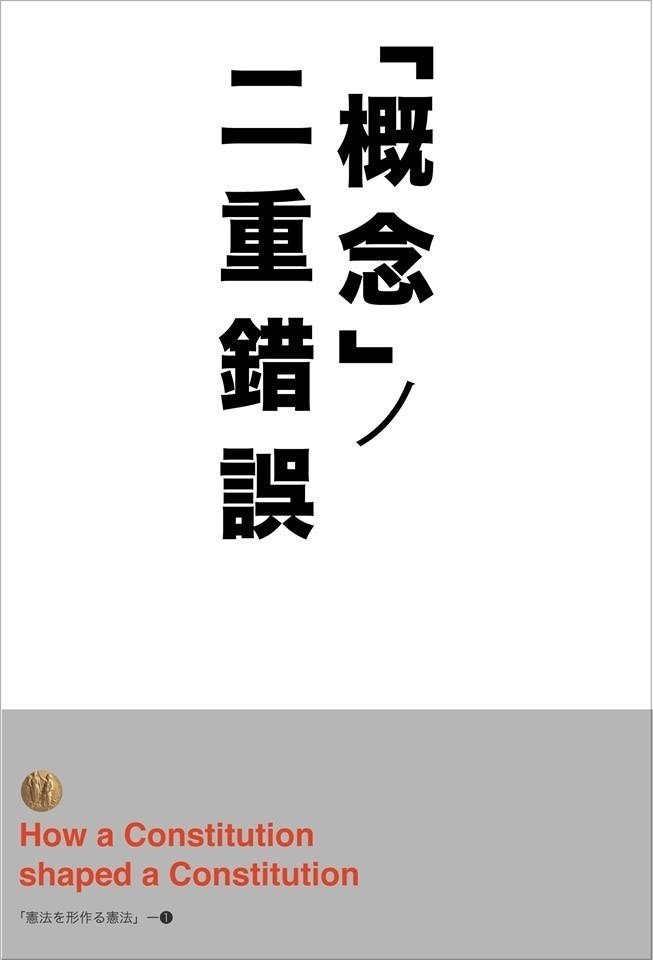
「概念」の二重錯誤
そもそも、現在の日本が抱えるパラドクスの原理は「憲法」自体に「矛盾」があるのではなく、「改憲」と「護憲」を「矛盾」だとする、私たちの頭の中の「論理の秩序」が間違っている。
日本の「憲法典」は「憲法」Constitution本来とは違った方法で使用する「転用=ずらし」と呼ばれる国民の主体性を回復しようとする試みであった。
日本では「憲法」とは、すなわち「憲法典」であると勘違いされている。
日本では「憲法」Constitutionとは「憲法典」という名の法典のことであるとの観念が根底にある。しかし、「憲法典」は「憲法」Constitutionにおいて、 重要ではあるが唯一の素材ではなく、もっとも重要な素材でもない。「憲法」Constitution と「憲法典」を混同して、そこに国家の基本に関するすべての規範が指示されているという理解は誤りである。「改憲派」、「護憲派」によるこの国の憲法論議は、専らこの「法典」をどうするかをめぐって争っている。そして、現在行われているのは、決して「議論」などではない、互いのヘイトによる「内戦」だ。仲間同士、隣同士戦っている。「護憲派」も「改憲派」も共にドン・キホーテに過ぎず、共に傷を受け、そして、共に受けた傷は癒えることはない。
また、多くの国民は多数決と民主主義を混同している。いたずらに多数決を尊重するのは単なる多数決主義(マジョリタリアニズム)であり、それは個人の意見を尊重しようとする民主主義とは、ひどく異なるものである。
このまま「憲法改正」が国民投票にかけられて、どちらの結果になるにしても実質的な「概念」が伴わず、「仏作って魂入れず」で何の意味も持たずこのまま永遠に争いが続くだけだ。民主主義の根幹において最も重要なのは、国民をシュミット的な敵味方に分断させぬよう、どうにか合意形成を探ることだが、現在の議論の有り様を見ているとどちらの結果になっても、将来に渡って大きな禍根を残すことになる。
現在、行われているのは「憲法」Constitution の論争ではなく、「憲法典」論争であり、「憲法学」論争である。
戦後憲法が「憲法を暮らしの中に」や「職場に憲法を」といったスローガンに象徴されるように、日常生活をめぐるあらゆる抑圧への抵抗の根拠として把握されることによって、国民に定着したという日本独特の憲法文化や日本人の憲法理解が実質的な存在として広く認知されている。
しかし、こうした文脈は「学者」や「議員」の限られた論理空間においては、とりわけ「憲法学」から見れば明らかな誤りとされている。だが、実際にはこの「憲法学」というのが〝くせもの〟なのである。西欧社会においてConstitutionとは国民と国家の間の社会契約として、国家機関の創設ないしその権限の制限を自ずと内包する言葉と捉えられており、わが国では、それによる「立憲主義」の「概念」を中心にした、憲法学者や議員たちの「護憲」、「改憲」双方のステレオタイプの衝突した議論が国民を大きく混乱させている。
そもそも、「公理」がないのに、文脈的な「命題」や「定理」を導き出すことなど出来ない。 「公理」は現実的である必要はないが、その「完結性」と「無矛盾性」が必要である。 ここをおさえないと、断片的で複雑な「定義」や「定理」が飛び交う、まるで「数学」や「哲学」のような議論から抜け出すことは出来ないのである。
「改憲派」は憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという「護憲派」の批判は意味不明だと言い、そして、「護憲派」はその批判が意味不明だと言い合っている。現在日本の抱えるパラドクスは「憲法」自体に「矛盾」があるからではなく、「改憲」と「護憲」を「矛盾」だとするわれわれの頭の中の「論理の秩序」が間違っているのである。
そもそも、「立憲主義」の護持と「集団的自衛権」の必要性はまったく異なる「位相」にある。つまり、「立憲主義を守れ」という主張と、「集団的自衛権は必要だ」という主張には因果関係はなく、いまだに正面からは対立していない。
「憲法」論争は本来の目的が置き去りにされ、「憲法学」論争となり、もはや「神学」論争のような様相を呈してきた。
この国の「議員」や「学者」たちにより展開される憲法論争は、「国家」および「国民」の平和と安全を目的とした具体的形象から離れた、「憲法」そのもの、「憲法」それ自体について問おうとしてしまっている。それはまさに「概念」の実体的使用の錯誤そのものであると言えるのである。
さまよい始めた、「立憲主義」
確かに、「立憲主義」の説明において「憲法は、国家権力の抑制を定め、国民の人権を守るものだ。」という主張自体は否定しないが、それは「憲法」Constitutionの重要な側面を規定した言い方であり、本来の「憲法」Constitutionを問われれば、「国家」の基本的なカタチについての立体的な「概念」の理解が必要である。
この「立憲主義」という言葉はいつごろから広まっていったのか。有斐閣の法律学全集の「憲法1 清宮四郎」1957年の初版第1刷にも、「立憲主義」という言葉は出ているが、現在のように広く使われ出したのは、2014年に安保法制が国会で審議されたころから、朝日新聞が「立憲主義」という聞き慣れない言葉を使い始めたことにより、当時野党が護憲派やリベラル勢力も自衛隊を認めたので「憲法9条を守れ」とはいいにくくなったため、今度は解釈改憲に反対して「立憲」か「非立憲」かという主張を展開したことにより急速に広まったと思える。
具体的には1972年の集団的自衛権に関する内閣法制局見解を安倍首相が変えるのは「解釈改憲」で「立憲主義」に反するものだというあたりから「立憲主義」が一人歩きし始めた。
しかし、一方でそもそも法制局長官は首相の部下であり、内閣が行政を支配するのが「立憲主義」であるなどと議論が混乱し始めたのである。
2015年の憲法審査会で、与党側の参考人が「安保法制は憲法違反だ」と言ったため、安保関連法案が国会の争点になり、「強行採決」などの騒ぎになった。前年の閣議決定は認めたのに関連法案が憲法違反だというのは辻褄が合わないが、当時の野党はこれで内閣が倒せると政局にしてしまったのである。
「憲法」Constitution の「概念」とは何か。
「憲法」Constitution の「概念」とは一体何だろうか。ある人は単に成文化された「法典」、「法規範」こそ「憲法」と呼び、ある人は国民と国家の間の社会契約として、国家機関の創設ないしその権限の制限こそといい、またある人は、アイデンティティや政治的統一体の構造や組織、つまり「国家」のあり方そのものこそといい、またある人は政治的な力関係や権力装置ではなく、それを信じる主体同士の関係の中で発生するものこそという。
そして、「人権」Human Rightsは、ある人は自己の「権利」こそ「人権」Human Rightsといい、ある人間は「人間愛」こそといい、またある人間は「通理」、「通義」こそ「人権」Human Rightsという。
もちろん、当然すべての「議論」において「概念」が一致しなければ共感できないということはない。「飲み屋」での議論においては各人様々な見解がある。人によって「人権」にもいろいろあることを知って、初めてそれまで自分が考えもしなかった「人権」についての様々な側面を見出せることがあるかも知れない。そして、ある人の言う「人権」には「なるほどそれもそうだな」と思えるかもしれないし、ある人の言う「人権」には「それはちょっと同意できないな」と思うかもしれない。こういった他者との会話の中で、「イデア」ではない「人権」の持つ様々な具体的側面を把握することができるのである。その中で共通項を見出したり、見出せなかったり、そういうことである。
しかし、それは一般国民レベルのたわいもない「議論」であって、全国民の代表である「議員」が同じようにいつまでも「飲み屋の議論」をやっている場合ではない。
憲法問題の本質は、日本人の「共感覚」(シナスタジア)を呼び起こすことが最も重要な命題なのであり、それは「まとまり」の形象にあると言えるのである。
確かに「自衛隊」という「概念」は、海外では通用しない。しかし、日本においての「共感覚」は、音は単なる音ではなく、また形は単なる形ではない。私たち日本人の「憲法」における「共感覚」はすでに生命におけるデフォルトであるというわけである。「共感覚」とは学習や訓練で得られるものではなく、ある刺激に対して通常の感覚だけでなく異なる種類の感覚をも生じさせる知覚現象をいう。
「知識」は「クオリア」には到達できない。真の平和への到達は「アルゴリズム」ではなく、「反知性」の問題なのである。
世の中には、科学や学問では説明できないことはいくらでも存在している。「議員」や「学者」が「不思議」を「謎」と誤解し、限られた論理空間でもっともらしい「解答」を導き出しても、こうした「謎解き」は所詮こじつけの「レトリック」に過ぎないのである。
憲法概念の獲得においては、知識・情報による理性的で実証主義的な思想への対抗策として情緒観念を受け継いだ反知性(プリミティブ)による観察が必要である。真の「知性」は「反知性」を否定しない。というより、否定することが出来ない。 それは「情緒」に正解などあり得ないからだ。「知性」が否定するのは、常に非論理的言説のみである。 「情緒」は、本来、個人の願望(願い)と記憶(思い出)を基本的な構成要素とする意識現象であり、この「情緒」を有する者は過去の記憶のなかに残る人や物、時間や空間を現在に取り戻したいとする願いを有し、その願いのなかで苦悩している。「戦後」という大きな世界観においても、先の大戦で家族を失い、家を失い、職を失った国民の喪失と悲哀は誰しもが想像に難くない。残された者は故人と向き合い、対話しながら、残された者たちが幸せに生きることを願いながら逝ったに違いない故人の意思として、さらには日本という国を再建してほしいという意思を受け止め、轍として未来に繋いでいく責任があるのである。
私たちが発想を変えなければならない。
立体的な「世界観」を持ち、「意識」で形象しなければ、この問題の解決には何万年の歳月が必要になる。私たちは網膜に映った「像」を見ているわけではない。視覚神経処理によって「世界」という『像』にしているのである。 主観世界を分析するには「内側」からの視点から周囲世界を観察しなくてはならないのである。
知的権威や理性偏重の実証主義、合理主義を標榜する「議員」や「学者」は、何かにつけて、すぐに「反知性」などと揶揄するが、「反知性」はそうした物事を大げさにしてチョコチョコ反応する無意識のカエルのような「議員」や「学者」などに対して懐疑的な立場をとる主義・思想であり、本来示すその意味は、データやエビデンスよりも肉体感覚やプリミティブな感情を基準に物事を判断することを指す言葉である。
その言葉のイメージより、健全な民主主義における必要な要素としての一面があり、むしろ、行き過ぎた合理主義を考えるために「反知性」に立脚した視点も重要なのである。
知性派を気取る「議員」、「学者」にとっては世界は「白線」だけだ。「ライントレーサー」の関心は、自分が「白線」の中心を走っているか、どれだけずれているかしか関心がない。たった4つのセンサーでなく、1000万画素のCCDカメラを搭載していたとしても、「ライントレイサー」にとっての世界は「白線」だけとなる。
そもそも世界のグラウンドは二つに大きく分かれている。ひとつは「白線」のグラウンドであり、そして、もうひとつは「瓦礫」のグラウンドである。しかし、何世代の未来に向けての時間性においては、私たちの立っているグラウンドは決して「フラット」なものではなく、世界中どこでも「デコボコ」の瓦礫のグラウンドなのである。紛争やテロ、自然災害、環境破壊などにより「瓦礫」グラウンドは白線に覆われた、決して「フラット」なものではなく、「デコボコ」のグラウンドでは「ライントレーサー」はその機能を発揮することはできない。
「議論」と言えば多くの人は「知性」と受け取るかもしれないが決してそうではない。少なくとも倫理や信仰については決して「知性」だけではない。 もちろん言っていることの整合性や合理性は考えるべきだが「議論」の文脈の中を流れているのは決して「アルゴリズム」などであってはならないのである。
「アルゴリズム」は過去のデータや処理結果をふまえて「論理空間」を組み立て、そこで未来のデータ処理方法を決定するのであり、「過去」によって完全に規定されている。しかし、そうしたアルゴリズムの融通のきかなさは欠点ではなく、本質的な性質なのだ。ビッグデータ時代になって、膨大なデータを扱えるようになっても、むしろ「過去」のデータの比重が大きくなっただけで本質は変わらない。
「概念」を個別から切り離して論じるのをよしとするいわゆる哲学書、思想書のスタイルよりも、普遍が一人の人間の生の個別にどのように絡みついて顕れてくるのかを提示できることこそが、単に人間の生の実感に寄り添っているというだけではなく、思想そのものの本来の表現方法であると言える。
少しの豆学問で知性派を気取る「学者」や「議員」の知性や論理など、クラウド環境下においては「自己学習」で十分に事足りる。「豆知識」は次の「豆知識」を呼び起こすだけだ。「ジャックと豆の木」では、豆の木は雲の上を突き抜ける巨木だったが、私たちはこのまま「豆知識」の木を登っていっていいのだろうか。これからの未来の形象においては、データやエビデンスよりも肉体感覚やプリミティブな感情を基準に物事を判断することが何よりも重要になってくる。
「護憲」と「改憲」、「保守」と「リベラル」、「立憲主義」と「安保法制」は、マスコミが作り出した「想像の共同体」である。
一般的には「実定法」は解釈抜きで意味を理解できるものでなければ、「実定法」としての役割を果たし得ない。しかし、条文自体を権威として受け止め、文言通りに理解して従うべきでないという条文は憲法の中には決して少なくない。「憲法9条」はそうした条文である。これは「憲法9条」だけが何か特別に問題があるわけではなく、そもそも完全な法など存在しないのだ。時の「政府」や「議員」たちの気まぐれで条文をいじってもまた別の新たな矛盾が生じてくるだけである。
この国の「議員」たちは、本来目指すべき、「国家」および「国民」の平和と安全の具体的形象から離れた「憲法」そのもの、「憲法」それ自体について問おうとしてしまっている。それはまさに「概念」の実体的使用の錯誤そのものであると言えるのだ。
そもそも、現在日本の抱えるパラドクスは「憲法」自体に「矛盾」があるからではなく、「改憲」と「護憲」を「矛盾」だとするわれわれの頭の中の「論理の秩序」が間違っているのである。「護憲」と「改憲」や、「保守」と「リベラル」、「立憲主義」と「安保法制」などはアカデミーやマスコミが作り出した「想像の共同体」である。「想像の共同体」とは政治学者ベネディクト・アンダーソン氏の主張で、近代国家の国民が国家共同体の一員であるとみなされる度合い、つまり、国民が互いに抱く結束感の強さは、マスメディアが人工的に作り出し、推進したものである、というものだ。
さらに言えば、経験として現れない限られた論理空間においてその関係性を根拠づけようとして因果関係を細分化していっても結論には到達しない。関係性に経験の事実としての根拠がない以上、常に「謎」の部分は残る。さまざまな秩序の「原因・根拠」なるものの本質は、事実的な、あるいはそれを表示する論理的な「因果の関係」としては捉えられない。なぜならそれは任意の観点を生み、したがって任意の系列を作るから、多くの原因と呼べるものを生み出して、まさしくそのためにどこにも行きつかないからだ。要するに「言葉の意味の混同」、「言葉の意味のすり替え・捻じ曲げ」によってもたらされた「論理の飛躍」、「詭弁」なのである。全く違う意味の表現を混同することによって、あるいは現実と異なる論理を差し挟むことによってパラドクスが導かれているのである。
まだ、生まれていない「日本国憲法」、日本はようやく問題の核心に近づいた。
「日本国憲法」の「概念」はまだどこにも存在していない。目の前にあるのは「憲法典」というまだ「卵」の時間性に過ぎないのだ。
現行の「日本国憲法」は国家の細胞核の中の固有の思想体を取り除いて、アメリカや、外国またはフランス人権宣言などの理想に基づいた遺伝子情報によるすでに一人前の細胞の核を入れた。
白ねずみの卵子から細胞核を取り除いて、黒ねずみの細胞の核を移植したとする。成長するとこのねずみは白じゃなくて黒になる。細胞を提供した黒ねずみと全く同じ遺伝子情報を持つ、姿形をコピーしたように全く同じようになる。こうした生物のことを「クローン」と呼ぶ。
つまり、そういう意味では「日本国憲法」は「クローン憲法」であると言える。しかし、たとえ、そのことが倫理的に問題があったとしても、生まれてくる「クローン」のそれも立派な生命であることに変わりはない。なぜなら、それは母胎を通して生まれてくるからだ。「母性」がその生命を現実体に導いていくのである。日本という母体に「母性」が存在すれば「日本国憲法」は立派に育っていく。
それは一体どういうことなのか。ー
つまり、「日本国憲法」はまだ生まれていないのである。
戦後日本社会が「紙幣」と「娯楽」という心性を「平和憲法」という言葉に置き換え、次世代に伝承できる「憲法」の思想核を育んでいないというのが日本国憲法の現在の時間性である。
アメリカを「神」とし、外国の思想核を持った現行の憲法典の今の時間性は「卵」の段階であり、「憲法」という生命の誕生は2050年以降もう少し先の話である。
「憲法」Constitution とは国民の意識における抽象化であり、概念化にことであると言える。現行の「憲法典」は国民の「概念」とは決して相似しているとは言えず、いくら条文を改訂したとしても、現行の「憲法典」では様々な具体的な問題について実質的な解決を導き出すことなど出来ないのである。
今、世界で起こっているのは、「戦後」、「ゲシュタルト」が崩壊していると見るべきである。
「ゲシュタルト」とは、総合的な知覚を意味し、「ゲシュタルト」崩壊とは、総合的な意味を認識できなくなる現象を指す。全体性を持ったまとまりのある構造から全体性が失われ、個々の構成部分にバラバラに切り離して認識し直されてしまう現象である。
日本の憲法論争はその顕著な例である。日本の「議員」や「学者」の脳には、「戦後」という大きな世界観が失われ「憲法典」における個々の条文に目を奪われ総合的な意味を認識できなくなってきている。
個々の条文を、ずっと見続けていると、「あれ?この言葉って、こんな意味だったかな?」と全体のコンテクストから離れて行き、その言葉が派生するシーニュやランガージュを感じるようになる。ずっと見ていると、総合的な意味がぼんやりしてきて、 ただの単純な言葉としてしか、見ることができなくなり、コンテクストを見失ってしまうことになる。これが、人間の脳の認知の不思議さであり、面白さでもあるのだ。
「憲法」Constitution の「概念」を獲得するためには条文の解釈から観ただけで分るものではない。私たちの「視知覚」は対象の一面のみを捉え知的理解は事象の因果関係だけを汲み上げる。そこには無数の視点と無数の理解の道筋があり、それだけで物的存在が人間の知覚理解の限界を超えるものであることが意味されている。
つまり、「憲法」Constitution は「知性」で完結するものではなく,それが繰り返し解釈されることによって浮かび上がる認識のまとまりであり、いわば未知の総体としてアプリオリに前提されているのである。アプリオリとは、経験的認識に先立つ先天的、自明的な認識や概念なのである。
「憲法典」と「憲法」Constitution が有機的な相応関係を保持する場合もあれば,両者の乖離が顕著となる場合もある。後者の乖離が生ずる原因としては,「憲法典」に関する国民の基本的な意味的理解(物語性)に問題がある場合もあれば,厳しい時代環境が相応関係の構築を許さないという場合もある。いずれにせよ,後者の乖離が顕著となる場合,国家社会の不健全化ないし退嬰化は避けられず,「憲法典」を改廃するに至るか,憲法典に相応する「国のかたち」の再構築に向けての相当意識的な努力が求められることになる。
「憲法」Constitution の議論では、まずはその「概念」の集約と共有化を行わなければ、結論は導き出せない。この国の「議員」がそのことを行わないのは、つまり、「議員」たちの目的は「議論」のための「議論」であり、「議論」の混乱なのである。つまり、自らの権益を守るためにマッチポンプのように問題を複雑化することが目的であるからなのだ。「議員」は「護憲」、「改憲」と叫ぶだけで年間数千万円の快適な生活を手に入れることができる。
「議員」の目的は決して「憲法」ではなく「議員」そのものにあり、知性派を標榜する憲法マニアの「議員」たちが少しばかりの情報の断片による「豆知識」に浸って退屈な評論を繰り返している現状は、国家や国民に対する最大の裏切りであると言える。
「憲法」は書物で学び、必要に応じて使うことができない、そういうやり方では「憲法」は身につかない。現実的な意味での「憲法」は習慣の結果として生まれる。実践することによって覚えられる類のものなのである。「議員」や「政党」が「憲法」を身につける第一歩はまずは実行することだ。それは技能を身につけるのと同じことである。知識よりも肉体感覚やプリミティブな感情を基準に物事を判断することが最も重要なのである。つまり、「習律」の問題なのである。日常の一つ一つの問題の背景に潜む、「憲法」の思想核と向き合うことでしか、ほんとうの「憲法」を手にすることは出来ないのである。
「憲法」というメロディー、全体は、部分の総和よりも大きい 。
「憲法」とはメロディーのようなものである。「憲法」constitution が本質として希求しているのは、決して難しい学問ではない。「お互いを尊重しあい、平和に過ごすということである。」つまり、これが目的である。そのために人類はHECPー人権、環境、共同、公共という個別の命題の抽象化、概念化と統合(インテグリティー)に取り組んで行かねばならない。インテグリティとは、誠実、完全性、全体性、整合性、統合性、などの意味を持ち、人間は誰しも自分の直面する世界について、あるイメージを作って生きている。これを世界イメージ、世界観、あるいは単に生活観のようなイメージをできるだけ広く筋の通ったものにする努力、それが思想であり、そうした全体としての一貫性を示すのがインテグリティと言う表現である。
そして、そのアプローチは決して一方向ではなく様々な選択肢があり、様々な意見が存在するのである。
しかし、現在の憲法論争は、結局のところ、こうした議論とは「概念」の罠にはまってしまった思考法なのだ。その「概念」がいったい何のことなのかよくわからないまま、その言葉を根拠のない論理で繋げていく「言語ゲーム」にすぎないのである。
「抽象化」、「概念化」においては、対立した事柄に共通した「本来の目的」を考えることによって、お互いを包括し、本当に必要な解決策を考えることができる。「本来の目的」が分かると、物事の本質や「原理」アルケーが見えてくる。
それは決して憲法論争を哲学論争にすべきであると言っているのではなく。哲学とは、世界の全体を「原理」アルケーの概念によって考えることであり、物語を使用せず「抽象概念」を使用することで世界説明を試みることである。
現行の「日本国憲法」は市民の運動によって、「概念」の相似から生まれたものではなく、「戦後」という歴史性から生まれた主権者不在の全く物語性のない、その時間性はまだ「卵」の状態であると言える。
日本国憲法典とは「抽象概念」により「原理」アルケーで人類世界を表象したものなのである。そもそもそういうものにすぎないということの理解が必要である。
そもそも「憲法」Constitutionの法源となる最も大切な神意や真理を理解するのに高度な知識も高文脈も全く必要としない、誰もが理解できる、そして実行できる、それが「憲法」Constitutionなのである。日常の一つ一つの問題の背景に潜む思想核と向き合うことでしか、ほんとうの「憲法」Constitution を手にすることは出来ない。
「政治」という「芸術」においては「議員」の「概念」は、単なるアレゴリー的衝動ではなく、「政治」を生命運動として捉えた相似形の連続した〝断片〟でなければならない。生活の中のありきたりの〝断片〟に込められた意味を寄せ集め、『より大きな共通点』を映し出すことで「国民」にほんとうの目的と選択肢を知らせることが、本来の全国民の代表である「議員」の役割なのである。
現行の「日本国憲法」は日本国民の心象を『より大きな共通点』で一つにまとめ、抽象化による「概念」の相似を形象したものではない、主権者不在の全く物語性のない法典であると言える。
「憲法典」の制定は,もとより法典に見合った「国のかたち」の形成維持を目指すものであるが, 「国のかたち」の形成維持は歴史的・動態的なプロセスであって,「憲法典」の制定によって完成ないし完結 するわけではない。
実質的な「憲法」は「憲法典」に尽されず,「憲法学」は法典集中の視野狭窄に陥っている。「憲法」Constitution とは国民の意識の抽象化であり、「概念化」であると言える。「概念」の伴わない憲法典の条文の文言の改訂など何の意味もなく、わが国はそんなことでいいかげん、いつまでも争っている場合ではないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
