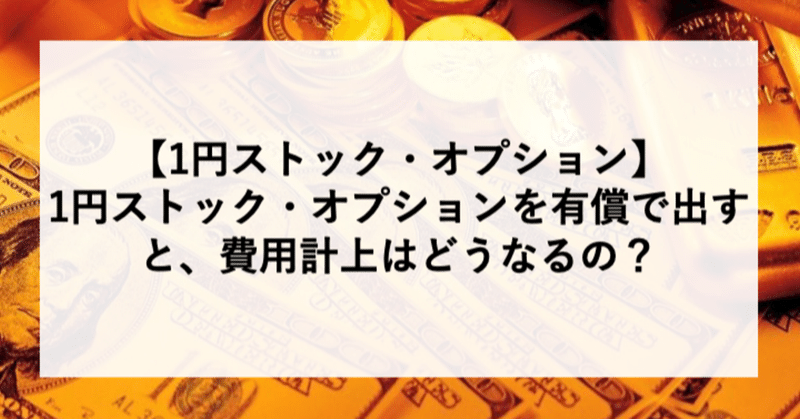
【1円ストック・オプション】 1円ストック・オプションを有償で出すと、費用計上はどうなるの?
こんにちは、大門(だいもん)です。
今回はここ数日、なぜか全く同じ質問を受けているので、「もしや思いのほかニーズがあるのでは?」と思った議題、1円ストック・オプションを有償で出した場合の費用計上について、取り上げたいと思います。
そもそも1円ストック・オプションとは?
1円ストック・オプションとは、上場企業の退職給付として出されることの多い、権利行使価格1円の無償税制「非」適格ストック・オプションになります。
なぜ退職給付として出されるかと言いますと、通常の無償税制非適格の場合は、権利行使時点で給与課税されるのですが、この給与課税を退職所得とみなすことで税率を引き下げることが目的になります。
つまり、退職と同時に権利行使しますと、権利行使時点の給与課税対象金額(権利行使時点の株価マイナス1円)が退職所得とみなされる、という整理になります。
無償税制「非」適格とされるのは、権利行使価格が発行時点の株価を大幅に下回っている(1円)ことが理由になります。

有償で1円ストック・オプションを出すとは?
上場企業の場合、有償ストック・オプションは「公正価値ー業績条件等を付けた発行価額」が費用計上対象になることは、以前の記事でまとめましたが、それでは有償ストック・オプションの権利行使価格を1円にした場合は、どういう費用処理がされるのでしょうか?
前段として、ストック・オプションの公正価値は、株価=権利行使価格の時には、株価の40%〜60%になりますが、例えば1,000円の株を1円(権利行使価格)で買える権利であれば、オプションの価値が跳ね上がり、40%〜60%の幅には収まらないことは、想像に難くないと存じます。

権利行使価格の引き下げ分は費用計上不要!
結論から申しますと、権利行使価格の引き下げ分は費用計上不要になります。理由は、権利行使価格を引き下げた時点でストック・オプションの公正価値が上がっている=費用計上金額が上がっている(※)にも関わらず、さらに権利行使価格引き下げ分(発行時点の株価との差額)を費用計上しますと、ダブルカウントすることになり、整合性が取れなくなる、というところにあります。
※例えば、公正価値500円のストック・オプションに達成確率10%の業績条件を付けた場合、発行価額は50円となり、費用計上金額は500円-50円=250円となります。
一方で、公正価値が900円に上がった後に、達成確率10%の業績条件を付けた場合、発行価額は90円となり、費用計上金額は900円-90円=810円となって、大きく上昇することとなります。
他にもストック・オプションにまつわる気になることがございましたら、下記よりお問い合わせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
