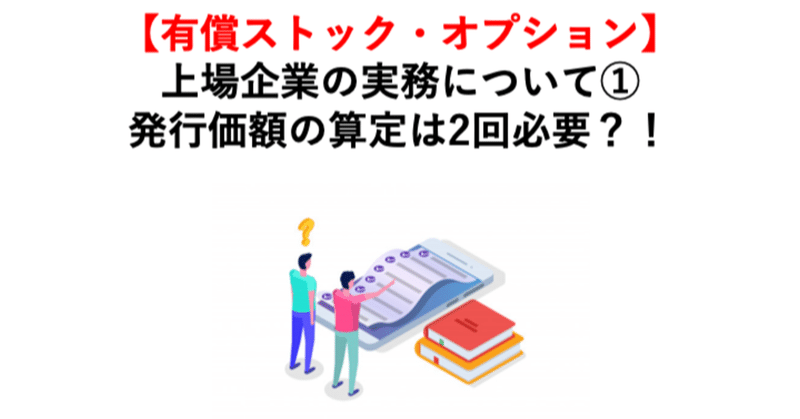
【有償ストック・オプション】 上場企業の実務について① 発行価額の算定は2回必要?!
こんにちは、大門(だいもん)です。
今回は、有償ストック・オプションを発行する中で、上場企業にのみ発生する実務をまとめていきたいと思います。その中でも今回は「発行価額」の算定を2回する必要がある、という点をまとめます。
そもそも「発行価額」とは?
詳しくはマガジンをご覧頂ければと存じますが、端的に申しますと「1個あたりのストック・オプションの時価」になります。上場企業の場合、常に株価が出ているので、発行決議日の前日終値の株価をベースに、発行価額の算定を行います。
ロジックについては、マガジンをご覧頂ければと思いますが、通常は第三者算定機関に委託して、レポートを取得する形になります。
なぜ算定が2回必要なのか?
さて、冒頭に書いた通り、なぜ発行価額の算定は2回必要なのか、というところ、結論から申しますと「発行決議日」と割当対象者が確定する「割当日」に2回算定する格好になります。
発行決議日は、「割当対象者が払い込む発行価額のベース」を算定するタイミングになります。1個あたりの発行価額を算出し、割当対象者は、払込期日までに発行価額を払い込む必要があります。
割当日は、「発行会社の費用計上金額のベース」を算定するタイミングになります。下の図をご覧頂ければと思うのですが、上場企業の場合、2018年4月の会計基準変更を機に、費用計上が求められるようになったため、2回目の算定という実務が発生した次第になります。

どうして割当日ベースで再度算定する必要があるのか?
IFRS(国際会計基準)でも同じですが、費用計上の基準日は割当=grantしたタイミングと見なされるので、割当日に再度発行価額を算定して、その算定結果を元に費用計上金額を割り出す、という格好になります。
では実際に費用計上が計上されるタイミングはいつになるのか?という疑問があると存じますが、こちらは設計次第で調整可能になります。
具体的に申しますと、(監査法人の解釈によりますが)費用計上は「権利行使が確定したタイミング」で計上されることが一般的になります。例えば、「22年6月期に営業利益●億円を達成していなければ失効」という条件をつけた場合は、22年6月期を到来してから費用計上が発生する格好(ベスティング条項を付けて先延ばしすることも設計上は可能)になります。
他にもストック・オプションにまつわる気になることがございましたら、下記よりお問い合わせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
