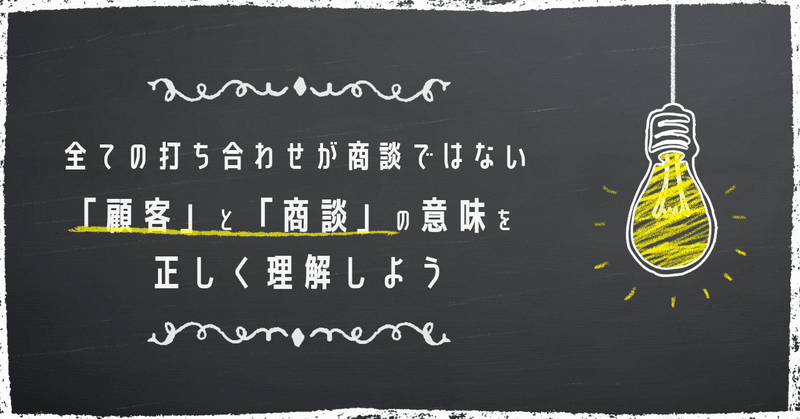
全ての打ち合わせが商談ではないーー「顧客」と「商談」の意味を正しく理解しよう
ビジネスを進める上で顧客の存在は必要不可欠です。顧客を開拓する段階では、熱量の高い人から情報収集だけが目的の人まで、さまざまなタイプの相手と接する必要があります。
その中から誰が本当の「顧客」なのか、明確に定義できていますか?
HAX Tokyoでスタートアップとの壁打ちの際に、ビジネスの進行具合を尋ねるとよく「すでにお客さんがいる」「引き合いがある」という返事が返ってきます。しかし、その中には名刺交換をしただけだったり、ミーティングをしたけれど具体的な進捗がない、といったケースも少なからずあります。
こうした認識の齟齬を生む原因は、顧客の定義の曖昧さにあります。ただ挨拶をしただけの状態から、購入に至るまで異なる段階があり、その全てを顧客と定義してしまうと、正しくビジネスを進めることができません。マクロな市場とミクロな顧客の双方を押さえ、ビジネスを着実に進めていくための捉え方についてお伝えします。
その打ち合わせでビジネスは進んでいるか
打ち合わせを行うことと、ビジネスが進むことは同義ではありません。顔合わせの機会を設けたとしても、
事業を進めるための具体的なアジェンダがない
漫然と技術やサービスを紹介するだけ
相手のコミットも引き出せない
という状況が続くようであれば、その相手は顧客であるとは言えません。
ビジネスを進めた先で売り上げを立てることから逆算し、適切なステップを踏むことを意識しましょう。
認知から購買に至るプロセスを正しく知る
顧客はいきなりお金を払うわけではありません。
会社やプロダクトの存在を知らない「潜在顧客」には、広告や展示を通じて認知されることが必要です。プロダクトが提供する価値を伝えて興味関心を引き出せれば、購入の可能性がある「見込み顧客」に進んだと言えます。さらに比較検討を経て、購入の可否を判断する段階に至れば、ようやく「購買顧客」としての関係になります。

ビジネスにつながる商談と呼べるのは、少なくとも見込み顧客よりも先の段階でのこと。アカデミア出身など営業に不慣れなチームは、潜在顧客ですらない人たちとの会話さえ商談と捉えてしまうことがありますが、展示会で喋ったあと、一度顔合わせをしたくらいでは「真の意味での商談」とは言えません。
誰かと話すことを全てをビジネスデベロップメントと捉えるのではなく、潜在顧客から購買顧客に至るプロセスをイメージして、相手がどの段階にいるのかを正しく認識しましょう。
「打ち合わせに別の部署も呼びたい」は良いサイン
顧客の段階が進むと、いくつかのサインが現れます。相手側から「打ち合わせをしましょう」と言われたのなら、興味関心のフェーズに入ったと言えます。比較検討フェーズへの最初の一歩は、価格や性能の競合比較など細かい話が始まること。一番のアピールポイントではない情報を必要とされた場合もポジティブに捉えて良いでしょう。
また、担当者の中心領域ではないことに話が及んだら、ステップが大きく進んだと捉えてOKです。技術サイドの人が価格の話に、営業サイドの人が機能の話に興味を持つのは、社内での調整に必要な情報を引き出そうとしている証拠です。
一担当者の興味を超え、他の部署やチームを呼んで話したり、部署を跨いだ機会のセッティングが行われたりすれば、より購入や契約の確度が上がっていきます。トップダウンで進む場合にも、担当部署が増えるのは良いサインです。
担当者との関係性が深まってきたら、購入に進むために必要なステップを聞くことも有効です。社内の承認を得るために必要な情報や、気をつけるべきポイントを聞き出し、それに応じた動きを試みましょう。特に、以下の4つの観点に着目すると良いでしょう。
予算|購入のための予算があるか
決裁権|先方の面談者に導入承認の決裁権があるか
必要性|自社が解決できるビジネス課題があるか
期限|いつ導入予定か
こうしたコミュニケーションを通じて、相手側から会社の状況や解決すべき課題などについて情報開示がされたら、それは「一緒に課題について考えてほしい」というメッセージです。相手の担当者を共犯者にするようなアプローチも意識してゴールを共有し、同じ目標に向かって進んでいきましょう。
市場規模はミクロとマクロのセットで考える
顧客を定義する際には、マクロな社会課題だけでなく、自分たちが本当に解決したいミクロな現場や対象者もセットで考えなければいけません。リサーチに長けたコンサルティング出身のチームにおいては、マクロな視点が優先されがちで、現場のコミュニケーションが後回しになっているケースも見られます。
市場規模の指標であるTAM・SAM・SOM(※)などを定める前に、まずは具体的なことから考えましょう。VCやエンジェルが投資判断をする際にも、市場規模が大きければお金を入れるわけではなく、その数字と導出したロジックを合わせて評価するからです。デスクトップリサーチだけの手触り感がない数字よりも、手を動かしたり人に話を聞いて作った蓄積があれば、数字の確からしさも向上します。
※TAM・SAM・SOMはそれぞれ市場規模を示す指標。
・TAM(Total Addressable Market):ある事業が対象とする市場全体
・SAM(Serviceable Available Market):TAMの中で実際にアプローチ可能な市場
・SOM(Serviceable Obtainable Market):SAMの中で実際に獲得できるであろう市場
顧客はそれぞれ個別具体性があり、それらを束ねたものが市場というわけではありません。人が何に困っているかを考え、積み上げた先に確かな市場が見えてくるのです。目の前の顧客だけを見るのでも、マクロな市場だけを見るのでもなく、中長期的な視点で事業開発を進めていきましょう。
取材・文:淺野義弘、編集:シンツウシン
スタートアップ向け壁打ち相談会(対面・オンライン)のお知らせ
HAX Tokyoでは、グローバル展開を目指すハードウェア スタートアップや、これから起業を目指している方向けのカジュアルな壁打ち会を実施しています。
HAX Tokyoのメンターが相談をお受けしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
【相談できることの一例】
資金調達を成功させるためにピッチ資料を改善したい
開発 設計など製造面での課題があり相談にのってほしい
PoCの良い進め方、いいプロトタイプ(MVP)の作り方を教えてほしい
企業との事業連携や事業開発をうまく進めるためのコツを知りたい
なお、HAX Tokyoへのエントリーやお問い合わせも、こちらの相談会でお請けしています。詳細は下記サイトからご確認ください。
この記事が参考になったら、SNSへのフォローもよろしくお願いします!
Twitter: https://twitter.com/HaxTokyo
Facebook: https://fb.me/haxtokyo
