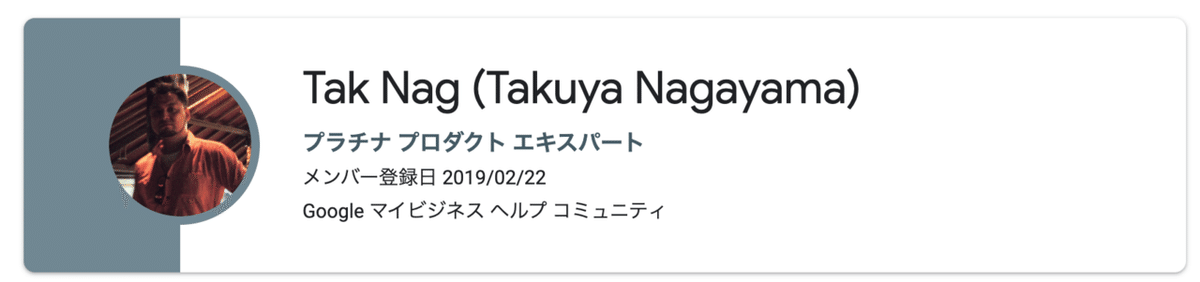エキスパートが徹底解説!見るべき指標・取るべき戦略:これからのGoogleマイビジネスの話をしよう#14
毎週火曜日、Googleマイビジネス(Googleビジネスプロフィール)のトレンドや考察をお届けする『これからのGoogleマイビジネスの話をしよう』というマガジンの第14回です。今回でいったんの最終回となります。
Googleマイビジネス(Googleビジネスプロフィール)に取り組む方は増えましたが、機能の使い方を知ることができても、結果をきちんと分析したり、売り上げに繋がるように活用する方法はなかなか普及していません。
最終回では、Googleマイビジネスプラチナプロダクトエキスパートの永山卓也さんに、Googleマイビジネス(Googleビジネスプロフィール)の指標の解説、実践的な分析、売上につながる運用方法や繁盛に繋がる俯瞰視点、オーナーに多いお悩みについて取材。
すぐできそうな実践テクニックから、マニアックな専門知識まで、この機会に全部訊いてきました。
■特集:マップ集客に留まらない俯瞰視点
■番外編:生きた情報の宝庫「公式ヘルプコミュニティ」の紹介
■今週の関連ツイート
■今週の関連記事
■あとがき
はじめに「Googleマイビジネス」「インサイト機能」について
Googleで地域や場所に関連するキーワード(例:ラーメン屋)で検索すると、通常の検索結果より先にGoogleマップやナレッジパネルが表示されるなど特別な検索結果が得られます。この特別の検索やGoogleマップでの検索のことを「ローカル検索」と言います。
「Googleマップユーザーの増加」や「お店を探すような検索ワードだと通常の検索より上に表示される」ことから、お店からの新しい情報発信の場所として注目されています。

ローカル検索で表示される情報は「オーナー・ユーザー・Googleの三者間」で作り上げられています。Googleマイビジネスは、このオーナー情報を管理できる無料のサービスで、営業情報・写真・投稿・クチコミ返信などを登録できます。

Googleマイビジネスのインサイト機能で、ユーザー分析をできる
Googleマイビジネスには、情報の管理以外にユーザー分析をする機能「インサイト機能」があります。施設のページが「どのように」「どれくらい」検索や表示されたかを確認できます。
掲載順位を確認することはできませんが「どれくらいのユーザーに施設を知ってもらえたか?」「施設を調べたユーザーがどんな行動を取ったか?」などを確認することができます。

<インサイト機能で主に分かること>

https://support.google.com/business/answer/7689763?hl=ja
このように様々な情報が確認できるインサイト機能ですが、分析の実践ノウハウや事例がそこまで多くありません。
そこで今回、Googleマイビジネスの分析方法と、結果から見た改善方法を、Googleマイビジネスプラチナプロダクトエキスパートの永山卓也さんに取材。
「Googleマイビジネスをどう運用したら、どんな成果につながりやすいのか?」という、これからのGoogleマイビジネスの使い方を探ります。
大前提「Googleマイビジネスをどこまで活用するか?」は店によって変わる
今回お話を伺ったのは、Googleマイビジネスプラチナプロダクトエキスパートの永山卓也さん。永山さんは、小規模店舗から大規模施設まで様々なローカルビジネスのコンサルティング業や店舗マネジメント業を行っています。
https://twitter.com/tak_nag_lug?s=21
ー創刊号でも監修にご協力いただき、ありがとうございました。今回、永山さんに改めて伺いたいのは「どうすれば商売繁盛につながるGoogleマイビジネスの活用ができるのか?」というテーマです。
永山さん:前提になりますが、そもそも店ごとに「Googleマイビジネス(ローカル検索)を通してどこまでやりたいか」を考える必要があると思います。
項目を埋めるだけでも単純に「検索者が得られる情報は増える」わけで、「情報を正確にするだけ」という運用方法もあるわけです。
どこまで突っ込んでマイビジネスを活用するかは、そのビジネスの業種業態、エリア、SNSなどの活用度、知名度、そして何より人の余裕(人的リソース)などによっても活用の度合いは変わってきます。
店舗の情報発信ツールは、Googleマイビジネス以外にもたくさんあり、人的リソースが限りある以上、それをどう配分するかが重要です。

ーGoogleマイビジネスの重要性は増してきていますが、あくまでも面のひとつであるという意識が大事なんですね。
永山さん:ただし、ローカルビジネスを行う事業主にとって「Gooleマイビジネスをまったく利用しないという選択肢は無い」ものではあるとは思います。情報の整備を行っても、無駄になる面が限りなく少ないためです。
ローカル検索は、既にたくさんの人に利用され、店舗・施設の候補は「通常のウェブサイトが表示される位置」より非常に目立つ位置に表示されています。検索者の現在位置や時間によって順位が変動するため、どんなお店でもチャンスがあります。

永山さん:Googleマイビジネスは、Googleのローカル検索を通して検索者にアピールできるツールで、活用の度合いに関係なく、ローカル検索で表示される店舗・施設情報は商売繁盛に繋がるための一翼を担っていると言えます。
なので、公開停止などの違反措置の大きなリスクを抱えながら行うような短期的な違反テクニック(例:ビジネス名などに脈略なくキーワードを入れたりする違反手法)でなければ「正しい情報が正しい手法で増えていき、情報を求める検索者に伝わる」わけで、すべてプラスに働いてくれます。
永山さん:あとは「どれだけ魅力を伝えられるか」です。もちろん、より深く、全てを伝えられるに越したことはありませんが、必ずしも店舗レベルでの細かい情報や個性を出さなくてもよいローカルビジネスもあります。
認知度が高い大手チェーン、例えば大手ファーストフード店のようなビジネスになると、むしろ差異があるデメリットの方が大きくなる可能性があります。
逆に地方部のFCケータイショップのように、接客も長く、地域に密着しているビジネスは、チェーン店であってもある程度店舗の色が出た方が良い業態もあります。
特集:エキスパートが徹底解説!見るべき指標、取るべき戦略
ーGoogleマイビジネスに本気で取り組む方が増えています。しかし、一方で「上位表示」や「表示数」のように、直接には売上と繋がりにくい指標を追う場合も多いようです。
永山さん:そうですね。個人的には業種業態にもよりますが、基本的には「検索数」と「アクション数」が指標としてはいいと思います。
上位表示が売上に繋がるどうかは一旦置いておいて、「上位表示」といっても現在位置からの距離や時刻などでも検索結果の順位は変化します。
とすると、条件は無数に存在するので、ある程度のローカル検索や店舗マーケティングの知見がないと、「順位」は指標化しても見当違いな指標を追う事にもなってしまうとは思います。
表示回数も「ナビ中」や「未検索時」に表示されるマーカーといった「目的外の表示」もまとめてカウントしてしまうため、売上に繋がる指標としては使いにくいですね。

永山さん:あとは「数字が増えた減った」で一喜一憂する前に「数値の変化が何を示しているのか?」を俯瞰で見る事が重要です。
例えば季節で需要が変動するビジネスであれば、インサイトに表示される数字も、季節でプラスになったりマイナスになったりします。

ーその「検索数」について、もう少し詳しく教えてください。
直接検索と間接検索の違い。ビジネス名を付けるポイント
ー検索数は、主に直接検索と間接検索の二つに分かれ、公式では「直接検索=ビジネスの名前や住所を直接検索したユーザー」、「間接検索数=提供している商品やサービス、またそのカテゴリを検索し、リスティングが表示されたユーザー」と説明されています。
この違いについてもう少し教えてください。検索ワードと設定した店名が少し違うだけで直接検索ではなくなるのでしょうか?
永山さん:完全な仕組み・仕様は公開されていませんが、ざっくり言うと、直接検索はいわゆる指名で「Googleが店舗名と認識している語句」「設定されているビジネス名そのもの」です。
完全マッチでなくてもある程度正しければ、指名されている(直接検索)と扱われるようです。ただ、キーワードを大量に入れていたり(違反)すると、指名されていると判断されなくなる場合もあります。
直接検索は知名度(視認性の高さ)の対象になり、検索ランキングのシグナルに用いられていますので、こういった行為は非常に危うい施策です。
間接検索はジャンルや商品名、特徴などの検索です。「まだどこに行くか分からない層」なので、直接検索とは検索している意図や質が違います。
永山さん:ホワイトな正しい運用を心掛けるとしても、ビジネス名に必ず「とても長い正式名称」をつける必要があるわけではないです。
例えば、正式名称が「おいしいご飯と地元土産の○○屋 総本店」で、看板にもそう書かれているが、ホームページやアメニティには「○○屋」と書かれていたりして、短い店名の方が浸透している場合がありますよね?
その場合「○○屋」と検索する方が圧倒的に多いでしょうから、冠を抜いた「○○屋」をビジネス名としても良いと思います。

ガイドラインにも「店舗、ウェブサイト、事務用品などで継続的に使用し、顧客に認知されている、実際のビジネスの名称を使用します」とあるのは「浸透している名称を選んでもよい」というGoogleの意図が読み取れます。
永山さん:「とても長い正式名称」にこだわることで、意図せず「店舗名」を利用者にもGoogleにも覚えてもらえないなどの弊害になっているケースもあります。
同時に検討しないといけないのは「土産物屋」という名称が入った方が、来店につながりやすいというケースです。
駅前からホテルまでのルートを検索しようと、マップを開いたときに「土産物屋○○屋」と目に入ると「○○屋」だけよりも立ち寄る候補に入れやすいですよね?
インサイトの検索数(直接検索、間接検索)、アクション数、検索クエリなどに、「検索する人の意図や動き」を読み取ることができるヒントが隠されているかもしれません。
ー店舗名の一つでも、いろんなアイデアが考えられるのですね…。
永山さん:あくまで「ルールを守った上で」になりますが。
(※なお実際には、長い正式なビジネス名を設定していても、様々な情報要素から短い愛称の店舗名を直接検索と扱う場合もあるそうです)

直接検索・間接検索の特徴・増やし方
ーそれぞれの特徴は分かりました。検索数の伸びは、集客のきっかけや来店増につながると思うのですが「直接検索」はどういったケースで増えるのでしょうか?
永山さん:店名で検索する人が増えたケースですね。TVで紹介されたり、チラシなど広告媒体、そして人の紹介(本来の意味の口コミ)、リピーターの醸成がうまく作用した結果と言えます。(ただし、ビジネス名などを変更した等の背景がある場合は除きますが)。
ー過去も取り上げましたが、SNSに取り組むことも効果がありそうですね。
永山さん:直接検索を増やす取り組みは、Googleマイビジネスではない領域での動きなので、この成果を如何にマイビジネスの情報整備に活かしていくかが鍵となります。見てくださる方は増えているわけなので。
ー逆に間接検索はどうしたら増えますか?
永山さん:間接検索が増えるのは、大きく2つのケースです。
・Googleにサービスや魅力、特徴、商品が認識され、関連づけされる
・もともと関連付けられていたキーワードが、季節やトレンド要因で需要が高まる
GoogleマイビジネスやSEOなどでのデジタル施策で、関連するキーワードを増やすのが有効です。Googleマイビジネスやウェブサイトで言及したり、口コミを集めることでGoogle側も店舗の情報が豊富になり、関連付けされ、それを強める効果があります。
お客様のニーズと自店の特徴がマッチする金脈(キーワード)を探す
ー関連するキーワードとは、具体的にはなんでしょうか?どう見つけたらよいでしょうか?
永山さん:まずは施設の特徴の整理とチェックをしましょう。「どんなキーワードで表示されて欲しいか?」「表示されているのか?」「そのキーワードにニーズがあるのか?」の確認が必要です。
1:自分たちの特徴を全部書き出す(ラーメン屋の例:ラーメン・豚骨ラーメン・醤油ラーメン・つけめん・駐車場・チャーシュー・子ども連れ・大盛り・激辛・深夜営業・ランチ)
2:実際にお客様が検索するであろうシチュエーションで検索してみて検索結果に表示されるか試す(ラーメン屋の例:渋谷駅前で「豚骨ラーメン 渋谷」と検索)
※検索結果は、距離の影響も受けます。実際のシチュレーション(最寄駅)に行って試すか、以下の記事を参考に、位置情報を設定して検索してください。

永山さん:表示されない場合は、その語句が店舗と関連付けられていない可能性があります。WEBサイトや投稿などで、その特徴を発信していく必要があります。
メインの特徴以外にも、季節によって増える期間限定商品や特別な商品で表示されると、間接検索数が大きく増えます。例えば、暑い時期の「かき氷」のようなキーワードですね。

永山さん:ただし、こういったトレンドのキーワードは、その季節になってから焦って動いても間に合わないことが多いです。事前に一年通した、自分たちに関連しそうなトレンドキーワードを書き出しておき、先手先手で発信していきましょう。
Googleトレンドも要チェックです。こうした「メイン商材にないトレンド性のある特徴」は一度洗い出しておくべきですね。
ーキーワードは、お店の方が「ジャンル」や「なんとなく」で決めている場合が多いような気がします。
永山さん:業種などの大きな検索キーワードに囚われすぎな方が多いです。業種以外の魅力を伝えられるキーワードや、商品レベルできちんと関連付けさせる方が有効な場合も多く、これを「金脈を掘る」と呼んでいます。お客様のニーズと自店の特徴がマッチする、そういう金脈(キーワード)を探す方がよいです。

ーお客様のニーズはどう探ったらよいでしょうか?
永山さん:自社サイトを持っているなら、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールでウェブサイト側のクエリを見てみると良いです。
自社サイトの検索に使われている言葉が「ローカル検索でも表示されるか?(関連付けされているか)」「Googleマイビジネスの検索語句レポートに載っているか」の二つをチェックしましょう。
ウェブ検索とローカル検索では、同じキーワードでも関連付けの強さの違いなどにより、表示される検索結果が異なることもあります。間接検索を増やす場合、自店舗の「取扱商品や特徴を全部ひっかかるか」試してみると良いです。
ローカル検索では、商品単位や特徴などをあらわすキーワードが関連づけされていないケースが少なくありません。例えば、ラーメン屋が「ラーメン」で表示されても「豚骨ラーメン」になると表示されない、なんてこともあります。

ー特徴のキーワードで「レポートには表示されないが、検索に表示されるキーワード」はどう捉えたら良いでしょうか?
永山さん:それは、単純に需要がないキーワードですね。例えば、あるカーディーラーの特徴で「風船を配るイベント」があったとします。
風船イベントというキーワードでひっかかるようになったとしても、その言葉で探すユーザーはいないですよね?キーワードの検討は、顧客心理に則る必要があります。
ー間接検索を増やすには検索順位を上げるのも有効ですよね。知名度・サイテーションを高めるために「NAP(店名・住所・電話番号)情報の表記揺れを統一する」という手法も聞きますが、いかがでしょうか?
永山さん:NAP情報は統一する価値はありますが、病的にやる必要はありません。
検索的には「一つのビックワードの関連づけを高めることだけを考える」よりも「関連するキーワードを増やす方を意識した施策」の方が、最終的に力になると思います。
NAPに関して病的に考える必要がないというのは、NAP情報の揺れを、割と認識している検索結果になっているからです。「1−1−1」と住所で検索すると、勝手に「1丁目1−1」になる場合があります。Googleは住所で検索した場合に、「ハイフン」「何丁目」を自動で認識して、ちゃんと対応するようになっているところかもそれが伺えます。。
ーNAPの統一を重視している方は多いので、意外でした。

永山さん:ただし「そもそもGoogleの住所データが正確かどうか」は確認するべきです。
というのも、Googleの登録情報が間違っている場合があり、住所で検索しても別の場所にマーカーが立つことがあります。店舗の隣側をクリックして住所の表記を見たり、自店舗の住所を直接入力して正しい場所にマーカーが立つかを確認してください。その場合、マップの報告で正しい住所を報告してください。
表示数の増減・季節性の変動には要注意
ーGoogleマイビジネスには「表示数(=Google 検索や Google マップでリスティングが表示された回数)」という指標もあります。「検索数は増えていないが、表示数は増えた」のケースも見かけますが、こうしたケースはどう捉えたらよいでしょうか?
永山さん:先ほども出ましたが、表示数だけ増えるケースで多いのは「未検索状態やナビ使用時にマーカーがたまたま表示されている」という理由です。交通量が多い場所や競合店舗がない地域だと起こります。
そして、細かいアップデートの後に突然表示されなくなり、表示数だけが急に減ってしまう場合もあります。「たまたま表示されている表示を多くカウントしている」ので、表示数の増減に一喜一憂するのは危険です。

ー逆に「更新しているのに、検索数が減ったケース」はどうでしょうか?私も経験があるのですが、実はこのケースは少なくないのではと。
永山さん:よく聞く話なので、最もきちんと説明したいケースです。こうした結果に直面したとき、テンションが下がってしまう方が多いですが「減った原因をどう考えるか?」が重要です。検索数の変動には、季節性も大きく、コロナの影響で検索動向も変わったからです。
Googleマイビジネスだけで見ていると「更新しているのに減った」と感じて、施策の有効性を見誤ってしまいそうですが、減ったこと自体より、原因や要因に目を向けるべきです。
季節性の確認には、Googleトレンドで大きなトレンドの増減などを比較するのも有効です。例えば「○○市 おでん」のキーワードは冬に向けて増えますが、当たり前ですが夏は減ります。

ー直接検索・間接検索のどちらから増やすべきなのでしょうか?
永山さん:業種業態で変わりますが、作業が違うので同時に行うのが理想です。基本的には直接検索数が増えることが喜ばしいですが「直接検索を増やすべきか?」は業種業態によります。
名指し検索される事が多く、競合が比較的多く発生する業態、例えば「ラーメン屋」などは「直接検索を増やしていく」ことを避けて通れません。
逆に「土産物屋」のように、店舗そのものが指名されるのが根本的に難しい業態は、間接検索の増加を優先的に取り組む方が良いです。取り扱う商材も多く、すべては関連付けられていないでしょうから。
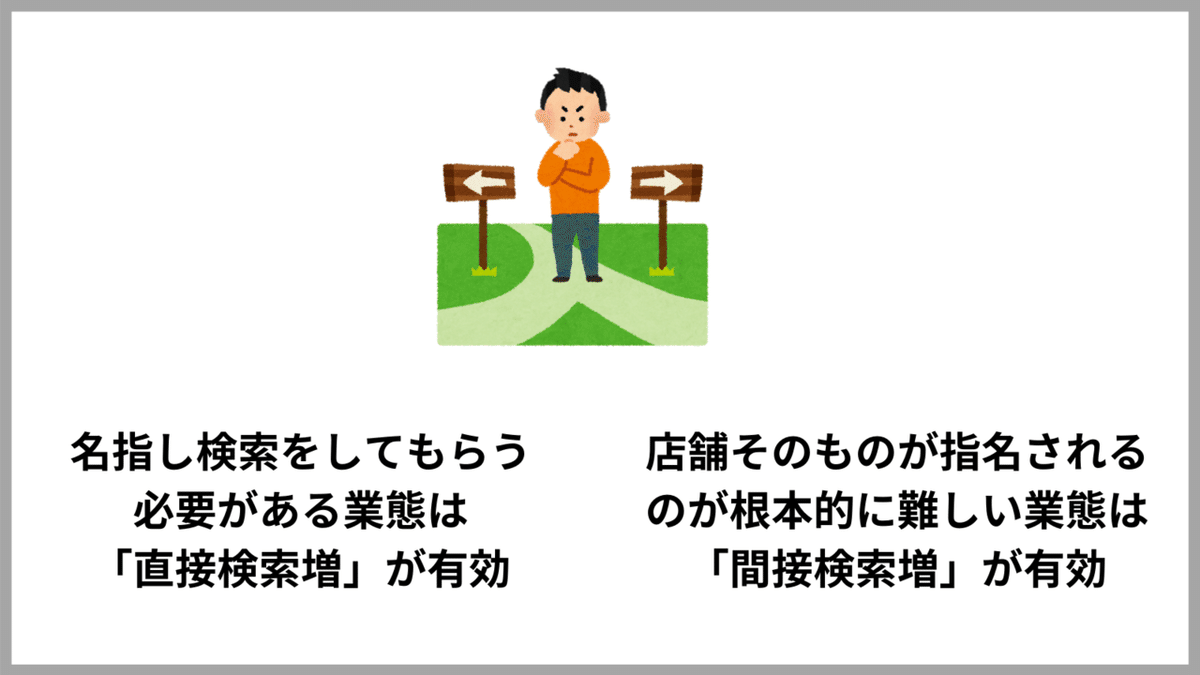
ケーススタディの改善策まとめ
A:表示数だけ増えた場合
→「たまたま表示されているだけ」が多いので、表示数の増減には一喜一憂するのは、あまり意味がない
B:直接検索を増やしたい場合
→直接検索を増やすには、紙や看板などのアナログ施策が有効。他にもデジタル・アナログ問わずGoogleマイビジネス以外の他の施策や広告媒体、SNS活用を検討するべき
C:間接検索数を増やしたい場合
→間接検索を増やすには、関連するキーワードを増やすのが有効。自店舗の「取扱商品や特徴が全部ひっかかるか」試してみる
D:更新を続けている変化がないケース
→「減った原因をどう考えるか?」が重要。季節性やその他の外的要因によるものか仮説を作ること。名指し検索をしてもらう必要がある業態は「直接検索増」、店舗そのものが目立つ必要のない業態は「間接検索増」に取り組むべき
増減より「どんな目的でアクションが起きているのか」を読み解くのが大事
ー店舗にもよりますが、Googleマイビジネス経由の自社サイトへのアクセスは月に数十件、多くても数百件程度がほとんどだと思います。
業態によってはSEOや広告からのアクセス数の方が多いと思いますが、マイビジネス経由のウェブアクセスをどう捉えたらよいでしょうか?
永山さん:その数は単純比較できません。アクセスの意図が異なるかもしれないからです。「なぜウェブサイトにアクセスしたのか」「どのページが目的なのか」を考えることが大事です。
インプレッション・アクション全体で見るなら、チェーンブランドや大型施設でもない限り、大半の店舗はGoogleマイビジネス(Google掲載の店舗情報)を超えるウェブサイトや広告はなかなか無いです。
ただ「ナレッジパネルを経由した自社サイトへのアクセス数」だけを切り取ると、そこまで多くない場合もあるでしょう。
それは、検索者が「ナレッジパネルの情報に求めているもの」と「自社サイトに求めているもの」が違うからです。
「営業時間を知りたい」ならナレッジパネルで希望は達せられます。経由して自社サイトに行った検索者は「わざわざ自社サイトに行く」理由があったわけです。詳しく知りたいとか、特定の項目について知りたいとか、予約フォームに行く等です。
つまり、ローカル検索において、ナレッジパネルから自社サイトへのアクセスは「足らない情報の受け皿」としての役割を自社サイトに求めているわけです。広告やウェブサイト検索にはそれがないので、数を単純比較しても意味はないわけですね。

永山さん:自社サイトへの誘導を必要とするビジネスで本気で取り組むならば、Googleアナリティクスなどのパラメータを入れて「マイビジネスに設置するリンクはどういったものが有効なのか?」を検証していくといいでしょう。自社サイト側でコンバージョンやユーザーの行動を追えると、見えてくるものもあるはずです。
実店舗のオーナーの方であれば、制作会社にご相談されてもいいでしょう。運用業者の方であれば、両方できれば、戦略の幅が広がり、より突っ込んだ施策が行えます。
ー自社サイトに行ったユーザーの目的が推理する必要があるということですね。
永山さん:永山さん:専門的に運用していくならばですけどね。その場合にはぜひ視野を広く持ってほしいです。「マイビジネスだけを見る」のではなく「マイビジネスやウェブサイトなどを含めて全体を見る」ようにするといいでしょう。
ただ、いち店舗の事業主の方がそこまで作業的にも知識的にも精通するのも難しい場合も多いと思いますので、その場合はそこまで考えず、「魅力的な発信を頑張ってアクションを増やす」くらいでも良いと思います。
ー運用をガッツリやっていくなら、施策が実際の売り上げとリンクしているかを考える必要がありますよね?アクション数と売上の関係性をどう考えたらよいでしょうか?
永山さん:「どんなアクションが売上につながりやすいか」は、業種業態によります。アクションがユーザーのどんな行動を意味しているのかをイメージする必要があります。
少し触れましたが「自分の店はホームページを見ないといけない店」なのか「ルート検索をする機会が多い店」なのか「電話で予約しないといけない店」なのかなどによります。

永山さん:同じ業種であっても、単純な数の比較はできません。例えば、駅前の店舗だとルート検索はされにくく、郊外ならルート検索されやすいですよね。同じルート検索1件でも、その1件の意味は違う重さになります。数字の増減の理由を紐解いていき、どういう風に展開していくのかが重要です。
ー業態や場所によって「どのアクションが出やすいか」や「アクションの意味」が変わるということですね。
永山さん:一つのアクションの価値も、店によって変わります。
家族客が多いファミリーレストランのような業態だと、1つのルート検索をグループ単位で考えてもいいわけです。その場合、グループ単価で算出することができます。
ーファミリーレストランなら予約は要らないけど単位はグループ、ヘアサロンは電話かサイトで予約し単位は1人、と業種業態で重要なアクションや効果の見方が変わるということですね。
永山さん:直接的な数字ではないにせよ、業種業態によっては、ルート検索などは効果測定の分かりやすい指標になると思います。
ーアクションの指標では「写真閲覧数」もありますが、個々の写真の閲覧傾向を確認し、最適化など図った方が良いでしょうか?
永山さん:誤解が多いのですが「閲覧数が多い写真=人気がある写真」ではありません。設定されている写真の種類のバランスや更新のタイミングで変わるからです。
例えば、外観ばかりだった店舗に一枚だけ内観やスタッフ写真があれば、写真の良し悪しにかかわらず、その写真の閲覧数は増えます。たまたま、その写真が多く出ただけなので、写真そのものの良し悪しと見る必要はないですね。

インサイトで分かる情報は、店舗マネジメントやブランディングそのものにも生かせる
永山さん:ラーメン屋のような業種は、本来ウェブアクセスや電話というアクションは必要ありません。もし、ラーメン屋で通話が増えているとしたら「どんな目的で、そのアクションが起きているのか」を読み解く必要があります。そして、仮説を立て、答えを探すわけです。
しかし店舗の方も、運用を代行する方も、片方だけの状況によっては「知識やピースが足らず仮説が浮かばない」「知識やピースが足らずその答えが導き出せない」こともよくあります。
ー例えば、店舗の方なら「最近取材された」ということ、運用の方なら「クチコミがたくさん入った」などは、それぞれの立場だから分かることがあるということですね…。
永山さん:「電話が増えている→ヒアリング(何の電話が増えています?)→アクションの内容が売上につながっているか判断する」という風に「この数字はなぜこうなったのか?」を俯瞰で見ると、色々見えてくることでしょう。

永山さん:インサイト機能は、Googleマイビジネスの活用だけではなく、店舗マネジメントやブランディングそのものに生かすことができます。
運用者は、GoogleマイビジネスやGoogleマップ、Google検索について詳しくなることも重要ですが、それ以上に「俯瞰した視点」を持って頂くといいでしょう。
僕は店舗コンサルティングを行いますが、例えば店舗によっては単純に電話のコール数を増やすことを目的にしない場合があります。「そもそもお店は電話をかけて欲しいのか?かけて欲しくないのか?」という大前提の認識が間違っていると、その数値を追っても価値を見い出しにくい場合があるので、まず店の目的を確認します。

永山さん:表示順位も同じことが言えます。例えば「お客様はローカルパックに掲載された候補だけで店を選ぶのか?」という視点です。実際のお店選びでは、もっと多くの候補から選びますよね?
「ローカルパックに表示される上位3位に入ること」は大事ですが、1位と2位とでは大した差がありませんし、仮にそれ以下だとしても、相当埋もれてしまうような状況でなければアクション数や検索数にそこまで影響しない事も多いです。そういう意味では「ランキング順位の追求もほどほどに」とも言えますね。
それぞれ取り組むべきことを理解すると、実際の売上につながりやすくなる
ー現場・運用者のそれぞれが心掛けておくことはなんでしょうか?
永山さん:運用者は「店舗が本当に喜ぶ運用とは何か」を考え、取り組むといいでしょう。そしてオーナーは「とにかく数を増やしてくれ」と丸投げではなく、自分でインサイトを見て可能な限り情報を把握するといいでしょう。
先程も言いましたが「増えた理由・減った理由」は、店舗でないと分からないことも多いからです。
そして「俯瞰的に見て、魅力的で行きたくなる店になっているか?」を意識すべきです。例えば「間接検索で表示されて『うちが一番行きたくなる』ようになっていますか?」など。
ー「かき氷で表示させる」だけでなく「かき氷を食べに行きたい店に写っているか」を意識すべきということですね。
永山さん:どちらも重要ではあるのですが、どちらかだけでは足らないということですね。
店は自分たちが売りたいものが伝わる魅力的な状況になっているか。インサイトは「ちゃんと魅力が伝わっているか」を見返すための資料に使うと足らない情報が見えてくると思います。
ある焼肉店のインサイトで「子ども連れ」で検索する人が多かったとします。表示された段階で、まずは第一段階をクリア。次に、店舗施策や商品作りも含めて、投稿などで「ソフトクリームにチョコソースで自分でデコれます」と見せるようにしたら「子ども連れ」で検索した人は、来店したくなるかもしれません。どちらかが足らないと、うまく機能しないわけです。

永山さん:そして、インサイトのデータは、マップ集客に留まらない使い方ができます。ファミリー向けサービスを看板やチラシで告知したり、子ども連れに響くサービスを増やしたりなどにも活かせます。
ーインサイトを読み込むと「どんな人に、どんな認知をされているか」イメージできるということですね。
永山さん:こういったアイデアは、従来のGoogleマイビジネスの活用では、あまり語られてきませんでした。インサイトには順位改善のヒントだけでなく、店舗運営のヒントに使えるデータが詰まっています。
分断しない俯瞰視点を持ち、プロダクトアウトからマーケットインの発想へ
永山さん:これまで店舗ビジネスの現場では、プロダクトアウト(いいものを作って売る)の意識が強すぎました。「良いものが売れる」が真実なら、世代継承されるものは廃れません。良いものを作る意識は非常に重要です。しかしそれだけでは駄目で、良いものの価値を「必要としている人に伝える」視点が必要ということです。
Googleマイビジネスを活用することで「どういう要望で見られているのか」自覚的になり、マーケットイン(顧客が望むものを作る)の思考も踏まえて取り組むといいでしょう。
検索意図を読み解くのは、上位表示させるためではなく、顧客のコンバージョン(転換)につながる動きを取るためです。目的と手段が逆になっているケースが本当に多いです。
売上に繋がるGoogleマイビジネスの活用は、俯瞰で店舗の姿を捉えて、インサイトの情報をもとに店舗の状況を把握し、魅力が伝わるように実際の営業に生かすことです。それが商売繁盛につながります。

番外編:生きた情報の宝庫「公式ヘルプコミュニティ」の多い質問・使い方の紹介
ー日々アップデートが続くGoogleマイビジネス。そして実際の活用方法は店それぞれによって違います。
生きた情報を手に入れるには、Googleマイビジネス公式ヘルプコミュニティを見るのが一番。Googleマイビジネスオーナーに共通する悩みや最近の話題を聞きました。

ーGoogleマイビジネス公式ヘルプコミュニティでは、どのような質問が多いでしょうか?
永山さん:多いのは「重複をどう解消したらいいか?」「オーナー登録申請したのにハガキが来ない」という質問ですね。
ー重複とは、ローカル検索の結果に同じ施設情報が2つ以上存在している状況、もしくは、自社のGoogleマイビジネス内に同じ施設情報が2つ以上存在している状況ですよね。どのようにお答えしているのでしょうか?
永山さん:実は重複の解消は、Googleのヘルプにあまり言及されていない情報でもあります。Google推奨の報告フォームを通してもいいんですが、店舗が本来メインにしたい側が選ばれない事態が起きたりしています。そうなったときに復旧するのが困難なので、直接サポートデスクをやり取りする方法をおすすめしていますね。
施設情報からの修正提案の場合だと可否は機械的処理、フィードバックからの送信だと作業確約無し・返信無し、サポート窓口だけ有人対応で基本返信ありとなっています。
https://support.google.com/business/gethelp
ー最近増えてきた質問はありますか?
永山さん:「検索しても表示されない」という質問も多いです。表示されない理由は、基本的には時間が解決する仕様です。店舗名はわりと早く反映されますが、ジャンルでの検索の場合、一月以上かかることも多いです。
ただし、若干注意が必要なのは、業種検索キーワードの文字ブレですね。「ヘアサロンM」という店舗があったとき「ヘアサロン」と検索したら表示されても、「美容室」では表示されないケースがあります。先述したローカル検索の精度の問題です。
通常のウェブ検索は、人の動きを読んで、意図したものを表示してくれます。それに比べると、まだローカル検索は未成熟な側面があります。実際に検索してみて引っかからないキーワードは、ウェブサイトやマイビジネスの投稿などを使いGoogleに「こういうビジネスをやっている」と認識してもらわなければ、引っかからない場合もあります。
こうした状況の時には、投稿や自社サイトでの情報発信で文字ブレを含めてしっかり紐付けていくことが重要です。
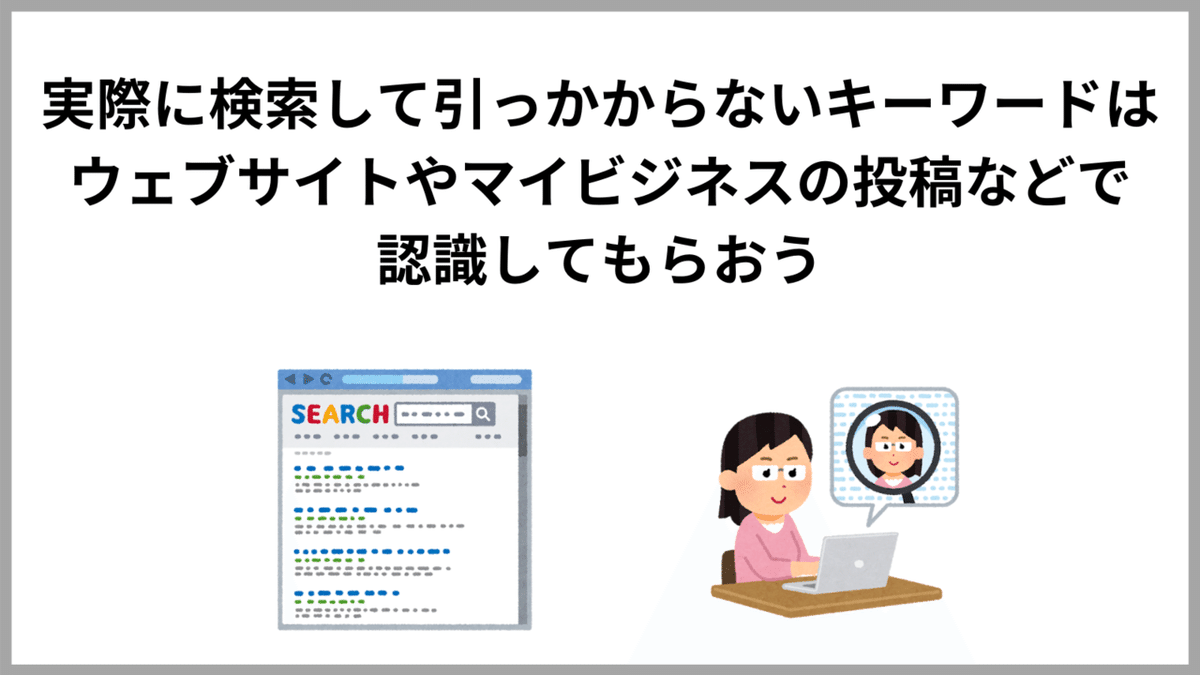
永山さん:「表示されない」問題では「未検索状態で店舗が表示されない」という相談もあります。
ー地図にマーカーが表示されている状態のことですね。たしかに、こうした形で自店を知ってもらいたいオーナーの気持ちはよく分かります。

永山さん:まずGoogleマップの仕様で、未検索状態での店舗表示は確約されていません。そして、検索者の情報・マップの拡大率・周辺の施設の多さ・知名度・インフラ的重要性・関連性などによっても変動するため、必ずしも同じ状況にはなりません。そのため、業種業態、知名度、エリアの状況によっては、出ない店舗・施設はどうしてもあります。
検索していない状態の表示というのは、来店に繋がる要素としては非常に小さいので、ここを気にしすぎる必要はないですね。
ーヘルプコミュニティの使い方で気をつけた方が良いことはありますか?
永山さん:ご相談される際には、一度ヘルプを読んで分からないことや、困っていること、当てはまらないこと、起こっている経緯や状況を詳しく書いていただけると、解決が早くなります。結構、情報が足らない事が多いです。
また、コンサルをしているわけではないので「1から10まで全て教えて欲しい!」とか「効果が出る方法を教えてほしい!」みたいな要望は難しいかもです。先程の話ではないですが、店舗の状況などで正解が違ってくるので、流石にそこまで突っ込んだ回答はできないからです。
ー自分でコミュニティ内の質疑応答を検索することもできますからね。
永山さん:逆に、ヘルプコミュニティに投稿して欲しいのは「不具合情報」です。Googleマイビジネスの不具合は体感的に他のプロダクトより多い印象で、常に何かしらの不具合が発生しています。
(不具合の一例)
・ジャンルと店舗名が逆になる
・商品が登録できない、削除される
・投稿できない
・オーナー登録時にエラーが出る
・クチコミ、クチコミ返信が反映されない、削除される
永山さん:「いつもはできていた」または「ヘルプを読んで正しいはずなのに、なぜかうまくいかない」時は、不具合が発生している可能性が高いです。そうした不具合を蓄積し、吸い上げ、Googleにフィードバックすることで、問題が解消されやすくなります。
相談主以外の利用者にもプラスのことなので「うまくいかない」「仕様かどうか分からない」そんな時にまず来てみて欲しいですね。

ー永山さん、貴重なアドバイスありがとうございました!
取材協力:Googleマイビジネスプラチナプロダクトエキスパート永山卓也さん
これまでのまとめ・過去回紹介
この連載を始めたのは、「Googleマイビジネスを取り組もう」という声は多くても「具体的にどうすればいいのか?」というコンテンツが不足していることがきっかけでした。「世の中に無いなら知っていそうな人に訊こう」「自分で調べよう」と様々なテーマで、これからのGoogleマイビジネスを取り上げてきました。
・第1回:MEO
・第2回:クチコミ
・第3回:クチコミの課題と実践(取材協力:カラビナハート株式会社 吉田さん)
・第4回:接客(取材協力:接客エキスパート 黒ワインさん)
・第5回:Instagram(取材協力:テテマーチ株式会社 福間さん)
・第6回:Twitter(取材協力:ツイッタラーさかかなさん)
・第7回:BotB企業やEC企業での活用
・第8回:Googleマップユーザー(取材協力:GoogleマップゴールドプロダクトエキスパートのJun KOBAYASHIさん)
・第9回:第1〜8回のまとめ
・第10回:Googleローカルガイド (取材協力:GoogleローカルガイドConnect Moderator HiroyukiTakisawaさん)
・第11回:Yahoo!プレイス(取材協力:ヤフー株式会社 鈴木さん・日高さん)
・第12回:MEOの基本の考え方(参考文献:『10年つかえるSEOの基本』)
・第13回:リアルな活用事例(取材協力:株式会社ハタフル 村上さん)
・第14回:Googleマイビジネスの分析と実践(取材協力:Googleマイビジネスプラチナプロダクトエキスパート 永山さん)
「知りたい話題を専門家に聞いてくれた」「ちょうど知りたい話題を深堀してくれた」「情報が濃くて網羅的」などの声をいただくことができたのは、取材にご協力いただいたみなさんのおかげです。この場を借りて、お礼を申し上げます。
今後はいったん休刊し、季刊発行へのリニューアルとローカルマーケティングを取り上げる新企画の準備を始めます。今後も不定期で更新していくつもりなので、マガジンのフォローなどがおすすめです!
それでは、またいつかお会いしましょう。
長谷川 翔一
今週の関連ツイート
先週のプラチナプロダクトエキスパートに続き、新しいゴールドエキスパートも誕生したそうです。おめでとうございます。
Googleより招待いただきまして、#Googleマイビジネス のゴールドプロダクトエキスパートになりした^^
— ババン/馬場勇至 (@bbnyuyu) October 27, 2020
最近はなかなか活動できておりませんが、先輩方を見習って、健全な運用をサポートできるよう精進いたします!
皆さま今後ともよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/WqJDloQ0Mh
無理やりクチコミを削除させようとするのは、おすすめしません。
あんまり話題になってないけど、名古屋の某店舗が以下の流れで炎上してますね
— Masano/マーケティング【WEBマーケティング(SEM・SEO・アクセス解析 etc)がメイン】 (@JM_0716) November 4, 2020
Googleマイビジネスで低評価の口コミ
↓
お店側が内容から顧客を特定してSMSで連絡
↓
初手から弁護士を立てている旨など割と強めの内容を送る
↓
SMSの内容をTikTokで晒されバズる
↓
Googleマイビジネスの口コミ大荒れ
わかります。MEOがわりと浸透しているので、いつも悩んでいます。
MEOという言葉を使う人は2種類いて、MEO対策って言葉使って胡散臭い営業をしている人と、本当はローカルSEOって言い方が正しいのをわかっているけど、MEOって言葉の方が知っている人多いのであえて使っている人。文脈でどうMEOって単語を使っているかでどっち側の人かはわかる場合が多い。 #MEO
— ガク@かどや&コムサポートオフィス(今井学) (@kasumi_gaku) October 28, 2020
気になります…個人的には点数での出し分けは、あまり良い打ち手ではないような。リアルなクチコミより、高評価クチコミを増やそうとする店が増える可能性もあるような。
「○○ おすすめ」で調べると一部キーワードで強制的に評価4以上が最初から表示されるの前からだっただろうか…? pic.twitter.com/IeyvTQ6Dz9
— Manabu Mizukami (@mamizu1128) November 2, 2020
こんなに違うとは…!「どんなお店に見えているのか?」を客観視する重要性。Googleマイビジネスでも同じことが言えるので、店舗オーナー側も、こうした俯瞰視点は持っておいた方が良いと思います。
お店の投稿(左)とUGC(右)なんですけど、UGCから店舗アカウントへ飛んだときに「絶対違うお店」って思って何度も確認したけど、やっぱり同じお店ww どっちがお店の写真かわからないのが最近の現実。。お客さんの方がお洒落なアングルを知ってたりするので、お店の方はUGCもぜひご参考に☺️💐 pic.twitter.com/b6jVREVvA1
— 艸谷(くさたに)真由{インスタグラマー社長「インスタグラムの新しい発信メソッド」の著者。 (@may_ugram) October 29, 2020
ホテル関係はいろいろ変わっていて、担当者さんは本当に大変ですね…。
「最近になって、管理画面を開けたらカテゴリが変わってた!」という宿泊施設様へ
— 今井ひろこ/Hiroko Imai @地方の小さな宿と店の集客をサポート (@Imai_Hiroko) November 1, 2020
宿泊施設で、10月にGoogleマイビジネスのカテゴリが改定されています。それについてブログで解説しています。#GoogleHotelAds#LocalSEO#GoogleHotelCenterhttps://t.co/BcfJV3s3t4
混雑の時間帯が改善されてきているとのこと
Google Maps、マイビジネスのフォーラムでも話題に挙がってた「混雑の時間帯と状況」のお話。
— Tak Nag Lug | Takuya Nagayama (@Tak_Nag_Lug) November 2, 2020
以前は蓄積データで良かったけどコロナ変動で乖離が凄くなった。
少しずつ改善されてる。
Google Japan Blog:Google マップ、混雑する時間帯や現在の混雑状況の舞台裏 https://t.co/lD7JxQPidH @google
日本だと少ない気がしますが、やろうと思えばやれる環境ではあるので注意。権限のリクエストで
海外では"Googleマイビジネスの乗っ取り"が増えています。
— 永露 仁吉🇻🇳ベトナム飲食店出店 (@nikichi_n) November 1, 2020
ダナンのあの有名な日本人経営のハンバーガー屋も被害に遭いました。
例えばクチコミが高く評判の良い店があったとします。
その店がオーナー登録されてない場合、何者かが自分がオーナーであると申請して乗っとるのです。
続↓
実はメッセージ機能、導入したことないのですが、覚えておきます。
Googleマイビジネスのメッセージ機能で、設定済受信端末が無く返信できなかったお話。
— Tak Nag Lug | Takuya Nagayama (@Tak_Nag_Lug) October 29, 2020
他の機能はサーバ保存されてるのでいいんだけど、実はメッセージ受信返信だけ端末の保存。(一応アカウントになってるけど公式的な復元方法が無い)
なので機種変とかで履歴は消える。https://t.co/WMitHRX9tP
この視点、忘れてはいけない…。
GoogleMAPで美容院を調べてると感じたのは、評価が4.7〜5.0が多くて
— まっつん¦大学生 (@5ncz8wts6OvzGNn) October 28, 2020
どれが本当に良いかパッと見じゃあわからなくなってるってこと。MEO対策してるのはわかるけど、ほとんどの店舗がお店でお客さんに口コミを書いてもらっていたら、消費者の視点だと逆にわかりずらいと思う。
今週の関連記事
住所の書き換えが一番多いのは意外でした。1週間で半数以上のGoogleマップ地点で、住所・属性・ビジネス名などのオーナー以外による変更がされているとのこと。保守と表示数の相関性には疑問がありますが、これだけ変動しているという事実がわかる貴重な調査。
リアルな情報を店頭でキャッチアップできると、打ち手の精度はかなり上がりますよね。この記事を読んで、本来の口コミ対策は「高評価を施策で増やし低評価を風評被害対策で削除する」ではなく、「なぜ利用されたかのリアルの声を店頭でリサーチし、低評価になりうる簡単で効果的なポイントをリアルタイムでキャッチし、ミスを減らす」ことなのかなと。
あとがき
「これからのGoogleマイビジネスの話をしよう」第14回を読んでいただき、ありがとうございました。今回で定期連載はいったん終了となります。今後も不定期で更新していくつもりなので、マガジンのフォローなどがおすすめです!
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。いつか、また!
いつもサポートありがとうございます!サウナの後のフルーツ牛乳代か、プロテイン代にします。「まあ頑張れよ」という気持ちで奢ってもらえたら嬉しいです。感謝。