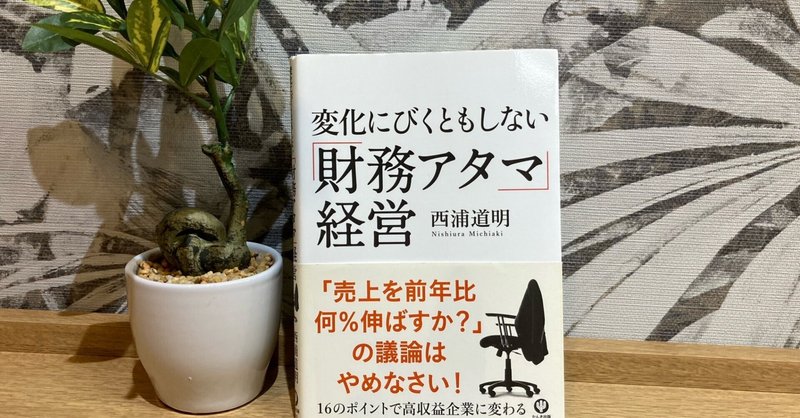
【ミニ社長塾 第19講】数字で経営を語る人が持っている、財務に対する考え方
おつかれさまです。
中小企業診断士で、社長の後継者に【徹底伴走】するコンサルタントの長谷川です。
1月末から2月にかけて社長塾を立て続けに行っています。20期生は少しずつ会社のことが見えてくる段階なのに対し、19期生は自社の将来のための計画づくりに励んでおられます。
(頭の切り替えが大変です……苦笑)
そんな中で先日行われたのが20期生の社長塾で、テーマが「財務」。社長塾を受けられる方のほぼ全員が課題として挙げられる科目です。
社長塾では2日間にわたり合計12時間の講義を受けていただき、徹底的に財務の見方を身につけてもらいました。
その財務をテーマに、今回は『数字で経営を語れる人が持っている、財務に対する考え方』としてお話いたします。決算書がある程度読めるようになってきたからこそ、改めて押さえていただきたい「財務アタマ」の話に関する話もします。
それでは、ミニ社長塾の第19講、スタートです!
1.財務はコミュニケーションツールです
財務を学ぶことには、大きく2つの理由があります。
一つ目は、会社の状況や特徴を把握すること。そして二つ目は、会社の状況や特徴を数字に置き換えて説明をすることです。
稲盛和夫さんの「実学」という書籍に、財務はこのように書かれています。
会計の分野では、複雑そうに見える会社経営の実態を数字によってきわめて単純に表現することによって、その本当の姿を映し出そうとしている。
もし、経営を飛行機の操縦に例えるならば、会計データは経営のコックピットにある計器盤にあらわれる数字に相当する。計器は経営者たる機長に、刻々と変わる機体の高度、速度、姿勢、方向を正確かつ即時に示すことができなくてはならない。そのような計器盤がなければ、今どこを飛んでいるのかわからないわけだから、まともな操縦などできるはずはない。
決算書に表示されている数字をただの数字と見るか、それとも財政面での活動の成果と見るかは、財務をどれくらい理解できているかによるんですね。
また、来期の経営計画を立てるとき、売上目標を前年比何%にするか、といった数字だけの議論になってしまうと、なかなかに達成が難しくなってしまいます……。なぜならば、数字と行動が連動しておらず、最終的には「気合と根性で頑張れ!」というところに着地してしまうからです。
実は、数値計画を立てるときには「後ろから」が鉄則です。具体的には、来期に達成したい(しなければならない)利益目標から逆算して売上目標を定めていく考え方になります。
この時にどのような行動をしていけばよいかを経営者と各責任者とで話し合われるのですが、数字に疎いと「どんぶり勘定」になってしまいます……。そうならないためにも行動計画や戦略を数字で可視化し、ファクトとロジックで詰めていく作業が大事になります。この時に、財務を学んである程度の理解が出来ていれば、数字を共通言語として役立てることが出来るんです。
2.最重要は、付加価値を最大化すること
社長塾では、社長に必須のリーダーシップの一つに財務アタマがあります。財務アタマとは、財務を強く意識して会社を絶対につぶさず伸ばしていく経営思考力、のことを意味します。財務アタマは、次の16項目に分類されてます。

会社を絶対につぶさないという点で、まず意識しないといけないことは手元に残るキャッシュです。そして、キャッシュの源泉は売上ではなく付加価値である、ということも併せて意識してください。
付加価値は自分たちが生み出した価値であり、自社に残るお金だからです。これを最大化することが重要で、数字で経営を語る人はPLだけではなくBSやCFを見ながら、常に付加価値をどう高めていくかを意識しています。
そこで、財務アタマの16項目のうち、特に押さえていただきたいのは次の5項目です。
①高付加価値主義
②値決めの主導権
③戦略経費
⑤ストックビジネス
⑥顧客の分散と多様化
お客様から自社の商品やサービスに対しお金を支払ってもらえるのは、価格に見合う、あるいは価格以上の価値があると認めてくれたからです。そのため、付加価値を高めていかなければ価格を上げることはできず、②値決めの主導権が取れないままになってしまいます。また、価値を高め続けるためには③戦略経費の視点は必ず持ってください。
※戦略経費とは、未来の売上や利益を創るために戦略的に投資する費用のことです。
戦略経費を考える上で注意することは、額でとらえるのではなく率でとらえた方が良い、ということです。額でとらえてしまうと、利益が出ていないときは節約可能費のように使わないという判断が生じてしまいますよね。そうすると、未来の売上や利益を手放してしまうことになりかねませんので、利益が出ているときもそうでないときも一定の率を未来への投資に使うという考え方の方が健全だと思います。
⑤や⑥は経営の安定化を図るためのものですが、どちらもお客様からしっかり価値を評価いただけていなければ難しいです……。そういう意味でも①の高付加価値主義が全ての起点のように、私は思います。
3.財務はスキルなので、やれば身につきます
財務は知っていれば分かるようになる知識ではなくて、やればやるほど分かるスキルだと私は思います。
弊社には多くの税理士や会計士の方々がいますが、彼ら彼女らは資格ホルダーだから財務に長けているわけではありません。毎日朝から晩まで多くの会社の決算書を向かい合っているから、財務に強いのです。つまり、量の問題なんですね。
社長塾での講義では、このことを分かっているからこそ立て続けにケーススタディとして色々な会社の決算書を見ていただきました。そして、そこから読み取れることは何か、を考えるにあたり、財務の型を使って反復練習をしていただきました。
改めてお伝えすると、財務分析のポイントは、大きく次の3つです。
①全体を見て、時系列での推移はどうなのか
②各経営指標は同業他社(業界平均)と比べてどうなのか
③数字の変化の要因や問題点は何かを、指標の意味から深堀りする
この3点を踏まえて、次は自社の決算書をもとに、自社のビジネスの状況を想像するトレーニングを行ってみてください。
一定のルールで経営をしているのであれば、数字に大きく変化はないはずです。それでも変化が見られるならば、どこかに変化が起こっているはずです。この因果関係を掴むことが、数字で経営を語ることに繋がります。是非継続して決算書から自社の状況や特徴を読み取ってください。
今回は、『数字で経営を語れる人が持っている、財務に対する考え方』というテーマでお話ししましたが、いかがでしたでしょうか?
今回の話題が、皆さまの経営にお役立ていただけますと幸いです。
次回の【ミニ社長塾】も、どうぞよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
