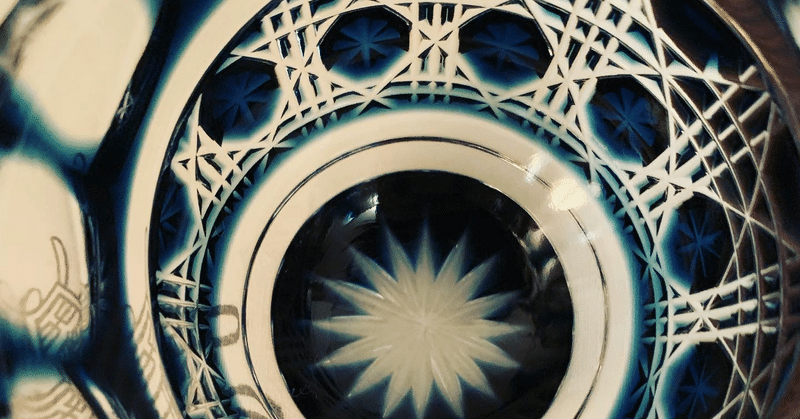
【短編小説】 藍を演じる②
ニ、庚の女
アラフォーのわたしは、しばらく、恋愛というものに縁がなかった。
いわゆる婚活イベントというものが流行っていた時期に、そもそも恋愛が苦手なわたしは、メンタルがついていかず、早々に脱落した。
お見合いもしてみた。大して気が合うわけでもないままなんとなくの流れで婚約のようなところまで流れ着いたとき、相手には失礼だがわたしは虚無感に襲われ逃げ出した。
三十を過ぎて年齢のことで男性に皮肉を言われたり、自分が気にしていたからか、年齢を理由に断られることが続いてなんだか自分には価値がないと刻印を押されたようで悔しくて悲しくて虚しかった。
あるとき、飲み会で知り合ってなんとなくいい感じになった人がいた。
告白をしたわけでもないが、わたしの気持ちがだだ漏れだったのだろう。こういったときの男性のセンサーは敏感なのをわたしは知っている。わたしの気持ちを察した彼はこう言った。
「君はもう33歳だから、今付き合うとすぐ結婚を迫るでしょ?だから僕は君の気持ちに応えることはできないかな。」
『君の気持ちに応えることはできない』、その言葉に胸がえぐられ多様に痛くてベッドに寄りかかって天井をみつめながら激しく泣いた。
しばらくたってから、この言葉の意味について気がついたことがある。
あのときの悲しみは、わたしのなかの魂のような存在が、わたしに無視され続けて悲しんでいる痛みで、気がついて欲しいというメッセージだったのではないかと。
「あんたは見かけも悪くないし、いい子なのになんでこう男に関しては縁がないねえ。どうしてうまくいかないもんかねえ。」
と正直者で心配性の母はぼやき、
「別に焦らなくていい。焦るな、焦るな。」
と呑気なことを言って遠回しに父はわたしを慰めた。
そんな両親も半ば諦めたのか、そのうちわたしの前では結婚に関することは口にしなくなった。
周りの友人が、恋愛、結婚、妊娠、出産、子育て、と、女性の人生のイベントが真っ盛りの三十代の大半を大した恋愛もせずにわたしはフリーで過ごしてきた。
大学を卒業してからずっと同じ会社に勤め、今は現場のマネージャーを任されている。
大好きなブランドの服に囲まれた職場で、人にも恵まれ続けられてきたことに感謝しているし、よくやっていると自分を褒めてあげたい。
それでもそこに後悔がないかといえば、ないわけでもない。
恋愛や結婚や、家族をつくることをすんなり手にしている友人たちに会うのは気が引けたし、そんな日の帰りはぐったりと疲れ、電車のなかで人知れず涙することもあった。
しかし、わたしには何か成し遂げなければならないことがある気がしてならなかった。周りと比べてどんな感情が湧いてこようともその予感だけは消えることはなかった。
だから自分が、何がしたいのかを知りたくなって、興味のあることを片っ端から調べ、学びに行った。そして、ついに四柱推命と出会った。
四柱推命とは、中国で春秋戦国時代の頃に誕生した東洋の占術のひとつで、生年月日と生まれた時間からその人の本質や運勢を紐解いていく。
読み解き方は多面的で複雑で、その学びに終わりはないと言われている。そしてなにより、伝え方にもセンスが問われるのだ。
そんな難解な占術の学びもなぜかわたしにとってはさほど難しくなかった。
まるで脳みその隅っこに占術の知識が眠っていて、それを呼び起こしながら答え合わせをしているようだった。スポンジが水を吸収するように知識を吸収し夢中で学び自分のものにしていった。
わたしは庚の女だ。うちに秘める鋭い直感力と強い信念がわたしを突き動かしていった。
渋谷の駅から少し歩いたところにある神社の近くの国道沿いのカフェを外での鑑定のお気に入りの場所にした。
大きな窓があって、日当たりがよく、横並びでゆったりと過ごすことができる大きなソファがある。
入り口から一番遠い窓際のソファがわたしの特等席だ。
ここでアールグレイのアイスティーを飲みながらだいたい2時間ほどの鑑定をする。
四柱推命を学び始めて数年が経っていたが、わたしは会社勤めと二足の草鞋で占い師を続けた。なぜか占い師を本業にすることには消極的だった。
手を出してはいけない、あまり深入りしてはいけない、本能的にそこに何か言いようのない怖れを感じていた。
続く。。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
