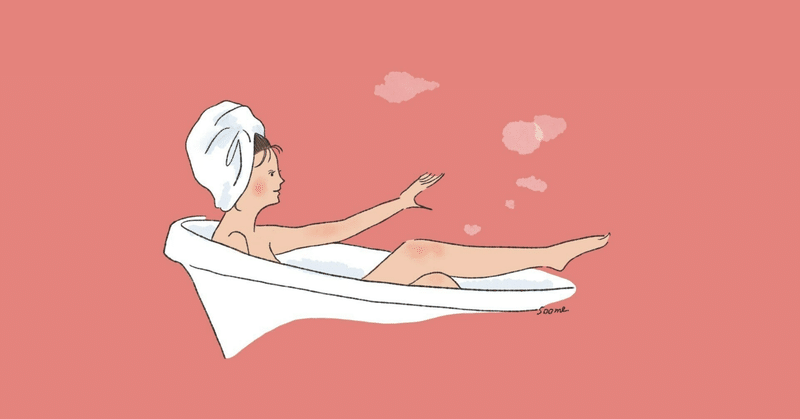
『風の独りごと』
水を撫でる。柔らかな抵抗を指の腹で心地よく感じる。外から差し込む日差しは窓を隔てて、水面に反射して蒼く煌めいて海のようだ。
私は津波を起こして風呂を出た。体をよく拭いてから新しい服を身にまとう。着たての服はひんやりとして清々しい。
髪を乾かした私は台所で朝食の準備にとりかかった。棚の中から取り出した茶筒をとんとんと叩いて茶葉を急須に落とす。その間に沸かしていたお湯がぽくぽくと音で知らせてきたので、火を止めて時間をかけて湯を急須に注ぐ。蓋をして暫く蒸らして湯呑に急須の口を傾けた。薄黄緑色の、真夏の日差しを弱めてくれる青葉のような色をした液体が音もなく急須の口から瑞々しい香りとともに流れ落ちる。そうこうしている間に炊き立てのご飯と出汁から作った味噌汁をお椀に注いで席に着く。そこで昨日つけておいたピクルスがあることを忘れていたので冷蔵庫に取りに戻った。
「いただきます」
合掌してから食事を始める。手を合わせてきちんと言葉にすることで食物に感謝と懺悔を告げる。
それはある日の朝のことだった。何気なく冷蔵庫から取り出した卵を割ってフライパンで目玉焼きを作っている最中、ふと私はとんでもないことをしている衝動に駆られた。毎日卵を産む鶏から人間が勝手に奪い取る。私たちからすれば鶏の卵一つに過ぎないが、親鳥からすれば愛する我が子なのだ。まだ生まれてもいない子を取り上げられるために大事に育てられていると知ったら鶏は卵を産んでくれるだろうか。食物連鎖、弱肉強食のある世界だとは理解しているが、自ら食物を育てるのは人間くらいだと恐ろしくなった。
やや大きめに頬張った口でしっかり咀嚼する。昆布でだしを取った味噌汁は少し口にしただけでうま味が口中に広がって美味しかった。
「ごちそうさまでした」
空になった食器を手にして台所へ向かう。少ない洗い物を終えて机を拭いたら時刻は八時半を回ったところ。
私は水差しと本棚から選んだ文庫本を手に窓近くの椅子へ腰かけた。そして横の鉢植えから伸びている棕櫚竹に水をあげた。せっかくだからと窓を開けるとこの星の息が爽やかに部屋へと入ってくる。
鳥のさえずりに自転車のベルの音、遠くからはどこかで走っている電車の音も聞こえる。私はそっとページをめくるとそれらの音は遥か彼方へと消えてゆく。
気が付いた時には文庫本が手元から離れて床で寂しそうに閉じられていた。胸を張って息を吸うと朝よりも濃密な空気が体内へと流れてゆく。
文庫本を拾いあげて覚えているところにしおりを挟む。時間はあるからまた明日にでも読もう。
外が陽気な天気なので少し散歩することにした。スニーカーの紐をキュッと結び、エコバッグ代わりのトートバッグに財布だけを入れて扉を開けた。
スーパーでの買い物を終えた帰り道、偶然出会ったパン屋さんに足を運んだ。香ばしい空気の中、クロワッサンとナッツのシュネッケンをトレイにのせて会計を済ませる。
家に着いた私は手洗いを済ませて台所でコーヒーを入れ始める。粉末を匙でフィルターに入れるだけで芳醇な香りが鼻孔をくすぐり、そこにお湯を注げばたちまち濃厚になって鼻が驚く。
口に入れたクロワッサンは微かな甘みと程よい柔らかさで、シュネッケンはずっしりと重みがあるにもかかわらずいつの間にか指は空をつまんでいた。
昼食を終えた私は机の上にスケッチブックと絵具を準備した。筆に水を含ませて、余分な水分をスポンジで摂ってから想いのままに無の中に色を塗りだした。実物を描いているわけではない。技法とか色彩のことなど全くわからないが、私は心を躍らせて筆を走らせた。
途中で友達から今日家に行ってもいいかと連絡が入ったので、抽象画製作は適当なところで終わらせた。今日は淡い色や明るい色を使った絵に仕上がった。誰に見られるわけでもないけれど十分に満足した。
友達が来るならと冷蔵庫の中から先ほど買った鶏肉を取り出して唐揚げを作ることにした。軽く下味をつけて白い粉をまとった鶏肉を小麦色の油の中へ入れていく。
顔を上げた先の窓外はすでに紅く染まってはかなく散ろうとしている。私は第二陣を揚げながらプルタブを開けた缶を傾ける。喉仏を動かすたびに程よい苦みと炭酸の清々しさが体の疲れを弾き飛ばしてくれた。
二本目を飲み終わろうとしたところでチャイムが鳴って友達が入ってきた。友達は私がすでに飲んでいることなんて関係ないようで私が渡した缶ビールで乾杯をしてしみる様に流し込む。
それから私たちはビールを片手に唐揚げを頬張りどうでもいい会話で笑いあう。友達は不思議なお題を出す。「春夏秋冬。他にどんな季節があったらうれしい」とか「海の中で暮らしたい、それとも空の上?」。正解はない。私たち自身の答えをだすまででそれ以上もない。だけど面白い。無いことだと分かっていても考えるだけで少し現実に近づきそう。
あれだけ大量に上げた唐揚げは嵐のごとく皿の上から無くなって、お酒もほどほどになったところで友達は帰っていった。
「生きろよ!」と近所から後日苦情が来かねないほどの大声で鼓舞して闇夜に消えた。きっと明日の彼女は終日ベッドの上で過ごすことだろう。
一人になった部屋はやけに広くて自分の部屋なのにどこにいたらいいかわからなくなる。とりあえず二人分の食器を洗ってお風呂に入った。体が温まったあとは寝室の机の前に座って棚から日誌を取り出した。最近は今日あった出来事や感じたことを平均して二ページくらい書いている。日誌を書き出した当初は久しぶりに持つペンに慣れずに落書きの様に汚い字だった。今ではようやく右手が感覚を取り戻してきている。
これは記録ではないので見返すことはほとんどない。ただ文字にすることで改めて自分と言う人間を再確認できるのだ。
頭で思い返して手に伝達した信号が文字となって無の紙につづられる。一行日記が苦手だった十歳の私に教えてあげたい。ついでに今の私の生活を伝えても当時の私はきっと首をかしげるだけで理解はできないだろう。
数えられるくらいのものは失った。お金は以前よりも少ないので外食も控えてお店で見つけた素敵な洋服も今買うべきか悩んでから買うようになった。恋人は触れないように距離を置いてそのまま去ってしまった。
だけど数えられないほど残ったものや守れたものもあった。友達は変わらず接してくれた。私を心配してくれているのを含めて学生の時のままだ。時間は増えたが、その分やってみたいことが生まれた。
朝がうれしくなった。昼が気持ちよくなった。夜が愛おしくなった。
私は時々つまらないことを考えている。ぐるぐるぐる、自分で自分を追い詰めて答えのない闇へ自ら沈殿していく。
でもそれも私だと思うと、沈殿した沼から這い出ることができるようになった。自力の時もあれば上で誰かが手を差し伸べてくれる時もある。
比較するのは馬鹿らしい。どうだと見せびらかすのは稚拙だ。
仕事を辞めたとき誰かに言われた。「いいよね。女性は選択肢があって」。私はその人の名前も顔も思い出せない。
自動で生きることはできるけど、そこには何もない。私は自ら生きたかった。
気が付けば窓外の空は長い夜から目を覚ましていた。体を起こして窓の前に立つ。薄い靄のかかった外はしとしとと濡れていた。
そのままお風呂場に行ってぬるいシャワーを浴びる。頭が軽く後ろに引っ張られて髪を切りたいと思った。
部屋に戻って朝食の準備をする。私はほうじ茶を口にして顔を上げた。それから窓を開けると、私の髪が無造作に跳ねた。
風が今日も私を呼んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
