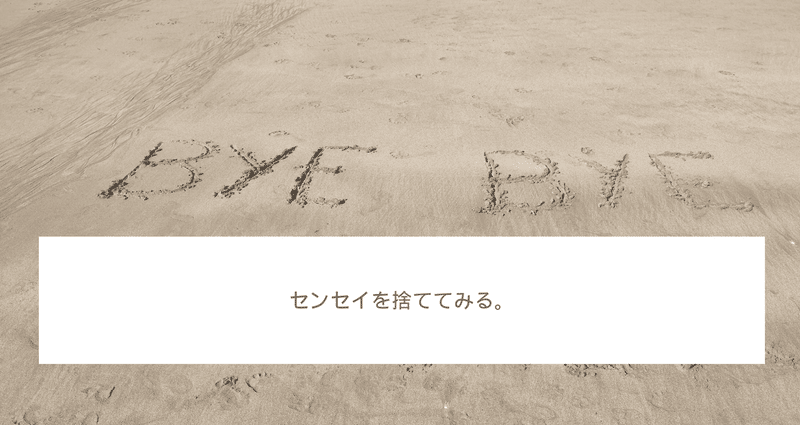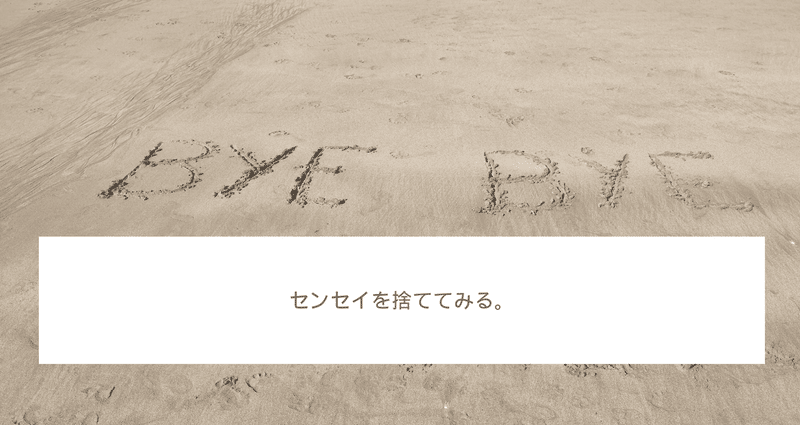学校長に期待すること #センセイを捨ててみる。
校長面談がありました。
「自己評価シート」の記載内容について、意見交換をするためです。
個々の教師が当該校においてやりたいことを書き連ねた紙が、「自己評価シート」です。教師の主要な仕事4項目について1年後のゴールを決め、年度内に2回、進捗状況を報告するといった内容です。
校長面談は、校長のカラーが出るまたとない機会です。
過去に私が受けた校長面談の中に、評価シートに記載した文章(私が書いたもの)を順に読み上げ、個々の目標について「いいですね」とか何の役にも立たないコメン