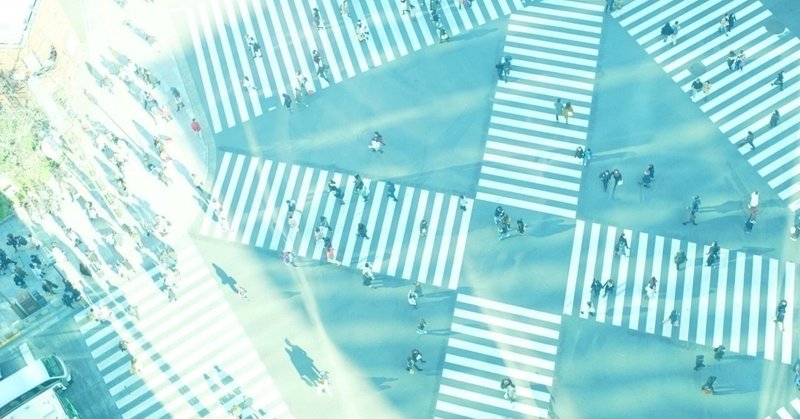
ドキュメンタリーは主張する 映画『A』と『主戦場』
こんなニュースを見た。
映画『主戦場』。慰安婦問題を題材としたこのドキュメンタリーに対し、「中立でない」と出演者らが抗議しているそうだ。
ドキュメンタリーに中立なんてあるのだろうか??
正直、ニュースを見たときに抱いた感想はこれだった。
誰かが題材を選び、取材し、編集する。そこには作り手の意図が絶対に込められる。意識的であれ、無意識的であれ。「中立」なドキュメンタリー、あるいは報道なんてない。「中立」性を求めるなんて無茶な話だと思って読んでいた。
そんな折、2つのドキュメンタリーを観た。
1つは、森達也監督の『A』。1998年に公開された、オウム真理教についてのドキュメンタリー。もう一つは『主戦場』(ミキ・テザキ監督)。
どちらにも、「剥き出しの暴力」が表れている。それは、「オウムの人たちなんて人間じゃない」と言って「あいつらに人権なんてないんだから」と憤る人の姿であったり、「慰安婦の人たちってお金をもらってたんですよ」と、それで問題が解決されるとでもいうように話す人の姿であったりする。もちろん、この二つの問題を全く同列に語ることはできないかもしれない。けれど、断片的な情報で決めつけ他人にレッテルを貼ってしまうことや、あるいは関心を示さないことといった暴力は共通していると感じた。そして、映像を通してそれを見ている私もその暴力と無縁ではないのだと思った。私はふとしたことがきっかけでその暴力に晒されるかもしれないし、自分が加担するかもしれない。あるいは今まで加担してきたのかもしれない(しれない、というより何かしらで加担してきただろう)。
ドキュメンタリーは中立ではない。森達也監督が『A』やその他の著作の中で何度も書いているように、映像には作り手の意図が込められる。
意図が込められるからこそ、映画がプロパガンダとして使われてきた歴史があるのだし、今でも気をつけていないと「感動」など耳障りのいい言葉にのみ込まれて、本当は問題のある考え方を刷り込まれることだって沢山ある。特に映画は、映像や音楽が組み合わさり感情に強く訴えかけてくる。それを利用してプロパガンダにしようと思えばいくらでもできるだろう。
だから観る側は考えないといけない。
『主戦場』を観て、あるいはニュースで「中立性がない」と怒る論客を見て「この人たち何を変なことを言っているのだろう」、と笑うこともできるかもしれないが、なぜそんな考え方が起こりそれが社会で許容されてしまうのか考えないといけない。
森達也監督は「これらの根底にあるのは、剥き出しになった『他者への憎悪』だ。様々に加工され装飾された憎悪が、世論や良識などの衣を纏いながら、メディアや司法や行政、そしてそれらの基盤となる市民社会という共同体の、重要な規範を無自覚にコントロールし始めている」(『A』p.252)と書いていた。
『A』も『主戦場』も、政治やメディアやあらゆるところに食い込んだ「剥き出しの憎悪」を捉えていた。
映画を観る前、私は「保守論客」の発言を笑っていたが、観た後は笑えなかった。こう考えている人が現実にいて、その人たちが学問や政治の場に立つことを許されているのだから。そして「憎悪」は一般社会に食い込んでおり、それを吸って生きている私が「憎悪」と無関係だとは言えない。
ドキュメンタリーは主張する。
大事なのは中立かどうかで争うのではなく、観た自分が考え続けることだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
