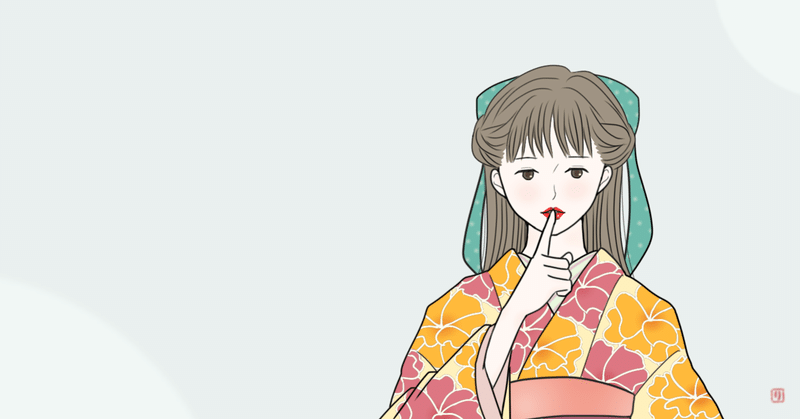
舞台に、花は咲き乱れ(十六)
季節がまた巡った。高校一年間を色分けすると、夏から秋にかけては極めて色濃いため、冬春は手応えのないうちにどこかへ行こうとしてしまう。待って、そう、その袖に掴まりかかるときがあるとすれば、見過ごせない大事なイベントがあるとき。たとえば、今日とか。
いつも以上に身だしなみに気を遣う。鏡の前で念入りに髪型や服装を確認し、でもまだゴーサインが出ない。送り出す側でこれでは、来年はもっと時間がかかるのではないかな――そう思い当たって、ふと心づく。そうか、来年の今頃、あたしは高校を卒業しているのか。そんなのちっとも思い浮かばなかった。まだずっと未来の話だと捉えていた。
そう、今日は卒業式。演劇部員はほかの生徒より早めに登校して、恒例の最後の言葉を聞きに行く。先輩方がなにを語るのか、そして来年あたしは……と、来年のことを今考えても仕方ない。目の前のすべてを目に焼き付けてこよう。
やっと心を含めた準備が整った。短く息を吐いてから、時計を見て慌てた。急がないと遅れてしまう。せっかく髪型をちゃんとしても走ったら乱れるから意味なかった――そんな後悔が脳裏を掠めつつも、とにもかくにも家を出た。
まっすぐ立って駅のホームで電車を待つ。等間隔に置かれた枕木の向こうに目を凝らし、その気配を意識する。あたしを目的地まで連れてゆく箱。やがて来た。
学校が近づいてくると、ちらほらと学生服姿の女生徒たちが現れる。旭山だけじゃなく翡翠ヶ丘の人たちもみな緊張感のある表情をしていて、そうだ、彼女たちも今日が卒業式だと思い出した。千穂さんや――瑞希さん。だんご頭の可憐な瑞希さんの顔が思い浮かぶ。葵さんに想いを伝える場面に出くわしたのは遥か昔のような心地。葵さんはとうにその影を消し、今また瑞希さんも遠くなろうとしている。
校舎を歩いていると、部員ばかりなことに気づく。挨拶をされ、部長扱いされるのも慣れてきたなという実感が湧いてくる。そのまま一緒に空き教室へ。去年ならここで体育座りをして待っていればよかったけれど、今年はあたしが先輩方を迎えに行かなければならない。ミナちゃんと芽瑠だけを伴って、三年生の教室を目指した。
三人揃って言葉数が少なかった。寂しさがじわじわと、真綿に水が染み込むように胸を侵していく。受験で三学期はほとんど会う機会すらなかったから、そのせいかもしれない。すでに彼女たちを対岸に見ている。
紅美子さんと愛さんは希望の大学への進学を決めている。二人とも大学でも演劇に関わるつもりでいるらしい。それぞれの大学で、どんな物語の糸を紡ぐのか。
教室の扉をノックした。――初めて演劇部の活動に参加しようとしたとき、その扉の先にはいのりさんがいた。笑顔で手招きしてくれた。あの瞬間はずっと忘れないだろう。
紅美子さんがいた。彼女もまた笑顔。少し潤んだ瞳と色づいた唇、なんだかいつにも増して美しくて息を飲んだ。奥には愛さんや、ほかの三年生も待ちかねていた。「どうぞ、こちらへ」自然とそんな言葉が出てきた自分に感心する。あたしの熱い部分と落ち着いた部分が別個の人格みたいに喋る。
「花音、部長がんばってるみたいね」
藍葉がいつも教えてくれるよ、と紅美子さんは小声で漏らす。校舎はしんとしているからそれでもちゃんと耳に届く。はい、前を向いたまま頷いた。
「でも、肩に力入れすぎないで、あなたはあなたらしくやってね」
その声はどこまでも優しい。と、愛さんが笑いを押し殺している気配がする。「それ、いのりさんに言われた言葉そのままじゃない」
「いいのよ。素敵なメッセージはまた伝えてあげなくちゃ」
「それじゃあ」二人を振り返って、後ろ歩きしながら答える。「あたしもそれを伝えます」
「今日は朝早くから集まってくれてどうもありがとう、と言うか、おつかれさま。いろいろとお世話になりました。堀愛です。
あたしが演劇部に入ったきっかけは、運命の糸に導かれたからです。最初は雰囲気がよさそうだと選んだ翡翠ヶ丘で、なんの部活に入るのか決めていなくて……それで、演劇部が盛んだって聞くから、見学に行ってみたらすごく魅了されました。ここでなら三年間楽しめるんじゃないかって期待が持てました。そして、その期待は現実のものとなりました。
入ってからさまざまな人との出会いがありました。特に紅美子のことは尊敬してます。いろんなことに気がつくし、大人っぽいって言われるあたしよりも、ずっと大人だなっていつも感じてました。
それから、顧問の相川先生。先生は顧問といっても名ばかりで、部活に顔を出す回数はわずかだったけれど、あたしにはその小さなきっかけで十分でした。――あたしは先生を愛してます。一人の男性として」
心が叫び出しそうだった。脇の下を汗が伝い、あたしはどうしたらいいのか分からなくて、中途半端な姿勢で愛さんを見つめた。しかし、愛さんに目で制される。大丈夫だから、と宥めるみたいに。すでに大丈夫ではない。
「あたしは相川先生と付き合ってます。先生と生徒だからずっと黙ってたけど、今日であたしは卒業だから、これからは公然とお付き合いできます。将来的には結婚するつもりです」
教室内がざわめく。それはそうだ、こんなこと明かされたら誰もが動揺する。ちらりと紅美子さんの表情を確かめると、彼女もまた同じように動揺の色が見える。どうやら知らなかったらしい。ひょっとしたら、この場で知っていたのはあたしだけでは。
ほんとに、最後にとんでもない爆弾を放ってくれる。
「……あー、やっと言えた。すっきりした。秘密の恋は、それはそれでそそられたかもしれないけど、やっぱり隠してるのはつらい。この日を待ってました。あたしは大学に進むけど、先生はこの学校に残るから、みんなよろしくね」
以上、と無理に話を終わらせて愛さんは下がってしまう。室内はざわめきが続いている。この空気をどうしてくれるのかしら。
最後は紅美子さんを残すのみだった。だけど、紅美子さんは困った顔で立ち尽くしている。
「――はあ、まったく。ぜんぜん知らなかった。まさか、としか言えないけど……でも、確かに二人はお似合いかもね。まあ、勝手に幸せになって下さい」
教室内に笑いが起こる。愛さんは悪びれた風もなく艶然と微笑んでいる。
「じゃあ最後に、あたし、刈谷紅美子から。あたしはこの学校を選ぶ段階から、演劇部に入るって決めてました。この中には旭山に行けなくてこっちに来た、って子もけっこういるだろうけど、あたしはここ一択でした。
中学生の頃からお芝居を観るのが好きで、自分も舞台に上がりたい、というより、その現場に関わりたいって心から思ってました。だから一年生のうちから照明とか音響とか、小道具、大道具、衣装なんかに積極的に関われて、とても満足できました。
一方、演じる難しさも知れました。あたしはもちろん初心者だったし、自信はずっとなかったけど、でもやりがいはありました。演じる側に立つことで見えた世界もあったし。
あたしはみんなにとってどんな部長でした? あとでゆっくり聞かせてください。――ほんとうに、三年生一同お世話になり、最後には度肝を抜いてしまいました。みんな、ありがとう。藍葉!」
急に呼ばれた藍葉は、反射的に立ち上がる。「はい!」
「いい子でいるのよ」
「子ども扱いしないでよ!」
また笑いが起きた。紅美子さんの話が終わり、演劇部恒例の名もなき集まりはお開きとなってしまう。愉快なのに、そのことを思い合わせると、途端に寂しさが去来して、涙まじりの笑いになった。
出会った瞬間に、別れまでの道筋が敷かれる。その瞬間はいつもきらきらしている。
●
今年の冬は暖かいそうで、例年より早く桜が鮮やかに咲き誇っていた。こんなに見事に色を付けてしまっては、それが散り、緑色の衣を纏うのもそう遠くないだろう。綺麗だな、と目を細める。毎春この花を目に留めているはずなのに、その度に新しい感動が胸に舞い込むのはどうして。出会いと別れの季節に重なるからかな。
校内が桜色に染まる午後、卒業式が無事に終わり、後輩たちは煉瓦道の左右で卒業生が来るのを待っている。一人ずつ、ゆっくりと講堂から出て歩いてくる。涙に暮れている者もいた。晴れやかな表情をしている者も、後輩に抱きついている者も、ピンと背筋を伸ばしている者もいた。みな、その人にしかなかった高校生活を反芻している。
二つ目のクラスの先頭で、千穂さんが歩を進めてきた。「入江」だから出席番号は早い。わたしとミナちゃんが並んでいるのに気づいて、近づいてきた。
「ご卒業おめでとうございます」
頭を下げる。上手いこと声が揃った。顔を上げると、千穂さんは満面の笑みだった。ほんとうに聖母だ。「ありがとう」
「千穂さん、泣かなかったですね」
「うん。まあ、式は式だし。秋の舞台の終わった後の方が寂しかった」
部長として一年、部を動かしてきた千穂さん。瑞希さんという大きな存在がいる中で、彼女はそれでも部の中心だった。誰にも等しく慕われる先輩だった。
「また、温泉入りに行きますね」
千穂さんは大学へ進学せず、実家の温泉宿で本格的に働き始める。未来の女将としての修業がスタートするのだ。
「七瀬、部長がんばって」
ミナちゃんが首を縦に振る。「はい、がんばります」
ミナちゃんの部長ぶりはだいぶ板についてきた。ここまでは気心の知れた仲間たちとやってこられたけれど、来月には新入部員がどっさり入ってくる。不安は小さくないだろう。わたしももう最高学年になるのだし、できる限り支えてあげよう――とは望むけど、どうかな。どうしても翡翠ヶ丘の脚本にかかりきりになってしまって、旭山にはほとんど顔を出せない気がする。少しでも相談に乗れればいい。
千穂さんが去ってからしばらく経ち、「柳井」だから後方にいた瑞希さんがやっと見えた。ちょうど一年前、部活から遠ざかっていた瑞希さんが、葵さんの言葉もあって再び舞台に立つと誓った。そして、その誓いは果たされた。主演としてその魅力を存分に発揮し、彼女は心残りのない横顔でステージを下りた。
「ご卒業おめでとうございます」
瑞希さんの美しいその面立ちを、心行くまで眺めていたいと思った。化粧が施され、髪も下ろしていた。前髪の下で揺れる両の瞳に吸い込まれそうな心地を覚える。
「ありがとう。二人とも、もう最上級生か。ついこの間出会ったばかりのような気がするのに」
それはわたしも同じだった。葵さんに連れられ演劇部に行き、瑞希さんと近づけたのは山へ登ったときだ。彼女の想いに強く心打たれた。
「瑞希さん、葵さんによろしくお伝えください」
瑞希さんは想い人を追いかけ、同じ大学への進学を決めた。また困ったことにならなければいいが、と思わないではない。だけど、純粋にまた一緒に演技がしたいみたいだから、その願いは叶えてほしい。
「ええ。来年の秋の舞台は一緒に観に来るよ。……もちろん、いのりさんとかも含めて」
そうだ、となにかを思い出したような顔をして、瑞希さんはわたしに耳打ちする。「小百合は想いを伝えないの? 大切な人に」
心臓を掴まれた。返す言葉もなく、ただ目を見つめるだけ。彼女は悪戯っぽい笑みを残して、片手を上げた。その去り方は葵さんと重なった。
「なにを言われたん?」
ミナちゃんが隣で怪訝そうな顔をしている。うん、内緒の話、とお茶を濁しておいた。ミナちゃんはふうん、と呟いて、それ以上追及してこなかった。
瑞希さんは感づいていたのだ。
桜の花びらが散った。新しい芽が吹いた。強い風がいくらか温かみを増してゆく。温泉街は夢や理想を追い求めて去っていった人たちを優しい眼差しで見送り、初心な気持ちで訪れる人たちを寛容な心で受け入れる。
学校は賑やかだった。新入生がやや興奮気味なのもあるけれど、一方で上級生たちも彼女らをいろんな思いを込めて見ている。特に、部活勧誘的な意味で。
「新入生、来てくれるやろか……」
ミナちゃんはため息まじりに呟く。新学期が始まって数日、今日から新入生の部活見学が解禁される。すでに校内での勧誘活動を励行し、後は待つばかり。演劇部はずっと一番人気の部だから、そのプレッシャーはほかの部長とは比較できない。でも、思う。ミナちゃんはストイックなのか、自分を過小評価してしまうきらいがある。わたしには分かる。彼女なら大丈夫だってこと、葵さんや千穂さんと遜色ない器だってこと。
「鈴花も、もう後輩ができるんだね」
傍にいた鈴花にそう声をかけると、彼女は不安げに眉を寄せ、「ほんとですね」と漏らした。こちらもいい先輩になれそうだけど。
「ついこの前、鈴花たちが入部してきた気がすんねんけど、さらにその下がもう来るんやな」
ミナちゃんは講堂の窓からまっすぐ降り注ぐ陽の光に手を伸ばす。ちらちらと影が揺れた。
今年は翡翠ヶ丘に出向く機会が多くなるだろうが、少なくとも初日はミナちゃんと一緒にいたかった。わたしがいても大きな支えにはならないのは知っているけれど、でもこんなに誰かのために動きたいって思えるようになったのは、この数年間の変化だ。わたしは変わった。花音に近づいているかな。
「ミナさんが部長なら、たくさん来ますよ、きっと。わたしも、ミナさんみたいな先輩がいてくれて安心できましたから」
先輩たちはミナちゃんのことを七瀬、と本名で呼んでいたが(葵さんは例外)、後輩たちはわたしらを真似してミナさん、と呼んでいる。部長になってもミナさん。いじらしい鈴花を、現部長は頭を撫でることで応えた。「ありがとう」
そして、鈴花の予言通り、しばらくしてから大勢の新入生が講堂になだれ込んできて、わたしたちは対応に追われた。あんなに不安げにしていたミナちゃんも鈴花も、彼女らが来るとスイッチが入って、機敏に動いていた。急な状況の変化に半ば動揺したわたしなんかとは、演じてきたキャリアが違うのだとつくづく思い知らされたのだった。
◯
差し出された入部届けを両手で受け取りながら、ハーフなのかな、と頭の片隅で考えた。髪も瞳も明るい茶色で、なにより目が醒めるくらいの美少女だった。彼女のわずかな表情の変化を、つい目で捉えようとしてしまう。だけど、どうやら生粋の日本人だと、入部届けを確認して知れる。そこには「村上柊子」と名が記されていた。
「よろしくお願いします」
頭を下げることなくそう言い、妙に落ち着き払った態度であたしからすっと離れた。そんな彼女に、どんな言葉も返せなかった。すっかり魅入られていた。
高校生活三年目の船が出航し、帆に風を受けるようにして、演劇部は順調にスタートを切った。新入部員は例年通り来てくれ、活動も滞りなくこなせている。あたしも少しずつ不安が薄れてきた。
そんな折、柊子は現れた。部活見学には一度も顔を見せず、正式に入部が決まる時期になってから不意に。どこか自信と余裕のありそうな挙措から、お芝居の経験者なのだろうと予想した。
「あの子、劇団に入ってたんだってね」
ある日のお昼休み、教室で昼食をともにしていると、ミナちゃんがふと漏らした。
「あの子、って?」
「ほら、村上柊子。最後に入部した子」
「ああ、すごくかわいかったわね。へえ、じゃあバリバリの経験者なんだ」
「うん、そりゃ『劇団さるすべり』だからね、厳しい指導を受けてきたはず」
ミナちゃんが挙げた劇団名は、舞台だけでなく映画やドラマなんかでもよく目にする、日本有数の劇団だった。
あんなに心惹かれる美少女だというのに、ミナちゃんは珍しく浮かれた様子がまったくない。むしろ、その口ぶりは複雑そうだった。
どうしてそんな大きな劇団にいたというのに、そこから抜けてしまったのか。そして、どうして高校の演劇部なぞに入ろうと思ったのか。気にはなるけれど、ストレートに訊けることではないだろう。それと、もちろん特別扱いするつもりはないが、それでも実力を遺憾なく発揮されれば必ず台頭してくる。そうなったとき、あたしはどうしたら――。
ここのところ、小百合は放課後、ずっと翡翠ヶ丘に来て部員たちを見つめている。基礎トレやエチュードなどに汗を流す一人ひとりをじっと観察し、その個性を焼き付けようとしている。すでに脚本のひな型はできあがっているらしいけど、新入生たちを見て大きく変える可能性もあるという。
あたしは部長として指示を出しながら、一方で自分の演技を探してもいる。これまでの時間はかけがえのない財産だけれど、それに安住していてはあっという間に取り残されてしまう。なにもしないで舞台に立つだなんて、厚かましい真似はできまい。その感情はいのりさんやかさねさん、紅美子さん、愛さんたちを見てきて自然に抱いた。
ミナちゃんと芽瑠はしばしばフォローをしてくれる。ミナちゃんは出会った頃に比べればだいぶ成長したというより、落ち着きを得た。それでも持ち前の明るさは失っていないから、後輩が自然と寄りつく。芽瑠もまた後輩の憧れの的。
藍葉は先輩になってからもいい意味で相変わらずで、その飾らない性格が親しみやすさを抱かせていた。彼女は紅美子さんというお手本を近くでずっと目の当たりにしてきたため、無理に偉ぶる必要はないと感覚的に理解しているのだ。片や、智恵子は――みんなと溶け込むのは、もう少し時間がかかりそうかな。
活動を重ねるたびに、柊子がその存在感をじわじわと増していた。背は高くないのに、どこから出るのかというほど大きなよく透る声を出す。表情が豊かだし、勘がいい。それに、これは彼女だけの魅力が為せる業だろうが、常に目が離せなくなる。その一挙手一投足が気になる。
「あの子、すごいね」
部活帰りの道すがら、小百合がそう言った。あの子、ミナちゃんもそんな風にして彼女を語っていた。「柊子のこと?」
「そういう名前なんだ。なんか、落ち着いてるというか、自分をよく分かってるというか……特に、笑顔が魅力的」
柊子は普段めったに笑わないけれど、演技となると花が咲いたような笑顔を振りまく。その天真爛漫さは彼女が本来持ち合わせているものなのか、それともそうと疑わせず装っているものなのか。
「秋の舞台に立たせようと思うんだ」
あたしの呟きを、小百合は聞こえない振りをした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
