
「子どもの宇宙」を読んだので
きっかけ:教育に関心が沸いたので、心理学の側面からも子どもについて
学びたいと思った。
読んだ日:2021年3月
オススメ:最近、アクティブラーニングや探求学習などの教育方法が重要視
されるなか、その根本的なところには「子どもを信じきれるかど
うか」、「子どもと本気で向き合えるか」といった問があると
私は思います。子どもへの信頼を取り戻したくて、
私はこの本を読みました。教育以前に子どもについて考えたい人
におすすめしたい本です。
※児童文学からの引用も豊富な本です。誰かが河合隼雄は文学者だと称したのが分かりました。ぜひ、興味がある方は、原本を読んでみてください。
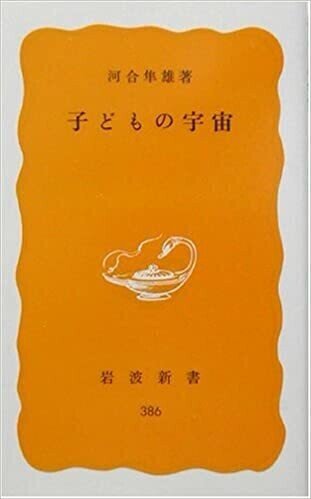
「大人になるということは、子どものときに持っていた素晴らしい宇宙の存在を忘れることではないか?」この問がこの本の全てです。「子どもの宇宙」を体験し、子どもの可能性を思い出すことがこの本の主題と言えるかもしれません。私がこの本を読んで、確かに感じたことは、子どもは深いレベルで物事を考えていて、主張をしているということです。その感想に至った例を幾つかこのnoteでは紹介します。
【家出について】
家出の背景に、子どもの自立への意思、個としての主張が存在していることは、誰でも気づかれることと思う。自分は一人の人間であり、自分なりの主張を持っているのだという気持ちが急激に起こってきて、それを行動によって示すとなると、「家出」ということになるが、外的現実はそれほど、甘くなくて、一人立ちして生きてゆくにしては自分は未だダメであることを思い知らされる。子どもは敗北感のみを味わうことになる。子どもの家出を親に対するひとつのプロテストとして受けとめて、親が子どもに対する自分態度について反省してみる場合は、親子関係の改変が見られ、まさに「雨降って地固まる」ということになる。
「家出」は家の不在を訴えているのである。これは何らかの擬似家族のなかにはいりこむような形になることが多い。擬似家族というのは、大人たちのいう不良集団とか暴力団とか、ともかく異常に濃密なしがらみによって結ばれている集団である。もとの家族内の関係の希薄さを補償するものとして、それはどうしても異常な濃密さを必要とするのである。ある少女の麻薬使用や危ない付き合いを非行と言うのは簡単ですが、この少女の度重なる家出が実は「家を求める」行為であり、擬似家族や擬似オッパイとして、暴力団や覚醒剤が無意識のうちに選ばれていることを、われわれは理解しなくてはならない。
【秘密の扱い方】
ある五歳の女の子が、痴漢に襲われそうになり、大変な恐ろしい感情体験をした。しかし、彼女はこのことを誰にも話さなかった。母親には話そうとしたのだが、どうしても言うことができなかった。成長するにつれ、心のなかに強いわだかまりを作り出した。遂に耐えられなくなった彼女は今まで秘密にしていた幼児期の体験を母親に思い切って打ち明けた。母親から返ってきたのは、「その年になって、今更何を言っているの」という冷たい言葉と嘲笑だけであった。彼女は母親の嘲笑に接して、自分が世界から切り離されていると感じた。しばらくして、彼女は自らの命を絶った。母親の何気ない拒否は、娘にとって世界からの拒否とさえ受けとめられ、それは死を促した。この女性にとって、痴漢に襲われたことは、人生の恐ろしさ、不可解さ、それら全てを凝集した体験であったのである。それは簡単に言語化できるものではなかった。
秘密をいつ、誰に、どのように打ち明けるかは極めて重要なことです。秘密を打ち明け、それを共有してゆこうとするとき、それに伴う苦しみや悲しみの感情も共にしてゆく覚悟がないと、なかなかうまくはゆかないものである。
【あちらの世界の存在】
児童文学にはあちらの世界がよく登場する。例えば、ナルニア国物語では、家のタンスを通り抜けるとあちらの世界(ナルニア国)が登場する。あちらの世界に至る「通路」の存在は、多くの示唆を与える。こちらの日常の世界はあちらの世界によって裏打ちされている。しかしながら、大人ばかりが現在では子どもたちまで忙しく(大人によって忙しくさせられてと言うべきだろうか)、あちらの世界との接触が絶たれ、そこに多くの問題が生じてきている。教育学者の蜂屋慶は、こちらの世界を「技術の世界」、あちらの世界を「超越の世界」として把え、近代教育の盲点の一つは、子どもに技術を身につけさせること、技術を教えることに熱中し、超越の世界の存在を忘れていることにあると指摘している。「技術の世界に住む人間は’よく’(目的)をどれほど達成したかによって測られる。子どもは、学校の成績によって測られる、上位の子ども、下位の子ども、と相対的に分けられる。子どもを相対的にとらえることが教育の基本になる。’ひとりひとりの子どもを大切に’と絶対的にとらえることを強調しても、超越の世界を無視しているために、その声は空虚である。」と蜂屋は述べている。蜂屋はまた、教師が絶対の世界に触れることによって、子どもの「性質や力量の差を超えてどの子どもも絶対的超越の世界の現れとなる、かけがえのない尊さをもつものとして子どもに接することになる」と述べている。
しかし、ここで重要なことは超越の世界にのみ心を奪われてしまうと、命を失うほどの危険が生じることである(例:浦島太郎)。それ故にこそ、上野の言う「通路」が必要となるのである。子どもに愛情を持って接するのは疑う余地のないことだが、大切なことは、われわれがその愛情を流しこむ「通路」をもっているか?、ということである。成績評価という「通路」のみで、子どもを一様に1から5に配列して、「ひとりひとりかけがえがない」などと言っていても、子どもたちはちゃんとその本質を見抜いているのである。「通路」をすぐに見いだせない、そんな時は慌てずに待つことが重要である。大人が子どもの魂に至る「通路」を知りたい、と思うとき、焦るのが一番禁物である。その子を暖かい目で見守っていると、魂の方から通路が開けてくる。
【裏切られる経験】
児童文学には、両親のもとを離れることにより話が始まることがある。石井桃子の『ノンちゃん雲に乗る』を例にとると、ノンちゃんは家族の裏切りに抗議して-家の近くではあるにしろ-家を出たのである。このことによって、ノンちゃんはこの世の時空を超えた世界を体験するのである。ノンちゃんにとって「裏切られた」ことが、「通路」となったということができる。確かに裏切りの体験は「通路」となりやすい。これまでのところ、ノンちゃんにとってお母さんは絶対的な存在だった。この世の何らかの存在を「絶対的」と思うことは素晴らしい。しかし、「絶対的」なことは必ずどこかで裏切りに会わねばならない。この世のものには、そもそも、絶対なんていうものはないのだから、これは致し方のないことである。そのとき、両者の間のこの世の絆が-絶対でないにしろ-どれほど強いものであったか、裏切り、裏切られた人がどれほど超越へ開いた心をもつか、などによって、裏切りは意味深い「通路」へと変化する。しかし、このような条件がうまく整わぬとき、裏切りは転落への「通路」として機能する。そこには、上野瞭の指摘した、意味のある往復運動が生じないのである。
【死の問題と子ども】
子どもは思いのほか死について考えている。
最近、コロナの影響で子どもの自殺者が増えているということですが、それに示唆を与える内容が書いてあったので紹介させていただきます。鎌倉時代の名僧、明恵上人が十三歳で自殺をしようとし、そのとき、「今は早十三歳に成りぬ。既に年老いたり」という言葉を残しているらしいです。ここで注目したいのは、十三歳で年老いたと感じるところです。思春期は「さなぎ」の時代だと作者(河合 隼雄)は述べていますが、思春期が訪れる一歩手前で、それは言うなれば毛虫としては老境にはいるわけだから、「年老いたり」と感じても別に不思議ではないと言える。実際、子どもたちをよく観察していると、「性」の衝動が動きはじめ、それと取り組むことによって大きい変化が生じる以前に、子どもとしての「完成」に達するように思われるときがある。子どもとしては、高い完成感と、早晩それが壊される、あるいは、汚されるだろうという予感が生じてきて、その完成を守るために自殺をするなどということもあるのではないか、と思われる。このようなとき、子どもの存在は限りなく透明度を増し、その子にとっては大人たちのすることなすことが汚らわしく、うとましく感じられるのではないだろうか。現在においても、十二、三歳の子どの自殺で、原因が不可解として報じられるもののなかには、このようなのが混じっているのではないかと推察される。自殺には多くの要因が重なっているし、また単純に原因と結果などという考えで割切れるものではない。ここに述べたことも、それが原因でなどというのではなく、子どもの自殺にむしろ、常識的には不可解な点が多く含まれていることを示そうとしたのである。
死は実に多くの疑問を人間に投げかけ、人間が生きることの意味の深化を求めてやまないものがある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

