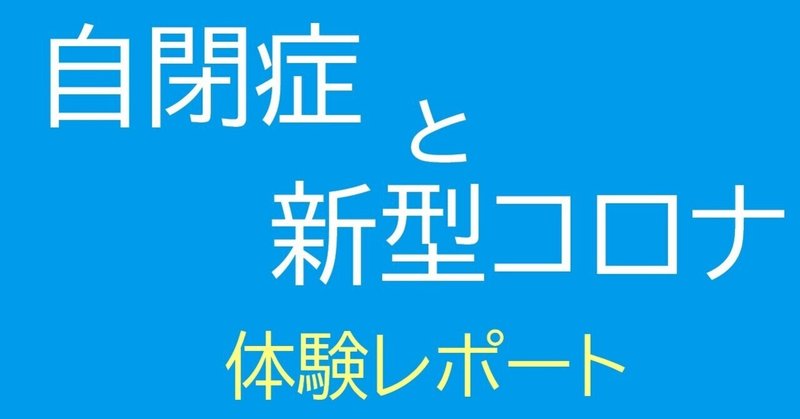
自閉症の子どもと新型コロナ感染について#1
webライター、はらのです。
私は現在、自閉症と知的障がいのある小学生の甥と同居しています。
その甥から母親である姉、父、義兄と次々に陽性判定されました。
本記事ではどのような経緯で感染し、感染後どのように対応しているのかをまとめています。
障がい児のいるご家庭も、そうでない方も、この体験談を通して少しでも不安が緩和されていくことを願います。
▼関連記事
▼新型コロナウイルスに関する各情報へのリンク
このレポートの主旨
新型コロナウイルスの一番恐ろしいところは「分からないこと」だと考えています。
感染率の高さ、重症率、後遺症などの要因も挙げられますが、どのような状況、条件でそれらが起こるのかのメカニズムは解明され切っていません。
分からないことだらけのコロナ禍において、誰かの体験談で心が落ち着くこともあるでしょう。
また、何かの対策の役に立つこともあるかもしれません。
withコロナへ向かいつつある中、どのようにして新型コロナと向き合えばいいのかの一助になればと考え、体験談として綴っていきたいと思います。
家族構成
最初に家族構成を。
両親、姉夫婦+甥、私、弟です。
自閉症や障がいを持つ家庭に多い家族構成ですが、下二人がいわゆる「こどおば・こどおじ」なのはちょっと珍しいかもしれません。
障がいを持っているのは甥ですが、基礎疾病持ちは母です。
基礎疾病持ちの親との同居と、自閉症の孫との同居の合わせ技みたいなもんですね。
濃厚接触者までの経緯
利用している放課後デイサービスでのクラスター発生を受けて、濃厚接触者判明からPCR検査に至ります。
放課後デイサービスとは、「放課後」「デイサービス」とあるように、子供向けのデイサービスです。
PCR検査時系列
8/20
・姉発熱
・放デからの連絡により甥の濃厚接触者判明
・保健所に連絡
・甥の翌日のPCR検査予約
※この時点で姉のPCR検査は断られる
8/21
・甥の陽性判明
・付き添いの姉、父のPCR検査
・姉、父の陽性判明
8/23
・義兄、母、私、弟でPCR検査
・義兄の陽性判明
地域差もあるかとは思いますが、PCR検査まで迅速に行われました。
クラスター発生源の放課後デイサービスが動いてくれていたから、というのもあるかもしれません。
PCR検査について
▼通常のPCR検査
甥は自閉症ということで、かかりつけ医と保健所に相談し、かかりつけの医院でPCR検査を行いました。
PCR検査の方法も鼻の粘液を採取するスタンダードな手法だったようです。
自閉症は人や場所に強いこだわりを見せることがあり、慣れている「いつもの先生」にお願い出来たのは幸いでした。
▼ドライブスルーPCR検査
一方私たちは、保健所指定の総合病院の駐車場で、ドライブスルーPCR検査を行いました。
ドライブスルーPCR検査ということで、車外から鼻の粘液を採取する方法を想像していましたが、実際は唾液採取でした。
唾液を染みこませたコットンを検査キットの中に戻したら、駐車場の出口で係員さんに手渡すという流れです。
いつ頃検査結果が出るのかと、体調管理シートと陰性の場合の過ごし方の紙を渡されて終了です。
複数人同乗して検査を受けた場合、代表者一名に連絡があります。
PCR検査の費用
濃厚接触者が新型コロナウイルスの疑いでPCR検査を行う際、1回目は無料で検査を受けられます。
しかし陰性者が自宅待機期間中に体調不良に陥って、二度目のPCR検査を行う際には自費となります。
因みにウイルスの株はランダムな検体を選んで調べるそうで、陽性の連絡時に自分がどの株に感染したのかまでは分かりません。
保健所の方は、現在調査する検体はほぼ変異種だとおっしゃっていました。
療養場所の協議
陽性者は保健所と医師が協議し、入院か自宅療養かが決定されます。
どのように過ごせばよいのか、一人一人に電話で説明がされました。
我が家の場合、父、義兄、姉、甥の全員が自宅療養です。
新型コロナウイルスは「急激な重症化」が非常に警戒されていますので、毎日一回保健所から体調確認の電話がかかってきます。
感染ルートと行動履歴の確認
陽性者はどのルートから感染したのか、ウイルスを保有した後どのような行動を取ったかの確認がなされます。
我が家の場合明確に放デからの家庭内感染だと分かったため、細かい追跡はありませんでした。
陽性判明直後は保健所をはじめ、勤め先などと頻繁に連絡を取り合うため地味に負担が大きい所だと思います。
陽性者の症状によっては陰性の同居者が対応することもあり、陽性者、陰性者共に忙しかったです。
療養期間
陽性者:発症から10日間。
陰性者:陽性者との接触を断ってから14日間。
陽性者は当然外出出来ません。
陰性者(濃厚接触者)は、食料の購入など必要な時のみ外出が許されています。
家庭内での住み分け
我が家の場合、陽性者は2部屋に分かれて過ごしています。
寝室1:父、姉、甥
寝室2:義兄
▼食事
各部屋に母、私のどちらかが持っていきます。
部屋の前に食事を置き、食事が済んだら部屋の前に食器を置く。
紙容器も利用していましたが、人数が多いため消費が激しく、紙コップ以外通常の食器に戻しました。
▼トイレ
陽性者、陰性者どちらも消毒をしながら使用しています。
トイレトレーニング中だった甥は、臨時的におむつに戻しているようです。
▼お風呂
陰性者が先に、陽性者が後に、という指導を保健所より受けました。
トイレとお風呂、どちらにも窓がありますので雨の時以外は常時開けて換気しています。
子どもの移動対策
自閉症のような、コミュニケーションが苦手な子どもに「言って聞かせる」ことは非常に困難です。
そのため、我が家では強硬手段を取りました。
父や姉は外せるけど、甥は外せないという状態でつっかえ棒をしています。
じっとしているのが苦手で、部屋から出たがる子どもにはとても有効です。
隔離生活が始まって2、3日すると、つっかえ棒が外れていても無理に部屋の外に出ようとはしなくなったそうです。
ママがずっと同じ部屋にいる、というのも大きいのではないかと思います。
しかし外出欲は無くなりませんから、上手く家庭内でやり繰りしていく必要があります。
自閉症児に限らず、小さなお子さんがいるご家庭ではここが一番大変な所と言っても過言ではありません。
やはり感染防止が第一
変異株の感染力は非常に驚異的です。
甥が濃厚接触者認定されてからわずか1日で、次々に陽性になっていきました。
しかし困ったことに、現在12歳未満のワクチン接種は行われていません。
感染した子どもが発症しても困りますが、無症状だと更に感染を広げることになります。
また居住地区や世代によっては予約が取れない、開始されていない状況です。
子どもの感染が拡大している今だからこそ、感染防止を第一に行動していきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
