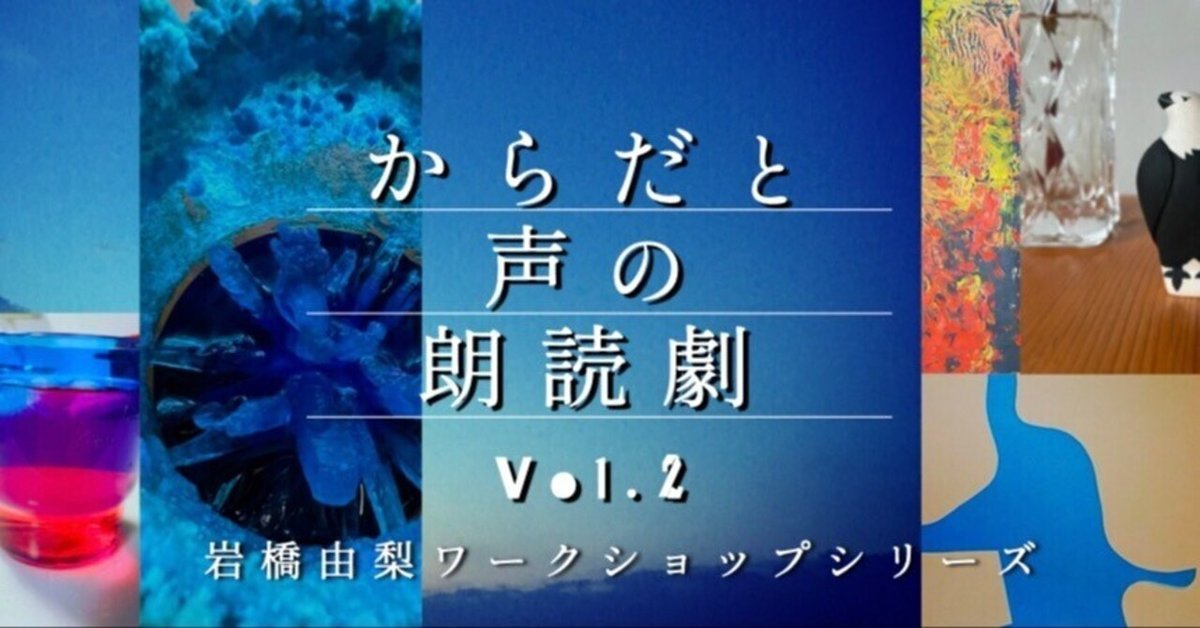
からだと声の朗読劇vol.2
22年6月から月に一度行っていたワークショップ「からだと声の朗読劇vol.1」が10月の発表会をもって無事に終了しました。
前回はテキストとの距離感を自分で試しながら読んでいただくことをメインに行いました。
複数で読むということよりも、むしろ個人作業にメインを置きました。
23年1月から、新たに「からだと声の朗読劇vol2」が始まりました。
おかげさまで定員を増やしての満員御礼!
前にも参加された方と、初めて参加される方との出会いです。
最初はこの場にどんな人がいるか、場を持っている私はどんな人か
自分は何を言えばいいのか、何をすればいいのか、誰もわかりません。
それでも、目の前の人とほんのひと時、共に場を体験します。
日常生活の中では、その方の社会的なプロフィールが必要かもしれませんが、ここではあまりそのことは重要視しません。
それよりも身体を普段とは違う意識で使ったことで何を感じたか、などを共有していく時間を重ねていきます。
不思議なのですが、同じことを経験しているのに、皆さんお1人ずつそこから受け取る感覚が微妙に違います。
今回も、「さわる」ではなく、「ふれる」ことをテーマに物に触れたり、人にふれたりしてみてくださいとオーダーしました。時節柄、人に直接触れるのではなく、気配を感じられるようにと提案したのですが、これがまた人によってさまざまな感想をいただきました。
「『さわる』と思うのと『ふれる』と思うのとではものとの接し方が違う」
「ふれてないのに、人の温かみを感じる」「植物と人工物では、明らかに違うということをあらためて感じる」「後半は一人一人ではなく、一個の生命体のようなものを感じて動いていた」など。
一人一人がどんなことを感受していたのかを共有することで、自分が意識していなかった部分も開かれていきます。
第1回目最初のテキストは、とあるミュージシャン同士の対談を読んでいただきました。
最近わたしは対談を声に出して読んでもらうことに少しハマっています。
実際に朗読する人の実感が声に現れるので、どんな読み方をするかで、変化します。戯曲を読むことと少し似ているところがあると思うのです。
今回は、4つの対談を用意しました。参加者を4グループに分けて、それぞれ1つずつ担当してもらいます。
この対談は、実際に対面で語り合ったことを文字に起こして記したものでです。多少編纂されているかもしれませんが、基本はあいづちや笑いなどの表記もあります。
その対談の一部を抜粋し、距離感や身体の向き、立ち位置を試してもらいながらで模索していただき、最後はそれを皆の前で発表することをお願いしました。
これが、まあ、本当におもしろい時間でした。
繰り返し読むうちに2人の関係性がどんどん変化していくのです。
実はこのテキスト、4つの対談のインタビュアーである聴き手はすべて同じ人で、語り手は4人とも違います。音楽キャリアが長いベテランの人や、性別の違う人などさまざまな立場の人がいます。
それぞれの人が歌詞を書くことやメロディーをつけることについての言葉のこだわり、音のこだわりを話しています。
私にとっては何度読んでも魅力的なテキストなのですが、今回それらを声に出してみなさんに読んでいただくことで、自分で黙読して楽しんでいたこととは違う体験が起こりました。
書かれていることは同じなのに、声に出されると、そうだったのか!と発見することがとても多かったのです。
ベテランの作詞家の方のインタビューを朗読してもらった時です。
1人で黙読してる時には、ふんふんそうなのかとただ納得するだけでしたが、声に出して読んでもらうと、作詞家の方に自分はこれだけのことをやってきたんだよ、とキャリアを語りながらベテラン感というものが溢れ出ていました。すると声に出しながら鼻を上に向けて、どんどん身体を大きく開いていくのです。後で聞くと声に出して読めば読むほど、どんどんそうなっていったのだそうです。そして聞き手であるインタビュアーのほうはどんどん奥へ引っ込んでいく感じでした。
声に出したからこそ、言葉に引っ張られて2人の身体や立ち位置が変化していったのですよね。これは面白いと思いました。
もしもこのベテラン感がたっぷりある言葉を、前屈みで首を突き出し、小声で常に語尾が下がっていくような読み方をすれば、言葉はまた変化して聞こえたのでしょうか?
試してみたいです!
さて、2回目はどうなるか・・・。
実験してみたい文章はたくさんあります!
つづく
