
清水典子歌集『貫流』
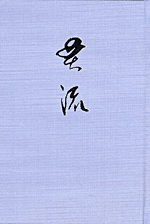
貫流
足音にうわつと飛びたつ群雀黄金稲穂の微光をひきて
原生林の走り根の苔ひくひくと脈うちわが手押し返しくる
さやさやと雪野をくだる堰の水躍る煌めき無尽にのせて
開山の遺徳をしのぶ坐禅石木洩れ陽さははさはさは揺るる
関係の書類を破棄しきつぱりとくちなし匂ふ庭におりたつ
露天風呂にすつぽり浸り根元より裸木ゆさぶる風を見てゐる
背後よりふんはり肩掛けかけくるる鍬胼胝厚き大き掌
栄光は前途にあると思ひつつ厨に玉葱きちきち刻む
笑まひつつ吾に這ひくるみどりごの重さどつしり抱きしめにけり
夕茜くづし野川にじやぶじやぶと鍬洗ふ葱がはげしく臭ふ
卒寿過ぎ二人の時惜し命惜し時よゆるゆる流れゆけかし
水口をあけて夕映え流し込む 穂孕む稲がほんのり匂ふ
跋 文
昭和二十四年に同郷の先輩歌人白倉三郎氏の紹介により「覇王樹」に入社されてから六十八年、結社一番のベテラン歌人となられた清水典子氏だが、今なお鮮新な作品を発表し続けている。九十三歳になられる氏には、すでに第一歌集『伏流』および第二歌集『湧水』があるが、第二歌集上梓後も家庭と人の縁、そして自然と農を詠い続けている。その短歌姿勢は謙虚で、折々私のような者にまで「こんな作品を作ったがどう思うか見てくれ」などと声を掛けてくれるのである。そのつど勉強させてもらってはいるものの、最近私の周辺で高齢ながら意欲的に歌集上梓を目論む人たちがいて、これはひとつ清水氏にも勧めてみようと、半ば強引に出版の誘いをさせてもらったものである。(中略)
こうして第三歌集『貫流』に辿り着く。あえて得意とする叙景歌掲出を意識しなかったが、とも角この歌集は読んで頂いたほうがその良さがわかるものと、私はあえて皮相な印象を加えないことにした。清水氏の歌は読めばわかる。そしてじわりじわりにじみ出る「愛」を感じずにはおれないのである。終戦直後の初手からほぼ完成されているこん日の清水短歌に、もし後年の作品につけ加えるものがあるとすれば、それは独自のオノマトぺの駆使であろう。オノマトペの利いた清水短歌、その妙味を是非多くの読者に味わって頂くことを願って、その珠玉の作品の一端を最後に紹介し、拙い跋文の筆を擱くことにする。
平成二十九年五月吉日 橋本 俊明 (覇王樹同人)
