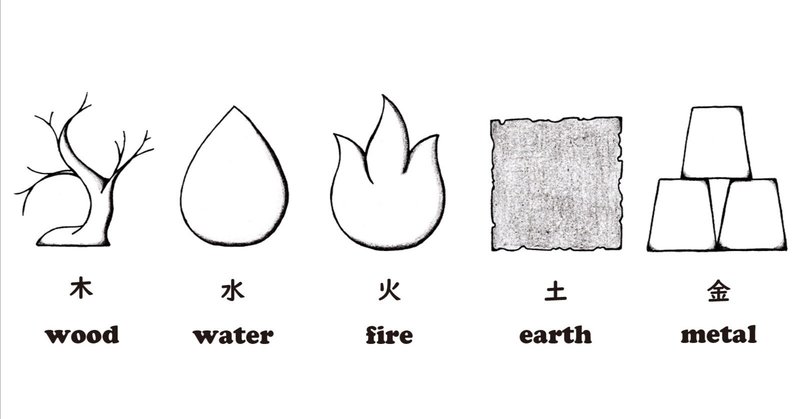
わかりやすい!中医学の基礎Vo.5
日本で漢方薬が広まるまで
現在、日本で使われている漢方薬の起源は、古代中国にあります。
当時最先端であった中国の思想や医学を積極的に取り入れ、日本の風土、気候などにあわせて独特の医学(漢方)が生まれました。
『気』『血』『水』の概念を学んだところで、漢方薬の歴史についてふれてみましょう。
漢方薬の歴史
漢方薬の歴史は古く、今から1800年ほど前に張仲景(ちょうちゅうけい)が記した「傷寒論」が、漢方薬が掲載されている書物の最も古いものとされています。
漢方薬はあまり詳しくなくてもほとんどの方が名前くらいは聞いたことがある「葛根湯」も、この傷寒論に記載されています。
はるか昔に発見され、時を経て受け継がれてきた漢方薬は、現在でも人々の健康に役立つものとして利用されているのです。
この時代に編纂され、現代の漢方治療・漢方処方に影響を与えている古典(中国の古い書物)は次の3つがあり、それぞれ表のような特徴があります。

日本での漢方医学の誕生
これらの古典は、本場中国でも医療体制や治療法に大きな影響を与え、中国伝統医学として様々な治療法や医療体制を築く礎となりました。
当時は、医療体制や治療法は、中国の方がはるかに進んでいたため、中国で使われている方法を積極的に取り入れていました。
飛鳥時代には、中国の伝統医学を取り入れ、「典薬寮」と言われる、宮廷官人の医療や医療関係者の養成・薬園などの管理を行った機関が設置されています。
奈良の正倉院には当時の生薬が保存されています
また、当時中国からもたらされた生薬(オンジ・ニンジン・ダイオウなどの60種類の生薬が、正倉院に伝わる「種々薬帳(しゅしゅやくちょう)」に記載されておりこのうち40種類の生薬は現存しています。
平安時代、貴族を治療した中国伝統医学
平安時代に入り、日本に取り入れられた中国の伝統医学を元に、日本で最初の医学書「医心方」が丹波康頼によって編纂されます。(丹波康頼は、中国皇帝の子孫で日本に帰化した人物です)
この頃は、漢方医学はまだ貴族だけのもので、一般庶民には普及していませんでした。
僧侶により民衆に広まった漢方
鎌倉時代入り、僧侶が中心となって漢方医学を民衆に伝えたとされています。
日本独自の医療である日本漢方が本格的に学問として体系化され、民間でも治療に使われ出したのは鎌倉・室町時代に入ってからで、江戸時代に入り、学問として広く普及させるために医学校の設立や医学書の出版が活発になりました。
それと同時に、漢方を使う上での考え方が異なる様々な学派が発生し、統一性が無くなりました。
西洋医学の普及で、出遅れた漢方医学
漢方薬を使用する上で、様々な意見があり統一性が無いため治療法としての確立が難しく、漢方薬の普及が広まらない中、明治に入り、西洋医学中心の新しい医学教育を確立し、医療の開業許可制度(医師免許制度)が制度化されました。
それまでは自分が医者だと名乗れば治療ができ、言わば誰でも医者になれた時代でした。
この制度化により、勉強して試験を受け、免許を取得しなければ医者になれず、医師は高度な技術職となったのです。
漢方薬を主体にして治療をしていた人々は、漢方医療を存続させようとしますが、明治政府はこれを否定し、漢方薬を使って治療を行うことは、実質的に医療ではないとされてしまいました。
事実上否定された漢方医学は、一部の医師や薬局の薬剤師、薬種商などが細々と伝え、また本として出版されて残されているだけだったのです。
昭和に入り、漢方薬が保険適応に!
昭和に入り、漢方医学の素晴らしさを伝えるべく数名の医師が主導し学会を作ったり、また西洋薬での副作用被害が相次いだことも追い風となり、日本で独自に発展を遂げた漢方医学が再び注目されました。
1976年、医療用医薬品として漢方薬が薬価収載され保険が適応され医師が処方できる薬となり、現在では広く使用されるようになっています。
このように、中国の伝統医学を元に、日本で独自の発展を遂げてきたのが現在使われている漢方医療・漢方薬なのです。
現在、日本で使用できる漢方薬の種類は、医療用として148種類、一般用(ドラックストアや薬局で購入できるもの)は294種類ですが、本場中国では、何千種類もの方剤があると言われています。
日本では、漢方薬を扱う際の考え方が異なる流派があり、中医学もその流派の一つです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
