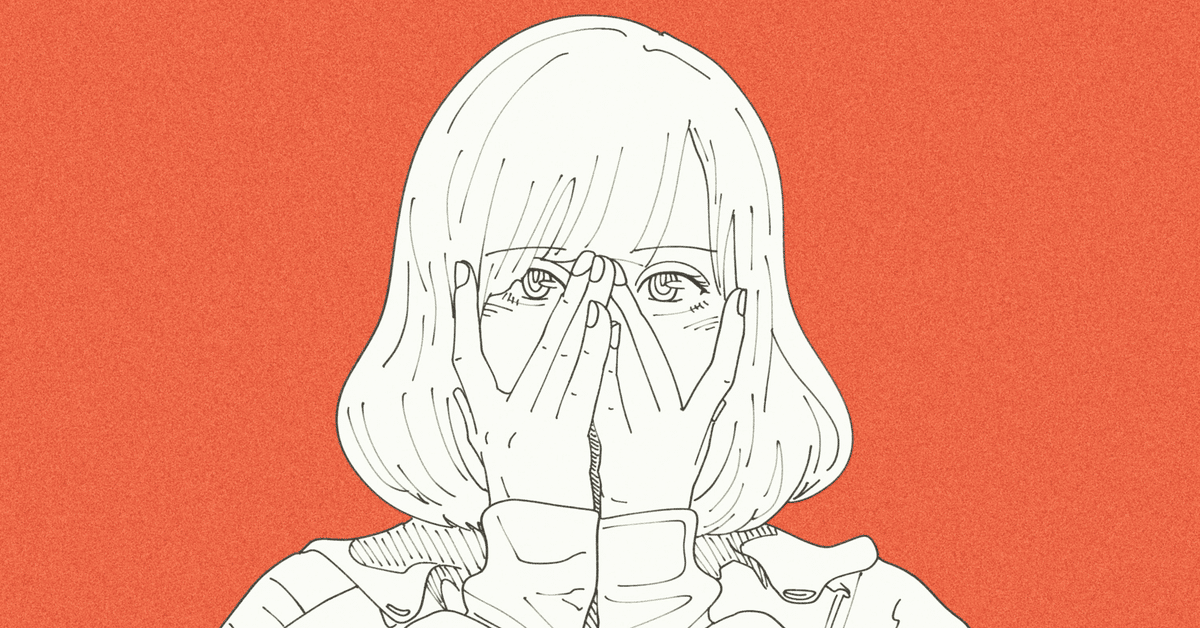
ピンクのキープS
私の頭に、変なものが生えてきた。
にょきにょきにょきにょき、生えてきた。
あなたの頭にも、あるかもよ。
「ん? なに?」
それに気づいたのは、本日は晴天なりって繰り返し言いたくなるような、カーテンから元気いっぱいの太陽光が入ってくる朝だった。
鎖骨あたりまで伸びた私の髪は、朝起きるとぐちゃぐちゃに絡まっているから、毎朝、洗面所を占領して髪を丁寧にとかす。その朝も、女子高生の命である髪を整えていた。
そのときだった。頭頂部で、ブラシが何かに当たった。
「ん?」
ブラシを洗面台に置いて、私は両手の指先で、自分の頭を触った。頭頂部から、髪の毛の中に指を入れて、頭皮をまさぐった。
何かある。私の頭に何かがあった。
それは、小さな突起のようなものだった。触るとお菓子のグミのような、シリコンのような、柔らかくてすべすべした感触があって、痛くも痒くもなかった。
なんだろ? たんこぶ? 頭ぶつけたっけ?
考えながら、この突起を見てみようと、頭を下げて頭頂部を鏡に映した。
「な、なに? これ」
ピンク色だった。
ショッキングピンクというのだろうか、鮮やかなピンク色の突起が、私の頭にあった。たんこぶでも、吹き出物でもない、ピンク色の円錐形の突起だ。高さは一センチぐらい。直径も一センチくらいの円錐形。
私は、洗面所の鏡の前で、それを何度も確認して、触って、愕然とした。
「あかり、早く、ご飯食べなさい」
お母さんがキッチンから私を呼んでいる。
しばらく考えて、私はとりあえず髪を結んだ。ピンクの突起は見なかったことにしよう、そう思ってポニーテールにした。突起はポニーテールの結び目の奥に上手く隠れた。
たぶん、大丈夫。
たぶん。
私は、朝ごはんを食べるためにダイニングルームに移動した。
テーブルには、パンやサラダやヨーグルトが並んでいて、お母さんはキッチンで私のお弁当を詰めていて、窓からは透き通った金色の光が踊りながら入ってきて、お父さんはいつものテレビチャンネルで朝の情報番組を観ながらコーヒーを飲んでいた。
「あかり、どうかしたの?」
お母さんが私の顔を覗き込んだ。
一瞬、ピンクの突起のことを言おうかなと迷ったけれど、このことを誰かに教えてしまうと、自分の身体に起こっている異変が確定されそうで、怖かった。
「ん、なんでもない」
私は朝ごはんを食べ始めた。
パンに齧りつきながらテレビを観た。アナウンサーにピンクのツノはない。視線を窓の外に向けると鳥が一羽飛んでいた。鳥にもピンクのツノはない。
なかったことにするはずのピンクの突起に、私の思考はくっついたまま離れなかった。
私は何かの病気なのだろうか。ピンクのツノが生える病気って、なに?
「はぁあ」
思わず、ため息が出た。
そのとたん……。
にょきにょき、頭頂部に異変を感じた。くすぐったくて、ちょっと引っ張られるような感覚。初めて経験する感覚だけど、分かった。
これは、何かが、何かが、伸びている感覚。
私は手に持っていたフォークをテーブルに放り投げると、走った。洗面所に戻った。
そして、ポニーテールの結び目を乱暴にほどいて、髪をかき分けて、また頭を鏡で確認した。
成長していた。私の頭の、一センチほどだったピンクの突起は、三センチほどに背を伸ばしていた。
手が震えた。
どうしよう。どうしよう。
少しでも落ち着こうと思って、叫び声の混じったような大きなため息をついてみた。
「あふぅ」
そのとたん、また、にょきにょきにょきにょき、頭頂部に異変を感じた。
鏡を見る。ピンクの突起が八センチほどに成長していた。もう、立派なツノだ。
「あかり、ご飯、食べないの?」
キッチンからお母さんの声がする。
私はぐちゃぐちゃになった髪を振り乱して、ダイニングルームに走って戻った。
「お母さん、私、私、大変なことになった」
お母さんは、なぁにというような呑気な顔をする。テレビからは陽気なアナウンサーの声が聞こえる。私の頭にピンクのツノが生えるというような異常事態が起こっていても、朝の空気はいつもと同じ、澄んでいた。
「私のここ、頭のここ、見て」
私は頭を下げて、お母さんに頭頂部を見せた。
お母さんはゆっくりと私の髪の毛をかき分け、あの突起を優しく触った。
私はお母さんに頭頂部を見せながら、泣き始めた。絶望的な気分で涙をこぼした。
『ピンクのツノが生えた女子高生現れる』
ヤフーニュースの見出しが頭に浮かんだ。
「あらぁ、可愛い、ピンクなのね」
お母さんの、まるでお気に入りの服を見つけたみたいな明るい声が、上から聞こえた。
「はぁ?」
私は頭を上げて、お母さんの顔を見た。
笑っている。自分の娘にピンクのツノが生えているのに、笑っている。
「お母さんは緑色だったから、不満だったのよ」
「どれどれ、おぉ、あかりにぴったりの色じゃないか。よく似合うよ」
お父さんがコーヒーカップを持ったまま、私の頭を見ている。
「これ、なに? お母さんたち知ってるの?」
お父さんとお母さんが、顔を見合わせた。
「お母さんたちにもあるのよ。見て」
そう言って、自分たちの頭頂部、髪の中を私に見せてくれた。
お母さんの頭には緑色の突起が、お父さんには青色の突起があった。二人の突起は五ミリくらい、通常は髪に隠されていたようで、私は今まで知らなかった。
「まだ、このキープSについて説明したことは、なかったわね」
「まだまだ早いと思っていたけど、あかりも大きくなったもんだなぁ」
両親は、娘の非常事態を前にして、穏やかに微笑み合っている。
「だから、これは、なに?」
「これはね、キープ•スマイリングの略で、キープSって呼ばれてるものなの。あかり、聞いたことない?」
私は首を横に振った。
「これはね、一か月についたため息が、千回を越えると、生えてくるの。十七歳以上からね。あかり、最近、ため息いっぱいついたでしょ?」
お母さんに言われて、私は考えた。確かに。確かに私は、ここ最近、ため息ばかりついていた。
模試の順位が上がらないこと、ときどき上手くいかない友達関係、将来なりたいものを探さないといけない不安や苛立ち、好きな男子ひかる君に声をかけられないこと、数えたら切りがないくらい、私の周りにはため息をつくる要素がいっぱいだった。
「このキープSは、ため息をつくたびに成長するのよ」
「はぁあ」
思わずため息をついてしまった。とたんに頭頂部で、キープSというものが伸びる感覚があった。その感覚に、また、ため息をつきそうになって、慌てて息を止めた。
お父さんとお母さんは、テーブルに座って、また朝ごはんを食べはじめた。何も問題なし、とでも言うように。
私も座ったけれど、食欲はなくなっていた。
「心配しないで。あかり、笑ってみて」
「え?」
この状況で笑えるはずがないじゃん、って思ったときに、お父さんが指で鼻を押し上げて変な顔をしたので、ついクスッと笑ってしまった。
しゅるしゅるしゅる。キープSが縮んで小さくなる感覚があった。頭に手を置いて確かめると、確かに小さくなっている。
「ね? キープSは、笑うと小さくなる。ため息をつくと大きくなるの」
「笑うと小さくなるキープS」
私は、お母さんの言葉を繰り返した。
「そうよ、これは、いつも笑顔でいようという願いのツノなの。だから、お母さんとお父さんは、目が覚めたらまず顔を見合わせて笑うの」
「ふーん」
私は口角を無理矢理上げて笑顔を作ってみた。
しゅるしゅるしゅる。キープSがさらに小さくなっていく感覚があったので、手で触ってみると、五ミリくらいに縮んでいた。これなら気にならない、かも。
「ほらほら、学校に遅れるわよ」
私のピンクのツノ騒動は、何事もなかったように扱われて、終了した。
それから、私は大急ぎで学校に行く支度をして、駅までポニーテールの髪を揺らしながら走り、いつもの電車に乗った。
電車の席は人で埋まっていたから、私は吊革に掴まって、座っている人々の頭頂部を見た。注意して見ると、なるほど、キープSが生えている人は沢山いた。
スーツを着たおじさんの頭にも、ハイヒールを履いたきれいなお姉さんにも、制服を着た学生の頭にもツノがある。キープSが目立つ人も目立たない人もいる。赤、青、紫、色も人それぞれで、キープS自体が個性的だった。
真っ黒の十五センチくらいのキープSを生やした疲れた顔のおじさんが乗車してくると、キープSのない、もしくは髪で隠れて見えないおばさんが笑顔で席を譲った。その笑顔につられたように笑ったおじさんの真っ黒のキープSがしゅるっと縮む。
なるほどね、と私は思った。キープSは目印にもなるんだ。キープSが大きくなった人には、思いやりを持って接して、ため息の理由を聞いてあげたり、笑顔になれるように手を貸してあげたり、そんなこともできるわけだ。
私は何も知らなかった。
自分にピンクのツノが生えるまで、他人のツノに気がつかなかった。それは、他人のため息に気がつかなかったということだ。
目を開けているのに、見ていなかった。耳があるのに、聞いていなかった。
同じ車両に、私が絶賛片思い中のひかる君がいた。座って文庫本を読んでいる。
私はひかる君の前に歩いて行った。そして、ひかる君の頭を上から見た。
銀色の小さなキープSが生えていた。
「カッコイイ。シルバーのツノじゃん」
私が心の中でつぶやいたとき、ひかる君が本から顔をあげた。目が合った。
「おはよう」
私は、初めてひかる君に声をかけた。思いっきりの笑顔で。
「おはよう」
ひかる君も挨拶してくれて、おまけに席を譲ってくれて、会話が弾んだ。
ピンクとシルバーのカップル、誕生するかもしれない。私は嬉しくなって、また笑った。
笑、笑、笑、笑、笑。
あなたの頭にも、変なものが生えてくる。
にょきにょきにょきにょき、生えてくる。
あなたのキープSは、何色ですか?
数年前に他のサイトに投稿した物語です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
