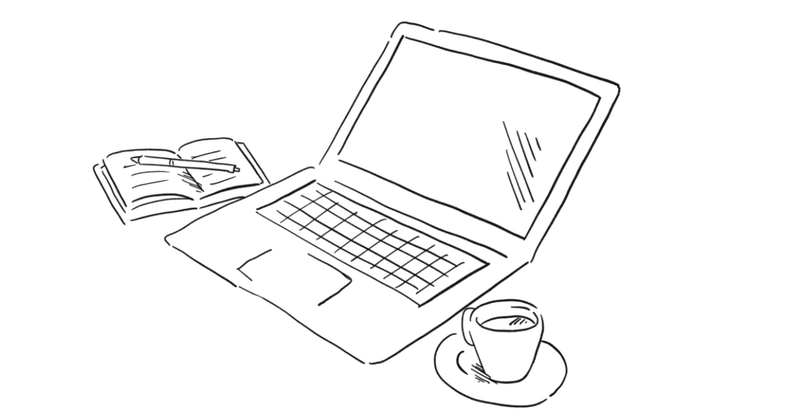
働くことがイヤな人が働く理由
私が「心のノート」と名付けているノートがある。
読んでいる本から印象に残ったフレーズを抜き出して書き留めておくためのノートだ。小説から抜き出していることもあれば、新書から抜き出しているものもある。
最近そのノートを読み返していて気がついた。なんと同じ本を2回取り上げている。手書きで書き写すのはそれなりにめんどうなので、心のノートに書き写すことは滅多にない。にもかかわらず、私に2回も筆をとらせたその本のタイトルを見て思わず笑ってしまった。
いや、どんだけ働くのイヤなんだ。
書き写した時期を見てみると、大学3年生のときとその3年後の社会人2年目のときになっている。これだけ見ると、働く前から働くのがイヤで、働いてみてもやっぱりイヤだったというように見える。でも書き写した中身を見てみると、たぶん働くことそのものがイヤだったわけではないことがわかる。
それにしても、たいそうおかしいと思うことは、自分の好きな仕事を見いだせない者を蔑視する現代日本の風潮だ。「自分のやりたいことがきっと何か一つあるはずだ」というお説教は、正真正銘の嘘だ。
就活をしていたとき、「やりたいこと」を聞かれることが心底いやだった。仕事にできるようなやりたいことや好きなことなんてないし、あったとしても変わりゆくものだし、やりたいことより適性のあることをやった方がいいと思ってるし(でも適性もわからないし)、そもそも仕事をしたくないのだ。面接で語れる内容も熱量もない。自己分析したところでないものが出てきたりもしない。自分の生計が立てられるぐらいの給料がもらえればそれでいい、なんて本心はとてもじゃないが口には出せないから、なんとかやりたいことっぽいことをひねり出すのに必死だった。
つまり、働くことがイヤだったのではなく、「やりたいことが何か一つはあるでしょ、それを仕事にすればいいのよ」みたいな就活の風潮がイヤだったのだ。あの頃の自分は視野が狭かったから、そんな風潮があると思い込んでいただけかもしれないが。
社会人2年目の私はこんな箇所を書き出している。
大部分の者が仕事に報われないのであり、そうした報われない人々が、それにもかかわらず続けるところ、続けざるをえないところに「仕事とは何か」という問いに対する地に着いた答えがあるように思う。理想的な要求ではなく、日々の現実的な要求に応えるものこそ、大方の仕事なのだと思う。この現実を見失ってはいけないと思う。
仕事が上手くいっていなかったわけでもないのだし、もうちょっと夢のあることを考えててもよかったんじゃない?2年目にしてはちょっと冷めてない?と我ながら思う。どうやら「仕事にやりがいはなくてもいい(そりゃあるに越したことはないけど)」という私の仕事観は、この頃には形成されていたらしい。
それでもいまだに「生活のために仕事するなんてつまらない」みたいな言葉を聞くと、揺らいでしまう。もっと社会にインパクトを残せる仕事をした方がいいんじゃないか、野心を持って仕事をすべきじゃないか、地元に帰って何か貢献すべきなんじゃないか、と。たぶん社会人2年目の私もこんな焦りを覚えていて、『働くことがイヤな人のための本』を読んで心を落ち着かせていたのだろう。
仕事にやりがいはあってもいいし、なくてもいい。やりたいことがなくても働いていい。だって働かないと生きていけないから。なんてことを自分に言い聞かせ、騙し騙し働いている。
(どみの)
よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートは記事を書くときのロイヤルミルクティー代に充てさせていただきます。
