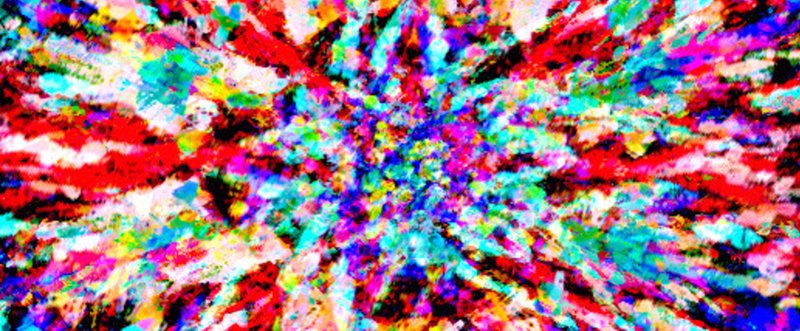
火と救い
何故、おれは今、この人に刃を向けられているのだろう。
月が陰ったからだろうか、雨が降ったからだろうか、星が見えないからだろうか、夜の闇が濃いからだろうか。この人がおれを憎んでいるからだろうか、それとも、おれが……
駆ける馬のように、巡る想いが頭を走っていくのを感じた。ああ、と思う。
――ああ、たぶん、それは考えても分からないことなのだろう。己の心もよくは分からないおれに、人の、おまえの心など、分かるはずもないのだ。
月の見えない夜。その色は深い。だが、その黒は目の前の、こちらの喉元に刃を突き付けている彼女が纏う蛍火によって、いくらかは和らいで見えた。木々の葉の調べと、彼女の呼吸する音が聴こえる。彼女の刃と瞳が、冷たい色を湛えてこちらを見据えていた。
そう、考えても分からない。
だが、何故、おれは今、この人に刃を向けられているのだろう。
犬童と薫子は、或る小さな村にやってきていた。
何処か燃え殻のようなその村は、誰が見ても、昔に棄てられたものだということが分かる。
渇き、ひび割れた地面に、時折吹く砂っぽい風。この棄てられた村を訪れた犬童は、貴石に照らされ美しくそびえ立つこの世界の、何か、仄昏い部分を覗き見たような気分になった。
「此処はなあ、わっちの生まれ故郷じゃよ、犬童」
隣で薫子がいつもと変わらぬ口調でそう言った。だが、その変わらぬ口調に一抹の違和感を覚えた犬童が、ちらと薫子の瞳を視界の隅で捉えた。彼女の弧を描いた口元から発せられる言葉は、いつもと同じ色を纏っている。しかし、その瞳。彼女の黄水晶は、まるでこの村が視界に入っていないかのようだった。今、彼女は一人だけで、此処とは違う場所に立っている、犬童はそう思った。
「まあ、見ての通りじゃな。此処は何故だか雨が降らなくてな……そのおかげで日照りが酷かった」
薫子が、まるで面白い昔話のように言った。ぬるい風が吹いて、犬童の耳飾りを揺らす。沈みゆく太陽が眩しくて、彼は瞬きをした。もう、夜は近いらしい。
「――人が、いないな」
そう犬童がぽつりと呟く。
「そりゃあ、なあ。此処はもう人里ではない。棄てられた村、なのじゃよ。……此処が棄てられたとき、わっちは一人、此処に残った。此処で果てた者の魂が、どうにもわっちをこの地から離してくれなくてな。まあ、結局韻響とおまえの主に連れられて此処を出たのじゃが――もう、果てた魂たちも還るべき処へ還っていることを願うよ」
横目に見た薫子の瞳は、やはり今日の空を映してはいなかった。その黄水晶に映るのは昔の村、あの日の空。そのことに犬童はぼんやりと気が付いていたがそれは、淡い淡い輪郭を保ったものだった。
「――じきに夜も更けるじゃろう。手分けして朝までやり過ごせそうな家を探すとするか」
犬童が何かを言う前に、薫子は軽い足取りで村の奥へと進んでいってしまった。その背を数呼吸の間眺めて、犬童も燃え殻の村の奥へと歩を進める。
乾いた風が頬をゆき過ぎていった。掠れた音を立てる枯れ葉や木々が、この村の辿ってきた道を表しているようだ。それは何処か、寂しさを孕んだものであった。
屋根が崩れている家、壁に穴が空いている家、最早原形を保てていない家、村の中に在る家はどれも皆そんな調子だった。酷い有様だな、犬童がそう思いかけたとき、彼の瞳に古いが比較的まともだと言えそうな家が映った。此処ならば、と木の扉に手を掛けようとすれば、その手に何か冷たいものが当たる。犬童は反射的にそれが降ってきた方を見上げたが、そこには闇に塗れかけた空を覆い隠す灰の雲ばかり。燃え殻の村に降ってきたのは、何年ぶりかは知れぬ雨だった。
傘はない。犬童は雨が強くならないうちに、と、薫子の姿を探すために踵を返した。
そして彼女の姿は、犬童が歩を進めて数十歩先、すぐに見つかった。
薫子は、灰の、雨が降る空を見上げていた。その表情は夜と月の光を遮る雲によってよく見えないが、彼女の口元は弧を描いている。
犬童が近付くと、彼女が笑っていることが分かった。喉の奥をくつくつと鳴らして笑っている。だがそれはどうやら、楽しさや嬉しさからではないようだった。薫子は犬童に気が付くと、空から視線を戻してまた笑った。
「――雨! あの日、あのとき、どれほど願っても降らなかった雨!……それが今降るか、今、降るか! ああ!……腹が立つ、なあ。隠れておる月を打ち砕きたいほど、腹が立つ」
犬童は薫子の瞳がおかしな色に燃えているのを見た。その美しい輝きの奥で今燃えるのは、怒りの炎、憎しみの炎、そしてそのいちばん奥に揺らめくのは、深い哀しみの炎だった。
犬童はその炎へ、何かを考える前に手を伸ばしていた。薫子の頬に彼の指先が触れる寸前、犬童は目の前で、何か白い光がひらめくのを感じた。それは、薫子が袖口から滑り出させた短剣の光だった。犬童の喉元に刃の切っ先が当たっている。彼はその刃を一瞥してから、身動きもせずに、再び薫子の方を見た。彼女は薄く笑っている。だが、その瞳にはやはり、哀しい炎が揺らめいていた。
「キョウとはじめて会うたときも、そう――こんな風に刃を向けたものじゃよ。……最近気付いたのだがな、わっちはどうやら、おまえが憎いらしい」
おまえが憎い、その言葉に犬童は柔らかく笑った。己の喉元に刃を向けている薫子の右手を自らの両手で包み、犬童は彼女の手を、自分の、人であれば心臓が在る位置まで持っていった。その刃の切っ先が、犬童の心臓部へ当たるように。
「――それを俺が、知らないと?」
薫子の瞳が揺れる。彼女の手を包む犬童の声は、いつになくやさしい色を纏っていた。薫子が怒りを孕んだ声で言う。
「死にたくなければ、抵抗してみせよ。……得物を取れ! それともこのまま、わっちの手に掛かるつもりか!」
「それも悪くは、ないな。……お前は人で、俺は物だ。物が人を愛したところで、人は物を愛せはしないだろう。だったら此処でお前の手に掛かるのも悪くない」
犬童は心の中で己を軽蔑した。
――この人は優しい人だ。おれがこういう言い方をすれば、どうすることもできないのは目に見えている。憎まれている理由は分からないが、今は何だか、それが少し分かるような気がした。いつからおれは、こんなにも汚くなったのだろう。それでも今の言葉は、紛れもないおれの本心だった。この人の手に掛かるのなら、そう、それも悪くはない。
「おまえを物、扱いなど――」
犬童はその琥珀の瞳にやさしい笑みを湛えて、それから薫子の右手にある短剣の刃を、先ほどより強く自分の胸に押し当てた。痛くはない。ただ、ぬるい哀しみのようなものが心の中に広がっていくのを犬童は感じた。思ったよりも、痛かったのだ。薫子の口から零れ落ちた、おまえが憎い、という言葉が。
「何故、喉元を狙った。お前がいちばんよく解っているだろう。……狙うなら、ここ――人の心臓が在る――ここだ」
そう言って、犬童は刃を己の心臓があるところへ押し当てる。落ちる雨は、痛くもなく、冷たくもなく、ただひたすらに二人の肌を濡らすだけだった。地面は砂漠の砂が水を吸うように、雨の恵みを喜んでいる。
「壊したいなら、そうすればいい」
もう少し力を入れれば、薫子の刃は犬童の肌に突き刺さる。薫子の手が震えた。彼女は歯を喰いしばって、犬童の両手から自らの右手を引き抜いた。ほとんど叫び声のような声を上げて、右手に持っていた短剣を何処かへ投げ飛ばす。彼女は頭を抱えてその場に崩れ落ちた。犬童は白くひらめいて飛んでいった刃には目もくれず、薫子の前に膝を突いて、彼女の顔を見る。湿った風が肌に触れていくのを彼は感じた。
「やめろ――やめろ、やめろ!……おまえを物扱いできるのなら、とっくにしている! おまえを殺せるのなら、とっくに殺している! できないから、できないから――どうして――わっちの願いは……どうして雨は、願ったときに降ってくれない? どうして愛した者は逝ってしまう? どうして――なあ――おまえがたいせつなんだ――きっと、たぶん、わっちはおまえが――なあ、どうしてたいせつな者をこんな……こんな理不尽な理由で……どうして、憎まねばならない? どうしてもっと、簡単に……。おまえは、おまえはどうして……どうしてそれを受け入れられる? どうしておまえ、そばに?」
犬童は少し笑って左右に首を振る。そうしてから、薫子の濡れそぼった肩を抱いた。雨が地面に落ちていく音と、枯れ木に雫がぶつかる音が重なって聴こえてきた。
「……分からない。分からないが、それでも」
呟くように言った犬童の背に、薫子の爪が突き立った。犬童は、あの刃よりも、この爪の方が心に随分近いように感じた。
夜の黒は深い。ぬるい雨が降る空には厚い雲。月は何処にいるかすらも分からない。
小さな嗚咽を聴きながら、犬童は薫子のその細い肩を抱いていた。
どうか、と想う。どうか、この人の瞳に宿る、哀しい炎が消えますように。それを消すのは自分がいい、そんなことは思わないから、どうかこの人が哀しみの青い炎に灼かれぬよう。そうだ、その炎をおれにくれてもいい。この人がこれ以上、何かを憎まないのならば、何かを憎むことを憎まないのならば、この人が笑うのならば、おれなんか、好きに燃やしてくれて構わない。
――ああ、だが、今は、今だけはただ、この人の肩を抱いていよう。
朝がくるまでは、この、銀の雨が止むまでは、ただ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
