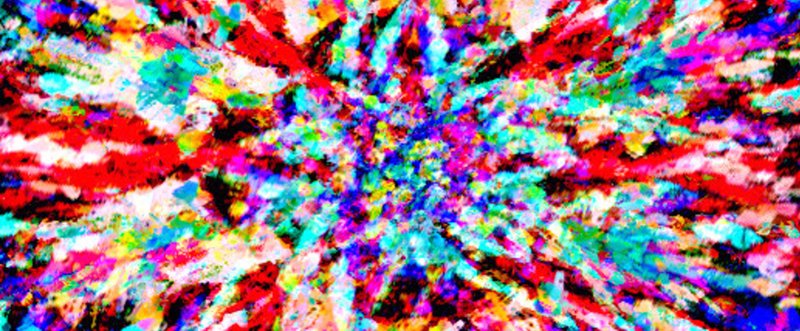
琥珀をやどす
靴音が地面に跳ね返る。その音を何の気もなしに聴きながら、犬童はふと、一人で街を歩くのが随分久しぶりだということに気が付いた。機械仕掛けの街を何の迷いもなく進み、彼はある、レンガ造りの壁のような門の前で立ち止まった。
(――月は沈み、太陽が昇る)
心の中だけで呟きながら、犬童はちょうど彼の右手の辺りにある、月の彫り込みがしてあるレンガを押し、その次に、左足の辺りにある太陽の姿が彫ってあるレンガをとん、と蹴った。そうすると、月と太陽のレンガの位置がカシャンという、その見た目に似つかわしくない音を立てて入れ替わった。
(命よ廻れ、ひとたび廻りだせば止まらぬ歯車のように……)
犬童は口の中でそう諳んじ、今度は門の真ん中にある大きな歯車を両手で回した。金属が動く、独特の重たい音を響かせながら、歯車は自らの四方にある大小の歯車を巻き込んで回転する。段々と速さを増すそれを眺めていると、レンガの壁は半分に割れ、少しずつ左右に開いていく。人が一人通れるほどの広さまで開くと、歯車の動きは止まり、まるで早く通れと無言で指図するようだった。これが、この家処の開門である。
犬童がその、広いとは言えないレンガとレンガの隙間を通り抜けると、門はひとりでに口を閉じた。久しぶりに聴く、その重たい音を少しばかり懐かしく感じながら、彼は少し先にある、門の仕掛けの割にはそこまで大きくない館の扉を目指して歩を進めた。
辺りを見回すと、金属でできている花たちが犬童の帰りを喜ぶかのように、陽光を反射させて煌々と輝いている。犬童はその中の一輪の前に膝を突き、葉の形を模したゼンマイを巻いてやった。そうすると機械の花は、まるで風に吹かれているかのようにそよそよと揺れ、その様子は何処か、犬童に向かって手を振っているようにも見えた。犬童はその冷たい銀の花びらに触れ、少しだけ微笑んで、彼にしか聞こえないほどの声で花たちに声を掛けた。
「――ただいま」
犬童は立ち上がり、数歩先にある館の扉を見つめた。さて、何と言って扉を開ければいいのだろう。そんな思いが彼の頭を掠めたが、腰に下げている蜜色の鍵に左手の硝子爪が触れると、考えるより先に扉の鍵穴に蜜色を差し込んでいた。控えめな音と共に鍵が開いたことが分かり、犬童は扉を引いて館の中に足を踏み入れた。
(……主は何処だろう)
犬童は館の中をゆっくりと見回した。そうする彼の視線が正面に戻った瞬間、何か、自分の立っている床が遠くの衝撃で揺れ動くのを犬童は感じた。彼は瞬時に己の気配を殺し、背の短槍に手をやって、床を揺らした衝撃の元凶を探すべく、滑るように走り出した。
(元凶はどうやら主の研究室や工房ではないらしいな。寝室?……それも違う。もっと向こうの部屋だ。でもこの先には厨房しか――……厨房?)
彼の心が何かを掴むより先に、彼の足が厨房に辿り着いた。扉に耳を当てると、なにやらがたがたと、物と物がぶつかるような音が聴こえてくる。犬童は短槍を構え、一度息を吐いてから勢いよく厨房の扉を開いた。
「……主?」
そうしてみると、犬童の視界に飛び込んできたのは、跳ね回る錫色をした縦長の薬缶――のようなものと、それをなんとか抑えようとする犬童の主――カルトだった。カルトは開いた扉の方を振り返り、驚きや嬉しさや焦りなどが一緒くたになった顔をして、いつもより少し大きな声で犬童に声を掛けた。
「――インドウ! 帰ったのか!……ち、ちょっと助けてくれないかい! こいつがどうにも落ち着かなくてさ!」
犬童は緊張を解き、手にしていた短槍を厨房の壁に立て掛けた。ぽんぽんと跳ねている薬缶と困り顔の主を見比べ、半ば安堵のような苦笑を漏らしてから忙しない錫色を捕まえる。犬童に掴まれた瞬間、薬缶は自らが生き物ではないことを途端に思い出したかのように静かになり、それを見たカルトはがっくりと肩を落とした。
「なんだよ、それはないだろ? 僕は自分の発明品に嫌われでもしてるって言うのかい?」
「いや、違う。これの底蓋を開けただけだ。……主、ほら、ここの歯車が噛み合っていない。恐らくこれを直せば」
そう言って犬童は薬缶をカルトに手渡した。その薬缶の錫色をした肌は、よく見ると細かい花の彫り込みがしてあって美しい。カルトは、なんだ、そうか、と安心した表情で自らの発明品を受け取り、腰の革袋から使い古されたねじ回しと鑷子を取り出して、厨房の中心にある机の椅子に座った。犬童もそれに倣うようにして向かいの椅子に座る。
「じゃあ今、直すね。……珈琲を飲もうと思ってただけなんだけどなあ。豆を挽いて淹れてくれるところまでやってくれる機械があったら便利だろ? だからさ、昨日、これを造ってみたんだけど……いやあ、インドウが帰ってきてくれて助かったよ。――おかえり」
カルトの言葉に、犬童は胸の底にあった靄のような思いが、すう、と消えていくのを感じた。おかえり、そう言ってもらえることがこんなにも嬉しいことだとは。柔らかく微笑む主に、犬童も少しだけ笑みを浮かべて頷いた。
「――ただいま、主」
犬童の返事にカルトも頷くと、彼は薬缶の機械部をいじくり始めた。中の歯車を一つ外へ出したところで、カルトは思い出したという風に口を開く。
「そういえば、カオルは?」
「寄りたい店があるから、後で来る、と……。というか、いつも一緒には行動していない」
凪いだ声でそう答えた犬童を見て、カルトは少しだけ笑い声を零してから、また機械と向き合った。
しばらく二人は心地好い沈黙を守り、犬童は壁に掛かった文字盤が時を刻む音をぼんやりと聴いていたが、やがてカルトが一息つくように背を椅子にもたれ掛けると、犬童がぽつりと呟いた。
「――この間、墓へ参った。キョウの、墓へ」
犬童の口から〝キョウ〟という言葉が出たことに、カルトは内心驚きながら、手に持っている工具を机の上へ置いた。
「カオルと?」
「ああ」
「……カオルがキョウのことを話すのは、もっと後になると思ってたんだけど、なあ。カオルがおまえに話す気になるまで、僕もキョウのことは黙っているつもりでいたんだ。カオルは彼女が逝ったとき、すごく――傷付いたみたいだから。……でも、キョウのこと、人に話せたんだ……よかった。時の力かな、それとも――」
その先の言葉を、カルトは音にしなかった。やさしく微笑む主を視界に宿しながら、犬童は言葉を紡いでいく。
「最初――はじめてカオルを見たときは……何をするにも面白そうな顔をして、勝気な態度をするから、悩みなどない人間なのだと思った。まるで、生きるのが楽しくて堪らない、そんな顔をして笑うから」
「――そうだね、彼女は感情を隠すのが巧いよ。人は誰にでもそんなところがあるとしてもね」
そう苦笑してみせたカルトに、犬童は睫毛を少しばかり伏せた。
「だが……墓の前に立って、思った。――哀しみを知らない人など、いないのだな。哀しんだことがない人など、この世には。あの丘の上では、カオルの笑顔が、痛いと感じた。おかしいだろう、主。彼女の火に燃やされたわけでもない、彼女の刀に斬られたわけでもないのに、痛かったんだ。ああ、壊れたのか、そう思った。だけど、違う。どうやら、違うらしい。解らないな、この、心……というものは。時々、怖くなる」
犬童は自分の心臓の辺りの服を、ぐ、と掴んだ。カルトのターコイズ色をした瞳が柔らかい線に細められる。
「僕もね、解らないよ、心なんてさ。気が付いたらもってたんだ。こんなもの、ない方がましだと思ったことも多い」
「……そう、か」
「そうだよ、ねえ、インドウ。怖くてもいいんだ、怖くても当たり前だよ、僕も怖い。だけど、どれだけ怖くても、いらないと思ってもね、そこにないものとしたらいけないよ。自分の心に知らないふりをしてはだめだ。胸の奥にあるものには、向き合った方がいい――自分が、向き合える内に。おまえにはこんなこと、言わなくたって平気だと思うけどね」
犬童はカルトの、やさしさの中に揺らがないものがある瞳を見て、ふと思った。――この人も、哀しんだことがあるのだ。おれが知らないだけで、きっと。犬童はそのことを少しだけ哀しく感じながら、そんな風に思う自分に眉根を寄せた。
「心があるとね、弱いところが生まれるんだよ。僕も、カオルだってそうさ」
「……カオルは強い」
カルトは曖昧に笑った。
「うん、そうだね。僕もそう思うよ。――でも、カオルにも弱いところはあるさ、心の中にね。……ああ見えて彼女は硝子のような人だよ、脆い部分もあるんだ。だから、守ってあげてね、インドウ」
犬童は頷いて、カルトの目を見て答えた。
「――主がそう望むなら」
カルトは肘杖をついて、音を立てず笑いながら、机に乗っている犬童の左手に視線をやった。
「おまえはそれを望まない? 僕が守れと言わなかったら、守らない?……殺せと言ったら、殺すのか?」
「……主はそんなこと、望まない、だろう」
「どうかなあ」
からかうように言うカルトに、犬童は短く息を吐いてやんわりと首を振った。左手の硝子に目を向けながら呟く。
「――分からない」
「うん?」
「分からない、守れと言われなかったとき、自分がどうするのか。……殺せと言われたとき、どうするのか。どう、すればいいのか」
少し苦しげな表情を浮かべる犬童の頭を、カルトが困ったように撫でた。犬童がその手を見上げる。
「ごめんね、少し意地悪だった。……答えが見えないときはね、インドウ、どうすればいいのかじゃなくて、どうしたいのか、で考えて」
「どう――したいのか……?」
「……その内分かるよ、時間がかかってもね。だいじょうぶ」
確信に満ちたカルトの瞳に、犬童は曖昧に頷いた。そうすると、心の中に在った言葉が口を突き、音になって犬童の外へ出ていった。
「……主は、寂しくないのか」
カルトのターコイズに、ふっ、と郷愁の色が浮かび、そしてすぐに溶け消えた。いつものやさしい笑みを浮かべながら、彼は犬童に答えを返す。
「寂しくないって言ったら……それは嘘になるけど。でもね、インドウ、悲しくはないんだよ。悲しくはないんだ。分かるかい、カオルやおまえがいるからだよ。だから僕は笑えるんだ」
そう告げると、カルトは照れ臭そうに頬を掻いて、また手元の薬缶に向き直った。薬缶の部品と主のねじ回しが軽い音を立て合うのを、聞くともなく聞きながら、犬童は瞼を閉じる。琥珀の色をした、彼の瞳の膜に、たくさんの思いが浮かんでは消えた。再び目を開ける瞬間に、先ほどの主の笑顔が花のように咲いて、また溶けるのを彼は感じた。
まるで少年のように笑うものだ。孤独など知らない、つめたいものなど知らない、自分はずっと太陽に照らされて生きてきたのだ、彼はそんな風に笑う。
(自分の心を隠すのが巧い。……それはあなたもそうだろう、主)
どんなにあたたかく笑っていても、この人は、己の最愛の人を亡くしているのだ。在りもしない心臓が、呼吸するたび痛む気がした。犬童は呟くように言葉を机に落とした。
「主。悲しくない――というのは、嘘だろう。……悲しくないわけがない」
「……悲しくないよ、今は、ほんとうに」
カルトの、静かな湖畔に似た瞳は波を立てなかった。主の揺らがぬその表情に、犬童は少しばかり怪訝な顔をした。
「そりゃあね、キョウを失ったときは悲しかったさ。死んじまおうかと思ったよ、息をするのも馬鹿々々しかった。でも、カオルがいたし……まだおまえが息をしていなかったから……どうせ死ぬなら、おまえが呼吸をしてからだって思ったんだよ。発明家としての意地みたいなものさ、それが僕を此処に留まらせた。……ほんとうに死んで、鬼嫁に怒られるのも結構、怖かったんだけどね」
犬童が首をひねってカルトに尋ねた。
「オニヨメ……とは、何だ?」
「……ふふ、僕の口からはとても」
曖昧に、しかし少しだけ楽しそうに笑う己の主に、犬童はますます心に疑問符を浮かべた。カルトはそんな犬童を見ると、また微かに笑みを浮かべ、ゆっくりと言葉の続きを紡いでいく。
「今、悲しくないのは時の力っていうのもあるよ。だけどね、いちばんは……たぶん、人を、おまえたちを愛せているからだと思う」
「――愛?」
「人は孤独なものだよ、インドウ、ほんとうにね。だけど人を愛さずにはいられない。僕たちは、人を愛さずには生きていけないんだよ。……だから、ありがとう、インドウ」
礼を言われた意味が解らず、犬童は押し黙る。しかし、胸から手のひらの辺りにかけて、何かあたたかい、血のようなものが巡っていくのを彼は感じた。彼は何となく、ほんの少しだけ、自分がどうしたいのか、それが分かった気がした。
犬童は椅子から立ち上がり、うなじで一つに纏めている髪を、それより高い位置でもう一度結い上げた。そうしてから厨房の水道で手を洗う。不思議に思った彼の主が、犬童に声を掛けた。
「インドウ、どうしたの?」
「……何か作ろう、と」
「料理、できるようになったのかい?」
「主よりは、な」
それを言われたカルトは、自分の作った料理の味を思い出して苦々しげに唸った。そのあと彼は、わざとらしく不貞腐れて机の上に両腕を投げ出した。
「カオルの好きなものでも作るの? いいなあ、カオルは! いつも想われててさあ、まったく……羨ましいよ」
子どものようにそう言う、自らの主を犬童は振り返る。目が合うと、犬童は声を零して柔く笑った。
「主も分からないな。……俺は主のことも、いつも想っている」
「……じゃあさ、食べたいものがあるんだけど」
「ああ、任せてくれ」
廊下の奥の方から、扉が開き、また閉まる音がした。二人は燃える焔の色を思い浮かべて、顔を見合わせる。同じ風に考えたことがどうにも可笑しくなり、二人は声を上げて笑った。目に見えない音たちが、楽しそうに床や天井を跳ね回る。
その笑い声を聞きつけやって来た薫子が、少しばかり怪訝な表情をしてから、なんだ、おまえらは仲がいいなあ、と呆れたように笑ったが、それはまた、別の話。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
