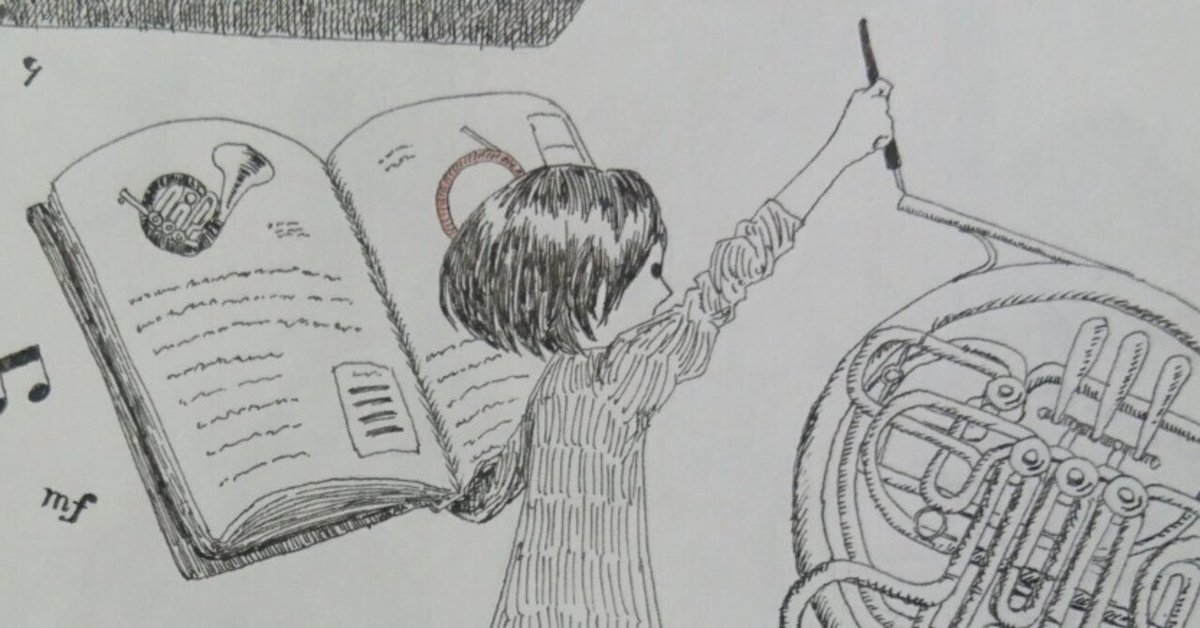
「合奏が怖い」という気持ち
HaFaBraプロジェクトなすの 花月です。
前回の「ヤン・ヴァンデルローストマーチ体験会」、そして6月の「ファンファーレオルケスト体験会」の開催要項やフライヤー上で、「楽器初心者やブランクをお持ちの方も大歓迎です」という旨の文言を必ず入れています。この文言は、私が合奏イベントを開催するにあたって一番大切にしていると言っても過言ではない部分です。
HaFaBraプロジェクトなすののモットーの一つとして、「誰もが安心して合奏に参加できる」イベントづくりを目指すことを掲げています。経験や技術に不安を抱えていても、「合奏したいかも…」という欲求の芽生えだけで参加できる場を作りたい。「合奏は本来、怖くある必要はないんだよ」と伝えたい。それは他でもない私、そして家族や友人も、「合奏に参加するのが怖い」という思いを抱えていた/今も抱えているからです。
このこだわりが生まれた経緯について書こうとしたら本当に長くなりそうなので、まず最初に、私(たち)が抱えていた「合奏が怖い」という気持ちがどのようなものであるか書きます。
もしかしたら読者の方のトラウマを呼び起こしてしまうかもしれないので、途中で閉じても構いません。ただしこの文章は、「こういう思いをしてきたからこそ、『本気で音楽に取り組むけど怖くない合奏』も存在するんだと伝えたい!!」というところにつながっていくことをご承知おきいただければ幸いです。
「合奏が怖い」という気持ち
私は吹奏楽をやめた
私は高校2年生の夏、当時所属していた吹奏楽部を退部しました。母校の吹奏楽部は3年生の夏のコンクールが終わるまで所属することが可能だったので、中途退部です。自分の意志でやめました。退部届の理由欄には「受験勉強」と書いたけど、本当は、単純に演奏することが楽しいと思えなくなったから、さらに言えば、バンドに所属して合奏に参加することが怖くて怖くて、苦痛でどうしようもなくなってしまったからやめました。少なくとも自分は、今後10年は合奏に参加することはないだろう、という気持ちでやめました。
楽器を吹くことも、吹奏楽という音楽も文化も好きでした。好きだったはずでした。中学時代から毎月、地元の本屋に1冊しか入荷しないバンドジャーナルを我先にと購入し、誌面に掲載されていたシエナ・ウインド・オーケストラの演奏会を聴くために、一家で東京へ行きました。ホルンを試奏するために、友達と浦和の島村楽器で開催された管楽器フェスタへ行きました。ついでに寄ったPARCOの本屋でオザワ部長の「吹奏楽部あるある」を衝動買いし、本の中に出てくる知らない曲を熱心に調べて聴きました。部活以外にも地域のバンドへ見学に行ったり、演奏会に参加させてもらったりしました。
中学3年生のとき、母を説得し、祖母からもお金を出してもらい、自分で貯めた3万円も合わせてホルンを買ってもらいました。高校では迷うことなく吹奏楽部に入部したし、それどころか「別の部活入ろうかな」と迷っていた中学の同級生を引き留めていました。1年生のときはコンクール出場メンバーになるために、始業前と昼休み、必ず自主練していました。我ながら熱心な奏者だったと思います。
高校に入学して以降、自分の中からそういう熱心さが徐々に消えていくのを、日々虚ろに眺めることしかできませんでした。いつしかバンドジャーナルは買わなくなり、YouTubeで吹奏楽曲を探して聴くこともなくなりました。部活に出るとお腹が痛くなるようになりました。中学時代は顧問から「もうちょっと小さくていいよ」と言われたことがあるくらいのフォルテを出せていたのに、2年生のコンクール前、いくら頑張って吹いても大きい音が出なくなりました。体がこわばって、全く息が入っていきませんでした。音は震えっぱなしでした。きっと先輩や同級生からは、私が真面目にやっているようにはとても見えなかったと思います。
2年生のコンクールは県大会銀賞に終わりました。「銀賞」というアナウンスを聞いて、落胆を大きく上回る安堵を覚えました。よかった、これでやっと解放される。
そうして私は吹奏楽部を退部しました。大学でも吹奏楽団に入ろうとは思わなかったし、それどころか楽器は実家に置きっぱなしにしていました。
吹奏楽団の悪夢を見る
全国の吹奏楽経験者の中で、「部活/楽団にまつわる悪夢を定期的に見る」人がどれほどの割合いるのか分からないけど、少なくとも私の周囲にはかなりいます。吹けない楽器を吹かされる夢、全く音が出ない夢、吹けないことを問い詰められる夢。
私の場合は、「部活を長期間欠席していて、『続けるのか辞めるのか、結局どっちにするんだ』と問い詰められる夢」を見る頻度が高いです。吹奏楽部をやめてもうすぐ10年になるけど、いまでも少なくとも半年に1回くらいの頻度で見ます。
私の親類の一人は小学生の時に「ブラスバンド部」に所属していて、大人になってから30年近いブランクを経て楽器を再開しました。しかし、そのとき入った吹奏楽団で、合奏の場に対する恐怖感を植え付けられてしまいました。
その人が経験したのは、平日昼間も練習できる時間のあるメンバーが、練習時間が限られているメンバーを一方的に追い詰める現場でした。両者の分断は進み、それどころか、団が進んで分断を加速させるような仕組みを設けました。退団する直前の話は詳しく聞いていないけど、本当に辛そうでした。バンドに所属していたときの話は、今でもあまりしたがりません。
それでも、気の合う仲間と一緒に少人数でのアンサンブルはしばらく続けていたようだけど、コロナ禍を経て、今では日常的に楽器を吹くことはありません。大人になってから経験した怖い記憶も、悪夢となって時折襲い掛かってきます。
楽しい記憶はちゃんと抱いている
私は月に何度か、妹の家に泊まりに行きます。大抵は私が東京のバンドの練習や演奏会に行く前後です。だから毎回多かれ少なかれ、音楽のことが話題になります。
ある日、何か音楽の話をしていたときに、「中学のときに演奏した(樽屋雅徳の)マードック(からの最後の手紙)、楽しかったな」という言葉が妹の口からこぼれました。それを耳にして、驚きと感動の入り混じった感情が胸に広がりました。昔演奏した曲の名前、それを演奏して楽しいと感じた記憶、それらが今でも心の中に抱かれているのがとても尊いことだと感じました。
妹は小学校のブラスバンド部でコルネットを、中学の吹奏楽部でサックスを吹いていました。そんなに目立ちたがりな性格ではないけれど、立派にソロも吹いていました。高校で別の部活に入ってからずっと吹奏楽からは離れていたけど、誘えば私の演奏会に来てくれるし、「ヴェノーヴァを買った」という報告も何年か前に聞きました。音楽を聴くこと、奏でることはずっと好きでいるのです。
私が昨年アルトサックスを衝動買いして「教えてよ」と無茶振りしたら、妹は一緒にスタジオに来てくれました。そのとき彼女は何年かぶりにサックスに息を吹き込んだけど、私が吹くよりもはるかに軽やかで滑らかなスケールを奏でていました。何よりとても楽しそうに楽器を吹いていて、横で見ているだけで幸せな気持ちになりました。そのアルトサックスはほぼ譲渡のつもりで妹の家に置いてきてあります。
そんな妹も、私が何度か体験会や見学に誘ってもなかなか首を縦に振ってくれませんでした。うまく吹けないこと、それでみんなに迷惑に思われることが怖い、申し訳ないからと言うのです。何という刷り込み。妹だけじゃない、かつて私と一緒に楽器を吹いていた他の人々もそう言います。そのように思わされて、体も心も強ばったまま合奏の場から去った人がこの世にはどれだけいるのでしょう。
合奏はやっぱり楽しい
3月に開催した「ヤン・ヴァンデルローストマーチ体験会」には、“悪夢”の項の親類、そして妹が来てくれました。ふたりとも数年ぶりの合奏参加です。
「うまく吹けなくて申し訳ないなあという気持ちや不安はもちろんあるけど、楽しかった。合奏って楽しいんだね」
こういう感想を貰いました。私の目標が一つ、達成された瞬間でした。とにかくそれを伝えたかった、伝えることができた。
「合奏は楽しい」と思ってもらうこと、それには指揮者の天野さんの力が不可欠でした。私は天野さんの指揮するバンド2つに所属しているけど、天野さんのリハーサルで恐怖を感じる瞬間、全くと言っていいほどありません。楽しいと面白い、適度な緊張があるのみです。それでいて、合奏中ずっと音楽に正面から向き合っていられる、それは体験会に出てくれた人には感じてもらえたと思います。打ち上げでも「天野さんの指揮良かったね!」とみんな口々に言っていました(それはここに書く前に天野さんに直接伝えるべきだったかもしれない)。
天野さん、次回のファンファーレオルケスト体験会の人誌さんのように、恐怖で合奏の場をコントロールすることなく、確固たる音楽観を持って音楽を組み上げてくれる指揮者がいること、そういう合奏が可能であることがもっと知られたらいいなと思います。スクールバンドでも、社会人バンドでも、恐怖による支配はふさわしくありません。奏者を萎縮させてパフォーマンスを落とすだけでなく、演奏人口を減らすことに繋がります。指揮だけでなく、バンドの運営においても、恐怖の力を利用してはいけません。もしかしたら後者の方が多くのバンドにとってより深刻な問題かもしれませんね。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。今この文章を書いている私自身がどのように「合奏が怖い」という気持ちを克服できたのか、その過程についてはまた別のところでお話しできたらいいなあと思っています。
6月29日(土)、宇都宮にて「ファンファーレオルケスト体験会」を開催します。金管楽器とサクソフォン、打楽器によってつくられる不思議な響きを体験しにきてください。全然怖くないです。曲の難度も抑えています。吹けないところがあるとか、そういうことは何も後ろめたく思うことなく参加して大丈夫です。貸出楽器が少しあります。
この文章を書いている人の昨日の日記↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
