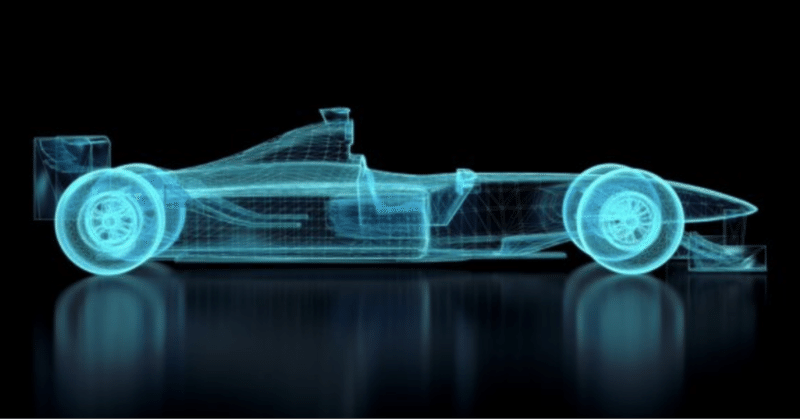
F1パフォーマンスエンジニアの仕事を考察してみる
こんにちは、トヨタWRCチームで働く山下です。
今週はラリー・エストニアがありました。そして、カッレが20歳でWRC優勝という史上最年少記録を打ち立てました!!
今シーズンのチームは7戦6勝と絶好調で、ボーナスが出ると聞いてワクワクしていたら、2月に加入した僕は僅か300ユーロ (約4万円)しか貰えずにとても落ち込みました。このまま好調を続けて冬のボーナスこそは!と密かに思う今日この頃です 笑
さて先日、Twitterでも流したのですがF1エンジニアを目指す or 興味のある学生、社会人に方にとって良さげな記事を英国Autosportで見つけました。
ハースF1でミック・シューマッハのパフォーマンスエンジニアを務めるエドワード・リーガンが仕事内容、遍歴、求められるスキルなどを回答しています。
F1でのパフォーマンスエンジニアに求められるスキルや経験が紹介されています(英語)。F1エンジニアを目指している人に良さげな記事かとhttps://t.co/jv4im9EsFs
— H. Yamashita@WRC (@yamashita_ms) July 5, 2021
僕も知りたいと思ったのと、その日本語訳の記事も出たのでインタビュー記事を、自分の経験と比較していこうと思います。留意点が2つあります。
1点目は、記事の内容を一部省略しているのと、僕の感想も交えて本記事を書いているので正確な情報が知りたい方は各自で確認してほしいこと。
2点目は、僕の野望は沢山ありますが、当面は現チームで頑張るので転職はするつもりはないことです 笑
(1) パフォーマンスエンジニアの主な仕事内容は?
コース上でミックが最大限力を発揮できるようにマシンを仕上げるために、彼と無線でやり取りをしているレースエンジニアと共に働いている。レースイベント前は、空力や車両ダイナミクス、タイヤなど他部門からのアドバイスも聞き入れてマシンセットアップへ集約していく。
マシンの走行中はテレメトリーを見ながらマシンが予想通りかつ全てが安全に機能しているかをチェックしている。サスペンションが想像通りに動いているか、マシンが正しい車高を維持しているか、タイヤの内圧が正常かを常に確認し、次の走行プランを考える。
走行後はデータを確認し、ドライバーが抱える問題や速く走ることを助けるために何が必要かを話し合う。改善が必要な部分が分かれば、セットアップ方法を検討する。
僕がこれまで所属したチームや友人のいる国内SGT300クラスのチームに限定すれば、レースエンジニアやデータエンジニアという役職は殆どのチームにありました。しかし、パフォーマンスエンジニアという役職を持った人には会うことがありませんでした。
チームによって役職の定義は様々だと思いますが、上述の説明だけ読むとこれら2つの役職の中間に位置してそうなポジションです。
僕の経験してきたデータエンジニアの業務は仕事の中心がデータを用いたシステムや部品の信頼性チェックの比重が高かったです (パフォーマンス面も見ます)。一方で、ここでのパフォーマンスエンジニアはもう少し他部署を先導しながらパフォーマンス向上させるのが中心の仕事なのかと思いました。
またテレメトリーがあるのはやはり最高峰のF1です。ホンダF1のSakura研究所で使っていることでも有名です。しかし、意外に思われるかもしれませんが多くのカテゴリではテレメトリーを使用してません。例えば国内レース (SuperGT, SuperFormula) や昨年までのチームが参戦していたユーロ・フォーミュラオープンも使用していませんでした。ルマン24時間レースなどは当然ありますが、WRCもサーキットではなく各ステージを移動していくためF1のような常時送受信できるテレメトリーは困難です。
(2) パフォーマンスエンジニアになるには?
サーキット帯同のパフォーマンスエンジニアへの一般的なルートとしては、ファクトリーで車両ダイナミクス部門のポジションで経験を積んだ後に、サーキットでの役職に移ることだ。コース上でのテストは限られているから、帯同するチャンスを得るのは難しい。しかし、レース週末にファクトリーの司令室から、サーキットにいるチームへ行なう後方支援として加わる機会はある。後方支援は、サーキット側のオペレーションに関する経験を深め、実際に帯同する時の基盤を作るにはとても良いチャンスだ。
サーキット帯同のチームにいるスタッフの経験は幅広い。他のフォーミュラシリーズからF1に昇格したスタッフもいれば、以前ファクトリーで働いていた経験を持つスタッフもいる。
ファクトリー経由という段階的にレース現場で働く準備をするキャリアパスについては知りませんでした。パフォーマンス系の役職では車両工学と各部品についての深い理解が前提なので、そのようなキャリアパスは理にかなっている気がします。
一方で僕は少し状況が違っていて、ラリー本番は基本的には帯同しませんが、実戦前のテストや来シーズン向けの新型車両の開発テストには帯同しています。WRCはシーズン中も、各欧州ラウンド前には開発テストが出来ること、また2022年シーズンから新型車両に切り替わるため、ずっと開発テストばかりです。
週休2日制が機能していなくて少し辛いのですが、精神と時の部屋(?)のように短期間で現場レベルに到達したい僕にとっては恵まれてるかもしれません。
サーキットやラリーの現場で活躍しているスタッフの経験が幅広いのはとても同感です。同僚の中には、シトロエンWRCチームから移籍してきたメンバーはかなり多いですし、F1経験者もいたりしてお互いに得意分野でカバーし合っている感じです。
(3) 求められる資格とは
私は大学では自動車工学を専攻していた。しかし、スタッフの多くがそれぞれ異なる分野から来ている。ほとんどの役割は仕事の経験を通して学ぶものなので、問題に冷静に対処するための心構えがあれば何でも構わない。
国内での採用に比べて欧州では専門性を重視する傾向が強いと思うので、個人的には少し意外な回答でした。僕は学生の頃に、自動車工学についてもう少し学んでおくべきだったと反省しています。ちなみに欧州トップカテゴリでエンジニアとして働きたいなら学位は持っていた方が有利なのは間違いありません。
僕は大学生の頃から経歴書を目立たせることを意識していたので、大学院の成績はオールAで卒業しました。実際は大したことなくても一目で優秀そうだと勘違いしてもらうためです。ギャップは後で埋め合わせ戦略です 笑
(4) 役立つスキルは?
私の経験則から言うと、幼い頃からF1のファンだったことが、就職する時にF1に関わっていたいという気持ちを後押しした。モータースポーツのファンで、その環境で働くことを夢見てこれに関わりたいと思っている人が大半だと思う。F1はテレビで見るほど華やかな世界ではないし、家族や自宅から離れる時間も多いから、このシリーズに情熱を持っていないと厳しいかもしれない。どんな仕事にも言えることだが、大変な日もある。しかし、何にも代え難い素晴らしい経験だ。
これはとても正直な回答と感じてすごく同意しました。僕もテレビで見たF1の世界に憧れて業界に飛び込みました。でも現場は華やかというよりはアナログで地味な世界です。幻滅したり、長い拘束時間のために離れていく人も多いです。実は僕も彼女とずっと遠距離です。一方で、貴重な経験が詰めるのも本当です。
(5) F1の仕事を経験するには?
多くのF1チームには、大学を卒業した人向けに新卒採用枠や、学生が数週間から1年間チームで様々な分野に携わることができる配属希望枠が設けられている。こうした枠ではかなり競争は激しいが、素晴らしい経験になる。
F1マシンは他の多くのシリーズよりはるかに複雑だが、配属の件を除けば根底にあるものは同じだ。下位カテゴリー経験を積むことは有益で、履歴書を目立たせることもできる。
F1チームを始め、欧州ではインターンで仕事の経験を積むのが一般的です。F1チームとコネクションのある大学もイギリスには多いです。下位カテゴリでの経験も有益ですが、F1やトップカテゴリの多くは同レベル、もしくは1つ下のカテゴリ経験を求める求人も多いです (F1ならWEC、FE、F2など)。
僕の前所属F3チームからメルセデス系F2チーム(HWA)に転職した友人がいますが、彼はおそらくF1を目指しています。F4など下位カテゴリだとトップカテゴリまで辿り着くのに時間を要してしまうので注意です。但し、それでも業界に入ることが1番大事だと思うので興味があって、チャンスがあれば先ずは飛び込むことをお勧めします。
(6) まとめ
実はレース現場の仕事でも、ラップタイムに直接的に関わる仕事ばかりではありません。極端の例ではサーキットにテレメトリーシステムを設置するエンジニアもいる訳で、彼らの多くはレース上で働いていてもレーシングカーを速くしている訳ではありません。そういったレース業界の裏側のさらに裏側にもエンジニアはたくさんいます。
そういう意味ではF1のパフォーマンスエンジニアの仕事内容は興味深く、大変だとは思いますが学生時代の僕がイメージしていたレース現場での仕事という感じでした。
もうひとつ印象に残ったのは、華やかに見えるF1でさえメディアが映す世界観からはズレがあると教えてくれていることです。僕もF1に憧れてモータースポーツの業界に飛び込みましたが現実の地味で過酷な作業とのギャップをすごく感じました。その意味でインタビューされているエドワードさんの言葉には信頼が置けそうな気がしました。
読んで頂いてありがとうございました。
スキやフォロー頂ければ励みになります。
自動運転とモータースポーツのテクノロジーについての記事を書きます! 未来に繋がるモータースポーツを創りたいです!
